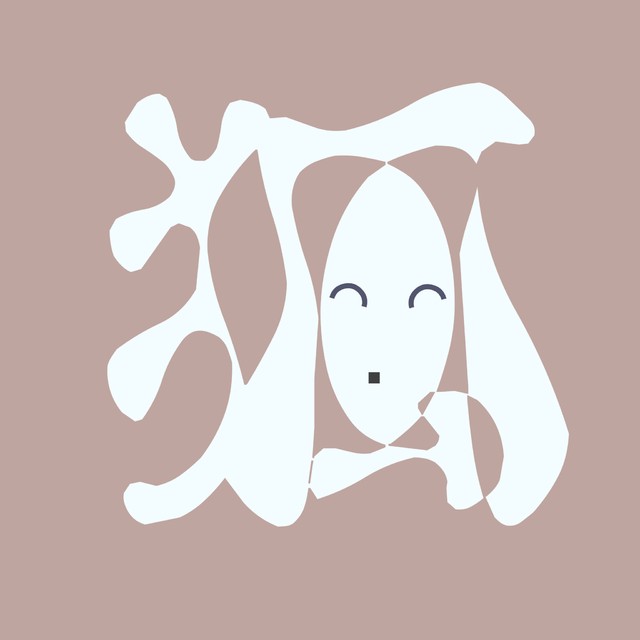1週間の休みの過ごし方
文字数 5,039文字
海岸線を走るローカル鉄道。2両編成の列車が長閑 に走る。
電車に乗ったのはいつ以来だろう。
僕は海とは反対側の窓際の席に座っていた。
窓の外を線路と並行して走っている国道を眺めていると、猛スピードで追いついて来た赤いポルシェが速度を落として並走し始めた。山中湖畔の別荘に保管してあった亡父のコレクションの中で一番スピードが出ると思われた4シーターだ。運転手の苔生 が窓から左手を出して親指を立てる。かと思うと、またすぐに加速してあっという間に見えなくなった。映画の主人公にでもなった気分なのだろう。まあどんな仕事でも楽しむのが一番だ。そんなことを思った時、小高い山の中腹に今日の目的地である西洋の城のようなホテルが見えた。
車内に目を転じると、2席ずつ向かい合った4人掛けのシートに1人か2人程度の混み具合だ。そんな中、地元の人や観光客に紛れて明らかにこの場の雰囲気に似つかわしくない乗客が3人いることが分かる。
1人は僕の席と通路を挟んで反対側のシートに座る身形 の良い老紳士だ。与党幹事長はじめ政界中枢と繋がっているとされるフィクサー、田所重次郎 ——その人ではなく、その兄、京一郎 だ。乗り鉄と呼ばれる鉄道オタクであると同時に乗り女 と揶揄されるほどの女好きらしい。先ほど見えたホテルのオーナーでもある。
もう1人は少し離れた通路側の席に座っている女性、謎の女——峰不二子じゃない。疫病神、紗莉那 だ。鍔 の広いハットで表情を隠し、ドレスと呼んでもいいようなタイトで光沢のある黒いワンピースを着ている。深いスリットを存分に活かし、白くて形の良い脚をこれ見よがしに組んで通路を塞いでいる。靴は歩くたびに床に穴があきそうなピンヒールだ。場違いにもほどがある。一度ワークマンにでも連れて行って全身コーディネートしてやりたい。
そして、この2人と同類項にはされたくないが、3人目は僕自身だ。
さて、僕も仕事をしよう。
パンフレットを取り出す。薄っぺたいが高級感はある。真っ黒な表紙を捲ると、中には5枚の絵画が載っている。この後、先ほどのホテルでこれら絵画のオークションが行われることになっているのだ。掲載されている作品はルノワール「イレーヌ・カーン・ダンヴェルス嬢」ほか、アンカーの「髪を編む少女」など計5作品。いずれも美しい少女を描 いた名品ばかりだ。
不意に田所がわざとらしい咳払いをするのが聞こえた。かと思うと、立ち上がって僕のすぐ斜め向かいの席まで移動して来た。
「何か?」
「君も参加するのかね?」
「ええ。ではあなたも?」
「いや、まあ、そんなところだ」
「楽しみですね。私は初めてなんですよ」
「なるほど。では一つ忠告をしておこう。知っていると思うが、このオークションは限られたメンバーだけで極秘裏に開催されるんだ。こんなところでそんなものを広げるんじゃない」
「これは失礼。つい待ち切れずに」
大人しくパンフを仕舞う。
田所は小さく頷いたように見えた。
「ところで君は?」
「失礼しました。鳴砂 コーポレーションの鳴砂と申します」
出鱈目だ。紗莉那を引っ繰り返しただけの偽名である。
腰を浮かせて差し出した名刺を、田所は小馬鹿にした表情を隠そうともせず片手で受け取った。
「ああ、ナリサね。仮想通貨でぼろ儲けしたとかいう」
「失礼ですが、主催者の田所さんとお見受けしましたが」
彼はいかにもというふうに頷いた。もし口に出していかにもなんて言われたら笑ってしまっていただろう。
「この度は参加を認めて頂き、ありがとうございました」
弟の重次郎は汚いことに手を染めながらも、それなりの傑物として評価する声もある人物だが、この京一郎という男は、弟の威を借りて己の欲望のままに悪事に手を広げているクズだという専らの評判だ。
「君もまだ若いのに、あれだね」
田所は言葉を濁しながら下卑た笑みを浮かべる。
「社会的に大っぴらにできない性癖なのですが、たまたまこちらの催し物を耳にしまして飛びつきました」
著名な絵画の真作がこんな片田舎のオークションに出るわけもない。実態は口にするのもおぞましい、名作絵画に見立てた5人の生身の少女たちのオークション、人身売買だ。令和の世の日本でそんなことが行われているなどと俄かには信じられなかった。
少し前、苔生の弟子だった人物が幼い娘一人を残して夫婦揃って事故で他界したのだという。その娘を引き取った人物が田所同様に時代劇の悪代官並みのクズだったらしく、田所の関連組織に娘を売り飛ばしてしまった。表向きは合法な養子縁組を装ってだ。それを知った苔生が紗莉那に相談し、その娘の救出を第一の目的に、あわよくば田所一味の壊滅もと目論んだのが今回の計画である。僕はまんまと巻き込まれてしまったわけだが、事情を知ってしまうと放っておくわけにはいかなかったのだ。
「おい、あの女を見ろ」
田所がいやらしい視線を送りながら、紗莉那を顎で指した。
「派手な女ですね。場違いにもほどがある」
田所は小さく笑った。
「確かにな。だが、良い女だ」
「性格は悪そうですよ」
「そんなものはどうでもいい。顔と身体が良けりゃ、男の喜ばせ方はわしが仕込んでやる」
下品なことをさらりと言ってのける。吐き気がしたが、田所はさらに下品に輪をかけた。
「あんな上玉はなかなかいないぞ。50万出してもいい」
「それは愛人としての月のお手当的な?」
「一晩だよ。愛人なら月に500は出してやる」
ここまではっきり言われると清々しい。
苦笑したところで車内アナウンスが目的の駅が近いことを告げた。
「君も駅に迎えが来ているんだろうね?」
「ええ、もちろん」
「どうしてわざわざ電車で来た?」
「鉄道が好きなんです。それだけです」
嘘だ。乗り鉄の田所がこの路線を使うことは分かったので、紗莉那をやつに近づけさせることが主な目的だった。策を弄すまでもなく、やつは紗莉那に食いついたようだが。
「じゃあな」
同じ駅で降りるのだが、とりあえず田所を見送った。その後を紗莉那が、まるでランウェイのように優雅に歩いて行く。足をかけてやりたい衝動を何とか抑えた。
列車が完全に停車する直前、車両がほんの少しだけ揺れた。
「きゃっ!」
女性の悲鳴が聞こえ、見ると紗莉那が田所に抱きつくようにして寄りかかっていた。
「すみません」
「いや、大丈夫かね」
田所は早速鼻の下を伸ばしている。
紗莉那との出会いを思い出した。彼女がぶつかって来て僕のスーツにラテをぶちまけた。それも全部彼女の計略だった。

僕は二人と距離を取ってホームに降り立った。
自動改札機と券売機、公衆電話しかない無人駅だ。海側の出口の先はすぐ砂浜になっている。いつか恋人でも連れて二人きりで来てみたいものだ。


国道側はロータリーになっていて、黒塗りのロールスロイスが田所を迎えに来ていた。運転手は既に苔生の弟子の一人に入れ替わっているはずだったが、田所は訝しむ様子もなく先に紗莉那を乗せて、自らも乗り込んだ。このまま紗莉那が田所を人質に抑え、警備を事実上無力化した上で、僕と苔生が娘たちを救出する計画だ。警察は田所と繋がっている可能性があるので当てに出来ない。
田所の車が去るのを見届けてから、ロータリーに停まっていたポルシェに乗り込む。苔生はルームミラー越しに無言で頷いた。ここまでは計画通りに運んでいるようだ。
「行こうか」
「参りましょう」
エンジンがかかる。重低音が肩凝りや腰痛に効きそうだ。
言うまでもなく苔生は武術の達人だが、実は僕だって弟子の一人だ。紗莉那も道場に通っていた。いわば今回は僕たちにとって兄弟弟子の娘の危機なのだ。苔生流 は特に実戦的な武術である。刃物などの武器を持った相手とも素手で渡り合い、倒すことを主眼にしている。社長業ばかりやっているよりは、たまにはこういう刺激があってもいいのかもしれない。
1週間前のことだった。
「お前の仕事の手伝いなんか、するわけがないだろう」
午後のひととき、僕は会社を離れて裏通りにある隠れ家カフェで時間を過ごすことがある。その日はブラック珈琲を飲みながらKindleOasisで京極夏彦の活字の沼に浸っていた。そんな至福の時間を、突然現れた紗莉那にぶち壊された。
「冷たいこと言わないで、話くらい聞いてくれてもいいでしょ」
社長室にこもっていても一人の時間は持てる。だが、職場は所詮仕事をする場でしかない。僕は仕事に忙殺されている自分が大嫌いなのだ。しかし、大勢の社員やその家族の生活まで背負っている立場上、投げ出すわけにもいかない。だから普段はまるで若手社員の如く、SHISHAMOの”明日も”を頭の中でガンガン鳴らしながら仕事に邁進しつつ、週に2,3度は秘書の明日香に頼んでカフェで過ごす時間を捻出してもらっている。つくづくもこの世で最も貴重なのは時間だ。
そんな貴重な時間を紗莉那に台無しにされた。断りもなく向かいの席に座って僕のKindleを取り上げ、鼻で笑いやがった。——塗仏 ? 何それ、美味しいの? とでも言わんばかりに。
毎度のことながら、これ見よがしに組まれた白くて形の良い脚がこちらの攻撃力を削 ぐ。
「聞いたところでどうせ泥棒だろうが」
「職業に貴賤はないって、お父さんに教わらなかったの?」
僕最大の黒歴史は、我が家に伝わるルビー目的に近づいて来た彼女と婚約寸前までの仲にまでなってしまったことだ。苔生の機転のおかげでその陰謀に気づき難を逃れたのだ。その後は行方を晦ましていた紗莉那だが、ある日突然現れて苔生が運転する僕の車を泥棒稼業の逃亡に利用しやがった。
「よし分かった。今度こそ今すぐに警察に通報してやる」
「じゃあいい。もともと必要なのはあなたよりも苔生さんの方だから」
やっぱりだ。苔生と紗莉那はどこか僕の知らないところで繋がっている。そもそもは苔生家が代々受け継ぐ何とかいう武術の苔生流の道場が存続の危機に陥った時、資金援助をして救ったのが父だったらしい。それを機に苔生は道場を自分の娘に任せて父の運転手になったという縁だ。そして父が亡くなった後も僕の運転手を続けてくれているのだが……。
「どういうことだよ」
「聞きたくないんでしょ」
「苔生は俺の運転手だぞ。お前の好きにはさせない」
「あ、そ。じゃあこれ発動しちゃおうかな」
紗莉那は1枚の紙を取り出して、ひらひらと振ってみせた。
「な、何だよ、それ」
とても嫌な予感がした。
「へへん。何と、苔生さんの有給休暇届」
「なにっ⁈」
「あなたが協力してくれなくたって、苔生さんは休暇を取って、わたしを手伝ってくれるんだって。あなただって普通免許くらい持ってるでしょ。自分で運転しなさいよね」
「お、おまえ、何か苔生の弱みでも握ってるのか?」
「あの人に弱みなんてあるの? あるなら高く買うけど?」
「じゃあ何だ? なんで苔生はおまえなんかに協力しようとするんだ?」
「苔生さんは優しい。あなたは冷たい。それだけのことでしょ」
その後、事情を知らされた僕に、断るという選択肢はなくなった。山中湖畔の別荘に向かう車中から恐る恐る、けれど、そんなことは気取られないように秘書の明日香に電話をし、向こう1週間の予定を全部キャンセルするように指示をした。
明日香は優秀な秘書だ。最高の秘書と言い換えてもいい。指示されたことは忠実かつ確実にこなす。指示を2度聞きしたことなど1度もない。ついでに言えば、紗莉那に負けず劣らず良い女だ。いくら誘っても応じないのが唯一の減点要素と言っていい。その明日香が電話の向こうで絶句するのが分かった。
「明日香、良く聞け。君は、スターク・インダストリーズにおけるミス・ポッツだ。任せた」
返事を聞かずに電話を切った。次のボーナスはポケットマネーで上乗せするから許して欲しい。
ルームミラー越しに運転中の苔生と目が合っ
た。
「何だよ?」
「いえ、別に」
「君はハッピーだとでも言って欲しいのか?」
「とんでもございません。ダウントン・アビーは好きですが、あ、いえ。この度のこと、ご協力に感謝します」
「いいよ。兄弟弟子の娘のことだ。助けないわけにはいかないじゃないか」
相変わらず言いたいことは富士山の2つ分くらいはあるものの、今回もぐっと飲み込む。なんで飲み込むのか、自分でもよく分からない。
こうして社長になって初めての1週間の休みが始まった。不謹慎にも、僕は少しわくわくしていた。
《了》
電車に乗ったのはいつ以来だろう。
僕は海とは反対側の窓際の席に座っていた。
窓の外を線路と並行して走っている国道を眺めていると、猛スピードで追いついて来た赤いポルシェが速度を落として並走し始めた。山中湖畔の別荘に保管してあった亡父のコレクションの中で一番スピードが出ると思われた4シーターだ。運転手の
車内に目を転じると、2席ずつ向かい合った4人掛けのシートに1人か2人程度の混み具合だ。そんな中、地元の人や観光客に紛れて明らかにこの場の雰囲気に似つかわしくない乗客が3人いることが分かる。
1人は僕の席と通路を挟んで反対側のシートに座る
もう1人は少し離れた通路側の席に座っている女性、謎の女——峰不二子じゃない。疫病神、
そして、この2人と同類項にはされたくないが、3人目は僕自身だ。
さて、僕も仕事をしよう。
パンフレットを取り出す。薄っぺたいが高級感はある。真っ黒な表紙を捲ると、中には5枚の絵画が載っている。この後、先ほどのホテルでこれら絵画のオークションが行われることになっているのだ。掲載されている作品はルノワール「イレーヌ・カーン・ダンヴェルス嬢」ほか、アンカーの「髪を編む少女」など計5作品。いずれも美しい少女を
不意に田所がわざとらしい咳払いをするのが聞こえた。かと思うと、立ち上がって僕のすぐ斜め向かいの席まで移動して来た。
「何か?」
「君も参加するのかね?」
「ええ。ではあなたも?」
「いや、まあ、そんなところだ」
「楽しみですね。私は初めてなんですよ」
「なるほど。では一つ忠告をしておこう。知っていると思うが、このオークションは限られたメンバーだけで極秘裏に開催されるんだ。こんなところでそんなものを広げるんじゃない」
「これは失礼。つい待ち切れずに」
大人しくパンフを仕舞う。
田所は小さく頷いたように見えた。
「ところで君は?」
「失礼しました。
出鱈目だ。紗莉那を引っ繰り返しただけの偽名である。
腰を浮かせて差し出した名刺を、田所は小馬鹿にした表情を隠そうともせず片手で受け取った。
「ああ、ナリサね。仮想通貨でぼろ儲けしたとかいう」
「失礼ですが、主催者の田所さんとお見受けしましたが」
彼はいかにもというふうに頷いた。もし口に出していかにもなんて言われたら笑ってしまっていただろう。
「この度は参加を認めて頂き、ありがとうございました」
弟の重次郎は汚いことに手を染めながらも、それなりの傑物として評価する声もある人物だが、この京一郎という男は、弟の威を借りて己の欲望のままに悪事に手を広げているクズだという専らの評判だ。
「君もまだ若いのに、あれだね」
田所は言葉を濁しながら下卑た笑みを浮かべる。
「社会的に大っぴらにできない性癖なのですが、たまたまこちらの催し物を耳にしまして飛びつきました」
著名な絵画の真作がこんな片田舎のオークションに出るわけもない。実態は口にするのもおぞましい、名作絵画に見立てた5人の生身の少女たちのオークション、人身売買だ。令和の世の日本でそんなことが行われているなどと俄かには信じられなかった。
少し前、苔生の弟子だった人物が幼い娘一人を残して夫婦揃って事故で他界したのだという。その娘を引き取った人物が田所同様に時代劇の悪代官並みのクズだったらしく、田所の関連組織に娘を売り飛ばしてしまった。表向きは合法な養子縁組を装ってだ。それを知った苔生が紗莉那に相談し、その娘の救出を第一の目的に、あわよくば田所一味の壊滅もと目論んだのが今回の計画である。僕はまんまと巻き込まれてしまったわけだが、事情を知ってしまうと放っておくわけにはいかなかったのだ。
「おい、あの女を見ろ」
田所がいやらしい視線を送りながら、紗莉那を顎で指した。
「派手な女ですね。場違いにもほどがある」
田所は小さく笑った。
「確かにな。だが、良い女だ」
「性格は悪そうですよ」
「そんなものはどうでもいい。顔と身体が良けりゃ、男の喜ばせ方はわしが仕込んでやる」
下品なことをさらりと言ってのける。吐き気がしたが、田所はさらに下品に輪をかけた。
「あんな上玉はなかなかいないぞ。50万出してもいい」
「それは愛人としての月のお手当的な?」
「一晩だよ。愛人なら月に500は出してやる」
ここまではっきり言われると清々しい。
苦笑したところで車内アナウンスが目的の駅が近いことを告げた。
「君も駅に迎えが来ているんだろうね?」
「ええ、もちろん」
「どうしてわざわざ電車で来た?」
「鉄道が好きなんです。それだけです」
嘘だ。乗り鉄の田所がこの路線を使うことは分かったので、紗莉那をやつに近づけさせることが主な目的だった。策を弄すまでもなく、やつは紗莉那に食いついたようだが。
「じゃあな」
同じ駅で降りるのだが、とりあえず田所を見送った。その後を紗莉那が、まるでランウェイのように優雅に歩いて行く。足をかけてやりたい衝動を何とか抑えた。
列車が完全に停車する直前、車両がほんの少しだけ揺れた。
「きゃっ!」
女性の悲鳴が聞こえ、見ると紗莉那が田所に抱きつくようにして寄りかかっていた。
「すみません」
「いや、大丈夫かね」
田所は早速鼻の下を伸ばしている。
紗莉那との出会いを思い出した。彼女がぶつかって来て僕のスーツにラテをぶちまけた。それも全部彼女の計略だった。

僕は二人と距離を取ってホームに降り立った。
自動改札機と券売機、公衆電話しかない無人駅だ。海側の出口の先はすぐ砂浜になっている。いつか恋人でも連れて二人きりで来てみたいものだ。


国道側はロータリーになっていて、黒塗りのロールスロイスが田所を迎えに来ていた。運転手は既に苔生の弟子の一人に入れ替わっているはずだったが、田所は訝しむ様子もなく先に紗莉那を乗せて、自らも乗り込んだ。このまま紗莉那が田所を人質に抑え、警備を事実上無力化した上で、僕と苔生が娘たちを救出する計画だ。警察は田所と繋がっている可能性があるので当てに出来ない。
田所の車が去るのを見届けてから、ロータリーに停まっていたポルシェに乗り込む。苔生はルームミラー越しに無言で頷いた。ここまでは計画通りに運んでいるようだ。
「行こうか」
「参りましょう」
エンジンがかかる。重低音が肩凝りや腰痛に効きそうだ。
言うまでもなく苔生は武術の達人だが、実は僕だって弟子の一人だ。紗莉那も道場に通っていた。いわば今回は僕たちにとって兄弟弟子の娘の危機なのだ。
1週間前のことだった。
「お前の仕事の手伝いなんか、するわけがないだろう」
午後のひととき、僕は会社を離れて裏通りにある隠れ家カフェで時間を過ごすことがある。その日はブラック珈琲を飲みながらKindleOasisで京極夏彦の活字の沼に浸っていた。そんな至福の時間を、突然現れた紗莉那にぶち壊された。
「冷たいこと言わないで、話くらい聞いてくれてもいいでしょ」
社長室にこもっていても一人の時間は持てる。だが、職場は所詮仕事をする場でしかない。僕は仕事に忙殺されている自分が大嫌いなのだ。しかし、大勢の社員やその家族の生活まで背負っている立場上、投げ出すわけにもいかない。だから普段はまるで若手社員の如く、SHISHAMOの”明日も”を頭の中でガンガン鳴らしながら仕事に邁進しつつ、週に2,3度は秘書の明日香に頼んでカフェで過ごす時間を捻出してもらっている。つくづくもこの世で最も貴重なのは時間だ。
そんな貴重な時間を紗莉那に台無しにされた。断りもなく向かいの席に座って僕のKindleを取り上げ、鼻で笑いやがった。——
毎度のことながら、これ見よがしに組まれた白くて形の良い脚がこちらの攻撃力を
「聞いたところでどうせ泥棒だろうが」
「職業に貴賤はないって、お父さんに教わらなかったの?」
僕最大の黒歴史は、我が家に伝わるルビー目的に近づいて来た彼女と婚約寸前までの仲にまでなってしまったことだ。苔生の機転のおかげでその陰謀に気づき難を逃れたのだ。その後は行方を晦ましていた紗莉那だが、ある日突然現れて苔生が運転する僕の車を泥棒稼業の逃亡に利用しやがった。
「よし分かった。今度こそ今すぐに警察に通報してやる」
「じゃあいい。もともと必要なのはあなたよりも苔生さんの方だから」
やっぱりだ。苔生と紗莉那はどこか僕の知らないところで繋がっている。そもそもは苔生家が代々受け継ぐ何とかいう武術の苔生流の道場が存続の危機に陥った時、資金援助をして救ったのが父だったらしい。それを機に苔生は道場を自分の娘に任せて父の運転手になったという縁だ。そして父が亡くなった後も僕の運転手を続けてくれているのだが……。
「どういうことだよ」
「聞きたくないんでしょ」
「苔生は俺の運転手だぞ。お前の好きにはさせない」
「あ、そ。じゃあこれ発動しちゃおうかな」
紗莉那は1枚の紙を取り出して、ひらひらと振ってみせた。
「な、何だよ、それ」
とても嫌な予感がした。
「へへん。何と、苔生さんの有給休暇届」
「なにっ⁈」
「あなたが協力してくれなくたって、苔生さんは休暇を取って、わたしを手伝ってくれるんだって。あなただって普通免許くらい持ってるでしょ。自分で運転しなさいよね」
「お、おまえ、何か苔生の弱みでも握ってるのか?」
「あの人に弱みなんてあるの? あるなら高く買うけど?」
「じゃあ何だ? なんで苔生はおまえなんかに協力しようとするんだ?」
「苔生さんは優しい。あなたは冷たい。それだけのことでしょ」
その後、事情を知らされた僕に、断るという選択肢はなくなった。山中湖畔の別荘に向かう車中から恐る恐る、けれど、そんなことは気取られないように秘書の明日香に電話をし、向こう1週間の予定を全部キャンセルするように指示をした。
明日香は優秀な秘書だ。最高の秘書と言い換えてもいい。指示されたことは忠実かつ確実にこなす。指示を2度聞きしたことなど1度もない。ついでに言えば、紗莉那に負けず劣らず良い女だ。いくら誘っても応じないのが唯一の減点要素と言っていい。その明日香が電話の向こうで絶句するのが分かった。
「明日香、良く聞け。君は、スターク・インダストリーズにおけるミス・ポッツだ。任せた」
返事を聞かずに電話を切った。次のボーナスはポケットマネーで上乗せするから許して欲しい。
ルームミラー越しに運転中の苔生と目が合っ
た。
「何だよ?」
「いえ、別に」
「君はハッピーだとでも言って欲しいのか?」
「とんでもございません。ダウントン・アビーは好きですが、あ、いえ。この度のこと、ご協力に感謝します」
「いいよ。兄弟弟子の娘のことだ。助けないわけにはいかないじゃないか」
相変わらず言いたいことは富士山の2つ分くらいはあるものの、今回もぐっと飲み込む。なんで飲み込むのか、自分でもよく分からない。
こうして社長になって初めての1週間の休みが始まった。不謹慎にも、僕は少しわくわくしていた。
《了》