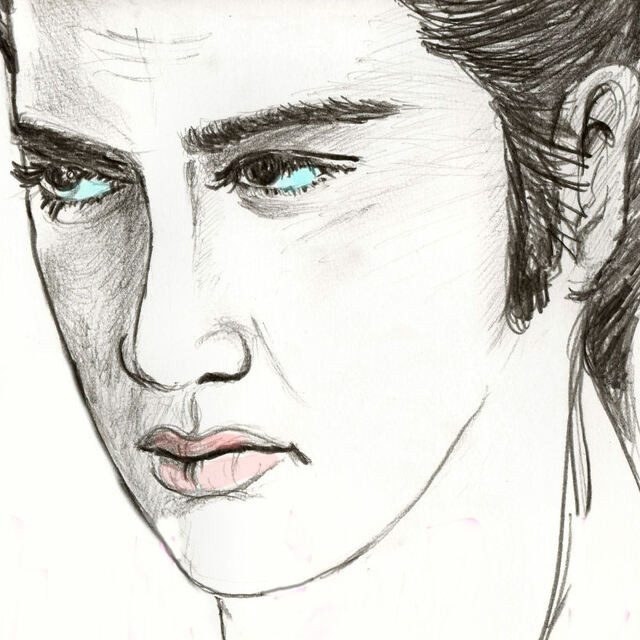第11話 父と子
文字数 1,661文字
与太郎は、老人の計らいでその店で働くことになった。店では妹のたえも一緒である。
彼は心から改心して働き続け、夕顔のたえと共にその借金を返し続けていた。心機一転、名前も善吉と改めた、その名付け親はあの老人である。
老人は善吉が返す金を溜めて、いつかそれを二人に与えるつもりである。その時は善吉が、金の有り難さが心から解ったときと決めていた。しかし、自分が実の親だとは決して言うまいと心に誓うのである。
今更、自分が親だと名乗り出る勇気もない。
せめて名乗らなくても、二人を見守るのが自分の役目だと思うからである。
その老人こそ、紛れもなく二人を赤ん坊の時に捨てた父親だった。老人の名前を弥平と言う。弥平は若い頃、貧しいながらも妻と仲良く暮らしていた時期があった。
その妻が双子を生んだ後に体調が思わしくなく、弥平は妻を懸命に介抱したのだが、その甲斐もなく妻は力尽き、最後に息を引き取る時だった。やつれ果てた妻は病の中で、苦しそうに弥平に言った。
「ねえ、あなた、私はもう遠いところへ旅だっていきます、でもどうしても……」
妻の微かな声を耳元で聞きながら、弥平は手を握り耳を澄ませていた。
「赤ん坊のことだね」
「はい、そのことだけが……気がかりで」
「わかった、大丈夫だから、安心しなさい」
「はい、わたしはそれだけが気がかりで、あぁ、嬉しい……」
そう言いながら、妻は夫の手を握りしめ、涙を浮かべながら眼を閉じた。彼は妻のそのまだ暖かい手をいつまでも握りしめていた。その日、弥平の妻は夫と二人の赤ん坊を残して旅立っていったのだ。
「私を一人にしないでくれ、お願いだ……」
弥平はいつまでも泣きながら妻の面影を追っていた。
弥平は妻が亡くなった後も、男手一つで双子の子供を何とか育てようとして頑張っていたのである。しかし、頼る親戚もなくやがて根が尽き果てていた。
妻を亡くした弥平には、幼子二人と、絶望だけが残った。
彼は生きる希望を無くし、子供を道ずれに死ぬつもりだった。だが、悩んだあげくにそれだけは思い止まった。
その結果、二人の幼い子供を、それぞれを違う場所に置くことを思いついたのである。
赤子の捨て場所を寺の前と、商家に選んだのである。
その場所で誰かがこの小さな子供を見つけ、拾い育てくれると念じたのである。その後、手ぶらになった弥平はふらついた足どりで川の中に身を投げようとしたそのときだった。どこかで妻の声を聞いたのである。
(あなた……どうか死なないで、私達の赤ちゃんを、どうか見守ってくださいな……)
それは虫の声かも知れない、或いは柳がそよぐ風がそう聞こえたのかもしれない。
二人の赤ん坊は捨てたが、自分まで死なないで欲しい、と妻が訴えているように弥平には聞こえた。その後、弥平は乞食同然に彷徨いながら放浪の旅を続けていた。
亡き妻の冥福を祈りつつ、捨てた赤ん坊に侘びていた。それは辛く長い旅だった。
その中で、これほどまで苦しむのなら、いっそこの谷底に、深い湖をみれば、そこに身を投げようかと幾度思ったことか……。
何年かの歳月が流れていった。弥平はようやく或る地に落ち着き、働く喜びを知ったのである。そこで地道に働いていく内にその努力がいつしか芽を吹き出していた。
誠実な弥平は商いに成功し、少しずつ財をなしていった。苦労をしているときに知り合った女が、彼の再婚した妻である。その妻との間に出来た娘がいる。
その娘も嫁に行き、一人の女の子を生んだ。孫娘は、あの祭りの縁日で手を繋いで歩いた「てまり」である。娘の亭主に商いを継がせ、今、弥平はのんびりと隠居をしていた。
しかし、弥平はどんな時にも、自分が捨てた赤ん坊の安否を忘れたことはなかった。いつか合いたいと思いながらも、今更捨てた自分が名乗り出る勇気が無かったのである。
ある時、偶然にも成長したその二人に出会ったのだ。彼は心で二人に佗びながらも自分のことは告げず、今は黙って見守ろうと心に決めたのである。いつか告げる日が来ることを心で念じながら。
彼は心から改心して働き続け、夕顔のたえと共にその借金を返し続けていた。心機一転、名前も善吉と改めた、その名付け親はあの老人である。
老人は善吉が返す金を溜めて、いつかそれを二人に与えるつもりである。その時は善吉が、金の有り難さが心から解ったときと決めていた。しかし、自分が実の親だとは決して言うまいと心に誓うのである。
今更、自分が親だと名乗り出る勇気もない。
せめて名乗らなくても、二人を見守るのが自分の役目だと思うからである。
その老人こそ、紛れもなく二人を赤ん坊の時に捨てた父親だった。老人の名前を弥平と言う。弥平は若い頃、貧しいながらも妻と仲良く暮らしていた時期があった。
その妻が双子を生んだ後に体調が思わしくなく、弥平は妻を懸命に介抱したのだが、その甲斐もなく妻は力尽き、最後に息を引き取る時だった。やつれ果てた妻は病の中で、苦しそうに弥平に言った。
「ねえ、あなた、私はもう遠いところへ旅だっていきます、でもどうしても……」
妻の微かな声を耳元で聞きながら、弥平は手を握り耳を澄ませていた。
「赤ん坊のことだね」
「はい、そのことだけが……気がかりで」
「わかった、大丈夫だから、安心しなさい」
「はい、わたしはそれだけが気がかりで、あぁ、嬉しい……」
そう言いながら、妻は夫の手を握りしめ、涙を浮かべながら眼を閉じた。彼は妻のそのまだ暖かい手をいつまでも握りしめていた。その日、弥平の妻は夫と二人の赤ん坊を残して旅立っていったのだ。
「私を一人にしないでくれ、お願いだ……」
弥平はいつまでも泣きながら妻の面影を追っていた。
弥平は妻が亡くなった後も、男手一つで双子の子供を何とか育てようとして頑張っていたのである。しかし、頼る親戚もなくやがて根が尽き果てていた。
妻を亡くした弥平には、幼子二人と、絶望だけが残った。
彼は生きる希望を無くし、子供を道ずれに死ぬつもりだった。だが、悩んだあげくにそれだけは思い止まった。
その結果、二人の幼い子供を、それぞれを違う場所に置くことを思いついたのである。
赤子の捨て場所を寺の前と、商家に選んだのである。
その場所で誰かがこの小さな子供を見つけ、拾い育てくれると念じたのである。その後、手ぶらになった弥平はふらついた足どりで川の中に身を投げようとしたそのときだった。どこかで妻の声を聞いたのである。
(あなた……どうか死なないで、私達の赤ちゃんを、どうか見守ってくださいな……)
それは虫の声かも知れない、或いは柳がそよぐ風がそう聞こえたのかもしれない。
二人の赤ん坊は捨てたが、自分まで死なないで欲しい、と妻が訴えているように弥平には聞こえた。その後、弥平は乞食同然に彷徨いながら放浪の旅を続けていた。
亡き妻の冥福を祈りつつ、捨てた赤ん坊に侘びていた。それは辛く長い旅だった。
その中で、これほどまで苦しむのなら、いっそこの谷底に、深い湖をみれば、そこに身を投げようかと幾度思ったことか……。
何年かの歳月が流れていった。弥平はようやく或る地に落ち着き、働く喜びを知ったのである。そこで地道に働いていく内にその努力がいつしか芽を吹き出していた。
誠実な弥平は商いに成功し、少しずつ財をなしていった。苦労をしているときに知り合った女が、彼の再婚した妻である。その妻との間に出来た娘がいる。
その娘も嫁に行き、一人の女の子を生んだ。孫娘は、あの祭りの縁日で手を繋いで歩いた「てまり」である。娘の亭主に商いを継がせ、今、弥平はのんびりと隠居をしていた。
しかし、弥平はどんな時にも、自分が捨てた赤ん坊の安否を忘れたことはなかった。いつか合いたいと思いながらも、今更捨てた自分が名乗り出る勇気が無かったのである。
ある時、偶然にも成長したその二人に出会ったのだ。彼は心で二人に佗びながらも自分のことは告げず、今は黙って見守ろうと心に決めたのである。いつか告げる日が来ることを心で念じながら。