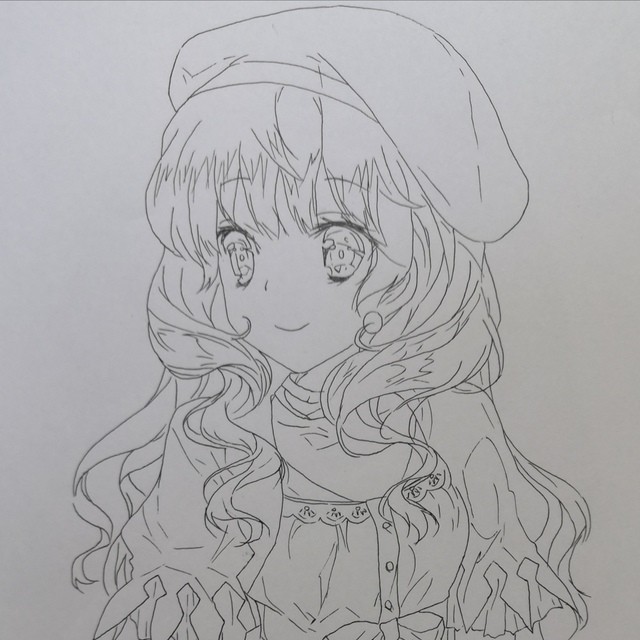2節:犬と猫
文字数 11,215文字
そこは深い海の底でした。
聞こえる音はどこかくぐもり、
見える景色は波間に歪み、
水に搦め取られた体は動かず、
仄かな意識の中、呼吸さえ忘れて、
私は、
私を眺めているだけでした。
書庫の通路を歩きながら、漠然と「これは夢だな」という認識をした。
しかし、「ここはどこ?」という質問をされたらどう答えればいいのだろう。
「夢の中」と答えるのが正しいのか、「図書室の書庫」と答えるのが正しいのか。
では、「私は誰?」という質問にはどう答えればいいだろう。ぼうっとした意識の中でまどろみながら考える。目の前で長い髪を揺らし、つま先立ちになりながら懸命に本に手を伸ばす私が「私」なのだろうか。それとも、そんな私を眺めている私が「私」なのだろうか。
目の前の私が、自分の身長より高い書庫の本棚から、無理やり本を取り出した反動で尻もちをついた。床に積もった埃が、私を包み込むように舞い上がる。その灰色を切り裂くように、金色の羽が一つ、輝きながら舞い降りる。
埃を吸い込み激しく咳き込みながら、私はその金色の羽をを拾い上げて、大切に抱きかかえていた本の間に挟んだ。
服についた埃を軽くはたいて、通路を挟んだ向かい側、螺旋階段の前へ行く。ポケットから取り出した鍵を挿すと、南京錠はその重厚さに似つかわしくない軽い音で開いた。そして、扉に幾重にも巻き付けられた鎖を引きはがして床に打ち捨てる。「ジャラリ」と軋む鎖を踏みしめて、螺旋階段に足をかけた。
階上は、円形状の小さな一室だった。置かれているものは本棚が一つだけ、壁の大窓は開かれ、穏やかな風と茜色の光を呼び込んでいた。
「――。」
窓から半身を乗り出して大きく息を吐きだした。この茜色の空は朝日だろうか、夕日だろうか。そんな他愛もない思案をした時だった。
「ヒメタルモノヨ。」
声、というにはあまりにも強い響きが世界に充満した。
耳だけでなく、世界に存在する全ての生きとし生けるものを震わせるほどの「声」が直接私に迫る。
「誰!何?」
半ば絶叫するように、声の主を探して振り返る。
――振り返った私と、私を見ていた私の、目が合った。
刹那。
「――っぐ!」
視界が脈打ち、強烈な頭痛が私を襲う。朦朧とする私の意識を繋ぎとめたのは呼吸困難。嘔吐するように息を絞り出す。息が吸い込めず、思わず喉を掻きむしった。
「夢なのに、痛くて、苦しい?」
陸に上がったばかりの人魚のように、ヒューヒューと喉が鳴り、四つん這いで赤い絨毯をを掻きむしる。
「ゲホッ!カハッ!」
大きな咳と共に涙と唾を撒き散らして、ようやく意識が鮮明になりつつあった。
緩やかに回復していく意識と視界、そして思考で、真っ先に感じ取ったのは違和感だった。
「うぅ・・・。」
頭痛はまだ消えない。頭に手を置いたまま、よろめく足でゆっくりと立ち上がった。
「やっぱり。」
声に出して呟く。何かが違う、先ほどまでと、何かが。
本棚に身体を預けて、もう一度窓の外に視線を向ける。空の茜色は、その赤さをさらに増しつつあった。
「ここから出よう。」
震える身体を必死に両腕で抱きしめながら、転がり落ちるように螺旋階段を降りた。
降りた先、目の前に広がるのは鬱蒼とした森林だった。
「はは、やっぱり夢か。」
こめかみを揉みほぐしながら再確認する。
最初に私がいたのは学校の書庫。学校の周りは閑静な住宅街で、こんな森はない。ふと後ろを振り返ると、降りてきたはずの螺旋階段も消えていた。
これを夢と呼ばずして何と呼ぶのか。
「めちゃくちゃ生々しい夢だけど。」
大きく深呼吸して、気持ちを落ち着かせる。木々の隙間から見上げる空は、急速に黒くなっていく。先ほどの茜色は、どうやら夕焼けだったようだ。
「ヒメタルモノヨ。」
再度、世界が揺り動かされる。軋む頭を抱えながら、膝から崩れ落ちた。
「こんな夢、早く覚めて。」
呻くように吐き捨てた。こんな不快な夢にどんな意味があるんだろう。というか、こんなに苦しいなら覚醒してもおかしくないはずなのに。
荒い呼吸を整えながら、恐る恐る周囲を見渡す。声の主はいったい誰なのか。もしくは何なのか。
その時、閃くように一つの答えが分かった。声の主についてではない、先ほど感じた違和感の正体である。
先ほどまで、私は「第三者的な視点」でこの夢を傍観していた。夢の中に田辺美乃という登場人物が居て、その登場人物を眺める私が居た。
それが今はどうだろう、私は私だ。私は私を眺めてはいないし、私を眺めている私も居ない。
「まぁ、だからどうしたって話なんだけどね。」
夢の中身について真面目に考察したところで何の意味もないだろう。
震える足で立ち上がりながら、もう一度周囲を見渡した。夜の帳が降り、世界を闇が支配しようとしていた。
しかもそれだけでなく、視界が白み始める。やっと夢から覚めるのだろうかと期待したが、目を凝らすと、それは木々の間に揺らめく霧であった。
森は霧に沈み、闇が蓋をしようとしていた。
月は、まだ出ていない。
開始―別視点/???ー
綺麗に切りそろえられた短冊に、美しい紋様を描きながら、少女は一つため息をついた。開け放たれた大窓から入り込む夜の冷気が、机上の蝋燭をかすかに揺らす。
「早かったのね、何かあった?」
筆を置き、背後の闇に問いかける。
「ほ、ほ、ほ。」
闇は静かに、そして穏やかに笑った。そして短く報告した。
「人が、一人。」
「…強いの?」
少女は少し考えて問うた。人が一人現れたくらいのよくある状況で、彼がわざわざ戻って報告するはずはない。
「いいえ。」
しかし彼の答えは、予想に反して、短い否定の言葉だけだった。
少女は後ろを振り返り、彼を見る。彼の丸い双眸が、机上の蝋燭を映して黄色く輝いていた。
「宝具を、二つ。」
無言で彼に続きを促すと、またしても予想外の答えが返ってきた。
「現れてすぐに誰かから奪ったってこと?」
唯一の可能性を挙げる。その可能性とて、限りなく低い可能性と知りながら。
「いいえ、最初から。」
彼の断言を聞き、少女の頬が微かに赤む。
「馬鹿な。ありえない。」
強く頭を振る。誰でも現れた時は、宝具は一人に一つ。例外は見たことも聞いたこともない。許されるはずもない。誰かから奪わなければ、複数持てるはずはない。
「我が目を、疑いました。」
絶句する私に、彼の双眸が俯いた。
「…えぇ、私も信じられないけれど…いえ、信じるわ、あなたを。」
何故なら、それが彼の宝具なのだから。
「それから、もう一つ。」
静かに彼は続けた。少女はその三角の耳をピクリと動かして傾聴した。
「人狩りが、近付いております。」
「――ウェルス‼」
彼の言葉がまだ言い終わらないうちに、少女の鋭い声が飛んだ。
彼女に答えるように、翼が風を巻き上げる音が響いた。
終了―別視点/???ー
かさり、と足元で落ち葉が鳴る。
私は白い海の中を彷徨っていた。
「なんだかなぁ。」
つま先で落ち葉を蹴り上げる。湿った落ち葉は、それほど巻き上がることもなく、静かに地面に戻っていく。
私はまだ夢から覚めないでいた。「これは夢だ」という強烈な自覚があるにも関わらず、頬をつねっても頭を叩いても夢の中だ。
「夢ならせめて面白いことがあるとかさあ?」
森の木々を相手に愚痴る。その場でじっとしていても良かったのかもしれないが、夢の中とはいえ、暗い森の中で膝を抱えて朝の目覚めを待つよりは、体を動かしている方が気が紛れた。
「王子様が迎えに来てくれるとかさ。」
もちろん現実ではそんな事は言わない。夢の中、私の妄想の中だからこそ言うのだ。自分の都合の良いように夢が展開しないかと。
「――!」
ふと立ち止まる。誰かの気配がした。
「――!」
聞こえる、遠くで誰かが叫んでいる。
できるだけ息を潜め、耳をそばだてる。白馬に乗った王子様なら構わないが、大熊やドラキュラみたいな化け物だったらたまらない。
「誰かいるか?」
ようやく聞き取れるまでに近付いた声は、人間の物だった。
続いて霧の中に蛍のような光球が幾つも浮かび上がる。そしてガチャガチャという金属の擦れあう音も。どうやら一人ではないようだ。
「すみませーん!」
意を決して大声を上げる。少し迷ったが、このまま一人で彷徨い続けるよりは良いだろう。
「誰かいるぞ!」
「こっちだ!」
「明かりを!松明を持ってこい!」
幾人もの男性の声が響いて、蛍のような明かりが私を取り囲んだ。
「何者だ!」
霧の中からゆっくりと姿を現した男性は、右手に抜身の剣を、左手に松明を持っていた。全身は金属の甲冑で覆われている。
「えっと、学生です?」
現れた男性の容姿に驚いて、声が尻すぼみになってしまう。
全身甲冑に剣、明かりは松明。これは中世風の夢なのだろうか?
少し考えてすぐに都合の良い結論にたどり着いた。
「あ、えと、お姫様。です。」
できる限り笑顔で、そして相手に聞こえるように大きな声で返事をする。
これが兵士なら、きっと王子様も居るはずだ。そしてその王子様は私を探しているはず――。
「はぁ?」
しかし、兵士の反応は予想外に冷たいものだった。その返事には嘲笑すら感じられる。
「えっと…。」
私は二の句が継げなくなってしまう。
その時、兵士の後ろからパンパンと手を叩く音が聞こえた。
足音と共に、兵士の囲みが割れ、美しい服を着た貴族風の男が進み出る。
「明かりを。」
その貴族風の男は兵士から松明を受け取ると、私の頬の横に掲げ、顎を掴まれた。
松明の熱さと眩しさで目を細めた。
貴族風の男が王子様なのだろうか。と思うが、私としてはタイプではないので、ぜひチェンジして欲しい。この男がイケメンなのは認めるが、能面のような笑顔が、その目が、その口元が、薄気味悪いのだ。
「ふん、まぁまぁな女ではないか、連れていけ。」
彼の印象を決定づけたのは、ねっとりと私の顔を眺めまわした後、そう兵士に指示を出した言葉だった。
「ほら、歩け。」
さらに、兵士が後ろから乱暴に私の背中を小突く。痛みに顔をしかめながら振り返ると、剣の柄で私を小突いていた。
「…はぁ。」
私を取り囲む兵士に気付かれないようにため息をつく。本当に何なのだ、この夢は。
「あぁ、そうだ。」
歩き始めようとした時、先頭にいた貴族風の男がこちらに戻ってきた。
私は思わず身を強張らせる。
「君の名前を聞いていなかったね。何というんだい?」
三日月のような目が、私を捉えていた。
「美乃です、田辺美乃…。」
言ってしまってから、「しまった」と気付いた。適当な名前を言えば良かった。ルナとかアルテミアとか、そんなお姫様チックな名前を。
「そうか、ありがとう。ではこれから君を安全な場所に案内しよう。」
彼の吊り上がって笑う唇が酷く陰惨な笑みに見え、こんな男に本名を教えてしまった事に、脳をチリチリと焼くような焦燥感が起きる。
何かやってはいけない事をしてしまったような。
「そうだ、君がその手に持っている、その本も預かろう。森を歩くには重いだろう?」
手を伸ばす彼に言われて、自分が大切に本を抱きかかえていた事を思い出す。
薄気味悪く差し出された手に嫌悪感を覚えた私は答えた。
「いえ、これは大丈夫です。」
「いいから渡せと言っているんだ!」
だが彼は、手を伸ばして私の腕から本を奪い取ろうとする。
私は必死に抵抗しようとしたが、すぐに周りの兵士から腕をねじ上げられた。
「っ痛!」
激痛に本を取り落とした。貴族風の男が「ふん。」と一瞥して本を取り上げる。
私は痛む肩をさすりながら、周りの男たちを睨みつけた。と、同時に、「夢の中の、たかが訳の分からない本のために、なぜ私はこんなに必死になっているのだろう。」そんな冷静な考えがよぎった。
その時だった。
「やれやれ、また貧乏くじか。」
上空からそんなつぶやきが聞こえた。
上を見上げるも、白い霧の向こうに夜の闇が広がるばかりで、声の主は見つからない。
視線を下に戻した時、私の周りから松明の明かりが消えた。兵士たちの姿ごと消えてしまい、唐突に闇の中に取り残される。松明の明かりに慣れた目では、周りの何も見えない。
手探りのような格好で、二、三歩進んだ時、何かを蹴り飛ばした感覚がった。ゆっくりとしゃがんで、地面を手探りで探す。何かボールのようなものが指先に触れ、手繰り寄せて持ち上げる。少しずつ暗闇に慣れてきた目に、浮かび上がったそのシルエットを見て、思考が停止した。
理性が理解を拒否している。
本能が理解を拒否している。
遅れてやってきた強烈な鉄錆の臭いが、私を現実に引きずり戻した。
鉄錆の臭いが喉にこびりつき、悲鳴も上げられない。鉄錆の液体が指にこびりつき、手に持っているものを放り出すこともできない。
ただ、震える手に握っていたその頭部が、その男の虚ろな目が、私を縛り付けるように私を見ていた。
「っ来るなぁ!来るなよぉ‼」
男の甲高い叫びが、私の金縛りを解いた。同時に胃の中からありとあらゆる液体が逆流する。
慌てて男の頭部を手放し、地面に両手をついてうずくまる。
私が嘔吐した地面には、しかし。先に水たまりができていたようだ。嘔吐を終え、新鮮な空気を求めて息を吸った瞬間、またしても鉄錆の臭いが胸に広がる。落ち葉に覆われた地面でさえ、その水たまりを吸い込むのに難儀しているのだろう。
周囲に幾つも散乱する、首を失った胴体から流れ出す液体が、ゆっくりと私の意識を塗りつぶそうとしていた。
遠くでは、男が貧相な細剣を振り回しながら「鬼」だ「悪魔」だと喚いている。その前に舞い降りたのは、長い剣を持って静かに佇む、悪魔だった。いや死神だろうか。
いずれにしても、その背中に見える一組の翼は、天使の神々しいそれではなく、狂気と血に染まった漆黒の翼だった。
「悪夢にしても限度があるでしょ。」
それを声に出していたのか、それとも私の思考の中での独り言なのかは、朦朧とし始めた私には、もはや分からない。それでも、暗転する視界に私はむしろ安心感さえ覚えた。これでようやくこの悪夢から解放される。
「悪魔か。確かに、私は善人ではないよ。君と同じでね。」
その声と共に、甲高い断末魔が途絶えた。
同時に、私の意識も途絶えた。
――鉄錆の臭いに沈みゆく中、視界の端に、黄金の翼を見た気がした。
ゆっくりと意識が浮上するにつれて、頭痛もその激しさを増してきた。
鼻と喉には不快な臭いがこびりつき、呼吸もままならない。
「今日は休もう。」
最悪な夢見、最悪な気分だ。学校に行く気にはなれない。
毛布を抱きしめ、寝返りをうつ。ふと、カチャカチャと食器がぶつかる音が耳に入った。続いて、何かの花だろうか、鼻と喉を癒す良い香りがする。引いていく頭痛と不快な臭いに安堵する。でも誰だろう、お母さんだろうか。そもそも今何時だろう。
ゆっくりと目を開けた私が、ぼんやりと目にした景色は、私が見たことのないものだった。恐る恐る起き上がり、周りを見回す。
どこかの部屋のようだった。屋根も壁も木製。部屋の真ん中にある、小さな木製の丸机に、一人の少女がティーセットを並べていた。
「ごきげんよう。」
目が合った少女が微笑む。
「…誰?」
辛うじて私が絞り出した声はそれだった。
「え?ここどこ?」
少なくとも私の家ではない。夜の間に拉致されたのだろうか。寝ぼけたままの頭が混乱していた。
「はい、とりあえずカモミールティー。落ち着くわ?」
取り乱す私に、少女がティーカップを握らせる。触れ合った暖かな手のぬくもりと、自分の手に持ったカップから立ち上る香りで、私の喉が渇ききっていたことを思い出す。ベットに座り直し、一気に飲み干した。
「――っ。」
その紅茶は、今まで生きてきた中で一番美味しいと思える飲み物だった。喉から胃に流れ落ちていく温かい液体が、私を内側から癒してくれる。
「あの。」
ようやく意識が完全に覚醒し、まともに考える事ができるようになる。
「うん。なぁに?」
少女は微笑みを絶やさない。
「…猫?」
何から尋ねようか悩んだ挙句、口をついて出た言葉は、「何がどうなっているのか」という状況を尋ねるものではなく、そんなどうでもいいような事だった。
これは少女も予想外だったらしい。「あはは。」と可愛らしく笑った後、こう答えた。
「えぇ、そうなの。私、猫又よ?」
そう、猫なのだ。彼女の頭には猫のような三角の耳が生えている。先ほどから、ちらちらと背中から覗く細長くて柔軟な太い紐は、尻尾だ。ただし、そのきままに揺れる尻尾は二本生えている。
「夢か。」
眩暈を覚えて、額に手を置く。どうやら私はまだ悪夢の中にいるらしい。
そして、言葉に出してみると、なるほど今は夢の中にいるのだという確固たる確証が持てた。
「えぇ、そうよ、ここは夢の中。」
少女も私の言葉を肯定してくれる。私が少し落ち着いたと思ったのか、少女がさらに続けた。
「改めて、初めまして。私はチヒロ。ここは私の家の一室よ。」
「あ、はい、ありがとうございます。私は――」
私が返事をしようとすると、チヒロと名乗った少女が手で制した。
「あなたはまだ名乗らなくていいわ。幾つか伝えておきたいことがあるの。」
聞いてもらっても良いかしら?と首をかしげるチヒロさんに、私は頷いた。
「まず、先ほどの名乗り。決して本名を名乗らない事。絶対よ。」
私の脳裏に、さっきの夢の中で本名を名乗ってしまった事がよみがえった。
「これはどんなに親しい人に対しても知られてはダメ。ましてや初対面の相手なんか論外よ。」
片目をつぶり、人差し指を立てて断言するチヒロさんが続ける。
「だから、そうね。できるだけ早く、自分の名前を決めておいて。本名に被らないやつ。いわゆるペンネームとかハンドルネームみたいなものよ。」
「は、はぁ。」
良くわからないけれど、本名がダメなのは分かった。
「それと、この本。」
ベットの脇に置かれた、赤い装丁の本を指さす。それは私が夢の中で持っていたものだ。
「この本も、軽々しく人に渡さない事。捨てたりしたらダメよ?まぁ、こっちは信頼できる人になら貸すこともあるけれど…いえ、やっぱりダメね、基本的に人の手に渡したらダメ。大切に自分で保管すること。」
二本目の指を立て、そう言った。
「はい、分かりました。」
神妙に頷く。どちらももう破ってしまったけれど。
「後は…うーん。そうね、おいおい教えていきましょう。」
少し悩んだチヒロさんは、視線を宙に彷徨わせた後、そう言って手を叩いた。
「あなた、今自分が夢の中に居るっていう自覚はちゃんとあるのよね?」
正面から私の目を真っすぐに見つめて、問われる。
「は、はい。あります。」
迫力に押されて、頷いた。
「オッケー。じゃあ補足しておくわ。」
チヒロさんが三本目の指を立てた。
「これは、夢で現実に起きている世界。」
チヒロさんの言葉を脳内で反芻する。
「現実であって現実でない。夢であって夢でない。」
「…。」
私は何と答えていいのか分からなくなった。
「今の世界と、覚めてからの世界。どちらが夢なのか、私にも分からない。」
まるで催眠術のようだ。
「まぁ一言で言うなら。」
真面目な口調から、明るい口調に変わるチヒロさん。
「こっちの世界でも死んではダメよ。死んだら終わり。良いわね?」
再度真面目な口調で迫るチヒロさんに、全身の毛穴が開くような恐ろしさで鳥肌が立った。
どれくらい沈黙が支配しただろう。ふいに、部屋の扉がノックされた。
「チヒロ、俺だ。入っていいか?」
男性の野太い声。
「良い?」
チヒロさんが小声で私に尋ねる。私は小さくうなずいて、ベットの上で姿勢を正した。
「嬢ちゃんは目を覚ま…したようだな」
部屋に入りながらそう語った男性と目が合った。
いや、男性?思考が固まる。
「おう、俺はエリヤだ。よろしく。」
その挨拶もどこか遠く聞こえる。
「この子、びっくりしちゃってるじゃない。」
チヒロさんがその男性を肘で小突いた。
「えっと…。」
我に返って、何か話そうと言葉を探す。
「さっきも言った通り、彼はエリヤ。私たちのチームメイトみたいなもので、まぁ、見た目の通り、犬よ。」
チヒロさんがもう一度説明してくれる。うん、私の目がおかしいわけじゃない。犬だ。
チヒロさんは、少女だ。少女に、耳と尻尾が生えている。あくまで原型は少女だ。
だけどエリヤさんは…。犬。犬なのだ。直立二足歩行する、犬である。顔も、手も、胴体も、足も、どこをとっても、犬なのである。
「ちょっと待て。何度も言うが、俺は犬じゃない。狼だ。れっきとした狼男だ‼」
エリヤさんがチヒロさんに食って掛かる。
「見ろ、この肉体美!この筋肉!どっからどう見ても狼だろう?」
エリヤさんがそう言って、色んなポージングをしながら私に目配せをしてくる。
「…はい、そうですね。」
私はそう答えるしかない。
「良いのよー、無理してこいつに合わせなくても。――お手。」
チヒロさんが右手を出す。
「わん。」
エリヤさんが左手を乗せる。
「おかわり。」
「わん。」
左手を出したチヒロさんに、エリヤさんの右手が乗った。
「三回回ってワン。」
「わん、わん、わん。」
チヒロさんの指示に、エリヤさんが華麗な三回転を決めた。
「っておいこら何やらせんだ‼」
エリヤさんの怒りの突っ込みがチヒロさんに入った。
「っ、ふふふ。」
思わず笑ってしまう。
「あっははは。」
笑いだしたら止まらなくなってしまった。
最初は血みどろの悪夢だったけど、こんな夢なら面白い。
「まぁ、なんだ。しばらくはこのクランに居たらいい。歓迎するぜ。」
恥ずかしそうに後頭部を掻きながら、エリヤさんが言った。
「はい、ありがとうございます。」
改めて、エリヤさんにお辞儀をする。
「えっと、さっきの『くらん』って、何ですか?」
気になったので、聞いてみた。
「そうねぇ、まぁ、部活みたいなものかしら。」
チヒロさんが顎に手を当てて答えた。
「ゲームやるんなら、ギルドって言えば分かりやすいかもな。」
エリヤさんが補足する。
「あ、ギルドなら分かります。みんなで集まって、協力するんですよね?」
ゲームの他にも、色んな小説や漫画で出てくるから、なんとなく分かる。
「あら、ギルドで通じるなら良かったわ。そう、私たちはクラン…つまり、ギルドを運営してるの。」
そう言ってチヒロさんは笑った。
「クラン名は『アートルム・フェーレース』。通称『黒猫』よ?」
ピッタリでしょ?と耳を動かしながら笑うチヒロさん。
「へぇ、楽しそうですね!メンバーはお二人なんですか?」
私はチヒロさんとエリヤさんを交互に見て聞いた。
「ううん、他にも四人いるわ。」
チヒロさんが指を折る。
「まずはクランマスター…リーダーの事ね、の私。そして、エリヤ、ユキ、ホウ、ウェルス。あと、ここには居ないもう一人、ね。」
名前を列挙しながらチヒロさんは思い出したように続けた。
「――そうそう、ウェルスには後でお礼を言っておいてね?あなたがろくでもない連中に襲われているところを助けて、ここまで運んでくれたのは彼なんだら。」
とんでもない情報だった。
「え、本当ですか?ウェルスさん…彼?男の人なんですか⁉」
さっきの悪夢が蘇る。あんな地獄にさっそうと現れて私を助けてくれた人がいるなんて。しかも男性。これこそ王子様に違いない。
「え?うん、まぁ、男よ?」
私の食いつきにチヒロさんが若干引いたのが分かった。でも気にしない。
「イケメンですか?――いえ、大丈夫です。きっとイケメンです。自分で確かめます‼」
早口でまくし立てる私に、エリヤさんも後ずさった。
「おう、まぁ、イケメンと言えばイケメンだな。ちょいと…まぁ…とっつきにくい奴ではあるが。」
「影があるイケメンなんですね⁉それで、今どこにおられるんですか?」
エリヤさんの説明を脳内変換して、さらに身を乗り出す。
「えーっと。そうね、ウェルスは滅多に姿を見せないから。それに今日は遠出して戻らないわ。」
チヒロさんは、私の勢いに目を白黒させながら、そう答えてくれた。
「シャイな方なんですね!今日は居られない…なら、明日お礼を言います!」
しかしそう言って気付いた。明日も同じ夢を見るとは限らないし、夢なんて覚めたらすぐに忘れてしまうから今しかチャンスはないのでは。
「あぁ…。」
頭を抱える。どうすれば王子様に会えるのか。
そんな私をよそに、チヒロさんとエリヤさんが小声で話し合う。
「ユメミルオトメ。ってやつか?」
「そうねえ。ウェルスが何て言うかしら。」
「んなもん…なぁ?」
「男同士、あんたからウェルスに一言入れておいてよ。」
「なっ!それを言うなら、女同士、この嬢ちゃんのフォローをしろよ!」
という会話を知らず、私は二人に詰め寄った。
「お願いがあります‼」
「「はい‼」」
チヒロさんとエリヤさんの返事が重なった。
「何とか、今日中にお会いできませんか‼」
直立不動の二人に、手を合わせて頼み込む。
「うーん…。」
チヒロさんは渋い顔。
「無理やり呼び戻せんこともないがぁ…それをやると、ウェルスの旦那は相当不機嫌になると思うぞ。」
エリヤさんも難しい顔だ。
「私も、そのウェルスさんにご迷惑はかけたくないんですが、明日も同じ夢なんて見ないでしょうし…。」
もう一度頭を下げる。が、それを聞いたチヒロさんは笑ってこう言った。
「あぁ、なんだ、そんな心配なら大丈夫よ。ちゃんと明日もここの夢を見るわ。今日の続きをね。だから明日でも大丈夫よ?」
「そうだな。明日も夜になれば、お前さんはここに来るはずだぜ。」
エリヤさんも続いた。
「え?」
私は不思議に思う。どうしてそんな保証ができるんだろう。そもそも、この会話も夢の中の話だから、そういう風に都合よくできているのだろうか。
「さっき言った、夢と現実の話に戻ってしまうのだけれど…。」
そう言ってチヒロさんは思案顔になる。
「言葉であれこれ説明するより、一週間くらい実際に過ごした方が分かりやすいと思うわ?」
一週間?二日連続で同じ夢を見ることも滅多にないというのに、一週間?
「そうだな、嬢ちゃんは一日目だし、あんまり色々説明しても付いてこれんだろう。」
エリヤさんがうなる。確かに、現時点で私は話から置いてけぼりをくらっているようだ。
「今日はもう遅いわ。きっと大丈夫だから、安心して?また明日、ここで会いましょう。」
そう言ってチヒロさんは微笑んだ。

チヒロ
寄稿:Twitter @pn_k2 紅火様
ありがとうございます。
聞こえる音はどこかくぐもり、
見える景色は波間に歪み、
水に搦め取られた体は動かず、
仄かな意識の中、呼吸さえ忘れて、
私は、
私を眺めているだけでした。
書庫の通路を歩きながら、漠然と「これは夢だな」という認識をした。
しかし、「ここはどこ?」という質問をされたらどう答えればいいのだろう。
「夢の中」と答えるのが正しいのか、「図書室の書庫」と答えるのが正しいのか。
では、「私は誰?」という質問にはどう答えればいいだろう。ぼうっとした意識の中でまどろみながら考える。目の前で長い髪を揺らし、つま先立ちになりながら懸命に本に手を伸ばす私が「私」なのだろうか。それとも、そんな私を眺めている私が「私」なのだろうか。
目の前の私が、自分の身長より高い書庫の本棚から、無理やり本を取り出した反動で尻もちをついた。床に積もった埃が、私を包み込むように舞い上がる。その灰色を切り裂くように、金色の羽が一つ、輝きながら舞い降りる。
埃を吸い込み激しく咳き込みながら、私はその金色の羽をを拾い上げて、大切に抱きかかえていた本の間に挟んだ。
服についた埃を軽くはたいて、通路を挟んだ向かい側、螺旋階段の前へ行く。ポケットから取り出した鍵を挿すと、南京錠はその重厚さに似つかわしくない軽い音で開いた。そして、扉に幾重にも巻き付けられた鎖を引きはがして床に打ち捨てる。「ジャラリ」と軋む鎖を踏みしめて、螺旋階段に足をかけた。
階上は、円形状の小さな一室だった。置かれているものは本棚が一つだけ、壁の大窓は開かれ、穏やかな風と茜色の光を呼び込んでいた。
「――。」
窓から半身を乗り出して大きく息を吐きだした。この茜色の空は朝日だろうか、夕日だろうか。そんな他愛もない思案をした時だった。
「ヒメタルモノヨ。」
声、というにはあまりにも強い響きが世界に充満した。
耳だけでなく、世界に存在する全ての生きとし生けるものを震わせるほどの「声」が直接私に迫る。
「誰!何?」
半ば絶叫するように、声の主を探して振り返る。
――振り返った私と、私を見ていた私の、目が合った。
刹那。
「――っぐ!」
視界が脈打ち、強烈な頭痛が私を襲う。朦朧とする私の意識を繋ぎとめたのは呼吸困難。嘔吐するように息を絞り出す。息が吸い込めず、思わず喉を掻きむしった。
「夢なのに、痛くて、苦しい?」
陸に上がったばかりの人魚のように、ヒューヒューと喉が鳴り、四つん這いで赤い絨毯をを掻きむしる。
「ゲホッ!カハッ!」
大きな咳と共に涙と唾を撒き散らして、ようやく意識が鮮明になりつつあった。
緩やかに回復していく意識と視界、そして思考で、真っ先に感じ取ったのは違和感だった。
「うぅ・・・。」
頭痛はまだ消えない。頭に手を置いたまま、よろめく足でゆっくりと立ち上がった。
「やっぱり。」
声に出して呟く。何かが違う、先ほどまでと、何かが。
本棚に身体を預けて、もう一度窓の外に視線を向ける。空の茜色は、その赤さをさらに増しつつあった。
「ここから出よう。」
震える身体を必死に両腕で抱きしめながら、転がり落ちるように螺旋階段を降りた。
降りた先、目の前に広がるのは鬱蒼とした森林だった。
「はは、やっぱり夢か。」
こめかみを揉みほぐしながら再確認する。
最初に私がいたのは学校の書庫。学校の周りは閑静な住宅街で、こんな森はない。ふと後ろを振り返ると、降りてきたはずの螺旋階段も消えていた。
これを夢と呼ばずして何と呼ぶのか。
「めちゃくちゃ生々しい夢だけど。」
大きく深呼吸して、気持ちを落ち着かせる。木々の隙間から見上げる空は、急速に黒くなっていく。先ほどの茜色は、どうやら夕焼けだったようだ。
「ヒメタルモノヨ。」
再度、世界が揺り動かされる。軋む頭を抱えながら、膝から崩れ落ちた。
「こんな夢、早く覚めて。」
呻くように吐き捨てた。こんな不快な夢にどんな意味があるんだろう。というか、こんなに苦しいなら覚醒してもおかしくないはずなのに。
荒い呼吸を整えながら、恐る恐る周囲を見渡す。声の主はいったい誰なのか。もしくは何なのか。
その時、閃くように一つの答えが分かった。声の主についてではない、先ほど感じた違和感の正体である。
先ほどまで、私は「第三者的な視点」でこの夢を傍観していた。夢の中に田辺美乃という登場人物が居て、その登場人物を眺める私が居た。
それが今はどうだろう、私は私だ。私は私を眺めてはいないし、私を眺めている私も居ない。
「まぁ、だからどうしたって話なんだけどね。」
夢の中身について真面目に考察したところで何の意味もないだろう。
震える足で立ち上がりながら、もう一度周囲を見渡した。夜の帳が降り、世界を闇が支配しようとしていた。
しかもそれだけでなく、視界が白み始める。やっと夢から覚めるのだろうかと期待したが、目を凝らすと、それは木々の間に揺らめく霧であった。
森は霧に沈み、闇が蓋をしようとしていた。
月は、まだ出ていない。
開始―別視点/???ー
綺麗に切りそろえられた短冊に、美しい紋様を描きながら、少女は一つため息をついた。開け放たれた大窓から入り込む夜の冷気が、机上の蝋燭をかすかに揺らす。
「早かったのね、何かあった?」
筆を置き、背後の闇に問いかける。
「ほ、ほ、ほ。」
闇は静かに、そして穏やかに笑った。そして短く報告した。
「人が、一人。」
「…強いの?」
少女は少し考えて問うた。人が一人現れたくらいのよくある状況で、彼がわざわざ戻って報告するはずはない。
「いいえ。」
しかし彼の答えは、予想に反して、短い否定の言葉だけだった。
少女は後ろを振り返り、彼を見る。彼の丸い双眸が、机上の蝋燭を映して黄色く輝いていた。
「宝具を、二つ。」
無言で彼に続きを促すと、またしても予想外の答えが返ってきた。
「現れてすぐに誰かから奪ったってこと?」
唯一の可能性を挙げる。その可能性とて、限りなく低い可能性と知りながら。
「いいえ、最初から。」
彼の断言を聞き、少女の頬が微かに赤む。
「馬鹿な。ありえない。」
強く頭を振る。誰でも現れた時は、宝具は一人に一つ。例外は見たことも聞いたこともない。許されるはずもない。誰かから奪わなければ、複数持てるはずはない。
「我が目を、疑いました。」
絶句する私に、彼の双眸が俯いた。
「…えぇ、私も信じられないけれど…いえ、信じるわ、あなたを。」
何故なら、それが彼の宝具なのだから。
「それから、もう一つ。」
静かに彼は続けた。少女はその三角の耳をピクリと動かして傾聴した。
「人狩りが、近付いております。」
「――ウェルス‼」
彼の言葉がまだ言い終わらないうちに、少女の鋭い声が飛んだ。
彼女に答えるように、翼が風を巻き上げる音が響いた。
終了―別視点/???ー
かさり、と足元で落ち葉が鳴る。
私は白い海の中を彷徨っていた。
「なんだかなぁ。」
つま先で落ち葉を蹴り上げる。湿った落ち葉は、それほど巻き上がることもなく、静かに地面に戻っていく。
私はまだ夢から覚めないでいた。「これは夢だ」という強烈な自覚があるにも関わらず、頬をつねっても頭を叩いても夢の中だ。
「夢ならせめて面白いことがあるとかさあ?」
森の木々を相手に愚痴る。その場でじっとしていても良かったのかもしれないが、夢の中とはいえ、暗い森の中で膝を抱えて朝の目覚めを待つよりは、体を動かしている方が気が紛れた。
「王子様が迎えに来てくれるとかさ。」
もちろん現実ではそんな事は言わない。夢の中、私の妄想の中だからこそ言うのだ。自分の都合の良いように夢が展開しないかと。
「――!」
ふと立ち止まる。誰かの気配がした。
「――!」
聞こえる、遠くで誰かが叫んでいる。
できるだけ息を潜め、耳をそばだてる。白馬に乗った王子様なら構わないが、大熊やドラキュラみたいな化け物だったらたまらない。
「誰かいるか?」
ようやく聞き取れるまでに近付いた声は、人間の物だった。
続いて霧の中に蛍のような光球が幾つも浮かび上がる。そしてガチャガチャという金属の擦れあう音も。どうやら一人ではないようだ。
「すみませーん!」
意を決して大声を上げる。少し迷ったが、このまま一人で彷徨い続けるよりは良いだろう。
「誰かいるぞ!」
「こっちだ!」
「明かりを!松明を持ってこい!」
幾人もの男性の声が響いて、蛍のような明かりが私を取り囲んだ。
「何者だ!」
霧の中からゆっくりと姿を現した男性は、右手に抜身の剣を、左手に松明を持っていた。全身は金属の甲冑で覆われている。
「えっと、学生です?」
現れた男性の容姿に驚いて、声が尻すぼみになってしまう。
全身甲冑に剣、明かりは松明。これは中世風の夢なのだろうか?
少し考えてすぐに都合の良い結論にたどり着いた。
「あ、えと、お姫様。です。」
できる限り笑顔で、そして相手に聞こえるように大きな声で返事をする。
これが兵士なら、きっと王子様も居るはずだ。そしてその王子様は私を探しているはず――。
「はぁ?」
しかし、兵士の反応は予想外に冷たいものだった。その返事には嘲笑すら感じられる。
「えっと…。」
私は二の句が継げなくなってしまう。
その時、兵士の後ろからパンパンと手を叩く音が聞こえた。
足音と共に、兵士の囲みが割れ、美しい服を着た貴族風の男が進み出る。
「明かりを。」
その貴族風の男は兵士から松明を受け取ると、私の頬の横に掲げ、顎を掴まれた。
松明の熱さと眩しさで目を細めた。
貴族風の男が王子様なのだろうか。と思うが、私としてはタイプではないので、ぜひチェンジして欲しい。この男がイケメンなのは認めるが、能面のような笑顔が、その目が、その口元が、薄気味悪いのだ。
「ふん、まぁまぁな女ではないか、連れていけ。」
彼の印象を決定づけたのは、ねっとりと私の顔を眺めまわした後、そう兵士に指示を出した言葉だった。
「ほら、歩け。」
さらに、兵士が後ろから乱暴に私の背中を小突く。痛みに顔をしかめながら振り返ると、剣の柄で私を小突いていた。
「…はぁ。」
私を取り囲む兵士に気付かれないようにため息をつく。本当に何なのだ、この夢は。
「あぁ、そうだ。」
歩き始めようとした時、先頭にいた貴族風の男がこちらに戻ってきた。
私は思わず身を強張らせる。
「君の名前を聞いていなかったね。何というんだい?」
三日月のような目が、私を捉えていた。
「美乃です、田辺美乃…。」
言ってしまってから、「しまった」と気付いた。適当な名前を言えば良かった。ルナとかアルテミアとか、そんなお姫様チックな名前を。
「そうか、ありがとう。ではこれから君を安全な場所に案内しよう。」
彼の吊り上がって笑う唇が酷く陰惨な笑みに見え、こんな男に本名を教えてしまった事に、脳をチリチリと焼くような焦燥感が起きる。
何かやってはいけない事をしてしまったような。
「そうだ、君がその手に持っている、その本も預かろう。森を歩くには重いだろう?」
手を伸ばす彼に言われて、自分が大切に本を抱きかかえていた事を思い出す。
薄気味悪く差し出された手に嫌悪感を覚えた私は答えた。
「いえ、これは大丈夫です。」
「いいから渡せと言っているんだ!」
だが彼は、手を伸ばして私の腕から本を奪い取ろうとする。
私は必死に抵抗しようとしたが、すぐに周りの兵士から腕をねじ上げられた。
「っ痛!」
激痛に本を取り落とした。貴族風の男が「ふん。」と一瞥して本を取り上げる。
私は痛む肩をさすりながら、周りの男たちを睨みつけた。と、同時に、「夢の中の、たかが訳の分からない本のために、なぜ私はこんなに必死になっているのだろう。」そんな冷静な考えがよぎった。
その時だった。
「やれやれ、また貧乏くじか。」
上空からそんなつぶやきが聞こえた。
上を見上げるも、白い霧の向こうに夜の闇が広がるばかりで、声の主は見つからない。
視線を下に戻した時、私の周りから松明の明かりが消えた。兵士たちの姿ごと消えてしまい、唐突に闇の中に取り残される。松明の明かりに慣れた目では、周りの何も見えない。
手探りのような格好で、二、三歩進んだ時、何かを蹴り飛ばした感覚がった。ゆっくりとしゃがんで、地面を手探りで探す。何かボールのようなものが指先に触れ、手繰り寄せて持ち上げる。少しずつ暗闇に慣れてきた目に、浮かび上がったそのシルエットを見て、思考が停止した。
理性が理解を拒否している。
本能が理解を拒否している。
遅れてやってきた強烈な鉄錆の臭いが、私を現実に引きずり戻した。
鉄錆の臭いが喉にこびりつき、悲鳴も上げられない。鉄錆の液体が指にこびりつき、手に持っているものを放り出すこともできない。
ただ、震える手に握っていたその頭部が、その男の虚ろな目が、私を縛り付けるように私を見ていた。
「っ来るなぁ!来るなよぉ‼」
男の甲高い叫びが、私の金縛りを解いた。同時に胃の中からありとあらゆる液体が逆流する。
慌てて男の頭部を手放し、地面に両手をついてうずくまる。
私が嘔吐した地面には、しかし。先に水たまりができていたようだ。嘔吐を終え、新鮮な空気を求めて息を吸った瞬間、またしても鉄錆の臭いが胸に広がる。落ち葉に覆われた地面でさえ、その水たまりを吸い込むのに難儀しているのだろう。
周囲に幾つも散乱する、首を失った胴体から流れ出す液体が、ゆっくりと私の意識を塗りつぶそうとしていた。
遠くでは、男が貧相な細剣を振り回しながら「鬼」だ「悪魔」だと喚いている。その前に舞い降りたのは、長い剣を持って静かに佇む、悪魔だった。いや死神だろうか。
いずれにしても、その背中に見える一組の翼は、天使の神々しいそれではなく、狂気と血に染まった漆黒の翼だった。
「悪夢にしても限度があるでしょ。」
それを声に出していたのか、それとも私の思考の中での独り言なのかは、朦朧とし始めた私には、もはや分からない。それでも、暗転する視界に私はむしろ安心感さえ覚えた。これでようやくこの悪夢から解放される。
「悪魔か。確かに、私は善人ではないよ。君と同じでね。」
その声と共に、甲高い断末魔が途絶えた。
同時に、私の意識も途絶えた。
――鉄錆の臭いに沈みゆく中、視界の端に、黄金の翼を見た気がした。
ゆっくりと意識が浮上するにつれて、頭痛もその激しさを増してきた。
鼻と喉には不快な臭いがこびりつき、呼吸もままならない。
「今日は休もう。」
最悪な夢見、最悪な気分だ。学校に行く気にはなれない。
毛布を抱きしめ、寝返りをうつ。ふと、カチャカチャと食器がぶつかる音が耳に入った。続いて、何かの花だろうか、鼻と喉を癒す良い香りがする。引いていく頭痛と不快な臭いに安堵する。でも誰だろう、お母さんだろうか。そもそも今何時だろう。
ゆっくりと目を開けた私が、ぼんやりと目にした景色は、私が見たことのないものだった。恐る恐る起き上がり、周りを見回す。
どこかの部屋のようだった。屋根も壁も木製。部屋の真ん中にある、小さな木製の丸机に、一人の少女がティーセットを並べていた。
「ごきげんよう。」
目が合った少女が微笑む。
「…誰?」
辛うじて私が絞り出した声はそれだった。
「え?ここどこ?」
少なくとも私の家ではない。夜の間に拉致されたのだろうか。寝ぼけたままの頭が混乱していた。
「はい、とりあえずカモミールティー。落ち着くわ?」
取り乱す私に、少女がティーカップを握らせる。触れ合った暖かな手のぬくもりと、自分の手に持ったカップから立ち上る香りで、私の喉が渇ききっていたことを思い出す。ベットに座り直し、一気に飲み干した。
「――っ。」
その紅茶は、今まで生きてきた中で一番美味しいと思える飲み物だった。喉から胃に流れ落ちていく温かい液体が、私を内側から癒してくれる。
「あの。」
ようやく意識が完全に覚醒し、まともに考える事ができるようになる。
「うん。なぁに?」
少女は微笑みを絶やさない。
「…猫?」
何から尋ねようか悩んだ挙句、口をついて出た言葉は、「何がどうなっているのか」という状況を尋ねるものではなく、そんなどうでもいいような事だった。
これは少女も予想外だったらしい。「あはは。」と可愛らしく笑った後、こう答えた。
「えぇ、そうなの。私、猫又よ?」
そう、猫なのだ。彼女の頭には猫のような三角の耳が生えている。先ほどから、ちらちらと背中から覗く細長くて柔軟な太い紐は、尻尾だ。ただし、そのきままに揺れる尻尾は二本生えている。
「夢か。」
眩暈を覚えて、額に手を置く。どうやら私はまだ悪夢の中にいるらしい。
そして、言葉に出してみると、なるほど今は夢の中にいるのだという確固たる確証が持てた。
「えぇ、そうよ、ここは夢の中。」
少女も私の言葉を肯定してくれる。私が少し落ち着いたと思ったのか、少女がさらに続けた。
「改めて、初めまして。私はチヒロ。ここは私の家の一室よ。」
「あ、はい、ありがとうございます。私は――」
私が返事をしようとすると、チヒロと名乗った少女が手で制した。
「あなたはまだ名乗らなくていいわ。幾つか伝えておきたいことがあるの。」
聞いてもらっても良いかしら?と首をかしげるチヒロさんに、私は頷いた。
「まず、先ほどの名乗り。決して本名を名乗らない事。絶対よ。」
私の脳裏に、さっきの夢の中で本名を名乗ってしまった事がよみがえった。
「これはどんなに親しい人に対しても知られてはダメ。ましてや初対面の相手なんか論外よ。」
片目をつぶり、人差し指を立てて断言するチヒロさんが続ける。
「だから、そうね。できるだけ早く、自分の名前を決めておいて。本名に被らないやつ。いわゆるペンネームとかハンドルネームみたいなものよ。」
「は、はぁ。」
良くわからないけれど、本名がダメなのは分かった。
「それと、この本。」
ベットの脇に置かれた、赤い装丁の本を指さす。それは私が夢の中で持っていたものだ。
「この本も、軽々しく人に渡さない事。捨てたりしたらダメよ?まぁ、こっちは信頼できる人になら貸すこともあるけれど…いえ、やっぱりダメね、基本的に人の手に渡したらダメ。大切に自分で保管すること。」
二本目の指を立て、そう言った。
「はい、分かりました。」
神妙に頷く。どちらももう破ってしまったけれど。
「後は…うーん。そうね、おいおい教えていきましょう。」
少し悩んだチヒロさんは、視線を宙に彷徨わせた後、そう言って手を叩いた。
「あなた、今自分が夢の中に居るっていう自覚はちゃんとあるのよね?」
正面から私の目を真っすぐに見つめて、問われる。
「は、はい。あります。」
迫力に押されて、頷いた。
「オッケー。じゃあ補足しておくわ。」
チヒロさんが三本目の指を立てた。
「これは、夢で現実に起きている世界。」
チヒロさんの言葉を脳内で反芻する。
「現実であって現実でない。夢であって夢でない。」
「…。」
私は何と答えていいのか分からなくなった。
「今の世界と、覚めてからの世界。どちらが夢なのか、私にも分からない。」
まるで催眠術のようだ。
「まぁ一言で言うなら。」
真面目な口調から、明るい口調に変わるチヒロさん。
「こっちの世界でも死んではダメよ。死んだら終わり。良いわね?」
再度真面目な口調で迫るチヒロさんに、全身の毛穴が開くような恐ろしさで鳥肌が立った。
どれくらい沈黙が支配しただろう。ふいに、部屋の扉がノックされた。
「チヒロ、俺だ。入っていいか?」
男性の野太い声。
「良い?」
チヒロさんが小声で私に尋ねる。私は小さくうなずいて、ベットの上で姿勢を正した。
「嬢ちゃんは目を覚ま…したようだな」
部屋に入りながらそう語った男性と目が合った。
いや、男性?思考が固まる。
「おう、俺はエリヤだ。よろしく。」
その挨拶もどこか遠く聞こえる。
「この子、びっくりしちゃってるじゃない。」
チヒロさんがその男性を肘で小突いた。
「えっと…。」
我に返って、何か話そうと言葉を探す。
「さっきも言った通り、彼はエリヤ。私たちのチームメイトみたいなもので、まぁ、見た目の通り、犬よ。」
チヒロさんがもう一度説明してくれる。うん、私の目がおかしいわけじゃない。犬だ。
チヒロさんは、少女だ。少女に、耳と尻尾が生えている。あくまで原型は少女だ。
だけどエリヤさんは…。犬。犬なのだ。直立二足歩行する、犬である。顔も、手も、胴体も、足も、どこをとっても、犬なのである。
「ちょっと待て。何度も言うが、俺は犬じゃない。狼だ。れっきとした狼男だ‼」
エリヤさんがチヒロさんに食って掛かる。
「見ろ、この肉体美!この筋肉!どっからどう見ても狼だろう?」
エリヤさんがそう言って、色んなポージングをしながら私に目配せをしてくる。
「…はい、そうですね。」
私はそう答えるしかない。
「良いのよー、無理してこいつに合わせなくても。――お手。」
チヒロさんが右手を出す。
「わん。」
エリヤさんが左手を乗せる。
「おかわり。」
「わん。」
左手を出したチヒロさんに、エリヤさんの右手が乗った。
「三回回ってワン。」
「わん、わん、わん。」
チヒロさんの指示に、エリヤさんが華麗な三回転を決めた。
「っておいこら何やらせんだ‼」
エリヤさんの怒りの突っ込みがチヒロさんに入った。
「っ、ふふふ。」
思わず笑ってしまう。
「あっははは。」
笑いだしたら止まらなくなってしまった。
最初は血みどろの悪夢だったけど、こんな夢なら面白い。
「まぁ、なんだ。しばらくはこのクランに居たらいい。歓迎するぜ。」
恥ずかしそうに後頭部を掻きながら、エリヤさんが言った。
「はい、ありがとうございます。」
改めて、エリヤさんにお辞儀をする。
「えっと、さっきの『くらん』って、何ですか?」
気になったので、聞いてみた。
「そうねぇ、まぁ、部活みたいなものかしら。」
チヒロさんが顎に手を当てて答えた。
「ゲームやるんなら、ギルドって言えば分かりやすいかもな。」
エリヤさんが補足する。
「あ、ギルドなら分かります。みんなで集まって、協力するんですよね?」
ゲームの他にも、色んな小説や漫画で出てくるから、なんとなく分かる。
「あら、ギルドで通じるなら良かったわ。そう、私たちはクラン…つまり、ギルドを運営してるの。」
そう言ってチヒロさんは笑った。
「クラン名は『アートルム・フェーレース』。通称『黒猫』よ?」
ピッタリでしょ?と耳を動かしながら笑うチヒロさん。
「へぇ、楽しそうですね!メンバーはお二人なんですか?」
私はチヒロさんとエリヤさんを交互に見て聞いた。
「ううん、他にも四人いるわ。」
チヒロさんが指を折る。
「まずはクランマスター…リーダーの事ね、の私。そして、エリヤ、ユキ、ホウ、ウェルス。あと、ここには居ないもう一人、ね。」
名前を列挙しながらチヒロさんは思い出したように続けた。
「――そうそう、ウェルスには後でお礼を言っておいてね?あなたがろくでもない連中に襲われているところを助けて、ここまで運んでくれたのは彼なんだら。」
とんでもない情報だった。
「え、本当ですか?ウェルスさん…彼?男の人なんですか⁉」
さっきの悪夢が蘇る。あんな地獄にさっそうと現れて私を助けてくれた人がいるなんて。しかも男性。これこそ王子様に違いない。
「え?うん、まぁ、男よ?」
私の食いつきにチヒロさんが若干引いたのが分かった。でも気にしない。
「イケメンですか?――いえ、大丈夫です。きっとイケメンです。自分で確かめます‼」
早口でまくし立てる私に、エリヤさんも後ずさった。
「おう、まぁ、イケメンと言えばイケメンだな。ちょいと…まぁ…とっつきにくい奴ではあるが。」
「影があるイケメンなんですね⁉それで、今どこにおられるんですか?」
エリヤさんの説明を脳内変換して、さらに身を乗り出す。
「えーっと。そうね、ウェルスは滅多に姿を見せないから。それに今日は遠出して戻らないわ。」
チヒロさんは、私の勢いに目を白黒させながら、そう答えてくれた。
「シャイな方なんですね!今日は居られない…なら、明日お礼を言います!」
しかしそう言って気付いた。明日も同じ夢を見るとは限らないし、夢なんて覚めたらすぐに忘れてしまうから今しかチャンスはないのでは。
「あぁ…。」
頭を抱える。どうすれば王子様に会えるのか。
そんな私をよそに、チヒロさんとエリヤさんが小声で話し合う。
「ユメミルオトメ。ってやつか?」
「そうねえ。ウェルスが何て言うかしら。」
「んなもん…なぁ?」
「男同士、あんたからウェルスに一言入れておいてよ。」
「なっ!それを言うなら、女同士、この嬢ちゃんのフォローをしろよ!」
という会話を知らず、私は二人に詰め寄った。
「お願いがあります‼」
「「はい‼」」
チヒロさんとエリヤさんの返事が重なった。
「何とか、今日中にお会いできませんか‼」
直立不動の二人に、手を合わせて頼み込む。
「うーん…。」
チヒロさんは渋い顔。
「無理やり呼び戻せんこともないがぁ…それをやると、ウェルスの旦那は相当不機嫌になると思うぞ。」
エリヤさんも難しい顔だ。
「私も、そのウェルスさんにご迷惑はかけたくないんですが、明日も同じ夢なんて見ないでしょうし…。」
もう一度頭を下げる。が、それを聞いたチヒロさんは笑ってこう言った。
「あぁ、なんだ、そんな心配なら大丈夫よ。ちゃんと明日もここの夢を見るわ。今日の続きをね。だから明日でも大丈夫よ?」
「そうだな。明日も夜になれば、お前さんはここに来るはずだぜ。」
エリヤさんも続いた。
「え?」
私は不思議に思う。どうしてそんな保証ができるんだろう。そもそも、この会話も夢の中の話だから、そういう風に都合よくできているのだろうか。
「さっき言った、夢と現実の話に戻ってしまうのだけれど…。」
そう言ってチヒロさんは思案顔になる。
「言葉であれこれ説明するより、一週間くらい実際に過ごした方が分かりやすいと思うわ?」
一週間?二日連続で同じ夢を見ることも滅多にないというのに、一週間?
「そうだな、嬢ちゃんは一日目だし、あんまり色々説明しても付いてこれんだろう。」
エリヤさんがうなる。確かに、現時点で私は話から置いてけぼりをくらっているようだ。
「今日はもう遅いわ。きっと大丈夫だから、安心して?また明日、ここで会いましょう。」
そう言ってチヒロさんは微笑んだ。

チヒロ
寄稿:Twitter @pn_k2 紅火様
ありがとうございます。