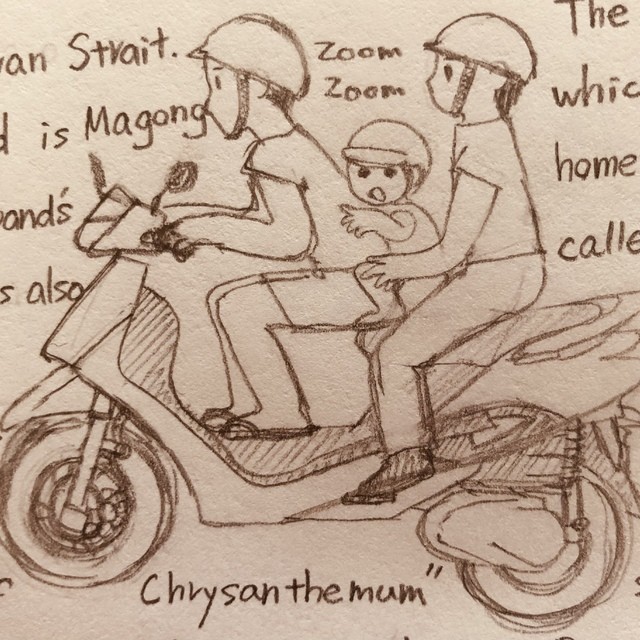ハープーン①
文字数 3,086文字
海面に上昇していくときには、太陽に向かって泳いでいくような気持ちになる。空と海が水のスクリーンで混ざって、世界が反転しているように見えるのだ。
「サク!」
漁が終わって船着場へ戻ってくると、ルカが待っていた。周りの作業員たちは、彼の顔の傷を遠巻きに見ているようだが、本人は気にせず船に近寄ってくる。
「ルカ、何かあったの」
鮑の籠を下ろしながら尋ねると、ルカは『大漁だな』と覗き込みながら言う。近くで横顔を見ると、少し痩せたかもしれない。根を詰めているか、不摂生しているか、多分どっちもだろう。
「試運転だ」
「スクリュー船の? 完成したんだね」
「まだ課題は有るんだけどな。ミスターローランドも立ち会うぞ」
お前も見にくるかと思って。隈の浮いた目元で笑う。やれやれ、ジナが心配して怒っている様子が目に浮かぶ。
「今から?」
「ああ、ミスタードーソンが操縦したがってるとかで……。何者なんだ、あの人」
そういえば元アメリカ海兵なんだっけ、と思い出す。海賊の間違いじゃなかろうか。ミスターローランドとセシル・ドーソンが対面するところには、あまりかなり居合わせたくないが、新しい船は見てみたい。
「……これ一個高いのか?」
ルカが鮑を指差して言う。思惑は分かっている。ジナに食べさせてやりたいのだ。俺は態とらしくルカの耳元に囁く。
「小売価格は知らないけど、一個採ると、俺たちに支払われるのはね……」
「マジか。ピット爺さんが言ってたのは本当だな」
「今度漁場以外で採れたら、工場の方へ持っていくよ」
仕事中に採ったものを私的に流用すると、バレたら多分セシル・ドーソンに殴られる。馬鹿、金になるモンを金にしないでどうする、お前が働いた対価だろうが。二人でこそこそ話していると、リャンが通りかかった。身に付けている革紐と鯱の牙のチョーカーは、ジナが作ったものだ。おうリャン、とルカは気軽に声をかける。
「久しぶりだな」
こくり、とリャンは頷く。他のダイバーたちとも仕事以外ではほとんど話しているところを見かけないが、この二人はそれなりに親しいらしい。もやもやとした気分になって一歩下がった俺を、ルカは可笑しそうに小突く。
「よかったな、一緒に仕事ができるようになって」
どういう意味。ずっと俺が気にしてたから? それとも潜水技術が追いついてきてるってこと? 実際のところ、リャンは俺に鮑採りについていろいろと教えてはくれるが、生い立ちや私生活について話したことはほとんどない。要するに、仕事においても、友人としても、信頼に値すると思われていないのだ。勝手に考え込んで勝手に落ち込んでいる俺を気にもとめず、ルカはリャンに向かって続ける。
「造船所で新しく造ったスクリュー船の試運転なんだ。お前も見にくるか」
「うん」
「え、リャン、船好きなの」
思わず声を上げてしまい、リャンがまたあの迷惑そうな顔をする。ルカは楽しげに言う。
「機械が面白いのは、人間がつくり出したからだよな」
「うん」
だからどういう意味。なんで二人して分かったような感じなの。もしかしてこの二人、口数が違うだけで結構似ているのかもしれない。なんて言うんだっけ、ええと、ツンデレ?
セント・ヘレナの港に、新しい汽船が泊まっている。午後の遅い光の中で、その優雅で強靭な曲線を晒す姿はまるで、大きな王冠のようだ。俺は見上げて溜め息を吐いた。リャンも隣りで目を細めて、機関部から伸びる煙突の先を見ている。すると甲板から人影が躍り出た。
「乗船したまえ、出航だ!」
舵を取るのはセシル・ドーソンである。その隣りにはフロック・コートを纏いステッキを持ったミスターローランドが立ち並ぶ。鐘の音が鳴り響く。誰よりも速く遠く、まだ人々は、自分がどこを目指しているのかも知らない。
***
潮風を切って、船は進む。船大工たちは機関室と船尾を行ったり来たりして記録を取っている。俺は邪魔しないように甲板の端で、流れる風景を見ていた。操舵室からミスターローランドどセシル・ドーソンの、議論しているのだか、ケンカしているのだが、漫才しているのだか分からない声が響いてくる。
「大洋に出る」
「許可するが、陸棚 に沿って走航しろ」
「大丈夫だろ? 安定はよさそうだぜ、速度は出んが」
どうやら湾外にまで航行するつもりらしい。船大工たちは波が泡が水が燃料がとばたばたし始める。ピット爺さんだけは、ずっと船尾に立って航跡を見つめている。リャンはどこだろうかと甲板を見渡すと、操舵室の影に隠れるようにして佇んでいた。
「リャン、気分悪いの?」
いつも顔色は良くないのだが、大きな目が苦痛に歪んでいるように見えた。港に着いた時には、颯爽としていてなんともなかった。船酔いなどするはずもない。うつむき加減の肩に触れると、ひどく冷えていた。
「……湾の外に出たくない」
細い声が震えている。もう平気になったと思ってたのに、と俺の手を振り解くが、船の揺れによろけそうになる。
「どうして?」
「思い出すからだ、ここへ来た時を」
喉元を掻いて、出ない声を無理に押し出すように話す。俺は見たことのないリャンの怒りだか憎しみだかが暗く燻った呻きに動揺して、立ち尽くした。
「逃げてきたんだ、本島の鉱山から」
清の漁村から売られてきた苦力 で、俺は主人に従って石炭や黄金を掘らなければならなかった。厳しい労働と、主人や年長の苦力たちからの折檻が辛くて、俺はある日見張りを掻い潜った。どんなに駆けても、ろくに食べていない少年の足ではそんなに遠くまで行ける訳でもない。けれど幸か不幸かセシル・ドーソンに拾われて、ここに連れてこられた。
「本島から客船に乗って、ヴァン・ディエメンに来た日を覚えてる」
よほど、あのきらきらとした波に跳び込めば、楽になるのかと、思っていたのだ。俺は何も言えなかった。現代の世界にも、実質的な奴隷労働はいくらでもある。けれど、俺自身が経験してきたことや、未来にはまず起こらない。俺は恵まれた生まれなのだ。そして、どうしようもなく、無知だ。リャン、と俺はなんとか名前を呼ぼうとした。
「おいおいおい、たまげたな!」
背後の操舵室から、セシル・ドーソンの興が乗りすぎた声が叫んだ。途端に、横波に叩かれて、船が大きく揺れる。俺とリャンは甲板に転がった。身体の節々をぶつけて目がチカチカするが、俺の腰の上に倒れ込んだリャンを支えて、俺はなんとか上体を起こした。その視界に、天の半分を覆う鋼 の翼がひるがえる。
皇后 !
俺は嘆息を吐いた。いつの間に近付いていたのか、漆黒のベールをはためかせるように、銀の飛沫を巻き上げて、優雅にブリーチする。まさに皇后の名にふさわしい。
「退避しろ、セシル!」
「スクリュー船は曲がれんよ、ブランディ。しかし気の強い女だな!」
ミスターローランドの叱咤と、セシル・ドーソンの興奮で上擦った声が聞こえる。がくんとスクリューの回転方向が変わり、船体が後退を始めたのが分かるが、皇后は取り巻くように、巨大な体躯で弧を描く。俺は見惚れて座り込んでいたが、皇后の側にほろほろと瞬く小さな影に気が付いた。こちらも呆然としているリャンの腕を引っ張って、指をさす。
「リャン、見て、仔クジラがいる」
リャンは我に返ったように目をしばたかせ、そちらを見た。母親の傍らで、くるくると戯れる柔らかそうな灰色の背が、傾き始めた陽光を受けて光っている。う、とリャンは喉を詰まらせると、声にならない声で泣き出した。皇后のヒレが掃き上げた海水が、滝のように甲板に降ってきて、リャンの涙も全て濡らしてしまった。
「サク!」
漁が終わって船着場へ戻ってくると、ルカが待っていた。周りの作業員たちは、彼の顔の傷を遠巻きに見ているようだが、本人は気にせず船に近寄ってくる。
「ルカ、何かあったの」
鮑の籠を下ろしながら尋ねると、ルカは『大漁だな』と覗き込みながら言う。近くで横顔を見ると、少し痩せたかもしれない。根を詰めているか、不摂生しているか、多分どっちもだろう。
「試運転だ」
「スクリュー船の? 完成したんだね」
「まだ課題は有るんだけどな。ミスターローランドも立ち会うぞ」
お前も見にくるかと思って。隈の浮いた目元で笑う。やれやれ、ジナが心配して怒っている様子が目に浮かぶ。
「今から?」
「ああ、ミスタードーソンが操縦したがってるとかで……。何者なんだ、あの人」
そういえば元アメリカ海兵なんだっけ、と思い出す。海賊の間違いじゃなかろうか。ミスターローランドとセシル・ドーソンが対面するところには、あまりかなり居合わせたくないが、新しい船は見てみたい。
「……これ一個高いのか?」
ルカが鮑を指差して言う。思惑は分かっている。ジナに食べさせてやりたいのだ。俺は態とらしくルカの耳元に囁く。
「小売価格は知らないけど、一個採ると、俺たちに支払われるのはね……」
「マジか。ピット爺さんが言ってたのは本当だな」
「今度漁場以外で採れたら、工場の方へ持っていくよ」
仕事中に採ったものを私的に流用すると、バレたら多分セシル・ドーソンに殴られる。馬鹿、金になるモンを金にしないでどうする、お前が働いた対価だろうが。二人でこそこそ話していると、リャンが通りかかった。身に付けている革紐と鯱の牙のチョーカーは、ジナが作ったものだ。おうリャン、とルカは気軽に声をかける。
「久しぶりだな」
こくり、とリャンは頷く。他のダイバーたちとも仕事以外ではほとんど話しているところを見かけないが、この二人はそれなりに親しいらしい。もやもやとした気分になって一歩下がった俺を、ルカは可笑しそうに小突く。
「よかったな、一緒に仕事ができるようになって」
どういう意味。ずっと俺が気にしてたから? それとも潜水技術が追いついてきてるってこと? 実際のところ、リャンは俺に鮑採りについていろいろと教えてはくれるが、生い立ちや私生活について話したことはほとんどない。要するに、仕事においても、友人としても、信頼に値すると思われていないのだ。勝手に考え込んで勝手に落ち込んでいる俺を気にもとめず、ルカはリャンに向かって続ける。
「造船所で新しく造ったスクリュー船の試運転なんだ。お前も見にくるか」
「うん」
「え、リャン、船好きなの」
思わず声を上げてしまい、リャンがまたあの迷惑そうな顔をする。ルカは楽しげに言う。
「機械が面白いのは、人間がつくり出したからだよな」
「うん」
だからどういう意味。なんで二人して分かったような感じなの。もしかしてこの二人、口数が違うだけで結構似ているのかもしれない。なんて言うんだっけ、ええと、ツンデレ?
セント・ヘレナの港に、新しい汽船が泊まっている。午後の遅い光の中で、その優雅で強靭な曲線を晒す姿はまるで、大きな王冠のようだ。俺は見上げて溜め息を吐いた。リャンも隣りで目を細めて、機関部から伸びる煙突の先を見ている。すると甲板から人影が躍り出た。
「乗船したまえ、出航だ!」
舵を取るのはセシル・ドーソンである。その隣りにはフロック・コートを纏いステッキを持ったミスターローランドが立ち並ぶ。鐘の音が鳴り響く。誰よりも速く遠く、まだ人々は、自分がどこを目指しているのかも知らない。
***
潮風を切って、船は進む。船大工たちは機関室と船尾を行ったり来たりして記録を取っている。俺は邪魔しないように甲板の端で、流れる風景を見ていた。操舵室からミスターローランドどセシル・ドーソンの、議論しているのだか、ケンカしているのだが、漫才しているのだか分からない声が響いてくる。
「大洋に出る」
「許可するが、
「大丈夫だろ? 安定はよさそうだぜ、速度は出んが」
どうやら湾外にまで航行するつもりらしい。船大工たちは波が泡が水が燃料がとばたばたし始める。ピット爺さんだけは、ずっと船尾に立って航跡を見つめている。リャンはどこだろうかと甲板を見渡すと、操舵室の影に隠れるようにして佇んでいた。
「リャン、気分悪いの?」
いつも顔色は良くないのだが、大きな目が苦痛に歪んでいるように見えた。港に着いた時には、颯爽としていてなんともなかった。船酔いなどするはずもない。うつむき加減の肩に触れると、ひどく冷えていた。
「……湾の外に出たくない」
細い声が震えている。もう平気になったと思ってたのに、と俺の手を振り解くが、船の揺れによろけそうになる。
「どうして?」
「思い出すからだ、ここへ来た時を」
喉元を掻いて、出ない声を無理に押し出すように話す。俺は見たことのないリャンの怒りだか憎しみだかが暗く燻った呻きに動揺して、立ち尽くした。
「逃げてきたんだ、本島の鉱山から」
清の漁村から売られてきた
「本島から客船に乗って、ヴァン・ディエメンに来た日を覚えてる」
よほど、あのきらきらとした波に跳び込めば、楽になるのかと、思っていたのだ。俺は何も言えなかった。現代の世界にも、実質的な奴隷労働はいくらでもある。けれど、俺自身が経験してきたことや、未来にはまず起こらない。俺は恵まれた生まれなのだ。そして、どうしようもなく、無知だ。リャン、と俺はなんとか名前を呼ぼうとした。
「おいおいおい、たまげたな!」
背後の操舵室から、セシル・ドーソンの興が乗りすぎた声が叫んだ。途端に、横波に叩かれて、船が大きく揺れる。俺とリャンは甲板に転がった。身体の節々をぶつけて目がチカチカするが、俺の腰の上に倒れ込んだリャンを支えて、俺はなんとか上体を起こした。その視界に、天の半分を覆う
俺は嘆息を吐いた。いつの間に近付いていたのか、漆黒のベールをはためかせるように、銀の飛沫を巻き上げて、優雅にブリーチする。まさに皇后の名にふさわしい。
「退避しろ、セシル!」
「スクリュー船は曲がれんよ、ブランディ。しかし気の強い女だな!」
ミスターローランドの叱咤と、セシル・ドーソンの興奮で上擦った声が聞こえる。がくんとスクリューの回転方向が変わり、船体が後退を始めたのが分かるが、皇后は取り巻くように、巨大な体躯で弧を描く。俺は見惚れて座り込んでいたが、皇后の側にほろほろと瞬く小さな影に気が付いた。こちらも呆然としているリャンの腕を引っ張って、指をさす。
「リャン、見て、仔クジラがいる」
リャンは我に返ったように目をしばたかせ、そちらを見た。母親の傍らで、くるくると戯れる柔らかそうな灰色の背が、傾き始めた陽光を受けて光っている。う、とリャンは喉を詰まらせると、声にならない声で泣き出した。皇后のヒレが掃き上げた海水が、滝のように甲板に降ってきて、リャンの涙も全て濡らしてしまった。