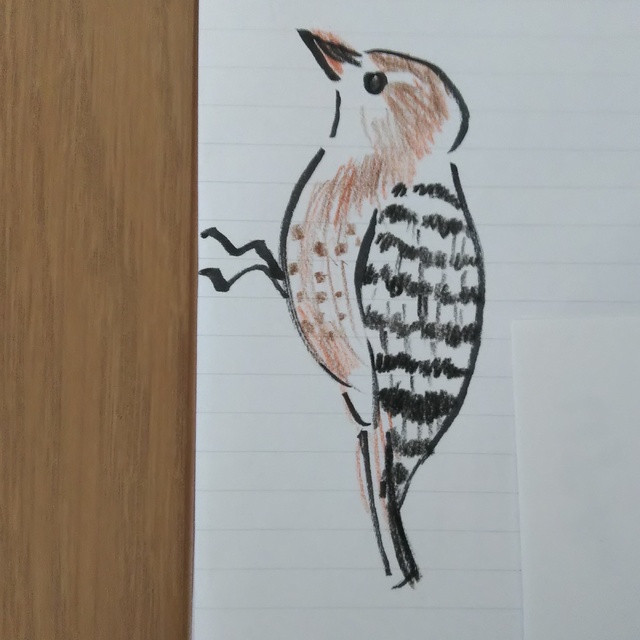第16話
文字数 2,460文字
襖の向こう側の風景を見た私は、ちょっと不思議な気分になった。
客間の長テーブルの向かい側、左から順番に、人間に戻った彼、お母さん、白髪が混ざった灰色の髪をしたお父さんと思われる男性、おばあさん、白髪頭のおじいさんと思われる男性、そしてミヅキちゃん。昨夜のケージを挟んだ並び方と同じ順番で、稲葉家が全員人間の姿で勢揃いしていた。
なぜ、家族全員が横一列に並んで座っていたのか…その理由は、直ぐにわかった。
「あら、カンナさん起きたのね。ほら、お父さん!」
お母さんはやや強めにお父さんの脇腹を肘で小突くと、お父さんは小さく咳払いをした。それまであぐらをかいていた足を正座に直し、私をジッと見上げた。
「えー、鈴木ーー!」
「スズオキよ!」
お母さんがさっきよりも強めにお父さんの脇腹を小突いた。
「…鈴置カンナさん、この度は我が家の危機に遠路遥々駆けつけていただき、誠にありーー!」
「そういう言い方しなくていいでしょ!もう!ただちゃんとお礼を言ってっていったのに!」
まるで結婚式のスピーチのようなお父さんに我慢ができなくなったようで、お母さんが割って入った。
ただ呆然していた私は、彼に視線を送ってみたけれど、うっすらと笑みを浮かべているだけだった。それでも、「これがウチの家族なんだよ」とでも言いたいのかなと、私には感じられた。
「ほれ、じいさんも」
今度は、おばあさんがおじいさんを促した。よく見ると、右の前腕に包帯が巻いてあった。
「いやいや、この度は本当に、どうもね。困ったねー」
「困ったのはアンタだ。全く」
おばあさんにピシャリと言われ、おじいさんは分かりやすく肩を落としていた。どうやら昨夜おばあさんが言っていた通り、相当おじいさんは絞られたようだった。
「あ…その、ご無事で良かったです。あ、申し遅れました!私、鈴置カンナと申します」
私は慌ててテーブルの前に正座すると、お父さんとおじいさんに改めて自己紹介をした。
「将来のミツルの嫁さんだ」
おばあさんが小声で呟いた。
「まぁた、お母さんったら!」
すかさずお母さんが叫んだ。
「あたしも賛成。お兄ちゃんの奥さんは、カンナさんくらいしっかりした人じゃないとダメだと思う」
ミヅキちゃんがさりげなく言った。
「ミヅキまでそんなこと!カンナさんが困るでしょう!?ウサギ男のお嫁さんになるってことはね、大変なことなんだから!毎月毎月、必ず亭主が役立たずになるんだから!」
彼と、お父さんと、おじいさんは、黙っていた。3人とも、同じ表情で。居心地が悪そうな表情で。
「だからこそ、気が利く人がいいんじゃん。お母さん気付いてた?カンナさん、玄関の床に泥がつかないように、汚れたコートを裏返しにたたんで置いてたんだよ?」
「もちろん気付いてたわよ。きっとアンタよりも早くね」
なぜか、お母さんは胸を張って言い返していた。
「なら、お母さんもわかってるでしょう?ここでカンナさん逃がしたら、お兄ちゃん絶対結婚できないよ?」
「そりゃあ、お母さんだってそうだったらいいなぁとは思うけれども!でも、それとこれとはまた違う話でしょう!?」
「その話はもういい。俺とカンナに昼飯」
女性陣の討論を終わらせたのは、彼のそんな一言だった。それは、彼のおばあさんが時々放った重みのある言葉とどこか似ていた。彼が言葉に威圧感を乗せられることに、ちょっと驚いた。いつも飄々としていたから。
「あら、そうだったわね!ごめんなさいね」
お母さんは恥ずかしそうにテーブルに乗り出していた体を引っ込めると、いそいそと部屋を出ていった。
彼のズルい所は地味に気が利く所だ。
お昼を過ぎても目覚めない私を察したのだろう、わざと自分の昼食の時間を私に合わせたに違いない。私が、独りで遅れた昼食をご馳走になる気まずさを紛らわせるために。
それを恩着せがましくではなく、当たり前のように自然にできる。この"察する力"は、きっとおばああさん譲りなのだろう。
違和感なく、私の隣に腰をおろし、何事もなかったなかったようにお味噌汁をすする。
(…本当に、ズルい奴)
その横顔を、私も同じように味噌汁をすすりながら盗み見ながら、そう思った。
昼食をご馳走になった頃、お父さんがビニールがかけられた私のコートを持ってきてくれた。どうやら本当にクリーニングに出していてくれたようだった。
本当は靴もクリーニングに出したかったそうなのだけれど、さすがに半日では難しいと、返されたそうだ。もちろん、私は全く構わなかったのだけれど。
私は彼と相談して、高速バスで帰ることにした。お父さんもお母さんも車でアパートまで送っていくと最後まで言ってくれていたけれど、彼とゆっくり話したかった私が、バスで帰ることを彼に強く希望したのだった。できるなら、昨夜私が辿ってきた道のりを、彼にも知って欲しかったからだ。
「本当にいいの?大澤のバス停まででも送ろうか?」
玄関まで見送りに来てくれたお母さんが言った。
「いいよ。すぐだから」
そう言う彼に、「お前の"すぐ"は感覚ズレでるけどな!」と、心で叫びながら、私はまだ汚れの残る靴をはいた。
「あと、これはカンナさんに」
お母さんは茶色い封筒を私に手渡した。受け取った時の感触で、お金が入っていることがわかった。ここまでの運賃だった。
「…でもこれはーー」
言いかけた時、お母さんの後ろから私を睨む、一人の視線を感じた。おばあさんだった。まるで「昨日言ったことを忘れたか?」とでも言いたげな表情だった。
「…ありがとうございます」
私は、封筒を受けとると、鞄にしまった。
「じゃあ」
彼が言った。
「あ、うん。お邪魔しました。いろいろご馳走していただいてありがとうございました」
私と彼が玄関を出ようとした時だった。
「カンナ」
不意に名前を呼ばれた私は振り返った。いつの間にか、おばあさんが一番前に立っていた。
「また、いつでもおいで」
おばあさんは、笑うこともなく小さな声でそう言った。
「…はい!」
私は強く頷いた。おばあさんが、私を"カンナ"と呼び捨てにしてくれたことが、とても嬉しかった。
つづく…
客間の長テーブルの向かい側、左から順番に、人間に戻った彼、お母さん、白髪が混ざった灰色の髪をしたお父さんと思われる男性、おばあさん、白髪頭のおじいさんと思われる男性、そしてミヅキちゃん。昨夜のケージを挟んだ並び方と同じ順番で、稲葉家が全員人間の姿で勢揃いしていた。
なぜ、家族全員が横一列に並んで座っていたのか…その理由は、直ぐにわかった。
「あら、カンナさん起きたのね。ほら、お父さん!」
お母さんはやや強めにお父さんの脇腹を肘で小突くと、お父さんは小さく咳払いをした。それまであぐらをかいていた足を正座に直し、私をジッと見上げた。
「えー、鈴木ーー!」
「スズオキよ!」
お母さんがさっきよりも強めにお父さんの脇腹を小突いた。
「…鈴置カンナさん、この度は我が家の危機に遠路遥々駆けつけていただき、誠にありーー!」
「そういう言い方しなくていいでしょ!もう!ただちゃんとお礼を言ってっていったのに!」
まるで結婚式のスピーチのようなお父さんに我慢ができなくなったようで、お母さんが割って入った。
ただ呆然していた私は、彼に視線を送ってみたけれど、うっすらと笑みを浮かべているだけだった。それでも、「これがウチの家族なんだよ」とでも言いたいのかなと、私には感じられた。
「ほれ、じいさんも」
今度は、おばあさんがおじいさんを促した。よく見ると、右の前腕に包帯が巻いてあった。
「いやいや、この度は本当に、どうもね。困ったねー」
「困ったのはアンタだ。全く」
おばあさんにピシャリと言われ、おじいさんは分かりやすく肩を落としていた。どうやら昨夜おばあさんが言っていた通り、相当おじいさんは絞られたようだった。
「あ…その、ご無事で良かったです。あ、申し遅れました!私、鈴置カンナと申します」
私は慌ててテーブルの前に正座すると、お父さんとおじいさんに改めて自己紹介をした。
「将来のミツルの嫁さんだ」
おばあさんが小声で呟いた。
「まぁた、お母さんったら!」
すかさずお母さんが叫んだ。
「あたしも賛成。お兄ちゃんの奥さんは、カンナさんくらいしっかりした人じゃないとダメだと思う」
ミヅキちゃんがさりげなく言った。
「ミヅキまでそんなこと!カンナさんが困るでしょう!?ウサギ男のお嫁さんになるってことはね、大変なことなんだから!毎月毎月、必ず亭主が役立たずになるんだから!」
彼と、お父さんと、おじいさんは、黙っていた。3人とも、同じ表情で。居心地が悪そうな表情で。
「だからこそ、気が利く人がいいんじゃん。お母さん気付いてた?カンナさん、玄関の床に泥がつかないように、汚れたコートを裏返しにたたんで置いてたんだよ?」
「もちろん気付いてたわよ。きっとアンタよりも早くね」
なぜか、お母さんは胸を張って言い返していた。
「なら、お母さんもわかってるでしょう?ここでカンナさん逃がしたら、お兄ちゃん絶対結婚できないよ?」
「そりゃあ、お母さんだってそうだったらいいなぁとは思うけれども!でも、それとこれとはまた違う話でしょう!?」
「その話はもういい。俺とカンナに昼飯」
女性陣の討論を終わらせたのは、彼のそんな一言だった。それは、彼のおばあさんが時々放った重みのある言葉とどこか似ていた。彼が言葉に威圧感を乗せられることに、ちょっと驚いた。いつも飄々としていたから。
「あら、そうだったわね!ごめんなさいね」
お母さんは恥ずかしそうにテーブルに乗り出していた体を引っ込めると、いそいそと部屋を出ていった。
彼のズルい所は地味に気が利く所だ。
お昼を過ぎても目覚めない私を察したのだろう、わざと自分の昼食の時間を私に合わせたに違いない。私が、独りで遅れた昼食をご馳走になる気まずさを紛らわせるために。
それを恩着せがましくではなく、当たり前のように自然にできる。この"察する力"は、きっとおばああさん譲りなのだろう。
違和感なく、私の隣に腰をおろし、何事もなかったなかったようにお味噌汁をすする。
(…本当に、ズルい奴)
その横顔を、私も同じように味噌汁をすすりながら盗み見ながら、そう思った。
昼食をご馳走になった頃、お父さんがビニールがかけられた私のコートを持ってきてくれた。どうやら本当にクリーニングに出していてくれたようだった。
本当は靴もクリーニングに出したかったそうなのだけれど、さすがに半日では難しいと、返されたそうだ。もちろん、私は全く構わなかったのだけれど。
私は彼と相談して、高速バスで帰ることにした。お父さんもお母さんも車でアパートまで送っていくと最後まで言ってくれていたけれど、彼とゆっくり話したかった私が、バスで帰ることを彼に強く希望したのだった。できるなら、昨夜私が辿ってきた道のりを、彼にも知って欲しかったからだ。
「本当にいいの?大澤のバス停まででも送ろうか?」
玄関まで見送りに来てくれたお母さんが言った。
「いいよ。すぐだから」
そう言う彼に、「お前の"すぐ"は感覚ズレでるけどな!」と、心で叫びながら、私はまだ汚れの残る靴をはいた。
「あと、これはカンナさんに」
お母さんは茶色い封筒を私に手渡した。受け取った時の感触で、お金が入っていることがわかった。ここまでの運賃だった。
「…でもこれはーー」
言いかけた時、お母さんの後ろから私を睨む、一人の視線を感じた。おばあさんだった。まるで「昨日言ったことを忘れたか?」とでも言いたげな表情だった。
「…ありがとうございます」
私は、封筒を受けとると、鞄にしまった。
「じゃあ」
彼が言った。
「あ、うん。お邪魔しました。いろいろご馳走していただいてありがとうございました」
私と彼が玄関を出ようとした時だった。
「カンナ」
不意に名前を呼ばれた私は振り返った。いつの間にか、おばあさんが一番前に立っていた。
「また、いつでもおいで」
おばあさんは、笑うこともなく小さな声でそう言った。
「…はい!」
私は強く頷いた。おばあさんが、私を"カンナ"と呼び捨てにしてくれたことが、とても嬉しかった。
つづく…