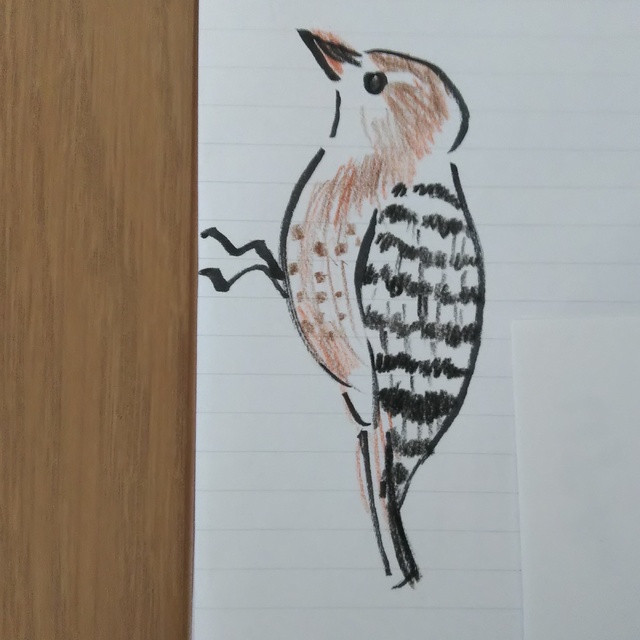第9話
文字数 2,465文字
宛もなく藪の中を歩き回った私は、街灯の明かりを頼りに道路に出てきた。足元を見ると、スニーカーは泥にまみれていた。コートも至るところに泥が擦れ、枯れ草が引っ掛かっていた。なんとなく頬に当たる違和感はきっとクモの巣だったのだろう。
けれど、私にはそれを気にする余裕もなかった。
街灯の下に、キャリーバッグとリュックが置いてあった。元の場所へ戻ってきたことがわかった。
思い足取りで道路を横断して、荷物の隣に膝を着いた。その衝撃が引き金になったように、私の心に不安が溢れだした。
彼を永遠に失ってしまったかもしれない恐怖。それを引き起こしてしまった自分の愚かさ。やっぱり余計なことをしなければよかったという後悔。
藪の中では彼を探すことに必死で感じなかった様々な不安が次々と膨れ上がり、心は今にも破裂しそうだった。意味はないとはわかっていても、私は両手で胸をおさえながら、その場にうずくまった。
彼の首に食らいつき、その小さな体を軽々と持ち上げる野犬の姿が目に浮かんだ。
ーーーどうしよう!
呼吸が浅くなっていた。いくら吸い込んでも、酸素が入ってこない。深呼吸をしようと思ってもできない。苦しい。まるで空気の薄い高山にでもいるようだった。
子どもの頃、こんな風に息ができなくなったことがあった。確か…初めてのピアノの発表会の前日だった。
そんな私を助けてくれたのは、その時もおばあちゃんだった。
おばあちゃんはたまたま私の家に遊びに来ていた。私は最後の追い込みで必死に鍵盤を叩いていた。
「カンナちゃんはがんばり屋さんだねぇ」
そう言ってくれたおばあちゃんの顔を見た途端、ずっと張りつめていた不安と緊張の糸がプツンと切れてしまった。私はピアノの前で息が出来なくなってしまった。
「苦しくなってもいいんだよ。ゆっくり息を吸って、ゆっくり息をはいてごらん」
その時も、おばあちゃんは焦る様子もなく、笑顔だった。私の背中を擦りながら、そう言ってくれた。おばあちゃんのあったかい掌に撫でられて、背中があったかくなっていく感覚を、今でも覚えている。
「カンナちゃんは何が心配なんだい?」
「…失敗、するかも。うまくできないかも、しれない」
「そう。それは心配だねぇ」
おばあちゃんはどんな時でも私を否定したりはしなかった。必ず一度、ちゃんと受け止めてくれた。
「先生から失敗してもいいんだよって、言われなかったかい?」
「…言われた」
「失敗していいって言われたって、誰だって失敗するのは嫌だもんねぇ」
おばあちゃんは、いつも私の心の中までお見通しだった。
「でもそれは、明日にならなきゃわからないことでしょう?それじゃあ、今できることはないのかな?」
そして、いつも私にヒントをくれた。不安と上手に付き合って、そしてそれを乗り越えていくヒントを。
「…練習、すること?」
「カンナちゃんがそう思うのなら、きっとそれが正解ね。大丈夫、カンナちゃんは明日のために今できることをちゃーんとやっているよ?心配しなくて大丈夫だよ」
それから、おばあちゃんは私の隣に座って、練習を見ていてくれた。
発表会の当日はやっぱり失敗してしまったけれど、おばあちゃんが作ってくれたお守りのシュシュを手首に巻いて本番に臨んだ私は、思ったよりも緊張せずに発表会を乗り越えることができた。
おばあちゃんの笑顔と言葉に、私はこれまで何度助けてもらってきただろう。
ーーー今できることはないのかな?
おばあちゃんの声は、こんな状況になっても、私にちゃんと届いていた。
(…今、できること)
いつの間には、胸の苦しさは和らいでいた。私は、あの時のようにまだ起こっていない未来の不安から抜け出すことができた。そして、今の自分に出来ることを考え始めた。
暗闇の中、山に逃げた黒い小さなウサギを探しだすことなんて、簡単にできるはずがない。警察がそんな相談に乗ってくれるとは思えないし、そもそも彼がウサギ男な時点で他人に助けを求めることはできない。土地勘もなければ山の知識もない私なんかが一人で探してたところで、きっと見つからないだろうし、下手すれば私が遭難してしまう。その前に野生のナニカに襲われてしまうかもしれない。
少しでも、彼を見つけだす可能性があるとすれば、彼が人間に戻ってからだと考えた。裸で山の中に放り出されることになる彼には申し訳ないけれど、それしか思い付かなかった。
人間に戻るまでの間、彼が野生のナニカに襲われないことを祈りながら、私はその場で待つことにした。
その場に座り込んで、彼が消えていった真っ暗な藪の中をジッと見つめた。
不意に、彼の眼が赤く光っていたことを思い出した。どうして眼が赤くなったのだろう?どうしてあんなに怒っていたのだろう?藪の奥にいた野生のナニカと関係があったのだろうか?
不安な気持ちと同じくらい、疑問が膨れ上がっていた。
どれくらい時間が経っただろう。
街灯の元に座り込んでいた私は、いつのまにか睡魔に襲われ、ウトウトしてしまっていた。そのせいで、コートの裾を引かれる小さな違和感に気づかなかった。
何気なく後ろに目をやった私は驚いた。
「ミツル君!?」
そこには、私のコートの裾をかじる黒いウサギの姿があった。
私は急いでウサギを抱き上げると、街灯の光を当てて、その姿をよく見てみた。黒い毛並みに、フワフワの抱き心地。重さ。大きさ。間違いない。彼だった。
「何やってるのよもぉ!本当に、本当に心配したんだからねぇ!?」
私は泣きながら彼に頬擦りした。いつもは嫌がるはずなのに、この時の彼は、嫌がる素振りを見せなかった。
「大丈夫!?怪我してない!?」
体を隈無くチェックしたけれど、私のように泥や雑草で汚れているくらいで、怪我らしい怪我は見当たらなかった。ちなみに、眼も赤く光ってはなくて、いつもの眼に戻っていた。
「良かったぁ」
一気に全身の力が抜けていくのを感じた。私はそこが道路脇の歩道だということも忘れて、胸に彼を抱いたまま仰向けに寝転んだ。
「…ありがとう。おばあちゃん」
木々の切れ間から、明るい満月が私を見下ろしていた。
つづく…
けれど、私にはそれを気にする余裕もなかった。
街灯の下に、キャリーバッグとリュックが置いてあった。元の場所へ戻ってきたことがわかった。
思い足取りで道路を横断して、荷物の隣に膝を着いた。その衝撃が引き金になったように、私の心に不安が溢れだした。
彼を永遠に失ってしまったかもしれない恐怖。それを引き起こしてしまった自分の愚かさ。やっぱり余計なことをしなければよかったという後悔。
藪の中では彼を探すことに必死で感じなかった様々な不安が次々と膨れ上がり、心は今にも破裂しそうだった。意味はないとはわかっていても、私は両手で胸をおさえながら、その場にうずくまった。
彼の首に食らいつき、その小さな体を軽々と持ち上げる野犬の姿が目に浮かんだ。
ーーーどうしよう!
呼吸が浅くなっていた。いくら吸い込んでも、酸素が入ってこない。深呼吸をしようと思ってもできない。苦しい。まるで空気の薄い高山にでもいるようだった。
子どもの頃、こんな風に息ができなくなったことがあった。確か…初めてのピアノの発表会の前日だった。
そんな私を助けてくれたのは、その時もおばあちゃんだった。
おばあちゃんはたまたま私の家に遊びに来ていた。私は最後の追い込みで必死に鍵盤を叩いていた。
「カンナちゃんはがんばり屋さんだねぇ」
そう言ってくれたおばあちゃんの顔を見た途端、ずっと張りつめていた不安と緊張の糸がプツンと切れてしまった。私はピアノの前で息が出来なくなってしまった。
「苦しくなってもいいんだよ。ゆっくり息を吸って、ゆっくり息をはいてごらん」
その時も、おばあちゃんは焦る様子もなく、笑顔だった。私の背中を擦りながら、そう言ってくれた。おばあちゃんのあったかい掌に撫でられて、背中があったかくなっていく感覚を、今でも覚えている。
「カンナちゃんは何が心配なんだい?」
「…失敗、するかも。うまくできないかも、しれない」
「そう。それは心配だねぇ」
おばあちゃんはどんな時でも私を否定したりはしなかった。必ず一度、ちゃんと受け止めてくれた。
「先生から失敗してもいいんだよって、言われなかったかい?」
「…言われた」
「失敗していいって言われたって、誰だって失敗するのは嫌だもんねぇ」
おばあちゃんは、いつも私の心の中までお見通しだった。
「でもそれは、明日にならなきゃわからないことでしょう?それじゃあ、今できることはないのかな?」
そして、いつも私にヒントをくれた。不安と上手に付き合って、そしてそれを乗り越えていくヒントを。
「…練習、すること?」
「カンナちゃんがそう思うのなら、きっとそれが正解ね。大丈夫、カンナちゃんは明日のために今できることをちゃーんとやっているよ?心配しなくて大丈夫だよ」
それから、おばあちゃんは私の隣に座って、練習を見ていてくれた。
発表会の当日はやっぱり失敗してしまったけれど、おばあちゃんが作ってくれたお守りのシュシュを手首に巻いて本番に臨んだ私は、思ったよりも緊張せずに発表会を乗り越えることができた。
おばあちゃんの笑顔と言葉に、私はこれまで何度助けてもらってきただろう。
ーーー今できることはないのかな?
おばあちゃんの声は、こんな状況になっても、私にちゃんと届いていた。
(…今、できること)
いつの間には、胸の苦しさは和らいでいた。私は、あの時のようにまだ起こっていない未来の不安から抜け出すことができた。そして、今の自分に出来ることを考え始めた。
暗闇の中、山に逃げた黒い小さなウサギを探しだすことなんて、簡単にできるはずがない。警察がそんな相談に乗ってくれるとは思えないし、そもそも彼がウサギ男な時点で他人に助けを求めることはできない。土地勘もなければ山の知識もない私なんかが一人で探してたところで、きっと見つからないだろうし、下手すれば私が遭難してしまう。その前に野生のナニカに襲われてしまうかもしれない。
少しでも、彼を見つけだす可能性があるとすれば、彼が人間に戻ってからだと考えた。裸で山の中に放り出されることになる彼には申し訳ないけれど、それしか思い付かなかった。
人間に戻るまでの間、彼が野生のナニカに襲われないことを祈りながら、私はその場で待つことにした。
その場に座り込んで、彼が消えていった真っ暗な藪の中をジッと見つめた。
不意に、彼の眼が赤く光っていたことを思い出した。どうして眼が赤くなったのだろう?どうしてあんなに怒っていたのだろう?藪の奥にいた野生のナニカと関係があったのだろうか?
不安な気持ちと同じくらい、疑問が膨れ上がっていた。
どれくらい時間が経っただろう。
街灯の元に座り込んでいた私は、いつのまにか睡魔に襲われ、ウトウトしてしまっていた。そのせいで、コートの裾を引かれる小さな違和感に気づかなかった。
何気なく後ろに目をやった私は驚いた。
「ミツル君!?」
そこには、私のコートの裾をかじる黒いウサギの姿があった。
私は急いでウサギを抱き上げると、街灯の光を当てて、その姿をよく見てみた。黒い毛並みに、フワフワの抱き心地。重さ。大きさ。間違いない。彼だった。
「何やってるのよもぉ!本当に、本当に心配したんだからねぇ!?」
私は泣きながら彼に頬擦りした。いつもは嫌がるはずなのに、この時の彼は、嫌がる素振りを見せなかった。
「大丈夫!?怪我してない!?」
体を隈無くチェックしたけれど、私のように泥や雑草で汚れているくらいで、怪我らしい怪我は見当たらなかった。ちなみに、眼も赤く光ってはなくて、いつもの眼に戻っていた。
「良かったぁ」
一気に全身の力が抜けていくのを感じた。私はそこが道路脇の歩道だということも忘れて、胸に彼を抱いたまま仰向けに寝転んだ。
「…ありがとう。おばあちゃん」
木々の切れ間から、明るい満月が私を見下ろしていた。
つづく…