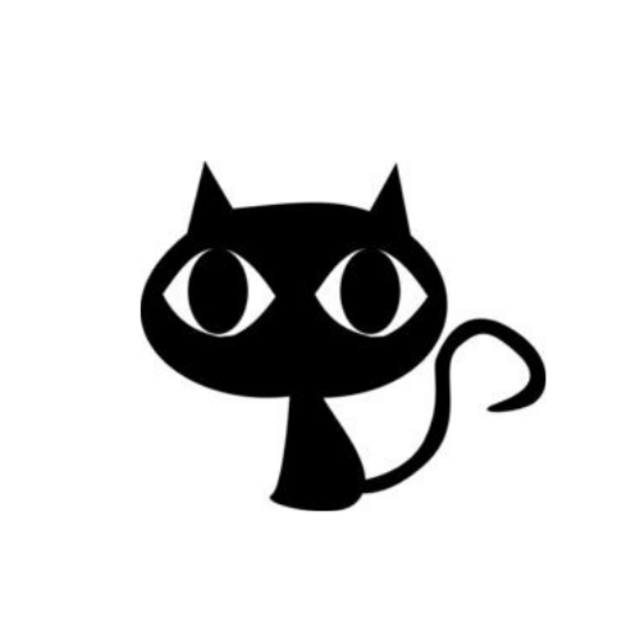天気は猫
文字数 8,661文字
雨に洗われたアスファルトが、黒く濡れて光っていた。
長崎は今日も雨だった——有名な歌がそう歌ってはいるが、聞くところによると、ここは特別に雨が多い地域ではないらしい。
それでもそんな歌が頭の隅にあるからか、私は本当にここは雨が多いのだと思っていた。思うことで実際の天気が変わるわけではないが、気持ちとしては大いに変わる。
だから、今日も出がけに雨が降り出しても、いつものことだと思って疑わなかった。長崎はいつも雨が降っているのだ、と。
しかし、しばらくすると、黒い雲間からところどころ強い光が差し込んできて、それはあっという間にあたりの景色を夏に変えた。私は畳んだ傘を持て余して、ズルズルと子供のように引きずりながら歩いた。
どうして傘ってこんなに邪魔なんだろう——急激な暑さによろけながら、私は思った。
雨が降っているときには自然に差していられても、晴れた途端、こんなにも邪魔になる。重たいわけじゃないけど、濡れているし、持ちにくいし、ああ、ホンット、晴れたときの傘ほど邪魔なものはない。
平日の午前に、傘を引きずる音は少々響きすぎ、私はようやくきちんとそれを腕にかけた。気を取り直して、歩き出す。目の前の坂道は、それでなくても気が遠くなるほど長い。
大学に入って最初の夏。
地元を離れて東京で暮らす私は、バイトで溜めたお金を使って、はるばるこの長崎まで帰ってきた。
坂の町。坂しかない町。ここがそう呼ばれていたことは知っていたけれど、離れるまでは実感がなかった。
坂を坂とも思っていなかったってわけじゃない。どんなに見慣れてたって、坂は坂だ。
けど、ほかの町には——少なくとも私が暮らし始めた東京には、こんなに坂がないものかと驚くほど、平坦だった。関東平野、つい地理で習った単語が頭に浮かび上がってきたくらいだ。
『東京って、坂がないとね』
どうしても訛ってしまう私の言葉に、新しい友人たちは、
『ないわけじゃないよ』
と、不思議そうに首をかしげ、その中の一人が、
『横浜にも、結構、坂あるよ』
と笑顔で言った。
けれど、その笑顔を見て、私は逆に「横浜にも坂がないんだな」と感じてしまった。
坂の町。坂しかない町。そこから出てきた私にとって、きっと横浜の坂はないに等しいものなのだろう。
背中にじんわり汗が出てくる。汗染みが出ないように下着を着てきたけれど、この分ではそれも無駄になりそうだ。
「あー、暑い」
声に出して言うと、ますます辛くなった。一歩を踏み出す足が辛い。畳んだ傘が邪魔だ。坂はまだ続いている。誰だって嫌になるような、この長い坂道。
けれど、同時に、私は辛いと感じている自分が不思議だった。なぜなら、私は彼のためにこの坂道を登っているのだ。高校の三年間付き合った、大好きな彼に会うために。
糸瀬 くんと私は、「奇跡のカップル」と呼ばれていた。別にそれは美女と野獣だとか、美男美女カップルだから、というわけではない。
私たちの高校では、文化祭のイベントとしてある恒例行事がある。それは「運命のくじ引き」という名称で、二、三年生はともかく、新入生である一年生は絶対参加というものだった。
やり方は、簡単。生徒が男女別に分かれ、くじを引く。くじには数字が書いてあって、同じ数字を引いた男女がペアになるという仕組みだ。
そして、ペアになった男女はどうするかというと、最終日の後夜祭を一緒に過ごさなくてはならない。そこで行われるゲームやクイズを、ペアでこなすのだ。
先輩たちは数字を交換し、好きな人とペアになったり、またどうしても嫌な人とペアになった場合は、バックレるなんてことも許された。けれど、一年の場合はそうもいかない。
強制的に組まされたペアで、運良く意中の人と……だなんて、少女漫画じゃありそうな展開だけど、実際にはそんなことは起こらない。否が応でも、確率というものの恐ろしさを味わうことになる。実は、私もそんな一人だった。
高校に入学して数ヶ月だというのに、私にはもう意中の人がいた。同じクラスの林田くん。野球部だから坊主だったけど、背が高くてかっこいい人だった。
もちろん、だからといって、猛烈アタックをかけていたわけではない。私は地味で大人しいほうだったし、男子に声をかけるなんて、とてもじゃないけどできなかった。
遠くから見ているだけ。それが私の恋。中学の時もそうだったし、それは高校に入ったって変わらないんだ。そう思って、過ごしていた。
だから、「運命のくじ引き」は、そんな私にとって大チャンスだった。
林田くんとペアでありますように、林田くんとペアでありますように!
そう願った私が引いたのは、89番。引いた瞬間、林 田く んだ——わけのわからないことを思ったことを覚えている。
けど、それはもちろん林田くんではなく——糸瀬くんだった。とはいっても、私はそのとき、彼の名前さえ知らなかった。顔は……見たことがあるなという程度。きっと向こうも同じだっただろう。
『岩永千紗です……』
肩を落として名乗った私に、
『糸瀬春紀です。よろしく』
彼はそう言って、はにかむような笑みを見せた。
地味目だけど優しそうな人だな——自分のことは棚に上げて、私はそう思った。少なくとも、一緒にいて不快なタイプの人じゃない、それどころか、すごく心地良い人だ、と。
そして、その予感は見事なほどに当たった。単純に言うと、私たちはとても相性が良かった。
では、どんな風に良かったのか。そう聞かれると、説明に困る。
それは例えば、長年付き合って夫婦みたいになったカップル、とでもいうか、それとももっと大げさに言えば、私たちは生き別れた双子なんじゃないかと思うくらい。それは林田くんに感じているようなときめきとは違う、安心感のようなものだった。
だから、今日初めて彼を意識したばかりだというのに、私はもう彼の隣にいるのが楽になっていた。林田くんのことは好きだ。けど、それはそれとして、私はもう彼から離れたくなかった。
『……なんか、岩永さんって、猫みたいや』
後夜祭が終わりに近づいてきた頃、糸瀬くんはぼそりとそうつぶやいた。
『猫?』
私が聞き返すと、
『うん、うちに遊びに来る野良によく似とる。あいつ、エサやるとよう懐いてすり寄ってくるくせに、堂々と違う場所でエサもらっとるんじゃ』
そう言って、くすりと笑う。
『どういう意味ね?』
意味を捉えかねて、私が顔をしかめると、
『いや、何となくそう思っただけ……猫っぽいって言われないと?』
『言われたことない』
『そうかな、おかしいとね』
私をじっと見て、首をかしげる。私はふと恥ずかしくなって、
『おかしくないとよ。ってか、エサをもらいに来る野良に似てるって、失礼じゃないと? 私、エサもらっとらんし』
むっとふくれてそう言うと、
『じゃ、これ』
彼は笑いながら、ポケットから飴を取り出した。二人でやったクイズゲームの参加賞だ。
『それ、私もあるから』
私もポケットから出してみせると、
『いいよ、もらっとけ』
彼は私の手のひらに飴を乗せた。
その瞬間——一体世界の何が変わったというのか、私の全身がかあっと熱くなった。そして、目の前にいる糸瀬くんが好きで好きでたまらなくなった。
『ほら、飴あげたら目の色が変わったとよ』
糸瀬くんはおかしそうに笑った。
『そんなに飴、好きだったと?』
『ううん……』
飛び出して爆発してしまいそうな心臓の音を聞きながら、私は首を振った。それから——もう本当に何が起こったのかわからないが——こつん、糸瀬くんの肩におでこをぶつけた。
『糸瀬くん……あの……』
『なに? 岩永猫さん?』
冗談を言いながらも、私の行動にさすがに驚いたのだろう、糸瀬くんの声がうわずる。私は何が何だかわからないまま、
『……好きです』
そう告白した。
なぜそんなことを言ったのか、自分でもわからない。けれど、私の告白を糸瀬くんは笑って受けた。
『直前まで、林田くんが好きって言っとったがね!』
翌日、友人たちは私を取り囲んで大騒ぎし、どうして? なんで? を繰り返した。
けど、一晩明けたその日になっても、私はなぜ糸瀬くんに告白したのか、自分でも理由がわかっていなかった。
そんな私の様子を察し、友人たちはある結論を導き出した。
つまり、これは「運命のくじ引き」が引き合わせた本当の運命であり、本当の運命に出会った二人は、例えほかに好きな人がいたとしても惹かれ合わずにはいられないのだ、と。
「運命のくじ引き」が本当の運命を引き当てた——その噂はすぐに広まり、そして私たちは「奇跡のカップル」、そう呼ばれるようになったのだった。
「……久しぶり」
坂を登り切り、そしてもうしばらく歩くと、公園の東屋から懐かしい影が手を上げた。
「元気だったと?」
「うん、元気だった。……って、LINEでいつもしゃべってるじゃん」
私は答えると、向かい側に腰を下ろした。タオルハンカチを取り出し、汗を拭う。日陰に通る風が気持ちいい。
「しゃべってる
すると、糸瀬くんは笑った。
「こがに短い間に、東京の人になったとね」
「そがなことないがね」
ぷっとふくれ、私は言った。
「私は変わっとらん」
「そうかね」
彼は目を細めると、私をじっと見た。高校時代には嬉しかったその視線が、いまは何となく嫌で、私はうつむいた。
〈やっと会えるね! 寂しかったよ!〉
スタンプで飾ったLINEではごまかせたその感情が、現実ではどうすることもできず、私は無言のまま、机の木目を見つめた。
大学生の私が公園に行く機会などない。あっても、東京の公園で東屋に座ったことはない。けれど、東京の東屋の机は、こんな木でできているものではなく、きっとプラスチックや石でできているのだろうと、そんなどうでもいい考えが頭をよぎった。
本当にどうでもいい——青春十八切符でわざわざ帰省した地元、それも彼氏を前に思うことじゃない。
「毎日、何してると?」
すると、彼がそう尋ねる。
「……LINEで報告してるじゃん」
「授業出て、レポート書いとるんじゃろ。それから新しい友達ができたとね。櫻川さんに、紀本さんに、河原井さんに……」
「ほら、言わなくても知っとる」
「それはそうじゃけど、ばってん——」
「だったら、聞かなくてもよかと」
自分でも言葉にトゲがあると思った。だから、なおさら顔が上げられなかった。けれど、どうしてこんなものの言い方になってしまうのか、わからなかった。
会いたい、そう思っていた気持ちは本当だ。高校時代の三年間が幸せだったのも。糸瀬くんのことが大好きだったのも。
それなのに、なんで私はこんなに苛立ってるんだろう。何がこんなに気持ちを重くするんだろう。
糸瀬くんを目の前にしても、何だか全然嬉しくない。楽しくない。あのときの燃えるような心が戻ってこない。
「……俺は、こっちでうまくやってるとよ」
私が聞かないからか、糸瀬くんは独り言を言うように話し始めた。
「東京に千紗が行ったのと同じに、こっちの大学にも東京の人がおると。長崎の方言に慣れんっちゅうて、いろいろおかしな聞き違いをするとよ。そりゃ、俺らは長崎弁なんてよう使わんばってん、そいつに言わせると、根本的にイントネーションが違うとね。だから、そういう話を聞く度に、千紗はうまくやれとうかねって心配になるとよ」
彼の手が、ためらいがちに私に伸ばされた。
何だろう、私は思い、それからふと思い出した。
高校の頃、私たちはよくこの公園で話をした。そのとき、二人はこんな風に向かい合うのではなく、隣に座り、ぴったりと肩を寄せ合っていた。
それは、寒い冬も、こんなふうに暑い夏でも同じだった。私の頭はいつも彼の肩にもたれ、彼はそんな私の手を握っていた。そうすると、彼の温もりが私の中に入り込み、私の温もりを足したそれが再び彼の中に戻り、その循環がいつまでも繰り返される。そんなことに、私は幸せを感じていたのだった。
けれど、いまの私は、差し出された手を無表情に見つめているだけだった。それも、なぜ彼がそうするのか、一瞬、わからずに。
まるで生き別れた双子みたいだ——あの夜感じた気持ちは、一体どこへ行ってしまったんだろう。私は少し混乱していた。
東京にいたときは、会いたいという気持ちでいっぱいだった。だというのに、実際に会ったらどうだろう。私はどこか他人行儀にかしこまっている。それどころか、彼の言葉を受け入れられず、イライラと当たり散らしている。
「……ほかに好きな人ができたと?」
とうとう彼が聞いた。聞かれても仕方ないことではあった。けれど、私は反発した。
「どうしてそがなこと言うと? もしかして、好きな人ができたんは、糸瀬くんのほうやないと?!」
言ってから、自分が顔を上げたことに気づいた。いままで避けていた彼と目が合った。そして、口を閉じた。
糸瀬くんは糸瀬くんのままだった。
あのときと変わらず、私を真っ直ぐに見つめていた。ということは、変わったのは私のほうだった。そう認めないといけないときがきていた。
「……別に好きな人なんて、おらんと」
私はつぶやいた。
それは本当だった。東京に好きな人なんていない。私の彼氏は、毎日LINEのやりとりをして、おはようからおやすみまで言い合う糸瀬くんだけだった。
「俺も、千紗のほかに好きなやつなんておらん」
彼もそう言った。やはり、真っ直ぐな目だった。その言葉が真実であることなど、目を見ればわかった。
「じゃあ、どうして……」
そんなこと聞くの——そう言うつもりだった。けれど、言えなかった。夏の日差しが照りつけているというのに、屋根に遮られたここは暗く、隠したい気持ちを隠し通せるような気がしていた。
糸瀬くんのことをもう好きではない——そんな自分でさえも認めたくない気持ちを、口が裂けても彼には言えない気持ちを。
私はうつむいたまま、机に立てかけた傘に視線を移した。
この雨の多い長崎で、糸瀬くんは私の優しい雨傘だった。雨には傘が必要であるように、私には糸瀬くんが必要だった。
けれど、私は東京に出てしまった。
東京が長崎よりも晴れの日が多いのかどうかは知らない。けれど、長崎に置いて行ってしまった私の傘を、私は必要とすることがなくなってしまった。
だからなのだろう——私の心が冷めてしまったのは。
ずいぶん身勝手な話だ。自分でもそう思う。けれど、私はきっとここを離れたときからそう思っていて——今回の帰省も、きっとその罪悪感がさせたのだろう。
会いたい——その気持ちは、好きな人に会いたいというものではなかった。初めから、気持ちが離れてしまったことを謝罪するために、私はここまで坂を登ってきたのだ。
「……ごめんなさい」
私はつぶやいた。
「嫌いになったわけじゃないし、ほかに好きな人がいるわけでもないと。けど、そうじゃないんやけど……」
「そか」
糸瀬くんもつぶやいた。
「何となく、気づいとったばってん……」
「気づいてたと?」
すると、彼は笑って私を見た。
「LINEもメールも、前はあんなにハートマークなんかつけんかったとよ。気持ちを盛り上げようとしとるんやろな、って思っとった」
「ごめんなさい」
私はもう一度謝った。そんな言葉しか言うことができなかった。しかし、彼は首を振った。
「いや、初めっから知っとったけん。千紗はそういう子やってこと」
「そういうって、どういうこと? 遠距離がダメな人やって?」
「いや。そうやない」
「じゃ、なに?」
不可解なことを言う彼に、私は思わず聞いた。
「そんな人って? 私が糸瀬くんのこと、嫌いになるだろうって、そう思ってたと?」
糸瀬くんから気持ちが離れてしまったのは、私だ。彼じゃない。だから、どんなに責められても仕方ない。
けれど、理不尽だとはわかっていても、悲しみがこみ上げた。
東京に行ってからはいざ知らず、いままでは私も彼に誠実だったのだ。好きで好きで、たまらなくて——もし、私が東京に行かなかったら、そう、私たちは結婚していただろう、そんな未来が簡単に予想できるほど好きだったのだ。
だというのに、「そういう子やと思っとった」という彼の言い様はあんまりだ。私は決して
「勘違いせんとってな。知ってて付き合った俺が悪いばってん」
「だから、そういうふうにいわれたら——」
辛くなり、私は小さく叫んだ。
「私が全部悪いみたいじゃない! 私だって、ちゃんと糸瀬くんが好きだったんだよ! だから、最初から糸瀬くんのことが好きじゃなかったみたいに言わないで!」
「いや、千紗は最初から俺のことが好きじゃなかったとよ」
しかし、彼は首を振った。
「林田のことを好いとったと」
「それは……でも」
どうしてそんなことを知ってるんだろう——私は不意を突かれて息を呑んだ。けれど、彼は、
「よかと。そんなこと、俺は気にしとらんと」
そうして、静かに続けた。
「俺がそう知ったのは、千紗と付き合い始めてしばらくした頃だったとよ。お節介な女子が教えてくれたと。けど、俺は千紗と付き合うことを選んだと」
「どうして」
私は尋ねる。
「いま、私に振られることを知ってたみたいに言うなら、そこで振ってくれれば良かったのに」
「それはできんかったとよ。俺、千紗を好いっとったから」
彼の目が伏せられる。懐かしい過去を思い出すように笑う。
「それに、俺は知っとったけん。少なくとも高校の三年間は、千紗といられるってことを」
「どうして」
私は言葉を繰り返した。
「好きでもない人に告白する女なんか、信用できんけん。どうして三年も持つって思ったと」
「それは……最初に言ったと」
彼は目を上げて私を見た。
「なにを」
聞き返した私を愛おしそうな目で見る。そして、
「覚えとうと? あの夜。運命のくじ引きした夜や。俺、言ったけん。千紗はうちに来る野良猫に似とるって」
「だから、どういうことよ」
「だから、そういうことやけん」
私を見つめたまま、彼は言った。
「千紗は猫や。俺の傍にいれば俺のもんやけど、ほかの所に行けば、ほかの人のもんになるとよ」
「それ、どういうこと!」
誰にでもついていく尻軽と言われたような気がして、私は思わず叫んだ。
「言ったでしょ! 私はちゃんと糸瀬くんのことが好きだったんだって! それなのに、そんなこと言うなんて……」
「じゃ、試してみるとか?」
すると、糸瀬くんは不意に立ち上がり、私に近づいた。キスをするほど近くに迫る。
「今日、千紗がとげとげしいんは、俺と会うのが久しぶりだからやけん。いわば、借りてきた猫や。けど、俺が強引に抱きしめてやれば、そのうち感覚を思い出すと。それで、思い出したら元の従順な猫に戻るとよ。そうやないか? あの夜も、俺が一番近くにいたから、千紗は俺のことを好きになったんや」
彼の熱気が肌に迫る。息づかいが、鼓動が、私に過去を思い出させる。
肩を寄せ合って、夜まで話し込んだ日々を、宿題を一緒にやった夏を、初めてキスをした日のことを、私は鮮明に思い出す。
彼の言うことは本当だ——全身でそう感じ、私は動けなくなっていた。
いま、抱きしめられたら、キスをされたら、私は再び彼のものになるだろう。冷めてしまったと思った心に再び火が点き、彼と結婚する未来が現実に思えるだろう。
けれど——また東京に帰ってしまったら。
いままで気づかなかった自分の冷酷さに、私はぞっとした。私は猫だ。一度、飼い主の元を離れてしまえば、路頭に迷う。そして、再び探しに歩き出すのだ。新しい飼い主を探しに。
「……だから、俺はもう千紗には触れん。いま元の千紗に戻っても、また離れれば同じことやけん。それに、こういう日が来ることは、千紗が東京の大学に行くって言い出したときから、わかってたことやけん」
熱が離れる。風の中へ消えてしまう。くすぶり始めた胸の火は冷え、私は再び糸瀬くんのことが好きなのかどうか、わからなくなってしまった。
「さよなら、千紗。いままでありがとう」
糸瀬くんが去って行く。その背中が消えていく。
「糸瀬く——」
私は呼ぼうとし——口を閉じた。
呼び止めてはいけない。いや、呼び止める理由などない。
飼い主は去ってしまった。行き先などわからない。
ならば、私は探しに行かなくてはならない。次の人を、次の飼い主を。私にエサと寝床を与えてくれる、優しい人を。
のろのろと傘を手に取ると、私は彼とは反対側に歩きだした。足の重かった行きとは違い、下り坂を下りる足は軽く、心は新しい未来を想像して、どこか弾んでいた。
長崎は今日も雨だった——有名な歌がそう歌ってはいるが、聞くところによると、ここは特別に雨が多い地域ではないらしい。
それでもそんな歌が頭の隅にあるからか、私は本当にここは雨が多いのだと思っていた。思うことで実際の天気が変わるわけではないが、気持ちとしては大いに変わる。
だから、今日も出がけに雨が降り出しても、いつものことだと思って疑わなかった。長崎はいつも雨が降っているのだ、と。
しかし、しばらくすると、黒い雲間からところどころ強い光が差し込んできて、それはあっという間にあたりの景色を夏に変えた。私は畳んだ傘を持て余して、ズルズルと子供のように引きずりながら歩いた。
どうして傘ってこんなに邪魔なんだろう——急激な暑さによろけながら、私は思った。
雨が降っているときには自然に差していられても、晴れた途端、こんなにも邪魔になる。重たいわけじゃないけど、濡れているし、持ちにくいし、ああ、ホンット、晴れたときの傘ほど邪魔なものはない。
平日の午前に、傘を引きずる音は少々響きすぎ、私はようやくきちんとそれを腕にかけた。気を取り直して、歩き出す。目の前の坂道は、それでなくても気が遠くなるほど長い。
大学に入って最初の夏。
地元を離れて東京で暮らす私は、バイトで溜めたお金を使って、はるばるこの長崎まで帰ってきた。
坂の町。坂しかない町。ここがそう呼ばれていたことは知っていたけれど、離れるまでは実感がなかった。
坂を坂とも思っていなかったってわけじゃない。どんなに見慣れてたって、坂は坂だ。
けど、ほかの町には——少なくとも私が暮らし始めた東京には、こんなに坂がないものかと驚くほど、平坦だった。関東平野、つい地理で習った単語が頭に浮かび上がってきたくらいだ。
『東京って、坂がないとね』
どうしても訛ってしまう私の言葉に、新しい友人たちは、
『ないわけじゃないよ』
と、不思議そうに首をかしげ、その中の一人が、
『横浜にも、結構、坂あるよ』
と笑顔で言った。
けれど、その笑顔を見て、私は逆に「横浜にも坂がないんだな」と感じてしまった。
坂の町。坂しかない町。そこから出てきた私にとって、きっと横浜の坂はないに等しいものなのだろう。
背中にじんわり汗が出てくる。汗染みが出ないように下着を着てきたけれど、この分ではそれも無駄になりそうだ。
「あー、暑い」
声に出して言うと、ますます辛くなった。一歩を踏み出す足が辛い。畳んだ傘が邪魔だ。坂はまだ続いている。誰だって嫌になるような、この長い坂道。
けれど、同時に、私は辛いと感じている自分が不思議だった。なぜなら、私は彼のためにこの坂道を登っているのだ。高校の三年間付き合った、大好きな彼に会うために。
私たちの高校では、文化祭のイベントとしてある恒例行事がある。それは「運命のくじ引き」という名称で、二、三年生はともかく、新入生である一年生は絶対参加というものだった。
やり方は、簡単。生徒が男女別に分かれ、くじを引く。くじには数字が書いてあって、同じ数字を引いた男女がペアになるという仕組みだ。
そして、ペアになった男女はどうするかというと、最終日の後夜祭を一緒に過ごさなくてはならない。そこで行われるゲームやクイズを、ペアでこなすのだ。
先輩たちは数字を交換し、好きな人とペアになったり、またどうしても嫌な人とペアになった場合は、バックレるなんてことも許された。けれど、一年の場合はそうもいかない。
強制的に組まされたペアで、運良く意中の人と……だなんて、少女漫画じゃありそうな展開だけど、実際にはそんなことは起こらない。否が応でも、確率というものの恐ろしさを味わうことになる。実は、私もそんな一人だった。
高校に入学して数ヶ月だというのに、私にはもう意中の人がいた。同じクラスの林田くん。野球部だから坊主だったけど、背が高くてかっこいい人だった。
もちろん、だからといって、猛烈アタックをかけていたわけではない。私は地味で大人しいほうだったし、男子に声をかけるなんて、とてもじゃないけどできなかった。
遠くから見ているだけ。それが私の恋。中学の時もそうだったし、それは高校に入ったって変わらないんだ。そう思って、過ごしていた。
だから、「運命のくじ引き」は、そんな私にとって大チャンスだった。
林田くんとペアでありますように、林田くんとペアでありますように!
そう願った私が引いたのは、89番。引いた瞬間、
けど、それはもちろん林田くんではなく——糸瀬くんだった。とはいっても、私はそのとき、彼の名前さえ知らなかった。顔は……見たことがあるなという程度。きっと向こうも同じだっただろう。
『岩永千紗です……』
肩を落として名乗った私に、
『糸瀬春紀です。よろしく』
彼はそう言って、はにかむような笑みを見せた。
地味目だけど優しそうな人だな——自分のことは棚に上げて、私はそう思った。少なくとも、一緒にいて不快なタイプの人じゃない、それどころか、すごく心地良い人だ、と。
そして、その予感は見事なほどに当たった。単純に言うと、私たちはとても相性が良かった。
では、どんな風に良かったのか。そう聞かれると、説明に困る。
それは例えば、長年付き合って夫婦みたいになったカップル、とでもいうか、それとももっと大げさに言えば、私たちは生き別れた双子なんじゃないかと思うくらい。それは林田くんに感じているようなときめきとは違う、安心感のようなものだった。
だから、今日初めて彼を意識したばかりだというのに、私はもう彼の隣にいるのが楽になっていた。林田くんのことは好きだ。けど、それはそれとして、私はもう彼から離れたくなかった。
『……なんか、岩永さんって、猫みたいや』
後夜祭が終わりに近づいてきた頃、糸瀬くんはぼそりとそうつぶやいた。
『猫?』
私が聞き返すと、
『うん、うちに遊びに来る野良によく似とる。あいつ、エサやるとよう懐いてすり寄ってくるくせに、堂々と違う場所でエサもらっとるんじゃ』
そう言って、くすりと笑う。
『どういう意味ね?』
意味を捉えかねて、私が顔をしかめると、
『いや、何となくそう思っただけ……猫っぽいって言われないと?』
『言われたことない』
『そうかな、おかしいとね』
私をじっと見て、首をかしげる。私はふと恥ずかしくなって、
『おかしくないとよ。ってか、エサをもらいに来る野良に似てるって、失礼じゃないと? 私、エサもらっとらんし』
むっとふくれてそう言うと、
『じゃ、これ』
彼は笑いながら、ポケットから飴を取り出した。二人でやったクイズゲームの参加賞だ。
『それ、私もあるから』
私もポケットから出してみせると、
『いいよ、もらっとけ』
彼は私の手のひらに飴を乗せた。
その瞬間——一体世界の何が変わったというのか、私の全身がかあっと熱くなった。そして、目の前にいる糸瀬くんが好きで好きでたまらなくなった。
『ほら、飴あげたら目の色が変わったとよ』
糸瀬くんはおかしそうに笑った。
『そんなに飴、好きだったと?』
『ううん……』
飛び出して爆発してしまいそうな心臓の音を聞きながら、私は首を振った。それから——もう本当に何が起こったのかわからないが——こつん、糸瀬くんの肩におでこをぶつけた。
『糸瀬くん……あの……』
『なに? 岩永猫さん?』
冗談を言いながらも、私の行動にさすがに驚いたのだろう、糸瀬くんの声がうわずる。私は何が何だかわからないまま、
『……好きです』
そう告白した。
なぜそんなことを言ったのか、自分でもわからない。けれど、私の告白を糸瀬くんは笑って受けた。
『直前まで、林田くんが好きって言っとったがね!』
翌日、友人たちは私を取り囲んで大騒ぎし、どうして? なんで? を繰り返した。
けど、一晩明けたその日になっても、私はなぜ糸瀬くんに告白したのか、自分でも理由がわかっていなかった。
そんな私の様子を察し、友人たちはある結論を導き出した。
つまり、これは「運命のくじ引き」が引き合わせた本当の運命であり、本当の運命に出会った二人は、例えほかに好きな人がいたとしても惹かれ合わずにはいられないのだ、と。
「運命のくじ引き」が本当の運命を引き当てた——その噂はすぐに広まり、そして私たちは「奇跡のカップル」、そう呼ばれるようになったのだった。
「……久しぶり」
坂を登り切り、そしてもうしばらく歩くと、公園の東屋から懐かしい影が手を上げた。
「元気だったと?」
「うん、元気だった。……って、LINEでいつもしゃべってるじゃん」
私は答えると、向かい側に腰を下ろした。タオルハンカチを取り出し、汗を拭う。日陰に通る風が気持ちいい。
「しゃべってる
じゃん
?」すると、糸瀬くんは笑った。
「こがに短い間に、東京の人になったとね」
「そがなことないがね」
ぷっとふくれ、私は言った。
「私は変わっとらん」
「そうかね」
彼は目を細めると、私をじっと見た。高校時代には嬉しかったその視線が、いまは何となく嫌で、私はうつむいた。
〈やっと会えるね! 寂しかったよ!〉
スタンプで飾ったLINEではごまかせたその感情が、現実ではどうすることもできず、私は無言のまま、机の木目を見つめた。
大学生の私が公園に行く機会などない。あっても、東京の公園で東屋に座ったことはない。けれど、東京の東屋の机は、こんな木でできているものではなく、きっとプラスチックや石でできているのだろうと、そんなどうでもいい考えが頭をよぎった。
本当にどうでもいい——青春十八切符でわざわざ帰省した地元、それも彼氏を前に思うことじゃない。
「毎日、何してると?」
すると、彼がそう尋ねる。
「……LINEで報告してるじゃん」
じゃん
、またそう言ってしまったことを突っ込まれるかと思ったが、今度は彼は何もいわなかった。代わりに、小さく笑うような気配がした。「授業出て、レポート書いとるんじゃろ。それから新しい友達ができたとね。櫻川さんに、紀本さんに、河原井さんに……」
「ほら、言わなくても知っとる」
「それはそうじゃけど、ばってん——」
「だったら、聞かなくてもよかと」
自分でも言葉にトゲがあると思った。だから、なおさら顔が上げられなかった。けれど、どうしてこんなものの言い方になってしまうのか、わからなかった。
会いたい、そう思っていた気持ちは本当だ。高校時代の三年間が幸せだったのも。糸瀬くんのことが大好きだったのも。
それなのに、なんで私はこんなに苛立ってるんだろう。何がこんなに気持ちを重くするんだろう。
糸瀬くんを目の前にしても、何だか全然嬉しくない。楽しくない。あのときの燃えるような心が戻ってこない。
「……俺は、こっちでうまくやってるとよ」
私が聞かないからか、糸瀬くんは独り言を言うように話し始めた。
「東京に千紗が行ったのと同じに、こっちの大学にも東京の人がおると。長崎の方言に慣れんっちゅうて、いろいろおかしな聞き違いをするとよ。そりゃ、俺らは長崎弁なんてよう使わんばってん、そいつに言わせると、根本的にイントネーションが違うとね。だから、そういう話を聞く度に、千紗はうまくやれとうかねって心配になるとよ」
彼の手が、ためらいがちに私に伸ばされた。
何だろう、私は思い、それからふと思い出した。
高校の頃、私たちはよくこの公園で話をした。そのとき、二人はこんな風に向かい合うのではなく、隣に座り、ぴったりと肩を寄せ合っていた。
それは、寒い冬も、こんなふうに暑い夏でも同じだった。私の頭はいつも彼の肩にもたれ、彼はそんな私の手を握っていた。そうすると、彼の温もりが私の中に入り込み、私の温もりを足したそれが再び彼の中に戻り、その循環がいつまでも繰り返される。そんなことに、私は幸せを感じていたのだった。
けれど、いまの私は、差し出された手を無表情に見つめているだけだった。それも、なぜ彼がそうするのか、一瞬、わからずに。
まるで生き別れた双子みたいだ——あの夜感じた気持ちは、一体どこへ行ってしまったんだろう。私は少し混乱していた。
東京にいたときは、会いたいという気持ちでいっぱいだった。だというのに、実際に会ったらどうだろう。私はどこか他人行儀にかしこまっている。それどころか、彼の言葉を受け入れられず、イライラと当たり散らしている。
「……ほかに好きな人ができたと?」
とうとう彼が聞いた。聞かれても仕方ないことではあった。けれど、私は反発した。
「どうしてそがなこと言うと? もしかして、好きな人ができたんは、糸瀬くんのほうやないと?!」
言ってから、自分が顔を上げたことに気づいた。いままで避けていた彼と目が合った。そして、口を閉じた。
糸瀬くんは糸瀬くんのままだった。
あのときと変わらず、私を真っ直ぐに見つめていた。ということは、変わったのは私のほうだった。そう認めないといけないときがきていた。
「……別に好きな人なんて、おらんと」
私はつぶやいた。
それは本当だった。東京に好きな人なんていない。私の彼氏は、毎日LINEのやりとりをして、おはようからおやすみまで言い合う糸瀬くんだけだった。
「俺も、千紗のほかに好きなやつなんておらん」
彼もそう言った。やはり、真っ直ぐな目だった。その言葉が真実であることなど、目を見ればわかった。
「じゃあ、どうして……」
そんなこと聞くの——そう言うつもりだった。けれど、言えなかった。夏の日差しが照りつけているというのに、屋根に遮られたここは暗く、隠したい気持ちを隠し通せるような気がしていた。
糸瀬くんのことをもう好きではない——そんな自分でさえも認めたくない気持ちを、口が裂けても彼には言えない気持ちを。
私はうつむいたまま、机に立てかけた傘に視線を移した。
この雨の多い長崎で、糸瀬くんは私の優しい雨傘だった。雨には傘が必要であるように、私には糸瀬くんが必要だった。
けれど、私は東京に出てしまった。
東京が長崎よりも晴れの日が多いのかどうかは知らない。けれど、長崎に置いて行ってしまった私の傘を、私は必要とすることがなくなってしまった。
だからなのだろう——私の心が冷めてしまったのは。
ずいぶん身勝手な話だ。自分でもそう思う。けれど、私はきっとここを離れたときからそう思っていて——今回の帰省も、きっとその罪悪感がさせたのだろう。
会いたい——その気持ちは、好きな人に会いたいというものではなかった。初めから、気持ちが離れてしまったことを謝罪するために、私はここまで坂を登ってきたのだ。
「……ごめんなさい」
私はつぶやいた。
「嫌いになったわけじゃないし、ほかに好きな人がいるわけでもないと。けど、そうじゃないんやけど……」
「そか」
糸瀬くんもつぶやいた。
「何となく、気づいとったばってん……」
「気づいてたと?」
すると、彼は笑って私を見た。
「LINEもメールも、前はあんなにハートマークなんかつけんかったとよ。気持ちを盛り上げようとしとるんやろな、って思っとった」
「ごめんなさい」
私はもう一度謝った。そんな言葉しか言うことができなかった。しかし、彼は首を振った。
「いや、初めっから知っとったけん。千紗はそういう子やってこと」
「そういうって、どういうこと? 遠距離がダメな人やって?」
「いや。そうやない」
「じゃ、なに?」
不可解なことを言う彼に、私は思わず聞いた。
「そんな人って? 私が糸瀬くんのこと、嫌いになるだろうって、そう思ってたと?」
糸瀬くんから気持ちが離れてしまったのは、私だ。彼じゃない。だから、どんなに責められても仕方ない。
けれど、理不尽だとはわかっていても、悲しみがこみ上げた。
東京に行ってからはいざ知らず、いままでは私も彼に誠実だったのだ。好きで好きで、たまらなくて——もし、私が東京に行かなかったら、そう、私たちは結婚していただろう、そんな未来が簡単に予想できるほど好きだったのだ。
だというのに、「そういう子やと思っとった」という彼の言い様はあんまりだ。私は決して
そういう子
ではない。「勘違いせんとってな。知ってて付き合った俺が悪いばってん」
「だから、そういうふうにいわれたら——」
辛くなり、私は小さく叫んだ。
「私が全部悪いみたいじゃない! 私だって、ちゃんと糸瀬くんが好きだったんだよ! だから、最初から糸瀬くんのことが好きじゃなかったみたいに言わないで!」
「いや、千紗は最初から俺のことが好きじゃなかったとよ」
しかし、彼は首を振った。
「林田のことを好いとったと」
「それは……でも」
どうしてそんなことを知ってるんだろう——私は不意を突かれて息を呑んだ。けれど、彼は、
「よかと。そんなこと、俺は気にしとらんと」
そうして、静かに続けた。
「俺がそう知ったのは、千紗と付き合い始めてしばらくした頃だったとよ。お節介な女子が教えてくれたと。けど、俺は千紗と付き合うことを選んだと」
「どうして」
私は尋ねる。
「いま、私に振られることを知ってたみたいに言うなら、そこで振ってくれれば良かったのに」
「それはできんかったとよ。俺、千紗を好いっとったから」
彼の目が伏せられる。懐かしい過去を思い出すように笑う。
「それに、俺は知っとったけん。少なくとも高校の三年間は、千紗といられるってことを」
「どうして」
私は言葉を繰り返した。
「好きでもない人に告白する女なんか、信用できんけん。どうして三年も持つって思ったと」
「それは……最初に言ったと」
彼は目を上げて私を見た。
「なにを」
聞き返した私を愛おしそうな目で見る。そして、
「覚えとうと? あの夜。運命のくじ引きした夜や。俺、言ったけん。千紗はうちに来る野良猫に似とるって」
「だから、どういうことよ」
「だから、そういうことやけん」
私を見つめたまま、彼は言った。
「千紗は猫や。俺の傍にいれば俺のもんやけど、ほかの所に行けば、ほかの人のもんになるとよ」
「それ、どういうこと!」
誰にでもついていく尻軽と言われたような気がして、私は思わず叫んだ。
「言ったでしょ! 私はちゃんと糸瀬くんのことが好きだったんだって! それなのに、そんなこと言うなんて……」
「じゃ、試してみるとか?」
すると、糸瀬くんは不意に立ち上がり、私に近づいた。キスをするほど近くに迫る。
「今日、千紗がとげとげしいんは、俺と会うのが久しぶりだからやけん。いわば、借りてきた猫や。けど、俺が強引に抱きしめてやれば、そのうち感覚を思い出すと。それで、思い出したら元の従順な猫に戻るとよ。そうやないか? あの夜も、俺が一番近くにいたから、千紗は俺のことを好きになったんや」
彼の熱気が肌に迫る。息づかいが、鼓動が、私に過去を思い出させる。
肩を寄せ合って、夜まで話し込んだ日々を、宿題を一緒にやった夏を、初めてキスをした日のことを、私は鮮明に思い出す。
彼の言うことは本当だ——全身でそう感じ、私は動けなくなっていた。
いま、抱きしめられたら、キスをされたら、私は再び彼のものになるだろう。冷めてしまったと思った心に再び火が点き、彼と結婚する未来が現実に思えるだろう。
けれど——また東京に帰ってしまったら。
いままで気づかなかった自分の冷酷さに、私はぞっとした。私は猫だ。一度、飼い主の元を離れてしまえば、路頭に迷う。そして、再び探しに歩き出すのだ。新しい飼い主を探しに。
「……だから、俺はもう千紗には触れん。いま元の千紗に戻っても、また離れれば同じことやけん。それに、こういう日が来ることは、千紗が東京の大学に行くって言い出したときから、わかってたことやけん」
熱が離れる。風の中へ消えてしまう。くすぶり始めた胸の火は冷え、私は再び糸瀬くんのことが好きなのかどうか、わからなくなってしまった。
「さよなら、千紗。いままでありがとう」
糸瀬くんが去って行く。その背中が消えていく。
「糸瀬く——」
私は呼ぼうとし——口を閉じた。
呼び止めてはいけない。いや、呼び止める理由などない。
飼い主は去ってしまった。行き先などわからない。
ならば、私は探しに行かなくてはならない。次の人を、次の飼い主を。私にエサと寝床を与えてくれる、優しい人を。
のろのろと傘を手に取ると、私は彼とは反対側に歩きだした。足の重かった行きとは違い、下り坂を下りる足は軽く、心は新しい未来を想像して、どこか弾んでいた。