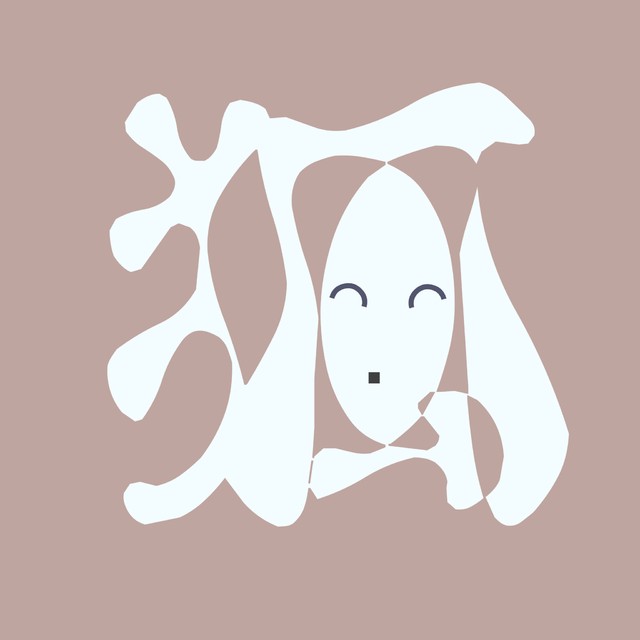最後の記憶
文字数 4,980文字
「ウルフマンは、わたしです」
まだ少女といって通用するあどけない表情。
停滞していた前線に台風が重なった暴風雨と、その影響で停電になった暗い部屋。
窓の外を走った稲光が、彼女の手の先で鈍く反射する。
私は彼女に刺された首をおさえながら、血が滴り落ちるのを感じていた。
*
停滞する前線の影響で、ここ数日、月はおろか太陽にすらお目にかかっていない。そこに台風が重なって未明から大荒れの天気になった。停電も発生していて夜よりも暗いものの、夜勤明けの朝だ。これから2日間の休みを心の拠り所に、傘も役に立たない暴風雨の中をびしょ濡れになりながらどうにかマンションに帰り着いた。
隣室の前を通りかかった時、稲妻が走り、部屋の中から女性の悲鳴と何かが割れる音がした。無視して通り過ぎればよかったのだが、気になって声をかけてしまった。暫くしてドアの隙間から顔をのぞかせた坂井玲奈 は何故かびしょ濡れだった。
彼女は大学生だ。別れた妻に着いて行った、もう何年も会っていない娘と年齢が近い。たまに挨拶を交わす程度だったが、スーパーからの帰り道で一緒になって話したのをきっかけに距離が縮んだ。人形のような美しい顔立ちで、並んで歩くと擦れ違う男たちが彼女に視線を止めるのがよく分かった。
——大丈夫?
雷に驚いてコップを割ってしまったと言う。足元を見る彼女につられて視線を落とすと、素足の彼女の足先に血が滲んでいるのが見えた。
——破片を踏んでしまって。
絆創膏がないと言うのでうちから持って来ると伝えて、一旦自分の部屋に戻った。ところが、気がつくと彼女はうちの玄関に立っていた。
——独りじゃ怖くって。
稲光とほぼ同時に雷鳴が轟いた。
——きゃっ!
彼女が腕の中にいた。細くて華奢なのに柔らかい女の身体だった。平静を保ち、彼女を部屋に上げてソファに座らせた。テーブルの上で乾電池式のLEDランタンを灯すと、キャンプみたいだと小さく笑う。Tシャツにショートパンツというスタイルで、濡れたTシャツが透けて目のやり場に困る。バスタオルを渡して肩に掛けさせた。自分では貼れないと言うので、傷口に破片が残っていないことを確かめて、用意した絆創膏を貼ってやった。
——何でそんなに濡れてるんだ?
——コンビニに行きかけて諦めて帰って来たところだったんです。
——危ないじゃないか。
物騒な事件も続いているんだと付け加えようとして、彼女は被害者の属性には該当しないことに思い至った。
——だって、食べるものが何もなかったから……。
最近ではコインランドリーで一緒になったこともあり、その時、父親から虐待を受けていた過去を聞かされた。高校卒業後は、弟と会うことはあっても両親とは疎遠らしい。弟のことは彼女がここに引っ越して来た日に、引っ越しの手伝いをしている姿を見た。その時は恋人かと思ったのだが、後に弟だと教えられた。弟を見たのはそれきりだ。
——もう少しここにいてもいいですか?
心細げに俯く彼女は、捨てられた仔猫のような守りたくなるオーラを発していた。
間隔をあけてソファの両端に座っていたが、沈黙が気まずい。
——スーパーの帰り道、満月前症候群の話をしたね。
彼女は満月の前後計5日間くらいは必ず体調を崩すのだそうだ。その日は満月から3日後で、やっと体調が戻って買い物に出られたとも言っていた。
——満月前症候群のこと、ご存知だったので嬉しかったです。理解されないことが多くて、実は恋人ともそれが原因で喧嘩別れしましたから。月が体調に影響するわけないとか、気のせいだとか甘えだとか言われて。お前は狼男かなんて言われたこともあります。せめて狼女にしてよって思いましたけど。
彼女は満月のような笑みを添えて明るく語ったが、私の胸は締め付けられた。満月前症候群を知ったのは、別れた妻がそうだったからだ。元妻も満月が近くなると頭痛や倦怠感が酷くなり、寝込むことが多かった。満月はほぼ1か月周期でやってくる。つまり毎月数日、酷い時は1週間もそんな状態が続く。玲奈が恋人から言われたという台詞は、私が妻に投げつけた言葉でもあった。妻の苦しみを理解せず、家事も出来ずに寝込んでいる妻に罵詈雑言を浴びせた。結果、妻は娘をつれて家を出た。満月前症候群のことを真剣に調べたのは家族を失った後のことだ。
そんなことを正直に打ち明けた。
——そうでしたか。理解するのが難しいのは分かります。
——最近でも頭痛とか倦怠感が酷いの?
——ええ、でも実は、わたしの場合はもっと厄介なことがあって——。
次の言葉を待ったが、彼女はそこで黙り込んでしまった。言いたくないこともあるだろう。私は彼女の脚を視線でなぞりながら、別の話題を探した。
——狼男といえば、ウルフマンの事件も早く解消すればいいけど。
彼女は伏し目がちだった目を一瞬だけ見開いて、またすぐ元の表情に戻った。
判明しているだけでも14人の犠牲者がいる連続殺人事件だ。被害者は40~50代の中年男性ばかり。いずれも男性器が切断された痕跡があるという猟奇殺人でもある。ある週刊誌が犯行は全て満月の前後に行われていることをセンセーショナルに報じて以降、この未知の犯人はウルフマンと呼ばれるようになった。
ひと際大きく雷が鳴り、悲鳴を上げた彼女がまた抱きついてきた。これまでも、細身ながら女性らしい曲線を帯びたその身体に劣情を催したことがないと言えば噓になる。妄想は自由だ。犯罪でも異常でもない。誰だって口には出せない妄想を抱くことくらいあるだろう。妄想だけで済んでいるうちは正常だ。私は妄想の中で幾度となく彼女を犯していた。
——大丈夫だよ。
言いながら腕に押し付けられた胸の膨らみを意識した時、自分の中で何かが弾 けた。
ソファの上に押し倒された彼女は、その瞬間だけ小さな悲鳴を上げたものの、抵抗は見せなかった。じっと目を見つめてくる。
——わたしのこと、抱きたいですか?
返事はせず、ゆっくりと顔を彼女に近づけた時、首筋に強い痛みが走り、反射的に飛び退いた。いつの間にそんなものを持っていたのか——静かに身体を起こす彼女の手にあるのは万年筆のようだった。
——山門 さんて最低な父親ですね。
——え?
——わたしの父と同じ。わたしはずっと父親から虐待を受けてました。弟ばかり可愛がられて、母は空気。でも、弟のことは嫌いじゃなかった。弟が悪いわけじゃないし、わたしのことを慕ってくれてもいた。父のことは大嫌い。母は嫌う価値すらない。
——中学2年の夏休みでした。その日は登校日で、家に帰ると母も弟もいなくて、酔った父だけがいました。無視して自分の部屋にいくと父が着いて来て、わたしのことをベッドに押し倒したんです。必死で抵抗しました。でも力では敵わない。諦めかけた時、手に触れたものがあったんです。この万年筆でした。父はわたしの制服のボタンを外すのに必死で、何だかその顔を見ていたら滑稽で、わたし、可笑しくなって笑っちゃいました。そしたら父と目が合って、次の瞬間にはこの万年筆を父の首に突き刺していました。
——後のことはよく覚えていません。家から父がいなくなって、でも、それ以外は何も変わらなかった気がします。どうしてでしょうね。
——でね、山門さん、その日、わたしが父を殺した日はちょうど満月だったの。それがウルフマンの最初の犯行——。そして、今日もちょうど満月なんですよ。昼も夜も関係ない。雲に覆われてたって関係ない。月はずっとそこにあるんです。そう——、
「ウルフマンは、わたしです」
まだ少女といって通用するあどけない表情は相変わらず人形のように美しい。稲光や雷鳴に怖がる素振りなど微塵も見せなくなった。
私は刺された首をおさえながら、自らの血が流れ落ちるのを感じていた。
「さっき言いかけたことを言いましょう。わたしの満月前症候群の厄介な症状。それは、発症している間のことを何も憶えていないってことなんです。父の首に突き立てた万年筆の感触。それだけは鮮明に憶えていて、それが満月の日のわたしの最後の記憶」
「自分を性的な目で見る中年男を父親同様に嫌悪して、殺して男性器を切除している——そういうことなのか?」
「どうなんでしょう。分かりません。だって何も憶えていないんですから」
死ぬことは怖くなかった。彼女の言う通り、私は最低な父親だ。娘のような女性に劣情を抱き、衝動を抑え切れなかった。もともと家族を失って以降、生きる意味など見い出せなかったのだ。死んで償おうとも思わなかった。生きる意味のない者が死んだところで、そこに意味など生まれはしないだろうから。
力が抜けるのを感じた。
首の傷がどの程度のものなのか分からないが、血は流れ続けている。このまま放置されれば死んでしまうかもしれない。
ふと感じた疑問が口を突いて出た。
「どうして自分がウルフマンだと知っているんだ?」
「え?」
「満月前後の記憶はないと君は言った。父親を刺した感触が最後の記憶だと。だったら、君はどうして自分がウルフマンだと知っているんだ?」
満月前症候群を発症している間だけ、以前の発症中の記憶も甦るのだと言われれば否定はできない。けれど、彼女がさっき言った意味はそうではない。
「そ、そんなこと……」
彼女の目に動揺が走った。
「自分のことだもの。知っていて当然でしょう」
「なら教えてくれ。どうやって男たちを殺した? 遺体をどう始末した?」
分かるはずがない。ついさっき、彼女自身が言ったのだ。自分にも分からない、何も憶えていないと。
どういうことなのか。私にも分からない。過去、満月の日に受けたトラウマによって満月の前後だけ殺人鬼になる——そんなことがあり得るのか。あるとして、何故彼女は憶えていないのか。何故憶えていないくせに知っているのか。
「本当に、君がウルフマンなのか?」
何度か稲妻が走り雷鳴が轟いても、玲奈は反応しなかった。視線が泳いでいた。その過程でたまたまこちらに向けられた視線が、明らかな意思を持って私の肩越しに背後を見たまま固まった。
そこに何がある?
振り向いたとき、誰かと激しくぶつかり、腹部に強い痛みが走った。
「なっ——」
立っていられなくなり、膝から崩れ落ちながら相手の顔を見た。
若い男。見知らぬ男——いや。
「き、君は——」
血に塗れたナイフを持ち、嫌らしい笑みを浮かべて立っていたのは玲奈の弟だった。
「駄目ですよ、お姉ちゃんに手を出しちゃ。ダサい中年男のくせして」
「き、君が——?」
「どこまで意識が持つか分からないけど、教えてあげましょう。そう。ウルフマンは姉じゃない。僕だ。父から虐待を受けていたのも僕なんだ。僕は父から性的虐待を受けていた。あの日も僕は父に犯されていたんです。そこに姉が帰って来た。僕たちのそんな姿を見て、もともと満月の日には不安定な質 だった姉はおかしくなった。姉の存在に気づかず腰を振り続けていた父の首に、姉は背後から万年筆を突き立てた。それだけが姉の犯行だ。おじさんが2人目だよ、姉が手を出したのは。何故だかわからないけど、喜んでいいんじゃないかな。でも、あとは全部僕なんだ。父の件以降、姉は満月の度に自分を見失った。僕はそれを利用した。父にとどめを刺した時、あいつの醜いブツを切り落としてやった時、僕はとても興奮したんだ」
声が遠くなったと思ったら、頬をぶたれた。目が覚めたように再び意識がはっきりとするが、すぐにまた霞んでいく。
「おじさん、ちゃんと聞いてる? お姉ちゃんにはおじさんみたいなスケベなおやじどもがいくらでも寄って来る。満月の前後、姉は暗示にかかり易くて、僕の言うままに動いた。僕一人じゃ死体の後始末も大変だからね。協力者は必要だったんだ。満月が過ぎれば綺麗さっぱり忘れてくれるし、今この瞬間のことだって3日もすれば憶えちゃいない。しかも自分がウルフマンだと思い込んでくれている。この先、捜査の手が及んでも捕まるのは僕じゃない。姉もこんな精神状態じゃ罪には問われないだろう。ね、おじさん、ああ、もうだめか。ちぇ、つまんないの。もう少し精神的に甚振 ってやろうと思ったのに——。ま、いっか。じゃあ、お姉ちゃん、とっとと済ませようか。この天気じゃ—————」
〈了〉
まだ少女といって通用するあどけない表情。
停滞していた前線に台風が重なった暴風雨と、その影響で停電になった暗い部屋。
窓の外を走った稲光が、彼女の手の先で鈍く反射する。
私は彼女に刺された首をおさえながら、血が滴り落ちるのを感じていた。
*
停滞する前線の影響で、ここ数日、月はおろか太陽にすらお目にかかっていない。そこに台風が重なって未明から大荒れの天気になった。停電も発生していて夜よりも暗いものの、夜勤明けの朝だ。これから2日間の休みを心の拠り所に、傘も役に立たない暴風雨の中をびしょ濡れになりながらどうにかマンションに帰り着いた。
隣室の前を通りかかった時、稲妻が走り、部屋の中から女性の悲鳴と何かが割れる音がした。無視して通り過ぎればよかったのだが、気になって声をかけてしまった。暫くしてドアの隙間から顔をのぞかせた坂井
彼女は大学生だ。別れた妻に着いて行った、もう何年も会っていない娘と年齢が近い。たまに挨拶を交わす程度だったが、スーパーからの帰り道で一緒になって話したのをきっかけに距離が縮んだ。人形のような美しい顔立ちで、並んで歩くと擦れ違う男たちが彼女に視線を止めるのがよく分かった。
——大丈夫?
雷に驚いてコップを割ってしまったと言う。足元を見る彼女につられて視線を落とすと、素足の彼女の足先に血が滲んでいるのが見えた。
——破片を踏んでしまって。
絆創膏がないと言うのでうちから持って来ると伝えて、一旦自分の部屋に戻った。ところが、気がつくと彼女はうちの玄関に立っていた。
——独りじゃ怖くって。
稲光とほぼ同時に雷鳴が轟いた。
——きゃっ!
彼女が腕の中にいた。細くて華奢なのに柔らかい女の身体だった。平静を保ち、彼女を部屋に上げてソファに座らせた。テーブルの上で乾電池式のLEDランタンを灯すと、キャンプみたいだと小さく笑う。Tシャツにショートパンツというスタイルで、濡れたTシャツが透けて目のやり場に困る。バスタオルを渡して肩に掛けさせた。自分では貼れないと言うので、傷口に破片が残っていないことを確かめて、用意した絆創膏を貼ってやった。
——何でそんなに濡れてるんだ?
——コンビニに行きかけて諦めて帰って来たところだったんです。
——危ないじゃないか。
物騒な事件も続いているんだと付け加えようとして、彼女は被害者の属性には該当しないことに思い至った。
——だって、食べるものが何もなかったから……。
最近ではコインランドリーで一緒になったこともあり、その時、父親から虐待を受けていた過去を聞かされた。高校卒業後は、弟と会うことはあっても両親とは疎遠らしい。弟のことは彼女がここに引っ越して来た日に、引っ越しの手伝いをしている姿を見た。その時は恋人かと思ったのだが、後に弟だと教えられた。弟を見たのはそれきりだ。
——もう少しここにいてもいいですか?
心細げに俯く彼女は、捨てられた仔猫のような守りたくなるオーラを発していた。
間隔をあけてソファの両端に座っていたが、沈黙が気まずい。
——スーパーの帰り道、満月前症候群の話をしたね。
彼女は満月の前後計5日間くらいは必ず体調を崩すのだそうだ。その日は満月から3日後で、やっと体調が戻って買い物に出られたとも言っていた。
——満月前症候群のこと、ご存知だったので嬉しかったです。理解されないことが多くて、実は恋人ともそれが原因で喧嘩別れしましたから。月が体調に影響するわけないとか、気のせいだとか甘えだとか言われて。お前は狼男かなんて言われたこともあります。せめて狼女にしてよって思いましたけど。
彼女は満月のような笑みを添えて明るく語ったが、私の胸は締め付けられた。満月前症候群を知ったのは、別れた妻がそうだったからだ。元妻も満月が近くなると頭痛や倦怠感が酷くなり、寝込むことが多かった。満月はほぼ1か月周期でやってくる。つまり毎月数日、酷い時は1週間もそんな状態が続く。玲奈が恋人から言われたという台詞は、私が妻に投げつけた言葉でもあった。妻の苦しみを理解せず、家事も出来ずに寝込んでいる妻に罵詈雑言を浴びせた。結果、妻は娘をつれて家を出た。満月前症候群のことを真剣に調べたのは家族を失った後のことだ。
そんなことを正直に打ち明けた。
——そうでしたか。理解するのが難しいのは分かります。
——最近でも頭痛とか倦怠感が酷いの?
——ええ、でも実は、わたしの場合はもっと厄介なことがあって——。
次の言葉を待ったが、彼女はそこで黙り込んでしまった。言いたくないこともあるだろう。私は彼女の脚を視線でなぞりながら、別の話題を探した。
——狼男といえば、ウルフマンの事件も早く解消すればいいけど。
彼女は伏し目がちだった目を一瞬だけ見開いて、またすぐ元の表情に戻った。
判明しているだけでも14人の犠牲者がいる連続殺人事件だ。被害者は40~50代の中年男性ばかり。いずれも男性器が切断された痕跡があるという猟奇殺人でもある。ある週刊誌が犯行は全て満月の前後に行われていることをセンセーショナルに報じて以降、この未知の犯人はウルフマンと呼ばれるようになった。
ひと際大きく雷が鳴り、悲鳴を上げた彼女がまた抱きついてきた。これまでも、細身ながら女性らしい曲線を帯びたその身体に劣情を催したことがないと言えば噓になる。妄想は自由だ。犯罪でも異常でもない。誰だって口には出せない妄想を抱くことくらいあるだろう。妄想だけで済んでいるうちは正常だ。私は妄想の中で幾度となく彼女を犯していた。
——大丈夫だよ。
言いながら腕に押し付けられた胸の膨らみを意識した時、自分の中で何かが
ソファの上に押し倒された彼女は、その瞬間だけ小さな悲鳴を上げたものの、抵抗は見せなかった。じっと目を見つめてくる。
——わたしのこと、抱きたいですか?
返事はせず、ゆっくりと顔を彼女に近づけた時、首筋に強い痛みが走り、反射的に飛び退いた。いつの間にそんなものを持っていたのか——静かに身体を起こす彼女の手にあるのは万年筆のようだった。
——
——え?
——わたしの父と同じ。わたしはずっと父親から虐待を受けてました。弟ばかり可愛がられて、母は空気。でも、弟のことは嫌いじゃなかった。弟が悪いわけじゃないし、わたしのことを慕ってくれてもいた。父のことは大嫌い。母は嫌う価値すらない。
——中学2年の夏休みでした。その日は登校日で、家に帰ると母も弟もいなくて、酔った父だけがいました。無視して自分の部屋にいくと父が着いて来て、わたしのことをベッドに押し倒したんです。必死で抵抗しました。でも力では敵わない。諦めかけた時、手に触れたものがあったんです。この万年筆でした。父はわたしの制服のボタンを外すのに必死で、何だかその顔を見ていたら滑稽で、わたし、可笑しくなって笑っちゃいました。そしたら父と目が合って、次の瞬間にはこの万年筆を父の首に突き刺していました。
——後のことはよく覚えていません。家から父がいなくなって、でも、それ以外は何も変わらなかった気がします。どうしてでしょうね。
——でね、山門さん、その日、わたしが父を殺した日はちょうど満月だったの。それがウルフマンの最初の犯行——。そして、今日もちょうど満月なんですよ。昼も夜も関係ない。雲に覆われてたって関係ない。月はずっとそこにあるんです。そう——、
「ウルフマンは、わたしです」
まだ少女といって通用するあどけない表情は相変わらず人形のように美しい。稲光や雷鳴に怖がる素振りなど微塵も見せなくなった。
私は刺された首をおさえながら、自らの血が流れ落ちるのを感じていた。
「さっき言いかけたことを言いましょう。わたしの満月前症候群の厄介な症状。それは、発症している間のことを何も憶えていないってことなんです。父の首に突き立てた万年筆の感触。それだけは鮮明に憶えていて、それが満月の日のわたしの最後の記憶」
「自分を性的な目で見る中年男を父親同様に嫌悪して、殺して男性器を切除している——そういうことなのか?」
「どうなんでしょう。分かりません。だって何も憶えていないんですから」
死ぬことは怖くなかった。彼女の言う通り、私は最低な父親だ。娘のような女性に劣情を抱き、衝動を抑え切れなかった。もともと家族を失って以降、生きる意味など見い出せなかったのだ。死んで償おうとも思わなかった。生きる意味のない者が死んだところで、そこに意味など生まれはしないだろうから。
力が抜けるのを感じた。
首の傷がどの程度のものなのか分からないが、血は流れ続けている。このまま放置されれば死んでしまうかもしれない。
ふと感じた疑問が口を突いて出た。
「どうして自分がウルフマンだと知っているんだ?」
「え?」
「満月前後の記憶はないと君は言った。父親を刺した感触が最後の記憶だと。だったら、君はどうして自分がウルフマンだと知っているんだ?」
満月前症候群を発症している間だけ、以前の発症中の記憶も甦るのだと言われれば否定はできない。けれど、彼女がさっき言った意味はそうではない。
「そ、そんなこと……」
彼女の目に動揺が走った。
「自分のことだもの。知っていて当然でしょう」
「なら教えてくれ。どうやって男たちを殺した? 遺体をどう始末した?」
分かるはずがない。ついさっき、彼女自身が言ったのだ。自分にも分からない、何も憶えていないと。
どういうことなのか。私にも分からない。過去、満月の日に受けたトラウマによって満月の前後だけ殺人鬼になる——そんなことがあり得るのか。あるとして、何故彼女は憶えていないのか。何故憶えていないくせに知っているのか。
「本当に、君がウルフマンなのか?」
何度か稲妻が走り雷鳴が轟いても、玲奈は反応しなかった。視線が泳いでいた。その過程でたまたまこちらに向けられた視線が、明らかな意思を持って私の肩越しに背後を見たまま固まった。
そこに何がある?
振り向いたとき、誰かと激しくぶつかり、腹部に強い痛みが走った。
「なっ——」
立っていられなくなり、膝から崩れ落ちながら相手の顔を見た。
若い男。見知らぬ男——いや。
「き、君は——」
血に塗れたナイフを持ち、嫌らしい笑みを浮かべて立っていたのは玲奈の弟だった。
「駄目ですよ、お姉ちゃんに手を出しちゃ。ダサい中年男のくせして」
「き、君が——?」
「どこまで意識が持つか分からないけど、教えてあげましょう。そう。ウルフマンは姉じゃない。僕だ。父から虐待を受けていたのも僕なんだ。僕は父から性的虐待を受けていた。あの日も僕は父に犯されていたんです。そこに姉が帰って来た。僕たちのそんな姿を見て、もともと満月の日には不安定な
声が遠くなったと思ったら、頬をぶたれた。目が覚めたように再び意識がはっきりとするが、すぐにまた霞んでいく。
「おじさん、ちゃんと聞いてる? お姉ちゃんにはおじさんみたいなスケベなおやじどもがいくらでも寄って来る。満月の前後、姉は暗示にかかり易くて、僕の言うままに動いた。僕一人じゃ死体の後始末も大変だからね。協力者は必要だったんだ。満月が過ぎれば綺麗さっぱり忘れてくれるし、今この瞬間のことだって3日もすれば憶えちゃいない。しかも自分がウルフマンだと思い込んでくれている。この先、捜査の手が及んでも捕まるのは僕じゃない。姉もこんな精神状態じゃ罪には問われないだろう。ね、おじさん、ああ、もうだめか。ちぇ、つまんないの。もう少し精神的に
〈了〉