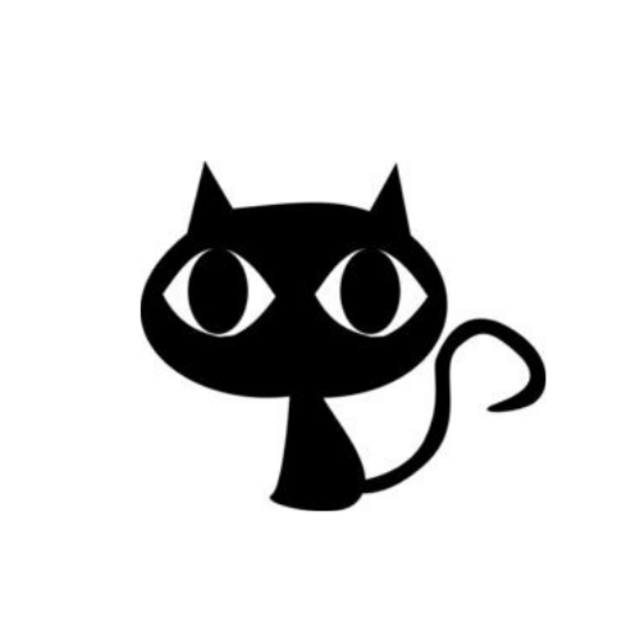楮(こうぞ)
文字数 6,354文字
薄暗い納屋で倦 ねていると、閉まりかけていた板戸が音なく開いた。差し込んだ色味の枯れた光の中で、真砂子の吐息が白く上がった。
「母さん、これ、どうしよか」
祐介の手には、押し寿司の木型があった。
「これだけじゃのうて、ようけあるんやけど」
「……誰か、もろうてくれる人がおるやろか」
「さあ。みんなそれぞれに持ちゆうやない?」
「そうよねえ。私もよう作らんし」
「なら――」
もったいないけど、捨てとこか――今日に限っても、何度目の台詞だろう。そう繰り返すうちに心は削がれていくようで、いたたまれず、真砂子は戸外へ出たのだった。そして、古びた納屋の戸を開けた。家の中と同じく、整理整頓されたそこには、使い方も分からないような農具たちが、出番を待ちかね、眠っていた。春、夏、秋、冬。去年死んだ真砂子の母、タケの営みは、巡る季節と共にあった。十六年前に夫の長蔵を亡くしてからは、そのあり方がより濃くなった。顔の見えない人のためではなく、自分の食べるだけ、真砂子や孫たちの食べるだけの米を作れば、時間はありのままに流れていく。早春、水路の掃除から始まって、代掻きに畔作り、苗作りに田植え、草引き、見回り、収穫にはざ 掛け、稲扱き、精米――季節に呼び起こされ、使われた農具たちは、仕事が終われば丁寧に泥を落とされ、何十年変わらぬ場所で眠りに落ちる。死ぬ前日まで、仕事をしていたタケのように、季節が巡れば再び目を覚ますのだと、当たり前のように信じ切って。
「わ、これ風呂やん。タンスと一緒に粗大ゴミにせにゃあ」
そのとき、祐介が素っ頓狂な声を上げた。真砂子は我に返り、その「風呂」を見て、笑うように息を漏らした。
「それは風呂やない。コシキよ」
「コシキ?」
「あんたは知らいでか。ばあちゃん、冬んなると——そうやね、ちょうど今頃になると、カジをやっとったでよ」
人の背丈ほどある、木でできた樽のようなコシキは、それを知らなければ五右衛門風呂のように見えるのか。ぴんと来ない顔の祐介に、真砂子は隅に立てかけられた、象牙のようなカジガラを指した。
「これ何。木?」
「カジガラやて。カジを蒸して、皮剥いで、その皮を紙漉きの材料にするろう? これは皮とった後のガラやけど、杭らぁに使うで、取っておくが」
しかし、それもタケが死んでしまえば、ただのゴミだ。
「紙漉き……」
祐介は一寸考え、「ああ、和紙の」と得心したように頷いた。
「中学ん時に、社会見学みたいなもんでやったがよ、あれか」
「吉野さんっちゅうおんちゃん、葬式に来たろう。あの人んくへやっとったでよ」
「いや、その人は分からんけど……そうか」
「あんたにも手伝わせたら良かったかも分からんな。ばあちゃんもそう思っとったかも」
「自分がようやらんくせに、何を」
「そら、わたしはやらんよ」
「なら、俺もやらせんよ。この人はなんで自分のやらんもんを、人にやらせるかね」
「ほいでもよ」
真砂子は骨のように滑らかなカジガラを撫でた。タケが死んだのは、カジを刈り終えたという晩のことだった。「明日に蒸すがやけんど、ちっと手伝 てくれんかね」——伺いの電話に、勤め人の真砂子は「急やき、無理よ」と答えざるを得なかった。「それに——」。高校卒業後、家を飛び出した真砂子は、祐介の言う通り泥を嫌い、タケの手伝いなどしたことがなかった。それは祐介を授かり、一人舞い戻った町で産み、女手一つで育てた後も同じだった。
タケもタケで、娘の手伝いなどなくとも、一人でうまくやっているようだった。一人で無理がある仕事——特にカジをするときには人を頼み、コシキを引っ張り出すのだった。「どうしたが、頼んだ人が来られなくなったが?」。それを知っていた真砂子は聞いたが、タケは「ほんなら、ええでね」と特に不機嫌になるわけでもなく、電話を置いてしまった。
しかし、それがタケとの最後の会話だった。次の日、胸騒ぎを覚えた真砂子が仕事終わりに山へ行くと、タケは布団の中で冷たくなっていた。丁寧に束ねられたカジはそのまま軒下にあり、タケが昨晩のうちに息を引き取ったことを教えていた。同じことを、医者も言った。「昨晩やろうね。でも穏やかなお顔をしとるから、苦しまなかったろうよ」と。
黙り込んだ真砂子をよそに、祐介は手の木型をゴミ袋に放ると、もう一度視線をコシキへやった。それから、小さく首を振り、冬の光に顔を向け、眩しそうに目を細めた。
カジを蒸すためのコシキは、一メートル半ほどあるカジの長さに合わせた、底のないドラム缶のような形状をしていて、使うときには別に木枠を組み立て、天秤のようなその片方に吊るして使う。そうして大釜で湯を沸かしたところに、カジの束を縦に詰め込み、テコの原理で持ち上げたコシキをすっぽりかぶせて蒸し上げる。適当なところで、もう一度テコの力でコシキを持ち上げ、カジを取り出す。乾いた薄青の空に、入道雲のような蒸気が上がる。その白に見惚れる余裕もなく、カジは冷めぬうちにムシロで包まれ、皮が剥かれる。ゴボウのように黒いカジの皮と、象牙のように白いカジガラが見る間に分かれ、積み上がっていく。その皮の方はまとめて紙漉きに回し、芯も束ねて春の苗立て に取っておく。その一連が、タケが長年続けたカジ仕事のやり方だった。
この山間の集落では、田と言っても、一枚が五畝ほどの棚田であり、稲を育てる平面よりも、斜面 の面積のほうが勝る。しかし、そのネキを放っているかといえばそうでもなく、そこにはゼンマイなどの山菜が自然に生えており、草刈りはそれら「春の楽しみ」を避けて行われる。一方、紙漉きのためのカジはといえば、これは地生えではなく、人の手によって植えられた冬の仕事の一つであった。幼い頃から見るでもなく、風景の一つとしてタケの仕事を見てきた真砂子の脳裏には、その光景がはっきりと焼きついていた。
秋。よく乾いた稲束がすっかり取り込まれてしまう頃、町のあちこちで祭りが催される。豊穣を祝う祭りだ。真砂子の集落でも豊穣祭とお宮祭りという二種類の祭りが開かれ、静かな集落はいっとき、賑わいを帯びる。しかし、それが終わってしまえば、再び山は静けさに包まれる。カジを刈るのは、その静けさが日常へと戻った頃である。
大工だった長蔵が建てたこの家は、一家所有の田から狭く急な坂道を十メートルほど上がった、坂の中腹あたりにあった。さらに坂を上がると、そこにはタケの兄——真砂子にとっては叔父の家があり、「義兄さんより高い場所に家は建たらん」という長蔵の一言で坂の中腹に決まったのだと、真砂子はタケに聞いたことがある。昔気質な話のようだが、実のところそれは方便で、「あんな坂、よう上らん」というのが本音だったと、これは長蔵が死んだときにタケが漏らした。その頃には、子がなかった叔父の家も途絶えていて、タケはその家の世話も欠かさなかったのだから、結局、坂を上らずに済んだのは、先に逝った長蔵だけだったということになる。しかし、その冬も変わらず刈ったカジ束を背負い、坂を上るタケは、「お父さんの判断は正しかったでね」と、白い息の下で笑うのだった。
「白黒写真で撮ったら、いつの時代かと思うほどの風景よね。大変なばっかりで、大したお金にもなりやせんし」
遅い昼を取りながら、真砂子は隣の祐介に話しかけるでもなく、独り言ちた。台風避けの長い軒は、冬の太陽こそ遮ることなく、親子の並ぶ縁側を温めている。真砂子が息を吐き出すと、ふうん、うまそうでもなく幕の内弁当をかき込みながら祐介が応えた。
「でも、ばあちゃんの写真なんかないろう。写真嫌いなんやから。魂が抜かれるゆうて、結婚式の写真も撮らざったに」
「それも、いつ時代の人間やっちゅうことやねえ」
真砂子は小さく笑った。町の狭いアパートに移した仏壇に飾ったタケの遺影は、長蔵の葬式のときのものだった。
「じいちゃんが逝んだけぇ、もういつ魂抜いてくれたちかまんゆうて撮ったがよねえ。けんど、立ち直ったら気持ちが変わって、やっぱしそんなもん撮らんといてくれゆうて。だから、撮らんずついたら、とうとう逝んでしもた」
「どうせ、遺影で必要になるんじゃけ、こっそり撮っといたらよかったがよ」
饒舌な母を気遣うように、祐介が言った。
「何も残らんのは、寂しいろ」
「どうやろうねえ」
真砂子はタケの顔を思い浮かべようとした。しかし、薄青の空のせいか、浮かんだのはタケの姿ではなく、カジを蒸す蒸気の鮮烈なまでの白さだった。真砂子は笑うように息をついた。
「あったらあったで、寂しいもんかもしらんで。記憶の中にあるほうが、ほんとの姿のままかもしれん」
「そういうもんかね」
祐介は言うと立ち上がり、空になった弁当箱をゴミ袋に突っ込んだ。それから、ふと坂の下に視線をやり、真砂子を振り向いた。
「誰ぞ来ゆうで。車が止まっちゅう」
「知らん車やね」
真砂子も立ち上がった。杉の樹間を透かすように、そちらを見る。枯れ草の色を蹴散らすような、きついオレンジ色が眼を射た。
「鉄砲撃ちやろか。この先に用があるゆうんは、それくらいやろ」
「なら、落ちたかの。見てきちゃろう」
集落道は細く、崖から落ちまいとするあまり、逆側の側溝にタイヤを落とす車が少なくない。様子を窺っていると、木の向こうに白髪頭がよぎり、「こんにちは」、訛りのない男の声が聞こえた。「どうも」、応える祐介の声。「大丈夫ですか」。
「え?」
「いや、手伝いが必要やろかと思うて」
「あ、すみません。ここに停めたら迷惑でした?」
「大丈夫ですけど、————」
どうやら脱輪したわけではないらしい。真砂子は、声から意識を逸らし、片付けに戻ろうとした。と、そのとき、「ああ——」、男の声がやけに明るく響いた。
「あのおばあさんのお孫さんなんですか。じゃ、ちょうどよかった。おばあさん、お元気ですか? あ、いえ、僕、怪しいもんじゃないんです。実は僕、地方の小さい祭りが大好きで。ここも面白い祭りがあるって言うんで、来てみたんですよ。そしたら、もう、このあたりは棚田が美しいでしょう。日本にまだこんな場所が残ってたんだって、僕、びっくりしちゃって。感動しちゃって。それで、これは絶対、残さなきゃならない風景だろうって——ああ、僕、カメラも祭りと同じくらい好きなもんで、それでもうその年のうちにもう一回有給とって、ちょうど今頃なんだけど、撮りに来たんですよ。それで——そうだ、見てもらった方が早いですね。どうぞ、これ」
男の声が途切れ、元の静寂が山を包んだ。祐介の息を呑む音が聞こえたような気がしたが、さすがにそれは空耳だろうか。祐介の沈黙があまりに長かったのか、男は痺れを切らしたように言った。
「ね、これ、よく撮れてるでしょう。賞をとって、新聞に載ったんですよ。日日新聞。見たかなあと思ったけど、その様子じゃ見てなかったみたいですね。じゃあ、わざわざ持ってきて良かった。ほら、審査員のコメント……『忘れ去られた日本の原風景を運良くも捉えた』って。ひどいでしょ、僕の腕とは関係なく、題材が良かったみたいな、ねえ。まあ、でもそりゃそうだって話なんて、報告ついでにリベンジというか、また撮らせてもらおうかなぁ、なんて——」
「祖母は、去年に亡くなりました」
固い声が、男の明るい声を遮った。
「それは……御愁傷様です」
男は声音をがらりと変えた。
「えっと、去年か。じゃあもうこの写真の後というか……」
「直後ですね」
「え? それはすごい偶然というか……えっと、じゃあお線香でもあげさせてもらっても——」
「済みません。仏壇はここにないがです」
「そうですか。……じゃ、これだけでも」
消え入るような声の後、車のドアが閉まる音がし、続いてエンジン音が聞こえた。オレンジ色が後退と前進を繰り返し、別れの挨拶のように赤いテールランプを一瞬光らせ、遠ざかっていく。タケを撮った人間がいた——ぼうとしていると、風が動き、気がつくと目の前に封筒を差し出す祐介がいた。真砂子はゆっくりと目を落とした。
「……聞こえとった?」
「うん。聞いとった」
「嫌なら、わしが捨てとこか」
「…………」
——どんな写真やった?
真砂子は光にかき消されるほどの声でつぶやいた。自分で見いやと言うように、祐介が封筒を押しつけた。真新しい封筒からは、糊とインクの匂いが立ち上った。冷たくかさついた指で中を探り、引き抜くと、大きく引き伸ばされた写真が陽に反射し、真砂子の目を眩ませた。直後、真砂子はタケと再会した。丁寧に束ねたカジを背負い、家までの坂道を上がる母。それは真砂子の記憶より、少し、ほんの少し小さな背中だった。
「これ、後ろから撮っちゅうろう」
祐介の声は低かった。
「ばあちゃんの許可なしにやったんで」
そやね——相槌は、声にならなかった。真砂子の目からは涙が湧いて、それはいくら固く唇をかみしめ、止めようとしても無駄だった。母さん、母さん。声にならない声で真砂子は叫んだ。その真砂子から目を逸らし、祐介が鼻をすすった。その途端、ぽたりと写真に滴が落ちた。
午後も三時を過ぎ、太陽が山に隠れると、あたりの気温は一気に下がり、底冷えがする。深緑色に押し黙った杉は一層暗く、身じろぎもせずに立っている。坂道の下に停めた、借り物の軽トラックには、粗大ゴミとなったタンスやコシキ、ゴミ袋が山積みされ、それは落ちないようにロープで固定されていた。
「今日はこればぁで置こか。ゴミの持ち込みは夕方までやし」
納屋の戸を閉めた祐介が、少し疲れた顔で言った。真砂子は頷き、玄関の鍵をかけた。無口なまま、二人で坂を下り、軽トラに乗り込む。と、真砂子の手が、助手席のドアを開けたまま止まった。
「何しよん。はよ乗りや」
「うん」
しかし、真砂子は片手でドアを押さえたまま、荷台のゴミ袋をじっと見た。ゴミとなったあの木型が、半透明の袋から透けていた。
「祐介」
「何?」
「母さんさ——」
真砂子はゆっくりと口を開いた。
「母さん、ばあちゃんの仕事をやってみよか。ここへ住んで、田ぁやって、山菜取って、カジやって。ほいだら、押し寿司も作る暇があるろう。木型もコシキもほかすことないし、家もこれ以上片付けいでもええし、そう、町の家にはあんたが住んで、気が向いたら、ときどき見にきてくれたらええ。母さんがばあちゃんにしよったように、月に一回でも、二回でも。そりゃ初めっからうまくはできんかもしれんけど、あんたにやるくらいの米ならできようね。なんの、九十のばあちゃんがやりよったことを、わたしができんでどうする。わたしだってまだまだ——」
「母さん」
熱に浮かされたように言葉を継ぐ真砂子を、祐介の落ち着いた声が遮った。真砂子は祐介を見た。祐介も真っ直ぐ真砂子を見た。運転席の窓を背に影となった祐介は、それまでのどんな瞬間よりも大人びていた。その祐介の口元が小さく動いた。
「無理よ」
「……でも」
「無理ぞね」
祐介の言葉に、真砂子は糸が切れたように口を噤んだ。それからしずしずと助手席に乗り込んだ。乾いた音で、ドアが閉まった。冷え切ったエンジンは何度か軋むような音を立てた後、ようやく発進の兆しを見せる。祐介が重そうにハンドルを切り、ゆっくりアクセルを踏み込んでいく。一年分の草を蓄えた田んぼと、今年も刈りどきを迎えたカジが、その後ろ姿を見送った。
「母さん、これ、どうしよか」
祐介の手には、押し寿司の木型があった。
「これだけじゃのうて、ようけあるんやけど」
「……誰か、もろうてくれる人がおるやろか」
「さあ。みんなそれぞれに持ちゆうやない?」
「そうよねえ。私もよう作らんし」
「なら――」
もったいないけど、捨てとこか――今日に限っても、何度目の台詞だろう。そう繰り返すうちに心は削がれていくようで、いたたまれず、真砂子は戸外へ出たのだった。そして、古びた納屋の戸を開けた。家の中と同じく、整理整頓されたそこには、使い方も分からないような農具たちが、出番を待ちかね、眠っていた。春、夏、秋、冬。去年死んだ真砂子の母、タケの営みは、巡る季節と共にあった。十六年前に夫の長蔵を亡くしてからは、そのあり方がより濃くなった。顔の見えない人のためではなく、自分の食べるだけ、真砂子や孫たちの食べるだけの米を作れば、時間はありのままに流れていく。早春、水路の掃除から始まって、代掻きに畔作り、苗作りに田植え、草引き、見回り、収穫に
「わ、これ風呂やん。タンスと一緒に粗大ゴミにせにゃあ」
そのとき、祐介が素っ頓狂な声を上げた。真砂子は我に返り、その「風呂」を見て、笑うように息を漏らした。
「それは風呂やない。コシキよ」
「コシキ?」
「あんたは知らいでか。ばあちゃん、冬んなると——そうやね、ちょうど今頃になると、カジをやっとったでよ」
人の背丈ほどある、木でできた樽のようなコシキは、それを知らなければ五右衛門風呂のように見えるのか。ぴんと来ない顔の祐介に、真砂子は隅に立てかけられた、象牙のようなカジガラを指した。
「これ何。木?」
「カジガラやて。カジを蒸して、皮剥いで、その皮を紙漉きの材料にするろう? これは皮とった後のガラやけど、杭らぁに使うで、取っておくが」
しかし、それもタケが死んでしまえば、ただのゴミだ。
「紙漉き……」
祐介は一寸考え、「ああ、和紙の」と得心したように頷いた。
「中学ん時に、社会見学みたいなもんでやったがよ、あれか」
「吉野さんっちゅうおんちゃん、葬式に来たろう。あの人んくへやっとったでよ」
「いや、その人は分からんけど……そうか」
「あんたにも手伝わせたら良かったかも分からんな。ばあちゃんもそう思っとったかも」
「自分がようやらんくせに、何を」
「そら、わたしはやらんよ」
「なら、俺もやらせんよ。この人はなんで自分のやらんもんを、人にやらせるかね」
「ほいでもよ」
真砂子は骨のように滑らかなカジガラを撫でた。タケが死んだのは、カジを刈り終えたという晩のことだった。「明日に蒸すがやけんど、ちっと
タケもタケで、娘の手伝いなどなくとも、一人でうまくやっているようだった。一人で無理がある仕事——特にカジをするときには人を頼み、コシキを引っ張り出すのだった。「どうしたが、頼んだ人が来られなくなったが?」。それを知っていた真砂子は聞いたが、タケは「ほんなら、ええでね」と特に不機嫌になるわけでもなく、電話を置いてしまった。
しかし、それがタケとの最後の会話だった。次の日、胸騒ぎを覚えた真砂子が仕事終わりに山へ行くと、タケは布団の中で冷たくなっていた。丁寧に束ねられたカジはそのまま軒下にあり、タケが昨晩のうちに息を引き取ったことを教えていた。同じことを、医者も言った。「昨晩やろうね。でも穏やかなお顔をしとるから、苦しまなかったろうよ」と。
黙り込んだ真砂子をよそに、祐介は手の木型をゴミ袋に放ると、もう一度視線をコシキへやった。それから、小さく首を振り、冬の光に顔を向け、眩しそうに目を細めた。
カジを蒸すためのコシキは、一メートル半ほどあるカジの長さに合わせた、底のないドラム缶のような形状をしていて、使うときには別に木枠を組み立て、天秤のようなその片方に吊るして使う。そうして大釜で湯を沸かしたところに、カジの束を縦に詰め込み、テコの原理で持ち上げたコシキをすっぽりかぶせて蒸し上げる。適当なところで、もう一度テコの力でコシキを持ち上げ、カジを取り出す。乾いた薄青の空に、入道雲のような蒸気が上がる。その白に見惚れる余裕もなく、カジは冷めぬうちにムシロで包まれ、皮が剥かれる。ゴボウのように黒いカジの皮と、象牙のように白いカジガラが見る間に分かれ、積み上がっていく。その皮の方はまとめて紙漉きに回し、芯も束ねて春の
この山間の集落では、田と言っても、一枚が五畝ほどの棚田であり、稲を育てる平面よりも、
秋。よく乾いた稲束がすっかり取り込まれてしまう頃、町のあちこちで祭りが催される。豊穣を祝う祭りだ。真砂子の集落でも豊穣祭とお宮祭りという二種類の祭りが開かれ、静かな集落はいっとき、賑わいを帯びる。しかし、それが終わってしまえば、再び山は静けさに包まれる。カジを刈るのは、その静けさが日常へと戻った頃である。
大工だった長蔵が建てたこの家は、一家所有の田から狭く急な坂道を十メートルほど上がった、坂の中腹あたりにあった。さらに坂を上がると、そこにはタケの兄——真砂子にとっては叔父の家があり、「義兄さんより高い場所に家は建たらん」という長蔵の一言で坂の中腹に決まったのだと、真砂子はタケに聞いたことがある。昔気質な話のようだが、実のところそれは方便で、「あんな坂、よう上らん」というのが本音だったと、これは長蔵が死んだときにタケが漏らした。その頃には、子がなかった叔父の家も途絶えていて、タケはその家の世話も欠かさなかったのだから、結局、坂を上らずに済んだのは、先に逝った長蔵だけだったということになる。しかし、その冬も変わらず刈ったカジ束を背負い、坂を上るタケは、「お父さんの判断は正しかったでね」と、白い息の下で笑うのだった。
「白黒写真で撮ったら、いつの時代かと思うほどの風景よね。大変なばっかりで、大したお金にもなりやせんし」
遅い昼を取りながら、真砂子は隣の祐介に話しかけるでもなく、独り言ちた。台風避けの長い軒は、冬の太陽こそ遮ることなく、親子の並ぶ縁側を温めている。真砂子が息を吐き出すと、ふうん、うまそうでもなく幕の内弁当をかき込みながら祐介が応えた。
「でも、ばあちゃんの写真なんかないろう。写真嫌いなんやから。魂が抜かれるゆうて、結婚式の写真も撮らざったに」
「それも、いつ時代の人間やっちゅうことやねえ」
真砂子は小さく笑った。町の狭いアパートに移した仏壇に飾ったタケの遺影は、長蔵の葬式のときのものだった。
「じいちゃんが逝んだけぇ、もういつ魂抜いてくれたちかまんゆうて撮ったがよねえ。けんど、立ち直ったら気持ちが変わって、やっぱしそんなもん撮らんといてくれゆうて。だから、撮らんずついたら、とうとう逝んでしもた」
「どうせ、遺影で必要になるんじゃけ、こっそり撮っといたらよかったがよ」
饒舌な母を気遣うように、祐介が言った。
「何も残らんのは、寂しいろ」
「どうやろうねえ」
真砂子はタケの顔を思い浮かべようとした。しかし、薄青の空のせいか、浮かんだのはタケの姿ではなく、カジを蒸す蒸気の鮮烈なまでの白さだった。真砂子は笑うように息をついた。
「あったらあったで、寂しいもんかもしらんで。記憶の中にあるほうが、ほんとの姿のままかもしれん」
「そういうもんかね」
祐介は言うと立ち上がり、空になった弁当箱をゴミ袋に突っ込んだ。それから、ふと坂の下に視線をやり、真砂子を振り向いた。
「誰ぞ来ゆうで。車が止まっちゅう」
「知らん車やね」
真砂子も立ち上がった。杉の樹間を透かすように、そちらを見る。枯れ草の色を蹴散らすような、きついオレンジ色が眼を射た。
「鉄砲撃ちやろか。この先に用があるゆうんは、それくらいやろ」
「なら、落ちたかの。見てきちゃろう」
集落道は細く、崖から落ちまいとするあまり、逆側の側溝にタイヤを落とす車が少なくない。様子を窺っていると、木の向こうに白髪頭がよぎり、「こんにちは」、訛りのない男の声が聞こえた。「どうも」、応える祐介の声。「大丈夫ですか」。
「え?」
「いや、手伝いが必要やろかと思うて」
「あ、すみません。ここに停めたら迷惑でした?」
「大丈夫ですけど、————」
どうやら脱輪したわけではないらしい。真砂子は、声から意識を逸らし、片付けに戻ろうとした。と、そのとき、「ああ——」、男の声がやけに明るく響いた。
「あのおばあさんのお孫さんなんですか。じゃ、ちょうどよかった。おばあさん、お元気ですか? あ、いえ、僕、怪しいもんじゃないんです。実は僕、地方の小さい祭りが大好きで。ここも面白い祭りがあるって言うんで、来てみたんですよ。そしたら、もう、このあたりは棚田が美しいでしょう。日本にまだこんな場所が残ってたんだって、僕、びっくりしちゃって。感動しちゃって。それで、これは絶対、残さなきゃならない風景だろうって——ああ、僕、カメラも祭りと同じくらい好きなもんで、それでもうその年のうちにもう一回有給とって、ちょうど今頃なんだけど、撮りに来たんですよ。それで——そうだ、見てもらった方が早いですね。どうぞ、これ」
男の声が途切れ、元の静寂が山を包んだ。祐介の息を呑む音が聞こえたような気がしたが、さすがにそれは空耳だろうか。祐介の沈黙があまりに長かったのか、男は痺れを切らしたように言った。
「ね、これ、よく撮れてるでしょう。賞をとって、新聞に載ったんですよ。日日新聞。見たかなあと思ったけど、その様子じゃ見てなかったみたいですね。じゃあ、わざわざ持ってきて良かった。ほら、審査員のコメント……『忘れ去られた日本の原風景を運良くも捉えた』って。ひどいでしょ、僕の腕とは関係なく、題材が良かったみたいな、ねえ。まあ、でもそりゃそうだって話なんて、報告ついでにリベンジというか、また撮らせてもらおうかなぁ、なんて——」
「祖母は、去年に亡くなりました」
固い声が、男の明るい声を遮った。
「それは……御愁傷様です」
男は声音をがらりと変えた。
「えっと、去年か。じゃあもうこの写真の後というか……」
「直後ですね」
「え? それはすごい偶然というか……えっと、じゃあお線香でもあげさせてもらっても——」
「済みません。仏壇はここにないがです」
「そうですか。……じゃ、これだけでも」
消え入るような声の後、車のドアが閉まる音がし、続いてエンジン音が聞こえた。オレンジ色が後退と前進を繰り返し、別れの挨拶のように赤いテールランプを一瞬光らせ、遠ざかっていく。タケを撮った人間がいた——ぼうとしていると、風が動き、気がつくと目の前に封筒を差し出す祐介がいた。真砂子はゆっくりと目を落とした。
「……聞こえとった?」
「うん。聞いとった」
「嫌なら、わしが捨てとこか」
「…………」
——どんな写真やった?
真砂子は光にかき消されるほどの声でつぶやいた。自分で見いやと言うように、祐介が封筒を押しつけた。真新しい封筒からは、糊とインクの匂いが立ち上った。冷たくかさついた指で中を探り、引き抜くと、大きく引き伸ばされた写真が陽に反射し、真砂子の目を眩ませた。直後、真砂子はタケと再会した。丁寧に束ねたカジを背負い、家までの坂道を上がる母。それは真砂子の記憶より、少し、ほんの少し小さな背中だった。
「これ、後ろから撮っちゅうろう」
祐介の声は低かった。
「ばあちゃんの許可なしにやったんで」
そやね——相槌は、声にならなかった。真砂子の目からは涙が湧いて、それはいくら固く唇をかみしめ、止めようとしても無駄だった。母さん、母さん。声にならない声で真砂子は叫んだ。その真砂子から目を逸らし、祐介が鼻をすすった。その途端、ぽたりと写真に滴が落ちた。
午後も三時を過ぎ、太陽が山に隠れると、あたりの気温は一気に下がり、底冷えがする。深緑色に押し黙った杉は一層暗く、身じろぎもせずに立っている。坂道の下に停めた、借り物の軽トラックには、粗大ゴミとなったタンスやコシキ、ゴミ袋が山積みされ、それは落ちないようにロープで固定されていた。
「今日はこればぁで置こか。ゴミの持ち込みは夕方までやし」
納屋の戸を閉めた祐介が、少し疲れた顔で言った。真砂子は頷き、玄関の鍵をかけた。無口なまま、二人で坂を下り、軽トラに乗り込む。と、真砂子の手が、助手席のドアを開けたまま止まった。
「何しよん。はよ乗りや」
「うん」
しかし、真砂子は片手でドアを押さえたまま、荷台のゴミ袋をじっと見た。ゴミとなったあの木型が、半透明の袋から透けていた。
「祐介」
「何?」
「母さんさ——」
真砂子はゆっくりと口を開いた。
「母さん、ばあちゃんの仕事をやってみよか。ここへ住んで、田ぁやって、山菜取って、カジやって。ほいだら、押し寿司も作る暇があるろう。木型もコシキもほかすことないし、家もこれ以上片付けいでもええし、そう、町の家にはあんたが住んで、気が向いたら、ときどき見にきてくれたらええ。母さんがばあちゃんにしよったように、月に一回でも、二回でも。そりゃ初めっからうまくはできんかもしれんけど、あんたにやるくらいの米ならできようね。なんの、九十のばあちゃんがやりよったことを、わたしができんでどうする。わたしだってまだまだ——」
「母さん」
熱に浮かされたように言葉を継ぐ真砂子を、祐介の落ち着いた声が遮った。真砂子は祐介を見た。祐介も真っ直ぐ真砂子を見た。運転席の窓を背に影となった祐介は、それまでのどんな瞬間よりも大人びていた。その祐介の口元が小さく動いた。
「無理よ」
「……でも」
「無理ぞね」
祐介の言葉に、真砂子は糸が切れたように口を噤んだ。それからしずしずと助手席に乗り込んだ。乾いた音で、ドアが閉まった。冷え切ったエンジンは何度か軋むような音を立てた後、ようやく発進の兆しを見せる。祐介が重そうにハンドルを切り、ゆっくりアクセルを踏み込んでいく。一年分の草を蓄えた田んぼと、今年も刈りどきを迎えたカジが、その後ろ姿を見送った。