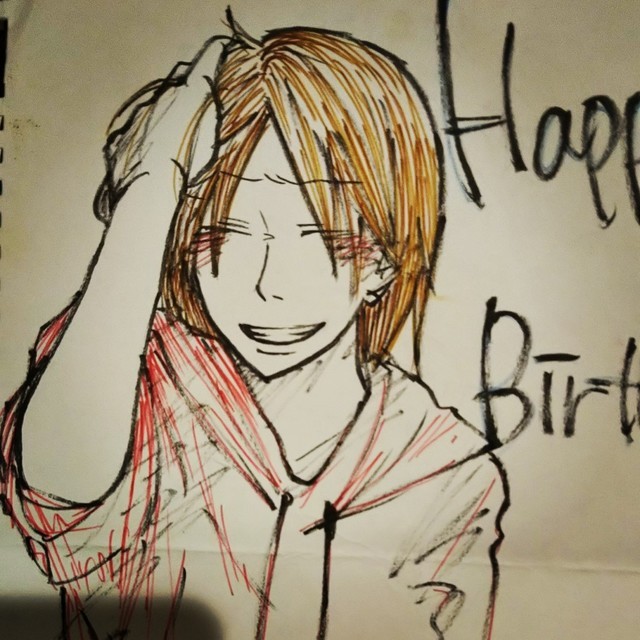15、2月10日(水)
文字数 3,388文字
コンコン、ガラッ。
「失礼しまーす」
「これまたお久しぶりですね。もう来ないものかと思っていました」
ドッ。
「・・・・・・。・・・・・・まさかぁ。寂しかったですか?」
「フッ。やる事がはかどって困る位です」
女生徒は組んだ足を揺らした。それと同時にその笑顔に心が凍てついたことを思い出す。思い出すが、あえて片肘をついて微笑んだ。あくまで自分は客人であり、立場上講師には対応する義務がある。講師は自ら肩をもみほぐすと、首を回した。
「・・・・・・で、本日はどのようなご用で?」
揺れる足。その動きがコンマ何秒レベルで変化する。あっちへ行ってそっちへ行って、蛇行運転を続けてきたやりとりは、今ようやく目的地に辿り着こうとしていた。
「先生あのね」
隔週水曜。これは志堂槙に定期的に訪れる戯れの記憶。
「偽物は本物になれると思いますか?」
「そうですね。あなたはどう思うんですか?」
「私は」
抜け落ちる愛想。表情に使っていた労力までも奪い去って、全てを脳に集中させる。
口元を覆った指先。その人差し指がとがった鼻先を一度だけタップする。
起動。それはスイッチ。
志堂槙は再生紙の答案用紙からペリペリと手を離した。
「私はなれないと思います。外見的なメッキは、はがれる。セフレは、昇格しない。始めから同じスタートラインに立っていない」
言いながら先生の言葉を待つ。早く止めて欲しくて待つ。違うと否定して欲しくて待つ。
けれど先生は片肘をついたまま動く気配を見せない。
「・・・・・・。・・・・・・で?」
「だから・・・・・・偽物は本物にはなれない」
「弾切れですか? これは随分とお早い」
ため息。嫌な空気が立ちこめる。息苦しさを覚える。
「・・・・・・。・・・・・・結構です。一つだけ破片をあげましょう。それでもうお帰り下さい」
前髪を掻き上げる。
造作は違う。何もかも異なる。なのに一瞬、かすめた記憶。
はっきりとした二重。丸いメガネの奥で強い光を放つ。それは「本来人に見せるものではない『一部』を分け与える」ことに対する、ある種の牽制だった。
〈他言無用〉
共有を嫌う。その口調は確かな強制力を持つ。
女生徒は一度だけうなずくと、続く言葉を待った。
「・・・・・・偽物が偽物として成立するのは、その間に共通項が存在するから。例えば言動が似ているとか、後ろ姿が似ているとか、雰囲気が似ているとか。この大学に関して言えば、そうですね・・・・・・」
その手が開く。あなた、と差されたようだった。
「教員含めて関西弁が主流の中、イントネーションが似ているとか、音の感じだけで間違うような事がないとは言い切れません。寝ぼけている時なんかは特に。夢の延長線上にばったり出くわしてしまう事だってあるかもしれない」
女生徒の動きが完全に止まる。思った通りだ。この男、知ってる。
ふわりとかすめた甘い香り。コーヒーの香りに確かに混じる。はっきりと第三者の存在を感じる。
「でもそれはあくまで偽物。不足を補うための代替。本物を求めるあまりつくり出した幻想。だから、理性の統治する平常に戻れば、不要」
「『いない』ことが現実である以上、理性の統治する平常にきちんと戻れるかは分かりませんよね? それは理想であって、その通りに動けるとは限らない」
講師は笑った。響く声。それは女生徒の胸をざわめかせ、最大限に不安をあおった。
「なんっ・・・・・・」
おかしなことは言っていないはずだ。笑われることなど、一言も。
至って真面目だった。折れ目がつくほど誠実に。
「動けますよ。僕は一切疑わない」
まだ肩を震わせながら、くつくつと音を立てる。透の出す声が震えた。
「そんなの・・・・・・分からない・・・・・・!」
「いつまでそんな事言っているんですか? いつまでそこにいるおつもりですか?」
ひやりとする。気温のせいではない。凍てつく。心が、思い出す。
この男は既に誰かとともに在る。その非情な目に透ける嘲り。
同じ場所にいたはずが、いつの間にか先を行かれる。次の瞬間、女生徒を襲ったのは、突風のような不安。
透はソファから腰を上げると、その傍らまで進んだ。
「・・・・・・。・・・・・・先生は寂しくないんですか?」
「ハテ。太古の昔から現代に至るまで、死ぬ時は皆
「もう、良くなっちゃったんですか?」
「必要とあらば望むでしょう。でもそれは今じゃない」
先生、という呼びかけが浮いた。
溢れたのは、想い。
「寂しい」
「・・・・・・。・・・・・・困りますね。あなたは僕の好みじゃあない」
言いながら背もたれに背中を預けて、肘をつく。下から見上げる視線は値踏み。
二十一歳、女子大生の市場価値。品定め。
損か、得か。
「・・・・・・。・・・・・・似たもの同士は、傷をなめ合うことで癒やされるとお思いですか?」
「同じ傷を負った者なら尚更」
「そうですか。あなたは感情を自分の中だけで処理することが出来ないようだ。どうしても表に出てしまう。それは多かれ少なかれ周りに影響する。良い影響ならまだしも、今のものは・・・・・・褒められたものじゃありませんね」
「埋まらない。大きな穴が空いたまま」
「よく分かりません。私とあなたが似た者同士なのかも、同じ傷を負っていると言えるのかも、これからしようとしていることが正しいのかも」
「どうせお互い偽物です」
「間違いない。しかし偽物同士が間違いを犯せば、正しい場所に戻って来られるなんて理論、聞いたことがありません」
「マイナスとマイナスを掛け合わせたらプラスになります」
「結局は実験が先か理論が先かの違いだけか。分からない以上、取り敢えずやってみた方が早そうですね」
二十一歳、女子大生。
成人。故に全て自己責任。
男は強要していない。むしろそれは、生徒たっての望みを叶えるための慈善活動と言い換えられた。
「・・・・・・隣り合う者同士が似たような色とは限りません。赤と橙の場合もあれば、赤と青の場合もある」
「承知の上です」
女生徒は講師の首に自らの腕を回した。その目の焦点は、合っていない。
「面影のあるもの全部、私のもの」
とてもじゃないが、それが正しいこととは言い難い。それでも。
成人。全ては自己責任。
「それは・・・・・・さぞ幸せでしょうね。守備範囲の広さは、絶対量を底上げする」
一方で、不純物を拾い上げてしまう可能性も高くなることは、黙っておく。
「・・・・・・。・・・・・・さすがに若いですね。綺麗な肌をしていらっしゃる」
目を見開く。女生徒の息が止まった。
〈『姫』〉
同時に強張る身体。
「あ」
あわてて引こうとするが、つかまれた腕がそれを許さない。
「ちょっと待って、先生」
外されたメガネが机の上でカタン、と音を立てた。
「お願い」
女生徒の頭によぎった声。それが引き金となって「理性の統治する平常」に引き戻す。それは冷静で正しい動き。でも。
「・・・・・・。・・・・・・手遅れです」
耳元でささやかれた声。その歯が女生徒の耳を噛んだ。
痛み。全身が、防衛本能が覚醒する。
冷静な頭は、冷静に現状を認識することによって、きちんと額面通りの傷を負う。それならせめて全て終わった後の方が良かったのかもしれない。後悔なら
意思と反する。強要されること自体、純粋な地獄だ。
「先生」
まだ戻れる。まだ間に合う。まだ取り返しがつく。そんな思いがことさら拍車をかけた。
すくんで、震える。
「・・・・・・忠告はしました。聞かなかったのはあなたです。近頃は何でもやり直しが利き過ぎる。環境のせいもありますが、甘やかされない方が良い」
そういう意味ではこれも教育です。そう言うと先生は首根っこを固定したまま、裾から手を差し入れた。
何の温度も伴わない。
マイナス掛けるマイナスはプラスなんかじゃない。
それは絶対零度。歯の根がかみ合わない。
こわいこわいこわいこわい。
「待って。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい」
腰が抜ける。膝をついて謝り続ける女生徒。その頭上に落ちたため息が傷口をなでた。
「・・・・・・興ざめです」
言いながら外すベルト。白衣の裾を払う。
「