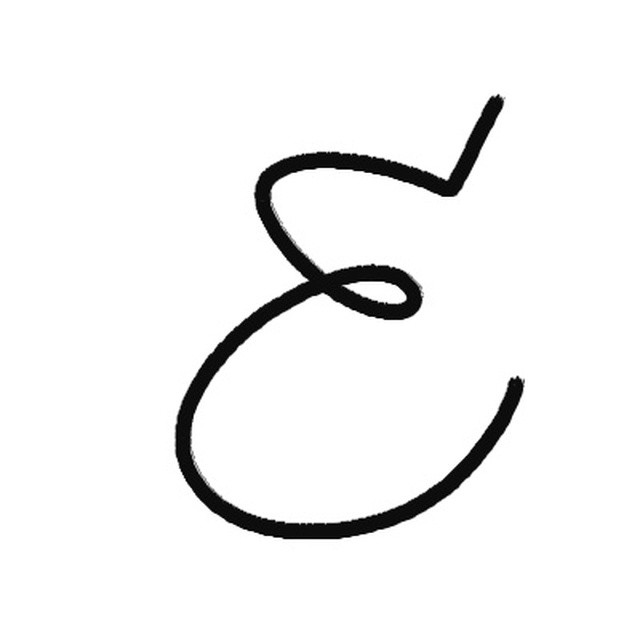第1話
文字数 3,332文字
「強盗と花束」
永見エルマ
ある朝、目が覚めてから僕は気がついた。
思ったよりもソファが狭い。
いつもの癖で朝早くに起きたが、いつもとは違ってすることがないからとのんびりコーヒーを入れてソファに座ろうと思った時だった。そのソファは一人掛けで、下には一五センチほどの足がついている。一人で座るには十分な大きさのはずだったが、その日その瞬間から、小さく見えてしまって仕方がなかった。もちろん、実際にソファのサイズが小さくなったわけでは無いし、寝ている間に入れ替えられたとか、何かしらの要因で目の錯覚が起きているとかいう荒唐無稽なトリックがあるわけではない。ソファは今まで通りのサイズで、今まで通りの見え方であることは間違いなかったのだが、心の目は小さくなっていると主張していたのだ。
実際に座ってみてもやはり小さい。こんなに肘が当たっていただろうか。こんなに足を広げづらかっただろうか。こんなにクッション面が狭かっただろうか。これじゃあまりに不便で、あまりに不全で、あまりに不能で仕方がない。
リビングを抜けて寝室に入ると、扉すぐ横のクローゼットを開く。中には突っ張りに掛けてある大量の洋服と胸下ほどの高さの衣装ケース、埃を被った大量の文庫本の山とタンスがあった。タンスの一番上の引き出しを開けると、そこから通帳を取り出す。
今の残高はと…。うむ、どうやら新しいソファを買うのに、お金が足りないわけでもないらしい。しかし、そうなると困った。どうも家具屋が遠い。うちから一番近くの家具屋まではどれくらいだったかな。忘れてしまったのか、そもそも知ってすらいないのかわからないけど、まあ僕の生活圏外であることにかわりはない。
三十分ほど策を考えて、そうして僕は思った。隣の家なら徒歩一分。経験なんてもちろんないけど、なんとかなると思った。キッチンに行くと、僕は包丁を持った。
人間ってのはどうにも満たされない生き物らしい。どうだろう。こうして紙の上にインクで文字を書いて、僕の全てを吐露してみようと試みて、結局僕には何にも訪れない。何かしらの未知が、ピカピカと光って僕の脳を刺激し、細胞の一つ一つを弾けさせてくれるかもと期待したのだが、結果は無だった。この世の神様がいないってのいうは背理法的に証明できるみたいだ。神様がこのよに存在すると仮定する。するとどうだろう。僕には、いや
ここまで書いていて思ったことがあるんだが、僕は思いのほか理性的のようだ。紙だか神だかに負けず劣らずの、薄っぺらい理性が僕にもまだ残っているみたいだ。こんなのがあったってどうにもならないし、なんならない方が良かった。どうせならこの紙と一緒に飛ばしてしまうというのはどうだろう。我ながらに良い案かもしれない。
デスクにある定規を使って、紙飛行機を作る。作るのは小さいころ以来だけど、思いの外、綺麗な紙飛行機になった。持ち手を握ると、窓から思い切り投げ出してやった。
ゆっくりといつもの習慣が死に始めたある昼、目覚めていつものようにコーヒーを飲み、画面の真っ暗なテレビを鑑賞している時だった。
死にゆく貴女に花を上げたい。
理由なんて思い浮かばなかったけど、強いて理由を挙げるなら上げたいと思ったからであろうか。今度も同じように寝室のクローゼットを開け、タンスの中の通帳を見る。通帳の一番下には一桁のゼロだけが書いてあり、それ以外のまっさらことには感心さえ覚える。
またしても困ったな。これじゃお金が足りないどころか、花束なんてそもそも予算圏外だ。今度はどうしたものか。どうせなら、美しい花を送って上げたいものだ。しかし、お金がどうにも…。
またも策を考える。不思議なことでもないのかもしれないが、今度は四、五分で思いついた。偶然にも今日は日曜日で、偶然にも隣は花屋で、偶然にもその花屋は今日が定休日だ。
盗めば良いと思った。今度もキッチンに包丁を取りに行く。その足で外へでて、僕は信号を待った。
これを読んでいるどこにいるとも知らぬあんたへ。願わくはこの手紙を読んで、自分が普通ではないということに気づき、そして自省と自制を自分の脳が蕩けるまで刻んでほしい。それだけが唯一まともになれる方法だからだ。気づいていないようだから、はっきりと言おう。実はあんたもまともじゃないのさ。そう、素知らぬ顔をしたあんただよ。何があんたらから真実を遠ざける?金か?金があって生活が成り立っているから、盲目になるのか?そんなものは全て忘れてしまえ。金にならない常識なんてものは全て忘れてしまえ。
どうせ何にもわかりはしない。他人の、僕の痛みなんてわかりなんてしないだろうよ。いいさ、精々笑って過ごしていれば良い。百年経てば誰でも土の中の骨なんだから。いずれはみんなそうなるんだ。だから…だから、今日ぐらいは
今までの習慣が完全に息をしなくなり、代わりに堕落が芽吹き始めたある夜、僕はわかった。
これから先には夢がない。
僕のこの生活の先に待ち受けているのは、底なしの虚無と絶望だけだ。こんなはずではなかった。どうも貴女がいないこの部屋は僕には広くて勿体無い。
四年前、大学四年生の僕らが出会い、卒業して共にこの部屋に暮らすまでは全てが順調だった。窓際の椅子で読書をする貴女をいつまでも見ていたかった。陽光があたり、風が入り込む。そうして長くて綺麗な黒髪を靡かせて、いつもみたいに右手で左耳に髪をかける君を、隣でいつまでも見ていたかった。クローゼットの中には大量の忘れ物があるんだよ。それに机の上の青い栞も。僕じゃ処理できないからさ、戻ってきてくれないか。僕の今までは貴女でできていて、貴女が居なくなるなんて考えてこともなかったんだ。
花屋の主人は優しかった。というのも、彼は僕が盗んだことを咎めたりしなかったのだ。代わりに彼が僕にくれたのは悲哀に満ちた目線だった。
僕は思う。強盗と花束に何の違いがあるのだろうか。
言葉は全能だ。言葉で言い表せないものなんてない。第一、言葉で言い合わせないものは「言葉で言い表せないもの」で言い表せているではないか。言葉を重ねれば、ニュアンスは遠くなれど、伝達することができる。重ねれば重ねるほど、より純一無雑なものとなって伝達できるのだ。言い表せないなんてのは言い表そうとしない怠け者の言葉だ。しかし、全能が故の欠点もある。それは目に見えないものをも表現できてしまうことだ。早い話、神様なんて作り物ってことさ。でなけりゃ僕が、
ああ。わかっている。本当は、心の奥底のどこかではわかっている。
きっと僕らは間違えて、間違えて、間違えている。
誰でも良い。誰でも良いから、そんな
朝日がその顔を出し、空を二藍色に染まり始めたのを窓から眺めていたある朝、僕は気がついた。
思ったよりも世界は広い。
これまで人生で僕は、決して怠け者というわけでなかったと思う。最低限なのかもしれないけれど、それでも人並みに努力してきたつもりだ。必死に「生きる」を努力したんだ。けれど、ついには何も実らなかった。驚くほどに、呆気ない僕の人生だ。
退職届を出したのが、三ヶ月半前。ある程度あった貯蓄は、あっという間に霧散し、無一文になったことは言うまでもない。こうなって思ったことは一つ。安心なんていうものが古今東西、津々浦々を探し回ったってどこにも存在しないということ。ああ、きっとこれもあんたらにはわからないだろう。
それからもう一つ。この世には終わった方が未だ増しなことだってあるってことも。
どうしてだろう、なぜだかソファが小さく見えた。
永見エルマ
ある朝、目が覚めてから僕は気がついた。
思ったよりもソファが狭い。
いつもの癖で朝早くに起きたが、いつもとは違ってすることがないからとのんびりコーヒーを入れてソファに座ろうと思った時だった。そのソファは一人掛けで、下には一五センチほどの足がついている。一人で座るには十分な大きさのはずだったが、その日その瞬間から、小さく見えてしまって仕方がなかった。もちろん、実際にソファのサイズが小さくなったわけでは無いし、寝ている間に入れ替えられたとか、何かしらの要因で目の錯覚が起きているとかいう荒唐無稽なトリックがあるわけではない。ソファは今まで通りのサイズで、今まで通りの見え方であることは間違いなかったのだが、心の目は小さくなっていると主張していたのだ。
実際に座ってみてもやはり小さい。こんなに肘が当たっていただろうか。こんなに足を広げづらかっただろうか。こんなにクッション面が狭かっただろうか。これじゃあまりに不便で、あまりに不全で、あまりに不能で仕方がない。
リビングを抜けて寝室に入ると、扉すぐ横のクローゼットを開く。中には突っ張りに掛けてある大量の洋服と胸下ほどの高さの衣装ケース、埃を被った大量の文庫本の山とタンスがあった。タンスの一番上の引き出しを開けると、そこから通帳を取り出す。
今の残高はと…。うむ、どうやら新しいソファを買うのに、お金が足りないわけでもないらしい。しかし、そうなると困った。どうも家具屋が遠い。うちから一番近くの家具屋まではどれくらいだったかな。忘れてしまったのか、そもそも知ってすらいないのかわからないけど、まあ僕の生活圏外であることにかわりはない。
三十分ほど策を考えて、そうして僕は思った。隣の家なら徒歩一分。経験なんてもちろんないけど、なんとかなると思った。キッチンに行くと、僕は包丁を持った。
人間ってのはどうにも満たされない生き物らしい。どうだろう。こうして紙の上にインクで文字を書いて、僕の全てを吐露してみようと試みて、結局僕には何にも訪れない。何かしらの未知が、ピカピカと光って僕の脳を刺激し、細胞の一つ一つを弾けさせてくれるかもと期待したのだが、結果は無だった。この世の神様がいないってのいうは背理法的に証明できるみたいだ。神様がこのよに存在すると仮定する。するとどうだろう。僕には、いや
僕ら
には祝福の一抹も与えてくださらなかったじゃないか。むしろ、優しさどころか試練ばっかりのようにも思える。少しくらいはくれてもよかったんじゃないだろうか?神のお恵みってやつを。紙の上で神の不在を証明してしまうなんて、皮肉だね。紙も神も薄っぺらってことなのかな。ここまで書いていて思ったことがあるんだが、僕は思いのほか理性的のようだ。紙だか神だかに負けず劣らずの、薄っぺらい理性が僕にもまだ残っているみたいだ。こんなのがあったってどうにもならないし、なんならない方が良かった。どうせならこの紙と一緒に飛ばしてしまうというのはどうだろう。我ながらに良い案かもしれない。
デスクにある定規を使って、紙飛行機を作る。作るのは小さいころ以来だけど、思いの外、綺麗な紙飛行機になった。持ち手を握ると、窓から思い切り投げ出してやった。
ゆっくりといつもの習慣が死に始めたある昼、目覚めていつものようにコーヒーを飲み、画面の真っ暗なテレビを鑑賞している時だった。
死にゆく貴女に花を上げたい。
理由なんて思い浮かばなかったけど、強いて理由を挙げるなら上げたいと思ったからであろうか。今度も同じように寝室のクローゼットを開け、タンスの中の通帳を見る。通帳の一番下には一桁のゼロだけが書いてあり、それ以外のまっさらことには感心さえ覚える。
またしても困ったな。これじゃお金が足りないどころか、花束なんてそもそも予算圏外だ。今度はどうしたものか。どうせなら、美しい花を送って上げたいものだ。しかし、お金がどうにも…。
またも策を考える。不思議なことでもないのかもしれないが、今度は四、五分で思いついた。偶然にも今日は日曜日で、偶然にも隣は花屋で、偶然にもその花屋は今日が定休日だ。
盗めば良いと思った。今度もキッチンに包丁を取りに行く。その足で外へでて、僕は信号を待った。
これを読んでいるどこにいるとも知らぬあんたへ。願わくはこの手紙を読んで、自分が普通ではないということに気づき、そして自省と自制を自分の脳が蕩けるまで刻んでほしい。それだけが唯一まともになれる方法だからだ。気づいていないようだから、はっきりと言おう。実はあんたもまともじゃないのさ。そう、素知らぬ顔をしたあんただよ。何があんたらから真実を遠ざける?金か?金があって生活が成り立っているから、盲目になるのか?そんなものは全て忘れてしまえ。金にならない常識なんてものは全て忘れてしまえ。
どうせ何にもわかりはしない。他人の、僕の痛みなんてわかりなんてしないだろうよ。いいさ、精々笑って過ごしていれば良い。百年経てば誰でも土の中の骨なんだから。いずれはみんなそうなるんだ。だから…だから、今日ぐらいは
僕ら
も間違ってもいいじゃないか。今までの習慣が完全に息をしなくなり、代わりに堕落が芽吹き始めたある夜、僕はわかった。
これから先には夢がない。
僕のこの生活の先に待ち受けているのは、底なしの虚無と絶望だけだ。こんなはずではなかった。どうも貴女がいないこの部屋は僕には広くて勿体無い。
四年前、大学四年生の僕らが出会い、卒業して共にこの部屋に暮らすまでは全てが順調だった。窓際の椅子で読書をする貴女をいつまでも見ていたかった。陽光があたり、風が入り込む。そうして長くて綺麗な黒髪を靡かせて、いつもみたいに右手で左耳に髪をかける君を、隣でいつまでも見ていたかった。クローゼットの中には大量の忘れ物があるんだよ。それに机の上の青い栞も。僕じゃ処理できないからさ、戻ってきてくれないか。僕の今までは貴女でできていて、貴女が居なくなるなんて考えてこともなかったんだ。
花屋の主人は優しかった。というのも、彼は僕が盗んだことを咎めたりしなかったのだ。代わりに彼が僕にくれたのは悲哀に満ちた目線だった。
僕は思う。強盗と花束に何の違いがあるのだろうか。
言葉は全能だ。言葉で言い表せないものなんてない。第一、言葉で言い合わせないものは「言葉で言い表せないもの」で言い表せているではないか。言葉を重ねれば、ニュアンスは遠くなれど、伝達することができる。重ねれば重ねるほど、より純一無雑なものとなって伝達できるのだ。言い表せないなんてのは言い表そうとしない怠け者の言葉だ。しかし、全能が故の欠点もある。それは目に見えないものをも表現できてしまうことだ。早い話、神様なんて作り物ってことさ。でなけりゃ僕が、
僕ら
が、こんなに不幸なわけがないんだ。もう良い。罪だとか罰だとか、もう全てがどうでも良いんだ。ああ。わかっている。本当は、心の奥底のどこかではわかっている。
きっと僕らは間違えて、間違えて、間違えている。
誰でも良い。誰でも良いから、そんな
僕ら
を少しくらい裁いてくれたって良いじゃないか。願わくは破滅のあらんことを。朝日がその顔を出し、空を二藍色に染まり始めたのを窓から眺めていたある朝、僕は気がついた。
思ったよりも世界は広い。
これまで人生で僕は、決して怠け者というわけでなかったと思う。最低限なのかもしれないけれど、それでも人並みに努力してきたつもりだ。必死に「生きる」を努力したんだ。けれど、ついには何も実らなかった。驚くほどに、呆気ない僕の人生だ。
退職届を出したのが、三ヶ月半前。ある程度あった貯蓄は、あっという間に霧散し、無一文になったことは言うまでもない。こうなって思ったことは一つ。安心なんていうものが古今東西、津々浦々を探し回ったってどこにも存在しないということ。ああ、きっとこれもあんたらにはわからないだろう。
それからもう一つ。この世には終わった方が未だ増しなことだってあるってことも。
どうしてだろう、なぜだかソファが小さく見えた。