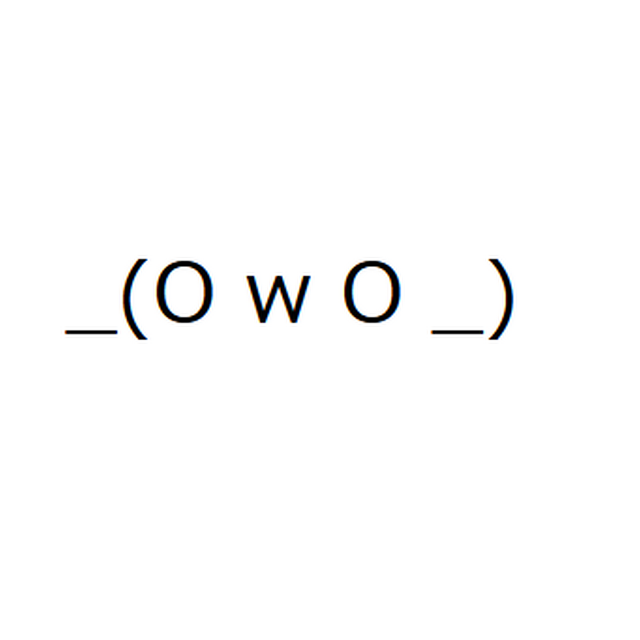♪ ♪ ♪
文字数 2,329文字
喫茶店の隅の窓側の席は、相川楓 のお気に入りの場所である。
店内に流れるレコードの音楽に混じって、通りを流れる喧騒 が耳元で聞こえるのが、たまらなく心地良いのだ。晴れの日でも雨の日でも、壁を背にして長椅子に腰掛け、コーヒー片手に文庫本を広げていれば、一時間でも二時間でも溶かすことができた。
この瞬間だけは、楓を邪魔するものは何もない。ケータイの電源は切ってあるし、背後の足音に気が散ることもない。客が不意にウェイターを呼んで、その声に驚くという心配もなかった。部屋全体を見渡せるこの特等席に居れば、全ては楓の目の前で起こり、完結し、整然としていた。物静かな雰囲気だけが楓を包み込み、安心して物語に浸ることができる。
窓を叩く音がしたのは、ちょうどそんな時だった。
音のする方を見ると、短い髪をライトブラウンに染めた青年が、こちらに笑顔を向けながら手を振っていた。
少しの間、楓はその男の顔を思い出せなかったが、目許にあるホクロと子どもっぽいエクボを見てピンときた。高校の時に付き合っていた、同級生の森屋篤史 である。
ジャケットの肩を少し濡らした篤史は、楓が自分と気付いてくれたのを認めると、そそくさと店の入口へと回り、小走りでかのじょの相席まで来た。今朝のニュースで、今日は一日中晴れと言っていたが、いつの間にか外は薄暗く、雨がパラついているらしい。
「久しぶりだね」
篤史は羽織っていたジャケットを脱いで背もたれに掛けると、近くまで来たウェイターにカフェオレをオーダーした。さっきは顔も覚えていなかったのに、篤史が甘党だということを、楓は既に知っていた。
「篤史こそ、どうして?」
楓は本を閉じ、カバンの横に置く。篤史は椅子に腰かけると、おしぼりで顔を拭いた。
「仕事の都合で来てるんだ。しばらくはこっちで過ごすつもり」
「そっかあ」
そこから言葉が出て来ず、
「なんか、会えてよかった」
と穏当に返した。髪染めてるから、一瞬誰だか分からなかったよ、と楓が笑うと、だよねー、と篤史も笑いながら前髪を触った。
そうだ、あの頃は、篤史は黒髪だったのだ。小さい頃から癖っ毛だった楓は、篤史のさらさらとした髪がとても羨ましかったのだ。今となっては、楓がストレートパーマをかけて落ち着いていて、篤史は毛先がくるっとしている。逆に、今の姿を見てよくわたしだと気付いたな、と楓はむしろ感心した。
「ねえ、聞いてもいい?」
と言ってみた。カフェオレを一口すする篤史は、
「何を?」
と首を傾 げる。
「彼女って、できた?」
篤史は、何だそんなことか、と言わんばかりの意気込みで、
「もちろん」
と言った。楓はそれを聞いてか愕然 としたが、篤史は
「いないよ」
と続けたことで、楓はほっ胸を撫でおろした。昔の恋人の恋愛事情なんて、別に気にしなくてもいいのだが、何となく気になったのだ。逆に、楓の方は彼氏いるの? と篤史は問いかけるが、今は仕事の方が忙しいから、と楓は曖昧に返した。
三十路はすぐそこだが、引っ込み思案で臆病な性格が災いして、都会に越してきてからも一向に出会いがない。ぎこちなかった一人暮らしにもすっかり慣れてきて、今の生活にそれほど不自由がないことが、なおさら厄介なのだ。単調な仕事、単調な毎日だったが、続けようと思えば一生続けられそうな気がしている。楓は思い出したかのように、
「ねえ、あたしたち、何で別れちゃったんだっけ」
と尋ねてみた。
「覚えてないの?」
「うん」
いかにも理由がありそうな口ぶりだったが、
「俺も分かんね」
という返事に、楓は肩透かしを食らって、
「何よそれ」
と笑った。
「卒業式までは覚えてる。証書貰ってから一緒に帰って、咲きはじめの桜の下でキスして、それっきり」
「ちょ、そんなこと言葉に出さないで。恥ずかしい」
楓は急に顔が熱くなる。勢いで言ってしまった篤史も、そんな楓を見て堪 らず目を逸 らした。
「でもさ、そっから先がなにもないんだよ。大学がお互い別々だったし、それが原因かも」
「そこで自然消滅ってことか」
言葉に詰まった二人は、飲み物に口をつけた。
当時はそれなりに熱っぽかった気がするが、今となっては、まるで何もなかったかのように、ピンぼけでひどく漠然としている。一緒にデパートに買い物に行ったり、遊園地に遊びに行ったこともあったはずだ。しかし、そこで何を買ったか、どんな乗り物に乗ったかと聞かれたら、これまた不明である。
記憶力にはそこそこ自信があったのだが、元カレと過ごした思い出というものが、これまた綺麗さっぱり抜け落ちていて、楓はまた肩を落とした。少なくとも、喧嘩別れでなかったことは、確かだったからだ。仕事であった嫌なことは直ぐにでも思い出せるのに、大切な思い出ばかりが光届かぬ海底に沈んでいた。
実現するかはともかく、二人はまた近いうちに会う約束をして、そのまま店を後にした。篤史の方は、駅を跨 いだ先にあるホテルに泊まるらしく、楓の帰り道とは反対の方向だった。手を振って別れて、二、三歩あるいたところで、楓はふと空を見上げた。
立ち込めていた雲が途切れ途切れになっていて、さっきの雨はすっかり上がっている。傘を持っていなかったから、雨に降られないのはうれしいはずなのだが、このときばかりは、少し濡れて帰ってもいいかな、と思った。それが何故なのかは、結局のところ分からなかった。
しおりを挟まずに本を閉じたことに、家に着いてから気付いた。しかも、その本はさっきの喫茶店に置き忘れている始末。楓は、自分の体の中で、今まで噛み合っていた歯車が、ここぞとばかりに狂い始めて、好き勝手に動いているような気がした。ほんの少し寂しくなったが、何だか面白かった。
店内に流れるレコードの音楽に混じって、通りを流れる
この瞬間だけは、楓を邪魔するものは何もない。ケータイの電源は切ってあるし、背後の足音に気が散ることもない。客が不意にウェイターを呼んで、その声に驚くという心配もなかった。部屋全体を見渡せるこの特等席に居れば、全ては楓の目の前で起こり、完結し、整然としていた。物静かな雰囲気だけが楓を包み込み、安心して物語に浸ることができる。
窓を叩く音がしたのは、ちょうどそんな時だった。
音のする方を見ると、短い髪をライトブラウンに染めた青年が、こちらに笑顔を向けながら手を振っていた。
少しの間、楓はその男の顔を思い出せなかったが、目許にあるホクロと子どもっぽいエクボを見てピンときた。高校の時に付き合っていた、同級生の森屋
ジャケットの肩を少し濡らした篤史は、楓が自分と気付いてくれたのを認めると、そそくさと店の入口へと回り、小走りでかのじょの相席まで来た。今朝のニュースで、今日は一日中晴れと言っていたが、いつの間にか外は薄暗く、雨がパラついているらしい。
「久しぶりだね」
篤史は羽織っていたジャケットを脱いで背もたれに掛けると、近くまで来たウェイターにカフェオレをオーダーした。さっきは顔も覚えていなかったのに、篤史が甘党だということを、楓は既に知っていた。
「篤史こそ、どうして?」
楓は本を閉じ、カバンの横に置く。篤史は椅子に腰かけると、おしぼりで顔を拭いた。
「仕事の都合で来てるんだ。しばらくはこっちで過ごすつもり」
「そっかあ」
そこから言葉が出て来ず、
「なんか、会えてよかった」
と穏当に返した。髪染めてるから、一瞬誰だか分からなかったよ、と楓が笑うと、だよねー、と篤史も笑いながら前髪を触った。
そうだ、あの頃は、篤史は黒髪だったのだ。小さい頃から癖っ毛だった楓は、篤史のさらさらとした髪がとても羨ましかったのだ。今となっては、楓がストレートパーマをかけて落ち着いていて、篤史は毛先がくるっとしている。逆に、今の姿を見てよくわたしだと気付いたな、と楓はむしろ感心した。
「ねえ、聞いてもいい?」
と言ってみた。カフェオレを一口すする篤史は、
「何を?」
と首を
「彼女って、できた?」
篤史は、何だそんなことか、と言わんばかりの意気込みで、
「もちろん」
と言った。楓はそれを聞いてか
「いないよ」
と続けたことで、楓はほっ胸を撫でおろした。昔の恋人の恋愛事情なんて、別に気にしなくてもいいのだが、何となく気になったのだ。逆に、楓の方は彼氏いるの? と篤史は問いかけるが、今は仕事の方が忙しいから、と楓は曖昧に返した。
三十路はすぐそこだが、引っ込み思案で臆病な性格が災いして、都会に越してきてからも一向に出会いがない。ぎこちなかった一人暮らしにもすっかり慣れてきて、今の生活にそれほど不自由がないことが、なおさら厄介なのだ。単調な仕事、単調な毎日だったが、続けようと思えば一生続けられそうな気がしている。楓は思い出したかのように、
「ねえ、あたしたち、何で別れちゃったんだっけ」
と尋ねてみた。
「覚えてないの?」
「うん」
いかにも理由がありそうな口ぶりだったが、
「俺も分かんね」
という返事に、楓は肩透かしを食らって、
「何よそれ」
と笑った。
「卒業式までは覚えてる。証書貰ってから一緒に帰って、咲きはじめの桜の下でキスして、それっきり」
「ちょ、そんなこと言葉に出さないで。恥ずかしい」
楓は急に顔が熱くなる。勢いで言ってしまった篤史も、そんな楓を見て
「でもさ、そっから先がなにもないんだよ。大学がお互い別々だったし、それが原因かも」
「そこで自然消滅ってことか」
言葉に詰まった二人は、飲み物に口をつけた。
当時はそれなりに熱っぽかった気がするが、今となっては、まるで何もなかったかのように、ピンぼけでひどく漠然としている。一緒にデパートに買い物に行ったり、遊園地に遊びに行ったこともあったはずだ。しかし、そこで何を買ったか、どんな乗り物に乗ったかと聞かれたら、これまた不明である。
記憶力にはそこそこ自信があったのだが、元カレと過ごした思い出というものが、これまた綺麗さっぱり抜け落ちていて、楓はまた肩を落とした。少なくとも、喧嘩別れでなかったことは、確かだったからだ。仕事であった嫌なことは直ぐにでも思い出せるのに、大切な思い出ばかりが光届かぬ海底に沈んでいた。
実現するかはともかく、二人はまた近いうちに会う約束をして、そのまま店を後にした。篤史の方は、駅を
立ち込めていた雲が途切れ途切れになっていて、さっきの雨はすっかり上がっている。傘を持っていなかったから、雨に降られないのはうれしいはずなのだが、このときばかりは、少し濡れて帰ってもいいかな、と思った。それが何故なのかは、結局のところ分からなかった。
しおりを挟まずに本を閉じたことに、家に着いてから気付いた。しかも、その本はさっきの喫茶店に置き忘れている始末。楓は、自分の体の中で、今まで噛み合っていた歯車が、ここぞとばかりに狂い始めて、好き勝手に動いているような気がした。ほんの少し寂しくなったが、何だか面白かった。