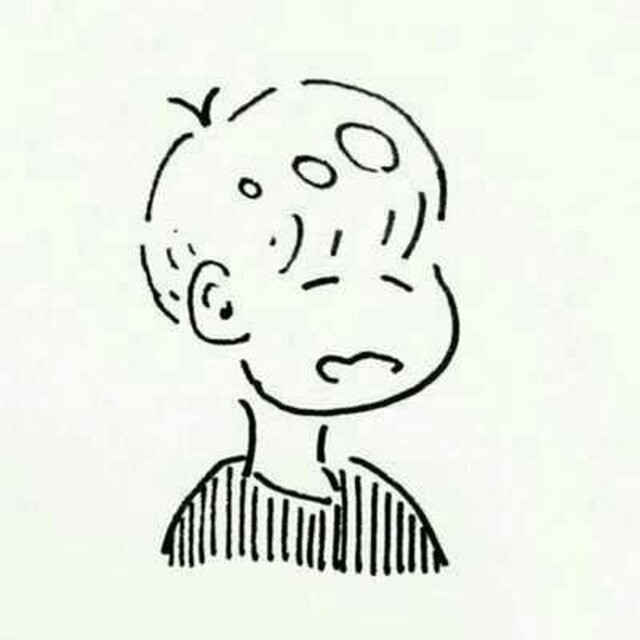第5話 父親
文字数 6,706文字
絵美は肩で息をしながら山道を歩いた。
山の地面はぬかるみ、歩く度に足の裏に土がこびりついて重くなった。木々の影が濃く、梢の間から覗く雨雲はひどく陰鬱な気配を持っていた。
絵美の傍らには、彼女と同じように苦しそうに歩く父がいた。もう意識が回復して、今はしっかりと自身の足で立って歩いていた。
父は一人で歩けるようになっても、逃げるそぶりは見せなかった。黙々と絵美の後ろをついてくる。逃げることなど考えてもいないのか。それともその必要はないと油断しているのか。
だが、その方が絵美にとって都合がいい。
――ただ、父と二人で話をしたかった。
「……もう、だいぶ離れてしまったな」
父は後ろを振り返って言った。
「…………」
絵美はそれには返事をせずに黙ったまま立ち止まった。父も共に立ち止まる。
絵美は振り返って、父を正面から見据えた。山の斜面で、絵美は父を見下ろすような位置に立っていた。額に血を流している父は、蒼白な顔を絵美に向けた。
――そういえば、父とこうやってまっすぐ顔を合わせるのはいつぶりだろうか。
「……聞きたいことがある」
絵美がそう切り出すと、父は「そうか」と小さく笑った。
「そうでもなければ、こんなところには来ないな」
父はそう言って周囲を見渡した。
ここは火葬場から少し離れた小さな山の中腹辺りだ。雨に濡れた木々が二人を覆っていて暗い。湿気が充満していて汗が吹き出た。
「……ここは、みんなを連れてよくキャンプをした山だな」
父は懐かしいものを見るような目で周囲の木々を眺めた。
「……そんなこと、もう覚えてない」
絵美は顔を背けて言った。父は「そうか」と呟くだけだった。
「……絵美、蒼太を唆したのもお前か?」
まだ血が少し流れている頭を押さえて、父は聞いた。「嫌な言い方」と絵美は苦笑いを浮かべて頷いた。
「そうだよ。私が計画して、蒼太が実行した」
「……そんなことしても、母さんは帰って来ないぞ」
「そんなことわかってるよ。……私はただ、お父さんにお母さんを葬らせたくなかっただけ」
父は首を傾げた。
「私は、お母さんをあんたになんか弔わせない。お母さんを連れて出て行ってやるから」
絵美は父をまっすぐ睨みながら言った。
「それで蒼太と二人で、お母さんを守りながら生きていくの。お父さんの手は借りない。あんたなんかを父親とはもう二度と思わないから」
絵美は自分を鼓舞するように、拳を作って胸を叩いた。
「その方が、お父さんも嬉しいでしょう? もうお金のことなんて気にしなくていいんだもん。私と蒼太から解放されて、好きに一人で生きていけるんだから、いいでしょう? 好きでもないお母さんのことも気にしなくていいんだしさ」
心臓が大きく鳴った。息が苦しかった。
――大丈夫、私は蒼太と生きていける。二人だけで大人になるんだ。お父さんがいなくても、私たちはちゃんと生きていける。
この感情は父への反抗心だろうか。それとも未熟な若さ故の無謀な発想なのだろうか。
(そんなこと、どうでもいい)
ただ、この決意は本物だ、と絵美は父を睨みながら思った。
蒼太と何度も話し合った。二人で未成年が生きていくにはどうすればいいかたくさん調べて、計画して、そしてこの道に後悔しないかと何度もお互いに確かめ合った。
二人はお互いの心が同じであると確信して、誓い合った。二人だけで今後の未来を話すのは楽しかった。ワクワクして心躍った。必ず実現させると、お互いに決意した。
だから、絵美は最後の決別のために父をここまで連れてきた。これは、姉弟が独立するための最後の儀式なのだ。父と袂を別つ前に、彼の本心を知る。そのためなら、どれだけ怖くても、この震える足を奮い立たせて父に立ち向かえると思った。
そんな絵美をしばらくの間父は呆然を見ていた。やがて、喉を鳴らすようにクッと小さく笑う。
「……おかしなことをする」
父は口元を隠すように右手で覆った。絵美はそんな父の乾いた声を聞きながら唾を飲み込む。
「……おかしいのは、どっちさ」
絵美は父を睨みつけた。
「お父さんはどうしてお母さんが死んじゃったことを悲しめないの?」
言葉にすると、なぜか絵美の胸も苦しくなった。
「お母さんが死んでから、お父さんが泣いている姿を見たことない。いつもお金の心配ばかりして……『絵美たちの将来のためだ』なんて言うけど、そんなことのせいで泣けないの?」
母が死んでから、家で見る父はいつもワイシャツに袖を通した姿だった。机の上にパソコンとノートを広げて、いつも何か作業をしている。一度も、絵美たちの方を見ようとはしなかった。
「どうして、最初にお金なの? お母さんが死ぬ前は、お父さん、そんなんじゃなかったじゃない」
絵美は脳裏に蘇る父の姿と、今目の前にいる男の冷たい瞳の色の違いに震えた。
母が死ぬ十日前、友達の家に遊びに行こうとした休日のことだった。待ち合わせ時間に遅刻してしまいそうだった絵美を、父は呼び止めて車で送ってやると提案してくれた。絵美は喜んで助手席に座り、待ち合わせの場所に着くまでの間、ずっと学校での出来事や友人のこと、悩んでいることを父に話した。父は無愛想だから、それに笑ったりはあまりしてくれない。けれど、ちゃんと聞いて一緒に考えてくれる人だった。ちゃんと、絵美のことを想って耳を傾けてくれる人なんだと思っていた。
――なのに。
『俺は愛したことなんて、一度もない』
暗い病室の中、父の声が嫌に響いていたのを覚えている。あの時と同じ瞳が、絵美の目の前にあった。
「なんで、お母さんが死んだとわかった時にあんなこと言ったの? お母さんを愛してなかったなんて、嘘だよね?」
ザァ、と一際強い風が吹いた。
「なんであんな嘘をつくの? 本当に愛してなかったのなら、どうして今まで一緒に暮らしてきたの?」
絵美の言葉は詰問のように語調が強くなる。次第に彼女の中で渦巻く、今まで言語化出来なかった感情たちが喉に溢れてきた。
だが、父は黙っている。
「ねぇ答えて」
絵美は声を荒げて詰め寄った。
「本当にお母さんを愛してなかったのなら、お父さんは私たちのことも愛してなかったの? 蒼太は? ……私ちゃんと覚えてるよ、初めて蒼太が小学校に入学した時、いつも仏頂面のお父さんが、笑ってたこと。……それに、私たちのことを愛してなかったら、『お前たちの将来のため』なんて言葉、普通使わないよね」
そうだよね、と絵美は地団駄を踏む幼子のように父に縋り付いて聞いた。
「お父さんの、本音を教えて?」
ただ、父が母を愛していたという言葉が欲しかった。それだけあれば、絵美は父を許すことができる。
絵美は、父が長い悪夢を見ているのだと思った。
母が死んだ時に口走った言葉は、母が死んだことによる動揺が生んだ虚言だ。そうとしか思えない。あれから父は、母の死から目をそらすためにお金を見ているのだ。目を逸らす理由があれば、人は走り続けられる。父は哀しみから逃げるためにお金と、絵美たちの将来を言い訳に悪夢を見続けているのだ。
だからこそ、悪夢から父が救われてほしいと思った。
だからこそ、父にあの時の言葉を撤回して欲しかった。
取り乱していたとはいえ、父は言ってはならない言葉を口にした。だから許せなかった。あの日から絵美は、父の言葉を思い出すたびに息が苦しくなって辛かった。
(私たち姉弟を、あんたの悪夢に巻き込まないで)
絵美はただ、父の真意が聞きたかった。ただ、父のことを信じたかった。
どんなに嫌いになって、どんなに許せないことを言ったとしても、絵美にとって父親は彼一人なのだから――せめて信じたい。
父は黙って絵美を見つめている。彼の視線には、怒りや戸惑いといった感情は感じられなかった。ただ、聞いてくれている。そこに、車に乗せてくれた時、黙って絵美の言葉を聞いてくれた父の面影を感じた。
あの冷たい目は、きっと嘘だ。そうに違いない。
二人の間で物寂しげな雨音だけが響く。
どれほどの沈黙があっただろう。父はゆっくりと目を閉じて、そして小さく笑った。
「……俺は、馬鹿な人間なんだよ」
父はそう言って、目をうっすらと開いて絵美を見る。
「そしてお前も馬鹿だな」
変わらず、冷たい瞳はそこにあった。
「……え?」
「俺は最初からずっと言ってるじゃないか。『誰も愛したことがない』と」
絵美は体がざわりと鳥肌で波打つのを感じた。父は小さなため息を吐く。
「絵美は、俺の本心が聞きたいと言ったな。その答えは簡単だよ。――『責任』だ」
「……責任?」
絵美は、今頃のように雨に濡れた服がべったりと自身の体に張り付く感覚に震えた。
「そうだ。『責任』だ。……お前はまだ子どもだから、わからないかなぁ」
父はそう言って面倒臭そうに頭を掻いた。
「お前は『人を愛せよ』なんて、簡単に言うけど、絵美の言う『愛』ってつまり何だ?」
「何って」
それは、と言いかけて言葉に詰まらせる。
絵美のことを大事にしてくれること。
絵美のことを好きって言ってくれること。
絵美のことを優しくしてくれること。
……どれもが『愛』とは言えない気がした。これは、ただの絵美にとって都合のいい願望だ。今まで絵美の中で確かな形のあったものが、少しずつ崩れるのを感じた。
「確かに小説や映画、人の噂話……どこもかしこも『人を愛せよ』と騒がれるが、つまり何をしろって話なんだ? 絵美は具体的に俺にどうして欲しかったんだ?」
お母さんをちゃんと看取って欲しかった。
お母さんのために泣いて欲しかった。
(……そんな父の姿を、私は『見たかった』?)
絵美は視線をそらす。
「……でも、お父さんはお母さんと結婚したじゃん」
自分でも、この言葉は話題を逸らすためのものだとわかっている。わかっていながら、絵美は言い訳のように口にしてしまった。
「お父さんはお母さんのことが好きだったんでしょう?」
それに父は感情のない声で答えた。
「俺が母さんと結婚したのは、お前が生まれたからだ」
絵美は無意識にビクリと震えた。
「別に母さんのことが好きだったからじゃない。子どもが生まれるってことはな、同時にその子を大人になるまで育てるっていう『責任』って名前の兄弟も一緒に生まれてくることなんだよ。それを俺は母さんと共に背負わなければならなかった。だから、生きていくために結婚した。……そこに『愛』なんて不確かなものはない」
意味がわからない、と絵美は思った。父は何を言っているのだろうか。
「子どもを育てるってことはな、金がかかるってことでもあるんだよ」
父は首をコキリと鳴らした。
「ほんっとうに、金がかかる。だけどそりゃ当たり前のことなんだ。生きるってことは社会に属して、人間として生きることを証明し続けることだからな。お金は言ってみたら、そのための証明書だ」
眉を顰める絵美を見て、父は肩を竦めた。
「社会ってのは、人が『人間』という生き物らしく生きるための仕組みであり装置だ。そうだな……車みたいなもんか。道路が『人間』らしい生き方を視覚化したものだとすると、その進み方を教えてくれる標識には教育、福祉、仕事……そういう『人間』としての暮らし、営みが示されている。……で、ガソリンが『人間』として動くための食事だ。それなら、お金こそが『人間』であることを示す証明書だろう。車が運転できることを他人に証明する免許証のように、この社会の一員であることを示すのがお金だ」
淡々とした彼の説明は、まるで学校で授業する先生のようだと思った。
「お金がなければ、人は『人間』として生きていけない。社会に属していないってことだからな。……社会に属せないのは『ひとでなし』だよ。俺たち親は、お前たち子どもを『人間』らしく道路の上を走らせられるように育てなくっちゃいけない。ちゃんとした車に乗せて、ちゃんと必要な時にガソリンを給油できて、ちゃんと運転できるように成長させる。間違っても事故を起こしたりしないように、車から勝手に降りないように、育てないといけない。
それが子を得て、親になる責任だ」
父はそう言うと、虚ろな目を絵美に向けた。
「お前は、せっかく父さんと母さんがここまで育てたのに、それを全部無駄にする気か?」
まるで幽鬼のように父の肌は白かった。そんな彼が口にした脅すような言葉に、絵美は腹の底まで冷たくなるような錯覚を起こす。
「お前は、今ならまだ間に合う。ちゃんとした道に歩みを戻せ」
そう言って父は絵美の肩に手を置いた。雨で冷えた体に、その手は温かかった。
だが、絵美にはそのぬくもりも、今は恐ろしい炎のように感じた。
肩に乗せられた父の手を払いのけて、絵美は顔を上げる。
「結局、お金なんだ……? そんなこと、どうでもいいじゃない。私はお父さんの気持ちを知りたいの。……お母さんの死は、悲しくなかったの?」
払われた手がじんじんと痛むのか、しばらくの間、父は宙に所在なく浮かぶ自身の手を眺めていた。
「悲しくは……あった」
彼はそう言うと、まるで自分の気持ちがそこで確信したように頷く。
「だけど、それだけだ」
そう言って絵美に笑いかけた。
「ふざけるな!」
絵美は父の襟を掴み、体重を父に傾ける。土はぬかるみ、父は簡単に倒れた。
父を組み伏して、その上に跨った絵美は襟を掴んだまま揺さぶった。
「何が『責任』だ! じゃあ何? お父さんは私が生まれなかったらお母さんとは結婚しなかたんだ? その程度の『愛』だったんだ?」
「だから、俺は誰も愛したことなんかない」
心底鬱陶しそうに、自分の襟を掴む絵美の手を睨んだ。
「……お前は自分で『愛』という言葉を叫びながら、それが何を意味しているのかわかってないんだ。だから教えてやる。――それはエゴだよ」
エゴ。
「絵美は、俺が気に入らないだけだ。それを全部『愛』なんて不明瞭な言葉にして俺に押し付けているんだ」
絵美は父の首を掴む手に力が入るのを感じた。
「……じゃあ、本当に私たちのことを、愛してくれたことはないの?」
あぁ、と父は頷く。
「俺はお前達の『父親』であろうとしたが、お前達を『愛そう』と思ったことはない」
父の虚ろな表情が絵美の心に鋭い凶器を刺し穿つ。絵美は自分の顔がくしゃくしゃに歪むのを感じた。
(違う)
「言っただろう。『責任』だと。子を育てるのは『父親』だ。それを果たすのは『父親』である俺だ」
父はそっと絵美の手を掴み、自分の襟元から絵美の手を放させた。
「そこに『子を愛せ』という強制はない」
(……違う、違う、ちがう)
絵美はうっすらと自分の瞳に涙が溜まるのを感じる。
――ずっと泣けなかったのに。
「どうして、そんなこと言うの」
声を出すと、余計に涙が溢れてきた。もう止めることが出来なかった。
「お父さんはちゃんと私たちのことを愛していたよ。でも、その気持ちが『愛』だとちゃんと理解できてないから、『責任』とか『義務』だとか、そんな適当な……自分にとってわかりやすい言葉で代用しているだけ。ちゃんと、愛してたよ。……どうしてこんな簡単なことがわからないの」
真下にある父の顔の頬に、自分の涙がポタポタと落ちるのを絵美は見た。
「『愛』がどんな形でもいいじゃない……私たちのことをちゃんと見てくれたら、それでいいじゃない」
未だに絵美は、ちゃんと『愛』がなんたるかを言葉にして説明することができなかった。
――だけど、絶対に……私は父のことを愛していた。
なのに。
「違う。『責任』は果たさなければならない『義務』だ。そこに愛だとか何だとか言うのはフィクションだ」
絵美はもう視界が涙で溢れてぼやけている。父の顔が歪んで見えない。
「俺はお前を愛したことはない」
絵美は首を振る。なんて不器用な人なんだろうと思った。
「もう、馬鹿なこと言わないで……」
父は顔を顰める。
「馬鹿を言っているのはお前だろう」
絵美はそっと目を閉じた。
――悟った。父と生きるのはやはり無理なんだ、と。
絵美は父のことが嫌いだが、愛している。でも、こんな父親と共に生きていけるとは思えなかった。
(どうして、お母さんが死ぬまでは一緒に歩んでいたはずの道が、こんな短い時間で違えてしまったのだろう)
この十七年間、どうしてこの父の歪みに気づいてやれなかったのだろうか。絵美は後悔ばかりが胸に募った。
(せめて、いつか……)
絵美は願う。父がいつか、だれかを愛することができる日を。
そして、愛されていたことを理解する日を。
絵美は強く拳を握り――そしてそれを振り上げた。
山の地面はぬかるみ、歩く度に足の裏に土がこびりついて重くなった。木々の影が濃く、梢の間から覗く雨雲はひどく陰鬱な気配を持っていた。
絵美の傍らには、彼女と同じように苦しそうに歩く父がいた。もう意識が回復して、今はしっかりと自身の足で立って歩いていた。
父は一人で歩けるようになっても、逃げるそぶりは見せなかった。黙々と絵美の後ろをついてくる。逃げることなど考えてもいないのか。それともその必要はないと油断しているのか。
だが、その方が絵美にとって都合がいい。
――ただ、父と二人で話をしたかった。
「……もう、だいぶ離れてしまったな」
父は後ろを振り返って言った。
「…………」
絵美はそれには返事をせずに黙ったまま立ち止まった。父も共に立ち止まる。
絵美は振り返って、父を正面から見据えた。山の斜面で、絵美は父を見下ろすような位置に立っていた。額に血を流している父は、蒼白な顔を絵美に向けた。
――そういえば、父とこうやってまっすぐ顔を合わせるのはいつぶりだろうか。
「……聞きたいことがある」
絵美がそう切り出すと、父は「そうか」と小さく笑った。
「そうでもなければ、こんなところには来ないな」
父はそう言って周囲を見渡した。
ここは火葬場から少し離れた小さな山の中腹辺りだ。雨に濡れた木々が二人を覆っていて暗い。湿気が充満していて汗が吹き出た。
「……ここは、みんなを連れてよくキャンプをした山だな」
父は懐かしいものを見るような目で周囲の木々を眺めた。
「……そんなこと、もう覚えてない」
絵美は顔を背けて言った。父は「そうか」と呟くだけだった。
「……絵美、蒼太を唆したのもお前か?」
まだ血が少し流れている頭を押さえて、父は聞いた。「嫌な言い方」と絵美は苦笑いを浮かべて頷いた。
「そうだよ。私が計画して、蒼太が実行した」
「……そんなことしても、母さんは帰って来ないぞ」
「そんなことわかってるよ。……私はただ、お父さんにお母さんを葬らせたくなかっただけ」
父は首を傾げた。
「私は、お母さんをあんたになんか弔わせない。お母さんを連れて出て行ってやるから」
絵美は父をまっすぐ睨みながら言った。
「それで蒼太と二人で、お母さんを守りながら生きていくの。お父さんの手は借りない。あんたなんかを父親とはもう二度と思わないから」
絵美は自分を鼓舞するように、拳を作って胸を叩いた。
「その方が、お父さんも嬉しいでしょう? もうお金のことなんて気にしなくていいんだもん。私と蒼太から解放されて、好きに一人で生きていけるんだから、いいでしょう? 好きでもないお母さんのことも気にしなくていいんだしさ」
心臓が大きく鳴った。息が苦しかった。
――大丈夫、私は蒼太と生きていける。二人だけで大人になるんだ。お父さんがいなくても、私たちはちゃんと生きていける。
この感情は父への反抗心だろうか。それとも未熟な若さ故の無謀な発想なのだろうか。
(そんなこと、どうでもいい)
ただ、この決意は本物だ、と絵美は父を睨みながら思った。
蒼太と何度も話し合った。二人で未成年が生きていくにはどうすればいいかたくさん調べて、計画して、そしてこの道に後悔しないかと何度もお互いに確かめ合った。
二人はお互いの心が同じであると確信して、誓い合った。二人だけで今後の未来を話すのは楽しかった。ワクワクして心躍った。必ず実現させると、お互いに決意した。
だから、絵美は最後の決別のために父をここまで連れてきた。これは、姉弟が独立するための最後の儀式なのだ。父と袂を別つ前に、彼の本心を知る。そのためなら、どれだけ怖くても、この震える足を奮い立たせて父に立ち向かえると思った。
そんな絵美をしばらくの間父は呆然を見ていた。やがて、喉を鳴らすようにクッと小さく笑う。
「……おかしなことをする」
父は口元を隠すように右手で覆った。絵美はそんな父の乾いた声を聞きながら唾を飲み込む。
「……おかしいのは、どっちさ」
絵美は父を睨みつけた。
「お父さんはどうしてお母さんが死んじゃったことを悲しめないの?」
言葉にすると、なぜか絵美の胸も苦しくなった。
「お母さんが死んでから、お父さんが泣いている姿を見たことない。いつもお金の心配ばかりして……『絵美たちの将来のためだ』なんて言うけど、そんなことのせいで泣けないの?」
母が死んでから、家で見る父はいつもワイシャツに袖を通した姿だった。机の上にパソコンとノートを広げて、いつも何か作業をしている。一度も、絵美たちの方を見ようとはしなかった。
「どうして、最初にお金なの? お母さんが死ぬ前は、お父さん、そんなんじゃなかったじゃない」
絵美は脳裏に蘇る父の姿と、今目の前にいる男の冷たい瞳の色の違いに震えた。
母が死ぬ十日前、友達の家に遊びに行こうとした休日のことだった。待ち合わせ時間に遅刻してしまいそうだった絵美を、父は呼び止めて車で送ってやると提案してくれた。絵美は喜んで助手席に座り、待ち合わせの場所に着くまでの間、ずっと学校での出来事や友人のこと、悩んでいることを父に話した。父は無愛想だから、それに笑ったりはあまりしてくれない。けれど、ちゃんと聞いて一緒に考えてくれる人だった。ちゃんと、絵美のことを想って耳を傾けてくれる人なんだと思っていた。
――なのに。
『俺は愛したことなんて、一度もない』
暗い病室の中、父の声が嫌に響いていたのを覚えている。あの時と同じ瞳が、絵美の目の前にあった。
「なんで、お母さんが死んだとわかった時にあんなこと言ったの? お母さんを愛してなかったなんて、嘘だよね?」
ザァ、と一際強い風が吹いた。
「なんであんな嘘をつくの? 本当に愛してなかったのなら、どうして今まで一緒に暮らしてきたの?」
絵美の言葉は詰問のように語調が強くなる。次第に彼女の中で渦巻く、今まで言語化出来なかった感情たちが喉に溢れてきた。
だが、父は黙っている。
「ねぇ答えて」
絵美は声を荒げて詰め寄った。
「本当にお母さんを愛してなかったのなら、お父さんは私たちのことも愛してなかったの? 蒼太は? ……私ちゃんと覚えてるよ、初めて蒼太が小学校に入学した時、いつも仏頂面のお父さんが、笑ってたこと。……それに、私たちのことを愛してなかったら、『お前たちの将来のため』なんて言葉、普通使わないよね」
そうだよね、と絵美は地団駄を踏む幼子のように父に縋り付いて聞いた。
「お父さんの、本音を教えて?」
ただ、父が母を愛していたという言葉が欲しかった。それだけあれば、絵美は父を許すことができる。
絵美は、父が長い悪夢を見ているのだと思った。
母が死んだ時に口走った言葉は、母が死んだことによる動揺が生んだ虚言だ。そうとしか思えない。あれから父は、母の死から目をそらすためにお金を見ているのだ。目を逸らす理由があれば、人は走り続けられる。父は哀しみから逃げるためにお金と、絵美たちの将来を言い訳に悪夢を見続けているのだ。
だからこそ、悪夢から父が救われてほしいと思った。
だからこそ、父にあの時の言葉を撤回して欲しかった。
取り乱していたとはいえ、父は言ってはならない言葉を口にした。だから許せなかった。あの日から絵美は、父の言葉を思い出すたびに息が苦しくなって辛かった。
(私たち姉弟を、あんたの悪夢に巻き込まないで)
絵美はただ、父の真意が聞きたかった。ただ、父のことを信じたかった。
どんなに嫌いになって、どんなに許せないことを言ったとしても、絵美にとって父親は彼一人なのだから――せめて信じたい。
父は黙って絵美を見つめている。彼の視線には、怒りや戸惑いといった感情は感じられなかった。ただ、聞いてくれている。そこに、車に乗せてくれた時、黙って絵美の言葉を聞いてくれた父の面影を感じた。
あの冷たい目は、きっと嘘だ。そうに違いない。
二人の間で物寂しげな雨音だけが響く。
どれほどの沈黙があっただろう。父はゆっくりと目を閉じて、そして小さく笑った。
「……俺は、馬鹿な人間なんだよ」
父はそう言って、目をうっすらと開いて絵美を見る。
「そしてお前も馬鹿だな」
変わらず、冷たい瞳はそこにあった。
「……え?」
「俺は最初からずっと言ってるじゃないか。『誰も愛したことがない』と」
絵美は体がざわりと鳥肌で波打つのを感じた。父は小さなため息を吐く。
「絵美は、俺の本心が聞きたいと言ったな。その答えは簡単だよ。――『責任』だ」
「……責任?」
絵美は、今頃のように雨に濡れた服がべったりと自身の体に張り付く感覚に震えた。
「そうだ。『責任』だ。……お前はまだ子どもだから、わからないかなぁ」
父はそう言って面倒臭そうに頭を掻いた。
「お前は『人を愛せよ』なんて、簡単に言うけど、絵美の言う『愛』ってつまり何だ?」
「何って」
それは、と言いかけて言葉に詰まらせる。
絵美のことを大事にしてくれること。
絵美のことを好きって言ってくれること。
絵美のことを優しくしてくれること。
……どれもが『愛』とは言えない気がした。これは、ただの絵美にとって都合のいい願望だ。今まで絵美の中で確かな形のあったものが、少しずつ崩れるのを感じた。
「確かに小説や映画、人の噂話……どこもかしこも『人を愛せよ』と騒がれるが、つまり何をしろって話なんだ? 絵美は具体的に俺にどうして欲しかったんだ?」
お母さんをちゃんと看取って欲しかった。
お母さんのために泣いて欲しかった。
(……そんな父の姿を、私は『見たかった』?)
絵美は視線をそらす。
「……でも、お父さんはお母さんと結婚したじゃん」
自分でも、この言葉は話題を逸らすためのものだとわかっている。わかっていながら、絵美は言い訳のように口にしてしまった。
「お父さんはお母さんのことが好きだったんでしょう?」
それに父は感情のない声で答えた。
「俺が母さんと結婚したのは、お前が生まれたからだ」
絵美は無意識にビクリと震えた。
「別に母さんのことが好きだったからじゃない。子どもが生まれるってことはな、同時にその子を大人になるまで育てるっていう『責任』って名前の兄弟も一緒に生まれてくることなんだよ。それを俺は母さんと共に背負わなければならなかった。だから、生きていくために結婚した。……そこに『愛』なんて不確かなものはない」
意味がわからない、と絵美は思った。父は何を言っているのだろうか。
「子どもを育てるってことはな、金がかかるってことでもあるんだよ」
父は首をコキリと鳴らした。
「ほんっとうに、金がかかる。だけどそりゃ当たり前のことなんだ。生きるってことは社会に属して、人間として生きることを証明し続けることだからな。お金は言ってみたら、そのための証明書だ」
眉を顰める絵美を見て、父は肩を竦めた。
「社会ってのは、人が『人間』という生き物らしく生きるための仕組みであり装置だ。そうだな……車みたいなもんか。道路が『人間』らしい生き方を視覚化したものだとすると、その進み方を教えてくれる標識には教育、福祉、仕事……そういう『人間』としての暮らし、営みが示されている。……で、ガソリンが『人間』として動くための食事だ。それなら、お金こそが『人間』であることを示す証明書だろう。車が運転できることを他人に証明する免許証のように、この社会の一員であることを示すのがお金だ」
淡々とした彼の説明は、まるで学校で授業する先生のようだと思った。
「お金がなければ、人は『人間』として生きていけない。社会に属していないってことだからな。……社会に属せないのは『ひとでなし』だよ。俺たち親は、お前たち子どもを『人間』らしく道路の上を走らせられるように育てなくっちゃいけない。ちゃんとした車に乗せて、ちゃんと必要な時にガソリンを給油できて、ちゃんと運転できるように成長させる。間違っても事故を起こしたりしないように、車から勝手に降りないように、育てないといけない。
それが子を得て、親になる責任だ」
父はそう言うと、虚ろな目を絵美に向けた。
「お前は、せっかく父さんと母さんがここまで育てたのに、それを全部無駄にする気か?」
まるで幽鬼のように父の肌は白かった。そんな彼が口にした脅すような言葉に、絵美は腹の底まで冷たくなるような錯覚を起こす。
「お前は、今ならまだ間に合う。ちゃんとした道に歩みを戻せ」
そう言って父は絵美の肩に手を置いた。雨で冷えた体に、その手は温かかった。
だが、絵美にはそのぬくもりも、今は恐ろしい炎のように感じた。
肩に乗せられた父の手を払いのけて、絵美は顔を上げる。
「結局、お金なんだ……? そんなこと、どうでもいいじゃない。私はお父さんの気持ちを知りたいの。……お母さんの死は、悲しくなかったの?」
払われた手がじんじんと痛むのか、しばらくの間、父は宙に所在なく浮かぶ自身の手を眺めていた。
「悲しくは……あった」
彼はそう言うと、まるで自分の気持ちがそこで確信したように頷く。
「だけど、それだけだ」
そう言って絵美に笑いかけた。
「ふざけるな!」
絵美は父の襟を掴み、体重を父に傾ける。土はぬかるみ、父は簡単に倒れた。
父を組み伏して、その上に跨った絵美は襟を掴んだまま揺さぶった。
「何が『責任』だ! じゃあ何? お父さんは私が生まれなかったらお母さんとは結婚しなかたんだ? その程度の『愛』だったんだ?」
「だから、俺は誰も愛したことなんかない」
心底鬱陶しそうに、自分の襟を掴む絵美の手を睨んだ。
「……お前は自分で『愛』という言葉を叫びながら、それが何を意味しているのかわかってないんだ。だから教えてやる。――それはエゴだよ」
エゴ。
「絵美は、俺が気に入らないだけだ。それを全部『愛』なんて不明瞭な言葉にして俺に押し付けているんだ」
絵美は父の首を掴む手に力が入るのを感じた。
「……じゃあ、本当に私たちのことを、愛してくれたことはないの?」
あぁ、と父は頷く。
「俺はお前達の『父親』であろうとしたが、お前達を『愛そう』と思ったことはない」
父の虚ろな表情が絵美の心に鋭い凶器を刺し穿つ。絵美は自分の顔がくしゃくしゃに歪むのを感じた。
(違う)
「言っただろう。『責任』だと。子を育てるのは『父親』だ。それを果たすのは『父親』である俺だ」
父はそっと絵美の手を掴み、自分の襟元から絵美の手を放させた。
「そこに『子を愛せ』という強制はない」
(……違う、違う、ちがう)
絵美はうっすらと自分の瞳に涙が溜まるのを感じる。
――ずっと泣けなかったのに。
「どうして、そんなこと言うの」
声を出すと、余計に涙が溢れてきた。もう止めることが出来なかった。
「お父さんはちゃんと私たちのことを愛していたよ。でも、その気持ちが『愛』だとちゃんと理解できてないから、『責任』とか『義務』だとか、そんな適当な……自分にとってわかりやすい言葉で代用しているだけ。ちゃんと、愛してたよ。……どうしてこんな簡単なことがわからないの」
真下にある父の顔の頬に、自分の涙がポタポタと落ちるのを絵美は見た。
「『愛』がどんな形でもいいじゃない……私たちのことをちゃんと見てくれたら、それでいいじゃない」
未だに絵美は、ちゃんと『愛』がなんたるかを言葉にして説明することができなかった。
――だけど、絶対に……私は父のことを愛していた。
なのに。
「違う。『責任』は果たさなければならない『義務』だ。そこに愛だとか何だとか言うのはフィクションだ」
絵美はもう視界が涙で溢れてぼやけている。父の顔が歪んで見えない。
「俺はお前を愛したことはない」
絵美は首を振る。なんて不器用な人なんだろうと思った。
「もう、馬鹿なこと言わないで……」
父は顔を顰める。
「馬鹿を言っているのはお前だろう」
絵美はそっと目を閉じた。
――悟った。父と生きるのはやはり無理なんだ、と。
絵美は父のことが嫌いだが、愛している。でも、こんな父親と共に生きていけるとは思えなかった。
(どうして、お母さんが死ぬまでは一緒に歩んでいたはずの道が、こんな短い時間で違えてしまったのだろう)
この十七年間、どうしてこの父の歪みに気づいてやれなかったのだろうか。絵美は後悔ばかりが胸に募った。
(せめて、いつか……)
絵美は願う。父がいつか、だれかを愛することができる日を。
そして、愛されていたことを理解する日を。
絵美は強く拳を握り――そしてそれを振り上げた。