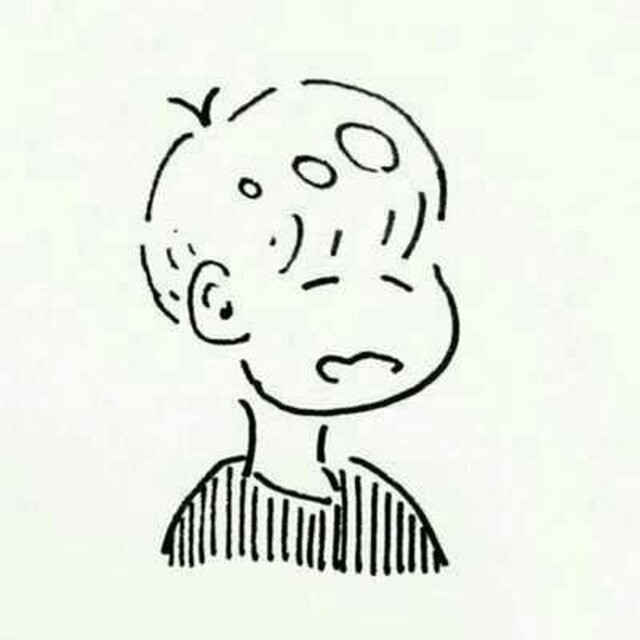第1話 母の死
文字数 2,371文字
降りしきる雨を鬱陶しいと感じ始めたのはいつからだろう。
絵美は足の爪を切りながら、ふと窓の外の景色を見上げて思った。真っ黒な雲から落ちてくる大きな雨粒は、窓ガラスにぶつかる度にパタパタと音を立てた。ガラスを濡らす雫は、そのまま重力に従ってゆっくりと流れ落ちていく。
耳をすましても雨音の激しい音以外、車の走行音も、風の音も、何も聞こえはしなかった。まるで分厚い暗幕に家全体が覆われたかのようだと思った。
「姉ちゃん」
弟の蒼太が部屋の扉から顔を覗かせた。中学生の彼は黒い詰襟の学生服に身を包んでいた。
「準備できた?」
「見れば分かるでしょ。ちょっと待ってて」
絵美は素早く、まだ切り終えていなかった片足の爪を切る。最後に小指の爪を切り終えて顔をあげると蒼太の顔が間近にあった。
「勝手に入ってくるなって、いつも言ってるでしょ」
蒼太はすぐには返事をせず、ちらりと絵美の顔を覗き込む。
「……今日はマニキュアしないんだな」
絵美は鼻を鳴らして、爪を切ったばかりの足を隠すように黒のハイソックスを履いた。
「いつもはつけてんじゃん」と蒼太はしつこく聞いてくる。
絵美は鏡の前に立ち制服を整えながら「そんな気分じゃない」と答えた。鏡に映る自分の顔はひどく陰鬱そうで、我ながら呆れてしまった。
でも、と絵美は思う。今日という日にこの顔は、ある意味お似合いなのかもしれない。
「それに今日みたいな日にマニキュアなんて……さすがにダメでしょ」
蒼太は「へぇ……」とため息のような返事をした。
別に蒼太はマニキュアのことなど聞きたかったわけではないことは絵美も分かっている。気を紛らわせたいだけなのだろう。
絵美は何気なく傍に立つ弟の顔を見た。
思えば蒼太はこの数年で随分成長した。小学校に通っていた頃は内気な性格だったのに、中学校に進学してサッカー部に入ってから、随分と友人を得て活動的になったと思った。肩幅もがっしりとして男らしい体型になった気がする。
少し前は、幼さが残る顔を綻ばせながら絵美に笑いかけてくれたのに、最近では話すことも少なくなった。
そんな彼を見ていると、もう以前の蒼太はいないんだな、と度々思うことがあった。
(でも、やっぱり蒼太は……蒼太だ。変わらない)
気まずくなると、どうでもいいようなことを絵美に尋ねて気を紛らわせる癖。相変わらずだな、と思った。
懐かしい思い出のアルバムを眺める気分で蒼太を見ていると、その視線に気づいたのか彼が顔を上げて目があった。すぐに蒼太は誤魔化すように窓の外に目を向ける。
「雨、止まねえな……」
そうね、と絵美も答えた。雨脚は先ほどよりも強くなったように見えた。
絵美の視界を満たすのは黒。誰もが悲しみに包まれている。コォン……と一際大きな鉦の音が鳴り響いた。
周囲は鯨幕で覆われて、中央には大きな白い棺が横たえられていた。その中で静かに眠る母の顔を、絵美はじっと見つめた。
母の亡骸には傷一つなく、まるで眠っているかのようだった。だが、その表情には生気がない。明らかにその肉体は死んでおり、二度と起き上がることはないことを雄弁に語っていた。
母のその眠る顔を見ていると、まざまざと思い出が甦り絵美はそのうち辛くなって目をそらした。絵美はねじ込むように花を棺に入れる。そのまま会場の隅に逃げるように小走りに駆けた。
絵美の後に、叔母が目元を赤くしながら、そっと棺桶の中に花を入れた。ポロポロと叔母は涙を流しながら、白いハンカチで目元を抑えている。
彼女の泣いている姿を見ながら、なぜ自分は泣けないのかと絵美は疑問に思った。
悲しくない訳ではない。辛くない訳ではない。ただ泣けない。
――なぜ泣けないのだろう。
その疑問は絵美の中に、まるで白い紙の上に墨を落としたようにそっと染み込んでいく。
葬式会場を見渡しながら、壁にもたれかかって絵美は思った。
母はいつも優しく、絵美や蒼太を思いやってくれていた。――絵美の世界には彼女が不可欠だった。
(……だったのに、お母さんは死んだ)
母の死は、言うなれば絵美の世界の一部の喪失だった。母が死んでから、絵美は胸の真ん中あたりに鈍い痛みをずっと抱えていた。
――なのに、泣けないのはなぜだろう?
母が死んだ時、絵美が一番最初に思ったことは『これからはお母さんのいない世界で生きていくんだな』という孤独感と『蒼太のことも、しっかり私が気をつけなくっちゃ』という使命感だった。
泣く、という行為を、絵美はすっかり忘れていたような気がする。
――なんて、そんな考え方、おかしいだろうか。
絵美はそんなことを考える自分を自嘲する。『泣く』という行為は考えて行われるものではない。自然と感情にまかせて溢れ出てくるものだ。
だから、絵美は不安だった。
――本当は、私はお母さんが死んだというのに悲しくないのかもしれない。
すぐに(そんな馬鹿な)と首を振り、そんなことを考える自分自身を軽蔑した。
絵美は母を愛していた。愛せないはずがない。あんなにも優しく絵美を愛してくれた母を。
(だから……)
今はただ、泣けないだけだ。――それだけのこと。
そうやって絵美は自分を納得させつつも、背筋が寒くなる感覚に震えた。
葬式会場には十数人の大人たちが、棺を囲んで並んでいた。顔なじみの従兄弟や初めて見る親戚。母の友人達が思い思いに故人を偲んでいる。みんな顔を泣き腫らし、目を赤くしていた。
そんな中、絵美は自分と同じように泣いていない唯一の人物を見つけた。――見つけた瞬間、思わず表情を顰めてしまった。
その人物は絵美と同じように会場の隅で壁にもたれかかり、周囲を見渡していた。手には献花の花を持ち、指で弄んでいる。
――絵美の父だ。
絵美は、自分が泣けないのは、全部あいつの所為だと思った。
絵美は足の爪を切りながら、ふと窓の外の景色を見上げて思った。真っ黒な雲から落ちてくる大きな雨粒は、窓ガラスにぶつかる度にパタパタと音を立てた。ガラスを濡らす雫は、そのまま重力に従ってゆっくりと流れ落ちていく。
耳をすましても雨音の激しい音以外、車の走行音も、風の音も、何も聞こえはしなかった。まるで分厚い暗幕に家全体が覆われたかのようだと思った。
「姉ちゃん」
弟の蒼太が部屋の扉から顔を覗かせた。中学生の彼は黒い詰襟の学生服に身を包んでいた。
「準備できた?」
「見れば分かるでしょ。ちょっと待ってて」
絵美は素早く、まだ切り終えていなかった片足の爪を切る。最後に小指の爪を切り終えて顔をあげると蒼太の顔が間近にあった。
「勝手に入ってくるなって、いつも言ってるでしょ」
蒼太はすぐには返事をせず、ちらりと絵美の顔を覗き込む。
「……今日はマニキュアしないんだな」
絵美は鼻を鳴らして、爪を切ったばかりの足を隠すように黒のハイソックスを履いた。
「いつもはつけてんじゃん」と蒼太はしつこく聞いてくる。
絵美は鏡の前に立ち制服を整えながら「そんな気分じゃない」と答えた。鏡に映る自分の顔はひどく陰鬱そうで、我ながら呆れてしまった。
でも、と絵美は思う。今日という日にこの顔は、ある意味お似合いなのかもしれない。
「それに今日みたいな日にマニキュアなんて……さすがにダメでしょ」
蒼太は「へぇ……」とため息のような返事をした。
別に蒼太はマニキュアのことなど聞きたかったわけではないことは絵美も分かっている。気を紛らわせたいだけなのだろう。
絵美は何気なく傍に立つ弟の顔を見た。
思えば蒼太はこの数年で随分成長した。小学校に通っていた頃は内気な性格だったのに、中学校に進学してサッカー部に入ってから、随分と友人を得て活動的になったと思った。肩幅もがっしりとして男らしい体型になった気がする。
少し前は、幼さが残る顔を綻ばせながら絵美に笑いかけてくれたのに、最近では話すことも少なくなった。
そんな彼を見ていると、もう以前の蒼太はいないんだな、と度々思うことがあった。
(でも、やっぱり蒼太は……蒼太だ。変わらない)
気まずくなると、どうでもいいようなことを絵美に尋ねて気を紛らわせる癖。相変わらずだな、と思った。
懐かしい思い出のアルバムを眺める気分で蒼太を見ていると、その視線に気づいたのか彼が顔を上げて目があった。すぐに蒼太は誤魔化すように窓の外に目を向ける。
「雨、止まねえな……」
そうね、と絵美も答えた。雨脚は先ほどよりも強くなったように見えた。
絵美の視界を満たすのは黒。誰もが悲しみに包まれている。コォン……と一際大きな鉦の音が鳴り響いた。
周囲は鯨幕で覆われて、中央には大きな白い棺が横たえられていた。その中で静かに眠る母の顔を、絵美はじっと見つめた。
母の亡骸には傷一つなく、まるで眠っているかのようだった。だが、その表情には生気がない。明らかにその肉体は死んでおり、二度と起き上がることはないことを雄弁に語っていた。
母のその眠る顔を見ていると、まざまざと思い出が甦り絵美はそのうち辛くなって目をそらした。絵美はねじ込むように花を棺に入れる。そのまま会場の隅に逃げるように小走りに駆けた。
絵美の後に、叔母が目元を赤くしながら、そっと棺桶の中に花を入れた。ポロポロと叔母は涙を流しながら、白いハンカチで目元を抑えている。
彼女の泣いている姿を見ながら、なぜ自分は泣けないのかと絵美は疑問に思った。
悲しくない訳ではない。辛くない訳ではない。ただ泣けない。
――なぜ泣けないのだろう。
その疑問は絵美の中に、まるで白い紙の上に墨を落としたようにそっと染み込んでいく。
葬式会場を見渡しながら、壁にもたれかかって絵美は思った。
母はいつも優しく、絵美や蒼太を思いやってくれていた。――絵美の世界には彼女が不可欠だった。
(……だったのに、お母さんは死んだ)
母の死は、言うなれば絵美の世界の一部の喪失だった。母が死んでから、絵美は胸の真ん中あたりに鈍い痛みをずっと抱えていた。
――なのに、泣けないのはなぜだろう?
母が死んだ時、絵美が一番最初に思ったことは『これからはお母さんのいない世界で生きていくんだな』という孤独感と『蒼太のことも、しっかり私が気をつけなくっちゃ』という使命感だった。
泣く、という行為を、絵美はすっかり忘れていたような気がする。
――なんて、そんな考え方、おかしいだろうか。
絵美はそんなことを考える自分を自嘲する。『泣く』という行為は考えて行われるものではない。自然と感情にまかせて溢れ出てくるものだ。
だから、絵美は不安だった。
――本当は、私はお母さんが死んだというのに悲しくないのかもしれない。
すぐに(そんな馬鹿な)と首を振り、そんなことを考える自分自身を軽蔑した。
絵美は母を愛していた。愛せないはずがない。あんなにも優しく絵美を愛してくれた母を。
(だから……)
今はただ、泣けないだけだ。――それだけのこと。
そうやって絵美は自分を納得させつつも、背筋が寒くなる感覚に震えた。
葬式会場には十数人の大人たちが、棺を囲んで並んでいた。顔なじみの従兄弟や初めて見る親戚。母の友人達が思い思いに故人を偲んでいる。みんな顔を泣き腫らし、目を赤くしていた。
そんな中、絵美は自分と同じように泣いていない唯一の人物を見つけた。――見つけた瞬間、思わず表情を顰めてしまった。
その人物は絵美と同じように会場の隅で壁にもたれかかり、周囲を見渡していた。手には献花の花を持ち、指で弄んでいる。
――絵美の父だ。
絵美は、自分が泣けないのは、全部あいつの所為だと思った。