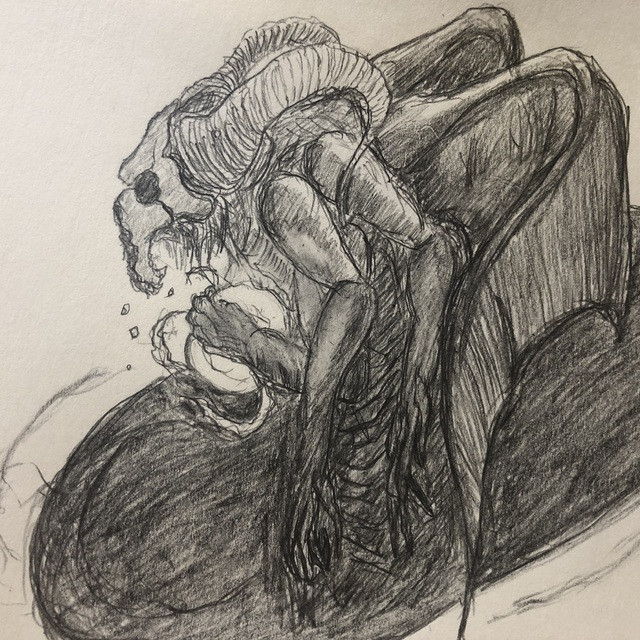後編
文字数 4,319文字
【三】
翌朝。
辰吉は何者かに体を揺すられて目を覚ました。
「起きて! 起きて! 早く!」
女性の声がする。わらべのような高い声。
飛び起きると、そこには白い着物を身にまとった女性が座っていた。
「お、おめぇ、お清か?」
「んだ」
お清が戻ってきた。あの世から帰ってきたんだ。嬉しさのあまり、辰吉はお清を抱きしめようとする。しかし、すぐに手を離してしまった。お清の体は異様なまでに冷たかったのだ。それはまるで、昨日の雪のように。
ふと、昨晩の出来事を思い出した。外に飛び出して、雪で小さな人形を作ったことを。
「それじゃおめぇ、まさか」
辰吉が尋ねると、お清は深く頷いた。
「辰吉さんが、あたしのことをここに呼んでくれたんだ」
「じゃあ、あの雪は?」
「あたしだ!」
どうやら彼女は、辰吉が作った雪人形に宿ってこの姿になったらしい。
神様が願いを聞いてくれた。辰吉はそう感じた。たとえ雪に宿っただけであっても、中身は生きていた頃と何ら変わらない、お清そのものだった。
「お清、ありがとう」
「なぁに言ってるの? ほら、早くしないと仕事に遅れるど?」
「仕事なんかどうでもええ!」
辰吉はすっくと立ち上がった。
「オラは、オラはお前と一緒にいたいんだ」
するとお清は眉間に皺を寄せて、
「何言ってんの? 与作さんを待たせたら駄目だ! ほら、早ぐぅ!」
今までのお清とは違っていた。何と言うか、少したくましくなったようだ。お清の成長が、辰吉は何だか嬉しかった。
「おめぇ、何つぅか、大人っぽくなったな」
「何言ってんだ! あたしは昔っからしっかりしとる」
言いながら、お清が辰吉の肩を叩いた。触れられただけで体の芯まで冷えるかのようだ。
「んじゃ、行ってくる」
「あっ、いってらっしゃーい!」
軽く手を上げて辰吉は外に出た。
雪はまだ積もっている。先の方に目を向けると、与作がいつものところで待っていた。辰吉は与作に向かって手を振り、ゆっくりと歩き出した。後ろではお清が辰吉を見送っている。いつもの光景が戻ってきた。
歩いてくる辰吉があまりに嬉しそうだったので、与作は何となく不安になった。気でも触れたのではないかと。
「なんだか、元気だな、おめぇ」
「そうかぁ?」
「まぁいいけんど。ほんじゃ、行くか」
「ああ!」
二人はまたいつもの森に向かった。
あの三日間が嘘のように、辰吉は仕事に精を出した。体にはあの力強さが戻っていた。与作は、初めは戸惑っていたが、友に元気が戻ったことを心の底から喜んだ。
その日の仕事は大成功、木もよく売れた。
帰り道、与作は何があったのか辰吉に聞いてみた。
「たった一日でこんなに元気になるなんて、何があったんだ?」
「さあなぁ。ま、良いことだなぁ」
「教えろよぅ」
与作が肘で突いてくる。
「いんや、駄目だ」
言ったところで、お清があの世から戻ってきたなんて話を信じてくれるだろうか。与作のことだから馬鹿にはしないと思うが、辰吉が幻でも見ているのではと勘違いするだろう。それこそ、まじない師でも連れてくるかもしれない。
道の途中で辰吉は与作と別れた。
もうじき日が暮れる。雪もそろそろ止んできたようだ。
家に戻ると、お清がいつものように、
「おかえりぃ!」
元気いっぱいに跳びついてきた。やはり冷たい。この冷たさが、お清がもうあちら側の存在であることを辰吉に実感させた。
違う。お清は帰ってきたんだ。間違いなく、生きてここにいるんだ。
辰吉は、彼女のぬくもりを意地でも感じようとしていた。
「ただいま。見てくれよ、この木ぃ」
「うわぁっ、すんげぇなぁ!」
「あはは、そういうところがお清らしいなぁ!」
席について夕食の支度を始める。たき火をつけて、昨日与作が作ったのと同じような煮汁を作り始めた。ところが、お清の様子がおかしい。たき火に近づこうとしない。
そうだった。彼女はただ戻って来たんじゃない。雪の人形を依代に姿を得たのだ。火に近づいたら溶けてしまう。
「ごっ、ごめんなぁ」
「ううん、あたしの方こそ、ごめん」
「いいや、オラはお清と一緒にいられればそれでいいんだぁ。ほら、まだ野菜もあるし、今日は煮汁はやめよう」
そう言って、辰吉は野菜を包丁で刻み始めた。お清はそんな彼の様子を微笑みながら見つめていた。
「さ、出来たぞ」
「うわぁ、美味そうだなぁ!」
「これだったら熱くねぇからな。さ、食べれ」
野菜を切って、少し味付けした料理。二人はそれを、時間をかけて食べた。
食事が終わったあとは、毎夜お馴染み、お清の不思議な話。今日も変な生き物を見たと嬉しそうに語る。
「さっきなぁ、天狗を見たんよ!」
「天狗ぅ?」
「んだ、そこの山に飛んでいくのを見たんだぁ」
「へぇ、不思議だなぁ」
「あとねぇ、こぉんくらいのネズミも見たんよぉ!」
お清が手で大きな円を描いて説明した。そのネズミは、顔が人間に似ていて、坊さんのように袈裟を着ているのだそうだ。
そんな鼠いるわけがないと言って外を見ると、辰吉は凍り付いた。
あたりはすっかり暗くなっているのに、一部真昼のように明るいところが。見ると、そこに袈裟を着た坊主がいた。だが、どこかおかしい。目を凝らして見てみると、坊主の腰辺りから太い紐が生えている。
「えっ?」
声をあげると、坊主が家の方を向いた。大きな耳が生え、前歯が突き出ている。
そして体は毛で覆われている。たった今お清が言っていた生き物と同じ風貌だ。
「な? おったろぅ?」
お清が辰吉の肩に手を置いて大きく揺らした。得意げな顔が可愛らしかった。
「んだなぁ、おったなぁ!」
袈裟を着た大きなネズミ。夜にそんなものを見たら恐ろしくて気絶してしまうだろうが、この時は何だか嬉しかった。お清と一緒に飛び跳ねて喜んだ。
「すげぇな、おめぇ!」
「んだぁ! あたしはすげぇんだぁ!」
山の麓の小さな家。辰吉とお清は一晩中はしゃいでいた。
【四】
それから一週間ばかり、辰吉とお清は今まで通りの楽しい生活を送った。
前と違うのは、夜になるとお清が遭遇した不思議な生き物達が現れることぐらいか。彼等は二人を取って食うつもりはないらしい。こちらを見て逃げ出してしまうものから、お辞儀をして去っていくもの、それから踊りを披露してくれたものもいた。彼等の見せる踊りは神秘的で、見ていると心が和んだ。しかしそれは、美しさだけではなく、お清と共に過ごしていたからこそ、より感動したのかもしれない。
ある日、仕事から戻ってきたときのこと。
大地を覆っていた雪が溶け、花もちらほら咲き始めている。
「ただいま!」
いつもなら跳んでくるお清が、今日は静かだった。何も答えてくれなかった。
「お清?」
足袋を脱いで、彼女に歩み寄る。それでも振り向いてくれない。
「なあ、どうしたぁ?」
と、お清の肩に手を置いてハッとした。
彼女の体が濡れていた。
恐れていたことが起きてしまった。驚きのあまりその場で固まってしまった。
「ごめん、辰吉さん、時間みてぇだ」
お清がゆっくりと立ち上がって振り返る。顔も、服も、素肌も何もかも整ったまま。しかし、ところどころ濡れて透きとおっている。溶けているのだ。辰吉はそう悟った。
「やっぱり雪の体じゃあなぁ。本当は、もっと一緒にいたかったけんど、神様は許してくれねぇみてぇだ」
「そんな、待ってくれよ! おめぇが死んだら、オラは、オラは生きていけねぇよぅ!」
それを聞くと、お清の顔が少し険しくなった。
「なぁ、今からでも遅くねぇ。神様んとこ行って、お祈りしよう! なぁ」
「辰吉さん!」
お清が辰吉の両肩を押した。
こんなことは今までなかった。何故彼女は自分にこんなことをするのだろう。
「そんなの、あたしが好きな辰吉さんじゃねぇ」
「え?」
「あたしは、お友達を大事にして、弱いあたしのことも気遣ってくれた、男らしい辰吉さんが好きだったんだぁ。……なのに、あたしがいなくなったら生きていけねぇなんて、そんなの辰吉さんじゃねぇ!」
お清が涙を流した。氷のような頬を雫がつたうと、色の濃い線が浮かんだ。
この涙には温もりがあるのだ。その温かさで、お清の肌が溶けているのだ。
「それに、辰吉さんが死んじまったら、与作さんはどうなるの?」
「与作?」
「死にそうになったとき、助けてくれたのは誰だ? 弱ってた辰吉さんに美味しい煮汁さ作ってくれたのは誰だ?」
彼女はあの日の様子をどこかから見ていたらしい。ちゃんと辰吉のことを見守っていたのだ。
そうか。
いつまでも弱音を吐いていたら、お清は安心して神様のところに行けなくなってしまう。
辰吉は俯いた。彼女の顔を見られなかった。
「ごめんなぁ」
「え?」
辰吉は、お清の前にひざまずいて謝った。
「ごめんなぁ! オラ、おめぇをがっかりさせちまってたんだなぁ! ごめんなぁ!」
辰吉の目から涙がぼろぼろと流れ落ちる。すると、涙よりも大きなしずくが彼の上に落ちてきた。それはお清の体から流れ出ていた。もう時間がない。
「お清!」
「辰吉さん、頑張ってな」
「か、必ず、必ずまた来いよ! たまぁに一回でいいから、オラに顔見せに来いよぉ!」
お清は何も言わず、笑みを浮かべて深く頷いた。
最後にもう一度抱きしめようとすると、彼女の体はまばゆい光に包まれて消えてしまった。
後に残ったのは、ほとんど溶けきったあの雪人形だった。
【五】
それからというもの、辰吉はますます仕事に精を出すようになった。
仕事中は木を切ることだけに集中し、町で子供が泣いていたら迷わず手を差し出し、老婆が倒れていたら仕事そっちのけで彼女を介抱した。
そんなことをしているうち、いつしか辰吉は村の人気者になっていた。名家の姫が結婚を申し込んできたりもした。だが辰吉は、どの相手の申し出も受けなかった。彼が認めた伴侶はただ一人だから。
「んじゃ、またな」
「おぅ」
あれから十年経ったある日。
今も与作と一緒に仕事をしている。
日がもうじき暮れる。外で遊んでいた子供達が家の中に入る。
寂しい道を進んでいくと、そこには木造の小さな家が。
「ただいま」
返事はない。ここに住んでいるのは辰吉ただ一人。
足袋を脱いで、たき火をつけ、晩ご飯を作り始める。今日は狸を捕らえたので、狸汁を作ることにした。
包丁を持って支度をしていると、外が急に明るくなった。もう日は暮れたはずだが。包丁を置いて外を見に行く。
「あっ」
驚いた。
雪が降っている。まだそんな時期ではないのに。周りを見てみると、どうやら雪は辰吉の家を囲むように降っているようだ。
不思議な光景に見とれていると、後ろから、
「おかえりぃ!」
聞き覚えのある声。仕事をしていても、村でお喋りしていても、一度たりとも忘れたことがないあの声。
辰吉は声のする方を振り返り、優しい口調でこう言った。
「ただいま」
綺麗な雪の降る、ある夜のことである。
翌朝。
辰吉は何者かに体を揺すられて目を覚ました。
「起きて! 起きて! 早く!」
女性の声がする。わらべのような高い声。
飛び起きると、そこには白い着物を身にまとった女性が座っていた。
「お、おめぇ、お清か?」
「んだ」
お清が戻ってきた。あの世から帰ってきたんだ。嬉しさのあまり、辰吉はお清を抱きしめようとする。しかし、すぐに手を離してしまった。お清の体は異様なまでに冷たかったのだ。それはまるで、昨日の雪のように。
ふと、昨晩の出来事を思い出した。外に飛び出して、雪で小さな人形を作ったことを。
「それじゃおめぇ、まさか」
辰吉が尋ねると、お清は深く頷いた。
「辰吉さんが、あたしのことをここに呼んでくれたんだ」
「じゃあ、あの雪は?」
「あたしだ!」
どうやら彼女は、辰吉が作った雪人形に宿ってこの姿になったらしい。
神様が願いを聞いてくれた。辰吉はそう感じた。たとえ雪に宿っただけであっても、中身は生きていた頃と何ら変わらない、お清そのものだった。
「お清、ありがとう」
「なぁに言ってるの? ほら、早くしないと仕事に遅れるど?」
「仕事なんかどうでもええ!」
辰吉はすっくと立ち上がった。
「オラは、オラはお前と一緒にいたいんだ」
するとお清は眉間に皺を寄せて、
「何言ってんの? 与作さんを待たせたら駄目だ! ほら、早ぐぅ!」
今までのお清とは違っていた。何と言うか、少したくましくなったようだ。お清の成長が、辰吉は何だか嬉しかった。
「おめぇ、何つぅか、大人っぽくなったな」
「何言ってんだ! あたしは昔っからしっかりしとる」
言いながら、お清が辰吉の肩を叩いた。触れられただけで体の芯まで冷えるかのようだ。
「んじゃ、行ってくる」
「あっ、いってらっしゃーい!」
軽く手を上げて辰吉は外に出た。
雪はまだ積もっている。先の方に目を向けると、与作がいつものところで待っていた。辰吉は与作に向かって手を振り、ゆっくりと歩き出した。後ろではお清が辰吉を見送っている。いつもの光景が戻ってきた。
歩いてくる辰吉があまりに嬉しそうだったので、与作は何となく不安になった。気でも触れたのではないかと。
「なんだか、元気だな、おめぇ」
「そうかぁ?」
「まぁいいけんど。ほんじゃ、行くか」
「ああ!」
二人はまたいつもの森に向かった。
あの三日間が嘘のように、辰吉は仕事に精を出した。体にはあの力強さが戻っていた。与作は、初めは戸惑っていたが、友に元気が戻ったことを心の底から喜んだ。
その日の仕事は大成功、木もよく売れた。
帰り道、与作は何があったのか辰吉に聞いてみた。
「たった一日でこんなに元気になるなんて、何があったんだ?」
「さあなぁ。ま、良いことだなぁ」
「教えろよぅ」
与作が肘で突いてくる。
「いんや、駄目だ」
言ったところで、お清があの世から戻ってきたなんて話を信じてくれるだろうか。与作のことだから馬鹿にはしないと思うが、辰吉が幻でも見ているのではと勘違いするだろう。それこそ、まじない師でも連れてくるかもしれない。
道の途中で辰吉は与作と別れた。
もうじき日が暮れる。雪もそろそろ止んできたようだ。
家に戻ると、お清がいつものように、
「おかえりぃ!」
元気いっぱいに跳びついてきた。やはり冷たい。この冷たさが、お清がもうあちら側の存在であることを辰吉に実感させた。
違う。お清は帰ってきたんだ。間違いなく、生きてここにいるんだ。
辰吉は、彼女のぬくもりを意地でも感じようとしていた。
「ただいま。見てくれよ、この木ぃ」
「うわぁっ、すんげぇなぁ!」
「あはは、そういうところがお清らしいなぁ!」
席について夕食の支度を始める。たき火をつけて、昨日与作が作ったのと同じような煮汁を作り始めた。ところが、お清の様子がおかしい。たき火に近づこうとしない。
そうだった。彼女はただ戻って来たんじゃない。雪の人形を依代に姿を得たのだ。火に近づいたら溶けてしまう。
「ごっ、ごめんなぁ」
「ううん、あたしの方こそ、ごめん」
「いいや、オラはお清と一緒にいられればそれでいいんだぁ。ほら、まだ野菜もあるし、今日は煮汁はやめよう」
そう言って、辰吉は野菜を包丁で刻み始めた。お清はそんな彼の様子を微笑みながら見つめていた。
「さ、出来たぞ」
「うわぁ、美味そうだなぁ!」
「これだったら熱くねぇからな。さ、食べれ」
野菜を切って、少し味付けした料理。二人はそれを、時間をかけて食べた。
食事が終わったあとは、毎夜お馴染み、お清の不思議な話。今日も変な生き物を見たと嬉しそうに語る。
「さっきなぁ、天狗を見たんよ!」
「天狗ぅ?」
「んだ、そこの山に飛んでいくのを見たんだぁ」
「へぇ、不思議だなぁ」
「あとねぇ、こぉんくらいのネズミも見たんよぉ!」
お清が手で大きな円を描いて説明した。そのネズミは、顔が人間に似ていて、坊さんのように袈裟を着ているのだそうだ。
そんな鼠いるわけがないと言って外を見ると、辰吉は凍り付いた。
あたりはすっかり暗くなっているのに、一部真昼のように明るいところが。見ると、そこに袈裟を着た坊主がいた。だが、どこかおかしい。目を凝らして見てみると、坊主の腰辺りから太い紐が生えている。
「えっ?」
声をあげると、坊主が家の方を向いた。大きな耳が生え、前歯が突き出ている。
そして体は毛で覆われている。たった今お清が言っていた生き物と同じ風貌だ。
「な? おったろぅ?」
お清が辰吉の肩に手を置いて大きく揺らした。得意げな顔が可愛らしかった。
「んだなぁ、おったなぁ!」
袈裟を着た大きなネズミ。夜にそんなものを見たら恐ろしくて気絶してしまうだろうが、この時は何だか嬉しかった。お清と一緒に飛び跳ねて喜んだ。
「すげぇな、おめぇ!」
「んだぁ! あたしはすげぇんだぁ!」
山の麓の小さな家。辰吉とお清は一晩中はしゃいでいた。
【四】
それから一週間ばかり、辰吉とお清は今まで通りの楽しい生活を送った。
前と違うのは、夜になるとお清が遭遇した不思議な生き物達が現れることぐらいか。彼等は二人を取って食うつもりはないらしい。こちらを見て逃げ出してしまうものから、お辞儀をして去っていくもの、それから踊りを披露してくれたものもいた。彼等の見せる踊りは神秘的で、見ていると心が和んだ。しかしそれは、美しさだけではなく、お清と共に過ごしていたからこそ、より感動したのかもしれない。
ある日、仕事から戻ってきたときのこと。
大地を覆っていた雪が溶け、花もちらほら咲き始めている。
「ただいま!」
いつもなら跳んでくるお清が、今日は静かだった。何も答えてくれなかった。
「お清?」
足袋を脱いで、彼女に歩み寄る。それでも振り向いてくれない。
「なあ、どうしたぁ?」
と、お清の肩に手を置いてハッとした。
彼女の体が濡れていた。
恐れていたことが起きてしまった。驚きのあまりその場で固まってしまった。
「ごめん、辰吉さん、時間みてぇだ」
お清がゆっくりと立ち上がって振り返る。顔も、服も、素肌も何もかも整ったまま。しかし、ところどころ濡れて透きとおっている。溶けているのだ。辰吉はそう悟った。
「やっぱり雪の体じゃあなぁ。本当は、もっと一緒にいたかったけんど、神様は許してくれねぇみてぇだ」
「そんな、待ってくれよ! おめぇが死んだら、オラは、オラは生きていけねぇよぅ!」
それを聞くと、お清の顔が少し険しくなった。
「なぁ、今からでも遅くねぇ。神様んとこ行って、お祈りしよう! なぁ」
「辰吉さん!」
お清が辰吉の両肩を押した。
こんなことは今までなかった。何故彼女は自分にこんなことをするのだろう。
「そんなの、あたしが好きな辰吉さんじゃねぇ」
「え?」
「あたしは、お友達を大事にして、弱いあたしのことも気遣ってくれた、男らしい辰吉さんが好きだったんだぁ。……なのに、あたしがいなくなったら生きていけねぇなんて、そんなの辰吉さんじゃねぇ!」
お清が涙を流した。氷のような頬を雫がつたうと、色の濃い線が浮かんだ。
この涙には温もりがあるのだ。その温かさで、お清の肌が溶けているのだ。
「それに、辰吉さんが死んじまったら、与作さんはどうなるの?」
「与作?」
「死にそうになったとき、助けてくれたのは誰だ? 弱ってた辰吉さんに美味しい煮汁さ作ってくれたのは誰だ?」
彼女はあの日の様子をどこかから見ていたらしい。ちゃんと辰吉のことを見守っていたのだ。
そうか。
いつまでも弱音を吐いていたら、お清は安心して神様のところに行けなくなってしまう。
辰吉は俯いた。彼女の顔を見られなかった。
「ごめんなぁ」
「え?」
辰吉は、お清の前にひざまずいて謝った。
「ごめんなぁ! オラ、おめぇをがっかりさせちまってたんだなぁ! ごめんなぁ!」
辰吉の目から涙がぼろぼろと流れ落ちる。すると、涙よりも大きなしずくが彼の上に落ちてきた。それはお清の体から流れ出ていた。もう時間がない。
「お清!」
「辰吉さん、頑張ってな」
「か、必ず、必ずまた来いよ! たまぁに一回でいいから、オラに顔見せに来いよぉ!」
お清は何も言わず、笑みを浮かべて深く頷いた。
最後にもう一度抱きしめようとすると、彼女の体はまばゆい光に包まれて消えてしまった。
後に残ったのは、ほとんど溶けきったあの雪人形だった。
【五】
それからというもの、辰吉はますます仕事に精を出すようになった。
仕事中は木を切ることだけに集中し、町で子供が泣いていたら迷わず手を差し出し、老婆が倒れていたら仕事そっちのけで彼女を介抱した。
そんなことをしているうち、いつしか辰吉は村の人気者になっていた。名家の姫が結婚を申し込んできたりもした。だが辰吉は、どの相手の申し出も受けなかった。彼が認めた伴侶はただ一人だから。
「んじゃ、またな」
「おぅ」
あれから十年経ったある日。
今も与作と一緒に仕事をしている。
日がもうじき暮れる。外で遊んでいた子供達が家の中に入る。
寂しい道を進んでいくと、そこには木造の小さな家が。
「ただいま」
返事はない。ここに住んでいるのは辰吉ただ一人。
足袋を脱いで、たき火をつけ、晩ご飯を作り始める。今日は狸を捕らえたので、狸汁を作ることにした。
包丁を持って支度をしていると、外が急に明るくなった。もう日は暮れたはずだが。包丁を置いて外を見に行く。
「あっ」
驚いた。
雪が降っている。まだそんな時期ではないのに。周りを見てみると、どうやら雪は辰吉の家を囲むように降っているようだ。
不思議な光景に見とれていると、後ろから、
「おかえりぃ!」
聞き覚えのある声。仕事をしていても、村でお喋りしていても、一度たりとも忘れたことがないあの声。
辰吉は声のする方を振り返り、優しい口調でこう言った。
「ただいま」
綺麗な雪の降る、ある夜のことである。