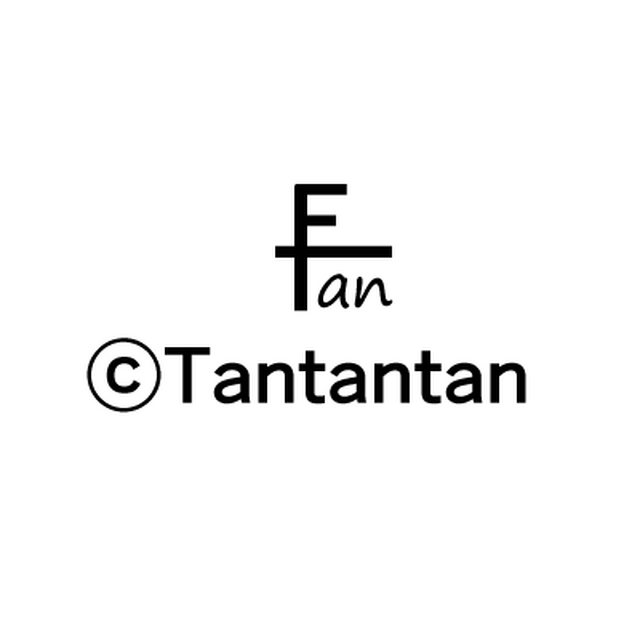十三位不文律
文字数 5,296文字
不束三探の十三位不文律
十三位不文律は三位十塔よりも強制力の低い縛りとなっている。
ミステリーの書き方やトリックパターンに影響を与えるものもあるため、自作品でも破ることもできるように、軽い縛りと定義した。
(1)一章必殺……一章にかならず殺人事件にそうおうする展開をいれることである。スリーアクトの一つ目。ロジカルミステリーにはリーダビリティが低いという欠点がある。それを補うためのつかみである。一般的なミステリーよりも、殺人事件をはやめに展開させている。一章必殺は殺人の伝聞に関する展開、死体の発見に関する展開の二種類に大別し、登場させている。
(2)サスペンスリーダビリティ……不束三探の作品群を、より読みやすいものとするためにとりいれている。不束三探の作品には、かならず、サスペンスリーダビリティがはいっている。それを公に宣言することで、読者が手をとりやすいようにしたかった。サスペンス要素が読みやすさへの一定保障になるからだ。
冒頭と結末を除いた中盤(遅れ早めの例外はある)に、サスペンス展開のいずれかを含んでいる。サスペンスリーダビリティは、スリルとアクションとドラマの三種類、存在している。一般的には、これらが多いほど、メディアミックス展開されやすい。スリーアクトの二つ目である。
(3)落ち生まれ結び……作品の終わり方を三項目に分けている。一般的に、落ちとは、物語の終わりを示した言葉だ。ただし、ロジカルミステリーの場合、解明の場面が挿入され、探偵役の語りがはじまる。
ほかのジャンルとはことなり、落ちが長くなる。
すぐに終わらないという点において、従来的な落ちとは、ことなっている。
よって、不束三探は、このスタイルの終わり方に、三つの区分をとった。『落ち』を終わり方の基本として、『結び』を最終段落および最終行としたのだ。両者のあいだに、『生まれ』という概念をあたらしくつくった。生まれは不束三探の造語である。殺人事件の解決以外に、もたらされる変化と定義している。
この『生まれ』は、『脈略上の変化』とも言える。万学の祖、アリストテレスの著作から引いている。意味合いとしては文学性にちかい。一章必殺、サスペンスリーダビリティ、落ち生まれ結びの三つを総称して、スリーアクトである。この三つはプロットの分類になるために、十三位不文律にとどめた。
(4)ニューリード・アゲイン……読者の完読率を高めるために、四段階のフォローを導入した。甲乙は比較的、ネタバレなし、丙丁はネタバレありとなっている。
後段ほど、解明度があがる。(甲)類別プロット表、(乙)パラグラフリーディング、(丙)当該作品の類別トリック集成、(丁)三答制の四つである。
ロジカルミステリーが苦手な人は、甲乙丙丁をすべて見てから、読みはじめてもらえると、わかりやすいはずだ。類別プロット表+と合わせて、再読するのもありである。完読できないことへの不安を和らげることが目的である。とにかく、自作品の完読率を高めたい一心の努力である。
(5)類別プロット表(手掛かり索引+)……作品の末尾に伏線の場所を明記する手法である。デイリー・キングは、手掛かり索引という名称で用いていた。
伏線を記載する書き方は、覚書を含めて、黄金期から存在している。伝統的な手法である。ただし、さっこんの作品群では、あまり見ることがない。
そこで、不束三探は、より現代的な形式として、蘇らせることにした。
自作の分類表の【第一】から【第八】=リ+トリック。【第九】から【第十】=フラグアトゥルー。三答制=アンサー。【第十一】から【第十五】=スリーアクト。【第十六】から【第二十】=レトリック。三位十塔による構成=スタイル。主体伏線と準伏線=ヒントの表記になっている。作品の終わりに記載しているトータルポイントは、その作品の情報密度をあらしている。
(6)アリストテレスの三説弁論……アリストテレスが弁論の際、わかりやすく民衆に伝えるために、とりあげた法則を不束三探がミステリーにあてはめたものである。ミステリーの殺人事件や伏線提示などに「可能と不可能」「過去と未来」「大と小」の三段階をとりいれている。
とくに可能と不可能の提示は、フツツカサンタン全疑法と密接に関係している。
代表的な可能と不可能は、アリバイである。ポジティブメタファーミステリーの特色を強く出すために、このアリバイは、かならず使用している。
不束三探の作品は、びっくり路線ではない。きっちり路線である。
意外性のある犯人ではなく、不可能な犯行をひとつひとつ精査し、最後には、すべて可能な犯行にかえている。それらの構成に三説弁論を使っている。分類上にのこしていないので、読者が目にすることはない。
あくまでも、白鳥における水面下のようなものである。
(7)七転八起の場面移動……七転八起は何度、失敗してもくじけず、そのたびに立ちあがって努力するという意味である。ロジカルミステリーは物語の停止性が高く、動きのある展開を演出しにくい傾向がある。それは読みにくさを生んでしまう。一定の対策が必要だと判断した。
不束三探は主人公が捜査を進めるなかで、つぎつぎと場面移動するプロットをとりいれるようにした。これが七転八起である。容疑者の居場所、由縁の名所、殺害現場などを最低、七回は移動するようにしている。
困難な事件を解き手たちの行動力で解決していく構成は、ポジティブメタファーミステリーの図式のひとつである。
その献身は推理量だけではなく、移動量にもあらわれている。
この定義もまた、読者が目にすることではない。作家努力のひとつである。サスペンスリーダビリティと同じように、ある程度の読みやすさを意識しているという指標のあらわれである。
(8)恋愛必携……恋愛要素は創作物の基本であり、最重要の要素のひとつである。トリックミステリーはかつて、人間性の欠如が指摘される時代があった。真偽はともかく、人格描写の穴埋めは、必要にちがいない。
どんな作品でも、人間性は不可欠だからだ。
不束三探の作品は、生まれやレトリックだけではなく、登場人物の恋愛模様を心がけている。容疑者同士の淡い恋愛描写にとどまることもあれば、恋愛要素を前面に出した作品もある。後者の代表作が不束三探サスペンスである。こちらは後日談を用いて、その恋愛成就をかならず、描写している。
少しでも、楽しみにしてもらえていたら、作家冥利に尽きる。
(9)探偵助手犯人の三すくみ……不束三探は古典的なミステリー形式を踏襲している。助手役が事件(犯人)に対して、遠回りの発言をして、探偵役が正しい方向に修正するという形式である。読者は助手役を低く見積もるかもしれないが、探偵は手掛かりを見つける助手を高く評価している。
つまり、探偵は犯人に強いが、助手に弱いのである。いっぽうの助手は探偵に強いが、犯人のつくった謎に弱い。逆に犯人は助手には強いが、探偵に弱い。
これは江戸時代の著作、児雷也豪傑譚の三すくみに基づいている。
いわゆる、ホームズワトソン形式である。不束三探の場合、三答制の都合上、探偵役がまちがった推理を行い、探偵役みずからが、それを否定する、いわゆる、探偵役が探偵役の推理を是正していく書き方とは、相性がよくない。
読者が推理するための判断基準がゆれるからだ。
ただし、こういった否定のサスペンスは、ミステリーの魅力のひとつである。
完全なる除外もまた、避けたかった。ゆえに、助手役にゆだねることにした。助手役に勿論破文、探偵役に示唆急文を使わせることで、信頼性と誤認、双方の舵取りをさせている。
(10)フツツカサンタン全疑法……疑った人物のなかに、かならず犯人が存在するという手法を指している。このフツツカサンタン全疑法には、ふたつの目的がある。
ひとつはバールストン先攻法への対策である。疑いから遠い者ほど、犯人であるという逆算(物語の最初に登場した人物が犯人というパターンも含まれる)によるメタ推理を避けるためだ。
ふたつは読者への挑戦のあとの消去法を省略するためである。必要前提をさきんじて提示することで、長尺な推理を避けることにした。登場人物のなかから容疑者を限定する場面を省力できる。作家側にとって、おおきなメリットがある。
必然的に、犯人は作品内で疑われた人物になる。
読者への挑戦よりまえに解決していない以上、犯行への不可能性が生じている。
つまり、このフツツカサンタン全疑法は、アリストテレスの三説弁論へと有機的に繋がることになるのだ。作者にとって、非常に使い勝手のいい縛りである。
(11)伏答点……伏答点(ふとうてん)にはふたつの縛りがある。読者への挑戦のあとに登場する真トリックと真リトリックの合計数を三つ以上にすること、逆に、双方の合計数を十三未満にすることである。トリックミステリーとしての魅力を保障させる数量が三つ以上となっている。トリック過多を防ぐ制限が十三未満である。少なすぎても物足りない。多すぎても整理できない。
両者のバランス調整が、伏答点となっている。不束三探が、延々とトリックをいれることを自制する、ブレーキとも言える。
(12)インパクトセンテンス……後の先、先の後は、章頭と章末の定義だったが、インパクトセンテンスは、文中の定義となっている。疑問、否定、仮説、新事実の四種類は、ストーリー上に変化をおよぼす割合がおおきい。この場面を読み流してしまった場合、全体理解の滞りが起きやすい。
作者としては、気をつけなくてはならない。
いちばんの対策は、これら四種類の展開を、文章の頭にいれることである。
基本的に読者の視点は、文中の上部へと集まる。ゆえに、インパクトのある文章は、文頭に置くほうが好ましいと言える。こういった配慮を定義したものが、インパクトセンテンスである。
空行をはさむことも効果的であり、不束の作品では神曲文体と併用されている。空行の前後には、疑問、否定、新事実、仮説のいずれかの言及がはいっている。もちろん、移動文、目的文、状況文、観察文の場合もある。
逆に、翻訳小説に見られる手法として、『クッションセンテンス』が存在している。インパクトセンテンスとは、逆の使い方である。会話文と同じ行に地の文をいれ、同じ登場人物の会話文がつづけられるものである。
インパクトの低い情報などに使われる。不束三探の作品でも、使用例は多々ある。三行縛りの都合上、連続的な文章を緩和しなくてはならないからだ。途中で文章を切る必要があるとき、こういったクッションセンテンスが不可欠となる。
相槌と独り言が最多例だろうか。会話をうながすパターン、自らの話をふくらませるパターンに使われている。
黄金期の海外ミステリーが好きな者にとっては、見慣れた手法である。
(13)電子書籍対応指向:平仮名優先文……文章は三十年ほどで、おおきく変容した。第一次の文章改革がワープロ、第二次の文章改革がパソコンと携帯電話、第三次の文章改革がスマートフォンとタブレットにあたる。
SNSが普及し、ひらがなから漢字に変換することがあたりまえとなり、現在、ひらがなのほうがスタンダードとなっている。
あたらしい世代ほど、電子書籍に親しみがあり、一般的な読書とかわりのない存在となっている。書く側も、その時代性に対応する必要がある。
電子書籍の場合、ディスプレイのサイズがちいさくなり、文章は自動調整される。このリデザインにより、作家の想定より作品内の行数が増大する。また、電子書籍は、ディスプレイ上の問題があり、画数の多い漢字は潰れる。
このふたつの問題を理解しておかなければならない。意識的に、ひらがなの量をふやし、ひとつひとつの行数をへらすことが重要である。わたしは、作品内の行数を、神曲文体によって、へらしている。漢字レベルも、逐一、調整している。
不束作品の漢字レベルは、横溝正史の名作『獄門島』をモデルにしている。ひらがなが多く、読みやすいという実感があるからだ。
制限パターンは、大尖塔に記載している。漢字化の共通認識をおおきくかえないようにするためだ。作品ごとに文体がかわると、同一性が失われ、作家性が薄れる。逆の立場だったら、好ましくない。ゆえに、漢字レベルの一定化を心掛けている。
なお、不束三探の分類表には、○章○計などの表記がはいっている。この表記も、電子書籍を考慮している。電子書籍ならば、単語検索とジャンプができる。類別プロット集成と照らし合わせることで、主項目の位置が把握しやすいはずだ。
軽→読者への挑戦前の準リ+トリック。計→読者への挑戦後の真リ+トリック。形→スリーアクト。型→レトリック。京→叙述曲のトリック。景→叙述曲のスリーアクトになっている。読み方は、すべて(けい)である。
考えてつくる。ミステリー特有の魅力が少しでも、伝わればと思っている。
十三位不文律は三位十塔よりも強制力の低い縛りとなっている。
ミステリーの書き方やトリックパターンに影響を与えるものもあるため、自作品でも破ることもできるように、軽い縛りと定義した。
(1)一章必殺……一章にかならず殺人事件にそうおうする展開をいれることである。スリーアクトの一つ目。ロジカルミステリーにはリーダビリティが低いという欠点がある。それを補うためのつかみである。一般的なミステリーよりも、殺人事件をはやめに展開させている。一章必殺は殺人の伝聞に関する展開、死体の発見に関する展開の二種類に大別し、登場させている。
(2)サスペンスリーダビリティ……不束三探の作品群を、より読みやすいものとするためにとりいれている。不束三探の作品には、かならず、サスペンスリーダビリティがはいっている。それを公に宣言することで、読者が手をとりやすいようにしたかった。サスペンス要素が読みやすさへの一定保障になるからだ。
冒頭と結末を除いた中盤(遅れ早めの例外はある)に、サスペンス展開のいずれかを含んでいる。サスペンスリーダビリティは、スリルとアクションとドラマの三種類、存在している。一般的には、これらが多いほど、メディアミックス展開されやすい。スリーアクトの二つ目である。
(3)落ち生まれ結び……作品の終わり方を三項目に分けている。一般的に、落ちとは、物語の終わりを示した言葉だ。ただし、ロジカルミステリーの場合、解明の場面が挿入され、探偵役の語りがはじまる。
ほかのジャンルとはことなり、落ちが長くなる。
すぐに終わらないという点において、従来的な落ちとは、ことなっている。
よって、不束三探は、このスタイルの終わり方に、三つの区分をとった。『落ち』を終わり方の基本として、『結び』を最終段落および最終行としたのだ。両者のあいだに、『生まれ』という概念をあたらしくつくった。生まれは不束三探の造語である。殺人事件の解決以外に、もたらされる変化と定義している。
この『生まれ』は、『脈略上の変化』とも言える。万学の祖、アリストテレスの著作から引いている。意味合いとしては文学性にちかい。一章必殺、サスペンスリーダビリティ、落ち生まれ結びの三つを総称して、スリーアクトである。この三つはプロットの分類になるために、十三位不文律にとどめた。
(4)ニューリード・アゲイン……読者の完読率を高めるために、四段階のフォローを導入した。甲乙は比較的、ネタバレなし、丙丁はネタバレありとなっている。
後段ほど、解明度があがる。(甲)類別プロット表、(乙)パラグラフリーディング、(丙)当該作品の類別トリック集成、(丁)三答制の四つである。
ロジカルミステリーが苦手な人は、甲乙丙丁をすべて見てから、読みはじめてもらえると、わかりやすいはずだ。類別プロット表+と合わせて、再読するのもありである。完読できないことへの不安を和らげることが目的である。とにかく、自作品の完読率を高めたい一心の努力である。
(5)類別プロット表(手掛かり索引+)……作品の末尾に伏線の場所を明記する手法である。デイリー・キングは、手掛かり索引という名称で用いていた。
伏線を記載する書き方は、覚書を含めて、黄金期から存在している。伝統的な手法である。ただし、さっこんの作品群では、あまり見ることがない。
そこで、不束三探は、より現代的な形式として、蘇らせることにした。
自作の分類表の【第一】から【第八】=リ+トリック。【第九】から【第十】=フラグアトゥルー。三答制=アンサー。【第十一】から【第十五】=スリーアクト。【第十六】から【第二十】=レトリック。三位十塔による構成=スタイル。主体伏線と準伏線=ヒントの表記になっている。作品の終わりに記載しているトータルポイントは、その作品の情報密度をあらしている。
(6)アリストテレスの三説弁論……アリストテレスが弁論の際、わかりやすく民衆に伝えるために、とりあげた法則を不束三探がミステリーにあてはめたものである。ミステリーの殺人事件や伏線提示などに「可能と不可能」「過去と未来」「大と小」の三段階をとりいれている。
とくに可能と不可能の提示は、フツツカサンタン全疑法と密接に関係している。
代表的な可能と不可能は、アリバイである。ポジティブメタファーミステリーの特色を強く出すために、このアリバイは、かならず使用している。
不束三探の作品は、びっくり路線ではない。きっちり路線である。
意外性のある犯人ではなく、不可能な犯行をひとつひとつ精査し、最後には、すべて可能な犯行にかえている。それらの構成に三説弁論を使っている。分類上にのこしていないので、読者が目にすることはない。
あくまでも、白鳥における水面下のようなものである。
(7)七転八起の場面移動……七転八起は何度、失敗してもくじけず、そのたびに立ちあがって努力するという意味である。ロジカルミステリーは物語の停止性が高く、動きのある展開を演出しにくい傾向がある。それは読みにくさを生んでしまう。一定の対策が必要だと判断した。
不束三探は主人公が捜査を進めるなかで、つぎつぎと場面移動するプロットをとりいれるようにした。これが七転八起である。容疑者の居場所、由縁の名所、殺害現場などを最低、七回は移動するようにしている。
困難な事件を解き手たちの行動力で解決していく構成は、ポジティブメタファーミステリーの図式のひとつである。
その献身は推理量だけではなく、移動量にもあらわれている。
この定義もまた、読者が目にすることではない。作家努力のひとつである。サスペンスリーダビリティと同じように、ある程度の読みやすさを意識しているという指標のあらわれである。
(8)恋愛必携……恋愛要素は創作物の基本であり、最重要の要素のひとつである。トリックミステリーはかつて、人間性の欠如が指摘される時代があった。真偽はともかく、人格描写の穴埋めは、必要にちがいない。
どんな作品でも、人間性は不可欠だからだ。
不束三探の作品は、生まれやレトリックだけではなく、登場人物の恋愛模様を心がけている。容疑者同士の淡い恋愛描写にとどまることもあれば、恋愛要素を前面に出した作品もある。後者の代表作が不束三探サスペンスである。こちらは後日談を用いて、その恋愛成就をかならず、描写している。
少しでも、楽しみにしてもらえていたら、作家冥利に尽きる。
(9)探偵助手犯人の三すくみ……不束三探は古典的なミステリー形式を踏襲している。助手役が事件(犯人)に対して、遠回りの発言をして、探偵役が正しい方向に修正するという形式である。読者は助手役を低く見積もるかもしれないが、探偵は手掛かりを見つける助手を高く評価している。
つまり、探偵は犯人に強いが、助手に弱いのである。いっぽうの助手は探偵に強いが、犯人のつくった謎に弱い。逆に犯人は助手には強いが、探偵に弱い。
これは江戸時代の著作、児雷也豪傑譚の三すくみに基づいている。
いわゆる、ホームズワトソン形式である。不束三探の場合、三答制の都合上、探偵役がまちがった推理を行い、探偵役みずからが、それを否定する、いわゆる、探偵役が探偵役の推理を是正していく書き方とは、相性がよくない。
読者が推理するための判断基準がゆれるからだ。
ただし、こういった否定のサスペンスは、ミステリーの魅力のひとつである。
完全なる除外もまた、避けたかった。ゆえに、助手役にゆだねることにした。助手役に勿論破文、探偵役に示唆急文を使わせることで、信頼性と誤認、双方の舵取りをさせている。
(10)フツツカサンタン全疑法……疑った人物のなかに、かならず犯人が存在するという手法を指している。このフツツカサンタン全疑法には、ふたつの目的がある。
ひとつはバールストン先攻法への対策である。疑いから遠い者ほど、犯人であるという逆算(物語の最初に登場した人物が犯人というパターンも含まれる)によるメタ推理を避けるためだ。
ふたつは読者への挑戦のあとの消去法を省略するためである。必要前提をさきんじて提示することで、長尺な推理を避けることにした。登場人物のなかから容疑者を限定する場面を省力できる。作家側にとって、おおきなメリットがある。
必然的に、犯人は作品内で疑われた人物になる。
読者への挑戦よりまえに解決していない以上、犯行への不可能性が生じている。
つまり、このフツツカサンタン全疑法は、アリストテレスの三説弁論へと有機的に繋がることになるのだ。作者にとって、非常に使い勝手のいい縛りである。
(11)伏答点……伏答点(ふとうてん)にはふたつの縛りがある。読者への挑戦のあとに登場する真トリックと真リトリックの合計数を三つ以上にすること、逆に、双方の合計数を十三未満にすることである。トリックミステリーとしての魅力を保障させる数量が三つ以上となっている。トリック過多を防ぐ制限が十三未満である。少なすぎても物足りない。多すぎても整理できない。
両者のバランス調整が、伏答点となっている。不束三探が、延々とトリックをいれることを自制する、ブレーキとも言える。
(12)インパクトセンテンス……後の先、先の後は、章頭と章末の定義だったが、インパクトセンテンスは、文中の定義となっている。疑問、否定、仮説、新事実の四種類は、ストーリー上に変化をおよぼす割合がおおきい。この場面を読み流してしまった場合、全体理解の滞りが起きやすい。
作者としては、気をつけなくてはならない。
いちばんの対策は、これら四種類の展開を、文章の頭にいれることである。
基本的に読者の視点は、文中の上部へと集まる。ゆえに、インパクトのある文章は、文頭に置くほうが好ましいと言える。こういった配慮を定義したものが、インパクトセンテンスである。
空行をはさむことも効果的であり、不束の作品では神曲文体と併用されている。空行の前後には、疑問、否定、新事実、仮説のいずれかの言及がはいっている。もちろん、移動文、目的文、状況文、観察文の場合もある。
逆に、翻訳小説に見られる手法として、『クッションセンテンス』が存在している。インパクトセンテンスとは、逆の使い方である。会話文と同じ行に地の文をいれ、同じ登場人物の会話文がつづけられるものである。
インパクトの低い情報などに使われる。不束三探の作品でも、使用例は多々ある。三行縛りの都合上、連続的な文章を緩和しなくてはならないからだ。途中で文章を切る必要があるとき、こういったクッションセンテンスが不可欠となる。
相槌と独り言が最多例だろうか。会話をうながすパターン、自らの話をふくらませるパターンに使われている。
黄金期の海外ミステリーが好きな者にとっては、見慣れた手法である。
(13)電子書籍対応指向:平仮名優先文……文章は三十年ほどで、おおきく変容した。第一次の文章改革がワープロ、第二次の文章改革がパソコンと携帯電話、第三次の文章改革がスマートフォンとタブレットにあたる。
SNSが普及し、ひらがなから漢字に変換することがあたりまえとなり、現在、ひらがなのほうがスタンダードとなっている。
あたらしい世代ほど、電子書籍に親しみがあり、一般的な読書とかわりのない存在となっている。書く側も、その時代性に対応する必要がある。
電子書籍の場合、ディスプレイのサイズがちいさくなり、文章は自動調整される。このリデザインにより、作家の想定より作品内の行数が増大する。また、電子書籍は、ディスプレイ上の問題があり、画数の多い漢字は潰れる。
このふたつの問題を理解しておかなければならない。意識的に、ひらがなの量をふやし、ひとつひとつの行数をへらすことが重要である。わたしは、作品内の行数を、神曲文体によって、へらしている。漢字レベルも、逐一、調整している。
不束作品の漢字レベルは、横溝正史の名作『獄門島』をモデルにしている。ひらがなが多く、読みやすいという実感があるからだ。
制限パターンは、大尖塔に記載している。漢字化の共通認識をおおきくかえないようにするためだ。作品ごとに文体がかわると、同一性が失われ、作家性が薄れる。逆の立場だったら、好ましくない。ゆえに、漢字レベルの一定化を心掛けている。
なお、不束三探の分類表には、○章○計などの表記がはいっている。この表記も、電子書籍を考慮している。電子書籍ならば、単語検索とジャンプができる。類別プロット集成と照らし合わせることで、主項目の位置が把握しやすいはずだ。
軽→読者への挑戦前の準リ+トリック。計→読者への挑戦後の真リ+トリック。形→スリーアクト。型→レトリック。京→叙述曲のトリック。景→叙述曲のスリーアクトになっている。読み方は、すべて(けい)である。
考えてつくる。ミステリー特有の魅力が少しでも、伝わればと思っている。