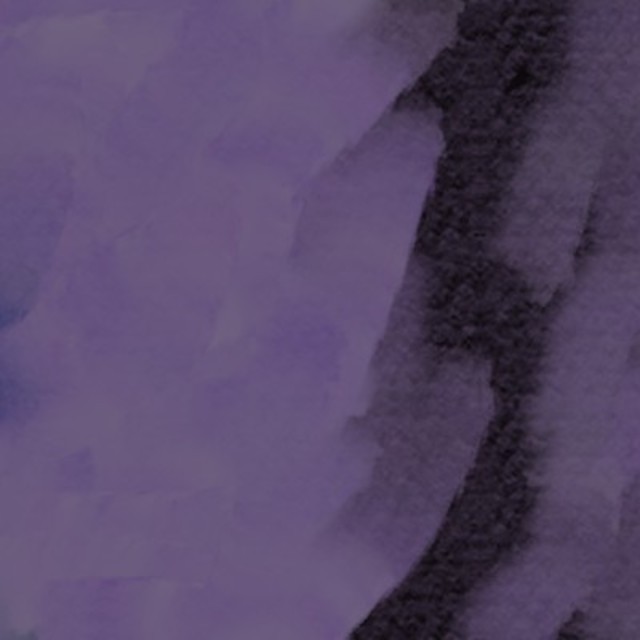運慶の罠
文字数 5,617文字
――お前の母ちゃん男と逃げたのか。
「だって、俺の母ちゃんが言ってたもん」
噂は、級友の口から私の耳にも届く。
――やめてよ。母さんはそんなことしないよ。
――じゃあ、うちの母ちゃんが嘘つきだってのか。
現に、母はいなくなっていた。
父は何も言わなかった。
母と逃げたという男は、校区の外れにある神社の神主だった。その社 は、消えた主 の代わりに穢れを押し付けられたか、たちまちのうちに寂れ果てた。
ご神木は大きな桜だった。神主が去ったばかりの頃は青々と葉を茂らせていたのが、すぐに立ち枯れてしまった。
まるで、罰を引き受けたかのようだと囁かれた。
翌年の春、その枯れ木が倒れた。
その後、父も私を置いて姿を消した。
私は父方の祖父母を通して、遠縁に当たる子供のできない夫婦の養子となった。隣県の住人となり名字も変わり、様々なショックが重なったせいか、それまでのことは記憶から薄れていった。
しかし、私は〈夢〉を見るようになった。
繰り返し繰り返し見る〈夢〉。
夜。
朽ちた、簡素な社殿。
崩れた壁の隙間から漏れる、揺れる明かり。
正座した男の後ろ姿。衣服越しにも見て取れるほど、痩せた腕を振り上げては、降ろす。
連れて動く肩甲骨。
銀に閃く反射。
搾り出すような長い吐息。
ゴゾリと、長く大きく異様なもの転がった。
木だ。木の幹がふたつに割れたのだ。
枯れて――枯れた木の間から、何かが生まれでた。
「もう逃げられないね」
囁き、割れた木の間に頭を沈めていく。
私の喉がヒッと鳴った。
男の頭が跳ね上がり、こちらを向く。
私はその顔を知っていた。
見る前から、きっと。
明かりに背を向け、走った。
おい、と呼ばれたが振り返らずに走った。
私は、何度となく見るその夢に囚われていた。中年の域に差し掛かってもなお、いや、ますます酷くなっている。
囚われ、急き立てられ――あの割れた木の間から出てきたものが何なのか、確かめなければならない。
〈夢〉だ。
〈夢〉の話だ。
それでも……私はあれが何なのか知っているはずで、だから確かめるというよりは思い出すという方が、きっと正しいのだという、自分でもよく判らない焦燥感に追われていた。
あの社殿が何処なのかは判っている。
母と逃げた神主がいたという、あそこだ。
しかし、あの場所はとうに更地になり、今では大型スーパーの駐車場になっている。
三十年近くが過ぎているのだ。
それでも何かないかと、この辺りの地方紙を取り寄せたりしていた。
〈桜の木で神像を――今秋個展を開く連慶 さん〉
小さな見出しのその記事には、モノクロだが写真もあった。荒い画像だったが、乱れ髪の女性を形創っているということは分かった。
私の〈夢〉の記憶が疼いた。
記事の末尾にあったギャラリーに問い合わせ、連慶という彫刻師に連絡を付けることができた。
個展を待たず、半ば押しかけるようにして連慶を訪ねた。
電話でのやり取りで、彼がかなりの酒飲みであることを察した。手土産はいい日本酒を奮発した。口が軽くなることを期待する、下心もあった。
しかし、肝心の〈問いたいこと〉が何なのかは、言葉にすることができないままだ。
「新聞で作品を拝見して、至極 感銘を受けまして」
電話でも告げた通りのことを、繰り返すしかなかった。これでは、ただの作品のファンだ。そうではない、ということを私自身は知ってはいるのだが、どうすれば伝えることができるのか――。
連慶はしきりに瞼を擦りながら、最初恐縮したようにしていたが、酒が入るにつれ、態度や口調がぞんざいになっていった。
木で出来てんだ、その人形は――個展の準備の話をしていたはずが、いきなり連慶は話題を変えた。
「生人形 って知ってるか」
知っている。
幕末から明治にかけて大いに流行った、木製の等身大の人形のことだ。生地に胡粉 を塗り重ねて作られた肌は、まるで生身の人間のようだったという。
今では芸術品扱いだが、元々は見世物興行に使われていたものだ。
これがなかなか――とんでもない代物で。どう見ても人形になど見えない精巧な作りのものが、極当たり前にあった。
マネキン人形にその技術は継承された後 、哀しいかな、徐々に稚拙 なものとなり衰退してしまう。
「有名所だと松本喜三郎や安本亀八なんだが、まぁ、そこまではいかなくても相当に腕のいい人形師が作ったものが、見世もんにごろごろしてた時代だったんだ」
連慶は残っていた酒を一気に煽 ると湯飲みの底に目を遣った。空いた方の手で瞼を擦る。
ここで口を挟むか、それとも様子をみるか。逡巡 していると、連慶は緩慢 な動きで顎を上げた。
激しく擦られた両の瞼は弛みきり、まともに開いてはいない。
よれた肉の隙間から、溶けた蝋のような白目と僅かばかりの黒目が覗いて――私を睨む。
連慶の、酒に濡れた唇が動いた。
「運慶 って知ってるか」
どろりと腐りとろけた声が言う。
「日本一の、ど偉い天才の……なんだ、彫刻家だか」
「正確には仏師ですね」
つい、嫌味な言い方をしてしまった。
「ああ、そうそう。その運慶が言うには、仏像ってのは木を彫って形造るんじゃなくて、予 め木の中に埋まっているものを彫り出すだけで」
滔々 と語りだしたのは、漱石の小説ではないか。
「それは小説の話です」
呆れた。
「小説家の書いた作り事ですよ」
「運慶を知ってるんだろ」
「あなたが言っている運慶とは違います」
「どう違うんだぁ」
連慶の声音は、更にどろりと溶ける。
ああ、しまった。
「運慶は運慶だろうが。お前、職人なめんじゃねぇぞ」
怒らせてしまったか。
連慶は、まだ未練たらしく握っていた茶碗を、土間に叩きつける。使い込まれ古びていたそれは、乾いた音をたてて割れた。
ヘタを打った。
どうすればこの場が収まるか、考える。とりあえず謝る、か。いっそ怯えてみせるか。それとも――。
「運慶なんだよ。あのでかいスーパー。そこの駐車場ができる前は神社だったのさ。そこの御神木はでかい桜の木だった。それで神さんを彫り出したのはヤツだ」
「な、」
私は絶句する。
何だ、何だこれは。私はまだ何も、肝心なことは話していないのだ。前情報など何もないはずなのだ。
連慶の言い出したことは、突然すぎるし合致しすぎる。どろりとした声音と〈夢〉の光景が重なった。
「俺がまだ小さかった頃、潰れちまったんだ、あの神社は。そこのご神木をぶった切って、女神さまの像を創って祀 ろうって男がいたんだ。そいつは運慶を名乗っていた。そんなことができるのは運慶しかいねぇだろ」
呑まれる。
「運慶はご神木の中の神様をそのまま彫り出すことができるんだ――俺はそう聞いた。小説なんかじゃねぇ。ちゃんと本人から聞いたんだ」
連慶は口元を手の甲で拭 い、舐めた。
「その運慶が、ご神木から彫り出したってェ神さんが、お前の聞きたい話だろ。違うか」
違うかって――違わない!
しかし、しかし!
「い、いや、運慶は現代の仏師ではないんです。ああ、もしかして、運慶を名乗る他の」
「違う。あれは本物の運慶だ。お前が何を言おうと、本物なんだ。よし、」
「教えてやる」
連慶は次の間の襖 を開けて、私に入るように促す。
「こんな話があった」
後ろ手で、連慶は襖を閉めた。
夜。
朽ちた、簡素な社殿。
崩れた壁の隙間から漏れる、揺れる明かり。
正座した男の後ろ姿。衣服越しにも見て取れるほど、痩せた腕を振り上げては、降ろす。
連れて動く肩甲骨。
銀に閃く反射。
搾り出すような長い吐息。
ゴゾリと、長く大きく異様なもの転がった。
木だ。木の幹がふたつに割れたのだ。
枯れて――枯れた木の間から、何かが生まれでた――。
「もう逃げられないね」
囁き、割れた木の間に頭を沈めていく。
隣りにいる友達の喉がヒッと鳴った。
男の頭が跳ね上がり、こちらを向く。
俺はその顔を知っていた。
見る前から、きっと。
友達が明かりに背を向け、走りだした。
おい、と呼んだが振り返らずに走っていった。
私は面食らう。
何を言っているんだ。
それは、私の〈夢〉じゃないか。
しかし、視点が違う?
――友達?
胸の奥に痛痒 。
通された部屋には彫刻刀が散乱し、あちこちに丸太が転がっている。どれもおそらく、桜だ。特有の匂いがこもっている。
「ひとり残された俺は座りションベンみてぇな恰好 でさ。みっともねぇザマの俺に、ヤツは言ったよ。坊やは何を見たのかな、ってな」
連慶は言葉を切り、私を誘うように見る。
解っていながら、まんまと、乗ってしまう。
「何を……見たのですか」
「そうそう。その声さ。ははは、おんなじだ」
予定調和の笑い。
「気色 悪ぃな。おんなじだよ。お前、あのときのヤツと同じくれェの歳だもんな。血ってやつァ怖いね。ビビっちまった俺は嘘をついたよ。何も見てませんってな」
――あの神社、夜中に明かりが点いてんだって。母ちゃんが隣のおばちゃんと話してたんだ。な、お化けかな。
――まさか。お化けなんかいないよ。
――母ちゃんが嘘つきだってのか。
――だって、お化けのわけないよ。
――じゃあ、確かめようぜ。そんでお化けだったら……お前、一人で逃げんなよ。
――そんなことしない。逃げるなら一緒だよ。
「見てませんとか言いながら、俺はヤツじゃなくて、ヤツが彫り出したアレから目が離せなかった」
相槌さえ打てなかった。
「蝋燭の火で、ぬめっと光ってたアレ。少し崩れてきてたけど女の形をしていた……ああ、そうだ。顔がおまえに似てた。なぁ、顔は母ちゃんで声は父ちゃんか。お前、うまいこと半分づつもらったもんだな。……それより」
連慶の弛んだ瞼が、ギュッと引き上がる。
「よくも一人で逃げやがったな」
膝に激しい痛みが走ると同時に、私は床に倒れた。連慶に蹴られたのだ。
「最初は〈お前〉だって判らなかった。電話んときも名前が違ったしな。何十年振りだ?」
「ぐっ」
運慶の下りではっきり分かったぜ――連慶は私の腹を踏みつけてくる。
――本当だって。すげぇそっくりに運慶が彫ったんだって、ありゃお前の、
――違うよ。それって課題図書で読んだ話じゃないか。あれは小説だよ。本当じゃない。もう僕の家の話はしないでくれよ!
記憶が蘇る。
――お前の母ちゃんは男と逃げた。
これを聞いたのは、そう、
――やめてよ。母さんはそんなことしないよ。
――じゃあ、俺の母ちゃんが嘘つきだってのか。
そうだ、あの噂を広げたのは……あの噂がきっかけで、神社の怪談話も手伝って……私を踏みつけているこいつが。
酒のせいだろう、青黒く浮腫んだ顔と焼けた声。目の形が分からないほど弛みきった瞼にボロボロの歯。同世代とさえ思わなかった。
まして、あの――あいつだったなんて、それこそ夢にも。
名前だって、連慶としか。
「奴は言った。僕はね、運慶なんだよ。ここの神主さんに頼まれて、ご神木からご神体を掘り出したんだ。ご覧、美しい女神さまだよ、ってな。子供捨てて逃げた女が、なァにが〈女神さま〉なもんか。だけど……真 に受けちまったんだ。そんだけ凄ぇ代物だったんだ、アレは」
真に受けなかったら、生きて帰れなかっただろうしなぁ――言いながら、連慶は私の腹を躙る。
「俺が見たのは〈女神さま〉だけだ。神主の野郎のことは、知らねぇ。少なくとも俺は見てねぇ」
ついに連慶は私の腹に腰を下ろし、額をぐっと押さえつける。
「よくも逃げてくれたよなぁ。俺、お前を信じてたんだぜ?」
連慶の体重が腹にかかる。
吐きそうだ。
「だけどまぁ、感謝してるさ。あのとき見たもんは、この目に焼き付いて離れやしねぇ。生き人形レベルなら俺にも何とか創れる。だが、アレは、あんなもんじゃねぇ。あんなもんじゃねぇんだ」
連慶は語る。
〈夢〉の話だ。それは私の――何故それを知っている。
「俺は運慶を夢見て精進してきたつもりなんだが、どうしても追いつけねぇ。名前で分かるだろ? あやかりたくて、でも痴 がましいからな、運慶のカンムリを取って連慶って名乗った」
有りがちか――と私に覆いかぶさるようにして、連慶は頬を歪める。
「だけどな、どんな木でも駄目なんだ。悔しいが、腕が足りなきゃ材料を良くしねぇとな。だから、ちっとばかしズルをしようと思っててねぇ」
額にあった連慶の手が角度を変え、目の上全部を覆ってきた。
「でもなぁ、誰をってなると、簡単にはやれねぇや。悶々としてたんだが、お前が現れて助かったよ。お前になら遠慮はいらねぇもんな」
「……痛い、は、な、してくれ」
腹に連慶の膝がめり込んでくる。
「お前の中の神さんは、俺が大事に祀ってやるよ。あのときの〈女神さま〉は、手に入れることが出来なかったからな。ははは、さっきのあれは嘘だ。見せるもんはねぇよ。まだ、な」
お前は裏切りもんだけど、これでお互い様だよなぁ――私の鼻先に、冷たく尖ったものがあてがわれた。
「最ッ高の材料が手に入ったぜ」
これで個展に間に合うな――もうとろけてはいないその声は、〈夢〉ではなかった。
「だって、俺の母ちゃんが言ってたもん」
噂は、級友の口から私の耳にも届く。
――やめてよ。母さんはそんなことしないよ。
――じゃあ、うちの母ちゃんが嘘つきだってのか。
現に、母はいなくなっていた。
父は何も言わなかった。
母と逃げたという男は、校区の外れにある神社の神主だった。その
ご神木は大きな桜だった。神主が去ったばかりの頃は青々と葉を茂らせていたのが、すぐに立ち枯れてしまった。
まるで、罰を引き受けたかのようだと囁かれた。
翌年の春、その枯れ木が倒れた。
その後、父も私を置いて姿を消した。
私は父方の祖父母を通して、遠縁に当たる子供のできない夫婦の養子となった。隣県の住人となり名字も変わり、様々なショックが重なったせいか、それまでのことは記憶から薄れていった。
しかし、私は〈夢〉を見るようになった。
繰り返し繰り返し見る〈夢〉。
夜。
朽ちた、簡素な社殿。
崩れた壁の隙間から漏れる、揺れる明かり。
正座した男の後ろ姿。衣服越しにも見て取れるほど、痩せた腕を振り上げては、降ろす。
連れて動く肩甲骨。
銀に閃く反射。
搾り出すような長い吐息。
ゴゾリと、長く大きく異様なもの転がった。
木だ。木の幹がふたつに割れたのだ。
枯れて――枯れた木の間から、何かが生まれでた。
「もう逃げられないね」
囁き、割れた木の間に頭を沈めていく。
私の喉がヒッと鳴った。
男の頭が跳ね上がり、こちらを向く。
私はその顔を知っていた。
見る前から、きっと。
明かりに背を向け、走った。
おい、と呼ばれたが振り返らずに走った。
私は、何度となく見るその夢に囚われていた。中年の域に差し掛かってもなお、いや、ますます酷くなっている。
囚われ、急き立てられ――あの割れた木の間から出てきたものが何なのか、確かめなければならない。
〈夢〉だ。
〈夢〉の話だ。
それでも……私はあれが何なのか知っているはずで、だから確かめるというよりは思い出すという方が、きっと正しいのだという、自分でもよく判らない焦燥感に追われていた。
あの社殿が何処なのかは判っている。
母と逃げた神主がいたという、あそこだ。
しかし、あの場所はとうに更地になり、今では大型スーパーの駐車場になっている。
三十年近くが過ぎているのだ。
それでも何かないかと、この辺りの地方紙を取り寄せたりしていた。
〈桜の木で神像を――今秋個展を開く
小さな見出しのその記事には、モノクロだが写真もあった。荒い画像だったが、乱れ髪の女性を形創っているということは分かった。
私の〈夢〉の記憶が疼いた。
記事の末尾にあったギャラリーに問い合わせ、連慶という彫刻師に連絡を付けることができた。
個展を待たず、半ば押しかけるようにして連慶を訪ねた。
電話でのやり取りで、彼がかなりの酒飲みであることを察した。手土産はいい日本酒を奮発した。口が軽くなることを期待する、下心もあった。
しかし、肝心の〈問いたいこと〉が何なのかは、言葉にすることができないままだ。
「新聞で作品を拝見して、
電話でも告げた通りのことを、繰り返すしかなかった。これでは、ただの作品のファンだ。そうではない、ということを私自身は知ってはいるのだが、どうすれば伝えることができるのか――。
連慶はしきりに瞼を擦りながら、最初恐縮したようにしていたが、酒が入るにつれ、態度や口調がぞんざいになっていった。
木で出来てんだ、その人形は――個展の準備の話をしていたはずが、いきなり連慶は話題を変えた。
「
知っている。
幕末から明治にかけて大いに流行った、木製の等身大の人形のことだ。生地に
今では芸術品扱いだが、元々は見世物興行に使われていたものだ。
これがなかなか――とんでもない代物で。どう見ても人形になど見えない精巧な作りのものが、極当たり前にあった。
マネキン人形にその技術は継承された
「有名所だと松本喜三郎や安本亀八なんだが、まぁ、そこまではいかなくても相当に腕のいい人形師が作ったものが、見世もんにごろごろしてた時代だったんだ」
連慶は残っていた酒を一気に
ここで口を挟むか、それとも様子をみるか。
激しく擦られた両の瞼は弛みきり、まともに開いてはいない。
よれた肉の隙間から、溶けた蝋のような白目と僅かばかりの黒目が覗いて――私を睨む。
連慶の、酒に濡れた唇が動いた。
「
どろりと腐りとろけた声が言う。
「日本一の、ど偉い天才の……なんだ、彫刻家だか」
「正確には仏師ですね」
つい、嫌味な言い方をしてしまった。
「ああ、そうそう。その運慶が言うには、仏像ってのは木を彫って形造るんじゃなくて、
「それは小説の話です」
呆れた。
「小説家の書いた作り事ですよ」
「運慶を知ってるんだろ」
「あなたが言っている運慶とは違います」
「どう違うんだぁ」
連慶の声音は、更にどろりと溶ける。
ああ、しまった。
「運慶は運慶だろうが。お前、職人なめんじゃねぇぞ」
怒らせてしまったか。
連慶は、まだ未練たらしく握っていた茶碗を、土間に叩きつける。使い込まれ古びていたそれは、乾いた音をたてて割れた。
ヘタを打った。
どうすればこの場が収まるか、考える。とりあえず謝る、か。いっそ怯えてみせるか。それとも――。
「運慶なんだよ。あのでかいスーパー。そこの駐車場ができる前は神社だったのさ。そこの御神木はでかい桜の木だった。それで神さんを彫り出したのはヤツだ」
「な、」
私は絶句する。
何だ、何だこれは。私はまだ何も、肝心なことは話していないのだ。前情報など何もないはずなのだ。
連慶の言い出したことは、突然すぎるし合致しすぎる。どろりとした声音と〈夢〉の光景が重なった。
「俺がまだ小さかった頃、潰れちまったんだ、あの神社は。そこのご神木をぶった切って、女神さまの像を創って
呑まれる。
「運慶はご神木の中の神様をそのまま彫り出すことができるんだ――俺はそう聞いた。小説なんかじゃねぇ。ちゃんと本人から聞いたんだ」
連慶は口元を手の甲で
「その運慶が、ご神木から彫り出したってェ神さんが、お前の聞きたい話だろ。違うか」
違うかって――違わない!
しかし、しかし!
「い、いや、運慶は現代の仏師ではないんです。ああ、もしかして、運慶を名乗る他の」
「違う。あれは本物の運慶だ。お前が何を言おうと、本物なんだ。よし、」
「教えてやる」
連慶は次の間の
「こんな話があった」
後ろ手で、連慶は襖を閉めた。
夜。
朽ちた、簡素な社殿。
崩れた壁の隙間から漏れる、揺れる明かり。
正座した男の後ろ姿。衣服越しにも見て取れるほど、痩せた腕を振り上げては、降ろす。
連れて動く肩甲骨。
銀に閃く反射。
搾り出すような長い吐息。
ゴゾリと、長く大きく異様なもの転がった。
木だ。木の幹がふたつに割れたのだ。
枯れて――枯れた木の間から、何かが生まれでた――。
「もう逃げられないね」
囁き、割れた木の間に頭を沈めていく。
隣りにいる友達の喉がヒッと鳴った。
男の頭が跳ね上がり、こちらを向く。
俺はその顔を知っていた。
見る前から、きっと。
友達が明かりに背を向け、走りだした。
おい、と呼んだが振り返らずに走っていった。
私は面食らう。
何を言っているんだ。
それは、私の〈夢〉じゃないか。
しかし、視点が違う?
――友達?
胸の奥に
通された部屋には彫刻刀が散乱し、あちこちに丸太が転がっている。どれもおそらく、桜だ。特有の匂いがこもっている。
「ひとり残された俺は座りションベンみてぇな
連慶は言葉を切り、私を誘うように見る。
解っていながら、まんまと、乗ってしまう。
「何を……見たのですか」
「そうそう。その声さ。ははは、おんなじだ」
予定調和の笑い。
「
――あの神社、夜中に明かりが点いてんだって。母ちゃんが隣のおばちゃんと話してたんだ。な、お化けかな。
――まさか。お化けなんかいないよ。
――母ちゃんが嘘つきだってのか。
――だって、お化けのわけないよ。
――じゃあ、確かめようぜ。そんでお化けだったら……お前、一人で逃げんなよ。
――そんなことしない。逃げるなら一緒だよ。
「見てませんとか言いながら、俺はヤツじゃなくて、ヤツが彫り出したアレから目が離せなかった」
相槌さえ打てなかった。
「蝋燭の火で、ぬめっと光ってたアレ。少し崩れてきてたけど女の形をしていた……ああ、そうだ。顔がおまえに似てた。なぁ、顔は母ちゃんで声は父ちゃんか。お前、うまいこと半分づつもらったもんだな。……それより」
連慶の弛んだ瞼が、ギュッと引き上がる。
「よくも一人で逃げやがったな」
膝に激しい痛みが走ると同時に、私は床に倒れた。連慶に蹴られたのだ。
「最初は〈お前〉だって判らなかった。電話んときも名前が違ったしな。何十年振りだ?」
「ぐっ」
運慶の下りではっきり分かったぜ――連慶は私の腹を踏みつけてくる。
――本当だって。すげぇそっくりに運慶が彫ったんだって、ありゃお前の、
――違うよ。それって課題図書で読んだ話じゃないか。あれは小説だよ。本当じゃない。もう僕の家の話はしないでくれよ!
記憶が蘇る。
――お前の母ちゃんは男と逃げた。
これを聞いたのは、そう、
――やめてよ。母さんはそんなことしないよ。
――じゃあ、俺の母ちゃんが嘘つきだってのか。
そうだ、あの噂を広げたのは……あの噂がきっかけで、神社の怪談話も手伝って……私を踏みつけているこいつが。
酒のせいだろう、青黒く浮腫んだ顔と焼けた声。目の形が分からないほど弛みきった瞼にボロボロの歯。同世代とさえ思わなかった。
まして、あの――あいつだったなんて、それこそ夢にも。
名前だって、連慶としか。
「奴は言った。僕はね、運慶なんだよ。ここの神主さんに頼まれて、ご神木からご神体を掘り出したんだ。ご覧、美しい女神さまだよ、ってな。子供捨てて逃げた女が、なァにが〈女神さま〉なもんか。だけど……
真に受けなかったら、生きて帰れなかっただろうしなぁ――言いながら、連慶は私の腹を躙る。
「俺が見たのは〈女神さま〉だけだ。神主の野郎のことは、知らねぇ。少なくとも俺は見てねぇ」
ついに連慶は私の腹に腰を下ろし、額をぐっと押さえつける。
「よくも逃げてくれたよなぁ。俺、お前を信じてたんだぜ?」
連慶の体重が腹にかかる。
吐きそうだ。
「だけどまぁ、感謝してるさ。あのとき見たもんは、この目に焼き付いて離れやしねぇ。生き人形レベルなら俺にも何とか創れる。だが、アレは、あんなもんじゃねぇ。あんなもんじゃねぇんだ」
連慶は語る。
〈夢〉の話だ。それは私の――何故それを知っている。
「俺は運慶を夢見て精進してきたつもりなんだが、どうしても追いつけねぇ。名前で分かるだろ? あやかりたくて、でも
有りがちか――と私に覆いかぶさるようにして、連慶は頬を歪める。
「だけどな、どんな木でも駄目なんだ。悔しいが、腕が足りなきゃ材料を良くしねぇとな。だから、ちっとばかしズルをしようと思っててねぇ」
額にあった連慶の手が角度を変え、目の上全部を覆ってきた。
「でもなぁ、誰をってなると、簡単にはやれねぇや。悶々としてたんだが、お前が現れて助かったよ。お前になら遠慮はいらねぇもんな」
「……痛い、は、な、してくれ」
腹に連慶の膝がめり込んでくる。
「お前の中の神さんは、俺が大事に祀ってやるよ。あのときの〈女神さま〉は、手に入れることが出来なかったからな。ははは、さっきのあれは嘘だ。見せるもんはねぇよ。まだ、な」
お前は裏切りもんだけど、これでお互い様だよなぁ――私の鼻先に、冷たく尖ったものがあてがわれた。
「最ッ高の材料が手に入ったぜ」
これで個展に間に合うな――もうとろけてはいないその声は、〈夢〉ではなかった。