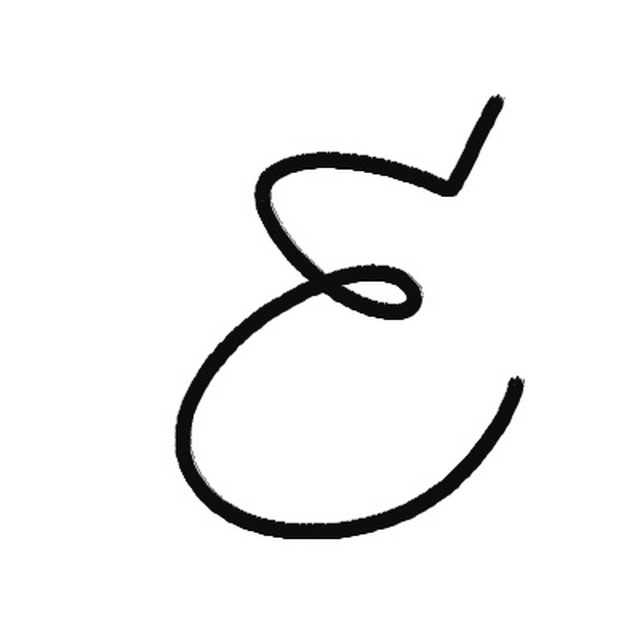第1話
文字数 8,749文字
「街ゆく爆弾魔」
永見妙
前書き
「爆破する」という単語は、爆弾だけに使われていいようなちんけで安っぽい言葉ではないと思う。何を「爆破」したいかは人それぞれであろうが、簡単でない「爆破」をこなした時、人は「生まれ変われる」と信じている。
死んだ目をして、青年は薄暗い街を歩いていた。街灯が街ゆく青年を照らしているが、流れゆく地面を写す、その勾玉のような眼には、正気は宿っていない。
ああ。誰も彼もみな、僕のことを見ていない。通り過ぎた奴らは僕のことを見向きもしないのだ。
歩いて革靴をコツコツと鳴らす。側の家からは、一家団欒の楽しげな声が聞こえる。青年はそんな家をよそ目に、小汚い路地裏へと入っていった。自宅までの帰路というわけでも、はたまた路地裏のゴミ箱を漁るわけというわけでもない。ただ目的もなく彷徨しているのだ。建物と建物の間からは、真ん丸の月が高く青年を覗いている。
不意にすぐ脇の階段に目が行った。どうやら非常階段らしい。何を思ってか、青年は階段を登り始めた。少しの間登ると、建物の屋上に辿り着いた。そこまでの高さのある建物ではないため、見晴らしは良くない。しかし、人が死ぬには十分な高さであった。青年は錆びた鉄柵に寄りかかり、ポケットから紙煙草とライターを取り出す。煙草にライターで火を付けると、目一杯吸い込み、脳を煙で充満させようとする。
忽ち青年は煙を吐いた。煙を吐いたと言うより、煙が逆流したという表現の方が正しい。実を言うと、青年は煙草を吸うのが初めてで、その煙を喉と肺が拒絶したのだ。自身が煙草を吸えないことがわかると、青年はもう一吸いもせずに吸い殻をそこらへ投げ捨てた。
青年は一息入れて新鮮な夜の空気を吸い込み、呼吸を整える。思考を虚ろに、体を軟体にしてゆく。建物の隙間から流れてくる夜風が頬にあたり、気持ちが良かった。体が空中を漂っているかのような、妙な浮遊感に襲われる。
こんなものなのか。だが、これはこれで良い。
静かに覚悟を決める。屋上に備え付けてある落下防止用の柵を跨ぎ越えると、数十センチ、自分の靴が収まるギリギリの幅に立った。下には歩道に街路樹、さらに二車線道路が見える。数人、歩行者がいるが、青年には気づかない。こうも見られないと、自分は実体を持たない気体なのかとさえ感じる。
もう一度、息を吸う。今度こそ爆破できるように。
一歩。歩み出すように、右足を前に出した。だが、結局今日もやれなかった。
窓から柔らかい朝日が頬にあたり、青年は目を覚ました。体を起こし、時計を確認すると、時計は六時を指している。普段は八時に目覚ましで起きるのだが、今日は自然と陽光で目が覚めた。今思うと、この時からすでに、この日が人生の転換期ならぬ、転換日であったことを暗に示していたのかもしれない。いつもなら二度寝をするところだが、その日は珍しくそのまま身支度を始めた。朝食を済ませ、歯を磨き、持ち物を確認すると、青年は大学へと歩き出す。
青年が住んでいるのは、やや古めかしい六畳間のアパートで、大学までは徒歩十分圏内に位置している。この部屋は扉の建て付けが悪く、閉める時はいつも大きな音を立てる。青年はそっと扉を閉め、鍵をかけてから、その足で大学へ向かう。時間を除いて、扉を閉めるまでの工程全てが恐ろしいまでにいつも通りであった。
午前六時の街は、陽の光に輝き、風に吹かれた木々たちが、楽しそうに揺れている。落ちた木の葉までもが踊っているようだ。これが世間一般で言うところの、心地の良い、清々しい朝だろう。
アパートの廊下を抜け、太陽の眩しさを体感すると、青年は下を向いて歩き出した。青年は外出時、きまって耳にイヤフォンをつけていた。日中常にイヤフォンを持ち歩き、暇さえあればその世界に逃げ浸りたいと考えていた。
大学へ着くと、何かから追われているわけでもないのに、逃げるように教室を目指す。今日の講義は、なんの面白みもなく、なんの実用性もない哲学概論だ。本が好きな青年は文学部に所属していた。多くの授業では何かしらの作品を読んでいるが、全てがそうなわけではない。時にはこのような取るに足らない授業も受けなくてはならないのだ。誰もいない教室の扉を開き、最後尾、角の席につくと、本を取り出す。東向きの窓からは、白い陽光が教室全体を照らしていた。
オスカーワイルド。
青年は静かな教室で読み始めた。
何度読んだって美しい。
透き通った空間に、透き通った時間。青年はすらすらと文章に目を通してゆく。
このまま、時が永遠に止まって仕舞え。あるいは僕が。
目を閉じて天井を仰ぐと、青年は毎朝こうだったらと切に願う。人を避けて教室の目立たない席を探す、騒がしく悲しい普段の朝とは大違いだった。周りが見えぬよう、そして周りが見ぬように這い回る必要のない朝。そんな中、オスカーワイルドを読む。青年は鋭く洗練されて、神秘的とさえ言える時間にただただ満足していた。
今なら爆破したって構わないのに。
青年が悦に浸っていたのも束の間、教室の透明は突如として失われた。教室の扉が開いたのだ。青年は反射的に扉の方、ではなく自身の机を見た。その行動には、青年の神秘の露呈に対する恥じらいと牙の抜け落ちた怒りとが見てとれた。誰が入ってきたかは確認せず、目線を下げたまま一呼吸入れる。ほんの十秒としないうちに昂りとも呼べないものは収まり、それと入れ替わるように疑問が湧いてきた。
なぜこんな早い時間に教室へ来たんだ。授業開始は九時で、今は六時半。なんとなく早く来た僕が言えたことではないが、あまりにも不自然じゃないか。
湧いてきた疑問が解決しないことは理解していたが、青年は無意識に何者かを横目に見る。同じく教室の最後尾、青年とは反対側の角に座っていたのは、青年と同様に哲学概論を受講している文学部の女子生徒だった。少人数な授業であったため、顔には見覚えがあったが、当然名前は知らなかった。音もなく歩みを進め、その長く綺麗な黒髪を靡かせながら席へ着く。黒縁の眼鏡をかけた彼女は、こちらを気に掛けることこともなくただ机の上で小説を開いた。
席について程なく、彼女は椅子を引いて、立ち上がった。青年は再び机を見ることになったが、目の端では彼女を捉えている。彼女は立ち上がると、机と机の合間を縫って徐々にこちらへ近づいてくる。疑問に思っていると、青年の隣まで来て、彼女はようやく口を開いた。
「すみません。このあたりに薄青色の栞、落ちていませんでしたか?」
「いえ、申し訳ないですけど、見ていません」
ある程度近づいてきた地点で話かけられる予想はついていたので、静かに返す。
「落としたのはいつ頃なんですか」
「二、三日前です」
「それなら、用務員が気付いて拾った可能性もあるかもしれないですね。もう事務室へは行ったんですか?」
「いいえ。なるほど、事務室ですか。そこは盲点でした。あとで行ってみます。ありがとうございました」
そう言って席に戻ろうとした彼女だったが、ふと机の上に置いてあった本の表紙に目がいき、ぼそりとつぶやいた。
「オスカーワイルド」
心臓が五月蝿かった。
「え?」
「あ、いえ、すみません。オスカーワイルドの文字が見えたもので。好きなんですか? ワイルド」
彼女は表情一つ変えずに尋ねるが、青年は動揺している様子であった。
「いえまあ、そうですね、はい」
「そうなんですか。私もワイルド、好きなんです」
青年の眼が微かに煌めいた。
「『幸福の王子』とかとても素敵なお話ですもんね」
「確かにあの銅像の自己犠牲は、僕も素敵だと思いますよ」
口先ばかりで実際に行動には移さないものの比喩という解釈もあるが。
青年は目線を少し逸らし、心の中でそうつぶやく。
そう、あの銅像についてとなると誰だって、自分の体を犠牲にしてでも街の人の幸せを願う優しい銅像と言うし、あの燕についてとなると誰だって、そばで健気に手伝うこれまたなんと優しい燕と言うのだ。その裏に皮肉が隠れているとも知らずに。
「実は私はそこまで、あのお話が好きというわけではないんですけどね」
彼女は右手で左耳にその長い髪をかけ、微笑みながら言う。
「どうしてなんですか?」
何か勘ぐったわけではなく、ただ会話の一環として尋ねた。それなのに、いや、それだからこそ、それは大きな一打であり、胸を裂くような衝撃となった。
「だって、まるで皮肉みたいだなって思いません? 動けないのに人々を幸せにしたいって銅像は口先ばかりだし、燕だって頼まれたから手伝うだけで結局のところ言われたことをやるだけの考えなしじゃないですか」
青年は過去を思い出していた。
翌日も昨日と同様、春風の心地良い朝だった。起床時間、身支度、扉の立て付けの悪さ、通学路、全てが昨日通りであったが、彼の心境だけは違った。講義が終わると、彼は定位置を目指す。中庭の端のベンチは、大きなイチョウと隣接する高い建物の構造上、日中ほぼ影で覆われている。涼しげな昼下がり、青年は昨日の女子生徒について考えていた。考えている、と表現しては、いかにも恋焦がれている風だが、青年は自身が恋などをできる人間ではないことを強く自覚している。彼女に対し、恋心を抱いているわけでない。がしかし、特別な感情が湧き、彼女が思考に割り込んでくるのだった。
原因については考えるまでもなく明白だった。彼女の一言をきいて思い出したあの夏。青年が見ているのは眼鏡の女子生徒ではなく、その影に見える
ああ、またなのか。
青年はベンチに身を預けて空を見上げる。羊雲が流れる今日の空はやけに高く見えた。青年はあの子のことを思い出すことにした。
高校生になった春、青年はクラスに馴染めずにいた。人と話すのが苦手だったわけでも、周りの人が自分よりも劣っているという尖った思想を持っていたわけでもない。ただあるべくして一人だった。誰だって青年のことを見ないし、青年だって誰も見ない。それに対して悲観はしていなかったし、それでよかった。しかし、一人で完結していた青年の世界に、あの子はノックもなしに入ってきた。
放課後、教室で頭を空っぽにオスカーワイルドを読んでいた時、彼女は突然話かけてきた。
「君、いつも本読んでるね。本好きなの?」
青年の言葉に詰まったが、なんとか捻り出す。その心臓は五月蝿いほどに大きかった。
「うん」
「オスカーワイルド? 知らないけど、有名な人なの?」
「まあそれなりには」
「へー、そうなんだ」
あの子は黙ってじっと表紙を見ている。
「何か用事?」
間に耐えられなかった青年の口から本音がこぼれた。
「いいや、特に。強いて言うなら、君に話かけることが用事かな」
微笑みながら言うあの子の真意が汲み取れない青年には、返す言葉が見つからなかった。見兼ねたあの子が続けて言う。
「君っていつも一人でいるよね。嫌われているってわけでもなさそうだし、なにか理由でもあるの?」
「理由なんかないよ。ただ人と話すよりも本を読むことのほうが好きで楽しいってだけだ」
青年はあの子の方を見ることができず、仕方なく机へと視線を落とす。あの子はその視線に入り込もうと、青年の正面へ回り込むと、机に向かってしゃがみ込んだ。
「じゃあ私と話すのは楽しいかな?」
あの子の薄く伸びた目が青年を覗き込むと、青年の逃げ場は消えてしまうのだった。
青年の思い出はいつもここで止まる。これが青年とあの子の出会いだった。今振り返ってみてもやはり、あの子のことを女性として意識してはいない。これは今も当時も変わらなかった。
しかし、それならなぜ覚えているのだろうと疑問が頭の中を巡る。何か思うところがあるから覚えている。青年はそんな気がしなくもないが、物珍しいただの思い出で、それ以上でも以下でもないのだといつも通り割り切った。そんなことより今はなぜ眼鏡の女子生徒があの子を思い出すのかをそちらの方を考えることにした。
そもそも彼女とあの子の間には共通点はない。僕の知っている限りにおいてだが、彼女は教室の隅でいつも本を読んでいるが、あの子はそうではなかった。きっとあの子が読んだのはあの本が最初で最後なのだろう。それに性格だって違う気がする。彼女のことにそこまで詳しいわけではないが、服装や話し方、髪型までもが違う。静かでどこか上品さを纏う雰囲気はいかにもな文学少女といった感じだ。その点、あの子はというと、元気すぎるほどで、天真爛漫を形にしたような少女だった。お喋り好きで、いつも誰かに囲まれている。そんな子だった。感心させられるほどに、二人は異なっている。
いくら分析を重ねても、結論は見えてこなかった。これも今も昔と一緒だった。
一週間後、また哲学の講義があった。この日は青年にとってはいつもと同じだった。この日が来る頃には、あの衝撃は二、三日もしないうちにすっかり頭から抜け落ちていて、眼鏡の女子生徒などもうどうでもよかった。
そもそも、青年が一方的に名前もわからない彼女に対して名前もわからない特別な感情を抱いていただけで、何か劇的な出来事が起きたわけではないのだから、至極当然のことだった。青年はそれを痛いほどに理解していた。
僕の周りで特別なことなど何も起きてはいない。人生は悲劇的なまでに非劇的なのだ。これじゃあ、あまりにも心無い。相談の相には心が無いとはよく言ったものだが、ここでもやはり心が無いようだ。それとも心が無いのは僕の方なのだろうか。あの子がいなくなってから、僕は空っぽになってしまった。いやあるいは、心奪われたと言った方が正しいのかもしれない。笑顔だとか涙だとか、憂鬱でさえも、あの頃から僕のものではなくて、まるで誰かから取ってつけたように思われてならないのだから。
青年はいつも通り角の席に座って、静かに教授の話を聞いていた。いつも通り、つまらなかった。不幸なことに、今日の授業では教授がグループを組むように指示をした。いわゆるグループディスカッションというやつだ。話すことを強制される悪しき風習に、青年は始まる前から嫌気が差していた。周囲の人が席を動かし始めてからようやく、青年もそれを真似る。
嫌なこととは往々にして重なるものだ。青年はその不幸にすぐに気がついた。机ごと振り向いた前の人物が、一週間前、栞の場所を訪ねてきた女子生徒だったのだ。
これは青年のとって紛れも無い不幸であった。得体のしれない何かに身構える必要があったからだ。
彼女と青年の間に会話はなかった。もしかしたら彼女は先週自分が話しかけたことを忘れているのではないかと感じるほどに、彼女は無機質で淡白だった。グループは出された議題について静かに話し合あう。
たった数十分の間、話し合うだけでディスカッションは終わった。しかし、何事もなくは終わらなかった。
青年はものの数十分で彼女に気を取られていた。他でもない彼女に。それは彼女が髪を耳にかけるような仕草をした時だった。どうやら彼女の癖のようで、頻繁に右手で左耳にかけていることに青年は気がついた。これはなんの変哲もない、ただの他人の癖であるし、実際青年から見れば、彼女はただの赤の他人と言って差し支えない。しかし青年とっては、彼にとっては、その赤の他人の仕草がとても重大なものだった。
あの子と全く同じなのだ。それはあの子の仕草で、あの子の癖なのだ。
ディスカッションが終わる頃には、青年はそれどころではなかった。青年は気が気でならなくて、目線も思考も全て彼女に吸い寄せられていた。
授業が終わると、彼女はグループに軽く礼を言って、風のように去った。彼女が教室を出るその一瞬まで、彼女に意識を注いでいた。
青年は心を放ったように固まって椅子に座っていた。その石化が解けるまではかなりの時間を要した。
今度も劇的なことは何一つ起きてはいなかった。しかし、青年には大きな一打であったのだ。
教室を出て、歩いて自宅へ帰る。そのわずかな時間でさえも、あの子のことを考えながら。体が、頭が、石になったかのように重かった。青年は体をベッドへ放り投げると、瞬きする間もなく眠ってしまった。
青年は夢を見ていた。
遠い夏。電車で二駅の隣町。石畳に並ぶ屋台。鈴虫の鳴き声。薄桜色の唇と浴衣、赤い花飾り。
夜空には大きな花が咲いた。振り向き笑う君も花みたいだった。頬にあたる風が生温かくて、妙に夜空が高かった。
どれも鮮明だ。まるでこの世界の彩度が何十倍にもあがったみたいに、全てが色鮮やかに彩られていた。
「先に行くね。待ってる」
あの子がそう言った。夢の中のあの子が僕に語りかけたのはこれが初めてだ。記憶にはないもので、僕の脳みそが作り上げたものに違いはなかった。それでも、僕は泣かずにはいられなかった。
僕からではなかった。最初で最後だった。
夢が終わる最後まで僕は泣いていた。
翌日は、まるで犬と猫が喧嘩しているみたいに土砂降りだった。
外は真っ暗だった。およそ午前四、五時であろうか。青年は重い体を持ち上げて、時刻を確認しようとする。小さな目覚まし時計に反射した自分を見て、初めて自分の頬に涙が流れていることに気がついた。
その事実に気づいた途端、腹の奥の方からえも言われぬ激情が押し寄せてきた。
なぜ泣いているのだろう。これはなん涙なのだろう。
傍には泣いていることに驚いた自分もいた。青年は暗い部屋の中、うずくまって嗚咽を吐くことしかできなかった。
心の水面が凪ぐまでには、しばらくかかった。今までにない経験だった。言葉にできない、という表現はよく聞くが、その多くが感情を言葉にするというプロセスが不可能なだけで、心は感情を曖昧にも捉え、評価しているものだ。しかし、青年にはそれすらもできていなかった。自分の中に押し寄せるものが何であるのか、どんな影響を与えるのかも、彼の心は理解できないのだった。ただ濁流のごとく激しく溢れでるのだった。
青年は夜が明ける前に、街へ出た。今度は体が変に軽い。頭の中はやはり空っぽだった。いや、正確には、頭の中はあの子のことで一杯であり、脳の隅まで一杯だからこそそれは何もないと同義だった。
ああ、あの子は何をしているのだろう。どうしていってしまったのだろう。
歩いて、歩いて、青年は気がつくと母校に辿り着いた。青年が合格した大学は家の近くではあったが、無理を言って一人暮らしを始めたのだった。今を振り返ってみると、少しでも離れて忘れてしまいたかったのかもしれない、と青年は感じた。もちろん、電気は一つも点いておらず、ただひっそりと立ち尽くしていた。
あの時と何も変わらなかった。あの子と出会ったのも、あの子と別れたのも、あの子と別れようとしたのも、全てこの場所だった。当然入ることはできないため、外から自分の教室を眺めていた。
今なら、今なら今度こそ。
決意した青年は校門を乗り越える。グラウンドを横切り、校舎脇の階段を登り始めた。屋上を目指し、パイプと出っ張りを駆使してなんとか登る。途中何度か足を滑らせかけて、肝を冷やしたし、その度に決意が揺らいだ。そもそも今自分が行なっているのは、犯罪以外の何物でもない。しかし、これからやることを考慮したら、これくらい怯えずにできるほどの胆力は必要だった。青年は屋上へ登り切ると、狭い幅に立った。屋上のフェンスはあまりに高くて登れたものではないが、その心配は必要なかった。
屋上はやはり高かった。下を覗くと、本能が足をすくませる。
屋上が思ったよりもずっと高いのも、足がすくむこの感覚も、遠くに見える建物が思いの外小さいのも、全てあの時と一緒だった。
僕の体を爆破する。思い出と共に。そう、僕の体は思い出でできているんだ。だから、思い出を、人生を、爆破するんだ。
あの時のショックは大きかった。クラスの担任になんの前触れもなく告げられた。外に興味のない僕の耳が無意識に捉え、そして頭に伝達したのは、彼女がここ最近学校を休みがちであったこと、その持病がありふれた病気であり、悪化の一途を辿っていたことだった。
大きなショックであった。しかし、それは文字通りの衝撃を意味しており、悲しみとか辛さとかを伴うものじゃなかった。ただ、わからなかった。やはりというべきなのだろうか。わからないことが多くなって、収拾のつかない青年だけが取り残された。
わからない、の次に青年が感じたのは、不条理だとか卑怯だとかだった。
あの子は、僕にしこりを残していなくなったのだ。自分でも解決できないしこりを。手も足もでなくて、唯一解決できるとしたら君だと思った。
だから、もう解決はできない。
涙が流れ始めた。
僕は…僕はもう一度、君に会いたい。
まだ聞いていないんだ。あの銅像を、燕を、あの物語をどう感じたか。君は僕のために読んでくれた。だから、聞かなくちゃ。きっと君なら、素敵な話だねって言うのだろう。それでいい。それでもいいから、君の話を聞かせてくれ。
陽が登ってきた。あたりは朝焼けで曙色に染まってゆく。涼しげな朝風が青年の頬を掠めた。
青年は再度覚悟を決めた。緩やかに、確かに。目の前には大きな花火が散った。
永見妙
前書き
「爆破する」という単語は、爆弾だけに使われていいようなちんけで安っぽい言葉ではないと思う。何を「爆破」したいかは人それぞれであろうが、簡単でない「爆破」をこなした時、人は「生まれ変われる」と信じている。
死んだ目をして、青年は薄暗い街を歩いていた。街灯が街ゆく青年を照らしているが、流れゆく地面を写す、その勾玉のような眼には、正気は宿っていない。
ああ。誰も彼もみな、僕のことを見ていない。通り過ぎた奴らは僕のことを見向きもしないのだ。
歩いて革靴をコツコツと鳴らす。側の家からは、一家団欒の楽しげな声が聞こえる。青年はそんな家をよそ目に、小汚い路地裏へと入っていった。自宅までの帰路というわけでも、はたまた路地裏のゴミ箱を漁るわけというわけでもない。ただ目的もなく彷徨しているのだ。建物と建物の間からは、真ん丸の月が高く青年を覗いている。
不意にすぐ脇の階段に目が行った。どうやら非常階段らしい。何を思ってか、青年は階段を登り始めた。少しの間登ると、建物の屋上に辿り着いた。そこまでの高さのある建物ではないため、見晴らしは良くない。しかし、人が死ぬには十分な高さであった。青年は錆びた鉄柵に寄りかかり、ポケットから紙煙草とライターを取り出す。煙草にライターで火を付けると、目一杯吸い込み、脳を煙で充満させようとする。
忽ち青年は煙を吐いた。煙を吐いたと言うより、煙が逆流したという表現の方が正しい。実を言うと、青年は煙草を吸うのが初めてで、その煙を喉と肺が拒絶したのだ。自身が煙草を吸えないことがわかると、青年はもう一吸いもせずに吸い殻をそこらへ投げ捨てた。
青年は一息入れて新鮮な夜の空気を吸い込み、呼吸を整える。思考を虚ろに、体を軟体にしてゆく。建物の隙間から流れてくる夜風が頬にあたり、気持ちが良かった。体が空中を漂っているかのような、妙な浮遊感に襲われる。
こんなものなのか。だが、これはこれで良い。
静かに覚悟を決める。屋上に備え付けてある落下防止用の柵を跨ぎ越えると、数十センチ、自分の靴が収まるギリギリの幅に立った。下には歩道に街路樹、さらに二車線道路が見える。数人、歩行者がいるが、青年には気づかない。こうも見られないと、自分は実体を持たない気体なのかとさえ感じる。
もう一度、息を吸う。今度こそ爆破できるように。
一歩。歩み出すように、右足を前に出した。だが、結局今日もやれなかった。
窓から柔らかい朝日が頬にあたり、青年は目を覚ました。体を起こし、時計を確認すると、時計は六時を指している。普段は八時に目覚ましで起きるのだが、今日は自然と陽光で目が覚めた。今思うと、この時からすでに、この日が人生の転換期ならぬ、転換日であったことを暗に示していたのかもしれない。いつもなら二度寝をするところだが、その日は珍しくそのまま身支度を始めた。朝食を済ませ、歯を磨き、持ち物を確認すると、青年は大学へと歩き出す。
青年が住んでいるのは、やや古めかしい六畳間のアパートで、大学までは徒歩十分圏内に位置している。この部屋は扉の建て付けが悪く、閉める時はいつも大きな音を立てる。青年はそっと扉を閉め、鍵をかけてから、その足で大学へ向かう。時間を除いて、扉を閉めるまでの工程全てが恐ろしいまでにいつも通りであった。
午前六時の街は、陽の光に輝き、風に吹かれた木々たちが、楽しそうに揺れている。落ちた木の葉までもが踊っているようだ。これが世間一般で言うところの、心地の良い、清々しい朝だろう。
アパートの廊下を抜け、太陽の眩しさを体感すると、青年は下を向いて歩き出した。青年は外出時、きまって耳にイヤフォンをつけていた。日中常にイヤフォンを持ち歩き、暇さえあればその世界に逃げ浸りたいと考えていた。
大学へ着くと、何かから追われているわけでもないのに、逃げるように教室を目指す。今日の講義は、なんの面白みもなく、なんの実用性もない哲学概論だ。本が好きな青年は文学部に所属していた。多くの授業では何かしらの作品を読んでいるが、全てがそうなわけではない。時にはこのような取るに足らない授業も受けなくてはならないのだ。誰もいない教室の扉を開き、最後尾、角の席につくと、本を取り出す。東向きの窓からは、白い陽光が教室全体を照らしていた。
オスカーワイルド。
青年は静かな教室で読み始めた。
何度読んだって美しい。
透き通った空間に、透き通った時間。青年はすらすらと文章に目を通してゆく。
このまま、時が永遠に止まって仕舞え。あるいは僕が。
目を閉じて天井を仰ぐと、青年は毎朝こうだったらと切に願う。人を避けて教室の目立たない席を探す、騒がしく悲しい普段の朝とは大違いだった。周りが見えぬよう、そして周りが見ぬように這い回る必要のない朝。そんな中、オスカーワイルドを読む。青年は鋭く洗練されて、神秘的とさえ言える時間にただただ満足していた。
今なら爆破したって構わないのに。
青年が悦に浸っていたのも束の間、教室の透明は突如として失われた。教室の扉が開いたのだ。青年は反射的に扉の方、ではなく自身の机を見た。その行動には、青年の神秘の露呈に対する恥じらいと牙の抜け落ちた怒りとが見てとれた。誰が入ってきたかは確認せず、目線を下げたまま一呼吸入れる。ほんの十秒としないうちに昂りとも呼べないものは収まり、それと入れ替わるように疑問が湧いてきた。
なぜこんな早い時間に教室へ来たんだ。授業開始は九時で、今は六時半。なんとなく早く来た僕が言えたことではないが、あまりにも不自然じゃないか。
湧いてきた疑問が解決しないことは理解していたが、青年は無意識に何者かを横目に見る。同じく教室の最後尾、青年とは反対側の角に座っていたのは、青年と同様に哲学概論を受講している文学部の女子生徒だった。少人数な授業であったため、顔には見覚えがあったが、当然名前は知らなかった。音もなく歩みを進め、その長く綺麗な黒髪を靡かせながら席へ着く。黒縁の眼鏡をかけた彼女は、こちらを気に掛けることこともなくただ机の上で小説を開いた。
席について程なく、彼女は椅子を引いて、立ち上がった。青年は再び机を見ることになったが、目の端では彼女を捉えている。彼女は立ち上がると、机と机の合間を縫って徐々にこちらへ近づいてくる。疑問に思っていると、青年の隣まで来て、彼女はようやく口を開いた。
「すみません。このあたりに薄青色の栞、落ちていませんでしたか?」
「いえ、申し訳ないですけど、見ていません」
ある程度近づいてきた地点で話かけられる予想はついていたので、静かに返す。
「落としたのはいつ頃なんですか」
「二、三日前です」
「それなら、用務員が気付いて拾った可能性もあるかもしれないですね。もう事務室へは行ったんですか?」
「いいえ。なるほど、事務室ですか。そこは盲点でした。あとで行ってみます。ありがとうございました」
そう言って席に戻ろうとした彼女だったが、ふと机の上に置いてあった本の表紙に目がいき、ぼそりとつぶやいた。
「オスカーワイルド」
心臓が五月蝿かった。
「え?」
「あ、いえ、すみません。オスカーワイルドの文字が見えたもので。好きなんですか? ワイルド」
彼女は表情一つ変えずに尋ねるが、青年は動揺している様子であった。
「いえまあ、そうですね、はい」
「そうなんですか。私もワイルド、好きなんです」
青年の眼が微かに煌めいた。
「『幸福の王子』とかとても素敵なお話ですもんね」
「確かにあの銅像の自己犠牲は、僕も素敵だと思いますよ」
口先ばかりで実際に行動には移さないものの比喩という解釈もあるが。
青年は目線を少し逸らし、心の中でそうつぶやく。
そう、あの銅像についてとなると誰だって、自分の体を犠牲にしてでも街の人の幸せを願う優しい銅像と言うし、あの燕についてとなると誰だって、そばで健気に手伝うこれまたなんと優しい燕と言うのだ。その裏に皮肉が隠れているとも知らずに。
「実は私はそこまで、あのお話が好きというわけではないんですけどね」
彼女は右手で左耳にその長い髪をかけ、微笑みながら言う。
「どうしてなんですか?」
何か勘ぐったわけではなく、ただ会話の一環として尋ねた。それなのに、いや、それだからこそ、それは大きな一打であり、胸を裂くような衝撃となった。
「だって、まるで皮肉みたいだなって思いません? 動けないのに人々を幸せにしたいって銅像は口先ばかりだし、燕だって頼まれたから手伝うだけで結局のところ言われたことをやるだけの考えなしじゃないですか」
青年は過去を思い出していた。
翌日も昨日と同様、春風の心地良い朝だった。起床時間、身支度、扉の立て付けの悪さ、通学路、全てが昨日通りであったが、彼の心境だけは違った。講義が終わると、彼は定位置を目指す。中庭の端のベンチは、大きなイチョウと隣接する高い建物の構造上、日中ほぼ影で覆われている。涼しげな昼下がり、青年は昨日の女子生徒について考えていた。考えている、と表現しては、いかにも恋焦がれている風だが、青年は自身が恋などをできる人間ではないことを強く自覚している。彼女に対し、恋心を抱いているわけでない。がしかし、特別な感情が湧き、彼女が思考に割り込んでくるのだった。
原因については考えるまでもなく明白だった。彼女の一言をきいて思い出したあの夏。青年が見ているのは眼鏡の女子生徒ではなく、その影に見える
あの子
なのだ。正確には青年は彼女を通して見えるあの子が気がかりなのだ。いつ何時だってあの子が青年の頭の裏側にいる。ああ、またなのか。
青年はベンチに身を預けて空を見上げる。羊雲が流れる今日の空はやけに高く見えた。青年はあの子のことを思い出すことにした。
高校生になった春、青年はクラスに馴染めずにいた。人と話すのが苦手だったわけでも、周りの人が自分よりも劣っているという尖った思想を持っていたわけでもない。ただあるべくして一人だった。誰だって青年のことを見ないし、青年だって誰も見ない。それに対して悲観はしていなかったし、それでよかった。しかし、一人で完結していた青年の世界に、あの子はノックもなしに入ってきた。
放課後、教室で頭を空っぽにオスカーワイルドを読んでいた時、彼女は突然話かけてきた。
「君、いつも本読んでるね。本好きなの?」
青年の言葉に詰まったが、なんとか捻り出す。その心臓は五月蝿いほどに大きかった。
「うん」
「オスカーワイルド? 知らないけど、有名な人なの?」
「まあそれなりには」
「へー、そうなんだ」
あの子は黙ってじっと表紙を見ている。
「何か用事?」
間に耐えられなかった青年の口から本音がこぼれた。
「いいや、特に。強いて言うなら、君に話かけることが用事かな」
微笑みながら言うあの子の真意が汲み取れない青年には、返す言葉が見つからなかった。見兼ねたあの子が続けて言う。
「君っていつも一人でいるよね。嫌われているってわけでもなさそうだし、なにか理由でもあるの?」
「理由なんかないよ。ただ人と話すよりも本を読むことのほうが好きで楽しいってだけだ」
青年はあの子の方を見ることができず、仕方なく机へと視線を落とす。あの子はその視線に入り込もうと、青年の正面へ回り込むと、机に向かってしゃがみ込んだ。
「じゃあ私と話すのは楽しいかな?」
あの子の薄く伸びた目が青年を覗き込むと、青年の逃げ場は消えてしまうのだった。
青年の思い出はいつもここで止まる。これが青年とあの子の出会いだった。今振り返ってみてもやはり、あの子のことを女性として意識してはいない。これは今も当時も変わらなかった。
しかし、それならなぜ覚えているのだろうと疑問が頭の中を巡る。何か思うところがあるから覚えている。青年はそんな気がしなくもないが、物珍しいただの思い出で、それ以上でも以下でもないのだといつも通り割り切った。そんなことより今はなぜ眼鏡の女子生徒があの子を思い出すのかをそちらの方を考えることにした。
そもそも彼女とあの子の間には共通点はない。僕の知っている限りにおいてだが、彼女は教室の隅でいつも本を読んでいるが、あの子はそうではなかった。きっとあの子が読んだのはあの本が最初で最後なのだろう。それに性格だって違う気がする。彼女のことにそこまで詳しいわけではないが、服装や話し方、髪型までもが違う。静かでどこか上品さを纏う雰囲気はいかにもな文学少女といった感じだ。その点、あの子はというと、元気すぎるほどで、天真爛漫を形にしたような少女だった。お喋り好きで、いつも誰かに囲まれている。そんな子だった。感心させられるほどに、二人は異なっている。
いくら分析を重ねても、結論は見えてこなかった。これも今も昔と一緒だった。
一週間後、また哲学の講義があった。この日は青年にとってはいつもと同じだった。この日が来る頃には、あの衝撃は二、三日もしないうちにすっかり頭から抜け落ちていて、眼鏡の女子生徒などもうどうでもよかった。
そもそも、青年が一方的に名前もわからない彼女に対して名前もわからない特別な感情を抱いていただけで、何か劇的な出来事が起きたわけではないのだから、至極当然のことだった。青年はそれを痛いほどに理解していた。
僕の周りで特別なことなど何も起きてはいない。人生は悲劇的なまでに非劇的なのだ。これじゃあ、あまりにも心無い。相談の相には心が無いとはよく言ったものだが、ここでもやはり心が無いようだ。それとも心が無いのは僕の方なのだろうか。あの子がいなくなってから、僕は空っぽになってしまった。いやあるいは、心奪われたと言った方が正しいのかもしれない。笑顔だとか涙だとか、憂鬱でさえも、あの頃から僕のものではなくて、まるで誰かから取ってつけたように思われてならないのだから。
青年はいつも通り角の席に座って、静かに教授の話を聞いていた。いつも通り、つまらなかった。不幸なことに、今日の授業では教授がグループを組むように指示をした。いわゆるグループディスカッションというやつだ。話すことを強制される悪しき風習に、青年は始まる前から嫌気が差していた。周囲の人が席を動かし始めてからようやく、青年もそれを真似る。
嫌なこととは往々にして重なるものだ。青年はその不幸にすぐに気がついた。机ごと振り向いた前の人物が、一週間前、栞の場所を訪ねてきた女子生徒だったのだ。
これは青年のとって紛れも無い不幸であった。得体のしれない何かに身構える必要があったからだ。
彼女と青年の間に会話はなかった。もしかしたら彼女は先週自分が話しかけたことを忘れているのではないかと感じるほどに、彼女は無機質で淡白だった。グループは出された議題について静かに話し合あう。
たった数十分の間、話し合うだけでディスカッションは終わった。しかし、何事もなくは終わらなかった。
青年はものの数十分で彼女に気を取られていた。他でもない彼女に。それは彼女が髪を耳にかけるような仕草をした時だった。どうやら彼女の癖のようで、頻繁に右手で左耳にかけていることに青年は気がついた。これはなんの変哲もない、ただの他人の癖であるし、実際青年から見れば、彼女はただの赤の他人と言って差し支えない。しかし青年とっては、彼にとっては、その赤の他人の仕草がとても重大なものだった。
あの子と全く同じなのだ。それはあの子の仕草で、あの子の癖なのだ。
ディスカッションが終わる頃には、青年はそれどころではなかった。青年は気が気でならなくて、目線も思考も全て彼女に吸い寄せられていた。
授業が終わると、彼女はグループに軽く礼を言って、風のように去った。彼女が教室を出るその一瞬まで、彼女に意識を注いでいた。
青年は心を放ったように固まって椅子に座っていた。その石化が解けるまではかなりの時間を要した。
今度も劇的なことは何一つ起きてはいなかった。しかし、青年には大きな一打であったのだ。
教室を出て、歩いて自宅へ帰る。そのわずかな時間でさえも、あの子のことを考えながら。体が、頭が、石になったかのように重かった。青年は体をベッドへ放り投げると、瞬きする間もなく眠ってしまった。
青年は夢を見ていた。
遠い夏。電車で二駅の隣町。石畳に並ぶ屋台。鈴虫の鳴き声。薄桜色の唇と浴衣、赤い花飾り。
夜空には大きな花が咲いた。振り向き笑う君も花みたいだった。頬にあたる風が生温かくて、妙に夜空が高かった。
どれも鮮明だ。まるでこの世界の彩度が何十倍にもあがったみたいに、全てが色鮮やかに彩られていた。
「先に行くね。待ってる」
あの子がそう言った。夢の中のあの子が僕に語りかけたのはこれが初めてだ。記憶にはないもので、僕の脳みそが作り上げたものに違いはなかった。それでも、僕は泣かずにはいられなかった。
僕からではなかった。最初で最後だった。
いや、最後になってしまった
。あの日を境に。届かない君に手を伸ばして、そのまま落ちてゆく僕を見ていて欲しかった。夢が終わる最後まで僕は泣いていた。
翌日は、まるで犬と猫が喧嘩しているみたいに土砂降りだった。
外は真っ暗だった。およそ午前四、五時であろうか。青年は重い体を持ち上げて、時刻を確認しようとする。小さな目覚まし時計に反射した自分を見て、初めて自分の頬に涙が流れていることに気がついた。
その事実に気づいた途端、腹の奥の方からえも言われぬ激情が押し寄せてきた。
なぜ泣いているのだろう。これはなん涙なのだろう。
傍には泣いていることに驚いた自分もいた。青年は暗い部屋の中、うずくまって嗚咽を吐くことしかできなかった。
心の水面が凪ぐまでには、しばらくかかった。今までにない経験だった。言葉にできない、という表現はよく聞くが、その多くが感情を言葉にするというプロセスが不可能なだけで、心は感情を曖昧にも捉え、評価しているものだ。しかし、青年にはそれすらもできていなかった。自分の中に押し寄せるものが何であるのか、どんな影響を与えるのかも、彼の心は理解できないのだった。ただ濁流のごとく激しく溢れでるのだった。
青年は夜が明ける前に、街へ出た。今度は体が変に軽い。頭の中はやはり空っぽだった。いや、正確には、頭の中はあの子のことで一杯であり、脳の隅まで一杯だからこそそれは何もないと同義だった。
ああ、あの子は何をしているのだろう。どうしていってしまったのだろう。
歩いて、歩いて、青年は気がつくと母校に辿り着いた。青年が合格した大学は家の近くではあったが、無理を言って一人暮らしを始めたのだった。今を振り返ってみると、少しでも離れて忘れてしまいたかったのかもしれない、と青年は感じた。もちろん、電気は一つも点いておらず、ただひっそりと立ち尽くしていた。
あの時と何も変わらなかった。あの子と出会ったのも、あの子と別れたのも、あの子と別れようとしたのも、全てこの場所だった。当然入ることはできないため、外から自分の教室を眺めていた。
今なら、今なら今度こそ。
決意した青年は校門を乗り越える。グラウンドを横切り、校舎脇の階段を登り始めた。屋上を目指し、パイプと出っ張りを駆使してなんとか登る。途中何度か足を滑らせかけて、肝を冷やしたし、その度に決意が揺らいだ。そもそも今自分が行なっているのは、犯罪以外の何物でもない。しかし、これからやることを考慮したら、これくらい怯えずにできるほどの胆力は必要だった。青年は屋上へ登り切ると、狭い幅に立った。屋上のフェンスはあまりに高くて登れたものではないが、その心配は必要なかった。
屋上はやはり高かった。下を覗くと、本能が足をすくませる。
屋上が思ったよりもずっと高いのも、足がすくむこの感覚も、遠くに見える建物が思いの外小さいのも、全てあの時と一緒だった。
僕の体を爆破する。思い出と共に。そう、僕の体は思い出でできているんだ。だから、思い出を、人生を、爆破するんだ。
あの時のショックは大きかった。クラスの担任になんの前触れもなく告げられた。外に興味のない僕の耳が無意識に捉え、そして頭に伝達したのは、彼女がここ最近学校を休みがちであったこと、その持病がありふれた病気であり、悪化の一途を辿っていたことだった。
大きなショックであった。しかし、それは文字通りの衝撃を意味しており、悲しみとか辛さとかを伴うものじゃなかった。ただ、わからなかった。やはりというべきなのだろうか。わからないことが多くなって、収拾のつかない青年だけが取り残された。
わからない、の次に青年が感じたのは、不条理だとか卑怯だとかだった。
あの子は、僕にしこりを残していなくなったのだ。自分でも解決できないしこりを。手も足もでなくて、唯一解決できるとしたら君だと思った。
だから、もう解決はできない。
涙が流れ始めた。
僕は…僕はもう一度、君に会いたい。
まだ聞いていないんだ。あの銅像を、燕を、あの物語をどう感じたか。君は僕のために読んでくれた。だから、聞かなくちゃ。きっと君なら、素敵な話だねって言うのだろう。それでいい。それでもいいから、君の話を聞かせてくれ。
陽が登ってきた。あたりは朝焼けで曙色に染まってゆく。涼しげな朝風が青年の頬を掠めた。
青年は再度覚悟を決めた。緩やかに、確かに。目の前には大きな花火が散った。