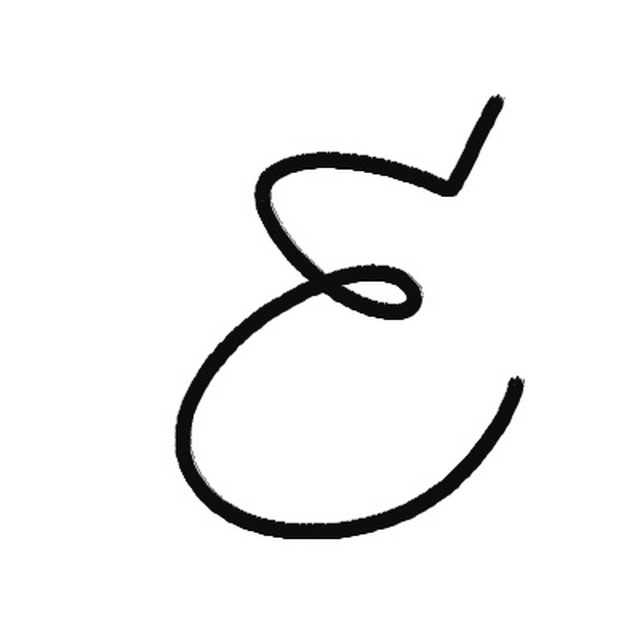第1話
文字数 26,125文字
「グッドウィルの泉」
永見妙
冷たい雪の降る夜、一人の赤ん坊が産声を上げた。
「はあ…はあ…。あなた、ほら見て、私たちの子供よ」
ミザリエは憔悴しきった目でチャーリーを見つめる。その手には助産師から渡された小さな赤ん坊を抱えていた。
「ああ、見えてる。見えてるとも。俺たちの子だ。ああ、なんて可愛いんだ」
涙を抑えられないマスク姿の父が分娩台の側に近寄り子供を抱える。少々グロテスクな顔を見て、思わずそうこぼした。
「目を瞑っているんだね。写真や人形とは違う。本当の本当に僕たちの子供なんだ。二人の宝なんだ」
押し寄せる感動も束の間、後の処置を控える赤ん坊は助産師に取り上げられると、奥の扉へと消えた。分娩室には最後まで泣き声が絶えなかった。
こうして、グッドウィルは泣きながら生まれ落ちた。苦痛に顔を歪ませ、これから身に降りかかる全ての悲劇を思い憂いながら、生を得た。十年間、グッドウィルは成長した。しかし、それは人とは違ったものだった。
ある夕方、ミザリエがいつものように部屋の掃除をしている時、外から帰ってきたグッドウィルが楽しそうにスキップをしながら、母に近寄った。
「ままがこれがたべよ、りょりしよ」
グッドウィルはそう言って、手を差し出す。紅くぬるぬるとした手のひらにはぐったりとして、少し口を開けたネズミを掴んでいた。ネズミがぴぎゅうと鳴く。ミザリエは思いも寄らないものに叫んでしまった。
「なんでこんなもの持ってるのよ!早く捨てなさい!」
そう言うと、彼女はグッドウィルの手を強く叩いた。ネズミはゴトンと床へ落ちる。赤くなったグッドウィルの手を見て母ははっと我に帰ると、今度は息子の手を強く握りしめた。
「ごめんなさい、ちょっとやりすぎてしまったわ」
良くなかったわと、母はグッドウィルの優しく両手を包み込む。今や願いとなった口癖をボソリと呟いた。
「おねがいだから、エライ子でいて」
当の本人はというと不思議でならなかった。母がサプライズに喜ばない理由、自分に罵声を浴びせた理由、自分の手を叩いた理由、そしてその後に泣きながら自分の手をさする理由。ひとつとして理解できなかったのだ。本人の中にあったのは喜んでくれるという低次な思考だった。彼はどうすれば良いのかわからなくて、立ち尽くして母を見ていた。ジンジンとした手の痛みはなかなか引かなかった。
その晩、目が覚めたグッドウィルは自分の部屋からトイレへ向かっていると、リビングで夫婦の会話が聞こえた。
「私…もう耐えられない。あの子のことを理解できないの。今日の夕、あの子が帰ってきたと思ったら、手にネズミを持っていたの。しかも血まみれのネズミをよ。あの子は家の前で見つけたって言っていたけれど、あの子はもう十才よ?普通なら気持ち悪がるものなんじゃないの?」
「まあ、落ち着いてよ。確かにあの子は普通の子とは違うかもしれないけれど、お医者さんも言ってたじゃないか。あの子に異常はないし、成長には個人差があるって」
「五年よ?普通の子が二年で会話できるのに、あの子は言葉を発するのに三年、会話が成立するまで五年もかかったのよ?当時は話しただけでも奇跡だと思ったけど、普通じゃないわ。小学校には入ってから五年間満足に友達もできないし、挙げ句の果てには医者からも近所からも家庭環境を疑われる始末よ。学校の成績も最悪。診断書がなくて学校も手のつけようがないって匙を投げてるわ。それにあの子が学校でなんて呼ばれているか知ってる?ナッツのグッドウィルよ?これじゃあ、あんまりだわ」
次第に金切り声になっていたミザリエはついに泣き始めてしまった。起きるかもしれないからとチャーリーはなんとか落ち着かせようとする。扉の隙間から見ていたグッドウィルは、なんだか怖くなって足が針金みたいに固まって動けなくなってしまった。
「この間だって危ないから車と道路には近づかないでって言ったのに、私が目を逸らした一瞬で道路を横切ろうとしてて…危うく轢かれかけたのよ。こんなことがこれからも何度もあるなんて、私にはもう無理よ」
「無理なんて言わないで。僕等はいつでも乗り越えてきたじゃないか。不妊の時だって諦めなかっただろう?確かにあの時は絶望のどん底だったけど、それでもいつも僕らのそばには神様がついていてくれたじゃないか。そして、あの子達はいつだって僕らの天使なんだ」
「天使?」
母の声に一層ヒステリックが増す。振り回す彼女の手をチャーリーは間一髪で避けた。
「天使なんて言い方はやめて!あなたなんにもわかってないわ。そりゃそうよね。あなたが産んだわけじゃないもの。グッドウィルのことも、あの子ことだって、何にもわからないわよね。あの子は…少なくともあの子は生きてるのよ」
泣くことしかできないミザリエはそれ以上何も言わなかった。チャーリーも完全かける言葉を失ってしまい、部屋には静寂が満ちる。二人が話している間、グッドウィルは怖くて逃げ出したいという気持ちしかなかった。そして、この無音に意を決して部屋へと逃げ込んだのだった。
その翌日、ミザリエとグッドウィルは何度目かわからない病院へ向かった。グッドウィルはなかなか行こうとせず、朝の支度は難航した。それも尤もで、痛い注射に何かわからないけどゴオンゴオンと音を立ててグッドウィルの体の周りを回るもの、さらには頭を締め付けるヘッドギアなど、グッドウィルからしてみると病院には嫌なものしかない。それらに動かずじっと耐えなくてはならないのが苦痛で仕方ないのなかった。
今日の来院の目的はウイルス検査だった。死んだネズミがどんな菌を持っているかはわかったものではないと母は心配していた。結果が良好だったことがわかると、グッドウィルはすぐに帰宅を許された。今までよりも早い帰宅に車の中でグッドウィルはご機嫌だった。帰宅後、ミザリエはグッドウィルを椅子に座らせた。
「グッドウィル。いい加減あんなことはやめなさい。もう二度とネズミには触っちゃダメよ」
「ぼくの…なにのよいない?」
「危ないウイルスがたくさんいるからよ。噛まれたりでもしたら大変なんだからね」
「ちりたい。ぼくわ…のなにがよい…よいない?」
「…なんでいけないか本当にわかってるの?」
「まんまあ」
グッドウィルは小首を傾げている。近くにある人形を手に取った。
「やろ」
魔が指すのは一瞬で、頭を床にぶつけるだとか目に人形をぶつけるだとか、そんなことは煮え滾った頭の中にはなかった。ごとごとと音を出しながら跳ね転がると、グッドウィルはやはり泣くほかなかった。
その日、床についたミザリエが見たのは恐ろしいあの日の夢だった。彼女はきっとグッドウィルのせいだろうと思った。夫婦二人は最寄りで最も大きな総合病院にいた。二才のグッドウェルは父に抱えられていた。青白い廊下の奥の扉を開けると、診察室につながっていて、一人のメガネをかけた老人がいた。パイプ椅子に夫婦が座ると、老人は話す。
「辛いかもしれませんが、よく聞いてください。お腹の中の赤ちゃんに染色体異常が確認されました。おそらく無事に赤ちゃんを産むことはできません。自然流産という形になるでしょう」
「そんな…どうにか、どうにか産んであげる方法はないんですか?」
「こればかりはどうしようもありません。たとえなんとかして子供を産んでも、子供が生き残る可能性は万に一つもありません。本当に残念ですが、赤ん坊を諦めるほかありません」
母は泣き崩れた。片手で顔を覆い、もう片方は自身のお腹にあてている。父は背中に片手で摩ってあげていた。グッドウィルはというと、父の片腕の中で壁のポスターを必死に見ていた。母は大粒の涙を流していた。
この後の出来事は、ミザリエにとってもグッドウィルにとっても忘れられないものだった。
帰宅した夫婦二人の間にはなおも重く苦しい空気が漂っていた。
「なもわなに?」
グッドウィルの手には胸にNemoと書かれたちいさなテディベアがあった。苦痛で母の顔が歪む。
「なで、なにでママはなくの?どおして?うれい?」
「嬉しいわけないわ。悲しいのよ。もうあの子のことは終わったの。これ以上ママを悲しくさせないで!」
今までのしつけとは違って少し、苛立ちと悪意のこもった声だった。それを聞き分けられないグッドウィルは、その態度にまるで新しいおもちゃを得たような、楽しい気持ちになった。
「にええも、にええも、なええも、…なえにも?」
「もうやめて!」
そう言ったミザリエはグッドウィルの頬を平手打ちした。慌ててチャーリーが止めに入ったが、母は自分のしようとしていることをやめようとはしなかった。
「あんたなんて…あんたなんて!」
グッドウィルは大声で泣いた。この日は一段と頬が痛くて仕方がなかったのだ。
ウィリアム家は歪みがさらなる歪みを産むサイクルに膠着し、その家庭は泥沼化していた。つまり、グッドウィルが異常な行動を取り、母がなぜこんなことをしたのかと怒号で問い詰める。いつからか、ウィリアム家では日常茶飯事となってしまった。自我の目覚めた幼児が自身の判断で行動し、その結果大人の理解のできないようなことをするのは決して異常ではない。問題がグットウィルの言語的、思考能力的、学習的な知能の遅れだったのは言うまでもなかった。
グッドウィルの学校生活は彼の家庭に劣らず劣悪だった。グッドウィルがいつものように一人で帰ろうとしていると、二人組が話しかけてきた。ひょろひょろのっぽがティム。ずる賢くて、いろんな悪知恵を働かせてはグッドウィルを騙している。この間は池に突き落とされた。ずんぐりとして太っちょの方がバルスで、図太い神経と横暴さが取り柄の彼は喧嘩もいつも負けなし。その力強さでグッドウィルに暴力を振っているのだった。二人は四六時中どこへ行くにしても一緒で、いつもグッドウィルをいじめる機会を探していた。
「おいナッツのグッドウィル、お前は根性なしだろ?最近噂になってるんだけどよ、この学校の裏山の奥の洞窟に化け物がでるんだとさ。そこまで案内してやるから、お前確認してこいよ」
「にかない。ままを、を…がぁ?おこらる」
「ナッツのくせに生意気だな。お前は口答えせずに俺たちの言うことを聞いとけばいいんだよ」
バルスが右腕を掴むと、すかさずティムが左へ潜り込んできて、その両手で細い左腕を握りしめた。グッドウィルは身を振るって抵抗する。二人はそんなの関係なしに裏山へと連れていった。
裏山は木々が鬱蒼としており、背丈の何十倍もの高木が彼らを見下ろしている。動物か何者かが常に一定の距離を保ってこちらをのぞいては、木々の奥へと消えてゆく。いつのまにか青い空は深緑色の天井に変わっていた。二十分ほど歩き続ける。
「おい、グッドウィル。お前怖くなってきたんじゃねえか?いまにもチビっちまいそうなんだろ?」
「へへへ、怖くなってるに決まってるよ」
ティムは薄汚い笑みを浮かべている。
「にかない。かえってじゃないとおこらる」
「なんだてめえ、強がってんじゃねえぞ!」
大きな声に反応したカラスが一斉に飛び跳ねた。
「もうちょっとで着くはずだ」
前日の雨のせいでぐちょぐちょとぬかるんだ地面を進む。勾配のある坂を登っていると、一際地面が盛り上がった場所に出た。その先が真暗闇の洞窟がひっそりとあった。
「ここがあの洞窟だな。よし入ってこい」
「はいってこいたらうち変えれる?」
「ああ、入って無事戻って来られたらな」
戻って来られたらな、と繰り返すティム。二人はうすら笑いを浮かべる。
グッドウィルは躊躇なく洞窟へと入る。中はジメジメとしていて、肌寒さに鳥肌が立った。当然ライトなど持っていないため、暗闇の中を進むことになり、グッドウィルは薄目ですたすたと歩いていく。足音が洞窟内でこだまする。洞窟はかなり小さいようで、五分ほど歩いていると分かれ道にも出会わずに最奥へと辿り着いた。そこには花緑青色に光り輝く泉があった。半径二メートルもないが、底は見えないほど深いようで、泉縁には苔が茂っている。
グッドウィルは泉に惹かれるように側へ近寄り、中を覗いてみた。底は見えない。面白いものも何もなく帰ろうと、泉を背にした時だった。
これはまた珍しいお客さんですね。
グッドウィルは振り返る。そこにはなにも変わらず、泉が佇んでいる。
私は泉の妖精です。ここへ訪ねてくれたお礼に、あなたの欲しいものを一つ与えましょう。
「なんでも?」
摩訶不思議な状況に好奇心をそそられる。恐怖はなかった。すこし考えてからふと母の口癖を思い出す。
「本当になんでもいいの?」
ええ。
「ならエライ子?にして。ままがいつも言うの。エライ子、エライ子。まま泣くんの。かぁいそう」
それは良い願いですね、と微笑んだ。
どれほど賢い子になりたいのですか?
「うーん、ばろすとちむ?」
それでは、その二人を連れてきてください。そしたら、あなたのことを賢くしてあげましょう。
入り口に戻ると、二人の手にはスコップが握られていた。
「な、なあ、バルス。ここまでやる必要なかったんじゃないのか?わざわざ化け物がいるなんて嘘ついて」
「いいから黙って掘れよ。お前もぶっ飛ばされてぇか?」
「おーい」
二人は素早くスコップを背中の後ろへ隠す。
「うえ、思ったよりも早いぞ」
グッドウィルは二人に近寄る。
「いっそになかにきて。そしたらエライ子」
「こいつは驚いた。とうとうナッツの中身が空っぽになっちまったようだ。何言ってんだ、おめえ?」
「ようせい」
「ほう、じゃあその妖精とやら見に行こうか」
ニシニシと笑う二人。新たなおもちゃの種を見つけたのだから、水を注がずにはいられなかったのだ。ティムは洞窟の余りの暗さに尻込みしたが、バルスに殴られるのもまた勘弁だった。三人は洞窟へと入り、泉まで辿り着く。二人組は例の泉を覗くがそこには泉水があるだけだった。
「なんだよ。何もねえじゃねえか」
何もないじゃねえか、とティムが繰り返す。やめだやめだとバルスが帰ろうとしたその時、妖精がグッドウィルに語りかけた。
二人を泉に落としなさい。
不思議に思ったが、言われたままにグッドウィルは泉の縁に立つ二人の背中を突き押した。
「何すんだてめえ」
首から上を出してバルスが上がろうとしたそのときだった。泉は音もなく一瞬で二人を飲み込み、あっという間に二人は深い底へ姿を消していった。もがき苦しむバルスをグッドウィルはなにも言わずに見下ろしていた。
「ばろす?ちむ?」
代わりに答えたのは妖精の声だった。
今あなたはこの二人の知識を得ました。きっとエライ子になれることでしょう。
「妖精さん?二人は?」
それきり泉は何も応えなかった。グッドウィルはしかたなく帰ることにした。
グッドウィルの異変に最初に気づいたのは、クラスメイトのジミーだった。彼女は近所に住む赤髪の女の子で、三つ編みのおさげがトレードマークだ。言ってしまえば、彼女はグッドウィルのお世話がかりだった。会話が成り立ちづらいグッドウィルに話しかけてくれる唯一の友達で、心優しい彼女は同じクラスで嫌厭されているグッドウィルを気にかけていた。登校中のグッドウィルを見つけると彼女は隣へ駆け寄った。
「あら、おはようグッドウィル。今日は遅刻じゃないのね」
「そうだね、いつもより二十分早いだけだけど」
ジミーは眉をひそめて、グッドウィルの顔を覗く。さも当たり前かのように言うグッドウィルに違和感があった。
「…あなた、いつも何時に登校していたか覚えてる?」
「九時半頃だったかな」
「じゃあもう一個質問。あなた、今朝はどんなだった?」
「いつも通りだよ。八時に起きて朝食、その後にリュックに教科書を入れたりしてから家を出てここまで歩いてきたんだよ」
ジミーはその問答の中ですぐに違和感の正体に気がついた。会話に知性を感じるのだ。きちんとした言葉遣いは最初に気がついたが、ある一定の時点から今までの時間を答えられることはなかったし、今まで自分の行動を端的に述べるなんてことも到底できなかった。ジミーが最後に話をしたのは昨日のお昼頃で、バルスに階段下の人目が届きにくい場所で暴力を振るわれていたのを止めた時だった。
「どうも一晩のうちに賢くなったみたいね」
一方、グッドウィルはというとなにも変化を感じてはいないわけでなかった。ぼんやりと霞のかかった思考領域が晴れているという感覚があり、それはいつもよりも鮮明な思考として現れていた。道端の花が綺麗だとか、通りすがりの老人が顔馴染みの気がして、もしかしたら以前に会っていたかもしれないだとか、そんな程度のものだがそれもグッドウィルにとっては高度なものであったのだ。
しかしそうはいっても、やはり自身への認識は今までの自分に尾を引いて不変であった。自身の成長を知覚する時は決まって進行形ではなく過去形で語られるものなのだ。ちょうど赤ん坊が自身をメタ的な視点から俯瞰することもなく、知らぬ間に成長するように、グッドウィルは己の成長に気づくことなく賢くなった。その振れ幅の小さな知能向上に気づけなかったのが故に、ジミーの言葉に驚くことになった。
「僕が賢くなってるって?どうしてそう思うんだ?」
「どうもこうもないわよ。あなた自分でわからないの?傍目から見てもいつもと違うことは明らかなのに」
「いつもと違うこと…そういえば今日は寄り道せずにまっすぐ学校に来たんだ。普段なら気になった花を摘んだりしてたんだけど、そう思うよりも先に学校へ行かなきゃって思ったんだ。どうして僕はあんなにも衝動的だったんだろうね」
「わからないことだらけね。まあ話は詳しく聞くわ。とりあえず教室へ向かいましょ」
この日の学校は苦労の連続となった。クラスはたちまちグッドウィルの話題で持ちきりになった。隣の席の人、そのまた隣の席の人、その前後左右といった具合に、グッドウィルのことがクラス全員に広まるのに時間はかからなかった。思いもよらなかったのは中にはグッドウィルのことを格好良いといった評価する声まで現れたことだった。休み時間は次から次へとくる訪問者の対応に追われたが、それは幸せな不幸せで、クラスメイトとのほぼ初めての会話はとても新鮮だった。
「本当にあのグッドウィルなの?」
「なんだか雰囲気が変わったね」
「何があったの?」
突如として人気者になったグッドウィルをジミーは少し外から見ていた。
「ちょっとみんな、グッドウィルは忙しいの。ほら行くわよ」
今や必要のない案内人の役割をこなそうと、ジミーは彼の腕を取るといつものように次の授業に連れて行くなんてこともあった。
クラスの授業はこれまでにないほどにスムーズにこなすことができた。文法や物語の読解、以前はできなかった四則演算はもちろん、割合や図形の理解、紀元前まで世界中の歴史、社会構造や政治、今までは意味をなさなかった文章の羅列を余すことなく網羅することができた。不可能から可能への転換には決まって喜びを伴うもので、放課後には勉学に没頭し、図書館で本を読み漁っては、今までぼんやりとしていた日常経験を知識として結びつけもした。
それから気になる子もできた。ジミーだ。グッドウィルは自分が自分で思っている以上に彼女が側に付き添ってくれていたことに気づくことができた。きっと彼女がいなければ、学校生活は破綻していただろう。次のクラスへ遅れず参加できたのも、生き物係の仕事を手伝ってくれ、中庭のウサギたちが死ななかったのも、当時の彼なら絶対にできなかった宿題の数々も、全て彼女のおかげなのだ。それらを思うと、彼女に対してえも言われぬ特別な感情の若芽が出るのだった。
ジミー、クラスメイト、その次に気づいたのがミザリエとチャーリーだった。その日の晩、図書館に籠ったせいでいつもより二、三時間ほど遅く自宅に帰ると、台所に母の姿を見た。いつのものかわからない洗い物をしていた。
最近はほとんど会話がなかった。何が平手打ちの原因になるかわからないグッドウィルにとっては当然だった。
「母さん」
今夜は話しかけてみることにした。うまくいくような気がしたのだ。
「今朝はサンドウィッチ、ありがとう」
作り置きのせいで冷めていたことは言わないことにした。
「体調はどう?あまりよくないって言ってたけど」
毎朝グッドウィルが起きると、机の上にはプレートと朝食が置いてある。しかし、そこに母の姿はない。朝は決まって自室に篭っているのだ。必要最低限の世話、それが食事の用意であって、それ以外は知ったことではないといった態度だった。
以前、ノックもせずに部屋に入ると、そこには朝寝髪で目の下にびっしりと隈をつけた母がベッドでうずくまっていた。その時は一度で済んだが、その時の経験を糧に部屋には近寄らないようにしていた。痛みの伴う経験が彼にとって最も効用なのは間違いなかった。グッドウィルはその時に言われた「体調が悪いから」という言葉をよく覚えていたが、いつから家族がこのような形になったのかは判断がつかなかった。
肉体労働者の父はというと、朝早くから仕事で家を出ており、日中はほとんど顔をあわせることがなかった。二重苦に挟まれながらも彼は彼なりに家庭を支えていた。グッドウィルに決して暴力を振るうことはなかったし、機能しない母の代わりにグッドウィルの世話を行い、少しでも彼の居場所であろうとした。そんなチャーリーをグッドウィルは信頼していた夜の帰りをいつも楽しみにていた。
「ママ?」
返事はなかった。とりつく島がなくて、相手の様子を窺う。彼女の目玉はまるで透明なガラスの球体のようだったが、決してビイドロ玉のような美しさはなかった。もう一度声をかけようとした。
「グッドウィル?」
母がこちらを振り返る。その目に少しだけ光が射し入った。
「あら、今日は随分おそかったのね」
グッドウィルの体は無意識に強張ってしまった。
「図書館で勉強をしてたんだ」
母は目を丸くした。返事など土台期待していなかったからだ。その様子は明らかに自分の耳を疑っていた。例えばもし、赤ん坊に語りかけているときにはっきりした言葉で明瞭に返答されると誰でも驚いてしまうだろう。同じような反応が彼女の頭の中で起きていた。
「もう一度言ってくれない?」
「放課後、学校に残って勉強してたんだ。本を読んだり、今まで習った教科書を読み直したりね」
今度はグッドウィルが発声した文章の意味を理解できた。しかし、その裏で意味するものにはまだ理解が及ばなかった。
「勉強ってそんな…それにきちんと会話も…。一体何が起こっているの?」
「僕にもよくはわからない。けれど今日はなんだかすごい頭の中がスッキリしているんだ」
彼はテーブルにつくと、今日の出来事について話した。自分の体調やジミーとの会話、授業中の全能感とさえ言えるほどの知能的成長とそれに追随する知的好奇心の向上。彼は時系列順に明確かつ簡潔に伝えた。
母は彼の話を聞きながら歓喜していた。必死に首を縦に振り、一言一句に相槌を打った。自分の息子と初めて意思の疎通を図ることができたのだ。彼女は真にグッドウィルの心と自身の心が通じ合った気がした。
午後七時、その日のウィリアム家の食卓は豪華なものになった。母は父のもとへ電話をよこすと、今日は何がなんでも早く帰ってくるようにと連絡した。その後、彼女は彼が帰ってくる前に食事を用意しなくてはとは躍起になって用意を進めた。久々に車を出して一緒に行ったスーパーではあちらこちら首を振っては、メモに目を落とすという動作を何度も繰り返していた。ここまで忙しない母をグッドウィルは見たことがなかった。久しぶりに振舞われた贅沢なテーブルの上から暖色のライトが三人を照らし、その夜は初めて会話が弾んだ。
この日を境に家庭内の不和は徐々に緩和し、夕餉の食卓では以前にはなかった暖かな雰囲気が溢れるようになった。父も毎日ではないものの早く帰るようになり、共に時間を過ごすことも増えた。
その後もグッドウィルは日々を学業に費やした。放課後、二時間は机に向かうことをルーティーンとし、その結果は学校のテストのような目に見える形ですぐに現れるようになった。その度に笑顔を見せ、「エライじゃない」と褒めてくれる母のことを思うとなお一層研鑽した。
三年後、グッドウィルが中学生になる頃には、一般的な高校生の学習範囲を全てマスターしていた。一年と経たずに今までの不足を補填し、もう二年で本来身の丈には合わない分野、範囲へと手を伸ばしていた。
この頃のグッドウィルは学校が退屈で仕方なかった。学校の中ではなにもかもが学習したものばかりで、学内テストでは全てが満点、学内順位は一位を総なめにした。小学生五年生の頃のように未知との出会いに心踊ることは無くなり、授業は彼をただ無意味に縛るものとなった。友人に関しても同じだった。今まで友好関係を築いてきた友達のほとんどとは、会話をすればするほどその低脳ぶりと退屈な人間性が透けて見えてしかたがなくて自然と疎遠になった。その結果、以前とは違った一人の高校生活となったが、それに不満は感じなかった。
学校生活を唯一彩るものが放課後のルーティーンだった。未知が既知となった今、その楽しみは全く違う方向へと変化した。その変化とは、その時間をジミーと共に過ごすようになったことだ。それほど大きくない街に住む二人は小学生から同じ環境にあり、ある日、ジミーから勉強を教えてくれと頼まれてから週に三日ほど指導をしていた。
とある日、いつものように図書館の学習スペースの隅で机を隣り合わせにしてテキストを解いている時だった。いつからか沸いた疑問を解くために彼は胸の内を明かしてみることにした。
「ジミー、君に聞いてみたいことがあるんだ」
ジミーは手を止めてグッドウィルの方を見て、「ええ」と返事をした。
「君は今まで僕にたくさん良くしてくれたよね」
「ええ、まあ、そうかもね」
「僕がまともな小学校生活を送れたのは間違いなく君のおかげだ。それにはとても感謝してる。でも一つ気がかりなことがあって、当時の君はどうして僕を手助けしようと思ったの?」
「うーん、どうしてねえ…難しい質問だわ。こう答えることにしましょう。あなたが危なっかしいと思ったからよ」
歯切れの悪く聞こえた彼女の言葉を脳味噌に落とし込んでみる。それからこう尋ねた。
「じゃあもう一つ、君は僕のことをどう思ってるの?」
「……」
妙な時間が流れる。彼女は少し間を置いてからばつの悪そうな顔で言った。
「とても賢いと思ってるわ。ちいさい頃では考えられないくらいにね。何かあったのかって心配になる程よ」
グッドウィルにとって彼女と過ごす時間は心地よかった。ほんのりと暖かさを帯びて、今までのグッドウィルの人生にはなかった何かしらを感じ取らせてくれ、彼女と接すると彼の中では何かが育っていくのような感覚があった。それが何かは彼にはわからなかったが、それは良いという言葉で表現するだけではあまりにも複雑で、放ってはおけないないような何かであった。
彼女の態度を何かをはぐらかし、本質から逸らそうとしているかのようだった。この問答では満足のいく答えは得られなかった彼はどこか急いたように続ける。
「自分でもなぜだかよくわからないけれど、僕は君のことを必要以上に考えてしまっている気がするんだ。手の打ちようがなかったから、こうして君に打ち明けてみることにした。ジミーは何かわからないかい?君にも同じようなことがあるんだろうか?」
今度はもっと長い沈黙だった。グッドウィルは彼女の顔を見つめ続けていたが、彼女の表情をなんと表現すればよいのかわからなかった。
「グッドウィル、あなたはなぜかわからないけれど突然賢くなって…それはもちろん良いことだわ。けれど、それは良いことばかりではなくてね。私だってわからないことだらけなの。すこし時間が欲しいわ」
彼女はこぼすように「ねえ、グッドウィル」と言うと、別れをつげて図書館を後にした。
一人残されたグッドウィルは惚けた頭で机に向かっていた。彼の頭の中を巡るのは彼女の沈黙と表情だった。賢くなったことで何かしらの不利益を彼女に与えた可能性が思い浮かんだが、それはすぐに否定した。最も彼を悩ませたのは私にもわからないと言う言葉だった。その言葉を飲み込むには、彼女の言葉はあまりにも趣旨に欠けていて、前後の文脈が破綻している。彼女が時間的猶予を得て何を考えたいのかすらも、彼にはわからなかった。
帰宅する前にジミーの座っていた椅子を片したが重く感じた。
三週間が過ぎた。あの日以来、ジミーが放課後に図書室へ姿を現すことはなく、気がつくとグッドウィルも足が遠のいていた。廊下ですれ違った時には挨拶を無視され、同じクラスでも話すことはなかった。次の授業の準備と教室への案内も無くなってしまい、異変があったのは明らかだ。もちろんグッドウィルは思考をとめどなく回し続けたが、何一つ成果はなかった。足掛かりを得るのはさらに一週間後で、身近なところだった。
深夜、グッドウィルが自室で就寝しようとしていると、どこからか物音がした。しばらく無視をしていたがどうにも止みそうにないから、出所を探ってみることにした。ところがその詮索はすぐに中止となった。なぜならその音が夫婦部屋から聞こえる音だったからだ。グッドウィルは男女の色恋や情事は知識としては当然知っていたが、もちろん自身に経験はなかった。ここ数年、良好に向かっていた夫婦は大きな山を越えてさらに固い愛を結んでいたことは気づいていたが、その場面に出くわすのは初めてだった。
思春期の青年にこの情事が与える影響は十二分で、今までグッドウィルの中で眠っていた異性に対する興味というのを遅咲きで開花させた。そして当然その対象はジミーへと向かい、始めて自分が彼女に恋愛感情を抱いているのではないかという結論を導き出した。眠気などとうに忘れ去ったグッドウィルが最初に行ったのは、溢れた知識欲を抑えるために心理学関する書物を探すことだった。
そうして計画を企てることになった。
よく晴れた日曜日であった。グッドウィルは母と共にハイキングに来ていた。頬かすめるそよ風が気持ちよくて、木々に止まった雛鳥たちがぴいぴいと鳴いている。
しばらく歩くと高い木々で足元が翳り始めた。
「休憩が必要かい?僕はもっと早く行けるんだけど」
心配の言葉をかけるが言葉だけに過ぎず、その足は遅くなる様子はなかった。
「私ももう歳なのね。あまり遠くへは行かないで。一緒に行きましょう」
乾いて固まった地面を進む。勾配のある坂を登り、一際地面が盛り上がった場所の上に立つ。その先が真暗闇の洞窟がひっそりとあった。
「見て、母さん。あんなところに洞窟があるよ。天然なのかな?興味が湧いてくるね。ちょっと入ってみない?」
「いいんだけど、ちょっとだけ休憩してからにしよう」
母はリュックからボトルを出すと水分補給をし、五分ほど休憩をした。
父は連れてこなかった。必要がないし連れてくると何かと面倒だと判断したからだった。
二人は暗くジメジメとした洞窟へと入る。中はやはり冷えていた。
「ライトを持ってきてるなんて用意がいいわね、グッドウィル」
グッドウィルはスタスタと歩いたために、二、三分もせずに奥まで到着した。
「分かれ道もなかったし、小さい泉があるだけみたいね。綺麗に光っててなんだか神秘的じゃない」
おそらく光に反応する苔のせいだよ、とグッドウィルは心の中で呟く。
全てがグッドウィルの狙い通りだった。ここまでの用意に時間はそうかからなかった。怪我をしたから救助してくれ、気になる洞窟があるから一緒に調査にきてくれ、そういうシナリオも考慮した。あの日以降、グッドウィルは時々洞窟に訪れては調査をしており、成果こそなかったものの、おかげで座標、周辺環境、構造、生息生物、気温や湿度、過去の地質学的、考古学的または神話学的な文献、全てがグッドウィルの頭の中だった。そうはいっても慎重に慎重を重ねて、前日の下見は怠らなかったのだが。
母は泉を覗き込んで観察していた。
グッドウィルが彼女の後ろに立つと、いとも容易く母は泉の中へ落とされるのだった。
よくやりましたね。
頭の中でそう響いた気がした。
一人帰宅したグッドウィルによって捜索状が出され、警察は最後に接触していたグッドウィルを調査することになった。彼の主張は自分が目を離した隙に彼女が一人でどこかへ行ってしまったというもので、少々不可解な点はあるものの、物証がなく死体も見つからないということで、この一件は不幸な事故、あるいは一過性の高い自殺として処理されることとなった。グッドウィルの近辺が落ち着くには少し時間がかかったが、こうして計画は第二段階へと移行することになった。
自分の母親を殺めるという行いをしたグッドウィルが最初に行ったのは、過去の自分の行いの重大さに気づき猛省するなどということではなく、単なる仮説の検証と状況の整理だった。グッドウィルは机に向かい、白紙を取り出すとさらさらとに書き上げていく。
まずは現在の状況。後日、母を一人探しに行く健気で可哀想な息子を装って山に入り、死体が浮かび上がってきていないことを確認した。今回の犯行で注力したのはできる限り一度目の再現をすることだ。ティムとバルスの場合、死体が発見されていないことから察するに泉に沈んでいる。水に突き落とされた人間は条件が揃えば膝丈ほどの水量でも殺すことができるが、死体を沈める場合には少し工夫を施す必要がある。今回は母を落としはしたが死には至らなかったため、無理矢理押し込んで溺死させ、その後、母のリュックに重しとなるようなものを入れた。万が一死体が腐敗性ガスによって上昇してくる可能性を考慮し、確認へ向かったが結果は良好だった。もう少し効率的な方法もあったかもしれないが、一度目の再現に重点を置いた結果だった。
次に仮説一の妖精の存否について。一度目の時の記憶はかなり曖昧なもので、ほとんど無いに等しかった。ティムとバルスともに行ったことでさえ、周りの証言がないとわからなかったほどだ。そんな中唯一覚えていたのが妖精との会話だった。泉に人を落とせばその人の知識を得るという会話が頭の中には残っていたのだ。当の本人だがこれについては疑わしく思っており、幼い自分が作り上げた妄想だと考えていた。しかしその一方で、妙に印象的なこの会話と他人から聞いた状況を合わせるに、やはりこの方法で自分の知能が上昇したと認めざるを得なくもあった。これがこの計画で検証したかった仮説一である。
確かにあの時、頭の中で声が聞こえた気がした。しかし、あの声は過度な興奮状態に陥った自身が作り出した幻聴という説を拭いきれず、妖精の実否は分からずじまいに終わった。
次に仮説二の愛の獲得について。こちらが本命であって、仮説一は副次的なものだ。仮説一が真だった場合、母を落とすことで「愛」という知識を得られるのではないかというのが仮説二だ。一度目はおそらく二人の友人(話を聞くに友人ではないが)の知識を得たいというのが叶えられたのであり、これに則って父を愛する母を落とすことで愛の正体を知ることができるのではないかというのが今回の狙いだった。
これは予想していたことだが、愛を知るという目的があまりにも抽象的で、事後目に見えてわかる変化が得られなかった。殺人後から約一週間観察を行ったが、自身に何かしらの変化は感じられなかった。こちらについては第二段階で確認することになるだろう。
一通りメモを書き終えると、初めからざっと目を通していく。全て読み終えるとグッドウィルは天井を見上げた。こうして目の前に自分の悪行を理路整然と書き上げてみると、グッドウィルの胸には罪の意識が湧いて出た。けれどそれは脆くて希薄かつ反省を含まないもので、彼の思う罪の意識とは、自分は刑法に反して罰を受けるに値する行為を行い、それを今後隠し通さなければならないというひどく実用的な罪の意識だった。
グッドウィルは我ながらとても傲慢だと感じた。彼女には彼女の罪があり、幸い顔周辺にはないが、それらは今でもずっと消えずに彼の肉体に刻まれている。怨恨が動機ならまだ筋も通っているのだが、そんなものは微塵もなかった。旧約聖書「創世記」の中でイブが蛇に唆されて知恵の実を食べたが、グッドウィルが誘われたのもやはり神秘を孕み、全能にさえも届きうる知恵だった。法知識を備えたグッドウィルが、殺人を悪いことという簡単なことをわかっていないわけはない。ただそれよりも知的好奇心が優っただけのことだった。
グッドウィルは立ち上って一息つくと、紙をくしゃくしゃにして暖炉へと投げ捨てた。
母の殺人から二週間後、彼は登校を再開した。事件が発覚してからは学校に休みを申請しており、この日から何食わぬ顔でまた学校生活を過ごし始めるはずだった。学校に着いて早々、名前は忘れてしまったが、同じクラスである女子生徒にこう話しかけられた。
「ねえグッドウィル、お母さんのことは…その…残念だったわね。けれど、安心して。私たちはあなたの味方で、あなたは一人じゃないわ」
休みの理由は教師のみに伝えていたが、どういうわけかクラス全体に事件のことは広まっていた。しかし、それはそれで後に都合が良かった。
「ああ、ありがとう」
こんな時は感情に従順になって慰めるのかと軽く軽蔑すると、ここではないと思いつつも練習通り涙を流した。
再開した学校生活で彼は一つのことを心がけた。それは意図的にジミーを避けることだった。といっても極力彼女と出会って会話が発生しないよう立ち回るだけで、要は相手を焦らし、機会を待つだけことだった。
学校が始まってから三日間、教室やカフェテリア隣に来た彼女をグッドウィルは「少し体調が悪くて」とだけ言い、その場を去るようにした。そして翌日席を開けたグッドウィルが戻ってくると、机の上にメモが貼ってあり、そこには「今日の放課後、図書館で待ってる。話がしたいの。ジミー」と書いてあった。
放課後、二人はいつも図書館で落ち合い、以前のように自学スペースの隅で机を隣合わせに座った。先に口を開いたのはジミーだった。
「お母さんのこと、聞いたわ。大変だったわね。その…体調はどう?」
「悪くはないよ」とあたかも悪そうに言う。
「そう…お父さんもさぞ辛かったでしょうね」
グッドウィルは黙りこむ。いつも静かな図書館だが今日は恐怖を感じるほどで、その沈黙がさらに彼女を追い詰める。
「私はね、グッドウィル、貴方を心配してたのよ。なかなかじっくり話す機会がなかったから…」
グッドウィルは機会を伺っている。
「学校でも元気ないみたいだし…そりゃああんなことがあったのだから元気出せって言う方が無理だけど」
相槌を軽く一回返すと、再び沈黙が降りた。すると今度はグッドウィルが口を開いた。
「ごめん、ジミー、なんて言ったらいいのか…」
グッドウィルは彼女の真正面に捉えて、まっすぐと目を見つめる。
「どうやらこういう時の僕はとても無力らしい」
ジミーを見つめる瞳から涙を流した。
「今だけでいい…今だけでいいから…僕のそばにいてくれないか」
グッドウィルがそう言い切るよりも前に、ジミーはグッドウィルを抱きしめた。力強く抱きしめられた彼女の腕に応えるように、グッドウィルは彼女の少し小さな体を抱きしめ返した。
「もちろんよ」
震える声でジミーが言った。顔は見えないが、泣いているのがわかった。
そうして彼らは数分で、永遠とも思えるような濃密な時間を過ごした。抱きしめた彼女の体はとても暖かかった。
泣き止んだ彼らは己の感情を余す所なく吐露しあった。何もかもグッドウィルの思い通りだった。まず接触を減らして不安を増大させ、さらにようやくの会話で本心を確認できるというカタルシスと自分を頼っているというアンダードッグ効果を引き起こせば良いだけのことだと考えていた。結局のところ心というのは信号に過ぎないのだとつくづく感じた。
そこからはとんとん拍子に事が進んだ。徐々に距離を縮めていった彼らは交際を始めることとなった。告白したのはジミーからで、回答は文句なしのイエスだった。こうしてグッドウィルは晴れて退屈の学校生活から一転し、愛する彼女と共に過ごす最高の学園生活を送る事となった。
中学校を卒業後、地方の高校へ進学するとさらに勉学に注力した。この段階ですでに高校科目もマスターしており、暇を持て余した彼が次に選んだ教材は法学、社会学、経済学、言語学、心理学、人間科学などあらゆる分野の大学参考書だった。中でも彼の興味を引いたのは、生物学だった。自身の知能向上の手がかりになるのではと思い、人間の脳の構造や知識の入手方法、そもそも知識そのものが何であるのかをなどを調べてきた。その関心の延長線上にあったのが生物学だった。
高校を卒業すると同時に有名大学へと進学した。大学では生物学を専攻し、人体の構造をより専門的に研究していくことにした。大学から給与型の奨学金を受け取りながら通学となり、通学時間を考慮した結果、大学近辺へ引っ越すこととなった。
ジミーは高校を卒業後、実家のパン屋で働きながら家の手伝いをしていた。二人の交際はなお続いていたが、グッドウィルの遠方への引っ越しにより、時間的、空間的距離ができてしまうのは仕方のないことだった。会う頻度はほぼ毎日から二、三ヶ月に一度に下がってしまったが、これは二人が話し合って下した決断であった。初めは彼女の感情を揺れてしまったが、将来の見通しが立ち次第同棲を始めるという約束を交わした二人の仲は雨降って地固まることとなった。
満を持して始まった大学初日、配属先となる研究所の教授アロガンと顔合わせをした。白髪の混じった口髭、少し後退した額に厳めしい顔つきはいかにも学者様といった風貌だった。コツコツと革靴を鳴らして教室に入室すると、彼は第一回目の授業としてオリエンテーションを始めた。教室と研究室を併設したクラスには三十人ほどが席に座っていた。
「私はこの学校の名誉教授アロガンだ。取り扱うものは授業によって多少異なってくるが、主として生物学を専門としている。今学期、このクラスの担当となった。よろしく頼む」
アロガンは話を始めた。
「まず初めに生物学を通して何を学びたいのかを君らに問うておきたい。その答えを己の中に持つものにとって、この四年間は非常に有意義なものになるだろう。またまだその答えを持たぬ者もそれを探求する努力を決して怠らぬよう日頃から己のセンサーの調整をしていてほしい。…ウィリアム、ウィリアムグッドウィルはいるかね?」
グッドウィルは席を立ち、返事をする。
「君が生物学を学ぶ目的は何かね?」
アロガンの視線には大きな期待が含まれていた。
「私の目的は主に脳の構造を理解し、知識とは何かを解き明かすことです」
「なるほど、脳科学的観点からみた知識か、良い答えだ」
アロガンは話を続ける。アロガンの目は再びクラス全体へと語る。
「私は学習の目的を見つけろと言ったが、そもそもまず生物学とはなにを学ぶのかを理解しなくてはならない。これもまた様々な言いようがあるが、私なりの言葉で表現するなら、つまるところ『生命』は何かを追求し、その根底にある共通原理を学ぶ学問だ。この学問には多様な切り口がある。生物を系統的に分類する分類学、進化を研究する進化学、生態を解き明かす生態学、行動を分析、研究する行動学。生体を対象にその仕組みを解明する生化学、生理学、生命の誕生や器官形成を探る発生学、遺伝子の役割を解明する遺伝子学、細胞を対象とする細胞生物学や分子生物学などの分野があるのだが…」
授業が終わると、教授はグッドウィルへ近寄った。
「グッドウィルだったな。これからよろしく頼む」
アロガンは力強くグッドウィルの手を握った。
「よろしくお願いします」
「初めての授業はどうだったかな?」
「今日の授業はまだ導入に過ぎません。早く専門的に学んでいきたいです」
「そうかそうか、それはよろしい限りだ。時に風の噂で聞いたのだが、君は入学テストで全ての科目でほぼ満点を取り、主席で入学したそうじゃないか」
「すごいことではありませんよ。要はいかに知識を持っているかですからね」
「そう簡単にできることではないさ。…そんな君に似合いの場所があるのだが興味ないかね?」
教授の話を聞くにこしたことはない、そう思ったグッドウィルが同意すると、アロガンは「立ち話もなんだから」と、二人はカフェテリアへ行くことになった。
アロガンが二人分のコーヒーを注文すると、空いている席に座った。かなり広く清掃の行き届いたカフェテリアだった。コーヒーを一口啜るとアロガンが言う。
「先ほどの話なのだがね、今、私の研究室では君の学びたがっていた脳を研究しているんだ。誰もが入れるわけではない。私が選んだ少数精鋭のグループだ。そこでは記憶や学習、予測、思考、言語などあらゆる脳の高次認知機能の仕組みを解き明かそうとしている。そこで提案なのだが、このグループに参加しないか?」
グッドウィルに断る理由はなく、むしろ成績評価につながるならと喜んで引受けた。事がすんなりと進むと、アロガンは目に見えて喜んだ。
「ならば早速案内しよう」
そう言って、立ち上がった教授に疑問を持った。
「申請書などは書かなくて良いのでしょうか?」
「いい、いい、そんなものは。それよりも君の研究部屋へと行こう」
案内されたのは『アロガン教授第二研究室』と書かれた部屋だった。中はそこそこの広さで、研究室というよりもすこし生活感のある勉強部屋といった様相だった。入って左手には壁一面に本棚が並んでおり、その本棚に向き合うような形で部屋の中央に質素なデスクとパソコンが置いてあった。部屋の右半分は給湯室のようになっており、小さなシンクや冷蔵庫、ポットなどが置いてあった。
「ここには選りすぐりの専門書が揃っているし、またすぐそこのパソコンからアクセスすれば、私の権限で最新の論文なども閲覧できる。監督者を付けられない都合上、どうしてもこの部屋での高度な実験は不可能だが、座学にはうってつけの環境というわけだな。実験をしたいときは悪いが今日のクラスで使用した教室で行ってくれ。ここにある備品なら好きに使ってくれて構わない。隣は私の部屋になっているから、私がいる時ならいつでも呼んでくれたまえ」
アロガンは部屋を歩きまりながら、楽しそうに話す。
「それから今後二、三ヶ月に一度ほどのペースで進捗を提出してくれ。そこまで慎重になる必要はないが、何をしているのかは把握しておきたいからな」
グッドウィルの正面に立ち止まると、自慢の髭をいじりながら尋ねた。
「さて、ここまでで質問はあるか?」
「…他の研究者たちに挨拶することは可能ですか?」
「…残念ながらそれは無理だな」
「どうしてかお聞かせ願えますか」
「彼らは忙しいのだ。彼らはそれぞれのタスクを抱えている。ここ最近はかなり躍起になっているようだから今日のうちに会うのは難しいだろう。また機会があれば紹介しよう。他に質問は?」
「いえ」
グッドウィルは胸の内に浮かんだ考えを押し込んで言った。
「では早速今日から研究に取り組んでくれたまえ。私はこれから会議だから、ここらでな」
「今日からですか?」
「嫌と言うなら構わない。善は急げという話さ」
アロガンはやたらとうるさい革靴をコツコツと鳴らすと、扉を開けて出ていった。
グッドウィルは椅子に腰掛けると、さっそくパソコンを起動した。研究内容はすでに目処が立っていて、それに関しては問題なかった。それよりも気がかりなのはアロガンだった。小さな違和感だが、突き詰めるに値しないし、今はこの環境を有効活用したほうが有益だとも思えた。グッドウィルは当面の自説を検証し始めた。
結局、その日はアロガンには会うことなく帰宅することにした。午後七時、帰宅したグッドウィルは食事を済ましてシャワーから出たとき、彼の携帯が鳴った。時刻を確認し、次に画面に出た名前を確認すると携帯を耳にあてる。
「やあジミー、そろそろ電話が来る頃かと思っていたよ」
「私もそろそろあなたが予想できるように頃じゃないかと予想してたところよ」
「その調子も相変わらずだね」
「引越ししてからの電話はほぼこの時間よ。あなたのことだから頭に入っていないわけないわ。それで、大学はどうだった?」
「まずまずってところだな。どうやら僕は有望株らしいよ」
「有能株?」
「教授にスカウトされてね。その教授のお膝元で研究することになったんだ」
「さすがといったところなのかしらね」
「まあうまくやるさ。これから忙しくなると思うんだけど、悪く思わないでくれよ。君と同じくらい研究も大切にしたいんだ」
「ええわかってるわ。お互いの生活があるものね。それにこっちだって忙しくなりそうだしね。私は声が聞けて満足よ」
しばらく何の意味のない会話を繰り広げると、二人は別れを告げて電話を切った。引越ししてから日課となっていたこの通話は二時間、一時間、三十分とここ最近徐々に通話時間が短くなってきていた。日課が形骸化しつつあることにグッドウィルは嬉しくもやや悲しくもあった。今一度自身の心情をまとめてみる。その時はそう遠くないだろうという予想に行き着くのは当然だった。
アロガンの元で研究を始めてから二ヶ月が過ぎた。研究は構想の段階までは順調だったが、突如としてブレーキをかけられることとなった。
「グッドウィル、今日は本報告の日なのだが、準備の程はいかがかな?」
土曜日の昼過ぎ、研究室第二へノックもせずに入ってきたアロガンはグッドウィルの背中からそう話しかけると、机へ近寄った。今日のアロガンは顔には教授の風貌が宿っていた。グッドウィルは資料を手渡すと、近くの椅子をアロガンのために持ってくる。
「前から進めていた神経伝達回路を強化する案についてなんですが、ようやく目処が立ってきました。僕が注目したのはニューロンの分化です」
アロガンは老眼鏡を鼻にかけると、ただ黙って資料に目を通していく。時々眼鏡越しにグッドウィルの顔をのぞいていた。
「前にも話した通り、この研究の出発点は知識とはなにか、そして知識の仕組みを解明することで人為的にそれを強化することができるのではないかです。そしてこの問いに関する解答が先ほど話したニューロンの分化です。従来の研究でニューロンが人間の高次機能に大きく関与していることは明白でした。成人の海馬では、どんなに歳をとっても新しくニューロンが生み出されつづけていて、学習などで海馬の活動が高まると、新生ニューロンの数が増加することが報告されていましたが、この仕組みについては全く不明でした。今回僕が発見したのは海馬にシータ波が伝わることでニューロン前駆細胞が刺激され、ニューロンへの分化が促進されるということです」
アロガンの顔は説明が進むにつれ、すこしずつ厳たるものになっていった。
「まずは実験方法からです。実験ではマウスから海馬を含むスライスを作製し、電極によりシータ波刺激を加えました。すると、海馬にあるGABA性ニューロンが興奮し、興奮性GABAの入力を受けて、ニューロン前駆細胞にカルシウム流入反応が起きることがわかりました。このカルシウム流入反応が引き金となって、ニューロンへの分化にスイッチを入れる転写因子の発現量が増加し、最終的に新たなニューロンの数が増加することがわかったのです」
「…なるほど。それで結論は?」
「いわゆる実行機能の低下を防げるかもしれないということです。人間の行動を制御する高次の認知スキルを老化させずに維持できれば、賢明な判断をより早く下せるようになり、集中力と記憶力が向上することが見込めます。もしかすると、脳を若返らせるということも夢ではありません。またうつ病などの精神病患者では海馬の新生ニューロン数も低下することがわかっています。となると、そういった疾患に対する薬剤としての活用も可能かもしれません」
アロガンはしばらく黙っていた。何度か資料をめくり直し、机にパタンと投げ捨てると、大きなため息をついた。
「簡潔に言おう。君にはがっかりだな。もう少し優秀な生徒かと思っていたよ」
彼の一言で部屋の空気は一気に支配され、何倍にも重さになってグッドウィルに降りかかった。
「具体的にどこに不足があるか教えていただけますか」
無意識に体が身構えていたグッドウィルは敵意を含んだ声色で尋ねた。
「ニューロン分化の仕組みを理論的に説明したところは褒めてやろう。確かにその解明は検証の余地があるかもしれん。もちろん詳しく見てからだが。だが、実行機能が向上するという仮説は抽象的かつ曖昧すぎる。君は実行機能という人間の賢さの一つに焦点に当てたに過ぎないんだ。人間の脳の中に細胞がどれほどあって、一つの機能のために何種類の細胞が作用していると思っている。賢さの要素一つを上げて、人間が賢くなるというのは早計だろう。単語こそ立派なもんだが、すこし空論すぎるな」
このようなアロガンをこの二ヶ月間で一度も見たことなかった。初日に会ったアロガンとはまるで別人だった。眉間に寄った皺、極端に曲がった口角、獲物を狩る老獅子のように鋭く冷酷な眼。グッドウィルを見つめるアロガンは、高圧や威圧という言葉に形を与えたかのようだった。
「確かに結論に根拠はありませんが、それはあくまで可能性の話を…」
アロガンは話を聞く素振りを一切見せなかった。
「課題はまだまだある。仮に君の仮説を実行したとして、説を立証するために被験者の健康と環境的、精神的ストレスをも管理する必要があるのはわかっているのか?ストレスは脳組織を老化させる。血流で運ばれるグルコース、ビタミン、ミネラル、脂肪、アミノ酸、電解質などの栄養素は脳にとって欠かせないものだ。当然、実験が長期化するなら老化による脳細胞の減少も考慮しないといけない。つまりだな、ニューロンが減る方法はいくらでもあるのに、簡単に検証できるわけがないだろう?マウスですら容易ではないのに人間でなんて、土台無理な話だ」
「それはそうですが、それを可能かどうか判断していくための報告であって…」
「それにだ、君は脳が若返る可能性もあると表現したが、それはどの年齢を対象にした話だ?仮に若年者の脳でこの実験を行う場合、それ以上の脳のスペックを強制的に与えるようなものだ。どう言った効果が得られるかわからないし、それこそ神の所業だとわかっているのか?…いいか。君はわかっていないようだから教えておく。今、君は小学校で自由研究を提出しろと言われているわけじゃない。権威あるアロガンのもとで、研究成果を挙げろと言われているのだ。できるかもしれない、これから考えるなんて不確定性のあるものは望んではいない。必要なのは確実と完璧だ。こんなものでは許可は下ろせない」
「しかし…」
「聞こえんのか。却下だと言っているのだ」
アロガンは一際大きな一言で会話を継続する意思がないことを示した。一言で場を制されてしまったが、グッドウィルは当然納得できなかった。アロガンはため息混じりに続ける。
「研究自体は悪い線はいっていない。だが、一度優秀な人間のもとで経験を積んだ方が良いことも確かだろう。この研究は私が引き継ごう。今後しばらくは、私がこの研究の主任となって進め、君は私のヘルプをこなしていってもらおう。それで良いかな?」
グッドウィルの顔から滲み出ている答えを受け取ったアロガンは手を突き出して彼を制した。
「私は否定の言葉が聞きたいのではない。良いか、これは君のために、そしてこれから失敗するであろう研究のために提案しているのだ。本来なら私に断られた地点で君の研究は終わっている。それを私とともに復活させ、さらなるものへ昇華させようといっているのだ。わかったな?」
大きな権威のもとにグッドウィルは下るほかなかった。アロガンは満足そうに頷くと、今日は帰るようにと伝えた。
帰り際、グッドウィルは資料とデータは他にないのかと尋ねられた。それだけだと答えると、グッドウィルはアロガンの研究室を後にした。
一週間後、グッドウィルはあの裏山を彷徨っていた。一週間前と現在置かれている状況の脈絡の無さに自分自身心底驚いていた。この一週間で青年グッドウィルは死んだ。
あの日、帰宅してからのグッドウィルは泥のように眠りこけた。翌日、今後のことについて尋ねようとアロガンの研究室に向かい、扉の前でノックをしようとした時だった。扉越しにけたたましい着信音が鳴り響き、その直後にアロガンの声が中から聞こえてきた。入室を中断したグッドウィルは、扉の横で立ち尽くしていた。当然、盗み聞きをするつもりなどなかった。長くなるなら出直そうかとも考えていたが、二、三分後には壁にへばりつくこととなった。
「ああ…もちろん順調だよ。それが思わぬ収穫があってね。例の生徒が思った以上に優秀だったらしく、彼の研究を私が行うことにしたんだ。本来ならちょっと話を聞いただけですぐ却下して、私の研究を手伝わせようと思っていたのだけれど、予想以上に出来が良くてね。私が引き継ぐという形で利用させてもらうことにしたんだ。…いやいや、盗んだなんて人聞きが悪いじゃないか。実際そう言われてはぐうの音も出ないが、例えばそこに金のなる木の種子があるとしたら誰でも蒔いて水をやるだろう?私もそうしたに過ぎないのだよ。いやあ、それにしても、若者とはなんと扱いやすいものか。どれほど青い芽でも挫折一つを経験させればたちまち自信を無くして伸び悩む。そうなればあとは私の元へ引き込むまだけだ。何個か嘘もついたがな。嘘も方便というやつだ」
腹のそこから熱く煮えたぎる怒りが湧いて出て、それは一分と経たないうちにそれは藍色に反転した。グッドウィルは底なしの阿保だと思った。アロガンに対してではなく、策略に気づけなかった自分自身に対してだった。今まで自分は誰よりも賢く、自分以外は下だと嘲り、見下していた。しかし、今、愚かだと思っていたものに騙された自分は、さらに愚かなのだと言わざるを得なかった。
尊大な自尊心を傷つけられたグッドウィルは、帰宅するとすぐにベッドに横たわった。しばらく虚ろな時間を過ごしていたが、携帯の着信音で我に帰ることになった。ジミーからだった。
「もしもし、ジミーだけど」
「ああ」
「今時間いいかしら?」
「ああ」
ジミーは黙りこくっていた。
「要件はなんだい?」
「急で申し訳ないのだけれど、真面目な話がしたいの」
一息入れた後、ジミーは言った。声には覚悟が籠っていた。
「今のあなたにとって私は特別かしら?」
ジミーの意図を理解していたグッドウィルは淡白に答えた。
「いいや」
「そう」
ジミーの大きな声に動揺は見られなかった。通話越しに微かに息を呑む音が聞こえた。
「あなたと付き合う時には時間が必要だった。あなたの変化の速度に私の心が追いつかなかった。けれど今は必要なさそうよ。…私たちもう終わりね」
「ああ、そうだろうね」
「…本当にあなたは変わってしまったのね。私が好きだったのはあの頃の純粋な彼だったのよ」
重い沈黙が流れた。左手で持つ携帯機も重くて仕方がなかった。グッドウィルは電話を切ろうとした。
「私は…まだ…」
携帯電話の向こう側で小さくそう聞こえたが、最後までは聞かなかった。
この日を境にグッドウィルは大学へ行くのが億劫になった。正確には必要最低限の生活に従事するようになった。もちろんその必要最低限に大学や外出、研究などが当てはまることはない。何をする気にならなかった。今振り返ると、燃え尽きてしまったのだろうと思う。そしてそれの意味するところとは、自分の胸で燃えていた灯りは見せかけだけは大きく盛っていたが、指先のマッチ棒よりも小さく脆弱なものなのだと悟った。
それから三日後の早朝、また事態が動くことになった。繊細で薄く脆い朝の憂いを携帯電話がかき消した。地元の総合病院からで、父が危篤なので親族に連絡しており、可能であれば今すぐにでもきて欲しいとの旨が伝えられた。グッドウィルは家を出て列車に乗ることとなった。それまでの無気力とは裏腹に体はまるで機械のように素早く支度を済ませた。午前七時頃、自宅を出てから総合病院に着くまでの八時間程は携帯をバックの中に入れていた。ここで携帯を握る手の強さで愛の強さが測ることができるのだろうと思うと、自分の無関心さにやはり驚かざるを得なかった。
結論から言うと、生きている間に父と会うことは叶わなかった。列車に乗って一時間も経たぬうちに携帯を通して、必死の治療も虚しくといった文言とともに臨終が伝えられ、この事件は呆気なく幕引きとなった。
グッドウィルが到着した時にはすでに死化粧が施された後だった。霊安室で数十分死体を見つめた後、看護師から事情を聞いた。父は勤務先で倒れているところを発見され、心筋梗塞の疑いで搬送されたそうだ。心筋梗塞はひとたび発症するとその死亡率は四〇%と高く、多くは病院で治療を受ける前に死亡している。その一方、心筋梗塞で入院した人の死亡率は一〇%以下で、早期の治療であれば一命を取り留める可能性が高い。不幸なことに父の場合は残業で一人残っているところ発症したと思われ、朝方病院運ばれたことを考えると倒れてから九時間以上時間が経っている可能性があった。看護師が言うには、運ばれた地点ですでに厳しい状況だったということだった。
久方振りにして最後の面会を終わらせたグッドウィルは待合室の片隅で一人座っていた。事態に一段落がつき、小休止にはうってつけの静かな空間だった。尤も小休止と言うにはあまりに長い時間だったが。
グッドウィルに悲しさはなかった。代わりに胸の中を占めていたのは虚しさだった。自身の記憶の中ではいつも父は優しかった。始めは家庭の不出来を補完するための必要愛であって、グッドウィルの知能向上とともにそれは純真で真実の愛へと昇華したのだと思う。けれど、それに釣り合うような気持ちはグッドウィルにはなかった。
過去を振り返る時間は長かったそして、深い長考の末、意を決してあの山へ向かうことにした。
時刻は午後八時。すでに陽は落ち、山は闇に包まれていた。地形は把握していても、暗闇の中を進むために目的地までは時間がかかった。意識は半ば朦朧とし、その頼りない知能の半分を使って歩いていた。もう半分には空っぽが詰まっていた。
真っ先にあの泉を思い浮かんだ。その考えは十分に傲慢だと思うが、そのほかに思い浮かばなかった。勾配のある坂を登っていると、一際地面が盛り上がった場所に出る。その先にあの洞窟が暗闇の中で口を開けていた。洞窟内の肌寒さに鳥肌が立つ。グッドウィルは薄目でよろよろと歩いていき泉の横で座り込んだ。するとどこからか小汚い鼠が現れて、彼の側へ近寄ってきた。
「やあ、イグノランティア、知識が欲しくなったのかい?」
鼠がちゅうちゅうと鳴いた。
「今にあげるよ。これで僕は元通りだ」
鼠は真っ黒な目でグッドウィルを見つめている。
「いや、あるいは何も変わらないのかもね」
もう一度鳴いて鼠はどこか闇へ消えていった。
グッドウィルは眼を瞑った。
地位、名声、立身出世。それらへと誘惑する金、傲慢。
失われた優しさや人情、得られた打算的恋愛。
過去、思い出、身に余るほどの純真。
そして、夢や若さ、頭脳や知識。既知と無知、成熟と未熟。
アロガンの思惑。
ジミーとの交際と決別。
父母との別れ。
愚かな自身。
「僕の人生で実ったものなど何一つなかった。本当に、本当に、自分は愚かだ」
グッドウィルはこれから来る文字通り死ぬほどの苦痛に思いを馳せながら、音も立てずに泉へとその身を投げた。
永見妙
冷たい雪の降る夜、一人の赤ん坊が産声を上げた。
「はあ…はあ…。あなた、ほら見て、私たちの子供よ」
ミザリエは憔悴しきった目でチャーリーを見つめる。その手には助産師から渡された小さな赤ん坊を抱えていた。
「ああ、見えてる。見えてるとも。俺たちの子だ。ああ、なんて可愛いんだ」
涙を抑えられないマスク姿の父が分娩台の側に近寄り子供を抱える。少々グロテスクな顔を見て、思わずそうこぼした。
「目を瞑っているんだね。写真や人形とは違う。本当の本当に僕たちの子供なんだ。二人の宝なんだ」
押し寄せる感動も束の間、後の処置を控える赤ん坊は助産師に取り上げられると、奥の扉へと消えた。分娩室には最後まで泣き声が絶えなかった。
こうして、グッドウィルは泣きながら生まれ落ちた。苦痛に顔を歪ませ、これから身に降りかかる全ての悲劇を思い憂いながら、生を得た。十年間、グッドウィルは成長した。しかし、それは人とは違ったものだった。
ある夕方、ミザリエがいつものように部屋の掃除をしている時、外から帰ってきたグッドウィルが楽しそうにスキップをしながら、母に近寄った。
「ままがこれがたべよ、りょりしよ」
グッドウィルはそう言って、手を差し出す。紅くぬるぬるとした手のひらにはぐったりとして、少し口を開けたネズミを掴んでいた。ネズミがぴぎゅうと鳴く。ミザリエは思いも寄らないものに叫んでしまった。
「なんでこんなもの持ってるのよ!早く捨てなさい!」
そう言うと、彼女はグッドウィルの手を強く叩いた。ネズミはゴトンと床へ落ちる。赤くなったグッドウィルの手を見て母ははっと我に帰ると、今度は息子の手を強く握りしめた。
「ごめんなさい、ちょっとやりすぎてしまったわ」
良くなかったわと、母はグッドウィルの優しく両手を包み込む。今や願いとなった口癖をボソリと呟いた。
「おねがいだから、エライ子でいて」
当の本人はというと不思議でならなかった。母がサプライズに喜ばない理由、自分に罵声を浴びせた理由、自分の手を叩いた理由、そしてその後に泣きながら自分の手をさする理由。ひとつとして理解できなかったのだ。本人の中にあったのは喜んでくれるという低次な思考だった。彼はどうすれば良いのかわからなくて、立ち尽くして母を見ていた。ジンジンとした手の痛みはなかなか引かなかった。
その晩、目が覚めたグッドウィルは自分の部屋からトイレへ向かっていると、リビングで夫婦の会話が聞こえた。
「私…もう耐えられない。あの子のことを理解できないの。今日の夕、あの子が帰ってきたと思ったら、手にネズミを持っていたの。しかも血まみれのネズミをよ。あの子は家の前で見つけたって言っていたけれど、あの子はもう十才よ?普通なら気持ち悪がるものなんじゃないの?」
「まあ、落ち着いてよ。確かにあの子は普通の子とは違うかもしれないけれど、お医者さんも言ってたじゃないか。あの子に異常はないし、成長には個人差があるって」
「五年よ?普通の子が二年で会話できるのに、あの子は言葉を発するのに三年、会話が成立するまで五年もかかったのよ?当時は話しただけでも奇跡だと思ったけど、普通じゃないわ。小学校には入ってから五年間満足に友達もできないし、挙げ句の果てには医者からも近所からも家庭環境を疑われる始末よ。学校の成績も最悪。診断書がなくて学校も手のつけようがないって匙を投げてるわ。それにあの子が学校でなんて呼ばれているか知ってる?ナッツのグッドウィルよ?これじゃあ、あんまりだわ」
次第に金切り声になっていたミザリエはついに泣き始めてしまった。起きるかもしれないからとチャーリーはなんとか落ち着かせようとする。扉の隙間から見ていたグッドウィルは、なんだか怖くなって足が針金みたいに固まって動けなくなってしまった。
「この間だって危ないから車と道路には近づかないでって言ったのに、私が目を逸らした一瞬で道路を横切ろうとしてて…危うく轢かれかけたのよ。こんなことがこれからも何度もあるなんて、私にはもう無理よ」
「無理なんて言わないで。僕等はいつでも乗り越えてきたじゃないか。不妊の時だって諦めなかっただろう?確かにあの時は絶望のどん底だったけど、それでもいつも僕らのそばには神様がついていてくれたじゃないか。そして、あの子達はいつだって僕らの天使なんだ」
「天使?」
母の声に一層ヒステリックが増す。振り回す彼女の手をチャーリーは間一髪で避けた。
「天使なんて言い方はやめて!あなたなんにもわかってないわ。そりゃそうよね。あなたが産んだわけじゃないもの。グッドウィルのことも、あの子ことだって、何にもわからないわよね。あの子は…少なくともあの子は生きてるのよ」
泣くことしかできないミザリエはそれ以上何も言わなかった。チャーリーも完全かける言葉を失ってしまい、部屋には静寂が満ちる。二人が話している間、グッドウィルは怖くて逃げ出したいという気持ちしかなかった。そして、この無音に意を決して部屋へと逃げ込んだのだった。
その翌日、ミザリエとグッドウィルは何度目かわからない病院へ向かった。グッドウィルはなかなか行こうとせず、朝の支度は難航した。それも尤もで、痛い注射に何かわからないけどゴオンゴオンと音を立ててグッドウィルの体の周りを回るもの、さらには頭を締め付けるヘッドギアなど、グッドウィルからしてみると病院には嫌なものしかない。それらに動かずじっと耐えなくてはならないのが苦痛で仕方ないのなかった。
今日の来院の目的はウイルス検査だった。死んだネズミがどんな菌を持っているかはわかったものではないと母は心配していた。結果が良好だったことがわかると、グッドウィルはすぐに帰宅を許された。今までよりも早い帰宅に車の中でグッドウィルはご機嫌だった。帰宅後、ミザリエはグッドウィルを椅子に座らせた。
「グッドウィル。いい加減あんなことはやめなさい。もう二度とネズミには触っちゃダメよ」
「ぼくの…なにのよいない?」
「危ないウイルスがたくさんいるからよ。噛まれたりでもしたら大変なんだからね」
「ちりたい。ぼくわ…のなにがよい…よいない?」
「…なんでいけないか本当にわかってるの?」
「まんまあ」
グッドウィルは小首を傾げている。近くにある人形を手に取った。
「やろ」
魔が指すのは一瞬で、頭を床にぶつけるだとか目に人形をぶつけるだとか、そんなことは煮え滾った頭の中にはなかった。ごとごとと音を出しながら跳ね転がると、グッドウィルはやはり泣くほかなかった。
その日、床についたミザリエが見たのは恐ろしいあの日の夢だった。彼女はきっとグッドウィルのせいだろうと思った。夫婦二人は最寄りで最も大きな総合病院にいた。二才のグッドウェルは父に抱えられていた。青白い廊下の奥の扉を開けると、診察室につながっていて、一人のメガネをかけた老人がいた。パイプ椅子に夫婦が座ると、老人は話す。
「辛いかもしれませんが、よく聞いてください。お腹の中の赤ちゃんに染色体異常が確認されました。おそらく無事に赤ちゃんを産むことはできません。自然流産という形になるでしょう」
「そんな…どうにか、どうにか産んであげる方法はないんですか?」
「こればかりはどうしようもありません。たとえなんとかして子供を産んでも、子供が生き残る可能性は万に一つもありません。本当に残念ですが、赤ん坊を諦めるほかありません」
母は泣き崩れた。片手で顔を覆い、もう片方は自身のお腹にあてている。父は背中に片手で摩ってあげていた。グッドウィルはというと、父の片腕の中で壁のポスターを必死に見ていた。母は大粒の涙を流していた。
この後の出来事は、ミザリエにとってもグッドウィルにとっても忘れられないものだった。
帰宅した夫婦二人の間にはなおも重く苦しい空気が漂っていた。
「なもわなに?」
グッドウィルの手には胸にNemoと書かれたちいさなテディベアがあった。苦痛で母の顔が歪む。
「なで、なにでママはなくの?どおして?うれい?」
「嬉しいわけないわ。悲しいのよ。もうあの子のことは終わったの。これ以上ママを悲しくさせないで!」
今までのしつけとは違って少し、苛立ちと悪意のこもった声だった。それを聞き分けられないグッドウィルは、その態度にまるで新しいおもちゃを得たような、楽しい気持ちになった。
「にええも、にええも、なええも、…なえにも?」
「もうやめて!」
そう言ったミザリエはグッドウィルの頬を平手打ちした。慌ててチャーリーが止めに入ったが、母は自分のしようとしていることをやめようとはしなかった。
「あんたなんて…あんたなんて!」
グッドウィルは大声で泣いた。この日は一段と頬が痛くて仕方がなかったのだ。
ウィリアム家は歪みがさらなる歪みを産むサイクルに膠着し、その家庭は泥沼化していた。つまり、グッドウィルが異常な行動を取り、母がなぜこんなことをしたのかと怒号で問い詰める。いつからか、ウィリアム家では日常茶飯事となってしまった。自我の目覚めた幼児が自身の判断で行動し、その結果大人の理解のできないようなことをするのは決して異常ではない。問題がグットウィルの言語的、思考能力的、学習的な知能の遅れだったのは言うまでもなかった。
グッドウィルの学校生活は彼の家庭に劣らず劣悪だった。グッドウィルがいつものように一人で帰ろうとしていると、二人組が話しかけてきた。ひょろひょろのっぽがティム。ずる賢くて、いろんな悪知恵を働かせてはグッドウィルを騙している。この間は池に突き落とされた。ずんぐりとして太っちょの方がバルスで、図太い神経と横暴さが取り柄の彼は喧嘩もいつも負けなし。その力強さでグッドウィルに暴力を振っているのだった。二人は四六時中どこへ行くにしても一緒で、いつもグッドウィルをいじめる機会を探していた。
「おいナッツのグッドウィル、お前は根性なしだろ?最近噂になってるんだけどよ、この学校の裏山の奥の洞窟に化け物がでるんだとさ。そこまで案内してやるから、お前確認してこいよ」
「にかない。ままを、を…がぁ?おこらる」
「ナッツのくせに生意気だな。お前は口答えせずに俺たちの言うことを聞いとけばいいんだよ」
バルスが右腕を掴むと、すかさずティムが左へ潜り込んできて、その両手で細い左腕を握りしめた。グッドウィルは身を振るって抵抗する。二人はそんなの関係なしに裏山へと連れていった。
裏山は木々が鬱蒼としており、背丈の何十倍もの高木が彼らを見下ろしている。動物か何者かが常に一定の距離を保ってこちらをのぞいては、木々の奥へと消えてゆく。いつのまにか青い空は深緑色の天井に変わっていた。二十分ほど歩き続ける。
「おい、グッドウィル。お前怖くなってきたんじゃねえか?いまにもチビっちまいそうなんだろ?」
「へへへ、怖くなってるに決まってるよ」
ティムは薄汚い笑みを浮かべている。
「にかない。かえってじゃないとおこらる」
「なんだてめえ、強がってんじゃねえぞ!」
大きな声に反応したカラスが一斉に飛び跳ねた。
「もうちょっとで着くはずだ」
前日の雨のせいでぐちょぐちょとぬかるんだ地面を進む。勾配のある坂を登っていると、一際地面が盛り上がった場所に出た。その先が真暗闇の洞窟がひっそりとあった。
「ここがあの洞窟だな。よし入ってこい」
「はいってこいたらうち変えれる?」
「ああ、入って無事戻って来られたらな」
戻って来られたらな、と繰り返すティム。二人はうすら笑いを浮かべる。
グッドウィルは躊躇なく洞窟へと入る。中はジメジメとしていて、肌寒さに鳥肌が立った。当然ライトなど持っていないため、暗闇の中を進むことになり、グッドウィルは薄目ですたすたと歩いていく。足音が洞窟内でこだまする。洞窟はかなり小さいようで、五分ほど歩いていると分かれ道にも出会わずに最奥へと辿り着いた。そこには花緑青色に光り輝く泉があった。半径二メートルもないが、底は見えないほど深いようで、泉縁には苔が茂っている。
グッドウィルは泉に惹かれるように側へ近寄り、中を覗いてみた。底は見えない。面白いものも何もなく帰ろうと、泉を背にした時だった。
これはまた珍しいお客さんですね。
グッドウィルは振り返る。そこにはなにも変わらず、泉が佇んでいる。
私は泉の妖精です。ここへ訪ねてくれたお礼に、あなたの欲しいものを一つ与えましょう。
「なんでも?」
摩訶不思議な状況に好奇心をそそられる。恐怖はなかった。すこし考えてからふと母の口癖を思い出す。
「本当になんでもいいの?」
ええ。
「ならエライ子?にして。ままがいつも言うの。エライ子、エライ子。まま泣くんの。かぁいそう」
それは良い願いですね、と微笑んだ。
どれほど賢い子になりたいのですか?
「うーん、ばろすとちむ?」
それでは、その二人を連れてきてください。そしたら、あなたのことを賢くしてあげましょう。
入り口に戻ると、二人の手にはスコップが握られていた。
「な、なあ、バルス。ここまでやる必要なかったんじゃないのか?わざわざ化け物がいるなんて嘘ついて」
「いいから黙って掘れよ。お前もぶっ飛ばされてぇか?」
「おーい」
二人は素早くスコップを背中の後ろへ隠す。
「うえ、思ったよりも早いぞ」
グッドウィルは二人に近寄る。
「いっそになかにきて。そしたらエライ子」
「こいつは驚いた。とうとうナッツの中身が空っぽになっちまったようだ。何言ってんだ、おめえ?」
「ようせい」
「ほう、じゃあその妖精とやら見に行こうか」
ニシニシと笑う二人。新たなおもちゃの種を見つけたのだから、水を注がずにはいられなかったのだ。ティムは洞窟の余りの暗さに尻込みしたが、バルスに殴られるのもまた勘弁だった。三人は洞窟へと入り、泉まで辿り着く。二人組は例の泉を覗くがそこには泉水があるだけだった。
「なんだよ。何もねえじゃねえか」
何もないじゃねえか、とティムが繰り返す。やめだやめだとバルスが帰ろうとしたその時、妖精がグッドウィルに語りかけた。
二人を泉に落としなさい。
不思議に思ったが、言われたままにグッドウィルは泉の縁に立つ二人の背中を突き押した。
「何すんだてめえ」
首から上を出してバルスが上がろうとしたそのときだった。泉は音もなく一瞬で二人を飲み込み、あっという間に二人は深い底へ姿を消していった。もがき苦しむバルスをグッドウィルはなにも言わずに見下ろしていた。
「ばろす?ちむ?」
代わりに答えたのは妖精の声だった。
今あなたはこの二人の知識を得ました。きっとエライ子になれることでしょう。
「妖精さん?二人は?」
それきり泉は何も応えなかった。グッドウィルはしかたなく帰ることにした。
グッドウィルの異変に最初に気づいたのは、クラスメイトのジミーだった。彼女は近所に住む赤髪の女の子で、三つ編みのおさげがトレードマークだ。言ってしまえば、彼女はグッドウィルのお世話がかりだった。会話が成り立ちづらいグッドウィルに話しかけてくれる唯一の友達で、心優しい彼女は同じクラスで嫌厭されているグッドウィルを気にかけていた。登校中のグッドウィルを見つけると彼女は隣へ駆け寄った。
「あら、おはようグッドウィル。今日は遅刻じゃないのね」
「そうだね、いつもより二十分早いだけだけど」
ジミーは眉をひそめて、グッドウィルの顔を覗く。さも当たり前かのように言うグッドウィルに違和感があった。
「…あなた、いつも何時に登校していたか覚えてる?」
「九時半頃だったかな」
「じゃあもう一個質問。あなた、今朝はどんなだった?」
「いつも通りだよ。八時に起きて朝食、その後にリュックに教科書を入れたりしてから家を出てここまで歩いてきたんだよ」
ジミーはその問答の中ですぐに違和感の正体に気がついた。会話に知性を感じるのだ。きちんとした言葉遣いは最初に気がついたが、ある一定の時点から今までの時間を答えられることはなかったし、今まで自分の行動を端的に述べるなんてことも到底できなかった。ジミーが最後に話をしたのは昨日のお昼頃で、バルスに階段下の人目が届きにくい場所で暴力を振るわれていたのを止めた時だった。
「どうも一晩のうちに賢くなったみたいね」
一方、グッドウィルはというとなにも変化を感じてはいないわけでなかった。ぼんやりと霞のかかった思考領域が晴れているという感覚があり、それはいつもよりも鮮明な思考として現れていた。道端の花が綺麗だとか、通りすがりの老人が顔馴染みの気がして、もしかしたら以前に会っていたかもしれないだとか、そんな程度のものだがそれもグッドウィルにとっては高度なものであったのだ。
しかしそうはいっても、やはり自身への認識は今までの自分に尾を引いて不変であった。自身の成長を知覚する時は決まって進行形ではなく過去形で語られるものなのだ。ちょうど赤ん坊が自身をメタ的な視点から俯瞰することもなく、知らぬ間に成長するように、グッドウィルは己の成長に気づくことなく賢くなった。その振れ幅の小さな知能向上に気づけなかったのが故に、ジミーの言葉に驚くことになった。
「僕が賢くなってるって?どうしてそう思うんだ?」
「どうもこうもないわよ。あなた自分でわからないの?傍目から見てもいつもと違うことは明らかなのに」
「いつもと違うこと…そういえば今日は寄り道せずにまっすぐ学校に来たんだ。普段なら気になった花を摘んだりしてたんだけど、そう思うよりも先に学校へ行かなきゃって思ったんだ。どうして僕はあんなにも衝動的だったんだろうね」
「わからないことだらけね。まあ話は詳しく聞くわ。とりあえず教室へ向かいましょ」
この日の学校は苦労の連続となった。クラスはたちまちグッドウィルの話題で持ちきりになった。隣の席の人、そのまた隣の席の人、その前後左右といった具合に、グッドウィルのことがクラス全員に広まるのに時間はかからなかった。思いもよらなかったのは中にはグッドウィルのことを格好良いといった評価する声まで現れたことだった。休み時間は次から次へとくる訪問者の対応に追われたが、それは幸せな不幸せで、クラスメイトとのほぼ初めての会話はとても新鮮だった。
「本当にあのグッドウィルなの?」
「なんだか雰囲気が変わったね」
「何があったの?」
突如として人気者になったグッドウィルをジミーは少し外から見ていた。
「ちょっとみんな、グッドウィルは忙しいの。ほら行くわよ」
今や必要のない案内人の役割をこなそうと、ジミーは彼の腕を取るといつものように次の授業に連れて行くなんてこともあった。
クラスの授業はこれまでにないほどにスムーズにこなすことができた。文法や物語の読解、以前はできなかった四則演算はもちろん、割合や図形の理解、紀元前まで世界中の歴史、社会構造や政治、今までは意味をなさなかった文章の羅列を余すことなく網羅することができた。不可能から可能への転換には決まって喜びを伴うもので、放課後には勉学に没頭し、図書館で本を読み漁っては、今までぼんやりとしていた日常経験を知識として結びつけもした。
それから気になる子もできた。ジミーだ。グッドウィルは自分が自分で思っている以上に彼女が側に付き添ってくれていたことに気づくことができた。きっと彼女がいなければ、学校生活は破綻していただろう。次のクラスへ遅れず参加できたのも、生き物係の仕事を手伝ってくれ、中庭のウサギたちが死ななかったのも、当時の彼なら絶対にできなかった宿題の数々も、全て彼女のおかげなのだ。それらを思うと、彼女に対してえも言われぬ特別な感情の若芽が出るのだった。
ジミー、クラスメイト、その次に気づいたのがミザリエとチャーリーだった。その日の晩、図書館に籠ったせいでいつもより二、三時間ほど遅く自宅に帰ると、台所に母の姿を見た。いつのものかわからない洗い物をしていた。
最近はほとんど会話がなかった。何が平手打ちの原因になるかわからないグッドウィルにとっては当然だった。
「母さん」
今夜は話しかけてみることにした。うまくいくような気がしたのだ。
「今朝はサンドウィッチ、ありがとう」
作り置きのせいで冷めていたことは言わないことにした。
「体調はどう?あまりよくないって言ってたけど」
毎朝グッドウィルが起きると、机の上にはプレートと朝食が置いてある。しかし、そこに母の姿はない。朝は決まって自室に篭っているのだ。必要最低限の世話、それが食事の用意であって、それ以外は知ったことではないといった態度だった。
以前、ノックもせずに部屋に入ると、そこには朝寝髪で目の下にびっしりと隈をつけた母がベッドでうずくまっていた。その時は一度で済んだが、その時の経験を糧に部屋には近寄らないようにしていた。痛みの伴う経験が彼にとって最も効用なのは間違いなかった。グッドウィルはその時に言われた「体調が悪いから」という言葉をよく覚えていたが、いつから家族がこのような形になったのかは判断がつかなかった。
肉体労働者の父はというと、朝早くから仕事で家を出ており、日中はほとんど顔をあわせることがなかった。二重苦に挟まれながらも彼は彼なりに家庭を支えていた。グッドウィルに決して暴力を振るうことはなかったし、機能しない母の代わりにグッドウィルの世話を行い、少しでも彼の居場所であろうとした。そんなチャーリーをグッドウィルは信頼していた夜の帰りをいつも楽しみにていた。
「ママ?」
返事はなかった。とりつく島がなくて、相手の様子を窺う。彼女の目玉はまるで透明なガラスの球体のようだったが、決してビイドロ玉のような美しさはなかった。もう一度声をかけようとした。
「グッドウィル?」
母がこちらを振り返る。その目に少しだけ光が射し入った。
「あら、今日は随分おそかったのね」
グッドウィルの体は無意識に強張ってしまった。
「図書館で勉強をしてたんだ」
母は目を丸くした。返事など土台期待していなかったからだ。その様子は明らかに自分の耳を疑っていた。例えばもし、赤ん坊に語りかけているときにはっきりした言葉で明瞭に返答されると誰でも驚いてしまうだろう。同じような反応が彼女の頭の中で起きていた。
「もう一度言ってくれない?」
「放課後、学校に残って勉強してたんだ。本を読んだり、今まで習った教科書を読み直したりね」
今度はグッドウィルが発声した文章の意味を理解できた。しかし、その裏で意味するものにはまだ理解が及ばなかった。
「勉強ってそんな…それにきちんと会話も…。一体何が起こっているの?」
「僕にもよくはわからない。けれど今日はなんだかすごい頭の中がスッキリしているんだ」
彼はテーブルにつくと、今日の出来事について話した。自分の体調やジミーとの会話、授業中の全能感とさえ言えるほどの知能的成長とそれに追随する知的好奇心の向上。彼は時系列順に明確かつ簡潔に伝えた。
母は彼の話を聞きながら歓喜していた。必死に首を縦に振り、一言一句に相槌を打った。自分の息子と初めて意思の疎通を図ることができたのだ。彼女は真にグッドウィルの心と自身の心が通じ合った気がした。
午後七時、その日のウィリアム家の食卓は豪華なものになった。母は父のもとへ電話をよこすと、今日は何がなんでも早く帰ってくるようにと連絡した。その後、彼女は彼が帰ってくる前に食事を用意しなくてはとは躍起になって用意を進めた。久々に車を出して一緒に行ったスーパーではあちらこちら首を振っては、メモに目を落とすという動作を何度も繰り返していた。ここまで忙しない母をグッドウィルは見たことがなかった。久しぶりに振舞われた贅沢なテーブルの上から暖色のライトが三人を照らし、その夜は初めて会話が弾んだ。
この日を境に家庭内の不和は徐々に緩和し、夕餉の食卓では以前にはなかった暖かな雰囲気が溢れるようになった。父も毎日ではないものの早く帰るようになり、共に時間を過ごすことも増えた。
その後もグッドウィルは日々を学業に費やした。放課後、二時間は机に向かうことをルーティーンとし、その結果は学校のテストのような目に見える形ですぐに現れるようになった。その度に笑顔を見せ、「エライじゃない」と褒めてくれる母のことを思うとなお一層研鑽した。
三年後、グッドウィルが中学生になる頃には、一般的な高校生の学習範囲を全てマスターしていた。一年と経たずに今までの不足を補填し、もう二年で本来身の丈には合わない分野、範囲へと手を伸ばしていた。
この頃のグッドウィルは学校が退屈で仕方なかった。学校の中ではなにもかもが学習したものばかりで、学内テストでは全てが満点、学内順位は一位を総なめにした。小学生五年生の頃のように未知との出会いに心踊ることは無くなり、授業は彼をただ無意味に縛るものとなった。友人に関しても同じだった。今まで友好関係を築いてきた友達のほとんどとは、会話をすればするほどその低脳ぶりと退屈な人間性が透けて見えてしかたがなくて自然と疎遠になった。その結果、以前とは違った一人の高校生活となったが、それに不満は感じなかった。
学校生活を唯一彩るものが放課後のルーティーンだった。未知が既知となった今、その楽しみは全く違う方向へと変化した。その変化とは、その時間をジミーと共に過ごすようになったことだ。それほど大きくない街に住む二人は小学生から同じ環境にあり、ある日、ジミーから勉強を教えてくれと頼まれてから週に三日ほど指導をしていた。
とある日、いつものように図書館の学習スペースの隅で机を隣り合わせにしてテキストを解いている時だった。いつからか沸いた疑問を解くために彼は胸の内を明かしてみることにした。
「ジミー、君に聞いてみたいことがあるんだ」
ジミーは手を止めてグッドウィルの方を見て、「ええ」と返事をした。
「君は今まで僕にたくさん良くしてくれたよね」
「ええ、まあ、そうかもね」
「僕がまともな小学校生活を送れたのは間違いなく君のおかげだ。それにはとても感謝してる。でも一つ気がかりなことがあって、当時の君はどうして僕を手助けしようと思ったの?」
「うーん、どうしてねえ…難しい質問だわ。こう答えることにしましょう。あなたが危なっかしいと思ったからよ」
歯切れの悪く聞こえた彼女の言葉を脳味噌に落とし込んでみる。それからこう尋ねた。
「じゃあもう一つ、君は僕のことをどう思ってるの?」
「……」
妙な時間が流れる。彼女は少し間を置いてからばつの悪そうな顔で言った。
「とても賢いと思ってるわ。ちいさい頃では考えられないくらいにね。何かあったのかって心配になる程よ」
グッドウィルにとって彼女と過ごす時間は心地よかった。ほんのりと暖かさを帯びて、今までのグッドウィルの人生にはなかった何かしらを感じ取らせてくれ、彼女と接すると彼の中では何かが育っていくのような感覚があった。それが何かは彼にはわからなかったが、それは良いという言葉で表現するだけではあまりにも複雑で、放ってはおけないないような何かであった。
彼女の態度を何かをはぐらかし、本質から逸らそうとしているかのようだった。この問答では満足のいく答えは得られなかった彼はどこか急いたように続ける。
「自分でもなぜだかよくわからないけれど、僕は君のことを必要以上に考えてしまっている気がするんだ。手の打ちようがなかったから、こうして君に打ち明けてみることにした。ジミーは何かわからないかい?君にも同じようなことがあるんだろうか?」
今度はもっと長い沈黙だった。グッドウィルは彼女の顔を見つめ続けていたが、彼女の表情をなんと表現すればよいのかわからなかった。
「グッドウィル、あなたはなぜかわからないけれど突然賢くなって…それはもちろん良いことだわ。けれど、それは良いことばかりではなくてね。私だってわからないことだらけなの。すこし時間が欲しいわ」
彼女はこぼすように「ねえ、グッドウィル」と言うと、別れをつげて図書館を後にした。
一人残されたグッドウィルは惚けた頭で机に向かっていた。彼の頭の中を巡るのは彼女の沈黙と表情だった。賢くなったことで何かしらの不利益を彼女に与えた可能性が思い浮かんだが、それはすぐに否定した。最も彼を悩ませたのは私にもわからないと言う言葉だった。その言葉を飲み込むには、彼女の言葉はあまりにも趣旨に欠けていて、前後の文脈が破綻している。彼女が時間的猶予を得て何を考えたいのかすらも、彼にはわからなかった。
帰宅する前にジミーの座っていた椅子を片したが重く感じた。
三週間が過ぎた。あの日以来、ジミーが放課後に図書室へ姿を現すことはなく、気がつくとグッドウィルも足が遠のいていた。廊下ですれ違った時には挨拶を無視され、同じクラスでも話すことはなかった。次の授業の準備と教室への案内も無くなってしまい、異変があったのは明らかだ。もちろんグッドウィルは思考をとめどなく回し続けたが、何一つ成果はなかった。足掛かりを得るのはさらに一週間後で、身近なところだった。
深夜、グッドウィルが自室で就寝しようとしていると、どこからか物音がした。しばらく無視をしていたがどうにも止みそうにないから、出所を探ってみることにした。ところがその詮索はすぐに中止となった。なぜならその音が夫婦部屋から聞こえる音だったからだ。グッドウィルは男女の色恋や情事は知識としては当然知っていたが、もちろん自身に経験はなかった。ここ数年、良好に向かっていた夫婦は大きな山を越えてさらに固い愛を結んでいたことは気づいていたが、その場面に出くわすのは初めてだった。
思春期の青年にこの情事が与える影響は十二分で、今までグッドウィルの中で眠っていた異性に対する興味というのを遅咲きで開花させた。そして当然その対象はジミーへと向かい、始めて自分が彼女に恋愛感情を抱いているのではないかという結論を導き出した。眠気などとうに忘れ去ったグッドウィルが最初に行ったのは、溢れた知識欲を抑えるために心理学関する書物を探すことだった。
そうして計画を企てることになった。
よく晴れた日曜日であった。グッドウィルは母と共にハイキングに来ていた。頬かすめるそよ風が気持ちよくて、木々に止まった雛鳥たちがぴいぴいと鳴いている。
しばらく歩くと高い木々で足元が翳り始めた。
「休憩が必要かい?僕はもっと早く行けるんだけど」
心配の言葉をかけるが言葉だけに過ぎず、その足は遅くなる様子はなかった。
「私ももう歳なのね。あまり遠くへは行かないで。一緒に行きましょう」
乾いて固まった地面を進む。勾配のある坂を登り、一際地面が盛り上がった場所の上に立つ。その先が真暗闇の洞窟がひっそりとあった。
「見て、母さん。あんなところに洞窟があるよ。天然なのかな?興味が湧いてくるね。ちょっと入ってみない?」
「いいんだけど、ちょっとだけ休憩してからにしよう」
母はリュックからボトルを出すと水分補給をし、五分ほど休憩をした。
父は連れてこなかった。必要がないし連れてくると何かと面倒だと判断したからだった。
二人は暗くジメジメとした洞窟へと入る。中はやはり冷えていた。
「ライトを持ってきてるなんて用意がいいわね、グッドウィル」
グッドウィルはスタスタと歩いたために、二、三分もせずに奥まで到着した。
「分かれ道もなかったし、小さい泉があるだけみたいね。綺麗に光っててなんだか神秘的じゃない」
おそらく光に反応する苔のせいだよ、とグッドウィルは心の中で呟く。
全てがグッドウィルの狙い通りだった。ここまでの用意に時間はそうかからなかった。怪我をしたから救助してくれ、気になる洞窟があるから一緒に調査にきてくれ、そういうシナリオも考慮した。あの日以降、グッドウィルは時々洞窟に訪れては調査をしており、成果こそなかったものの、おかげで座標、周辺環境、構造、生息生物、気温や湿度、過去の地質学的、考古学的または神話学的な文献、全てがグッドウィルの頭の中だった。そうはいっても慎重に慎重を重ねて、前日の下見は怠らなかったのだが。
母は泉を覗き込んで観察していた。
グッドウィルが彼女の後ろに立つと、いとも容易く母は泉の中へ落とされるのだった。
よくやりましたね。
頭の中でそう響いた気がした。
一人帰宅したグッドウィルによって捜索状が出され、警察は最後に接触していたグッドウィルを調査することになった。彼の主張は自分が目を離した隙に彼女が一人でどこかへ行ってしまったというもので、少々不可解な点はあるものの、物証がなく死体も見つからないということで、この一件は不幸な事故、あるいは一過性の高い自殺として処理されることとなった。グッドウィルの近辺が落ち着くには少し時間がかかったが、こうして計画は第二段階へと移行することになった。
自分の母親を殺めるという行いをしたグッドウィルが最初に行ったのは、過去の自分の行いの重大さに気づき猛省するなどということではなく、単なる仮説の検証と状況の整理だった。グッドウィルは机に向かい、白紙を取り出すとさらさらとに書き上げていく。
まずは現在の状況。後日、母を一人探しに行く健気で可哀想な息子を装って山に入り、死体が浮かび上がってきていないことを確認した。今回の犯行で注力したのはできる限り一度目の再現をすることだ。ティムとバルスの場合、死体が発見されていないことから察するに泉に沈んでいる。水に突き落とされた人間は条件が揃えば膝丈ほどの水量でも殺すことができるが、死体を沈める場合には少し工夫を施す必要がある。今回は母を落としはしたが死には至らなかったため、無理矢理押し込んで溺死させ、その後、母のリュックに重しとなるようなものを入れた。万が一死体が腐敗性ガスによって上昇してくる可能性を考慮し、確認へ向かったが結果は良好だった。もう少し効率的な方法もあったかもしれないが、一度目の再現に重点を置いた結果だった。
次に仮説一の妖精の存否について。一度目の時の記憶はかなり曖昧なもので、ほとんど無いに等しかった。ティムとバルスともに行ったことでさえ、周りの証言がないとわからなかったほどだ。そんな中唯一覚えていたのが妖精との会話だった。泉に人を落とせばその人の知識を得るという会話が頭の中には残っていたのだ。当の本人だがこれについては疑わしく思っており、幼い自分が作り上げた妄想だと考えていた。しかしその一方で、妙に印象的なこの会話と他人から聞いた状況を合わせるに、やはりこの方法で自分の知能が上昇したと認めざるを得なくもあった。これがこの計画で検証したかった仮説一である。
確かにあの時、頭の中で声が聞こえた気がした。しかし、あの声は過度な興奮状態に陥った自身が作り出した幻聴という説を拭いきれず、妖精の実否は分からずじまいに終わった。
次に仮説二の愛の獲得について。こちらが本命であって、仮説一は副次的なものだ。仮説一が真だった場合、母を落とすことで「愛」という知識を得られるのではないかというのが仮説二だ。一度目はおそらく二人の友人(話を聞くに友人ではないが)の知識を得たいというのが叶えられたのであり、これに則って父を愛する母を落とすことで愛の正体を知ることができるのではないかというのが今回の狙いだった。
これは予想していたことだが、愛を知るという目的があまりにも抽象的で、事後目に見えてわかる変化が得られなかった。殺人後から約一週間観察を行ったが、自身に何かしらの変化は感じられなかった。こちらについては第二段階で確認することになるだろう。
一通りメモを書き終えると、初めからざっと目を通していく。全て読み終えるとグッドウィルは天井を見上げた。こうして目の前に自分の悪行を理路整然と書き上げてみると、グッドウィルの胸には罪の意識が湧いて出た。けれどそれは脆くて希薄かつ反省を含まないもので、彼の思う罪の意識とは、自分は刑法に反して罰を受けるに値する行為を行い、それを今後隠し通さなければならないというひどく実用的な罪の意識だった。
グッドウィルは我ながらとても傲慢だと感じた。彼女には彼女の罪があり、幸い顔周辺にはないが、それらは今でもずっと消えずに彼の肉体に刻まれている。怨恨が動機ならまだ筋も通っているのだが、そんなものは微塵もなかった。旧約聖書「創世記」の中でイブが蛇に唆されて知恵の実を食べたが、グッドウィルが誘われたのもやはり神秘を孕み、全能にさえも届きうる知恵だった。法知識を備えたグッドウィルが、殺人を悪いことという簡単なことをわかっていないわけはない。ただそれよりも知的好奇心が優っただけのことだった。
グッドウィルは立ち上って一息つくと、紙をくしゃくしゃにして暖炉へと投げ捨てた。
母の殺人から二週間後、彼は登校を再開した。事件が発覚してからは学校に休みを申請しており、この日から何食わぬ顔でまた学校生活を過ごし始めるはずだった。学校に着いて早々、名前は忘れてしまったが、同じクラスである女子生徒にこう話しかけられた。
「ねえグッドウィル、お母さんのことは…その…残念だったわね。けれど、安心して。私たちはあなたの味方で、あなたは一人じゃないわ」
休みの理由は教師のみに伝えていたが、どういうわけかクラス全体に事件のことは広まっていた。しかし、それはそれで後に都合が良かった。
「ああ、ありがとう」
こんな時は感情に従順になって慰めるのかと軽く軽蔑すると、ここではないと思いつつも練習通り涙を流した。
再開した学校生活で彼は一つのことを心がけた。それは意図的にジミーを避けることだった。といっても極力彼女と出会って会話が発生しないよう立ち回るだけで、要は相手を焦らし、機会を待つだけことだった。
学校が始まってから三日間、教室やカフェテリア隣に来た彼女をグッドウィルは「少し体調が悪くて」とだけ言い、その場を去るようにした。そして翌日席を開けたグッドウィルが戻ってくると、机の上にメモが貼ってあり、そこには「今日の放課後、図書館で待ってる。話がしたいの。ジミー」と書いてあった。
放課後、二人はいつも図書館で落ち合い、以前のように自学スペースの隅で机を隣合わせに座った。先に口を開いたのはジミーだった。
「お母さんのこと、聞いたわ。大変だったわね。その…体調はどう?」
「悪くはないよ」とあたかも悪そうに言う。
「そう…お父さんもさぞ辛かったでしょうね」
グッドウィルは黙りこむ。いつも静かな図書館だが今日は恐怖を感じるほどで、その沈黙がさらに彼女を追い詰める。
「私はね、グッドウィル、貴方を心配してたのよ。なかなかじっくり話す機会がなかったから…」
グッドウィルは機会を伺っている。
「学校でも元気ないみたいだし…そりゃああんなことがあったのだから元気出せって言う方が無理だけど」
相槌を軽く一回返すと、再び沈黙が降りた。すると今度はグッドウィルが口を開いた。
「ごめん、ジミー、なんて言ったらいいのか…」
グッドウィルは彼女の真正面に捉えて、まっすぐと目を見つめる。
「どうやらこういう時の僕はとても無力らしい」
ジミーを見つめる瞳から涙を流した。
「今だけでいい…今だけでいいから…僕のそばにいてくれないか」
グッドウィルがそう言い切るよりも前に、ジミーはグッドウィルを抱きしめた。力強く抱きしめられた彼女の腕に応えるように、グッドウィルは彼女の少し小さな体を抱きしめ返した。
「もちろんよ」
震える声でジミーが言った。顔は見えないが、泣いているのがわかった。
そうして彼らは数分で、永遠とも思えるような濃密な時間を過ごした。抱きしめた彼女の体はとても暖かかった。
泣き止んだ彼らは己の感情を余す所なく吐露しあった。何もかもグッドウィルの思い通りだった。まず接触を減らして不安を増大させ、さらにようやくの会話で本心を確認できるというカタルシスと自分を頼っているというアンダードッグ効果を引き起こせば良いだけのことだと考えていた。結局のところ心というのは信号に過ぎないのだとつくづく感じた。
そこからはとんとん拍子に事が進んだ。徐々に距離を縮めていった彼らは交際を始めることとなった。告白したのはジミーからで、回答は文句なしのイエスだった。こうしてグッドウィルは晴れて退屈の学校生活から一転し、愛する彼女と共に過ごす最高の学園生活を送る事となった。
中学校を卒業後、地方の高校へ進学するとさらに勉学に注力した。この段階ですでに高校科目もマスターしており、暇を持て余した彼が次に選んだ教材は法学、社会学、経済学、言語学、心理学、人間科学などあらゆる分野の大学参考書だった。中でも彼の興味を引いたのは、生物学だった。自身の知能向上の手がかりになるのではと思い、人間の脳の構造や知識の入手方法、そもそも知識そのものが何であるのかをなどを調べてきた。その関心の延長線上にあったのが生物学だった。
高校を卒業すると同時に有名大学へと進学した。大学では生物学を専攻し、人体の構造をより専門的に研究していくことにした。大学から給与型の奨学金を受け取りながら通学となり、通学時間を考慮した結果、大学近辺へ引っ越すこととなった。
ジミーは高校を卒業後、実家のパン屋で働きながら家の手伝いをしていた。二人の交際はなお続いていたが、グッドウィルの遠方への引っ越しにより、時間的、空間的距離ができてしまうのは仕方のないことだった。会う頻度はほぼ毎日から二、三ヶ月に一度に下がってしまったが、これは二人が話し合って下した決断であった。初めは彼女の感情を揺れてしまったが、将来の見通しが立ち次第同棲を始めるという約束を交わした二人の仲は雨降って地固まることとなった。
満を持して始まった大学初日、配属先となる研究所の教授アロガンと顔合わせをした。白髪の混じった口髭、少し後退した額に厳めしい顔つきはいかにも学者様といった風貌だった。コツコツと革靴を鳴らして教室に入室すると、彼は第一回目の授業としてオリエンテーションを始めた。教室と研究室を併設したクラスには三十人ほどが席に座っていた。
「私はこの学校の名誉教授アロガンだ。取り扱うものは授業によって多少異なってくるが、主として生物学を専門としている。今学期、このクラスの担当となった。よろしく頼む」
アロガンは話を始めた。
「まず初めに生物学を通して何を学びたいのかを君らに問うておきたい。その答えを己の中に持つものにとって、この四年間は非常に有意義なものになるだろう。またまだその答えを持たぬ者もそれを探求する努力を決して怠らぬよう日頃から己のセンサーの調整をしていてほしい。…ウィリアム、ウィリアムグッドウィルはいるかね?」
グッドウィルは席を立ち、返事をする。
「君が生物学を学ぶ目的は何かね?」
アロガンの視線には大きな期待が含まれていた。
「私の目的は主に脳の構造を理解し、知識とは何かを解き明かすことです」
「なるほど、脳科学的観点からみた知識か、良い答えだ」
アロガンは話を続ける。アロガンの目は再びクラス全体へと語る。
「私は学習の目的を見つけろと言ったが、そもそもまず生物学とはなにを学ぶのかを理解しなくてはならない。これもまた様々な言いようがあるが、私なりの言葉で表現するなら、つまるところ『生命』は何かを追求し、その根底にある共通原理を学ぶ学問だ。この学問には多様な切り口がある。生物を系統的に分類する分類学、進化を研究する進化学、生態を解き明かす生態学、行動を分析、研究する行動学。生体を対象にその仕組みを解明する生化学、生理学、生命の誕生や器官形成を探る発生学、遺伝子の役割を解明する遺伝子学、細胞を対象とする細胞生物学や分子生物学などの分野があるのだが…」
授業が終わると、教授はグッドウィルへ近寄った。
「グッドウィルだったな。これからよろしく頼む」
アロガンは力強くグッドウィルの手を握った。
「よろしくお願いします」
「初めての授業はどうだったかな?」
「今日の授業はまだ導入に過ぎません。早く専門的に学んでいきたいです」
「そうかそうか、それはよろしい限りだ。時に風の噂で聞いたのだが、君は入学テストで全ての科目でほぼ満点を取り、主席で入学したそうじゃないか」
「すごいことではありませんよ。要はいかに知識を持っているかですからね」
「そう簡単にできることではないさ。…そんな君に似合いの場所があるのだが興味ないかね?」
教授の話を聞くにこしたことはない、そう思ったグッドウィルが同意すると、アロガンは「立ち話もなんだから」と、二人はカフェテリアへ行くことになった。
アロガンが二人分のコーヒーを注文すると、空いている席に座った。かなり広く清掃の行き届いたカフェテリアだった。コーヒーを一口啜るとアロガンが言う。
「先ほどの話なのだがね、今、私の研究室では君の学びたがっていた脳を研究しているんだ。誰もが入れるわけではない。私が選んだ少数精鋭のグループだ。そこでは記憶や学習、予測、思考、言語などあらゆる脳の高次認知機能の仕組みを解き明かそうとしている。そこで提案なのだが、このグループに参加しないか?」
グッドウィルに断る理由はなく、むしろ成績評価につながるならと喜んで引受けた。事がすんなりと進むと、アロガンは目に見えて喜んだ。
「ならば早速案内しよう」
そう言って、立ち上がった教授に疑問を持った。
「申請書などは書かなくて良いのでしょうか?」
「いい、いい、そんなものは。それよりも君の研究部屋へと行こう」
案内されたのは『アロガン教授第二研究室』と書かれた部屋だった。中はそこそこの広さで、研究室というよりもすこし生活感のある勉強部屋といった様相だった。入って左手には壁一面に本棚が並んでおり、その本棚に向き合うような形で部屋の中央に質素なデスクとパソコンが置いてあった。部屋の右半分は給湯室のようになっており、小さなシンクや冷蔵庫、ポットなどが置いてあった。
「ここには選りすぐりの専門書が揃っているし、またすぐそこのパソコンからアクセスすれば、私の権限で最新の論文なども閲覧できる。監督者を付けられない都合上、どうしてもこの部屋での高度な実験は不可能だが、座学にはうってつけの環境というわけだな。実験をしたいときは悪いが今日のクラスで使用した教室で行ってくれ。ここにある備品なら好きに使ってくれて構わない。隣は私の部屋になっているから、私がいる時ならいつでも呼んでくれたまえ」
アロガンは部屋を歩きまりながら、楽しそうに話す。
「それから今後二、三ヶ月に一度ほどのペースで進捗を提出してくれ。そこまで慎重になる必要はないが、何をしているのかは把握しておきたいからな」
グッドウィルの正面に立ち止まると、自慢の髭をいじりながら尋ねた。
「さて、ここまでで質問はあるか?」
「…他の研究者たちに挨拶することは可能ですか?」
「…残念ながらそれは無理だな」
「どうしてかお聞かせ願えますか」
「彼らは忙しいのだ。彼らはそれぞれのタスクを抱えている。ここ最近はかなり躍起になっているようだから今日のうちに会うのは難しいだろう。また機会があれば紹介しよう。他に質問は?」
「いえ」
グッドウィルは胸の内に浮かんだ考えを押し込んで言った。
「では早速今日から研究に取り組んでくれたまえ。私はこれから会議だから、ここらでな」
「今日からですか?」
「嫌と言うなら構わない。善は急げという話さ」
アロガンはやたらとうるさい革靴をコツコツと鳴らすと、扉を開けて出ていった。
グッドウィルは椅子に腰掛けると、さっそくパソコンを起動した。研究内容はすでに目処が立っていて、それに関しては問題なかった。それよりも気がかりなのはアロガンだった。小さな違和感だが、突き詰めるに値しないし、今はこの環境を有効活用したほうが有益だとも思えた。グッドウィルは当面の自説を検証し始めた。
結局、その日はアロガンには会うことなく帰宅することにした。午後七時、帰宅したグッドウィルは食事を済ましてシャワーから出たとき、彼の携帯が鳴った。時刻を確認し、次に画面に出た名前を確認すると携帯を耳にあてる。
「やあジミー、そろそろ電話が来る頃かと思っていたよ」
「私もそろそろあなたが予想できるように頃じゃないかと予想してたところよ」
「その調子も相変わらずだね」
「引越ししてからの電話はほぼこの時間よ。あなたのことだから頭に入っていないわけないわ。それで、大学はどうだった?」
「まずまずってところだな。どうやら僕は有望株らしいよ」
「有能株?」
「教授にスカウトされてね。その教授のお膝元で研究することになったんだ」
「さすがといったところなのかしらね」
「まあうまくやるさ。これから忙しくなると思うんだけど、悪く思わないでくれよ。君と同じくらい研究も大切にしたいんだ」
「ええわかってるわ。お互いの生活があるものね。それにこっちだって忙しくなりそうだしね。私は声が聞けて満足よ」
しばらく何の意味のない会話を繰り広げると、二人は別れを告げて電話を切った。引越ししてから日課となっていたこの通話は二時間、一時間、三十分とここ最近徐々に通話時間が短くなってきていた。日課が形骸化しつつあることにグッドウィルは嬉しくもやや悲しくもあった。今一度自身の心情をまとめてみる。その時はそう遠くないだろうという予想に行き着くのは当然だった。
アロガンの元で研究を始めてから二ヶ月が過ぎた。研究は構想の段階までは順調だったが、突如としてブレーキをかけられることとなった。
「グッドウィル、今日は本報告の日なのだが、準備の程はいかがかな?」
土曜日の昼過ぎ、研究室第二へノックもせずに入ってきたアロガンはグッドウィルの背中からそう話しかけると、机へ近寄った。今日のアロガンは顔には教授の風貌が宿っていた。グッドウィルは資料を手渡すと、近くの椅子をアロガンのために持ってくる。
「前から進めていた神経伝達回路を強化する案についてなんですが、ようやく目処が立ってきました。僕が注目したのはニューロンの分化です」
アロガンは老眼鏡を鼻にかけると、ただ黙って資料に目を通していく。時々眼鏡越しにグッドウィルの顔をのぞいていた。
「前にも話した通り、この研究の出発点は知識とはなにか、そして知識の仕組みを解明することで人為的にそれを強化することができるのではないかです。そしてこの問いに関する解答が先ほど話したニューロンの分化です。従来の研究でニューロンが人間の高次機能に大きく関与していることは明白でした。成人の海馬では、どんなに歳をとっても新しくニューロンが生み出されつづけていて、学習などで海馬の活動が高まると、新生ニューロンの数が増加することが報告されていましたが、この仕組みについては全く不明でした。今回僕が発見したのは海馬にシータ波が伝わることでニューロン前駆細胞が刺激され、ニューロンへの分化が促進されるということです」
アロガンの顔は説明が進むにつれ、すこしずつ厳たるものになっていった。
「まずは実験方法からです。実験ではマウスから海馬を含むスライスを作製し、電極によりシータ波刺激を加えました。すると、海馬にあるGABA性ニューロンが興奮し、興奮性GABAの入力を受けて、ニューロン前駆細胞にカルシウム流入反応が起きることがわかりました。このカルシウム流入反応が引き金となって、ニューロンへの分化にスイッチを入れる転写因子の発現量が増加し、最終的に新たなニューロンの数が増加することがわかったのです」
「…なるほど。それで結論は?」
「いわゆる実行機能の低下を防げるかもしれないということです。人間の行動を制御する高次の認知スキルを老化させずに維持できれば、賢明な判断をより早く下せるようになり、集中力と記憶力が向上することが見込めます。もしかすると、脳を若返らせるということも夢ではありません。またうつ病などの精神病患者では海馬の新生ニューロン数も低下することがわかっています。となると、そういった疾患に対する薬剤としての活用も可能かもしれません」
アロガンはしばらく黙っていた。何度か資料をめくり直し、机にパタンと投げ捨てると、大きなため息をついた。
「簡潔に言おう。君にはがっかりだな。もう少し優秀な生徒かと思っていたよ」
彼の一言で部屋の空気は一気に支配され、何倍にも重さになってグッドウィルに降りかかった。
「具体的にどこに不足があるか教えていただけますか」
無意識に体が身構えていたグッドウィルは敵意を含んだ声色で尋ねた。
「ニューロン分化の仕組みを理論的に説明したところは褒めてやろう。確かにその解明は検証の余地があるかもしれん。もちろん詳しく見てからだが。だが、実行機能が向上するという仮説は抽象的かつ曖昧すぎる。君は実行機能という人間の賢さの一つに焦点に当てたに過ぎないんだ。人間の脳の中に細胞がどれほどあって、一つの機能のために何種類の細胞が作用していると思っている。賢さの要素一つを上げて、人間が賢くなるというのは早計だろう。単語こそ立派なもんだが、すこし空論すぎるな」
このようなアロガンをこの二ヶ月間で一度も見たことなかった。初日に会ったアロガンとはまるで別人だった。眉間に寄った皺、極端に曲がった口角、獲物を狩る老獅子のように鋭く冷酷な眼。グッドウィルを見つめるアロガンは、高圧や威圧という言葉に形を与えたかのようだった。
「確かに結論に根拠はありませんが、それはあくまで可能性の話を…」
アロガンは話を聞く素振りを一切見せなかった。
「課題はまだまだある。仮に君の仮説を実行したとして、説を立証するために被験者の健康と環境的、精神的ストレスをも管理する必要があるのはわかっているのか?ストレスは脳組織を老化させる。血流で運ばれるグルコース、ビタミン、ミネラル、脂肪、アミノ酸、電解質などの栄養素は脳にとって欠かせないものだ。当然、実験が長期化するなら老化による脳細胞の減少も考慮しないといけない。つまりだな、ニューロンが減る方法はいくらでもあるのに、簡単に検証できるわけがないだろう?マウスですら容易ではないのに人間でなんて、土台無理な話だ」
「それはそうですが、それを可能かどうか判断していくための報告であって…」
「それにだ、君は脳が若返る可能性もあると表現したが、それはどの年齢を対象にした話だ?仮に若年者の脳でこの実験を行う場合、それ以上の脳のスペックを強制的に与えるようなものだ。どう言った効果が得られるかわからないし、それこそ神の所業だとわかっているのか?…いいか。君はわかっていないようだから教えておく。今、君は小学校で自由研究を提出しろと言われているわけじゃない。権威あるアロガンのもとで、研究成果を挙げろと言われているのだ。できるかもしれない、これから考えるなんて不確定性のあるものは望んではいない。必要なのは確実と完璧だ。こんなものでは許可は下ろせない」
「しかし…」
「聞こえんのか。却下だと言っているのだ」
アロガンは一際大きな一言で会話を継続する意思がないことを示した。一言で場を制されてしまったが、グッドウィルは当然納得できなかった。アロガンはため息混じりに続ける。
「研究自体は悪い線はいっていない。だが、一度優秀な人間のもとで経験を積んだ方が良いことも確かだろう。この研究は私が引き継ごう。今後しばらくは、私がこの研究の主任となって進め、君は私のヘルプをこなしていってもらおう。それで良いかな?」
グッドウィルの顔から滲み出ている答えを受け取ったアロガンは手を突き出して彼を制した。
「私は否定の言葉が聞きたいのではない。良いか、これは君のために、そしてこれから失敗するであろう研究のために提案しているのだ。本来なら私に断られた地点で君の研究は終わっている。それを私とともに復活させ、さらなるものへ昇華させようといっているのだ。わかったな?」
大きな権威のもとにグッドウィルは下るほかなかった。アロガンは満足そうに頷くと、今日は帰るようにと伝えた。
帰り際、グッドウィルは資料とデータは他にないのかと尋ねられた。それだけだと答えると、グッドウィルはアロガンの研究室を後にした。
一週間後、グッドウィルはあの裏山を彷徨っていた。一週間前と現在置かれている状況の脈絡の無さに自分自身心底驚いていた。この一週間で青年グッドウィルは死んだ。
あの日、帰宅してからのグッドウィルは泥のように眠りこけた。翌日、今後のことについて尋ねようとアロガンの研究室に向かい、扉の前でノックをしようとした時だった。扉越しにけたたましい着信音が鳴り響き、その直後にアロガンの声が中から聞こえてきた。入室を中断したグッドウィルは、扉の横で立ち尽くしていた。当然、盗み聞きをするつもりなどなかった。長くなるなら出直そうかとも考えていたが、二、三分後には壁にへばりつくこととなった。
「ああ…もちろん順調だよ。それが思わぬ収穫があってね。例の生徒が思った以上に優秀だったらしく、彼の研究を私が行うことにしたんだ。本来ならちょっと話を聞いただけですぐ却下して、私の研究を手伝わせようと思っていたのだけれど、予想以上に出来が良くてね。私が引き継ぐという形で利用させてもらうことにしたんだ。…いやいや、盗んだなんて人聞きが悪いじゃないか。実際そう言われてはぐうの音も出ないが、例えばそこに金のなる木の種子があるとしたら誰でも蒔いて水をやるだろう?私もそうしたに過ぎないのだよ。いやあ、それにしても、若者とはなんと扱いやすいものか。どれほど青い芽でも挫折一つを経験させればたちまち自信を無くして伸び悩む。そうなればあとは私の元へ引き込むまだけだ。何個か嘘もついたがな。嘘も方便というやつだ」
腹のそこから熱く煮えたぎる怒りが湧いて出て、それは一分と経たないうちにそれは藍色に反転した。グッドウィルは底なしの阿保だと思った。アロガンに対してではなく、策略に気づけなかった自分自身に対してだった。今まで自分は誰よりも賢く、自分以外は下だと嘲り、見下していた。しかし、今、愚かだと思っていたものに騙された自分は、さらに愚かなのだと言わざるを得なかった。
尊大な自尊心を傷つけられたグッドウィルは、帰宅するとすぐにベッドに横たわった。しばらく虚ろな時間を過ごしていたが、携帯の着信音で我に帰ることになった。ジミーからだった。
「もしもし、ジミーだけど」
「ああ」
「今時間いいかしら?」
「ああ」
ジミーは黙りこくっていた。
「要件はなんだい?」
「急で申し訳ないのだけれど、真面目な話がしたいの」
一息入れた後、ジミーは言った。声には覚悟が籠っていた。
「今のあなたにとって私は特別かしら?」
ジミーの意図を理解していたグッドウィルは淡白に答えた。
「いいや」
「そう」
ジミーの大きな声に動揺は見られなかった。通話越しに微かに息を呑む音が聞こえた。
「あなたと付き合う時には時間が必要だった。あなたの変化の速度に私の心が追いつかなかった。けれど今は必要なさそうよ。…私たちもう終わりね」
「ああ、そうだろうね」
「…本当にあなたは変わってしまったのね。私が好きだったのはあの頃の純粋な彼だったのよ」
重い沈黙が流れた。左手で持つ携帯機も重くて仕方がなかった。グッドウィルは電話を切ろうとした。
「私は…まだ…」
携帯電話の向こう側で小さくそう聞こえたが、最後までは聞かなかった。
この日を境にグッドウィルは大学へ行くのが億劫になった。正確には必要最低限の生活に従事するようになった。もちろんその必要最低限に大学や外出、研究などが当てはまることはない。何をする気にならなかった。今振り返ると、燃え尽きてしまったのだろうと思う。そしてそれの意味するところとは、自分の胸で燃えていた灯りは見せかけだけは大きく盛っていたが、指先のマッチ棒よりも小さく脆弱なものなのだと悟った。
それから三日後の早朝、また事態が動くことになった。繊細で薄く脆い朝の憂いを携帯電話がかき消した。地元の総合病院からで、父が危篤なので親族に連絡しており、可能であれば今すぐにでもきて欲しいとの旨が伝えられた。グッドウィルは家を出て列車に乗ることとなった。それまでの無気力とは裏腹に体はまるで機械のように素早く支度を済ませた。午前七時頃、自宅を出てから総合病院に着くまでの八時間程は携帯をバックの中に入れていた。ここで携帯を握る手の強さで愛の強さが測ることができるのだろうと思うと、自分の無関心さにやはり驚かざるを得なかった。
結論から言うと、生きている間に父と会うことは叶わなかった。列車に乗って一時間も経たぬうちに携帯を通して、必死の治療も虚しくといった文言とともに臨終が伝えられ、この事件は呆気なく幕引きとなった。
グッドウィルが到着した時にはすでに死化粧が施された後だった。霊安室で数十分死体を見つめた後、看護師から事情を聞いた。父は勤務先で倒れているところを発見され、心筋梗塞の疑いで搬送されたそうだ。心筋梗塞はひとたび発症するとその死亡率は四〇%と高く、多くは病院で治療を受ける前に死亡している。その一方、心筋梗塞で入院した人の死亡率は一〇%以下で、早期の治療であれば一命を取り留める可能性が高い。不幸なことに父の場合は残業で一人残っているところ発症したと思われ、朝方病院運ばれたことを考えると倒れてから九時間以上時間が経っている可能性があった。看護師が言うには、運ばれた地点ですでに厳しい状況だったということだった。
久方振りにして最後の面会を終わらせたグッドウィルは待合室の片隅で一人座っていた。事態に一段落がつき、小休止にはうってつけの静かな空間だった。尤も小休止と言うにはあまりに長い時間だったが。
グッドウィルに悲しさはなかった。代わりに胸の中を占めていたのは虚しさだった。自身の記憶の中ではいつも父は優しかった。始めは家庭の不出来を補完するための必要愛であって、グッドウィルの知能向上とともにそれは純真で真実の愛へと昇華したのだと思う。けれど、それに釣り合うような気持ちはグッドウィルにはなかった。
過去を振り返る時間は長かったそして、深い長考の末、意を決してあの山へ向かうことにした。
時刻は午後八時。すでに陽は落ち、山は闇に包まれていた。地形は把握していても、暗闇の中を進むために目的地までは時間がかかった。意識は半ば朦朧とし、その頼りない知能の半分を使って歩いていた。もう半分には空っぽが詰まっていた。
真っ先にあの泉を思い浮かんだ。その考えは十分に傲慢だと思うが、そのほかに思い浮かばなかった。勾配のある坂を登っていると、一際地面が盛り上がった場所に出る。その先にあの洞窟が暗闇の中で口を開けていた。洞窟内の肌寒さに鳥肌が立つ。グッドウィルは薄目でよろよろと歩いていき泉の横で座り込んだ。するとどこからか小汚い鼠が現れて、彼の側へ近寄ってきた。
「やあ、イグノランティア、知識が欲しくなったのかい?」
鼠がちゅうちゅうと鳴いた。
「今にあげるよ。これで僕は元通りだ」
鼠は真っ黒な目でグッドウィルを見つめている。
「いや、あるいは何も変わらないのかもね」
もう一度鳴いて鼠はどこか闇へ消えていった。
グッドウィルは眼を瞑った。
地位、名声、立身出世。それらへと誘惑する金、傲慢。
失われた優しさや人情、得られた打算的恋愛。
過去、思い出、身に余るほどの純真。
そして、夢や若さ、頭脳や知識。既知と無知、成熟と未熟。
アロガンの思惑。
ジミーとの交際と決別。
父母との別れ。
愚かな自身。
「僕の人生で実ったものなど何一つなかった。本当に、本当に、自分は愚かだ」
グッドウィルはこれから来る文字通り死ぬほどの苦痛に思いを馳せながら、音も立てずに泉へとその身を投げた。