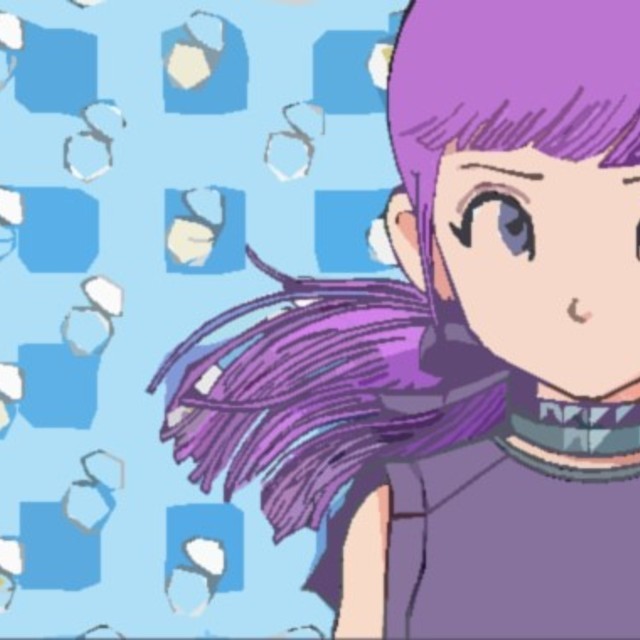Home, Sweet Home
文字数 2,390文字
太陽が建物の谷間に沈むかけた夕暮れどき。人々が家路へと向かう市場の隅にその小さな店はあった。ステンドグラスがはめ込まれた分厚い木の扉が目を引く木造平屋の建物には「テイラー・ポランスキー」の看板がかかっている。若い夫婦が営むその店は、丁寧な仕事と穏やかな人柄で評判の仕立て屋だった。
店内の壁には折りたたまれた布地や糸車、色とりどりのボタンが所狭しと並べられており、カウンターの奥の作業場からはカタカタカタと小気味よいミシンの音が聞こえていた。ミシンを踏んでいるのはヘルマン・ポランスキー。緩やかに巻いた栗毛色の髪の彼は腕のたつ裁縫職人であり、この店の主人でもある。夕陽の差し込む作業場で、彼は明日納品する婦人用のワンピースの裏地を縫いつけていた。
「あなた、夕食ができたわよ」
作業場と居間をつなぐ扉が開き、黒髪の女性が顔を覗かせた。
「わかったよ、アンナ。もう終わる」
ヘルマンが顔をあげて妻に向かって優しい笑顔を見せた時、カランカランと店の扉の呼び鈴が鳴った。
「あら、オットーさん。こんばんは」
店内へと足を踏み入れた恰幅のよい紳士に向かって、アンナが店の奥から声をかけた。
「やあ、もう閉店だったかな」
オットーは皮手袋をはめた右手で中折れ帽を脱ぐと、帽子を胸の前にかざしてヘルマンに視線を向けた。
「いえ、大丈夫です。御用はなんでしょう」
ヘルマンは立ち上がり、作業場からカウンターに歩み寄った。
「鳥打帽をあつらえて欲しいんだ」
額に皺をよせてオットーが済まなさそうに告げると、ヘルマンの頬がわずかに硬直した。
「わかりました。期限はいつでしょうか」
「ちょうど一週間後の午後九時に配達してもらえるかな。詳しいことはこの中に書いてある」
コートのポケットからオットーが取り出した茶封筒を、ヘルマンは会釈しながら受け取った。
「ありがとう。よろしく頼むよ」
オットーはヘルマンの肩を軽く叩くと、アンナに一礼して店を出ていった。
「前にもオットーさん、鳥打帽を作らなかったっけ」
アンナの声に振り向かず、ヘルマンはオットーが出ていった扉を見つめて黙って頷いた。
夕食を済ませたヘルマンはチーズの塊を削り、赤ワインのボトルのコルクを抜いた。ワインを自分のグラスに注ぎ、アンナのグラスにも注ごうとすると、彼女は手の平でグラスに蓋をした。
「今夜はやめておくわ、ヘルマン」
「どうして。具合でも悪いの」
「ううん、そうじゃないけど。ちょっと疲れてるみたい。先に休ませてもらっていいかな」
アンナの赤い唇がヘルマンに近づいて、彼の唇に触れた。
「おやすみなさい」
上目遣いでヘルマンを見て、アンナは居間から出ていった。
彼女を見送ったヘルマンは、オットーから渡された茶封筒を開けた。中には三枚の写真と便箋が一枚入っていた。三枚の写真のうち一枚は髭面の男の顔を正面から写したもの、もう一枚は横顔、もう一枚は全身姿だった。便箋には写真の男の名前、身長、体重、身体的特徴、方言、習慣、食事の好み、仕草の癖など、男のパーソナリティが詳細に記されていた。
オットーからの注文は鳥打帽ではなく、写真の男の暗殺だった。仕立て屋のヘルマン・ポランスキーの裏の顔は、凄腕の殺し屋であった。オットーは組織の諜報員であり、年に数回ヘルマンに殺しの依頼をもってくるのである。鳥打帽の注文は暗殺依頼の暗語だった。
一週間後か。口に含んだワインをグイッと飲み込み、ヘルマンは大きな息を吐いた。アンナと結婚してから七回目の任務だ。裏稼業のことを、ヘルマンはまだ彼女に告げていなかった。腕のたつ彼であるが、いつも無事に帰ってらこれる保証はない。そろそろアンナに告白するべきだろうか。
グラスに残ったワインを一気に飲み干すと、ヘルマンは机に突っ伏して、寝室に行かずにそのまま眠りについた。
「それじゃあ、オットーさんのところに配達に行ってくるよ」
一週間後の夜。軽く夕食をすませたヘルマンは暗器を忍ばせたボストンバッグを片手に、玄関でアンナに声をかけた。
「あなた、ちょっと待って」
台所から出てきたアンナは右手にこぶし大の石、左手に掌ほどの大きさの金属片を持っていた。彼女はヘルマンの目の前で石を金属片にカチンと打ち付けて、まばゆい火花をパッと散らした。
「なんだい、それは」
「ヤポンというアジアの国の『火きり』という風習よ。出かける家人の無事を祈って火花を飛ばすの。蚤の市でこの前見つけたのよ」
「無事を祈ってなんて、俺は鳥打帽を配達に行くだけ……」
ヘルマンの言葉が終わるのを待たずに、アンナは彼に抱きついて胸に顔を埋めた。
「知ってるのよ、わたし」
彼女はヘルマンの胸に頭を強く押しつけた。
「知ってるって、なにを……」
「隠さなくていいのよ。だって夫婦だもの」
アンナが顔をあげてヘルマンを見上げた。彼女の瞳は涙で濡れていた。
「でもあなたは何も言わなくていいの。わたしは信じてる。あなたのやっていることはよくないことかも知れないけれど、きっと理由があるんだって」
アンナの肩にかけたヘルマンの手が小さく震えた。
「でもお願い。約束して。絶対に無事に帰ってくるって」
アンナの瞳から涙がほろりとこぼれ落ちた。ヘルマンの背中に回した両手をほどくと、彼女は自分の腹にその手を重ねた。
「……生まれてくる子供のためにも」
「子供、できたのか」
「うん、この前お医者さんにみてもらったの。来年の春に生まれるって」
ヘルマンは目を大きく見開いて、アンナの体を包み込むように抱きしめた。
「ありがとう、アンナ。俺は絶対に帰ってくるよ。お前のためにも、子供のためにも」
二人はお互いのぬくもりを慈しみ、唇を重ねた。柱時計の鐘がヘルマンに出発の時刻を知らすまで、二人はきつく抱き合った。
のちに最強の暗殺者となるヘイランが生まれる半年前の、とある夫婦の物語である。
店内の壁には折りたたまれた布地や糸車、色とりどりのボタンが所狭しと並べられており、カウンターの奥の作業場からはカタカタカタと小気味よいミシンの音が聞こえていた。ミシンを踏んでいるのはヘルマン・ポランスキー。緩やかに巻いた栗毛色の髪の彼は腕のたつ裁縫職人であり、この店の主人でもある。夕陽の差し込む作業場で、彼は明日納品する婦人用のワンピースの裏地を縫いつけていた。
「あなた、夕食ができたわよ」
作業場と居間をつなぐ扉が開き、黒髪の女性が顔を覗かせた。
「わかったよ、アンナ。もう終わる」
ヘルマンが顔をあげて妻に向かって優しい笑顔を見せた時、カランカランと店の扉の呼び鈴が鳴った。
「あら、オットーさん。こんばんは」
店内へと足を踏み入れた恰幅のよい紳士に向かって、アンナが店の奥から声をかけた。
「やあ、もう閉店だったかな」
オットーは皮手袋をはめた右手で中折れ帽を脱ぐと、帽子を胸の前にかざしてヘルマンに視線を向けた。
「いえ、大丈夫です。御用はなんでしょう」
ヘルマンは立ち上がり、作業場からカウンターに歩み寄った。
「鳥打帽をあつらえて欲しいんだ」
額に皺をよせてオットーが済まなさそうに告げると、ヘルマンの頬がわずかに硬直した。
「わかりました。期限はいつでしょうか」
「ちょうど一週間後の午後九時に配達してもらえるかな。詳しいことはこの中に書いてある」
コートのポケットからオットーが取り出した茶封筒を、ヘルマンは会釈しながら受け取った。
「ありがとう。よろしく頼むよ」
オットーはヘルマンの肩を軽く叩くと、アンナに一礼して店を出ていった。
「前にもオットーさん、鳥打帽を作らなかったっけ」
アンナの声に振り向かず、ヘルマンはオットーが出ていった扉を見つめて黙って頷いた。
夕食を済ませたヘルマンはチーズの塊を削り、赤ワインのボトルのコルクを抜いた。ワインを自分のグラスに注ぎ、アンナのグラスにも注ごうとすると、彼女は手の平でグラスに蓋をした。
「今夜はやめておくわ、ヘルマン」
「どうして。具合でも悪いの」
「ううん、そうじゃないけど。ちょっと疲れてるみたい。先に休ませてもらっていいかな」
アンナの赤い唇がヘルマンに近づいて、彼の唇に触れた。
「おやすみなさい」
上目遣いでヘルマンを見て、アンナは居間から出ていった。
彼女を見送ったヘルマンは、オットーから渡された茶封筒を開けた。中には三枚の写真と便箋が一枚入っていた。三枚の写真のうち一枚は髭面の男の顔を正面から写したもの、もう一枚は横顔、もう一枚は全身姿だった。便箋には写真の男の名前、身長、体重、身体的特徴、方言、習慣、食事の好み、仕草の癖など、男のパーソナリティが詳細に記されていた。
オットーからの注文は鳥打帽ではなく、写真の男の暗殺だった。仕立て屋のヘルマン・ポランスキーの裏の顔は、凄腕の殺し屋であった。オットーは組織の諜報員であり、年に数回ヘルマンに殺しの依頼をもってくるのである。鳥打帽の注文は暗殺依頼の暗語だった。
一週間後か。口に含んだワインをグイッと飲み込み、ヘルマンは大きな息を吐いた。アンナと結婚してから七回目の任務だ。裏稼業のことを、ヘルマンはまだ彼女に告げていなかった。腕のたつ彼であるが、いつも無事に帰ってらこれる保証はない。そろそろアンナに告白するべきだろうか。
グラスに残ったワインを一気に飲み干すと、ヘルマンは机に突っ伏して、寝室に行かずにそのまま眠りについた。
「それじゃあ、オットーさんのところに配達に行ってくるよ」
一週間後の夜。軽く夕食をすませたヘルマンは暗器を忍ばせたボストンバッグを片手に、玄関でアンナに声をかけた。
「あなた、ちょっと待って」
台所から出てきたアンナは右手にこぶし大の石、左手に掌ほどの大きさの金属片を持っていた。彼女はヘルマンの目の前で石を金属片にカチンと打ち付けて、まばゆい火花をパッと散らした。
「なんだい、それは」
「ヤポンというアジアの国の『火きり』という風習よ。出かける家人の無事を祈って火花を飛ばすの。蚤の市でこの前見つけたのよ」
「無事を祈ってなんて、俺は鳥打帽を配達に行くだけ……」
ヘルマンの言葉が終わるのを待たずに、アンナは彼に抱きついて胸に顔を埋めた。
「知ってるのよ、わたし」
彼女はヘルマンの胸に頭を強く押しつけた。
「知ってるって、なにを……」
「隠さなくていいのよ。だって夫婦だもの」
アンナが顔をあげてヘルマンを見上げた。彼女の瞳は涙で濡れていた。
「でもあなたは何も言わなくていいの。わたしは信じてる。あなたのやっていることはよくないことかも知れないけれど、きっと理由があるんだって」
アンナの肩にかけたヘルマンの手が小さく震えた。
「でもお願い。約束して。絶対に無事に帰ってくるって」
アンナの瞳から涙がほろりとこぼれ落ちた。ヘルマンの背中に回した両手をほどくと、彼女は自分の腹にその手を重ねた。
「……生まれてくる子供のためにも」
「子供、できたのか」
「うん、この前お医者さんにみてもらったの。来年の春に生まれるって」
ヘルマンは目を大きく見開いて、アンナの体を包み込むように抱きしめた。
「ありがとう、アンナ。俺は絶対に帰ってくるよ。お前のためにも、子供のためにも」
二人はお互いのぬくもりを慈しみ、唇を重ねた。柱時計の鐘がヘルマンに出発の時刻を知らすまで、二人はきつく抱き合った。
のちに最強の暗殺者となるヘイランが生まれる半年前の、とある夫婦の物語である。