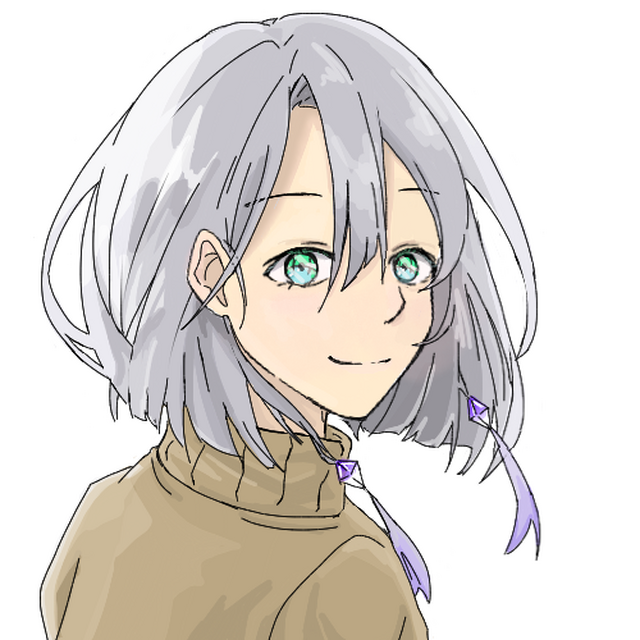5.最悪な日
文字数 3,773文字
——全く、最悪だ。
ヒサトは小さくつぶやいた。
ここは大都市圏から少し外れた場所にあるビル街。といってもオフィスが立ち並ぶだけではなく、ヒサトのいるビルの向かい側にはホテルがあって、そこから少し歩けば大型複合商業施設が姿を現すような繁華な場所だ。
電車も通勤時を除いてはほとんど混んでいない。理想的な場所と言えるだろう。
ヒサトは今、まっさらなオフィスビルの三階にいる。大きくとられた明かり取りの窓には堂々と“三木村探偵事務所”との文字がある。
そしてヒサトはその探偵の助手であった。あの三木村探偵に彼のような愚鈍な助手が要るかどうかは甚だ疑問だが。
そんなことはさておき、今、三木村探偵事務所の中は静かだった。原因は以前から発生している殺人事件——手口も被害者もバラバラだが——がつながっているかもしれない件についてだ。
それを言い出したのは探偵だった。
「これらはつながっている、かもしれない」
同じ警察署の管轄内で立て続けに起こっていると言うだけで、被害者にも殺害方法にも共通点などなかったのだが、探偵はなぜかそう言った。たしかに三件連続というのは奇妙ではあったがそこまで気にかける話でもないのに。
三木村探偵はそういう風に事件を解決していた。答えが先にあって、後から論理を埋めるのだ。もちろんそれで失敗したことはない。だからヒサトも疑わない。
探偵の言葉を疑わないのはヒサトだけではない。警察もである。数々の事件を解決してきた探偵は、警察とも
探偵の言葉に流されるがまま、無駄な考えを起こしては首を振ってそれらを掻き消し、記録と向き合っては頭をひねる。もちろん何一つわからない。
「ううん。やっぱり違うのかなあ」
そういって探偵は頭を掻く。手こずっているのだろう。
「しかし、これらの事件は繋がっていたんだ、って先生おっしゃってましたよね」
ここぞとばかりにヒサトが会話に加わった。
「うーん。その筈なんだけどねえ」
そう唸って探偵は首をもたげた。手を顎にあて、考え込むように部屋の中を歩き回る。靴が地面にあたってことことと音が鳴る。いつも思っているのだが、階下の人はうるさく無いのだろうか。
時々立ち止まったり、天井を見上げたり。そうかと思えばまた歩き回り始める。
その傍らで、ヒサトが探偵をじっと見つめていた。彼は格別洞察力があるわけでも、何か特殊な能力を持ち合わせているわけでもない。もちろん探偵に認められたことなどない。探偵が何を考えているかなど解らないし、自分なりに答えを組み立てようとしても正解には決して辿り着けないだろう。
つまりは諦めている。幾度となく探偵の事件解決についていった。その中でも結末を予想できたものなど一つもない。“予測”ではなく“予想”ですら無理だったのだ。探偵の思考を読み取ろうと努力することはまるで無駄な努力と思われた。
「あっ」
いきなり探偵が立ち止まった。組んでいた腕が解け、ぶらんと垂れ下がる。そしてさらに忙しなく歩き始めた。同時にぶつぶつと呟き始める。
「第一の被害者——」
「金城さん?」
反射的にその名を口に出す。捜査に加われる貴重な機会だ。大事にしなければ。
「そう。彼のお店に通っていたのは確か——」
「ええっと」
出番をやっと見つけたヒサトは水を得た魚のように動き始めた。手の届く場所にあったノートパソコンを開き、カタカタとキーボードを叩き始める。
「話を聞いたのは常連十人ほどですね。ええっと」
「ううん。二番目の被害者の交友関係は」
「そ、それはですね」
「それだとしたら、三番目にも」
完全に振り回されている。ヒサトとは違って、探偵の頭には事件に関する情報が完全にインプットされていた。困惑するヒサトを放置したまま探偵は頭を高速回転させていく。
ヒサトはこの疎外感が嫌いだったのかもしれない。
「そうだ。あれだ。青色の。じゃあそれが全てをつなぐ——」
突然の大声と言葉にヒサトは思わず立ち上がった。
「うわぁ」
軽く息を整える。
探偵は彼の動向など全く気にせず、窓に近寄り、考え込んだ。そして、いきなり、つかつかと歩いていき、ばんっと備え付けのクローゼットを乱暴に開けた。中から帽子とコートを取り出す。
乱雑にそれを羽織り、頭にかぶせる。一言、「ちょっと、行ってくる」とだけ残して、部屋から出ていってしまった。
ヒサトには声をかける暇さえない。開けっぱなしになっているドアに近づいて外を覗き込んでも静かな階段があるだけだった。
さっきまでとは違い、静寂がおとずれた。ヒサトは道路に面した窓から道路を覗く。行き交う車と人に紛れて、探偵は帽子を片手で押さえてコートをはためかせながら走っていった。
大きくため息をついて先ほどの椅子に座り直す。
散々悩んだ末に先ほどのノートパソコンを開いた。二番目の被害者の名前が検索欄に表示されているタブを消去して、新しく検索エンジンを開いた。
URL欄に一生使わないような文字化けによく似た文字列を打ち込んでいく。最後にEnterキーを押して、現れたのは真っ白いページ。
そこでヒサトは慣れた手つきで画面上でカーソルを走らせ、クリックしていく。十秒くらいして息をついた。力が抜けたように椅子にもたれかかる。ぼうっと天井を見上げた。
ノートパソコンの画面はもう白いだけではなくなっていた。真ん中には青くてごちゃごちゃしたロゴ。青だけなのにどこか毒々しい。
それは、探偵が調査していた事件の被害者の友人。ややこしい立ち位置の人に共通していたもの——。
姿勢を戻したヒサトがさらにカーソルを動かし続ける。
少しして画面にはさらに変化が訪れた。青く毒々しいマークはそのままで、下に検索欄のようなものが現れた。中に書かれているのは“三木村ろくを殺害して”という文字。
それを目にしていきなり危機感を覚えたのかヒサトはキョロキョロと周りを見回した。そしてやっと落ち着いたようで椅子に座り直した。
その時、キキーッと道路の方で盛大なブレーキ音が鳴った。衝突音はしなかった。大きな音に顔を顰める。よくあることではあるが、びっくりすることに変わりはないのだろう。
しかしその音に驚いてヒサトはびくっと手を浮かせた。反射的にサイトを閉じてしまう。彼の奥底の願いが反映された依頼は、今日も送信されることなく消えることもなく、サイト内にとどまったままだった。
ふう。深く息をついて魂を抜かれたようにふらふらとヒサトは立ち上がった。その足が置いてあった
開放感を味わいたかったのか、ヒサトはふと窓の外、そびえ立つホテルやビルに埋め尽くされた空の方に目をやった。
こちらに目を向けられ、咄嗟に
「ふう。びっくりした」
耳から盗聴用のイアフォンを取り出し、丸めて入れ物に直した。少し痛む耳を手で押さえる。
「それにしても、あのヒサトとかいう助手、全く警戒心がないなあ。大丈夫かなあ。自分のパソコンでアクセスするなんて」
適当に呟くながら部屋の中を見渡す。何もなかった。
「あの探偵も大丈夫かなあ。あれじゃあ全く面白くない」
イアフォンケースをぽつんとある備え付けのテーブルの上に置いた。何もすることがない。気が抜けてしまったのだ。
いくらか考え込んで立ち上がる。
「もう、やっちゃうか」
これ以上待っていても探偵は僕のところへは辿り着かない。ヒサトが依頼を送信する前に願いを叶えて、彼の驚く顔を見るというのもなかなかのものではなかろうか。
まあ、探偵は早く消しておくに越したことはないだろう。
そう決めた僕は、上着を羽織って部屋から出た。
探偵はどちらに向かったっけ。
どうでもいいと思っていたから曖昧な記憶しかない。それを頼りにぶらぶらと歩く。
「あの、これ、見覚えあります?」
その時、いきなり後ろを歩いていた人に声をかけられた。振り向いて見せられた青い絵に反応するまもなく、彼は目深に被っていた帽子をとり、僕の腕を捻りあげる。
それを合図に周囲から一斉に人が集まってきた。
「殺人教唆の疑いで、逮捕する」
僕を囲んだ人たちのうちの誰かがそう言った。
「バレてないなんてこと、あると思う? 君の幼稚なお遊びが。しかも盗聴器なんて、古いよ」
楽しみながらそう言う探偵の背後には、ヒサトが立っていた。服装はもちろん一緒。だが、こちらを見つめる目だけがさっきまでの愚鈍なものと違っている。
「じゃあ、全部——」
「そう。演技。そもそも僕には助手がいないよ。彼は、刑事。ちょっと貸してもらってるだけさ。だいぶ前からね」
そう探偵は得意に笑う。横に立つヒサトを名乗っていた刑事は迷惑そうに微笑んだ。心の声を代弁してやろう。“お前が無償の雑用に使ってるだけだろう”
「ヒサトも、感謝してるよ。それにしても、なんて書いたの?」
「なんのことですか?」
「とぼけるなよ。帰って調べればすぐバレるぞ」
「冗談ですよ。ただの冗談。自由に書けと言ったじゃないですか」
「確かにそう言ったが——。本当に冗談か? 見られて困るもの、書いてたんだろ」
「違いますよ」
訝しげな探偵と冷や汗をかいた助手——もとい刑事が危うい会話をする傍ら、僕は刑事たちにパトカーに押し込まれた。
——全く、最悪だ。
そう心の中でつぶやいて、僕は小さく首を横に振った。
ヒサトは小さくつぶやいた。
ここは大都市圏から少し外れた場所にあるビル街。といってもオフィスが立ち並ぶだけではなく、ヒサトのいるビルの向かい側にはホテルがあって、そこから少し歩けば大型複合商業施設が姿を現すような繁華な場所だ。
電車も通勤時を除いてはほとんど混んでいない。理想的な場所と言えるだろう。
ヒサトは今、まっさらなオフィスビルの三階にいる。大きくとられた明かり取りの窓には堂々と“三木村探偵事務所”との文字がある。
そしてヒサトはその探偵の助手であった。あの三木村探偵に彼のような愚鈍な助手が要るかどうかは甚だ疑問だが。
そんなことはさておき、今、三木村探偵事務所の中は静かだった。原因は以前から発生している殺人事件——手口も被害者もバラバラだが——がつながっているかもしれない件についてだ。
それを言い出したのは探偵だった。
「これらはつながっている、かもしれない」
同じ警察署の管轄内で立て続けに起こっていると言うだけで、被害者にも殺害方法にも共通点などなかったのだが、探偵はなぜかそう言った。たしかに三件連続というのは奇妙ではあったがそこまで気にかける話でもないのに。
三木村探偵はそういう風に事件を解決していた。答えが先にあって、後から論理を埋めるのだ。もちろんそれで失敗したことはない。だからヒサトも疑わない。
探偵の言葉を疑わないのはヒサトだけではない。警察もである。数々の事件を解決してきた探偵は、警察とも
深い
つながりがある。探偵の言葉に流されるがまま、無駄な考えを起こしては首を振ってそれらを掻き消し、記録と向き合っては頭をひねる。もちろん何一つわからない。
「ううん。やっぱり違うのかなあ」
そういって探偵は頭を掻く。手こずっているのだろう。
「しかし、これらの事件は繋がっていたんだ、って先生おっしゃってましたよね」
ここぞとばかりにヒサトが会話に加わった。
「うーん。その筈なんだけどねえ」
そう唸って探偵は首をもたげた。手を顎にあて、考え込むように部屋の中を歩き回る。靴が地面にあたってことことと音が鳴る。いつも思っているのだが、階下の人はうるさく無いのだろうか。
時々立ち止まったり、天井を見上げたり。そうかと思えばまた歩き回り始める。
その傍らで、ヒサトが探偵をじっと見つめていた。彼は格別洞察力があるわけでも、何か特殊な能力を持ち合わせているわけでもない。もちろん探偵に認められたことなどない。探偵が何を考えているかなど解らないし、自分なりに答えを組み立てようとしても正解には決して辿り着けないだろう。
つまりは諦めている。幾度となく探偵の事件解決についていった。その中でも結末を予想できたものなど一つもない。“予測”ではなく“予想”ですら無理だったのだ。探偵の思考を読み取ろうと努力することはまるで無駄な努力と思われた。
「あっ」
いきなり探偵が立ち止まった。組んでいた腕が解け、ぶらんと垂れ下がる。そしてさらに忙しなく歩き始めた。同時にぶつぶつと呟き始める。
「第一の被害者——」
「金城さん?」
反射的にその名を口に出す。捜査に加われる貴重な機会だ。大事にしなければ。
「そう。彼のお店に通っていたのは確か——」
「ええっと」
出番をやっと見つけたヒサトは水を得た魚のように動き始めた。手の届く場所にあったノートパソコンを開き、カタカタとキーボードを叩き始める。
「話を聞いたのは常連十人ほどですね。ええっと」
「ううん。二番目の被害者の交友関係は」
「そ、それはですね」
「それだとしたら、三番目にも」
完全に振り回されている。ヒサトとは違って、探偵の頭には事件に関する情報が完全にインプットされていた。困惑するヒサトを放置したまま探偵は頭を高速回転させていく。
ヒサトはこの疎外感が嫌いだったのかもしれない。
「そうだ。あれだ。青色の。じゃあそれが全てをつなぐ——」
突然の大声と言葉にヒサトは思わず立ち上がった。
「うわぁ」
軽く息を整える。
探偵は彼の動向など全く気にせず、窓に近寄り、考え込んだ。そして、いきなり、つかつかと歩いていき、ばんっと備え付けのクローゼットを乱暴に開けた。中から帽子とコートを取り出す。
乱雑にそれを羽織り、頭にかぶせる。一言、「ちょっと、行ってくる」とだけ残して、部屋から出ていってしまった。
ヒサトには声をかける暇さえない。開けっぱなしになっているドアに近づいて外を覗き込んでも静かな階段があるだけだった。
さっきまでとは違い、静寂がおとずれた。ヒサトは道路に面した窓から道路を覗く。行き交う車と人に紛れて、探偵は帽子を片手で押さえてコートをはためかせながら走っていった。
大きくため息をついて先ほどの椅子に座り直す。
散々悩んだ末に先ほどのノートパソコンを開いた。二番目の被害者の名前が検索欄に表示されているタブを消去して、新しく検索エンジンを開いた。
URL欄に一生使わないような文字化けによく似た文字列を打ち込んでいく。最後にEnterキーを押して、現れたのは真っ白いページ。
そこでヒサトは慣れた手つきで画面上でカーソルを走らせ、クリックしていく。十秒くらいして息をついた。力が抜けたように椅子にもたれかかる。ぼうっと天井を見上げた。
ノートパソコンの画面はもう白いだけではなくなっていた。真ん中には青くてごちゃごちゃしたロゴ。青だけなのにどこか毒々しい。
それは、探偵が調査していた事件の被害者の友人。ややこしい立ち位置の人に共通していたもの——。
姿勢を戻したヒサトがさらにカーソルを動かし続ける。
少しして画面にはさらに変化が訪れた。青く毒々しいマークはそのままで、下に検索欄のようなものが現れた。中に書かれているのは“三木村ろくを殺害して”という文字。
それを目にしていきなり危機感を覚えたのかヒサトはキョロキョロと周りを見回した。そしてやっと落ち着いたようで椅子に座り直した。
その時、キキーッと道路の方で盛大なブレーキ音が鳴った。衝突音はしなかった。大きな音に顔を顰める。よくあることではあるが、びっくりすることに変わりはないのだろう。
しかしその音に驚いてヒサトはびくっと手を浮かせた。反射的にサイトを閉じてしまう。彼の奥底の願いが反映された依頼は、今日も送信されることなく消えることもなく、サイト内にとどまったままだった。
ふう。深く息をついて魂を抜かれたようにふらふらとヒサトは立ち上がった。その足が置いてあった
開放感を味わいたかったのか、ヒサトはふと窓の外、そびえ立つホテルやビルに埋め尽くされた空の方に目をやった。
こちらに目を向けられ、咄嗟に
僕
はカーテンを引いた。「ふう。びっくりした」
耳から盗聴用のイアフォンを取り出し、丸めて入れ物に直した。少し痛む耳を手で押さえる。
「それにしても、あのヒサトとかいう助手、全く警戒心がないなあ。大丈夫かなあ。自分のパソコンでアクセスするなんて」
適当に呟くながら部屋の中を見渡す。何もなかった。
「あの探偵も大丈夫かなあ。あれじゃあ全く面白くない」
イアフォンケースをぽつんとある備え付けのテーブルの上に置いた。何もすることがない。気が抜けてしまったのだ。
いくらか考え込んで立ち上がる。
「もう、やっちゃうか」
これ以上待っていても探偵は僕のところへは辿り着かない。ヒサトが依頼を送信する前に願いを叶えて、彼の驚く顔を見るというのもなかなかのものではなかろうか。
まあ、探偵は早く消しておくに越したことはないだろう。
そう決めた僕は、上着を羽織って部屋から出た。
探偵はどちらに向かったっけ。
どうでもいいと思っていたから曖昧な記憶しかない。それを頼りにぶらぶらと歩く。
「あの、これ、見覚えあります?」
その時、いきなり後ろを歩いていた人に声をかけられた。振り向いて見せられた青い絵に反応するまもなく、彼は目深に被っていた帽子をとり、僕の腕を捻りあげる。
それを合図に周囲から一斉に人が集まってきた。
「殺人教唆の疑いで、逮捕する」
僕を囲んだ人たちのうちの誰かがそう言った。
「バレてないなんてこと、あると思う? 君の幼稚なお遊びが。しかも盗聴器なんて、古いよ」
楽しみながらそう言う探偵の背後には、ヒサトが立っていた。服装はもちろん一緒。だが、こちらを見つめる目だけがさっきまでの愚鈍なものと違っている。
「じゃあ、全部——」
「そう。演技。そもそも僕には助手がいないよ。彼は、刑事。ちょっと貸してもらってるだけさ。だいぶ前からね」
そう探偵は得意に笑う。横に立つヒサトを名乗っていた刑事は迷惑そうに微笑んだ。心の声を代弁してやろう。“お前が無償の雑用に使ってるだけだろう”
「ヒサトも、感謝してるよ。それにしても、なんて書いたの?」
「なんのことですか?」
「とぼけるなよ。帰って調べればすぐバレるぞ」
「冗談ですよ。ただの冗談。自由に書けと言ったじゃないですか」
「確かにそう言ったが——。本当に冗談か? 見られて困るもの、書いてたんだろ」
「違いますよ」
訝しげな探偵と冷や汗をかいた助手——もとい刑事が危うい会話をする傍ら、僕は刑事たちにパトカーに押し込まれた。
——全く、最悪だ。
そう心の中でつぶやいて、僕は小さく首を横に振った。