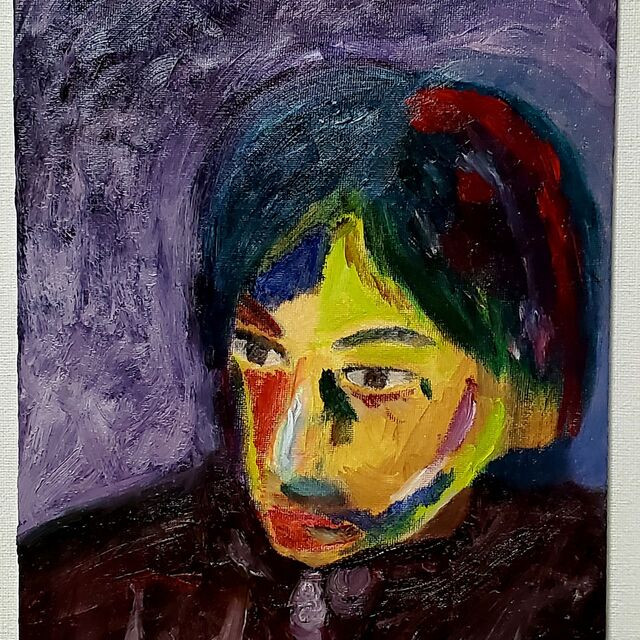とある真冬の幸福論
文字数 1,742文字
十二月三十一日。
さて、いつにしようか。
雪。大晦日。一年の終わり。
誰かの誕生日。誰かの忌日。
春の風はまだ遠い。
マフラーが飛んでいく。祖母が編んでくれた思い出の。
段ボール箱にしまっていたはずのアルバムが、ある日ふと、世界で一番バレたくない人にバレる夢を見た。
ぼくの世界は、決してきれいではないけれど、決して汚くもない。いや、幻想かもしれない。
上ってきた階段になにかを落とした気がする。誰かがぼくの名前を呼ぶ。それも詩的に。
歌おう、詩を。
「ねえ、それ、いくらあるの?」
ビルの屋上。
「さあ。二十万ぐらいじゃない?」
少女だった。
「いらないなら、ちょうだい」
ぼくは少し考えながら、
「これも、夢?」
と聞いてみた。
少女は、笑った。
「夢だよ」
髪の毛はぼさぼさ、服はぼろぼろ。
「かわいそうだね」
「あなただって」
突風。
目に雪が――。
この話はお金についてである。私が思う現時点でのイメージを文字に起こしているだけなのだが、なんせ貧相な発想しかないので、いまのところこんな陳腐な物語になってしまっているが、ここからどうにか盛り上げてみたい。いや、盛り上げてみせる。それがお金に対して、この主人公に対して、なによりもこの薄幸の少女に対する贖罪ではないだろうか。
寒い。もう冬だ。
幸運を祈る。
少女は、涙した。
「どっちの意味で?」
「両方よ」
風になびく。
かじかんだ指の隙間から、お札が一枚飛んでいった。
「あっ」
ぼくは、ようやく自分の名前を思い出した。
雪が降った翌日は、音がない。目を覚まして、その辺に落ちている、まだ燃やされていない本をパラパラとめくる。哲学も思想もない、単調な文字の羅列。ぼくの頭の中そっくりで、だからきっと腹が立ったのだろう、今にも消えそうな火種の中に無造作に突っ込んだ。その音で、少女は目を覚ました。
いや、待て。私はいったいなにを書いているのだろうか。この物語は、あまりにも冷たい。
(ここ最近、私は幸せに浸っている。幸福とは、一種の毒だ。頭の中がぼんやりとして、今までできていたことがまるでできなくなり、青天の霹靂、思えば、気が狂いそうになりながらも、向精神薬を断絶したときに見た夜空の星の瞬きのように、幸福はまぶしく、涙が溢れてしまう、そんなものなのだ)
氷河期。人類の終焉。
年は暮れ。雪。廃墟。
西暦は分からないが、おそらく、未来だ。
少女。どうにか、幸せになってほしいものだが。
「そのお金で、なにが買えたの?」
そうか、とぼくは思った。
「なんでも買えたさ。食べ物はもちろん、服、車、家、健康、友人、恋人、家族、好きなところに行けて、好きな夢が見られて、寿命だって金次第、大切な人の命も――」
少女は手の中にあるお札を見つめながら、悲しそうに言った。
「今は、なにが買えるの?」
すきま風。まるで泣き声のように。
「なにも買えないよ」
太陽が懐かしかった。もう一度、ただもう一度だけ。
「きみは、なにが欲しいの?」
腹が減った。ぼくたちは、もうすぐ死ぬ。
「ちょっと考えさせて」
少女は水を口に含んで、お札を抱いたまま、横になった。ぼくに背中を向けて。
鼻がかゆい。目が痛い。なにもかもが冷たくて、眠ることすら恐ろしくて、燃えていく先人たちの遺産に虚無感を覚えながら、なぜ人間はものを考えるのだろうか、と目の前の現実を逃避してみたり、きっと、ぼくたちは暇なのだ、永遠に、目的も、やるべきことも、本当はなに一つなくて、生きる意味も、死ぬ意味も、その価値観にゆさぶりを掛けながら他人を生み出し、ゲーム、遊び、言ってしまえば、ぼくたちはひたすらに遊んでいるのだ、見てくれ、この目の前に広がる神々しいまでの真っ白な世界を! ぼくたちは、暇で暇で仕方がない!
愚か。
「今夜……」
そう言いかけたとき、少女がこっちを振り向いて、
「わたし、お金で買えないものが欲しい」
ぼくは、口をつぐんだ。そんなもの、そんなもの――。
もう一度だけ。
「それなら、もうそんなものいらないね」
光。
炎に照らされて、涙の跡がありありと見える。
頭がぼんやりとしてくる。
ぼくは幸福を思い出していた。
きっと、彼女も同じだと思う。
幸せは、イメージ。
人間の。
心象の。
永遠の。
さて、いつにしようか。
雪。大晦日。一年の終わり。
誰かの誕生日。誰かの忌日。
春の風はまだ遠い。
マフラーが飛んでいく。祖母が編んでくれた思い出の。
段ボール箱にしまっていたはずのアルバムが、ある日ふと、世界で一番バレたくない人にバレる夢を見た。
ぼくの世界は、決してきれいではないけれど、決して汚くもない。いや、幻想かもしれない。
上ってきた階段になにかを落とした気がする。誰かがぼくの名前を呼ぶ。それも詩的に。
歌おう、詩を。
「ねえ、それ、いくらあるの?」
ビルの屋上。
「さあ。二十万ぐらいじゃない?」
少女だった。
「いらないなら、ちょうだい」
ぼくは少し考えながら、
「これも、夢?」
と聞いてみた。
少女は、笑った。
「夢だよ」
髪の毛はぼさぼさ、服はぼろぼろ。
「かわいそうだね」
「あなただって」
突風。
目に雪が――。
この話はお金についてである。私が思う現時点でのイメージを文字に起こしているだけなのだが、なんせ貧相な発想しかないので、いまのところこんな陳腐な物語になってしまっているが、ここからどうにか盛り上げてみたい。いや、盛り上げてみせる。それがお金に対して、この主人公に対して、なによりもこの薄幸の少女に対する贖罪ではないだろうか。
寒い。もう冬だ。
幸運を祈る。
少女は、涙した。
「どっちの意味で?」
「両方よ」
風になびく。
かじかんだ指の隙間から、お札が一枚飛んでいった。
「あっ」
ぼくは、ようやく自分の名前を思い出した。
雪が降った翌日は、音がない。目を覚まして、その辺に落ちている、まだ燃やされていない本をパラパラとめくる。哲学も思想もない、単調な文字の羅列。ぼくの頭の中そっくりで、だからきっと腹が立ったのだろう、今にも消えそうな火種の中に無造作に突っ込んだ。その音で、少女は目を覚ました。
いや、待て。私はいったいなにを書いているのだろうか。この物語は、あまりにも冷たい。
(ここ最近、私は幸せに浸っている。幸福とは、一種の毒だ。頭の中がぼんやりとして、今までできていたことがまるでできなくなり、青天の霹靂、思えば、気が狂いそうになりながらも、向精神薬を断絶したときに見た夜空の星の瞬きのように、幸福はまぶしく、涙が溢れてしまう、そんなものなのだ)
氷河期。人類の終焉。
年は暮れ。雪。廃墟。
西暦は分からないが、おそらく、未来だ。
少女。どうにか、幸せになってほしいものだが。
「そのお金で、なにが買えたの?」
そうか、とぼくは思った。
「なんでも買えたさ。食べ物はもちろん、服、車、家、健康、友人、恋人、家族、好きなところに行けて、好きな夢が見られて、寿命だって金次第、大切な人の命も――」
少女は手の中にあるお札を見つめながら、悲しそうに言った。
「今は、なにが買えるの?」
すきま風。まるで泣き声のように。
「なにも買えないよ」
太陽が懐かしかった。もう一度、ただもう一度だけ。
「きみは、なにが欲しいの?」
腹が減った。ぼくたちは、もうすぐ死ぬ。
「ちょっと考えさせて」
少女は水を口に含んで、お札を抱いたまま、横になった。ぼくに背中を向けて。
鼻がかゆい。目が痛い。なにもかもが冷たくて、眠ることすら恐ろしくて、燃えていく先人たちの遺産に虚無感を覚えながら、なぜ人間はものを考えるのだろうか、と目の前の現実を逃避してみたり、きっと、ぼくたちは暇なのだ、永遠に、目的も、やるべきことも、本当はなに一つなくて、生きる意味も、死ぬ意味も、その価値観にゆさぶりを掛けながら他人を生み出し、ゲーム、遊び、言ってしまえば、ぼくたちはひたすらに遊んでいるのだ、見てくれ、この目の前に広がる神々しいまでの真っ白な世界を! ぼくたちは、暇で暇で仕方がない!
愚か。
「今夜……」
そう言いかけたとき、少女がこっちを振り向いて、
「わたし、お金で買えないものが欲しい」
ぼくは、口をつぐんだ。そんなもの、そんなもの――。
もう一度だけ。
「それなら、もうそんなものいらないね」
光。
炎に照らされて、涙の跡がありありと見える。
頭がぼんやりとしてくる。
ぼくは幸福を思い出していた。
きっと、彼女も同じだと思う。
幸せは、イメージ。
人間の。
心象の。
永遠の。