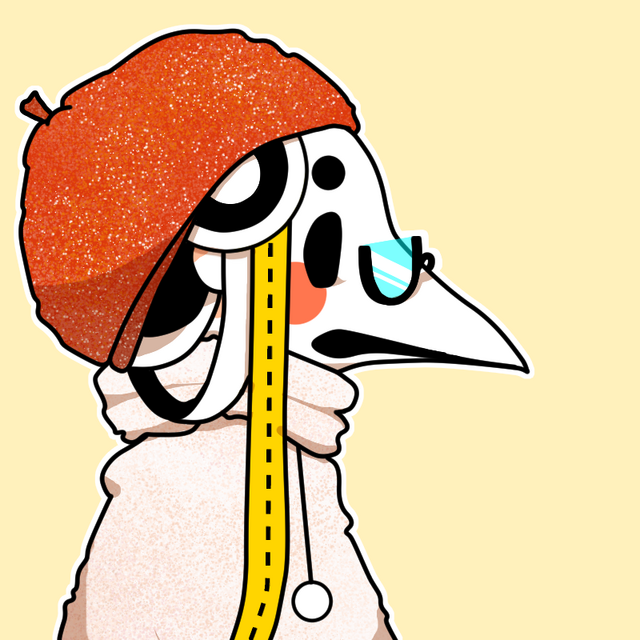カリフォルニアレモネード
文字数 3,678文字
カラン
扉を開けると小気味良い音を立ててベルが鳴った。半分ほどの客入りの店内にはうるさくない程度の笑い声と音楽がお互いを調和させるように流れている。昼間は喫茶店をやっているだけあって、バーの時間帯でもどことなく昼の穏やかな木漏れ日を感じさせるような店内に、酒と煙草の匂いが混じり合って薄く漂う様は他の店では見ることの出来ないお気に入りのポイントだ。
カウンターの向こう側に佇む店主は昔から無愛想で、客が入ってきても案内すらせずに黙々とグラスを磨く。この店は俺が高校生の時からあり、よくもまぁ、こんな店主で潰れないものだと言われることもあるようだが、おっちゃんの入れるコーヒーとカクテルほど美味いものはない。
邪魔するよ、と声を掛けるとおっちゃんは遠い目をして角に寄せて繋げられたテーブル席の方を見つめる。ああ、あそこね。
大人数が来ることを想定していない為、俺達が集まるときはいつもこうしてテーブルを寄せてつける。そこには四人の男女と一つ空いた席がある。他のお客の邪魔にならないよう、広くない店内をゆっくりと進んで空いたその席に座った。
「遅れてごめん。お待たせ」
目の前を見ると既にカクテルが置いてあった。俺の好きなカリフォルニアレモネードだ。こんな風に先に注文してくれたのはこの中でも一番の気遣い屋のマナだろうか。はっきりとした顔立ちとオーラのせいか彼女は怖いと高校の頃からよく言われていたが誰よりも優しく、さり気ない気配りが出来る友人だ。
「マナ、カクテルありがとうな」
「ケイゴはカリフォルニアレモネード好きだったよね」
マナは隣で突っ伏しているミキの背中を撫でながら俺のカクテルをじっと見て呟いた。
その言葉に反応するように伏せっていたミキが体を起こす。緩く巻かれた髪が動きに合わせて肩から落ちる。
「そんな洒落たモノが好きとか…ほんっともう…飲まなきゃやってらんない。ほら、ヤマトも飲んで!」
「ミキちゃん飲みすぎ…」
「いーのいーの!今日は飲むの絶対飲むの…ヤマト飲んでっかー?」
「飲むのはいいが、帰るのが大変になるぞ」
「そうだぞミキ。もう送るの無理だからな」
そう言って宥めてみたがミキは聞く耳持たずといった様子で、うにゃうにゃとよく分からないことを言っている。
大学生の頃、俺とミキは住んでいるアパートが近く、五人で集まると酔い潰れたミキを送っていったものだ。卒業しそれぞれが職に就いたあともミキは飲み過ぎると送っていけと言うことがあった。そのアパートはもう引っ越したんだと言っても聞かず、結局俺とヤマトがタクシーに押し込む、までがいつものセットだった。だからこそあまり飲ませたくなかったのだが、まさか遅れて来るまでの間にここまで出来上がるとは………。
「そういえば勤め始めた頃、ユウダイがケイゴのスーツに吐いて大変だったな」
隣に座るヤマトが懐かしむように喉を鳴らして笑う。
あの時は本当に大変だった。替えのスーツはあったものの、すでに深夜だった為クリーニングに出せないわ、次の日会社の前で顔面蒼白のユウダイに土下座されるわで通りかかった会社の先輩に大笑いされた。ユウダイはこの中で一番頭がよく知識も豊富だが変なところで融通が効かない。それもまた、彼らしさなのかもしれないが。
そのあと、土下座するユウダイを何とか立たせ、引きずるように会社から離れたあとに入った定食屋で彼は言った。
就職したてで、毎日緊張してたんだ。僕は人間関係が得意じゃないし…それでみんなと会って気が緩んじゃって…と。
彼が職場で緊張していた理由は何となく分かっていた。ユウダイは自分自身に厳しい。その厳しさが「こうであるべきだ」と制限をかけ、人と関係性を作る最初の部分がうまくいかない。けれどこうして謝れる素直さも持ち合わせている。それを俺達は知っている。きっと本人にも思うところがあるだろう。余計なことは言うまいと大丈夫だよ。ユウダイなら大丈夫だって、とだけ返すとごめん。いや、ありがとうと言って笑った。その顔はいい笑顔だった。
そしてそのユウダイは現在ヤマトの隣でミキと同じようにテーブルに突っ伏している。しかも寝ていた。スーツ事件以来、酒は飲まないようになったと言っていたし実際前に会ったときも飲んでいなかったのにこれは一体どうしたものか。
「ユウダイくん寝ちゃったね」
「まぁ…飲めないのに無理矢理飲んでたからな」
「二人ともどうして止めてやらなかったのさ」
「今日も結構無理して時間作ってきたみたい」
「来ないって選択肢がなかったんだろ。俺だってそうだし。マナもだろ?」
「うん…私もヤマトも夜勤じゃなくて良かったね」
「二人は夜勤あるもんな…」
マナとヤマトは介護士として入所型の老人ホームに勤務している。それぞれ会社は違うが、やはり夜勤がしんどいとよくグループメッセージで言っていた。ミキはアパレル関係、ユウダイはSE。大学卒業後、俺達は日々の生活に追われ少しずつ集まるのが難しくなっていった。それでも時間を見つけては都合をつけていたが、ここ四、五年はメッセージのやり取りだけになっていた。それを悲しいだとか寂しいとは思わない。時々連絡をとって、元気で幸せなら嬉しい。会えばまた昨日の続きのように笑い合える、そういう関係だった。貴重で尊敬出来る友人たち。地続きの日常から離れ、けれど自分をよく知っている人がいる。それは俺にとって幸せなことだった。
「ちょっとお手洗いに連れて行くね」
マナがミキを支えながら立ち上がる。おぼつかない足取りのミキは向かう途中、う…気持ち悪い…いやでもまだ飲む…あーもーケイゴのバカヤロー…気持ち悪い…とぶつぶつ言っていた。え?あれ?なんで俺怒られてるの?何という理不尽。
二人が化粧室へ消えるとヤマトが煙草を取り出し火をつける。同じように火をつけると普段は身体に悪いからと三人から一斉にお小言が飛んでくるのが常だったせいか、少し静かに感じる。
「もっと、早く、会っておけば良かった」
吐き出した紫煙に隠すように乗せられたその言葉からはヤマトの感情が見えない。
他の三人とは違い、ヤマトは中学生の頃からの付き合いだ。どういった経緯で仲良くなったのかは思い出せない。それほどに違和感のない、当たり前のことだったのかもしれない。勉強会と銘打って徹夜でゲームしたり、親の居ない間にビールを飲んでみたり、馬鹿なことをたくさんやった。初めて煙草を吸ったのもこいつと一緒だったっけ。何をさせても卒なくこなし、情に厚く面倒見が良い。
憧れのような、尊敬のような、ライバルのような親友。面と向かっては絶対に言わないけれど、ヤマトと友達になれて良かった。もちろん、マナもミキもユウダイもだ。
置かれたカリフォルニアレモネードはグラスに汗をかき、氷が溶けて水になってしまっている。色は下へ、透明は上へ。綺麗なまでに分かれたそれを混ぜようと手を伸ばしてやめた。
腕時計を見るとそろそろいい時間だった。遅れて来たのに先に抜けるのは申し訳ないが、仕方ない。
ユウダイを起こさないように静かに立ち上がる。マナとミキはまだ戻らない。すぐには無理だろうが、まぁ、また会えるだろう。
「じゃあな。集まってくれてありがとう。みんなによろしく」
ヤマトにそう伝えて来たときと同じようにドアへと向かう。その時、背中に言葉がぶつかった。それは本当に小さな、呻くような、ともすれば泣き出してしまいそうな声だった。
「ケイゴ、なに勝手に死んでんだよ。バカヤロ…ッ」
「………ごめんな」
外へ出るときにベルの音は聞こえなかった。俺が"自分が通ってもベルは動かない"と認識してしまったから。
最後にみんなに会えて良かった。最後にこの店でみんなと飲めて良かった。誰にも見えていなくても感じられなくても嬉しかった。きっとヤマトがおっちゃんの店で仲間内での精進落しをしようと言ったのだろう。
「………あれ?」
気が付くと頬を冷たいものが伝っていた。
ベルと同じく涙はもう流れないものだと思っていたのに。溢れる涙は止まらず、止めることも出来ず、せっかくみんなが送り出してくれたというのに、それなのに、いやそれでも。
「もっとみんなと居たかったなぁ…」
当たり前のように、みんなと笑い合って、歳をとって、酒を飲んで、たまに自分自身が嫌になっても生きていく。痛くても悲しくても生きていく。ただ、それだけを望んでいた。
そんなことを今更になって気が付くなんて。
月のない暗い夜の下、入れ違いに別の客がバーへ行っていく。
一瞬開いた扉から流れ出る音楽と食べ物の匂い。外の空気と混ざり合うことで、煙草やアルコールが余計に際立つ。閉じたあとも薄っすらと笑い声を通す扉の前を通り過ぎた時、一度だけ振り返った。そこに特別なものはなく、ただ閉じた扉が小さな秘密を守っていた。
了
カリフォルニアレモネード/永遠の感謝
このお話の解釈〈自分が死んだ後の自分を見送った人達を最後に軽く自分が見送って去る時の風景〉は、はびえる様(TwitterID/@ Tanindamon)から頂きました。
ありがとうございました。
扉を開けると小気味良い音を立ててベルが鳴った。半分ほどの客入りの店内にはうるさくない程度の笑い声と音楽がお互いを調和させるように流れている。昼間は喫茶店をやっているだけあって、バーの時間帯でもどことなく昼の穏やかな木漏れ日を感じさせるような店内に、酒と煙草の匂いが混じり合って薄く漂う様は他の店では見ることの出来ないお気に入りのポイントだ。
カウンターの向こう側に佇む店主は昔から無愛想で、客が入ってきても案内すらせずに黙々とグラスを磨く。この店は俺が高校生の時からあり、よくもまぁ、こんな店主で潰れないものだと言われることもあるようだが、おっちゃんの入れるコーヒーとカクテルほど美味いものはない。
邪魔するよ、と声を掛けるとおっちゃんは遠い目をして角に寄せて繋げられたテーブル席の方を見つめる。ああ、あそこね。
大人数が来ることを想定していない為、俺達が集まるときはいつもこうしてテーブルを寄せてつける。そこには四人の男女と一つ空いた席がある。他のお客の邪魔にならないよう、広くない店内をゆっくりと進んで空いたその席に座った。
「遅れてごめん。お待たせ」
目の前を見ると既にカクテルが置いてあった。俺の好きなカリフォルニアレモネードだ。こんな風に先に注文してくれたのはこの中でも一番の気遣い屋のマナだろうか。はっきりとした顔立ちとオーラのせいか彼女は怖いと高校の頃からよく言われていたが誰よりも優しく、さり気ない気配りが出来る友人だ。
「マナ、カクテルありがとうな」
「ケイゴはカリフォルニアレモネード好きだったよね」
マナは隣で突っ伏しているミキの背中を撫でながら俺のカクテルをじっと見て呟いた。
その言葉に反応するように伏せっていたミキが体を起こす。緩く巻かれた髪が動きに合わせて肩から落ちる。
「そんな洒落たモノが好きとか…ほんっともう…飲まなきゃやってらんない。ほら、ヤマトも飲んで!」
「ミキちゃん飲みすぎ…」
「いーのいーの!今日は飲むの絶対飲むの…ヤマト飲んでっかー?」
「飲むのはいいが、帰るのが大変になるぞ」
「そうだぞミキ。もう送るの無理だからな」
そう言って宥めてみたがミキは聞く耳持たずといった様子で、うにゃうにゃとよく分からないことを言っている。
大学生の頃、俺とミキは住んでいるアパートが近く、五人で集まると酔い潰れたミキを送っていったものだ。卒業しそれぞれが職に就いたあともミキは飲み過ぎると送っていけと言うことがあった。そのアパートはもう引っ越したんだと言っても聞かず、結局俺とヤマトがタクシーに押し込む、までがいつものセットだった。だからこそあまり飲ませたくなかったのだが、まさか遅れて来るまでの間にここまで出来上がるとは………。
「そういえば勤め始めた頃、ユウダイがケイゴのスーツに吐いて大変だったな」
隣に座るヤマトが懐かしむように喉を鳴らして笑う。
あの時は本当に大変だった。替えのスーツはあったものの、すでに深夜だった為クリーニングに出せないわ、次の日会社の前で顔面蒼白のユウダイに土下座されるわで通りかかった会社の先輩に大笑いされた。ユウダイはこの中で一番頭がよく知識も豊富だが変なところで融通が効かない。それもまた、彼らしさなのかもしれないが。
そのあと、土下座するユウダイを何とか立たせ、引きずるように会社から離れたあとに入った定食屋で彼は言った。
就職したてで、毎日緊張してたんだ。僕は人間関係が得意じゃないし…それでみんなと会って気が緩んじゃって…と。
彼が職場で緊張していた理由は何となく分かっていた。ユウダイは自分自身に厳しい。その厳しさが「こうであるべきだ」と制限をかけ、人と関係性を作る最初の部分がうまくいかない。けれどこうして謝れる素直さも持ち合わせている。それを俺達は知っている。きっと本人にも思うところがあるだろう。余計なことは言うまいと大丈夫だよ。ユウダイなら大丈夫だって、とだけ返すとごめん。いや、ありがとうと言って笑った。その顔はいい笑顔だった。
そしてそのユウダイは現在ヤマトの隣でミキと同じようにテーブルに突っ伏している。しかも寝ていた。スーツ事件以来、酒は飲まないようになったと言っていたし実際前に会ったときも飲んでいなかったのにこれは一体どうしたものか。
「ユウダイくん寝ちゃったね」
「まぁ…飲めないのに無理矢理飲んでたからな」
「二人ともどうして止めてやらなかったのさ」
「今日も結構無理して時間作ってきたみたい」
「来ないって選択肢がなかったんだろ。俺だってそうだし。マナもだろ?」
「うん…私もヤマトも夜勤じゃなくて良かったね」
「二人は夜勤あるもんな…」
マナとヤマトは介護士として入所型の老人ホームに勤務している。それぞれ会社は違うが、やはり夜勤がしんどいとよくグループメッセージで言っていた。ミキはアパレル関係、ユウダイはSE。大学卒業後、俺達は日々の生活に追われ少しずつ集まるのが難しくなっていった。それでも時間を見つけては都合をつけていたが、ここ四、五年はメッセージのやり取りだけになっていた。それを悲しいだとか寂しいとは思わない。時々連絡をとって、元気で幸せなら嬉しい。会えばまた昨日の続きのように笑い合える、そういう関係だった。貴重で尊敬出来る友人たち。地続きの日常から離れ、けれど自分をよく知っている人がいる。それは俺にとって幸せなことだった。
「ちょっとお手洗いに連れて行くね」
マナがミキを支えながら立ち上がる。おぼつかない足取りのミキは向かう途中、う…気持ち悪い…いやでもまだ飲む…あーもーケイゴのバカヤロー…気持ち悪い…とぶつぶつ言っていた。え?あれ?なんで俺怒られてるの?何という理不尽。
二人が化粧室へ消えるとヤマトが煙草を取り出し火をつける。同じように火をつけると普段は身体に悪いからと三人から一斉にお小言が飛んでくるのが常だったせいか、少し静かに感じる。
「もっと、早く、会っておけば良かった」
吐き出した紫煙に隠すように乗せられたその言葉からはヤマトの感情が見えない。
他の三人とは違い、ヤマトは中学生の頃からの付き合いだ。どういった経緯で仲良くなったのかは思い出せない。それほどに違和感のない、当たり前のことだったのかもしれない。勉強会と銘打って徹夜でゲームしたり、親の居ない間にビールを飲んでみたり、馬鹿なことをたくさんやった。初めて煙草を吸ったのもこいつと一緒だったっけ。何をさせても卒なくこなし、情に厚く面倒見が良い。
憧れのような、尊敬のような、ライバルのような親友。面と向かっては絶対に言わないけれど、ヤマトと友達になれて良かった。もちろん、マナもミキもユウダイもだ。
置かれたカリフォルニアレモネードはグラスに汗をかき、氷が溶けて水になってしまっている。色は下へ、透明は上へ。綺麗なまでに分かれたそれを混ぜようと手を伸ばしてやめた。
腕時計を見るとそろそろいい時間だった。遅れて来たのに先に抜けるのは申し訳ないが、仕方ない。
ユウダイを起こさないように静かに立ち上がる。マナとミキはまだ戻らない。すぐには無理だろうが、まぁ、また会えるだろう。
「じゃあな。集まってくれてありがとう。みんなによろしく」
ヤマトにそう伝えて来たときと同じようにドアへと向かう。その時、背中に言葉がぶつかった。それは本当に小さな、呻くような、ともすれば泣き出してしまいそうな声だった。
「ケイゴ、なに勝手に死んでんだよ。バカヤロ…ッ」
「………ごめんな」
外へ出るときにベルの音は聞こえなかった。俺が"自分が通ってもベルは動かない"と認識してしまったから。
最後にみんなに会えて良かった。最後にこの店でみんなと飲めて良かった。誰にも見えていなくても感じられなくても嬉しかった。きっとヤマトがおっちゃんの店で仲間内での精進落しをしようと言ったのだろう。
「………あれ?」
気が付くと頬を冷たいものが伝っていた。
ベルと同じく涙はもう流れないものだと思っていたのに。溢れる涙は止まらず、止めることも出来ず、せっかくみんなが送り出してくれたというのに、それなのに、いやそれでも。
「もっとみんなと居たかったなぁ…」
当たり前のように、みんなと笑い合って、歳をとって、酒を飲んで、たまに自分自身が嫌になっても生きていく。痛くても悲しくても生きていく。ただ、それだけを望んでいた。
そんなことを今更になって気が付くなんて。
月のない暗い夜の下、入れ違いに別の客がバーへ行っていく。
一瞬開いた扉から流れ出る音楽と食べ物の匂い。外の空気と混ざり合うことで、煙草やアルコールが余計に際立つ。閉じたあとも薄っすらと笑い声を通す扉の前を通り過ぎた時、一度だけ振り返った。そこに特別なものはなく、ただ閉じた扉が小さな秘密を守っていた。
了
カリフォルニアレモネード/永遠の感謝
このお話の解釈〈自分が死んだ後の自分を見送った人達を最後に軽く自分が見送って去る時の風景〉は、はびえる様(TwitterID/@ Tanindamon)から頂きました。
ありがとうございました。