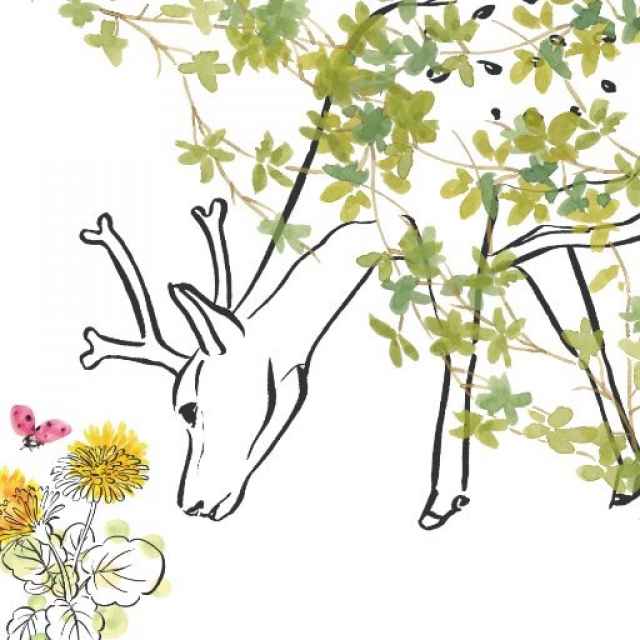1-2
文字数 3,411文字
静寂が包み込む空間の中で、シスターの柔らかな声だけが響く。
それなりの年齢を重ねている彼女の腰は少し曲がってしまっているけれど、穏やかなその声はきちんと教会中に届いている。何処か力強いその声には年齢を感じさせない程の力があった。
「神は我々に試練を与えました。それは辛く、苦しい道のりですが……その先にある幸福を掴み取るに値する人間にのみそれは与えられているのです。恐れることはありません、試練を与えられている我々に待つのは他ならぬ幸福の日々です」
シスターの言葉を人々は静かに聞いている。そんな彼らを、私は教会の片隅でまた静かに眺めていた。
昼下がりの礼拝が終わった後、私は教会の入り口に立って出席者の見送りをしていた。教会を後にする人々に軽く会釈をしていく。
「いつも見送りありがとうね、シルフィちゃん」
正面から声を掛けられる。よく耳にしている低い声は教会の近くで酒場を営んでいるマスターのものだ。私は顔を上げてにこりと笑顔を浮かべる。
「ううん。シスターみたいに有り難いお話も、手伝いだって沢山は出来ないから。これくらいはね」
「十分だよ。今日は目の調子、大丈夫なのかい?」
その問いに私は一つ頷く。
「うん、まあね。痛くはないから」
「そうかい?まあ、あまり無理しないようにね」
「ありがとう」
お礼を言うとマスターは「それじゃあね」と言いながら今度こそ教会を後にしていった。もしかしたら軽く手を振ってくれたのかもしれない。去り際に少しだけ空気が揺れたのが伝わってきたから。
けれどそれを私が目視で確認することは出来ない。
両目を包帯で幾重にも巻かれている私は現在、視界を奪われている為だ。
教会から人々が帰っていった後、私は扉を閉めて一息吐く。
視界が奪われていること自体はもう慣れてしまっているけれど、だからといって普通の人間と同じように動けるわけではないのだ。シスターと同じ修道服を身に付けていても私自身に出来ることは案外少ない。
「シルフィ」
後ろから呼び掛けられて、私はくるりと後ろを振り返る。礼拝中に聞こえていた声と同じ老女の声、シスターだ。
「何? シスター」
「教会の掃除が終わったら、少し荷物持ちを手伝ってくれるかい。家にある食料が乏しくなってきててねえ」
「うん、勿論」
「助かるよ」
そう言って、シスターは私の手を取ると何かを握らせてくれる。
布状の感触がするそれは柔らかい材質で出来ている布巾だ。目の見えない私は箒で塵を集めるよりも窓や扉、調度品を拭く方が向いている。初めは上手く出来なかったけれど二年も経てば見えなくてもそれなりに出来るようになるものだ。
最早日課となっているそうした仕事を今日も私は淡々とこなしていく。
粗方の掃除が終わった所で、私はシスターと一緒に地下倉庫へと足を運んでいた。
こぢんまりとした教会だから地下倉庫は決して広くはないけれど、それでも隣に建てられている家よりは広い。そういうわけでこの倉庫には教会で使う物に加えて穀物等保存の利く食料も保管しているのだ。
目の見えない私は物を識別することが出来ないので、代わりにシスターが必要な物を探して私に持たせてくれる。
ずしりとした重みと麻袋から伝わるごつごつとした感触。きっと中身は芋か何かだろう。
「重たくはないかい?」
私がしっかりと受け取ったことを確認してから、シスターが荷物から手を離す。同時にそんなことを聞かれて、私は首を縦に振った。
「平気だよ」
「辛くなったら無理せず休んで良いからね」
「これくらいなら大丈夫だよ、家だって近いんだから」
あまりに心配するシスターに思わず笑ってしまうと、彼女もつられたように笑い声を上げた。
「あはは、そうさね。老いぼれのあたしと違ってシルフィは若いんだから、無用な心配だったねえ」
「そういうこと。行こう」
そうして二人で笑い合っていたけれど、突然大きな物音がして私達はびくりと肩を揺らした。音のした方向から察するに上だろう。
「おや、何かねえ騒々しい」
「……まさか」
シスターは不思議そうな様子で首を傾げていたけれど、私には既に思い当たる節があった。
神聖な教会に似つかわしくないそれは、前にも聞いたことがあったからだ。
「ちょっと!」
階上に戻るとまず耳に入ってくるのは、男達の下品な笑い声だった。
やっぱり、と内心思いながら私は大きな声を上げる。
すると私の声に気付いた男の一人が「おや」と一旦笑い声を収める。
「これはこれはシルフィ嬢。本日も麗しいお姿ですな」
包帯を巻いている女に麗しいも何もあるものか。そう思うけれど口には出さない。それが皮肉かつ嫌味であることなんて今更取り立てるのも馬鹿らしいからだ。
「何事かと思えば、全く……オベールさん、神の御前で堂々と酒を飲むのは止めておくれ。騒ぎ立てるのもね」
微かに鼻を掠めるアルコールの匂いはどうやら男達が持ち込んでいた酒が原因らしい。恐らくワインか何かだろう。
先に男達の方に向かっていったシスターの後に続いて私も荷物を近くに置くと傍に近寄った。それだけでアルコールの匂いが殊更きつくなる。こんな真昼間から一体どれだけの酒瓶を空けたのだろう。
「すまねえなあシスター・ドロシー。今日は部下達も休みなんで景気良く一杯振舞ってるんですよ。気分が良くなりすぎてるらしい……ほらお前らも謝んなあ」
「へえ、すんませえん」
全く悪いと思っていないような声の調子で数人の男達がオベールに続く。勿論、そんな上辺だけの謝罪で私が納得する筈もなくぎゅっと眉を吊り上げた。
「……用がないなら早く帰って。そして二度と来ないで」
「はは、俺も嫌われたもんだ。だがまあ生憎と用はあるんだ」
私の牽制を意にも介さず、オベールは「シスター」と彼女に声を掛けた。
「そろそろ考えてくれましたかね、例の話」
「またそれかい……悪いけど、教会も庭も家も立ち退く気はないよ。此処が神の御前である限り、あたし達が土地を売り払うわけにはいかないのさ」
「勿論、承知しておりますとも。この町に活気があるのはシスターが献身的に皆の心を支えているからでしょう。しかし、この場所にこだわる必要はないと思うんですがねえ。代わりの住処は我々がきちんと用立てますし」
つらつらと調子の良いことを並べているけれど、それが欺瞞であることを既に私は知っていた。だからこそ、こんな男の話を肯定するわけにはいかない。
「嘘ばっかり、代わりの住処に教会や庭を作れるスペースなんてないくせに」
「心外ですなあシルフィ嬢。勿論それらについてもきちんと配慮させて頂いておりますとも」
「酒と女と金にしか興味のない貴方達は知らないでしょうけど、一日中日差しが届かない陰鬱とした場所では薬草も果物も育たないの。神様だってそんな場所、いられないに決まってる」
「てめえ、黙って聞いてりゃオベール様になんて口を!」
「きゃっ!」
私の物言いが余程気に食わなかったのか、部下の一人が私の腕を掴んでくる。
そのまま強く引っ張られてよろける私にシスターが「シルフィ!」と焦ったような声を上げた。反動で頭に付けていたウィンプルがぱさりと床に落ちてしまう。
しかしオベールが「止めろ」と制止の言葉を掛けたことで男の動きが止まった。
「盲目とはいえ立派な淑女だ、分別を弁えろ」
「……は、すんません」
「ウチの者が失礼致しました、シルフィ嬢。お怪我はありませんか?」
先程の男とは違い至って優しい手付きで私の手を取ったオベールが何かを手渡してくる。それが頭から落ちてしまったウィンプルだということに気付いて私は不本意ながらそれを受け取った。
「……大丈夫」
「それは良かった。部下が失礼を働いたことですし、今日はこれでお暇することとしましょう」
「行くぞ」とオベールが声を掛けると男達の足音が少しずつ遠ざかっていく。どうやら本当に教会から出て行ってくれるようだ。
「今日の所は引きますが……シスター・ドロシー。お話、良く考えておいて下さい」
次はこれでは済まない、と言外に脅されているような気がした。
私もシスターも何も言えず、ただ奴らがいなくなってくれたことに安堵するしかないのだった。