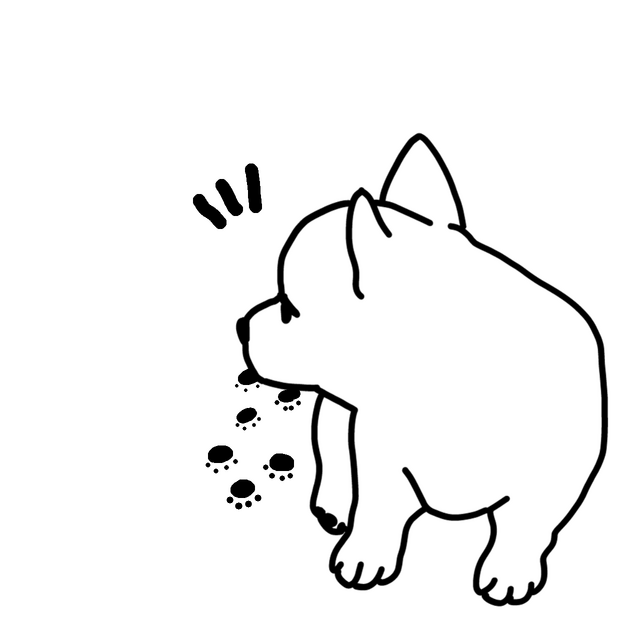第1話
文字数 3,109文字
これは僕が体験したちょっとした、いや、とんでもない奇跡の話。
困ったことになった。僕の目の前にいる小さな女の子は僕の右足にしがみついて離れようとしない。僕は頭を抱える。
「僕のこと知ってるの?」
「わたし、いきたいとこ、あるの」
幼女がたどたどしい口調で答え、僕の質問に答えることなく僕の手を引いて歩き出してしまった。
「は、るとこっ、ち。」
と幼女が僕の名前を呼んだ。
その瞬間僕の頭の中で、ある人と幼女の姿が重なった。
「まさかな。」
そう自分に言い聞かせて、幼女に大人しくついて行く。幼女は小さな手で僕の大きな手を引いていく。にこやかな表情で懸命に僕を案内する幼女の姿はやはり僕の記憶の中のあの人の姿によく似ている。けれどあの人は大人だったし、そもそももう生きていない。白血病で三年前に亡くなった。大好きな人だった。僕の一生を懸けて守りたい、本気でそう思った初めての人だった。白い肌に黒く長い艶髪が印象的な、華奢な女性だった。偶然といえばそれで済むのだろうが、それにしても似すぎているし偶然だとしたら、あの幼女はなぜ僕の名前を知っているのだろう。
「はると着いたよ。」
僕は面食らった。そこは僕の家だったから。
「どうして僕の家を…」
と僕が言い切る前に幼女は家の中へ入っていってしまった。慌てて背中を追いかける。
「ちょっと、人の家に勝手に入るなんてどういう…」
さすがに我慢できず、幼女を咎めようとした僕は言葉を失った。僕の目の前に、そこにいた。もう一度だけでいいから顔を見たい、声を聞きたい、触れたいと幾日も幾日も願った大切な人が、僕の目の前にいた。
「久しぶり、はると。」
僕は信じられなかった。
はるかはくすくす笑いながら静かに口を開いた。
「はると気づかなかったの?」
「え?」
「あの女の子、私だよ。小さいときの。」
わけが分からない。
「わけわかんないって顔してるね。」
はるかはにやにやしながら説明を始めた。
「私ね、はるとに会いに来たんだ。言い残したことを伝えにね。遺書はあったけど、もしこの遺書を渡したら私が死を認めたみたいになっちゃうって思って渡せなかった。私は自分の死を認めるのが怖かった。はるとの中から『私』がいなくなっちゃうのが怖かった。でもやっぱり伝えておけば良かったって、もう一回はるとに会いたいって後悔して、それで会いに来たの。せっかくまた会えるならびっくりさせようと思って小さい頃の姿で来ちゃった。」
間違えるはずがない。僕の目の前にいるのは僕の恋人だ。非科学的だ。きっと誰もが言うだろう。しかし僕の本能が、細胞が、そう言っている。視界が涙で歪んで上手く話せない。話したいことはたくさんあるのに言葉が詰まって出てこない。
「会いたかった…」
絞り出してようやく音になった気持ちはこれだけだった。はるかは愛おしそうな顔で僕の背中をさする。そして優しく僕の手を引いて歩き出した。僕はそっと手を伸ばして拾い上げたものをポケットへ入れた。
はるかが連れて来た場所は僕たちがよく散歩をしに来ていた公園だった。この公園に来るのは本当に久しぶりだ。もしかしたら僕はこの場所を無意識に避けていたのかもしれない。この場所ははるかとの思い出が一番詰まっているところだったから。
はるかの隣を歩きながら僕は右手をポケットの中へ動かす。指先が震えるのが分かる。いかに僕がはるかを愛していたのか、痛感する。最愛の人に拒絶されたくない、と思うほどに心臓の鼓動が早くなり、息が苦しくなる。それでも今、ここで言え。もう会えないのだから。ここでしか僕の後悔は果たせない。
「はるか、渡したいものがあるんだ。」
はるかが僕の顔を見つめる。僕は震える指でゆっくりと箱の蓋を開ける。彼女のために買った大粒のダイヤが太陽の光を浴びて目映く光り、白く美しいはるかの顔を暖かく照らす。
僕ははるかの指に指輪をはめようと手を伸ばす。指先で触れたはるかを包んでいる空気は氷のように冷たかった。
カラン。
指輪が落ちて乾いた音がした。僕の指先は彼女の指に触れることを許してはくれなかった。はるかの体は半透明になって今にも消えてしまいそうだった。
「ほんとははるかが生きてる間に言いたかった。けど、間に合わなかった。この指輪ははるかの病気が完治したら言おうと思って買っておいた指輪。渡せないまま残ったこれを見るたびに現実を突きつけられてすごく後悔した。だから言わせてほしい。はるか、愛してる。世界で一番。誰よりも。」
「はると…」
「僕は三年間ずっと、これをはるかに渡してやりたかった。」
はるかの瞳が涙でいっぱいになっていくのが見える。彼女の大きな瞳から零れた涙が僕の手の甲に落ちる。刹那、柔らかい光がふわっと僕たちを包んだ。暖かい光の中で僕は夢を見た。はるかと出会ってからの毎日が僕の中に流れ込んできた。僕はゆっくりと目を開ける。目の前には花嫁姿のはるかが立っていた。はるかの体はさっきよりも薄く透けている。
「私もはるとを愛せて幸せだった。私もはるとに言いたかったことがあるの。」
「うん。」
「私と出会ってくれて、私を好きになってくれて、私を選んでくれて、私を大切にしてくれて、ずっと一緒にいてくれてありがとう。私はあなたに愛されてすごくすごく幸せだった。はるとはいつだって私にたくさんの愛をくれた。本当だったらもっと一緒にいたかった。私もはるとにたくさんの愛をあげたかった。ずっと一緒にいることができなくてごめんね。」
そう言ってはるかは足元に落ちたままの指輪を拾い上げた。
「これもありがとう。」
はるかは自分の手のひらの上で光っている婚約指輪を見ながらそう言った。
「生きてる間に渡せなくてごめん。」
「ううん。渡そうとしてくれてたって分かっただけで幸せだよ。」
はると、と僕の名前を呼ぶ声が聞こえる。だんだんと目の周りが熱くなっていくのが分かる。視界が滲む。
「相変わらず泣き虫だね。」
はるかはいつも通り溌剌として、それでいて繊細だった。全てを理解して、それでも僕のために明るく振る舞っているのが分かる。
「はると聞いて、私ねほんとにほんとに幸せだったよ。私はこの先一緒にいられないけど、はるとも幸せになってね。」
とめどなく溢れる涙をこらえ、僕は顔を上げた。最後くらい僕の笑顔を見て逝ってほしいから。
「約束する。きっと幸せになるよ。だから空から見守っててね。」
僕は光に溶け込んでいくはるかを抱きしめた。触れることはできなかったけれど、初めて会ったときのはるかのあの笑顔のようなあたたかさが僕を包んだ。暖かな幸せな光の中で僕は指輪が地面に落ちていくのを見ていた。
「愛してるよ、はるか」
春。暖かな光が僕たちを包み込んでいる。僕は自分の背中に宝物を抱えてはるかが待つ場所へ歩いていく。
「ぱぱー、ここどこ?」
はるかのお墓に着くなり娘が背中で不思議そうに辺りをキョロキョロ見渡す。
「パパの大切な人のお墓だよ。」
「おともだち?」
「ううん。とっても大好きな人だよ。」
「でもままもひかりもしんでないよ、ぱぱ。」
「ママのことじゃないよ。ひかりが生まれてくる前にパパのことを好きだって言ってくれた人。」
「ぱぱもこのひとのことすき?」
「もちろん。だから今日はここに来たんだよ。約束を果たしにね。」
「やくそく?」
「『私の分まで幸せになってね』っていう約束。」
「そのひとはしあわせじゃなかったの?」
「とっても幸せそうだったよ。」
そう言いながら僕はあの日のはるかの幸せそうな笑顔を思い出していた。
ーはるか。僕は今幸せだよ。君もそっちで幸せに暮らしていることを願うよ。
春風がさらさらと吹いて、お墓の前に供えている指輪がきらりと光った気がした。
困ったことになった。僕の目の前にいる小さな女の子は僕の右足にしがみついて離れようとしない。僕は頭を抱える。
「僕のこと知ってるの?」
「わたし、いきたいとこ、あるの」
幼女がたどたどしい口調で答え、僕の質問に答えることなく僕の手を引いて歩き出してしまった。
「は、るとこっ、ち。」
と幼女が僕の名前を呼んだ。
その瞬間僕の頭の中で、ある人と幼女の姿が重なった。
「まさかな。」
そう自分に言い聞かせて、幼女に大人しくついて行く。幼女は小さな手で僕の大きな手を引いていく。にこやかな表情で懸命に僕を案内する幼女の姿はやはり僕の記憶の中のあの人の姿によく似ている。けれどあの人は大人だったし、そもそももう生きていない。白血病で三年前に亡くなった。大好きな人だった。僕の一生を懸けて守りたい、本気でそう思った初めての人だった。白い肌に黒く長い艶髪が印象的な、華奢な女性だった。偶然といえばそれで済むのだろうが、それにしても似すぎているし偶然だとしたら、あの幼女はなぜ僕の名前を知っているのだろう。
「はると着いたよ。」
僕は面食らった。そこは僕の家だったから。
「どうして僕の家を…」
と僕が言い切る前に幼女は家の中へ入っていってしまった。慌てて背中を追いかける。
「ちょっと、人の家に勝手に入るなんてどういう…」
さすがに我慢できず、幼女を咎めようとした僕は言葉を失った。僕の目の前に、そこにいた。もう一度だけでいいから顔を見たい、声を聞きたい、触れたいと幾日も幾日も願った大切な人が、僕の目の前にいた。
「久しぶり、はると。」
僕は信じられなかった。
はるかはくすくす笑いながら静かに口を開いた。
「はると気づかなかったの?」
「え?」
「あの女の子、私だよ。小さいときの。」
わけが分からない。
「わけわかんないって顔してるね。」
はるかはにやにやしながら説明を始めた。
「私ね、はるとに会いに来たんだ。言い残したことを伝えにね。遺書はあったけど、もしこの遺書を渡したら私が死を認めたみたいになっちゃうって思って渡せなかった。私は自分の死を認めるのが怖かった。はるとの中から『私』がいなくなっちゃうのが怖かった。でもやっぱり伝えておけば良かったって、もう一回はるとに会いたいって後悔して、それで会いに来たの。せっかくまた会えるならびっくりさせようと思って小さい頃の姿で来ちゃった。」
間違えるはずがない。僕の目の前にいるのは僕の恋人だ。非科学的だ。きっと誰もが言うだろう。しかし僕の本能が、細胞が、そう言っている。視界が涙で歪んで上手く話せない。話したいことはたくさんあるのに言葉が詰まって出てこない。
「会いたかった…」
絞り出してようやく音になった気持ちはこれだけだった。はるかは愛おしそうな顔で僕の背中をさする。そして優しく僕の手を引いて歩き出した。僕はそっと手を伸ばして拾い上げたものをポケットへ入れた。
はるかが連れて来た場所は僕たちがよく散歩をしに来ていた公園だった。この公園に来るのは本当に久しぶりだ。もしかしたら僕はこの場所を無意識に避けていたのかもしれない。この場所ははるかとの思い出が一番詰まっているところだったから。
はるかの隣を歩きながら僕は右手をポケットの中へ動かす。指先が震えるのが分かる。いかに僕がはるかを愛していたのか、痛感する。最愛の人に拒絶されたくない、と思うほどに心臓の鼓動が早くなり、息が苦しくなる。それでも今、ここで言え。もう会えないのだから。ここでしか僕の後悔は果たせない。
「はるか、渡したいものがあるんだ。」
はるかが僕の顔を見つめる。僕は震える指でゆっくりと箱の蓋を開ける。彼女のために買った大粒のダイヤが太陽の光を浴びて目映く光り、白く美しいはるかの顔を暖かく照らす。
僕ははるかの指に指輪をはめようと手を伸ばす。指先で触れたはるかを包んでいる空気は氷のように冷たかった。
カラン。
指輪が落ちて乾いた音がした。僕の指先は彼女の指に触れることを許してはくれなかった。はるかの体は半透明になって今にも消えてしまいそうだった。
「ほんとははるかが生きてる間に言いたかった。けど、間に合わなかった。この指輪ははるかの病気が完治したら言おうと思って買っておいた指輪。渡せないまま残ったこれを見るたびに現実を突きつけられてすごく後悔した。だから言わせてほしい。はるか、愛してる。世界で一番。誰よりも。」
「はると…」
「僕は三年間ずっと、これをはるかに渡してやりたかった。」
はるかの瞳が涙でいっぱいになっていくのが見える。彼女の大きな瞳から零れた涙が僕の手の甲に落ちる。刹那、柔らかい光がふわっと僕たちを包んだ。暖かい光の中で僕は夢を見た。はるかと出会ってからの毎日が僕の中に流れ込んできた。僕はゆっくりと目を開ける。目の前には花嫁姿のはるかが立っていた。はるかの体はさっきよりも薄く透けている。
「私もはるとを愛せて幸せだった。私もはるとに言いたかったことがあるの。」
「うん。」
「私と出会ってくれて、私を好きになってくれて、私を選んでくれて、私を大切にしてくれて、ずっと一緒にいてくれてありがとう。私はあなたに愛されてすごくすごく幸せだった。はるとはいつだって私にたくさんの愛をくれた。本当だったらもっと一緒にいたかった。私もはるとにたくさんの愛をあげたかった。ずっと一緒にいることができなくてごめんね。」
そう言ってはるかは足元に落ちたままの指輪を拾い上げた。
「これもありがとう。」
はるかは自分の手のひらの上で光っている婚約指輪を見ながらそう言った。
「生きてる間に渡せなくてごめん。」
「ううん。渡そうとしてくれてたって分かっただけで幸せだよ。」
はると、と僕の名前を呼ぶ声が聞こえる。だんだんと目の周りが熱くなっていくのが分かる。視界が滲む。
「相変わらず泣き虫だね。」
はるかはいつも通り溌剌として、それでいて繊細だった。全てを理解して、それでも僕のために明るく振る舞っているのが分かる。
「はると聞いて、私ねほんとにほんとに幸せだったよ。私はこの先一緒にいられないけど、はるとも幸せになってね。」
とめどなく溢れる涙をこらえ、僕は顔を上げた。最後くらい僕の笑顔を見て逝ってほしいから。
「約束する。きっと幸せになるよ。だから空から見守っててね。」
僕は光に溶け込んでいくはるかを抱きしめた。触れることはできなかったけれど、初めて会ったときのはるかのあの笑顔のようなあたたかさが僕を包んだ。暖かな幸せな光の中で僕は指輪が地面に落ちていくのを見ていた。
「愛してるよ、はるか」
春。暖かな光が僕たちを包み込んでいる。僕は自分の背中に宝物を抱えてはるかが待つ場所へ歩いていく。
「ぱぱー、ここどこ?」
はるかのお墓に着くなり娘が背中で不思議そうに辺りをキョロキョロ見渡す。
「パパの大切な人のお墓だよ。」
「おともだち?」
「ううん。とっても大好きな人だよ。」
「でもままもひかりもしんでないよ、ぱぱ。」
「ママのことじゃないよ。ひかりが生まれてくる前にパパのことを好きだって言ってくれた人。」
「ぱぱもこのひとのことすき?」
「もちろん。だから今日はここに来たんだよ。約束を果たしにね。」
「やくそく?」
「『私の分まで幸せになってね』っていう約束。」
「そのひとはしあわせじゃなかったの?」
「とっても幸せそうだったよ。」
そう言いながら僕はあの日のはるかの幸せそうな笑顔を思い出していた。
ーはるか。僕は今幸せだよ。君もそっちで幸せに暮らしていることを願うよ。
春風がさらさらと吹いて、お墓の前に供えている指輪がきらりと光った気がした。