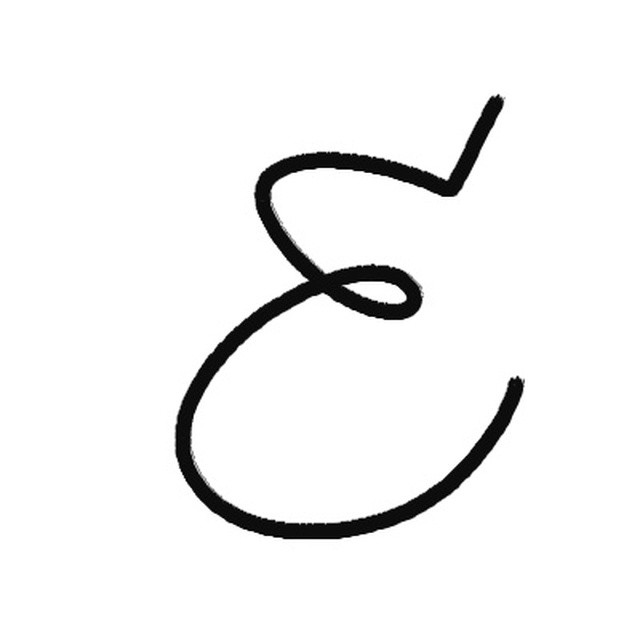第1話
文字数 2,938文字
「咲いてコスモス、凛と散れ」
永見エルマ
ある日、同棲している彼氏が帰ってきた時だった。
良い匂いがした。シトラス調の甘い匂い。
その日は同期の同僚と焼肉を食べてくると言っていたけど、鼻をかすめたのは香水の良い匂いだった。彼は帰って、スーツと鞄をテーブルの上に放ると、すぐ寝室へと向かおうとした。
「お疲れ様。今日はどうだった?同期の人たちと一緒だったんでしょう?」
探りを入れてみようと試みたが、返事は淡白だった。彼は顎を触りながら言う。
「うん。まあ、よかったよ」
今回はどこへ行ったの、と尋ねるよりも早く彼は続ける。
「ごめん。今日は疲れたから先に寝るね」
そう言うと、彼は返事も待たずにさっと寝室へと消えていった。
今更今の生活に不満を言うつもりもない。ただ少し甘い日常の延長線にあるのが今の生活で、世の中のカップルはみんなこうなるものかとも思う。しかし、今回ばかりはそうはいきそうになかった。
私はね、知ってる。君は嘘をつくとき…。
もう少し早く連絡をくれればよかったのにと思うと、キッチンの冷めた夕食を冷蔵庫に入れ、鞄とスーツを片付けた。
「結局、その日はわからず仕舞いだったの」
土曜日の昼下がり、小さい頃からの親友と私は、とあるカフェに来ていた。親友は目を瞑り、腕を組みながら話を聞いている。
「けど、先週の土曜日はね、向こうから久しぶりにデート行こうって言ってくれたの。私が前から行きたいって言っていた絵画展に誘ってくれて。その時は舞い上がっちゃってたのかな、そんなの気のせいだって思ったの」
「実際はそうじゃなかったってこと?」
「いや…それはまだわかんない」
「けど、その線が濃厚だからこうやってあたしを呼んでるわけでしょ?何があったのよ?」
私はホットコーヒーを両手で握って、冷えた手を温めながら返す。
「べつに大したことはないんだけどさ、なんていうか、その…冷めてたのよね」
「なによそれ。あんたたちって何年だっけ?」
「付き合い始めたのは二年生だから、ええと…今年で三年目」
「できたてほやほやってわけでもないし、そんなことで悩んでるなんてあんたって子は」
やれやれとため息を吐くと、親友はカップのホットコーヒーを啜る。
「違うの。私だっていつまでも熱々だなんて思ってないわ。もちろん倦怠期だってあったわよ。ただ、今までは曲がりなりにも優しさというか思いやりがあった気がするのよ。けど先週はそれがなかったの」
「ふーん、ま、言いたいことはわかるわよ。なんとなく」
私は口紅のついたカップの縁を指でなぞる。
「なんか、今までに比べて携帯を見る時間は多いし、レストランとかでは会話はほとんどないし。以前は記念で建物だったりシンボルの前で一緒に写真を撮ったりなんかもしてたんだけどな」
彼女はいつものようにもじもじした私を見かねた様子で言う。
「いい?男なんてのはねえ、星の数ほどいるの。星の数ほどいて、文字通り星屑なわけ。どれもこれも有象無象なのよ。その中で一際輝くから、一番星は綺麗に見えるものなんでしょうけど。毅然としいればいいのよ。毅然と」
「…まああんたの見る目がないってことはないだろうし、女の勘ってのは馬鹿にできないものよ」
私から見た彼女の切れ長の目は物憂さを孕んで外を眺めている。子供を挟んで手を繋ぐ家族、厚着をして散歩を楽しむ老夫婦、冬の凍てつく寒さに負けまいと身を寄せ合うカップル。窓の外では人の往来が絶え間なく続いていた。
「もしかしたら、もう潮時なのかもしれないわねえ」
彼女は残念そうに言った。
今日の相談の結果、話を聞いてもらえたことで不安がほんの少し和らいだ反面、他人の意見を取り入れてこれまたほんの少し不安が現実味を帯びてきた。今日はゆっくりお風呂に入って寝よう、そう思っていたが、事態は思うようには進まなかった。帰宅後、彼が私服であることに気がついた。午前中、私が出る頃にはパジャマだったのだが、いつの間にか着替えていたらしい。外出したのか聞いたところ、返事はそうだよの一つきりだった。深く聞かずに、いつも通り夕食を作った。問題はここからだった。
「最近、仕事の方はどうなの?」
「うーん、まあまあかな。流石に半年も経てばある程度はできるようになってきたよ。そっちの方は?結構大変って言ってたよね?」
こちらのことをちらちらと窺いながら会話を続ける彼に、少し違和感を感じる。
「相変わらず大変」
ここで会話は途切れてしまった。静かになった部屋には一定間隔で食器の金属音が鳴り響く。夕食を食べ終えると。彼の方が先に口を開いた。
「あのさ」
「ん?」
「今日、一緒にお風呂入らない?」
思いがけないその言葉で、私の言葉が詰まる。
「急にどうしたのよ?」
「いや、別になんでもないけど、たまには良いかなって」
彼は顎をさすっている。今日の彼からは、ただならぬ雰囲気を感じる。早い話、そう言われて嬉しかった。我ながら馬鹿で単純な女だと思うけれど、頭で否定するよりも先に心が許し容れてしまったのだから仕方ない。
そうして案の定、私はベッドの上で彼を受け入れることになってしまった。赤ら引く頬は常夜灯の奥に秘められ、淑やかに肌を露わにする。私より少し大きい彼の体を抱くと、なんだか知らない人みたいに感じた。
その夜は愛を呑みこんだ。
夢を見ていた。最初は大学の教室。一人でいる私に声をかけてくれた。同じ授業をとって次第に仲良くなって、一年経ってから私から交際を申し込んだ。あの時は全部が初々しくて。なんというか、楽しかったなあ。
ああ、行かないで。消えて行かないで。私を抱き締めて、抱き締めて。
そうして長い朝がきた。
この話の幕引きは恐ろしいほどに呆気なかった。ほんの些細なことから日常が壊れるっていうのは多分こういうことをいうんだろう。
うつ伏せで向こうを向いた彼の顔は見えない。私は起き上がり、携帯を手に取る。昨日の夜、私がお風呂に入っているうちに何着か連絡が来ていたようで、親友の彼女からだった。
実は昨日、自宅の近くで彼が女性に会っていたこと。彼がその女性とキスしていたこと。それを偶然見てしまったこと。着信に出ない私に送ったメッセージには、そういった旨のことが書かれていた。
数日後、電車に乗って浜辺に来た。夜の海は青藍に澄んでいて、銀色の月が空にも海にも浮かんでいる。潮騒が耳を食んで、心地が良かった。しばらく座って、なぜだか、走りたくなって、そうして気がついたら浜辺を走っていた。冬の海は冷たくて、ざばざばと小波を蹴って、外反扁平足の素足足が悲鳴をあげていた。もしかしたら、彼は知らないかもしれない。
私の疑心は確信になって、それは前の私たちとはもう違うということであって…。酸いも甘いも、愛も憂いも全て味わった。今や私たちの間には明朝体の愛がゆらゆらと浮いている。
ここから、私たち、もう一度やり直せるのかな。
三ヶ月が経った。彼は消えた。部屋の中はがらんとしている。私はベッドに横たわっていた。相対的に広くなった部屋の、覗くにはあまりにも小さな窓を見て気がついた。外にははらはら、ひらひら、ピンク色の春が咲いていた。
永見エルマ
ある日、同棲している彼氏が帰ってきた時だった。
良い匂いがした。シトラス調の甘い匂い。
その日は同期の同僚と焼肉を食べてくると言っていたけど、鼻をかすめたのは香水の良い匂いだった。彼は帰って、スーツと鞄をテーブルの上に放ると、すぐ寝室へと向かおうとした。
「お疲れ様。今日はどうだった?同期の人たちと一緒だったんでしょう?」
探りを入れてみようと試みたが、返事は淡白だった。彼は顎を触りながら言う。
「うん。まあ、よかったよ」
今回はどこへ行ったの、と尋ねるよりも早く彼は続ける。
「ごめん。今日は疲れたから先に寝るね」
そう言うと、彼は返事も待たずにさっと寝室へと消えていった。
今更今の生活に不満を言うつもりもない。ただ少し甘い日常の延長線にあるのが今の生活で、世の中のカップルはみんなこうなるものかとも思う。しかし、今回ばかりはそうはいきそうになかった。
私はね、知ってる。君は嘘をつくとき…。
もう少し早く連絡をくれればよかったのにと思うと、キッチンの冷めた夕食を冷蔵庫に入れ、鞄とスーツを片付けた。
「結局、その日はわからず仕舞いだったの」
土曜日の昼下がり、小さい頃からの親友と私は、とあるカフェに来ていた。親友は目を瞑り、腕を組みながら話を聞いている。
「けど、先週の土曜日はね、向こうから久しぶりにデート行こうって言ってくれたの。私が前から行きたいって言っていた絵画展に誘ってくれて。その時は舞い上がっちゃってたのかな、そんなの気のせいだって思ったの」
「実際はそうじゃなかったってこと?」
「いや…それはまだわかんない」
「けど、その線が濃厚だからこうやってあたしを呼んでるわけでしょ?何があったのよ?」
私はホットコーヒーを両手で握って、冷えた手を温めながら返す。
「べつに大したことはないんだけどさ、なんていうか、その…冷めてたのよね」
「なによそれ。あんたたちって何年だっけ?」
「付き合い始めたのは二年生だから、ええと…今年で三年目」
「できたてほやほやってわけでもないし、そんなことで悩んでるなんてあんたって子は」
やれやれとため息を吐くと、親友はカップのホットコーヒーを啜る。
「違うの。私だっていつまでも熱々だなんて思ってないわ。もちろん倦怠期だってあったわよ。ただ、今までは曲がりなりにも優しさというか思いやりがあった気がするのよ。けど先週はそれがなかったの」
「ふーん、ま、言いたいことはわかるわよ。なんとなく」
私は口紅のついたカップの縁を指でなぞる。
「なんか、今までに比べて携帯を見る時間は多いし、レストランとかでは会話はほとんどないし。以前は記念で建物だったりシンボルの前で一緒に写真を撮ったりなんかもしてたんだけどな」
彼女はいつものようにもじもじした私を見かねた様子で言う。
「いい?男なんてのはねえ、星の数ほどいるの。星の数ほどいて、文字通り星屑なわけ。どれもこれも有象無象なのよ。その中で一際輝くから、一番星は綺麗に見えるものなんでしょうけど。毅然としいればいいのよ。毅然と」
「…まああんたの見る目がないってことはないだろうし、女の勘ってのは馬鹿にできないものよ」
私から見た彼女の切れ長の目は物憂さを孕んで外を眺めている。子供を挟んで手を繋ぐ家族、厚着をして散歩を楽しむ老夫婦、冬の凍てつく寒さに負けまいと身を寄せ合うカップル。窓の外では人の往来が絶え間なく続いていた。
「もしかしたら、もう潮時なのかもしれないわねえ」
彼女は残念そうに言った。
今日の相談の結果、話を聞いてもらえたことで不安がほんの少し和らいだ反面、他人の意見を取り入れてこれまたほんの少し不安が現実味を帯びてきた。今日はゆっくりお風呂に入って寝よう、そう思っていたが、事態は思うようには進まなかった。帰宅後、彼が私服であることに気がついた。午前中、私が出る頃にはパジャマだったのだが、いつの間にか着替えていたらしい。外出したのか聞いたところ、返事はそうだよの一つきりだった。深く聞かずに、いつも通り夕食を作った。問題はここからだった。
「最近、仕事の方はどうなの?」
「うーん、まあまあかな。流石に半年も経てばある程度はできるようになってきたよ。そっちの方は?結構大変って言ってたよね?」
こちらのことをちらちらと窺いながら会話を続ける彼に、少し違和感を感じる。
「相変わらず大変」
ここで会話は途切れてしまった。静かになった部屋には一定間隔で食器の金属音が鳴り響く。夕食を食べ終えると。彼の方が先に口を開いた。
「あのさ」
「ん?」
「今日、一緒にお風呂入らない?」
思いがけないその言葉で、私の言葉が詰まる。
「急にどうしたのよ?」
「いや、別になんでもないけど、たまには良いかなって」
彼は顎をさすっている。今日の彼からは、ただならぬ雰囲気を感じる。早い話、そう言われて嬉しかった。我ながら馬鹿で単純な女だと思うけれど、頭で否定するよりも先に心が許し容れてしまったのだから仕方ない。
そうして案の定、私はベッドの上で彼を受け入れることになってしまった。赤ら引く頬は常夜灯の奥に秘められ、淑やかに肌を露わにする。私より少し大きい彼の体を抱くと、なんだか知らない人みたいに感じた。
その夜は愛を呑みこんだ。
夢を見ていた。最初は大学の教室。一人でいる私に声をかけてくれた。同じ授業をとって次第に仲良くなって、一年経ってから私から交際を申し込んだ。あの時は全部が初々しくて。なんというか、楽しかったなあ。
ああ、行かないで。消えて行かないで。私を抱き締めて、抱き締めて。
そうして長い朝がきた。
この話の幕引きは恐ろしいほどに呆気なかった。ほんの些細なことから日常が壊れるっていうのは多分こういうことをいうんだろう。
うつ伏せで向こうを向いた彼の顔は見えない。私は起き上がり、携帯を手に取る。昨日の夜、私がお風呂に入っているうちに何着か連絡が来ていたようで、親友の彼女からだった。
実は昨日、自宅の近くで彼が女性に会っていたこと。彼がその女性とキスしていたこと。それを偶然見てしまったこと。着信に出ない私に送ったメッセージには、そういった旨のことが書かれていた。
数日後、電車に乗って浜辺に来た。夜の海は青藍に澄んでいて、銀色の月が空にも海にも浮かんでいる。潮騒が耳を食んで、心地が良かった。しばらく座って、なぜだか、走りたくなって、そうして気がついたら浜辺を走っていた。冬の海は冷たくて、ざばざばと小波を蹴って、外反扁平足の素足足が悲鳴をあげていた。もしかしたら、彼は知らないかもしれない。
私の疑心は確信になって、それは前の私たちとはもう違うということであって…。酸いも甘いも、愛も憂いも全て味わった。今や私たちの間には明朝体の愛がゆらゆらと浮いている。
ここから、私たち、もう一度やり直せるのかな。
三ヶ月が経った。彼は消えた。部屋の中はがらんとしている。私はベッドに横たわっていた。相対的に広くなった部屋の、覗くにはあまりにも小さな窓を見て気がついた。外にははらはら、ひらひら、ピンク色の春が咲いていた。