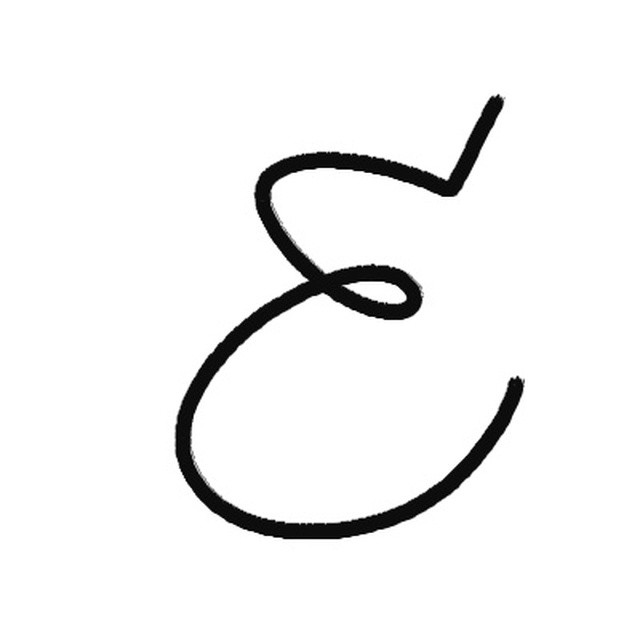或る男
文字数 4,901文字
或る男
永見エルマ
男は夢見心地だった。ゆっくりと自身の目を開くが、入ってくるのはほの暗い、ぼやけた灰色と上方から射す白色のみ。
「うう。」
あたりを観察するが見えるのは、自身の前方二、三メートル先に見える大きな鉄製の扉と四方を囲む鉄筋コンクリートだけであった。部屋の大きさはおよそ四、五畳で、中央の自身が座っている木製の椅子の他に家具などは一切なく、部屋の中央に吊るされた豆電球が静かに男を見下ろしている。壁や床には所々黒いシミなどの汚れが目立っており、無機質な空間はどこか刑務所を思わせる。しかし、自身が着ているのは囚人服ではなく、白のシャツに紺のジーパンという、男が好んで着ていた普段着であった。
一体どこなんだ、ここは。
意識がまだはっきりしていない。わけもわからぬままとりあえず男は立ちあがろうとした。しかし、体が動かない。そこで初めて男は、自分が椅子に縛られていることに気がついた。両手首と両足首、それぞれ椅子の肘掛けと足に沿うように麻紐で固定されているのだ。その光景に男はますます困惑する。
「おい。どうなっているんだ。誰かいないのか。」
思った通りではあるが、返事はない。えも言われぬ不安が男を襲う。ひんやりとした空気をまとう部屋のなかで、男の額には汗が滲み始めていた。
「おい。誰かいないのか。」
もう一度叫ぶが、やはり返事はない。男はいわゆる不安症の類いを抱えていた。次第に呼吸が速く、浅くなっていく。手足が小刻みに震え、落ち着こうという気持ちとは裏腹に、目は異常なまでにぎょろぎょろと周囲を見渡し、少しでも多くの情報を得ようとする。
右手を胸に当てたい。
動悸が止まらない時に行う、男の中でのおまじないのようなものだ。しかし、腕は届かない。不意にギギギギと音を立てて、目の前の扉が開いた。男の水晶体はその音に反応し、そちらを向いて必死に情報を取ろうとしている。扉から現れたのは、全身黒いスーツを身に纏った大男であった。目元はサングラスで隠れており、右手には警棒のような黒い棒を持っている。その様相はボディーガードを思わせた。扉から出てきた大男はコツコツと革靴の音を立てて男に近づき、男の前で立ち止まった。動悸を起こしている男は、乱れた息遣いのままなんとか言葉を吐き出す。
「あんた、誰だ。ここはどこなんだ。」
大男は何も答えない。ただ椅子の前で立ち止まったまま、男を見下ろしている。その表情からは何も読み取ることができない。
すると、突然大男は右手の黒い棒で、男の顔面に重い一撃を喰らわせた。男は受けたエネルギーのなすがままに右を向く。何が起こったのか理解が追いつかず、あまりの唐突さに声も出なかった。男の右頬に鈍い痛みが残っているうちに、大男は間髪入れず再度棒で男を殴る。
「うう。」
二度目は自分が殴られていることを理解できた。痛みもしっかりと知覚している。しかし、何をされているかはわかっても、なぜされているのかがわからない。
「お前はなんなんだ。どうして俺を殴る。」
大男は何も答えない。
「おい。なんとか答えてくれ。」
今度は脳天めがけて振り下ろされる。ゴンと低音が鳴り響き、男の体を上から下へと鈍痛が走る。衝撃の波が頭皮、頭蓋を通過し、脳味噌を振動させる。無論、今までと同様に殴る力には容赦がない。
どうしてこいつは俺を殴る。俺が何かしたからだろうか。それとも、今まで何もしなかったからだろうか。
ふらつく頭で考えるが、当然答えはでなかった。
「やめてくれ。」
震える脳味噌を働かせて、なんとか吐き出したが、その台詞を言い終わる前には、またしても殴られていた。また右頬だった。右頬はうっすらと葡萄色に青く腫れ始め、口内には鉄分を含んだ血が滲んできている。その味に不快感を覚えた。
もしやこの大男は、私が喋るから殴っているのではないだろうか。
ふとそのような考えが頭に浮かび、男は何も言わず黙って大男を見上げる。その沈黙に応えるように、大男も動かない。部屋には静寂が満ちて、ただ男の小刻みの呼吸音が聞こえるだけ。ゆったりと時間が流れてゆく。
殴ってこないのか。本当に俺が話すと殴るようにしていたというのか。この男が殴ってくるまでは、この仮定が正しいことが証明されている。しかし、これが正しいならば、ますます謎は深まる。一体全体どうして、俺が話しかけると殴るというのだ。全ての人間に平等に与えられた権利である、自分の意見を発するという行為が、どうして人を殴るトリガーとして罷り通るのだろうか。いや、そもそも、人間を殴ること自体が残虐極まりない、法で罰せられるべき行為だというのに、況や椅子に縛られて無抵抗の人間を殴っていい理由があるわけがない。いやあってはならない。
男の脳味噌は衝撃から回復してはいないが、それとは関係なく芋づる式に思考を続けている。まるで知性が体のことを知ったことではないと言っているふうだ。しかし、この思考は激しい震えと共に止められる。
再び大男から殴られていた。否応もなく、問答無用で、お構い無しに。
話しても無効。黙しても無効。仮定は否定された。
黙々と痛みに耐えながら、男は自身が叱られているような感覚を覚えていた。男はいたって普通のどこにでもいるような人間だった。何事も成さず、何事も犯さない、代わりの利く代替品で、上位互換が出回っている世の中で自分は不必要だということを熟知した人間であった。そんな人間が今、理不尽に暴力を受けている。これは、男の怠慢を叱責し、男の体からそれを絞り出そうする儀式なのではないかとさえ感じていた。
「もう、やめてくれ。」
それからもしばらくの間、殴打は続いた。大男のスイングは、右頬を狙う傾向にあったが、乱雑で意志の感じられるようなものではない。ただ男に暴力を与えるためだけに振られているといった印象であった。男の顔面は痣だらけになり、乾いた鼻血が人中にこびりついている。気がつくと男はうなだれて何も話さなくなっていた。これは決して先の仮定の再確認などではなく、ただの無気力から来るものであった。視線の先には大男の足と革靴が映っているはずなのだが、男にはそれが認識できていない。男はただ下方にある虚空を見つめていた。意気消沈し、精魂尽き果てて、ただ一秒でも早く過ぎ去ってくれと願いながら。
不意にガチャンと重い金属音が鳴り響いた。男がゆったりと顔を上げると、そこにはもう大男の姿はなかった。かわりに、扉の向こう側で革靴のコツンコツンと鳴る音だけが響いていた。
終わったのか。なんなのか判別もつかないこの地獄が。
男は安堵した。それが一時の休息であったとしても、その全てを満喫しようとした。自身がどれだけの間、殴られていたのかはわからない。ほんの十分だったのか、それとも陽が上ってから沈むほどの時間だったのか、今の男にはそれすら見当がつかない。暴力に次ぐ暴力とこの窓一つもない閉塞的な空間によって、男の時間的感覚は完全に崩壊していた。
少しの間、男はまた考えていた。思考は濁流のごとく流れ出て、止まるところを知らない。自身の体調や置かれている状況、部屋の温度から果ては壁のシミの意味するところまで、あらゆることを対象に思考を巡らしていた。特殊な環境下で少しでも冷静を保とうと理性が働いているのであろうが、それは男の精神を悪化させるだけであった。混濁した意識の中でさえも理性は働き続け、男はついに己も気付かぬうちに眠りに落ちた。
ガチャンという大きな音で、男は目を覚ました。何者かが扉を開けたのだ。起床直後で意識は覚醒していないが、その音に肩はまるで教員に寝ているところを叱られた学童のように跳ねていた。思考が意識を先行して働き始める。
どれほどの間、眠っていたのだろう。体感ではゆうに十二時間を超える長時間の睡眠であった。しかし、こんな状況でそれほどの長い時間、眠ることを許されるなんてことがあるのだろうか。普通、といってもこの状況がすでに普通ではないが、拘束し殴り上げた人間を心ゆくまで眠らせておくというのは少し不可解な気もする。回復した俺をまた痛めつけようという魂胆であろうか。
男の前にはまたしても全身黒いスーツを身に纏い、サングラスをかけた男が立っていた。その左手には昨日同様の黒い棍棒が握られている。男の目は否が応でもその棍棒に吸い寄せられた。悪い予想が頭をよぎり、再び動悸に襲われる。
ああ。胸に手を当てたい。
服装は一見すると昨日の人間と同一人物である。だが、そうではない可能性もある。まず、右手ではなく左手に棒を握っているというのが一つの根拠だ。もう一つの根拠はというと、今目の前に立っている男の方が昨日の男より僅かに小柄のように感じるということだ。が、確信は持てない。男はたった数時間前の記憶に自信が持てなかった。
来る、今に来る、と男は目を瞑ってその時を待っていた。たった数秒がまるで悠久の時のように感じられる。再び胸が苦しくなってゆく。予想通り、左頬めがけて黒服の男は殴ってきた。電撃が左頬を伝い、まだ癒えていない右頬にまで流れる。歯が数本、グチっと音を立てて抜け落ちた。口内は前回とは比にならない量の血が流れ出し、顎をつたってだらだらと垂れ流しになっている。
ああ、また始まった。
どうして俺は殴られなくてはならないのか。俺は今までの人生において、至極真っ当に生きてきた。曲がりなりにも職に就き、月並みな家庭を持って、世間一般でいうところの凡庸な生活を送ってきたというのに。
そうだ。俺は凡庸だ。俺は何も悪くない。何も悪いことはしていない。この暴行は完全悪で、正義はこちらにあるのだ。誰がどう見たって俺に正義があることは明確じゃないか。世界中どの人間からにも賛同を得られるはずだ。
黒服の男は両手で力強く棒を握る。両腕を頭上まで高く上げると、男の側頭部右を目標に素早く振り下ろした。どんと鈍い音が部屋中に響き渡る。黒服の男が放った一撃により、男は大きく姿勢を崩した。椅子は倒れ、貼り付けられた男の体はくの字に曲がったまま、顔と膝を床に押し付けられる形となった。あまりの激痛に男は絶叫していた。床をのたうち回ることも負傷部位を抑えることも封じられている男は、歯茎を剥き出しに悶え苦しむことしかできない。目を見開くと、灰色の床に男の思考を含んだ血が流れ出ている。赤黒い血には汚らしい男の笑みが見えた。それが変えようのない明白な事実なのか、認知の歪みから生じたただの幻だったのかはわからない。
黒服の男は棒を手放し、一歩男に近づいて片膝をつく。椅子の足と背もたれを掴み、椅子を起そうと勇んだ鼻息だか溜息だかが聞こえた。体勢を直し終えた黒服の男は、ズボンをはたいて襟を正す。一息ついているが、やはり何を考えているのかはわからない。
体勢を直されてもなお、男は叫んでいた。側頭部の痛みは少しばかりだが和らぎ、叫ぶほどではない。叫びの原因は側頭部よりも激しい損傷を負った男の精神であった。男の耳には自身の発狂の音波が侵入する。頭はどくどくと脈を打ち、熱を上げている。が、それ以上の速度で頭に登った血が抜けてゆく。不思議と男の心は落ちつていった。理性が言う。不思議と痛みを感じないのは、神経の誤作動だろうか、それとも本当に痛みを感じていないのかと。
その後も、男は理性と感情の間を彷徨った。思考はドス黒く変色し、渦を巻いて男を飲み込んでゆく。沸々と怒りが込み上げ、キッと相手を睨み上げた矢先、怯えたウサギのような目になる。そんなやりとりの繰り返しであった。ある時は抵抗の意を示そうと殴り掛かろうとし、ある時は涙を流してやめてくれと懇願し、またある時には自分は殴られ罰せられるべき人間なのだと、その暴力を受け入れた。
そうして、男は死んだ。相手が誰なのかを考えながら死んだ。自分が誰なのかを考えながら死んだ。自分が今死んでいるのかを考えながら死んだ。最後の最後まで結論は出なかった。右手は胸への道半ばで息絶え、脳は変形し思考は歪曲していた。ただ、男は朦朧とした意識の中で夢見心地であった。
永見エルマ
男は夢見心地だった。ゆっくりと自身の目を開くが、入ってくるのはほの暗い、ぼやけた灰色と上方から射す白色のみ。
「うう。」
あたりを観察するが見えるのは、自身の前方二、三メートル先に見える大きな鉄製の扉と四方を囲む鉄筋コンクリートだけであった。部屋の大きさはおよそ四、五畳で、中央の自身が座っている木製の椅子の他に家具などは一切なく、部屋の中央に吊るされた豆電球が静かに男を見下ろしている。壁や床には所々黒いシミなどの汚れが目立っており、無機質な空間はどこか刑務所を思わせる。しかし、自身が着ているのは囚人服ではなく、白のシャツに紺のジーパンという、男が好んで着ていた普段着であった。
一体どこなんだ、ここは。
意識がまだはっきりしていない。わけもわからぬままとりあえず男は立ちあがろうとした。しかし、体が動かない。そこで初めて男は、自分が椅子に縛られていることに気がついた。両手首と両足首、それぞれ椅子の肘掛けと足に沿うように麻紐で固定されているのだ。その光景に男はますます困惑する。
「おい。どうなっているんだ。誰かいないのか。」
思った通りではあるが、返事はない。えも言われぬ不安が男を襲う。ひんやりとした空気をまとう部屋のなかで、男の額には汗が滲み始めていた。
「おい。誰かいないのか。」
もう一度叫ぶが、やはり返事はない。男はいわゆる不安症の類いを抱えていた。次第に呼吸が速く、浅くなっていく。手足が小刻みに震え、落ち着こうという気持ちとは裏腹に、目は異常なまでにぎょろぎょろと周囲を見渡し、少しでも多くの情報を得ようとする。
右手を胸に当てたい。
動悸が止まらない時に行う、男の中でのおまじないのようなものだ。しかし、腕は届かない。不意にギギギギと音を立てて、目の前の扉が開いた。男の水晶体はその音に反応し、そちらを向いて必死に情報を取ろうとしている。扉から現れたのは、全身黒いスーツを身に纏った大男であった。目元はサングラスで隠れており、右手には警棒のような黒い棒を持っている。その様相はボディーガードを思わせた。扉から出てきた大男はコツコツと革靴の音を立てて男に近づき、男の前で立ち止まった。動悸を起こしている男は、乱れた息遣いのままなんとか言葉を吐き出す。
「あんた、誰だ。ここはどこなんだ。」
大男は何も答えない。ただ椅子の前で立ち止まったまま、男を見下ろしている。その表情からは何も読み取ることができない。
すると、突然大男は右手の黒い棒で、男の顔面に重い一撃を喰らわせた。男は受けたエネルギーのなすがままに右を向く。何が起こったのか理解が追いつかず、あまりの唐突さに声も出なかった。男の右頬に鈍い痛みが残っているうちに、大男は間髪入れず再度棒で男を殴る。
「うう。」
二度目は自分が殴られていることを理解できた。痛みもしっかりと知覚している。しかし、何をされているかはわかっても、なぜされているのかがわからない。
「お前はなんなんだ。どうして俺を殴る。」
大男は何も答えない。
「おい。なんとか答えてくれ。」
今度は脳天めがけて振り下ろされる。ゴンと低音が鳴り響き、男の体を上から下へと鈍痛が走る。衝撃の波が頭皮、頭蓋を通過し、脳味噌を振動させる。無論、今までと同様に殴る力には容赦がない。
どうしてこいつは俺を殴る。俺が何かしたからだろうか。それとも、今まで何もしなかったからだろうか。
ふらつく頭で考えるが、当然答えはでなかった。
「やめてくれ。」
震える脳味噌を働かせて、なんとか吐き出したが、その台詞を言い終わる前には、またしても殴られていた。また右頬だった。右頬はうっすらと葡萄色に青く腫れ始め、口内には鉄分を含んだ血が滲んできている。その味に不快感を覚えた。
もしやこの大男は、私が喋るから殴っているのではないだろうか。
ふとそのような考えが頭に浮かび、男は何も言わず黙って大男を見上げる。その沈黙に応えるように、大男も動かない。部屋には静寂が満ちて、ただ男の小刻みの呼吸音が聞こえるだけ。ゆったりと時間が流れてゆく。
殴ってこないのか。本当に俺が話すと殴るようにしていたというのか。この男が殴ってくるまでは、この仮定が正しいことが証明されている。しかし、これが正しいならば、ますます謎は深まる。一体全体どうして、俺が話しかけると殴るというのだ。全ての人間に平等に与えられた権利である、自分の意見を発するという行為が、どうして人を殴るトリガーとして罷り通るのだろうか。いや、そもそも、人間を殴ること自体が残虐極まりない、法で罰せられるべき行為だというのに、況や椅子に縛られて無抵抗の人間を殴っていい理由があるわけがない。いやあってはならない。
男の脳味噌は衝撃から回復してはいないが、それとは関係なく芋づる式に思考を続けている。まるで知性が体のことを知ったことではないと言っているふうだ。しかし、この思考は激しい震えと共に止められる。
再び大男から殴られていた。否応もなく、問答無用で、お構い無しに。
話しても無効。黙しても無効。仮定は否定された。
黙々と痛みに耐えながら、男は自身が叱られているような感覚を覚えていた。男はいたって普通のどこにでもいるような人間だった。何事も成さず、何事も犯さない、代わりの利く代替品で、上位互換が出回っている世の中で自分は不必要だということを熟知した人間であった。そんな人間が今、理不尽に暴力を受けている。これは、男の怠慢を叱責し、男の体からそれを絞り出そうする儀式なのではないかとさえ感じていた。
「もう、やめてくれ。」
それからもしばらくの間、殴打は続いた。大男のスイングは、右頬を狙う傾向にあったが、乱雑で意志の感じられるようなものではない。ただ男に暴力を与えるためだけに振られているといった印象であった。男の顔面は痣だらけになり、乾いた鼻血が人中にこびりついている。気がつくと男はうなだれて何も話さなくなっていた。これは決して先の仮定の再確認などではなく、ただの無気力から来るものであった。視線の先には大男の足と革靴が映っているはずなのだが、男にはそれが認識できていない。男はただ下方にある虚空を見つめていた。意気消沈し、精魂尽き果てて、ただ一秒でも早く過ぎ去ってくれと願いながら。
不意にガチャンと重い金属音が鳴り響いた。男がゆったりと顔を上げると、そこにはもう大男の姿はなかった。かわりに、扉の向こう側で革靴のコツンコツンと鳴る音だけが響いていた。
終わったのか。なんなのか判別もつかないこの地獄が。
男は安堵した。それが一時の休息であったとしても、その全てを満喫しようとした。自身がどれだけの間、殴られていたのかはわからない。ほんの十分だったのか、それとも陽が上ってから沈むほどの時間だったのか、今の男にはそれすら見当がつかない。暴力に次ぐ暴力とこの窓一つもない閉塞的な空間によって、男の時間的感覚は完全に崩壊していた。
少しの間、男はまた考えていた。思考は濁流のごとく流れ出て、止まるところを知らない。自身の体調や置かれている状況、部屋の温度から果ては壁のシミの意味するところまで、あらゆることを対象に思考を巡らしていた。特殊な環境下で少しでも冷静を保とうと理性が働いているのであろうが、それは男の精神を悪化させるだけであった。混濁した意識の中でさえも理性は働き続け、男はついに己も気付かぬうちに眠りに落ちた。
ガチャンという大きな音で、男は目を覚ました。何者かが扉を開けたのだ。起床直後で意識は覚醒していないが、その音に肩はまるで教員に寝ているところを叱られた学童のように跳ねていた。思考が意識を先行して働き始める。
どれほどの間、眠っていたのだろう。体感ではゆうに十二時間を超える長時間の睡眠であった。しかし、こんな状況でそれほどの長い時間、眠ることを許されるなんてことがあるのだろうか。普通、といってもこの状況がすでに普通ではないが、拘束し殴り上げた人間を心ゆくまで眠らせておくというのは少し不可解な気もする。回復した俺をまた痛めつけようという魂胆であろうか。
男の前にはまたしても全身黒いスーツを身に纏い、サングラスをかけた男が立っていた。その左手には昨日同様の黒い棍棒が握られている。男の目は否が応でもその棍棒に吸い寄せられた。悪い予想が頭をよぎり、再び動悸に襲われる。
ああ。胸に手を当てたい。
服装は一見すると昨日の人間と同一人物である。だが、そうではない可能性もある。まず、右手ではなく左手に棒を握っているというのが一つの根拠だ。もう一つの根拠はというと、今目の前に立っている男の方が昨日の男より僅かに小柄のように感じるということだ。が、確信は持てない。男はたった数時間前の記憶に自信が持てなかった。
来る、今に来る、と男は目を瞑ってその時を待っていた。たった数秒がまるで悠久の時のように感じられる。再び胸が苦しくなってゆく。予想通り、左頬めがけて黒服の男は殴ってきた。電撃が左頬を伝い、まだ癒えていない右頬にまで流れる。歯が数本、グチっと音を立てて抜け落ちた。口内は前回とは比にならない量の血が流れ出し、顎をつたってだらだらと垂れ流しになっている。
ああ、また始まった。
どうして俺は殴られなくてはならないのか。俺は今までの人生において、至極真っ当に生きてきた。曲がりなりにも職に就き、月並みな家庭を持って、世間一般でいうところの凡庸な生活を送ってきたというのに。
そうだ。俺は凡庸だ。俺は何も悪くない。何も悪いことはしていない。この暴行は完全悪で、正義はこちらにあるのだ。誰がどう見たって俺に正義があることは明確じゃないか。世界中どの人間からにも賛同を得られるはずだ。
黒服の男は両手で力強く棒を握る。両腕を頭上まで高く上げると、男の側頭部右を目標に素早く振り下ろした。どんと鈍い音が部屋中に響き渡る。黒服の男が放った一撃により、男は大きく姿勢を崩した。椅子は倒れ、貼り付けられた男の体はくの字に曲がったまま、顔と膝を床に押し付けられる形となった。あまりの激痛に男は絶叫していた。床をのたうち回ることも負傷部位を抑えることも封じられている男は、歯茎を剥き出しに悶え苦しむことしかできない。目を見開くと、灰色の床に男の思考を含んだ血が流れ出ている。赤黒い血には汚らしい男の笑みが見えた。それが変えようのない明白な事実なのか、認知の歪みから生じたただの幻だったのかはわからない。
黒服の男は棒を手放し、一歩男に近づいて片膝をつく。椅子の足と背もたれを掴み、椅子を起そうと勇んだ鼻息だか溜息だかが聞こえた。体勢を直し終えた黒服の男は、ズボンをはたいて襟を正す。一息ついているが、やはり何を考えているのかはわからない。
体勢を直されてもなお、男は叫んでいた。側頭部の痛みは少しばかりだが和らぎ、叫ぶほどではない。叫びの原因は側頭部よりも激しい損傷を負った男の精神であった。男の耳には自身の発狂の音波が侵入する。頭はどくどくと脈を打ち、熱を上げている。が、それ以上の速度で頭に登った血が抜けてゆく。不思議と男の心は落ちつていった。理性が言う。不思議と痛みを感じないのは、神経の誤作動だろうか、それとも本当に痛みを感じていないのかと。
その後も、男は理性と感情の間を彷徨った。思考はドス黒く変色し、渦を巻いて男を飲み込んでゆく。沸々と怒りが込み上げ、キッと相手を睨み上げた矢先、怯えたウサギのような目になる。そんなやりとりの繰り返しであった。ある時は抵抗の意を示そうと殴り掛かろうとし、ある時は涙を流してやめてくれと懇願し、またある時には自分は殴られ罰せられるべき人間なのだと、その暴力を受け入れた。
そうして、男は死んだ。相手が誰なのかを考えながら死んだ。自分が誰なのかを考えながら死んだ。自分が今死んでいるのかを考えながら死んだ。最後の最後まで結論は出なかった。右手は胸への道半ばで息絶え、脳は変形し思考は歪曲していた。ただ、男は朦朧とした意識の中で夢見心地であった。