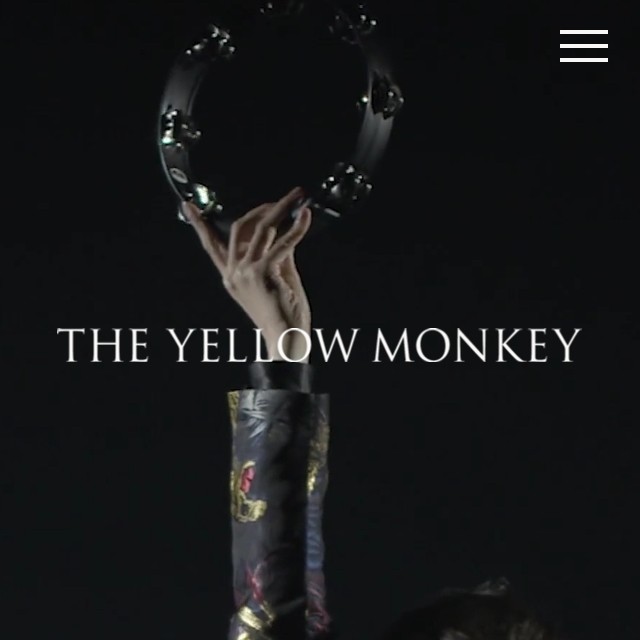第1話
文字数 4,957文字
ついていない時、というものは連鎖反応を伴うらしく、その日の俺はひしゃげた車のバンパーみたいに自分の存在自体を惨めに感じながら、年末の混み合う電車に揺られていた。
仕事で大ヘマをして、年末年始の休暇前の三日間は上司を巻き込んでのお詫び行脚で終わり、最終勤務日の忘年会はいたたまれずバックレた。年明け、どんな顔して出勤していいか分からない。
休暇初日に半同棲している彼女と大げんかをした。大晦日を明日に控えた今日、彼女が帰省する新幹線のホームに見送りに行ったが気まずい空気は変わらず、彼女は目も合わせずにじゃ、と新幹線に乗ってしまった。
電車は沢山の買い物を下げた人や大きな旅行バッグを持った人で混み合っていた。隣の外国人のキャリーケースが繰り返し右足に当たってイライラする。目的の駅に着いた頃には、俺の心の中のバンパーの凹みは修復不可能なくらいにボコボコになっていた。
改札を出ると、幼馴染のテツが手を振っていた。派手なツアージャケットを着て、左肩に大きなトートバッグをかけている。この近くのホールで行われるコンサートに来ているのだ。膨らんだトートバッグにもジャケットと同じロゴがデザインされている。俺とテツが住む場所は快速と各駅停車を乗り継いで2時間弱離れている。テツは幼稚園から高校まで一緒だった、幼馴染であり大親友だ。同じ商業科の高校を卒業し、地元企業に就職した俺と隣の市にある大学の商業科に進んだテツとで、一時期疎遠になっていた時もあるがテツが大学を卒業し地元で就職してからは、また学生時代の様な付き合いに自然と戻っていった。
「まじ、腹減った。朝から3時間物販並んでんの。見て見て、数量限定のネックレス。これ買いたくてさぁ、カオルがブーたれてんのスルーして来たわ」
笑顔でネックレスの入った箱を見せつけながら、飯食お、飯、とうるさい。カオルは俺たちの一つ下の後輩でテツの奥さんだ。高校時代から付き合い、別れてよりを戻してを繰り返し、おととしデキ婚をした。1歳になる深月ちゃんは、笑顔がテツによく似た女の子だ。俺の行きつけの定食屋に行きそれぞれ定食を注文した。
「カオルちゃん、よく許しててくれたね。30日のコンサートなんか」
「いや、強行突破よ。高校時代からこのバンドの大ファンなのあいつも知ってんだし、結婚してからは年に一度しかライブに行かずに我慢してんだから、むしろ気持ちよく送り出して欲しいよ。」
「そんな事言って出てきたの?」
「まさか。言えるわけねぇじゃん。ミーのオムツ変えてる横を、ごめんなさい!って絶叫しながら走り抜けてきたわ。行きの電車でごめんなさいのスタンプ押しまくりよ」
「お前、今日家入れんの?」
「分かんね」
定食が運ばれて来て会話が一時中断する。テツの前にはとんかつ定食。俺の前には茄子と豚肉の味噌炒めが置かれた。お腹が空いたと言っていただけあって、テツは凄い勢いでとんかつを平らげていく。おばちゃんにご飯お代わりできるよ、と声をかけられて、あざます!大盛いいっすか?と嬉しそうに茶碗を差し出して笑われている。おかわりの茶碗を受け取って、キャベツを箸で集めながら
「で、今年も帰んないの?」
と、テツが何気ないフリをして聞いてくる。
「ん。そのつもり」
俺も何でもない風に答える。テツがキャベツをわしわし噛みながら俺の顔を見てくる。なんだよ、と言いごはんをかきこむ。
「よくある話だけどさ、子供ができたら親の気持ちが分かる、ってやつで。俺から見たら、お前が意地張ってるようにしか見えねぇぞ」
「分かってるよ」
「話し合ってみろよ」
俺がもそもそと茄子を食ってごまかすのを、テツはため息をついてダメ出ししてくる。
「親友だから言うんだぞ。おばさん、いいお母さんだぜ」
いつもならおかわりする定食の味が、今日はなんだかしょっぱく胃に重い。なんとか完食して箸を置いた。
その後カフェに移りテツのコンサート開演前まで、たわいも無い話で盛り上がった。別れ際、テツはじゃ、と手を挙げてふと真顔になり
「おばさん、今も同じとこで働いてるよ。俺、時々行くんだ。講習会行ったり勉強してるって、すごく上手いよ、おばさんの施術」
それだけ言うと、さっさと背を向けて去って行った。親友だからこその優しさと無遠慮さに、修復不可能な俺の心のバンパーが原型をとどめないまでに叩き潰された。
高卒で就職した地元企業から、県庁所在地にある今の会社へ転職をしたのは3年前、大学に進学した同級生達が就職し2年目を迎えた頃だった。俺が幼稚園の頃に両親が離婚し、それからは母と二人暮しだった。離婚の原因を母からはっきり聞いたことはないが、周りの大人の話をもれ聞くに、父親のモラハラと経済DVだった様だ。あまりの父親の態度に双方の親族が間に入りなんとか離婚が成立したらしい。母はサバサバとした人で、俺に父親の愚痴を言ったりする事はなかったし、整体師の資格を持っていたので駅前の百貨店内にある整骨院で働いて俺を育ててくれた。シフト制の仕事の為、土日出勤も多く母が作り置きしたご飯を一人で食べることもままあったが、小学校からサッカー部入れてくれたので、週末を一人寂しく過ごすことはなくなった。ただ、周りの子達の様に人気メーカーのシューズは買えず安いメーカーのものばかりだったのが、子供心に少し恥ずかしく、自分は貧乏なんだと思っていた。仕事柄、母が週末の手伝いや応援に来られる事はまれで、事情を知っている周りから責められる事はなくても、どこか後ろめたい気持ちが拭えなかった。
高校卒業したら就職することに決めて商業高校に進学した。進路相談では、母は大学進学を勧めてくれたが、分不相応な気がして碌に相談もしないまま、学校の推薦で地元の規模は小さいが堅実な会社に就職した。地元の特産品を加工してネットで販売している会社で、パソコンの技術を買われてサイトの運営するチームに配属された。商品開発のチームと連携し、いかに商品が魅力的に見えるか、購買意欲を誘うかを考え試行錯誤する仕事は楽しかったし、同僚にも恵まれ特に不満もなく毎日を過ごしていた。そんな毎日に翳りが見え始めたのは、大学を卒業した同級生達の就職祝いで集まった時だった。俺と同じく高卒で就職した者が3名に、大卒で就職が決まった者5名で居酒屋に集い近況報告からスタートしたその会で、各々の就職先を聞くにつれ俺の気持ちはどんどん盛り下がっていった。高校時代、俺より成績の悪かったヤツらが世間に名の知れた企業に就職していたり、初任給が四年目の俺より高かったりした。高卒と大卒で違いがあるのは当たり前だと頭で分かっていたが、実際に現実として目の前にさらされると自分でも驚く程ショックだった。地元の中小企業に通い、母と暮らすアパートに帰る自分の生活が突然惨めに思えた。それから毎日をもんもんと過ごし、唐突にこの県で一番大きな市である県庁所在地で働こう、と思い立った。ここに居る限りこの気持ちから逃げられない、という思いが頭から離れず、転職サイトを利用して県庁所在地にある輸入品販売会社に内定をもらい、それまで4年働いた会社を退職した。上司にも社長にも引き止められたが、その時の俺の気持ちは固まっていてどんな言葉にも揺れる事はなかった。有休消化の間にアパートを探し、母に転職と引っ越しを告げた。母は当然驚いたし事後報告に激怒した。それは当然の事だったが、劣等感に卑屈になっていた俺は逆ギレし、怒鳴りあいの末俺は部屋に引きこもった。決して仲の悪い親子ではなかったが、単純に顔を合わせる時間が短かった事と母に理由を聞かれた時になんと言っていいか分からず言い出せなかった事が最悪な結果となった。俺は逃げる様に母の出勤中に家を出た。
それから今日に至るまで、母に連絡をしていない。母からは時々、元気にしているか。風邪はひいてないか、等とラインが来るが、既読スルーを繰り返している。テツが母のお店に顔を出してくれるのは、おそらく俺の近況を伝えるためだろう。母のラインは、だいたいいつも、テツと電話したり会った後に送られて来る。
出かける前より重い気持ちで自宅に帰り、その日はテレビを見ながら深酒をして酔いつぶれて寝てしまった。気づくとカーテンの隙間から明るい日差しが室内に差し込んでいる。酒臭い室内の空気を逃がそうと窓を開けると、肌に刺さる様な冷たい北風が吹き込み一気に目が覚めた。歯を磨き顔を洗いコーヒーを淹れてローテーブルの前に座る。部屋の隅の棚に目がいった。そこには、家を出た日に持って出た旅行バッグが置いてある。この部屋に来て棚にしまって以来3年間一度も触っていない。というか、触ることができなかった。身勝手だな、と口をついて出た。俺の独り相撲だったと、分かっていて目を逸らしていた。立ち上がって棚まで行き、バッグを手に取った。空っぽのバッグはだらんと力なく俺の手からぶら下がる。その時、右手の指先に何か硬いものが触れた。バッグの上から触ってみると内側に何かノートの様なものがあることに気づいた。確かめてみると、バッグの内側の小さいポケットに入っている様だ。バッグを開けて中からそれを取り出して中を見た瞬間、俺は立ち上がりコートを羽織って部屋を飛び出した。スマートフォンで時間を確認すると、11時を回ったところだった。俺は駅に向かって脇目もふらずに走り出した。
その駅で降りるのは、テツの結婚式以来だ。駅前の百貨店に向かい、上りのエスカレーターに乗る。母が働くのは5階にある整骨院だ。フロアの生活雑貨の棚を抜けて店の入り口が見えるところまでは行ったものの、そこから先に進む勇気が持てず、全く興味のないアロマの瓶を見るフリをしながら入り口をチラチラと伺う。いい加減、店員から不審な目で見られているのでは、と心配になる位の時間逡巡し、意を決しかけたところで呆気なく母が店から出てきた。時計を見ると14時過ぎ、お店のユニフォームの上にコートを羽織っているので休憩だろう。母は全く俺に気づかず目の前を通り過ぎエスカレーターに向かう。俺は慌てて後を追い、「かあさん!」思わず叫んでいた。母はピタリて立ち止まり、たっぷり2秒はそのままの姿勢でいて急に勢いよく振り向いた。俺を見て、びっくりした表情のまま固まっている。3年前と変わらない。服や持ち物は質素だけど身綺麗に清潔感のある母の姿がある。鼻の奥がツンとして視界がぼやけてきた。かあさん、かあさん、声にならずに心の中で繰り返しながら俺はバッグの中から見つけた物を取り出した。それは、俺名義の郵便局の通帳だった。そこには離婚してから成人するまでの養育費と、俺が働き出してから家に入れていたお金が振り込まれていた。俺が出て行く日の夜、寝ている間に入れてくれたのだろう。母は女手一つの余裕のない経済状況のなかでも、俺の為に苦労して積み立ててくれていたのだ。サッカーのシューズだって、母は古くなるたびにきちんと新しい物を買ってくれていたのに、メーカーがどこだとかしようもない事で劣等感を募らせた自分が心底情けなかった。母は俺の差し出した通帳と俺を交互に見て、吹き出す様に笑った。
「三年も気づかなかったの?バカね。ちゃんと片付けしなさい、っていつも言ってたでしょ」
「ごめんなさい」
自然と言葉が出た。出たら、涙も止まらなくなった。ごめんなさい。ごめんなさい。
泣きながら繰り返す俺の頭を、かあさんの手がわしゃわしゃと撫で回した。
「大晦日だから、お蕎麦食べに行こう。西口出たとこのお蕎麦やさん美味しいのよ。ご馳走して」
うん。と頷いてコートの袖で涙を拭うと母がポケットからハンカチを出して渡してくれた。
「いい歳して、ハンカチくらい持ち歩きなさい。ハンカチ使用料で、海老天も付けちゃうんだから」
先を歩きながら話す母の声も震えがちになっている。
「お蕎麦食べたら、先にうち帰ってなさい。今日は早番だから終わったらスーパーで待ち合わせて買い物しよっか。明日はお雑煮しなきゃね」
泣き笑いで母の話に頷きながら、俺は大晦日の駅前の商店街を、母と並んで歩いた。
仕事で大ヘマをして、年末年始の休暇前の三日間は上司を巻き込んでのお詫び行脚で終わり、最終勤務日の忘年会はいたたまれずバックレた。年明け、どんな顔して出勤していいか分からない。
休暇初日に半同棲している彼女と大げんかをした。大晦日を明日に控えた今日、彼女が帰省する新幹線のホームに見送りに行ったが気まずい空気は変わらず、彼女は目も合わせずにじゃ、と新幹線に乗ってしまった。
電車は沢山の買い物を下げた人や大きな旅行バッグを持った人で混み合っていた。隣の外国人のキャリーケースが繰り返し右足に当たってイライラする。目的の駅に着いた頃には、俺の心の中のバンパーの凹みは修復不可能なくらいにボコボコになっていた。
改札を出ると、幼馴染のテツが手を振っていた。派手なツアージャケットを着て、左肩に大きなトートバッグをかけている。この近くのホールで行われるコンサートに来ているのだ。膨らんだトートバッグにもジャケットと同じロゴがデザインされている。俺とテツが住む場所は快速と各駅停車を乗り継いで2時間弱離れている。テツは幼稚園から高校まで一緒だった、幼馴染であり大親友だ。同じ商業科の高校を卒業し、地元企業に就職した俺と隣の市にある大学の商業科に進んだテツとで、一時期疎遠になっていた時もあるがテツが大学を卒業し地元で就職してからは、また学生時代の様な付き合いに自然と戻っていった。
「まじ、腹減った。朝から3時間物販並んでんの。見て見て、数量限定のネックレス。これ買いたくてさぁ、カオルがブーたれてんのスルーして来たわ」
笑顔でネックレスの入った箱を見せつけながら、飯食お、飯、とうるさい。カオルは俺たちの一つ下の後輩でテツの奥さんだ。高校時代から付き合い、別れてよりを戻してを繰り返し、おととしデキ婚をした。1歳になる深月ちゃんは、笑顔がテツによく似た女の子だ。俺の行きつけの定食屋に行きそれぞれ定食を注文した。
「カオルちゃん、よく許しててくれたね。30日のコンサートなんか」
「いや、強行突破よ。高校時代からこのバンドの大ファンなのあいつも知ってんだし、結婚してからは年に一度しかライブに行かずに我慢してんだから、むしろ気持ちよく送り出して欲しいよ。」
「そんな事言って出てきたの?」
「まさか。言えるわけねぇじゃん。ミーのオムツ変えてる横を、ごめんなさい!って絶叫しながら走り抜けてきたわ。行きの電車でごめんなさいのスタンプ押しまくりよ」
「お前、今日家入れんの?」
「分かんね」
定食が運ばれて来て会話が一時中断する。テツの前にはとんかつ定食。俺の前には茄子と豚肉の味噌炒めが置かれた。お腹が空いたと言っていただけあって、テツは凄い勢いでとんかつを平らげていく。おばちゃんにご飯お代わりできるよ、と声をかけられて、あざます!大盛いいっすか?と嬉しそうに茶碗を差し出して笑われている。おかわりの茶碗を受け取って、キャベツを箸で集めながら
「で、今年も帰んないの?」
と、テツが何気ないフリをして聞いてくる。
「ん。そのつもり」
俺も何でもない風に答える。テツがキャベツをわしわし噛みながら俺の顔を見てくる。なんだよ、と言いごはんをかきこむ。
「よくある話だけどさ、子供ができたら親の気持ちが分かる、ってやつで。俺から見たら、お前が意地張ってるようにしか見えねぇぞ」
「分かってるよ」
「話し合ってみろよ」
俺がもそもそと茄子を食ってごまかすのを、テツはため息をついてダメ出ししてくる。
「親友だから言うんだぞ。おばさん、いいお母さんだぜ」
いつもならおかわりする定食の味が、今日はなんだかしょっぱく胃に重い。なんとか完食して箸を置いた。
その後カフェに移りテツのコンサート開演前まで、たわいも無い話で盛り上がった。別れ際、テツはじゃ、と手を挙げてふと真顔になり
「おばさん、今も同じとこで働いてるよ。俺、時々行くんだ。講習会行ったり勉強してるって、すごく上手いよ、おばさんの施術」
それだけ言うと、さっさと背を向けて去って行った。親友だからこその優しさと無遠慮さに、修復不可能な俺の心のバンパーが原型をとどめないまでに叩き潰された。
高卒で就職した地元企業から、県庁所在地にある今の会社へ転職をしたのは3年前、大学に進学した同級生達が就職し2年目を迎えた頃だった。俺が幼稚園の頃に両親が離婚し、それからは母と二人暮しだった。離婚の原因を母からはっきり聞いたことはないが、周りの大人の話をもれ聞くに、父親のモラハラと経済DVだった様だ。あまりの父親の態度に双方の親族が間に入りなんとか離婚が成立したらしい。母はサバサバとした人で、俺に父親の愚痴を言ったりする事はなかったし、整体師の資格を持っていたので駅前の百貨店内にある整骨院で働いて俺を育ててくれた。シフト制の仕事の為、土日出勤も多く母が作り置きしたご飯を一人で食べることもままあったが、小学校からサッカー部入れてくれたので、週末を一人寂しく過ごすことはなくなった。ただ、周りの子達の様に人気メーカーのシューズは買えず安いメーカーのものばかりだったのが、子供心に少し恥ずかしく、自分は貧乏なんだと思っていた。仕事柄、母が週末の手伝いや応援に来られる事はまれで、事情を知っている周りから責められる事はなくても、どこか後ろめたい気持ちが拭えなかった。
高校卒業したら就職することに決めて商業高校に進学した。進路相談では、母は大学進学を勧めてくれたが、分不相応な気がして碌に相談もしないまま、学校の推薦で地元の規模は小さいが堅実な会社に就職した。地元の特産品を加工してネットで販売している会社で、パソコンの技術を買われてサイトの運営するチームに配属された。商品開発のチームと連携し、いかに商品が魅力的に見えるか、購買意欲を誘うかを考え試行錯誤する仕事は楽しかったし、同僚にも恵まれ特に不満もなく毎日を過ごしていた。そんな毎日に翳りが見え始めたのは、大学を卒業した同級生達の就職祝いで集まった時だった。俺と同じく高卒で就職した者が3名に、大卒で就職が決まった者5名で居酒屋に集い近況報告からスタートしたその会で、各々の就職先を聞くにつれ俺の気持ちはどんどん盛り下がっていった。高校時代、俺より成績の悪かったヤツらが世間に名の知れた企業に就職していたり、初任給が四年目の俺より高かったりした。高卒と大卒で違いがあるのは当たり前だと頭で分かっていたが、実際に現実として目の前にさらされると自分でも驚く程ショックだった。地元の中小企業に通い、母と暮らすアパートに帰る自分の生活が突然惨めに思えた。それから毎日をもんもんと過ごし、唐突にこの県で一番大きな市である県庁所在地で働こう、と思い立った。ここに居る限りこの気持ちから逃げられない、という思いが頭から離れず、転職サイトを利用して県庁所在地にある輸入品販売会社に内定をもらい、それまで4年働いた会社を退職した。上司にも社長にも引き止められたが、その時の俺の気持ちは固まっていてどんな言葉にも揺れる事はなかった。有休消化の間にアパートを探し、母に転職と引っ越しを告げた。母は当然驚いたし事後報告に激怒した。それは当然の事だったが、劣等感に卑屈になっていた俺は逆ギレし、怒鳴りあいの末俺は部屋に引きこもった。決して仲の悪い親子ではなかったが、単純に顔を合わせる時間が短かった事と母に理由を聞かれた時になんと言っていいか分からず言い出せなかった事が最悪な結果となった。俺は逃げる様に母の出勤中に家を出た。
それから今日に至るまで、母に連絡をしていない。母からは時々、元気にしているか。風邪はひいてないか、等とラインが来るが、既読スルーを繰り返している。テツが母のお店に顔を出してくれるのは、おそらく俺の近況を伝えるためだろう。母のラインは、だいたいいつも、テツと電話したり会った後に送られて来る。
出かける前より重い気持ちで自宅に帰り、その日はテレビを見ながら深酒をして酔いつぶれて寝てしまった。気づくとカーテンの隙間から明るい日差しが室内に差し込んでいる。酒臭い室内の空気を逃がそうと窓を開けると、肌に刺さる様な冷たい北風が吹き込み一気に目が覚めた。歯を磨き顔を洗いコーヒーを淹れてローテーブルの前に座る。部屋の隅の棚に目がいった。そこには、家を出た日に持って出た旅行バッグが置いてある。この部屋に来て棚にしまって以来3年間一度も触っていない。というか、触ることができなかった。身勝手だな、と口をついて出た。俺の独り相撲だったと、分かっていて目を逸らしていた。立ち上がって棚まで行き、バッグを手に取った。空っぽのバッグはだらんと力なく俺の手からぶら下がる。その時、右手の指先に何か硬いものが触れた。バッグの上から触ってみると内側に何かノートの様なものがあることに気づいた。確かめてみると、バッグの内側の小さいポケットに入っている様だ。バッグを開けて中からそれを取り出して中を見た瞬間、俺は立ち上がりコートを羽織って部屋を飛び出した。スマートフォンで時間を確認すると、11時を回ったところだった。俺は駅に向かって脇目もふらずに走り出した。
その駅で降りるのは、テツの結婚式以来だ。駅前の百貨店に向かい、上りのエスカレーターに乗る。母が働くのは5階にある整骨院だ。フロアの生活雑貨の棚を抜けて店の入り口が見えるところまでは行ったものの、そこから先に進む勇気が持てず、全く興味のないアロマの瓶を見るフリをしながら入り口をチラチラと伺う。いい加減、店員から不審な目で見られているのでは、と心配になる位の時間逡巡し、意を決しかけたところで呆気なく母が店から出てきた。時計を見ると14時過ぎ、お店のユニフォームの上にコートを羽織っているので休憩だろう。母は全く俺に気づかず目の前を通り過ぎエスカレーターに向かう。俺は慌てて後を追い、「かあさん!」思わず叫んでいた。母はピタリて立ち止まり、たっぷり2秒はそのままの姿勢でいて急に勢いよく振り向いた。俺を見て、びっくりした表情のまま固まっている。3年前と変わらない。服や持ち物は質素だけど身綺麗に清潔感のある母の姿がある。鼻の奥がツンとして視界がぼやけてきた。かあさん、かあさん、声にならずに心の中で繰り返しながら俺はバッグの中から見つけた物を取り出した。それは、俺名義の郵便局の通帳だった。そこには離婚してから成人するまでの養育費と、俺が働き出してから家に入れていたお金が振り込まれていた。俺が出て行く日の夜、寝ている間に入れてくれたのだろう。母は女手一つの余裕のない経済状況のなかでも、俺の為に苦労して積み立ててくれていたのだ。サッカーのシューズだって、母は古くなるたびにきちんと新しい物を買ってくれていたのに、メーカーがどこだとかしようもない事で劣等感を募らせた自分が心底情けなかった。母は俺の差し出した通帳と俺を交互に見て、吹き出す様に笑った。
「三年も気づかなかったの?バカね。ちゃんと片付けしなさい、っていつも言ってたでしょ」
「ごめんなさい」
自然と言葉が出た。出たら、涙も止まらなくなった。ごめんなさい。ごめんなさい。
泣きながら繰り返す俺の頭を、かあさんの手がわしゃわしゃと撫で回した。
「大晦日だから、お蕎麦食べに行こう。西口出たとこのお蕎麦やさん美味しいのよ。ご馳走して」
うん。と頷いてコートの袖で涙を拭うと母がポケットからハンカチを出して渡してくれた。
「いい歳して、ハンカチくらい持ち歩きなさい。ハンカチ使用料で、海老天も付けちゃうんだから」
先を歩きながら話す母の声も震えがちになっている。
「お蕎麦食べたら、先にうち帰ってなさい。今日は早番だから終わったらスーパーで待ち合わせて買い物しよっか。明日はお雑煮しなきゃね」
泣き笑いで母の話に頷きながら、俺は大晦日の駅前の商店街を、母と並んで歩いた。