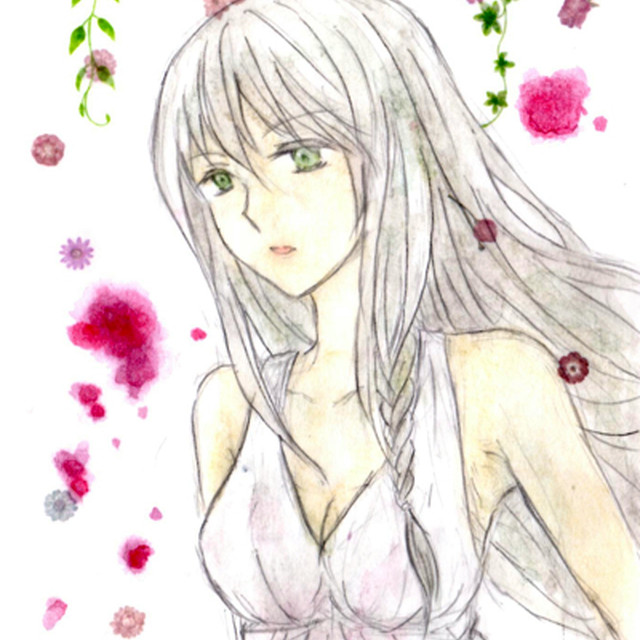墓守の兄弟
文字数 16,827文字
村外れの墓地、その傍らにある古い小屋。
そこに身を寄せ合い、住まうは墓守の兄弟。
村人たちからどれほど虐げられ、どれほど酷い仕打ちを受けようが、彼らが決して挫かれることはなかった。
互いが互いの存在を支えとし、互いが互いを庇いあう。
兄を守るためならば。
弟を守るためならば。
どんなことをしても。たとえ己が地獄の炎に焼かれようとも構わない。
そうして墓守の兄弟は罪を重ねる。
夜毎に荒らす畑。体の大きな弟の少しでも腹が満たされるようにと、兄は掻き集めた作物を持ち帰る。
兄を傷つけんとする者を前に、穏やかで優しい弟は鬼と化し、その手を血で穢す。
それは全て自分達が生きるため。
他人が、世間がどうであれ、互いに互いがいればそれでよかった。
けれどそんな時間は長く続かない。
罪は明るみに出ることとなり、二人は罪人として追われる身となる。
***
西の大国の政栄える都市。
次期国家元首候補とされた男は、ある日不正を暴かれ政界を追われた。
男は妻と共に牢に囚われ、裁判にかけられ、そして大勢の民の前で処刑された。
二人の子どもはまだ成人前であったため、罪に問われることはなかったが、平穏な暮らしも財も全てを奪われた。
彼らは僻地の村へと送られ、墓の隣の小屋を住まいとして与えられ、墓守の役目を請け負うこととなった。
墓守は下賤の民の務め。
兄弟は罪人の子と謗られ、石を投げられた。
また、食べ物は満足に与えられることなく、泥水を啜るような、過酷な日々が続いた。
それでも彼らは生きることをあきらめなかった。
いつか再び、二人で人としての暮らしを取り戻すため、今はただこの地獄を耐え抜こうと決めていた。
兄にとって弟、弟にとって兄は互いに残された唯一の家族であり、守るべきものでもあった。
「民の不満を自分達に向かわせないために俺達みたいな奴が存在する。目を逸らさせるための役割。けどいつまでもこんなまやかしみたいなことが続くはずがない。放っておいても、こんな政権そのうち潰れる」
それはこの小屋に連れてこられたその日に、兄のアウルムが言った言葉だ。
まるで予言のようなそれは、遠からず現実のものとなっていった。
どこからともなく聞こえてくる噂話。
首都で起こった反乱、国民の怒りはとうとう政府に向かったという。
「あと少し、あと少しの辛抱だからな」
アウルムが言う。
「あいつらが裏でやってたことも、いずれ公になる。その日はそう遠くないと、俺は思ってる」
「兄さん……」
「そうしたら、俺ら今度こそどこにでも行ける。堂々と陽の下を歩ける。喜べ、ジル。もっとまともな仕事について、家に住んで、そしたら美味い飯だって思う存分食えるぞ。おんぼろ小屋での生活も、安い給金も、不味い飯も今だけの我慢だ」
アウルムは壁に掛かったフード付きの外套を取って羽織るとジルヴァルドを振り向き、にっと笑う。
ジルヴァルドは慌てて兄の背中に声を投げかける。
「待ってください、給金の受け取りなら今日はおれが……!」
「いいから、それよりもおまえはそれ洗っておいてくれ」
数少ない着替えの服を放って渡し、返答を待つこともなくアウルムはさっさと小屋を出て行ってしまう。
しかし、真冬の井戸の水は凍るように冷たい。
だったら自分がその役目を引き受けるべきかと、納得してしまった己の考えの甘さを後々後悔することとなるのを、ジルヴァルドはこの時まだ知る由などなかった。
***
給金の受け取りは一日一度。夜の鐘が五つを過ぎた頃。
村長の家を訪ねるのは大抵、アウルムの役目だった。
手渡されるのは僅かな金と固くなったパンや腐った果物などの本来ならば処分されるだろう食料。
見目の良いアウルムは、たまに村長から望まれれば体を明け渡すこともあって、そんな時は心持ち多くの給金と、ちょっとした菓子が手に入ることもあった。
けれどそれだけでは足りないからと、アウルムは帰り道に畑からいくつかの作物を盗んで帰る。
ばれない程度に、色んな場所から少しずつ掻き集める。夜の暗闇の中で人目がないのをいいことに。
ジルヴァルドには言っていない。
言えばきっと悲しませることになる。それどころか自分がなんて言いだしかねない。
弟には知る必要のない事実。
悲しませたくない。手を汚させたくない。
罪を背負うのは自分だけで十分だ。
しかし冬の冷えた空気の中、実る作物は少ない。毎年のことだが悩ましい問題だ。
仕方ない。
アウルムは畑の傍らに建てられた小屋に向かう。
小屋には秋に収穫したものが貯蔵されている。それを少し分けてもらうのだ。もちろん黙って。
足音と息遣いを殺しつつ近づいたところで、突然の激痛が足を襲った。
「ああああああああ!!」
アウルムは地面に倒れ込み、悲鳴を上げる。
すぐさま民家から村人たちが飛び出してきた。
角灯の灯りで照らし出されたアウルムの足には、ギザギザの刃がいくつもついたハサミがしっかりと食い込んでいる。それは獣を罠にかける時の道具だった。
「かかったぞ!」
「この野菜ドロボウ!」
「おい、見てみろ、こいつはあの罪人の子だ! 野菜ドロボウはコイツだったんだ!」
三人の男たちは口々に言い、痛みのあまり動けずにいるアウルムを取り囲む。
無理矢理立たされ、どこかに連れて行かれた。
そこは誰かの家の倉庫らしく、農具や藁が暗がりに見えた。
「さあ、どうしてくれようか」
「罪人には罰を、制裁を」
じりじりと近づいてくる男たちにアウルムは固く目を瞑る。
これまでかと諦めかけた時だ。頭上で鈍い音がして、目の前に倒れ込んできたのは村人の一人。
何が起こったのか見上げるアウルムの目に映ったのは、驚きに立ちすくむ男達と大きな黒い影。影は、残った二人の内の一人へ向けて、その手に持った鍬を振り下ろす。
再び鈍い音と共に男の体は崩れ落ち、残る一人は悲鳴を上げて逃げ出す。
影が、鍬を投げ捨て駆け寄ってくる。
「兄さん!」
「あ……ジ、ジル?」
暗がりの中に浮かぶ弟の姿にアウルムは動揺する。
ジルヴァルドはアウルムの足の怪我に気が付くと、顔を歪ませた。
「酷い怪我を……」
「俺のことはいい! それよりも、お前今すぐここから逃げろ! すぐに人が来るぞ!」
倉庫内には強い血の臭いが充満している。
地面に転がる男たちはピクリとも動かない。
このままでは、ジルヴァルドは人殺しの罪で捕えられてしまう。そうなったら今度こそ命はない。
ところがジルヴァルドは首を横に振る。
「嫌です!」
「ジル!」
「兄さんを置いてはいけません!」
ジルヴァルドはしゃがみこんだままアウルムに背を向ける。
一瞬躊躇ったが、それよりも時間が惜しかった。頑固な弟の意に従い、腕を伸ばす。
首に腕を回して、背中に圧し掛かると、ジルヴァルドは軽々とアウルムの身体を持ち上げる。
動かすと足の傷が痛んだが、それを気にしている暇もない。
ジルヴァルドはアウルムをおぶさり走り出す。
行く宛てもないまま。
なるべく姿を隠せるように森の中へ逃げこむ。
「ごめんなさい、ごめんなさい、兄さん……何も知らないでごめなさい!」
耳元を風が過ぎる中、ジルヴァルドの声が小さく聞こえた気がした。
「ジルヴァルド……」
呼びかける声に返答はない。ジルヴァルドはただ走り続ける。
月明かりさえ届かない、道なき道を。アウルムを背負って。
足の傷口からはポタリ、ポタリと血が滴り落ち、地面に染みを作り出す。痛みは増すばかりで、身体に力が入らない。嫌な汗が額を伝う。
アウルムは一度目を閉じ、耳を澄ます。
風を切る音と、荒い息遣い、それから木々のざわめき。いずれも身近に聞こえるものばかり。
追手の気配はまだないが、捕まるのも時間の問題だろう。
「ジル、もういい。もういいから俺を、置いて行ってくれ」
アウルムの懇願するような声にも、ジルヴァルドは耳を貸そうとはしなかった。
足が痛い。
痛いのに眠い。体が怠くて眠い。手足が、瞼が重い。
強烈な眠気に耐え切れずアウルムは意識を手放した。
***
木々に囲まれた中を駆け抜ける弟の背中に、負ぶさる自分。
再び目覚めた時、変わらぬ光景と状況にアウルムは心のどこかで安堵してしまう。
眠っていたのはほんの一瞬だったのだろうか。
あれからどれくらいの時間が過ぎて、どれくらい走ったのだろう。
雨の匂いがする。
湿ったような独特の匂い。
多分もうすぐ雨が降ってくるだろう。
匂いには昔から敏感だった。特に雨の匂いを嗅ぎとるのが得意で、その予測はほぼ確実に当たった。
ああ、今夜は土砂降りになるなと考えていると、頬を冷たいものが掠めた。もう降り出したのかと、振り仰ぐが、それ以上雨粒は落ちてこない。
不思議に思っていたら、今度は鼻を啜るような音が聞こえてきてようやく気づく。
「ジル?」
カラカラに乾いた喉でアウルムはどうにか声を出す。
「泣いてるのか?」
気だるい腕を持ち上げて、顔に触れる。
その頬はまた痩せているような気がした。
「ごめんな、ジル……」
こんな目に合わせて。
もう少しだったのにな。
もう少しで、政権は変わって、そうしたら両親の無実だって明らかになって。
アウルムは心の中で呟く。
返ってくるのは、風の音と小さな嗚咽、それから――――
開けた場所に出る。
目の前には大きな川が広がっていて、雨はまだ降っていないというのに流れは早い。それもそのはず、川下の先は唐突にその流れが途切れていた。
滝だ。
呆然と立ち尽くすジルヴァルド。
アウルムは身を捩ってジルヴァルドの背から降りる。
地面に足をついた瞬間、麻痺しかけていた痛覚が甦って、途端に立っていられず地面に座り込んでしまう。
我に返ったジルヴァルドが慌てて膝をつく。
「兄さん!」
「ジル、これまでだ」
「何を言ってるんですか、早くもう一度おれの背に」
「お前一人ならどうにか泳いで渡れる。俺のことは構わず行け!」
「嫌です!」
「ジル! 頼むから言うこと聞いてくれ!」
ジルヴァルドは頑なに首を横に振り、兄の身体を強引に抱えようとする。
抵抗しかけたアウルムは近づいてくる大勢の足音と草を分ける音にハッとする。
松明の灯りが二人を照らし出し、高らかに叫び声が響き渡る。
「いたぞ! こっちだ!」
その声に導かれ、村人たちが続々と姿を現す。
「もう逃げられんぞ、観念しろ!」
一歩、また一歩と歩を進める村人達に、ジルヴァルドは絶望した表情で途方に暮れている。アウルムの逃げろと叫ぶ必死の声も届いていないようだった。
ちらりと川を振り返る。
流れが早く、川の先は滝。下手をしたら命はない。それでも………
ごめん、ジル。
意を決して、ジルヴァルドを突き飛ばす。
諦めにすっかり力の抜けていたジルヴァルドの身体は簡単に揺らいで勢いよく川に落ちる。
「にいさ……!?」
もがいて岸に手をつこうとするが、激しい流れに呑まれてジルヴァルドの身体はどんどん遠ざかって行く。
ざわつき、駆け寄ってくる村人たちがアウルムを捕えにかかる。
そんなことも構わずに、アウルムはジルヴァルドの姿が見えなくなるまで川を見つめていた。
ぽつりと天から雫が落ちてきた。
雨は、初め小振りだったが、縄をかけられ、村に運ばれる間にどんどん強く、どんどん激しくなっていった。
助けられなくてごめん、重荷になってごめん。
どうか生きて、
俺の分まで生き延びて。
神様、どうか、弟を助けてください―――
目覚めた時、清潔なベッドの上で暖かな食事を与えられて、悪意のない言葉と優しい笑顔を向けられて。
天国かと思った。
けれど、そうではないとすぐに理解できてしまう。
だっておれは人を殺めた。
兄さんを守るためとはいえ、二人の人の命を奪ってしまった。
このことについては後悔していない。後悔はしていないが、考えると頭と胸が痛んだ。
そして何よりも、どうしてここに兄がいないんだろう、どうしてあの時、兄から離れてしまったんだろうと。
今、兄はどこでどうしているのか。
最後の最後で微かに見えた光景。
それは兄が村人たちの手に掛かる瞬間だった。
「う、あッ……」
こみ上げてくる吐き気に噎せこむ。
喉の奥と胸が気持ち悪くて、頭がガンガン鳴る。
咳と共に吐きだした酸い臭いのする液体がシーツを汚す。
「ジルさん!」
隣の部屋から僧服に身を包んだ女性が駆け込んでくる。
彼女はこの教会のシスターで、ジルヴァルドの意識が戻る前から、ずっと看病してくれていたらしい。そして今でも、満足に身体を動かすことができず寝たきりのジルヴァルドの世話をしてくれていた。
彼女の話によると、滝から落ち川に流されていたところを助けてくれたのは、この教会の神父だったそうだ。彼もまた優しげな男で、ジルヴァルドの様子を気にして医者を呼んでくれたり、必要な時には手を貸してくれたりした。
どうしておればかりがこんなに恵まれた環境にいるのだろう。
どうしてここにいるのは兄じゃないんだろう。
温かい手が背中をさすってくれる。
「気分が悪いんですか? 大丈夫、大丈夫ですからね、すぐにお医者様を呼んできますから」
「へ、き、です……すみません」
「ジルヴァルドさん……」
シスターは黙ってシーツの汚れを拭うと、後で新しいものに替えますねと言い置いて部屋を出て行く。
心苦しさに潰れそうな胸を抱え、ジルヴァルドは小さく丸くなって声を殺しながらまた泣いた。
意識が戻ってから、既に数十日が過ぎていた。
ベッドの上で、ただ無為に過ごす日々。
過去を悔いて、自分を責めて、現実を嘆いて呪って。
なぜ、どうして。気が付けば自問自答を繰り返している。
どうして自分はまだ生きているのだろう。
兄がいないなら、もう自分には生きる意味などないのに。
今でも鮮明に思い出されるのは最後に見た兄の顔。
寂しげに、悲しげに、けれど笑っていた。
川の流れに呑まれ、あっという間に引き離されてしまった。
たった一人残された家族。
命尽きるまで、守ろうと決めていたのに。最後の最後で、手を離してしまった。
兄が無抵抗に捕えられる様を見ていることしかできなかった。
あの足では、きっともう逃げられやしない。
あれから何度も夢に見る。
兄が酷い目に合わされ、苦しむ姿を。ぼろぼろになって打ち捨てられる姿を。
そしてその度に己の叫び声で目を覚ました。
そんな日々が続いて、ジルヴァルドの身体は徐々に弱っていった。
眠りは浅く、食欲は減退し、見る間に痩せこけていった。
助けてくれた神父や、心配してくれるシスターに申し訳ないという気持ちがないわけではないが、この世に兄がいないのだと思うと、全てがどうでもよくなる。
ふと動かした視界の隅には小さな卓、その上に置かれた透明の水差しとグラス。
不穏な考えが頭をよぎる。
このまま何も口にしないだけでも、緩やかに死は訪れるだろう。
けれどもう、この世に未練もない。だったら少しでも早く兄の元へ行きたい。
「ッ………」
一人では起き上がることもままならない身体で這うようにし、腕の力を使って、どうにか動く。
シーツがよれて皺になり、ジルヴァルドの身体と一緒に床に落ちた。
激痛が足と腰に走って、動けずにいると、物音を聞きつけてきたらしいシスターが驚きの悲鳴を上げた。
「ジルヴァルドさん、どうしたんですか!」
「もういいんです、もう」
「何を……とにかく、ベッドに戻りましょう」
「お願いします、どうかおれのことは放っておいてください」
床に倒れ込んだままのジルヴァルドを助け起こそうしていたシスターは、その悲愴な声音に動きを止める。
こんな風に人前で弱音を吐いたりしてみっともないと、兄がこの場にいたら叱られたに違いない。
しかしどうせ兄はもういない。
「君のお兄さんは生きていますよ」
コツッと静かに足音が響いて、目の前に僧服の裾と黒い靴の先が見えた。
見上げるとそこには神父の姿があって、彼は呆気にとられるジルヴァルドの脇にしゃがみこんでくる。
「今、なんて……」
「君のお兄さんは生きています。村では相当酷い扱いを受けていたみたいですが、今はきちんと保護されて病院で治療を受けているそうです」
「どうしてそれを……」
ジルヴァルドは彼らに自分の事情は話していなかった。
神父やシスターも無理に聞いてこようとしなかったからだ。
眼鏡をかけた優しげな面差しの神父は少し微笑んで言う。
「お兄さんのことが気になるでしょう? 私の知っていることは全部お話しましょう。だから落ち着いて、まずはベッドにお戻りなさい」
***
兄が生きている。
その言葉はジルヴァルドの胸に強く響いた。
さっきまでの荒んだ気持ちは一息に霧散し、目の前が明るくなる。
「申し訳ありませんが、勝手に色々調べさせてもらいました。君の素性はすぐにわかりましたよ。二年前、横領の罪で失脚に追い込まれたメタレイア議員の子息、そうですね?」
ベッドの横の椅子に腰かけ、彼はそう切り出した。
ジルヴァルドは黙って頷く。
神父は膝の上で両手を組み合わせると、視線を落とし、床を見つめながら話を続けた。
「意識を取り戻した時、君は名前以外何も話そうとしませんでした。それにいつも虚無を抱えているような暗い目をしていて、だからずっと気になっていて……それで君が倒れていた川をずっと上って行った先にある村を地図で見つけました。君も君のお兄さんも、随分と大変な目に合ってきたんですね」
「………」
「ああ、ごめんなさい。聞きたいのはそういうことではないですよね。私は、この間村に行って君たちの話を知ったんです。村の墓場は荒れていて、近くにいたひとに訊いてみたら、今は墓守が不在だからと言われてね。一人は三か月前に森の奥の滝から落ちて行方不明、もう一人は」
彼はそこで一旦言葉を切ると、小さく息を吐きだした。
眉が寄って、眉間の間に皺が刻まれ険しい顔つきになる。
「もう一人は、村人二人を殺害・逃亡の罪で酷い拷問を受けたと……」
ジルヴァルドは血が滲むほどに唇を噛む。
聞くまでもなくわかっていたことだが、事実として知らされるとやはり胸が痛んだ。
「ですがジルヴァルド、君が眠っている間に、政権が変わったことは前に伝えましたね」
「はい……」
「その時、メタレイア議員の無実が証明されました。メタレイア議員は横領なんかしていなかった、そしてそれをずっと信じていた人がいたんです。メタレイア議員の支持者でもあるブロンセ議員です。メタレイア議員の不正に加担した疑いで、拘束されていたらしいのですが。そのブロンセ議員が解放されて、君たちのことを探していたそうです。それで村で君の兄を見つけて、保護してくれたのだと。今は、病院で治療を受けているとそう聞いています」
その日から、ジルヴァルドの様子は大きく変わった。
食事をしっかりとるようになり、積極的に医師の治療も受けるようになった。
努力の甲斐あって、歩けるようになるまで数ヶ月はかかるだろうと言われていた足は、まだぎこちなく緩慢な動きではあったが、たった一ヶ月足らずで回復した。
全てを諦めていた目には、光が戻っていた。
ジルヴァルドがリハビリに勤しむ間、神父はブロンセ議員に手紙を書き、連絡を取っていたらしい。
しばらくして教会に現れた厳めしい顔つきの初老の男に、ジルヴァルドは何となく見覚えがあった。
応接室で父と話す横顔。
そっと扉の隙間から覗き見ただけの記憶の中にある姿よりも、今は幾分痩せ衰えて見えた。
無事でよかった。
彼が言ったのはそれだけだったが、不思議とその一言の中にすべての感情が詰まっているように思えた。
ジルヴァルドは彼に連れられ、慣れ親しんだ街へと戻ってきた。
幼い頃から育ってきた街並みは懐かしくもあったが、同時に恐ろしく物悲しい記憶をも呼び起こした。
ジルヴァルドは外套のフードを被り、顔を隠すと俯き加減に道を急いだ。やがて街角にそびえる大きな建物が見えてくると、複雑な感情はすっかり忘れ去られ、ジルヴァルドの意識はその一点へと集中する。
もうすぐ兄に会える。
もうすぐ。やっと。
兄はもう自分の無事を聞いているだろうか。
怪我はもう治っただろうか。いや、完治していないからこそ、まだ病院にいるのだろう。
それならばこれからは自分が兄の手となり足となろう。今度こそ兄の支えになりたい。
そんなことを考えていたら、前を歩いていたブロンセが急に足を止めた。
不思議そうに眼を瞬かせるジルヴァルドに、ブロンセが言う。
「これから目の当たりにする現実は、君にとって残酷なものかもしれない。けど、どうか兄さんの傍に。どうか力になってやってくれ。おまえはあいつにとって残されたたった一人の家族なんだ」
ブロンセの言葉の意味は、すぐにジルヴァルドの理解するところとなった。
木の緑がいっぱいに広がる大きな窓のついた、広い贅沢な部屋の片隅。車椅子に腰かけ、ぼんやりと窓の外を眺めてる小柄な青年。
淡い金色の柔らかそうな髪と同色の瞳の、以前にも増してやつれたその横顔。
胸の内がざわつく。
一気に溢れ出た感情がじわりと頭の先まで広がるような感覚。
「兄さん……」
ふらつきながら、部屋に足を踏み入れる。
「兄さん!」
思わず漏れ出た呟きは、今度こそ呼び声に変わる。
ところが目の前にいるはずの青年はまるでジルヴァルドの声が聞こえていないかのように、窓の外を見つめ続けている。
「兄さん、おれです。兄さん?」
ジルヴァルドは車椅子の前に回ると、痩せた腕を掴み必死になって呼びかける。
そこで青年の目はようやくジルヴァルドを捕えた。ほんの僅かな動きだったが、ひどく緩慢だった。
茫洋とした瞳がジルヴァルドの不安げな顔を映し出す。
薄く開いた唇から自分の名前が紡がれることを一瞬期待したが、彼は薄く微笑むだけであった。
ジルヴァルドは衝撃のあまり表情を失い、兄の肩越しにブロンセを見やる。
「我々が君の兄を見つけた時、彼は既にその状態だった。いや、それ以上に酷い状態だったと言ってもいい。傷と、痣だらけで……呼び掛けても揺さぶっても何の反応もない。まるで、ただ息をしているだけの、人形のような」
ジルヴァルドは再び兄に視線を戻す。
兄はにこにこと自分に笑顔を向けている。ジルヴァルドには、その笑顔の裏に何の感情もないように思えた。
「彼の眼は何も映さず、何も感じ取らず、そして実の弟である君のことすら恐らく認識していない」
「兄さん、なんで、こんな……」
無意識に漏れた呟きに、ブロンセは答えを寄越してくる。
「よほど酷い目にあったんだろう……医師が言うには、恐怖や嫌悪や絶望や、そういった様々な感情に押し潰されそうになって、自身を守るために自ら心を閉ざしたのではないかと」
それから、ブロンセは僅かに間を置いて言う。
明確な治療法は今のところない、と。
ややあって、ジルヴァルドは重い口を開いた。
「……すみません、少しだけ二人にしてもらえませんか?」
ブロンセは頷き、部屋を出て行く。
扉が閉まり、足音が遠ざかると、ジルヴァルドはもう一度兄の顔を見上げた。
兄は、初め部屋を訪れた時と同じように、窓の外を見ていた。
若葉生い茂る木々の枝。その隙間から零れる白いこもれび。時折風が吹いて、葉を揺らす。どこかから鳥の鳴き声は聞こえるが、その姿は見えない。
穏やかだが、特段変化もなく面白みのない光景だ。
けれど、兄の視線は先程からずっとその光景に注がれ続けている。
ジルヴァルドは再び兄を呼ぶ。
「兄さん」
もちろん兄は無反応だったが、構わずジルヴァルドは話し続けた。
「兄さん、おれは無事です。兄さんのおかげで、あの後親切な神父様とシスターに助けてもらって、それで……おれ、最初は兄さんはもうあいつらに殺されたんだって、死んでしまったんだって思い込んでて、それならおれは生きてても仕方ない、早く兄さんや父さん母さんのところに逝きたいって思ったりもしたけれど。でも、兄さんが生きてるってわかって嬉しかったんです」
ジルヴァルドの声はきっと、兄に届いていないだろう。
そんなことはわかっている。
わかっていながら、それでもジルヴァルドは声を発する。
「おれはただ、兄さんが生きてることが嬉しくって、でもまさか、こんなことになっているなんて思いもしませんでした」
あの後一体どんな酷い目にあったのだろう。
どれほど恐ろしい思いをしたのだろう。痛い思いをしたのだろう。辛く、苦しい時を過ごしたのだろう。
車椅子の肘掛けに乗せられた手を取り握る。
うっすら残る傷痕を見つけて、指でなぞる。傷自体すっかり塞がってはいるが、皮膚が僅かに膨らんでいた。
「あの日、あの大きな川を前にしておれは一瞬でも諦めてしまいました。その結果、兄さんから手を離してしまった。どうして最後の最後まで諦めずにいられなかったのか、どうして、兄さんの手をしっかり握っていなかったのか。悔やんだところで、何も変わらないって、どうしようもないことなんだってわかってます」
頭ではわかっているが、気持ちだけはどうしようもなかった。
ジルヴァルドの頬を、熱い涙が一筋伝い落ちていく。
一度溢れ出すと止まらなかった。
ぼろぼろと大粒の雫が零れて、兄の膝を濡らす。
泣くなんていつ以来だろう。死にたいって思ったあの時も、両親が目の前で殺された時でさえ涙なんて出なかったのに。
小さな頃は、よく泣いていた気がする。
転んで膝をすりむいた時。父の仕事で母が共に出かけることになった時。いたずらをして叱られた時。
その度に手を差し出してくれる人がいた。
――――泣くなジル。
そう言って頭を撫でてくれて。
――――俺が一緒にいるからな。
ふと、握っていたか細い手が、ジルヴァルドの手の中から逃げ出す。
その手が蝶のようにふわりとジルヴァルドの頭に添えられて、ゆっくりと髪を撫でるように動かされる。
「に、いさん……?」
驚いたジルヴァルドが、兄を振り仰ぐ。
彼は窓に向けていた視線をジルヴァルドに移し、やはり微笑を浮かべるばかりだ。
どこか虚無を抱えたような笑み。
だが。
昔と同じ手つきで、優しくて温かくて、思い出す。
幼い日のことを。
冒険と称してこっそり屋敷を抜けだしたことがある。迷ううち夜になり、見知らぬ場所で暗闇で、兄の方こそ不安だっただろうに、そんな中でもジルヴァルドを励まし、庇い続けてくれた。
兄はずっとジルヴァルドを守ってくれていた。
ずっと。
それは、成長しジルヴァルドが兄よりも大きくなってからも。全てを奪われ、貧しい生活を強いられるようにようになってからも。
そうして今も。
ジルヴァルドはぐいっと拳で頬を拭う。
頭を撫でる手を取り、両手で握りしめて、ジルヴァルドは兄をまっすぐに見た。
「兄さん、一人にしてごめんなさい。でもこれからはずっとおれが傍にいます。おれが、兄さんを守りますから」
✴︎✴︎✴︎
兄、アウルムと再会してから、早くも一年が経とうとしていた。
状況は何も変わらない。
アウルムは今も自我を失ったままで、今はジルヴァルドが身の周りの世話をしている。
顔の前にスプーンを持って行けば、アウルムは口を開く。そうしてゆっくりと咀嚼し、飲み下す。
相変わらず表情は変化に乏しく反応も少ないが、時折笑顔を見せてくれるし、窓の外を眺めるのが好きらしい。
季節は春。
病室から見える木の花の蕾も膨らみ、あと少しで開きそうだ。
「少し散歩でもしましょうか」
車椅子を押し、庭に出る。
暖かい陽気の中を蝶が舞い、花の香りが風に運ばれてくる。
庭の木々や草花は手入れされて美しい。
鳥のさえずりが聞こえる。離れた場所で地面を啄む小鳥の姿にジルヴァルドは目を細める。
「兄さん、わかりますか? ツグミです。うちの庭にも良く来てましたね」
返答などないことを知りながら、ジルヴァルドはこれまで何度も根気強く語りかけてきた。
いつか自分の声が届くのではないかと。何か心に響く言葉があるのではないかと。
そして、今回もアウルムはジルヴァルドの言葉に何の反応も示さない。
ところが兄の様子は普段とやや異なっていて、ジルヴァルドはそれに気が付いた。
「どうかしましたか?」
何かに気を取られているかのように、アウルムの目はただ一点に据えられたまま動かない。
視線の先を追ってみると、そこには花壇を手入れする庭師の姿があった。しかし日よけの帽子を被り、作業に勤しむ老爺に見覚えはない。
「あの人のことが気になるんですか?」
ちょっと待っててくださいねと言い置いて、ジルヴァルドは庭師の元へ走る。
「あの、すみません」
庭師は作業の手を止め、顔を上げると、はてと首を傾げる。
それからジルヴァルドの背後にある車椅子を見つけて、納得したように頷いた。
「ここの患者さんのご家族さんじゃな、ちょっと待っとけ」
彼は先程まで手入れしていた白い花をハサミで切って、ジルヴァルドに寄越した。
「え、あ、いいんですか?」
「少し間引いてやらんとな、ええから病室に飾ってやりな」
ひらひらと手を振ると、庭師は道具を抱えて立ち去る。
やはり知り合いではないようだ。
何が気になったのだろうと首を捻りつつ、ジルヴァルドはアウルムの元に戻る。
「お待たせしました、兄さん?」
見ればアウルムはうとうとと船を漕いでいて、ジルヴァルドは微笑むと、車椅子の後ろに回った。
「今日は暖かくて気持ちが良いですもんね。そろそろ部屋に戻りましょう」
病室に戻って、アウルムの体をベッドに移動させると、ややあって静かな寝息が聞こえてくる。
先刻分けてもらった花は花瓶に活けて、枕元の棚の上に置き、ジルヴァルドは傍らの椅子に腰かける。
穏やかな寝顔だ。
一体どんな夢を見ているのだろう。
「おやすみなさい……」
そう呟いて、椅子から立ち上がる。
今の間に洗濯を済ませてしまおう。
今日は朝から晴れで、綺麗な青空が広がっている。心地よい風と日差しに布団のシーツも良く乾くだろう。
***
甘い匂いがする。
花の匂いだ。
アウルムはこの匂いが好きだ。
ずっと前からそうだった気がする。
どうしてだったか、何の花なのか、それはわからない。覚えていない。
だけどふわりと優しくて、安心する。
「おやすみなさい……」
静かな声。
これもまたずっと前から知っている。
今、自分はとてもしあわせだ。
やさしいものばかり。
あたたかいものばかり。
とてもしあわせで、うれしい。
瞼を閉じれば、意識はすぐに眠りの中へと沈んでゆく。
ああ、またこの夢だ。
手入れの行き届いた広い庭。
大きな木の根元、アウルムは若い緑の草の上に寝そべって伸びをする。
太陽の光は伸びた枝葉で遮られて眩しさはない。さわさわと葉が風に擦れる音。頭上を蝶が舞う。
静かで穏やかで美しい花が咲き乱れていて。自分の他には誰もいない。誰に咎められることもなく、好きなだけこうしてのんびりしていられる場所だ。
まるで物語に出てくる楽園のようだと思う。
ふと、赤い小さなテントウムシがアウルムの鼻の頭に止まった。くすぐったさに身体を起こして、頭を振る。
テントウムシはまたどこかへ飛んでいき、アウルムはそこで初めて耳慣れない声に気が付いた。
それは遠く聞こえてくる、誰かの泣き声のようだった。
いつもは鳥の声と風の音、それに木のざわめきくらいしか聞こえないのに。一体、自分以外の誰がこの庭にいると言うのだろう。
ここはアウルムだけの場所なのに。
大事な大事な、秘密の場所なのに。
文句を言ってやろうと、立ち上がる。
スズラン、モクレン、クチナシ、ハナミズキ、マーガレット。
白い花々に彩られた道の真ん中を、アウルムは憤然と歩いて行く。
そうして突き当たりに見えてきたのは、ノイバラの木とその手前で座り込んで泣いている小さな子ども。
短い銀髪の少しふっくらとした男の子だ。二、三歳くらいだろうか。自分よりもずいぶん年下のように見える。
アウルムは男の子の前に立つと、腕組みをし、腹立ちを声に含めて呼びかけてみた。
「おいチビ」
男の子は吃驚したように泣くのを止め、きょとんとしてアウルムを見上げてくる。
「おまえどこから入った。ここは俺の庭だぞ」
「ぷれぜと……」
「ぷれぜと?」
「おはな、にーちゃんにあげるの……」
「ああ、兄ちゃんへのプレゼントに花をあげたいってことか?」
男の子はこくりと首を縦に振ってみせる。
アウルムはその場にしゃがみこみ、視線を合わせると更に問いかけた。
「それで、お前はなんで泣いていたんだ?」
「……」
男の子は黙って、指で指し示す。
そこにはノイバラの木があった。
アウルムの背丈よりも高く伸びたその木は、可憐な白い花をいくつも咲かせている。
「ああ、これが欲しかったのか? ちょっとくらいなら取っても、ッ!?」
言ってアウルムは細い枝に手を伸ばすが、指先に痛みを感じてすぐに引っ込める。指先には丸く小さく血が滲んでいた。
そうか、バラには棘があるんだったなと思って、今度は慎重に枝に触れる。
それでも無数の棘はアウルムの手の甲や指を傷つけたが、我慢して手首を僅かに捻って枝を一本折り取ってやる。
「怪我しないように気をつけろよ」
差し出されたノイバラの枝を受けとると、男の子はぱっと顔を輝かせ、少しだけ笑った。
さて、もう一度昼寝でもするかと来た道を戻ろうとした時だ。
くいっとズボンの裾を引く手があった。振り返ると、男の子がアウルムのズボンを掴んでいて、丸くて可愛らしい目でじっと見つめてくる。
「……おい、もっと欲しいなんて言うなよ」
男の子は、今度は首を横に振る。
「そしたら何、まさか帰り方がわからんなんてことは……」
困ったことに、そのまさかであった。
今度は頭を縦に振る姿に、アウルムは長く仰々しい溜息を吐く。
それから男の子に向かって手を差し出してやる。
「ほら。俺も一緒に兄ちゃん探してやる」
どこの誰かもしれぬ子どもの守りなんて面倒くさいが、どうしてだかこのまま放っておくことはできなかった。
男の子は花を持った方とは反対の手でアウルムの手を握ってくる。
不安の表れなのか妙に強い力だった。
庭の傍には白い壁の大きな屋敷がある。多分そこの子どもだろうと思って、アウルムは男の子の手を引きながら屋敷の入り口を探した。
壁沿いにぐるりと歩いていくと、玄関の扉はすぐに見つかった。
扉を叩いても、呼びかけても応じる者は誰もいない。仕方なくそっと押してみると、鍵はかかっておらず、扉は簡単に開いた。
中は赤い絨毯が敷かれて、真正面には左右に伸びる階段が見える。
そこへ来てようやく、男の子の顔から不安が取り除かれた。見覚えのある場所まで戻ってこられたということかもしれない。
やれやれとばかりにアウルムは手を離そうとしたが、小さな指はしっかりとアウルムの手を握って離れない。それどころか今度は男の子がアウルムの手を引いて、屋敷の中へと入ってゆく。
「こら! もう一人で帰れんだろ!? 手ぇ離せって!」
困惑してアウルムは言うが、男の子は小走り気味にエントランスを抜けて、唯一大きく開かれた扉の部屋へとまっすぐに向かう。
繋がれた手を振り払おうとするが、どういうわけか敵わない。
そして―――
華美な装飾がなされたエントランスと比べると、調度品が少なく簡素な印象の部屋。
窓から吹きこむ風に、ふわりふわりと揺れるレースのカーテン。
その手前には小さな木の椅子と大きなベッド。そしてベッドの上には、目を閉じて動かない青年の姿。
男の子はやっとアウルムから手を離して、ベッドの方へと駆けて行く。
アウルムはその光景に一瞬目を疑う。
男の子が瞬きの間に、眠る青年と同じ年頃の姿に変わったのだ。
銀の短い髪と凛々しい眉、丸い目はそのままで、けれどたくましく成長した幅のある身体。
彼は木の椅子に座り、ベッドの上を見つめる。
「兄さん……」
呟く声は切なく、そしてどこか悲しげだった。
眉根が寄って、瞳が揺れて、今にも泣きだしそうに表情を歪ませている。
青年に目覚める気配はない。
何だろう。
胸がずきずきする。
一体あれは誰なんだろう。
どうしてこんなに胸が痛いんだろう。
自分はあの銀髪の男を知っている気がする。
とても気になる。
それなのに思い出そうとすると、頭がひどく痛んだ。
やめろ。考えてはいけない。やめろ。やめろ。
やめろ。
全て忘れたままでいる方がいい。
何も思い出さず、何も理解せず、何も感じず。
そうすれば何も恐ろしくない。
悲しむこともない。
苦しいばかりの過去なんて捨ててしまえ。
そうすれば解放される。
楽になれる。
頭を抱えるアウルムの耳に、再びあの囁くような声が聞こえてきた。
「兄さん」
男はずっと大事そうに持っていたノイバラの花を枕元に静かに置く。
途端に窓から強烈な風が吹き込んできて、アウルムは思わず腕で顔を庇う。
風が治まり、次に目を開けると、先程まで部屋であったその場所はがらりと変わっていた。
一面の星空。
黒いヴェールに散りばめられたビーズ飾りのように、強く、弱く輝きを放つ星々。
足元が何だかふわふわしていて、見てみると白い靄みたいなところに足首まで沈んでいる。まるで雲の上にいるようだと、アウルムは思う。
「すげぇだろ?」
突然、背後から声を投げかけられて驚く。
「これ、今雲の上にいるんだぞ」
得意げな顔で言ったのは、金色の髪の少年だ。
少年は後ろに倒れ込むようにして、雲の上に寝そべると、アウルムにも隣に来るよう促してくる。
「見ろよ。すげえ近くに星があるんだ」
アウルムは少年の隣に足を抱えて座ると、天を振り仰ぐ。
彼の言うとおり、地上で見るよりもずっと星が大きく間近に感じられた。
「綺麗だろ?」
少年の言葉に、アウルムは無言で頷く。
「ここにはなんでもあって、なんでもできる。好きなことを好きなだけしていていいんだ」
少年は言って、目元を笑ませる。
その顔を不思議な気分で眺めながら、アウルムは口を開いた。
「訊いてもいいか?」
「ん?」
「ここは、どういう場所だ?」
少年は勢いをつけて跳ねるように起き上がると、ゆっくりと前方に歩いていく。
「うーん、そうだなあ……ここはまあ、言うなれば卵の殻の中みたいなもんかな」
「卵?」
「そう、ここにいれば安全。色んな怖いことから守ってくれて、あたたかくて安心できる。そんなとこ」
「殻の外は、どうなってる?」
「怖いことがたくさんある。辛いことも」
少年は足を止めて、くるりと身体ごと振り返った。
「けど、ここにいればそんな心配はいらない。考える必要もない」
彼は芝居じみた仕草で両手を広げてみせる。
アウルムは立ち上がり、数歩進んで少年に近づいた。
「ほんとに、ここは楽園みたいなとこだよな……苦しいことも悲しいこともなくて、好きなことばかりしていられて居心地良くて」
まっすぐに向けた視線の先には、髪と同じ色の瞳がある。その中を覗き込みながら、アウルムは言う。
「俺は初めここに来た時、すげえ疲れてた。何もしたくなくて、何も考えたくなくて、だからこの場所に逃げ込んだ。嫌なこと全部、ぜんぶ投げ出して、この中に閉じこもって、それで何もかも忘れられて。お前の言うとおり、ここは安全だ。ここにいれば、何も心配はいらない。けどな何か、」
アウルムは服の胸の辺りを掴んで、ぎゅっと拳を握る。
「何か物足りんなって思ってた」
ぽっかりと胸に穴が空いたような感覚。
それが何なのかずっとわからなかった。
「嫌なことと一緒に、何か大事なことまで忘れてしまってるような、ずっとそんな気がしてた……そして、やっとわかったんだ」
少年は短く吐息し、肩を竦める。
「さっきのあれ。あれはお前見せたものだろう?」
「さあ、なんのことやら。わからねぇな」
少年の空々しい言葉に、アウルムは苦笑する。
また少し、少年に近づいてアウルムが言う。手を伸ばせば触れる距離。
「俺、そろそろ帰らなきゃだ」
「せっかくこんな楽園みたいな場所にいるのに? わざわざ嫌な思いをしにいくって言うのか?」
少年は口元に意地の悪い笑みを刻む。
アウルムの意思も今から答える内容も何もかも、きっとわかっているんだろう。
だって彼は、他ならぬアウルム自身なのだ。
「でも、ジルが待ってる」
腕を組んでもう一度短い溜息を吐きだして、もう一人の自分は手を差し伸べてくる。
ここを出れば、これまで避け続けてきたすべてものがそこにある。
大丈夫という自信があるわけではない。不安は重く胸に圧し掛かる。
でも泣いている弟を、放ってはおけない。
何せアウルムはジルヴァルドのただ一人の兄だ。
差し出された手を取って、アウルムは目を閉じる。
脳裏をよぎるのはこれまで起こったすべての出来事。
アウルムの中で時間が一気に進んでいく。
***
甘い花の香り。
カーテン越しに差し込む、柔らかな午後の陽光。
途切れがちに聞こえる誰かの話し声。
真っ白なシーツの中に沈む重い身体。
アウルムはゆっくりと瞼を持ち上げる。
寝覚めにぼんやりする頭で、ゆっくりと目だけを動かし周囲を見回す。
部屋の扉近くに見える背中。誰かと何やら話しているらしい。
軽く頭を下げるその後ろ姿。
大きなその背中。
知っている。
そうだ、あれはたった一人の。
急激にこみ上げてきた感情が喉元でつかえる。
アウルムは震える声にその想いを全てのせ、その名を呼んだ。
「ジル……!」
そこに身を寄せ合い、住まうは墓守の兄弟。
村人たちからどれほど虐げられ、どれほど酷い仕打ちを受けようが、彼らが決して挫かれることはなかった。
互いが互いの存在を支えとし、互いが互いを庇いあう。
兄を守るためならば。
弟を守るためならば。
どんなことをしても。たとえ己が地獄の炎に焼かれようとも構わない。
そうして墓守の兄弟は罪を重ねる。
夜毎に荒らす畑。体の大きな弟の少しでも腹が満たされるようにと、兄は掻き集めた作物を持ち帰る。
兄を傷つけんとする者を前に、穏やかで優しい弟は鬼と化し、その手を血で穢す。
それは全て自分達が生きるため。
他人が、世間がどうであれ、互いに互いがいればそれでよかった。
けれどそんな時間は長く続かない。
罪は明るみに出ることとなり、二人は罪人として追われる身となる。
***
西の大国の政栄える都市。
次期国家元首候補とされた男は、ある日不正を暴かれ政界を追われた。
男は妻と共に牢に囚われ、裁判にかけられ、そして大勢の民の前で処刑された。
二人の子どもはまだ成人前であったため、罪に問われることはなかったが、平穏な暮らしも財も全てを奪われた。
彼らは僻地の村へと送られ、墓の隣の小屋を住まいとして与えられ、墓守の役目を請け負うこととなった。
墓守は下賤の民の務め。
兄弟は罪人の子と謗られ、石を投げられた。
また、食べ物は満足に与えられることなく、泥水を啜るような、過酷な日々が続いた。
それでも彼らは生きることをあきらめなかった。
いつか再び、二人で人としての暮らしを取り戻すため、今はただこの地獄を耐え抜こうと決めていた。
兄にとって弟、弟にとって兄は互いに残された唯一の家族であり、守るべきものでもあった。
「民の不満を自分達に向かわせないために俺達みたいな奴が存在する。目を逸らさせるための役割。けどいつまでもこんなまやかしみたいなことが続くはずがない。放っておいても、こんな政権そのうち潰れる」
それはこの小屋に連れてこられたその日に、兄のアウルムが言った言葉だ。
まるで予言のようなそれは、遠からず現実のものとなっていった。
どこからともなく聞こえてくる噂話。
首都で起こった反乱、国民の怒りはとうとう政府に向かったという。
「あと少し、あと少しの辛抱だからな」
アウルムが言う。
「あいつらが裏でやってたことも、いずれ公になる。その日はそう遠くないと、俺は思ってる」
「兄さん……」
「そうしたら、俺ら今度こそどこにでも行ける。堂々と陽の下を歩ける。喜べ、ジル。もっとまともな仕事について、家に住んで、そしたら美味い飯だって思う存分食えるぞ。おんぼろ小屋での生活も、安い給金も、不味い飯も今だけの我慢だ」
アウルムは壁に掛かったフード付きの外套を取って羽織るとジルヴァルドを振り向き、にっと笑う。
ジルヴァルドは慌てて兄の背中に声を投げかける。
「待ってください、給金の受け取りなら今日はおれが……!」
「いいから、それよりもおまえはそれ洗っておいてくれ」
数少ない着替えの服を放って渡し、返答を待つこともなくアウルムはさっさと小屋を出て行ってしまう。
しかし、真冬の井戸の水は凍るように冷たい。
だったら自分がその役目を引き受けるべきかと、納得してしまった己の考えの甘さを後々後悔することとなるのを、ジルヴァルドはこの時まだ知る由などなかった。
***
給金の受け取りは一日一度。夜の鐘が五つを過ぎた頃。
村長の家を訪ねるのは大抵、アウルムの役目だった。
手渡されるのは僅かな金と固くなったパンや腐った果物などの本来ならば処分されるだろう食料。
見目の良いアウルムは、たまに村長から望まれれば体を明け渡すこともあって、そんな時は心持ち多くの給金と、ちょっとした菓子が手に入ることもあった。
けれどそれだけでは足りないからと、アウルムは帰り道に畑からいくつかの作物を盗んで帰る。
ばれない程度に、色んな場所から少しずつ掻き集める。夜の暗闇の中で人目がないのをいいことに。
ジルヴァルドには言っていない。
言えばきっと悲しませることになる。それどころか自分がなんて言いだしかねない。
弟には知る必要のない事実。
悲しませたくない。手を汚させたくない。
罪を背負うのは自分だけで十分だ。
しかし冬の冷えた空気の中、実る作物は少ない。毎年のことだが悩ましい問題だ。
仕方ない。
アウルムは畑の傍らに建てられた小屋に向かう。
小屋には秋に収穫したものが貯蔵されている。それを少し分けてもらうのだ。もちろん黙って。
足音と息遣いを殺しつつ近づいたところで、突然の激痛が足を襲った。
「ああああああああ!!」
アウルムは地面に倒れ込み、悲鳴を上げる。
すぐさま民家から村人たちが飛び出してきた。
角灯の灯りで照らし出されたアウルムの足には、ギザギザの刃がいくつもついたハサミがしっかりと食い込んでいる。それは獣を罠にかける時の道具だった。
「かかったぞ!」
「この野菜ドロボウ!」
「おい、見てみろ、こいつはあの罪人の子だ! 野菜ドロボウはコイツだったんだ!」
三人の男たちは口々に言い、痛みのあまり動けずにいるアウルムを取り囲む。
無理矢理立たされ、どこかに連れて行かれた。
そこは誰かの家の倉庫らしく、農具や藁が暗がりに見えた。
「さあ、どうしてくれようか」
「罪人には罰を、制裁を」
じりじりと近づいてくる男たちにアウルムは固く目を瞑る。
これまでかと諦めかけた時だ。頭上で鈍い音がして、目の前に倒れ込んできたのは村人の一人。
何が起こったのか見上げるアウルムの目に映ったのは、驚きに立ちすくむ男達と大きな黒い影。影は、残った二人の内の一人へ向けて、その手に持った鍬を振り下ろす。
再び鈍い音と共に男の体は崩れ落ち、残る一人は悲鳴を上げて逃げ出す。
影が、鍬を投げ捨て駆け寄ってくる。
「兄さん!」
「あ……ジ、ジル?」
暗がりの中に浮かぶ弟の姿にアウルムは動揺する。
ジルヴァルドはアウルムの足の怪我に気が付くと、顔を歪ませた。
「酷い怪我を……」
「俺のことはいい! それよりも、お前今すぐここから逃げろ! すぐに人が来るぞ!」
倉庫内には強い血の臭いが充満している。
地面に転がる男たちはピクリとも動かない。
このままでは、ジルヴァルドは人殺しの罪で捕えられてしまう。そうなったら今度こそ命はない。
ところがジルヴァルドは首を横に振る。
「嫌です!」
「ジル!」
「兄さんを置いてはいけません!」
ジルヴァルドはしゃがみこんだままアウルムに背を向ける。
一瞬躊躇ったが、それよりも時間が惜しかった。頑固な弟の意に従い、腕を伸ばす。
首に腕を回して、背中に圧し掛かると、ジルヴァルドは軽々とアウルムの身体を持ち上げる。
動かすと足の傷が痛んだが、それを気にしている暇もない。
ジルヴァルドはアウルムをおぶさり走り出す。
行く宛てもないまま。
なるべく姿を隠せるように森の中へ逃げこむ。
「ごめんなさい、ごめんなさい、兄さん……何も知らないでごめなさい!」
耳元を風が過ぎる中、ジルヴァルドの声が小さく聞こえた気がした。
「ジルヴァルド……」
呼びかける声に返答はない。ジルヴァルドはただ走り続ける。
月明かりさえ届かない、道なき道を。アウルムを背負って。
足の傷口からはポタリ、ポタリと血が滴り落ち、地面に染みを作り出す。痛みは増すばかりで、身体に力が入らない。嫌な汗が額を伝う。
アウルムは一度目を閉じ、耳を澄ます。
風を切る音と、荒い息遣い、それから木々のざわめき。いずれも身近に聞こえるものばかり。
追手の気配はまだないが、捕まるのも時間の問題だろう。
「ジル、もういい。もういいから俺を、置いて行ってくれ」
アウルムの懇願するような声にも、ジルヴァルドは耳を貸そうとはしなかった。
足が痛い。
痛いのに眠い。体が怠くて眠い。手足が、瞼が重い。
強烈な眠気に耐え切れずアウルムは意識を手放した。
***
木々に囲まれた中を駆け抜ける弟の背中に、負ぶさる自分。
再び目覚めた時、変わらぬ光景と状況にアウルムは心のどこかで安堵してしまう。
眠っていたのはほんの一瞬だったのだろうか。
あれからどれくらいの時間が過ぎて、どれくらい走ったのだろう。
雨の匂いがする。
湿ったような独特の匂い。
多分もうすぐ雨が降ってくるだろう。
匂いには昔から敏感だった。特に雨の匂いを嗅ぎとるのが得意で、その予測はほぼ確実に当たった。
ああ、今夜は土砂降りになるなと考えていると、頬を冷たいものが掠めた。もう降り出したのかと、振り仰ぐが、それ以上雨粒は落ちてこない。
不思議に思っていたら、今度は鼻を啜るような音が聞こえてきてようやく気づく。
「ジル?」
カラカラに乾いた喉でアウルムはどうにか声を出す。
「泣いてるのか?」
気だるい腕を持ち上げて、顔に触れる。
その頬はまた痩せているような気がした。
「ごめんな、ジル……」
こんな目に合わせて。
もう少しだったのにな。
もう少しで、政権は変わって、そうしたら両親の無実だって明らかになって。
アウルムは心の中で呟く。
返ってくるのは、風の音と小さな嗚咽、それから――――
開けた場所に出る。
目の前には大きな川が広がっていて、雨はまだ降っていないというのに流れは早い。それもそのはず、川下の先は唐突にその流れが途切れていた。
滝だ。
呆然と立ち尽くすジルヴァルド。
アウルムは身を捩ってジルヴァルドの背から降りる。
地面に足をついた瞬間、麻痺しかけていた痛覚が甦って、途端に立っていられず地面に座り込んでしまう。
我に返ったジルヴァルドが慌てて膝をつく。
「兄さん!」
「ジル、これまでだ」
「何を言ってるんですか、早くもう一度おれの背に」
「お前一人ならどうにか泳いで渡れる。俺のことは構わず行け!」
「嫌です!」
「ジル! 頼むから言うこと聞いてくれ!」
ジルヴァルドは頑なに首を横に振り、兄の身体を強引に抱えようとする。
抵抗しかけたアウルムは近づいてくる大勢の足音と草を分ける音にハッとする。
松明の灯りが二人を照らし出し、高らかに叫び声が響き渡る。
「いたぞ! こっちだ!」
その声に導かれ、村人たちが続々と姿を現す。
「もう逃げられんぞ、観念しろ!」
一歩、また一歩と歩を進める村人達に、ジルヴァルドは絶望した表情で途方に暮れている。アウルムの逃げろと叫ぶ必死の声も届いていないようだった。
ちらりと川を振り返る。
流れが早く、川の先は滝。下手をしたら命はない。それでも………
ごめん、ジル。
意を決して、ジルヴァルドを突き飛ばす。
諦めにすっかり力の抜けていたジルヴァルドの身体は簡単に揺らいで勢いよく川に落ちる。
「にいさ……!?」
もがいて岸に手をつこうとするが、激しい流れに呑まれてジルヴァルドの身体はどんどん遠ざかって行く。
ざわつき、駆け寄ってくる村人たちがアウルムを捕えにかかる。
そんなことも構わずに、アウルムはジルヴァルドの姿が見えなくなるまで川を見つめていた。
ぽつりと天から雫が落ちてきた。
雨は、初め小振りだったが、縄をかけられ、村に運ばれる間にどんどん強く、どんどん激しくなっていった。
助けられなくてごめん、重荷になってごめん。
どうか生きて、
俺の分まで生き延びて。
神様、どうか、弟を助けてください―――
目覚めた時、清潔なベッドの上で暖かな食事を与えられて、悪意のない言葉と優しい笑顔を向けられて。
天国かと思った。
けれど、そうではないとすぐに理解できてしまう。
だっておれは人を殺めた。
兄さんを守るためとはいえ、二人の人の命を奪ってしまった。
このことについては後悔していない。後悔はしていないが、考えると頭と胸が痛んだ。
そして何よりも、どうしてここに兄がいないんだろう、どうしてあの時、兄から離れてしまったんだろうと。
今、兄はどこでどうしているのか。
最後の最後で微かに見えた光景。
それは兄が村人たちの手に掛かる瞬間だった。
「う、あッ……」
こみ上げてくる吐き気に噎せこむ。
喉の奥と胸が気持ち悪くて、頭がガンガン鳴る。
咳と共に吐きだした酸い臭いのする液体がシーツを汚す。
「ジルさん!」
隣の部屋から僧服に身を包んだ女性が駆け込んでくる。
彼女はこの教会のシスターで、ジルヴァルドの意識が戻る前から、ずっと看病してくれていたらしい。そして今でも、満足に身体を動かすことができず寝たきりのジルヴァルドの世話をしてくれていた。
彼女の話によると、滝から落ち川に流されていたところを助けてくれたのは、この教会の神父だったそうだ。彼もまた優しげな男で、ジルヴァルドの様子を気にして医者を呼んでくれたり、必要な時には手を貸してくれたりした。
どうしておればかりがこんなに恵まれた環境にいるのだろう。
どうしてここにいるのは兄じゃないんだろう。
温かい手が背中をさすってくれる。
「気分が悪いんですか? 大丈夫、大丈夫ですからね、すぐにお医者様を呼んできますから」
「へ、き、です……すみません」
「ジルヴァルドさん……」
シスターは黙ってシーツの汚れを拭うと、後で新しいものに替えますねと言い置いて部屋を出て行く。
心苦しさに潰れそうな胸を抱え、ジルヴァルドは小さく丸くなって声を殺しながらまた泣いた。
意識が戻ってから、既に数十日が過ぎていた。
ベッドの上で、ただ無為に過ごす日々。
過去を悔いて、自分を責めて、現実を嘆いて呪って。
なぜ、どうして。気が付けば自問自答を繰り返している。
どうして自分はまだ生きているのだろう。
兄がいないなら、もう自分には生きる意味などないのに。
今でも鮮明に思い出されるのは最後に見た兄の顔。
寂しげに、悲しげに、けれど笑っていた。
川の流れに呑まれ、あっという間に引き離されてしまった。
たった一人残された家族。
命尽きるまで、守ろうと決めていたのに。最後の最後で、手を離してしまった。
兄が無抵抗に捕えられる様を見ていることしかできなかった。
あの足では、きっともう逃げられやしない。
あれから何度も夢に見る。
兄が酷い目に合わされ、苦しむ姿を。ぼろぼろになって打ち捨てられる姿を。
そしてその度に己の叫び声で目を覚ました。
そんな日々が続いて、ジルヴァルドの身体は徐々に弱っていった。
眠りは浅く、食欲は減退し、見る間に痩せこけていった。
助けてくれた神父や、心配してくれるシスターに申し訳ないという気持ちがないわけではないが、この世に兄がいないのだと思うと、全てがどうでもよくなる。
ふと動かした視界の隅には小さな卓、その上に置かれた透明の水差しとグラス。
不穏な考えが頭をよぎる。
このまま何も口にしないだけでも、緩やかに死は訪れるだろう。
けれどもう、この世に未練もない。だったら少しでも早く兄の元へ行きたい。
「ッ………」
一人では起き上がることもままならない身体で這うようにし、腕の力を使って、どうにか動く。
シーツがよれて皺になり、ジルヴァルドの身体と一緒に床に落ちた。
激痛が足と腰に走って、動けずにいると、物音を聞きつけてきたらしいシスターが驚きの悲鳴を上げた。
「ジルヴァルドさん、どうしたんですか!」
「もういいんです、もう」
「何を……とにかく、ベッドに戻りましょう」
「お願いします、どうかおれのことは放っておいてください」
床に倒れ込んだままのジルヴァルドを助け起こそうしていたシスターは、その悲愴な声音に動きを止める。
こんな風に人前で弱音を吐いたりしてみっともないと、兄がこの場にいたら叱られたに違いない。
しかしどうせ兄はもういない。
「君のお兄さんは生きていますよ」
コツッと静かに足音が響いて、目の前に僧服の裾と黒い靴の先が見えた。
見上げるとそこには神父の姿があって、彼は呆気にとられるジルヴァルドの脇にしゃがみこんでくる。
「今、なんて……」
「君のお兄さんは生きています。村では相当酷い扱いを受けていたみたいですが、今はきちんと保護されて病院で治療を受けているそうです」
「どうしてそれを……」
ジルヴァルドは彼らに自分の事情は話していなかった。
神父やシスターも無理に聞いてこようとしなかったからだ。
眼鏡をかけた優しげな面差しの神父は少し微笑んで言う。
「お兄さんのことが気になるでしょう? 私の知っていることは全部お話しましょう。だから落ち着いて、まずはベッドにお戻りなさい」
***
兄が生きている。
その言葉はジルヴァルドの胸に強く響いた。
さっきまでの荒んだ気持ちは一息に霧散し、目の前が明るくなる。
「申し訳ありませんが、勝手に色々調べさせてもらいました。君の素性はすぐにわかりましたよ。二年前、横領の罪で失脚に追い込まれたメタレイア議員の子息、そうですね?」
ベッドの横の椅子に腰かけ、彼はそう切り出した。
ジルヴァルドは黙って頷く。
神父は膝の上で両手を組み合わせると、視線を落とし、床を見つめながら話を続けた。
「意識を取り戻した時、君は名前以外何も話そうとしませんでした。それにいつも虚無を抱えているような暗い目をしていて、だからずっと気になっていて……それで君が倒れていた川をずっと上って行った先にある村を地図で見つけました。君も君のお兄さんも、随分と大変な目に合ってきたんですね」
「………」
「ああ、ごめんなさい。聞きたいのはそういうことではないですよね。私は、この間村に行って君たちの話を知ったんです。村の墓場は荒れていて、近くにいたひとに訊いてみたら、今は墓守が不在だからと言われてね。一人は三か月前に森の奥の滝から落ちて行方不明、もう一人は」
彼はそこで一旦言葉を切ると、小さく息を吐きだした。
眉が寄って、眉間の間に皺が刻まれ険しい顔つきになる。
「もう一人は、村人二人を殺害・逃亡の罪で酷い拷問を受けたと……」
ジルヴァルドは血が滲むほどに唇を噛む。
聞くまでもなくわかっていたことだが、事実として知らされるとやはり胸が痛んだ。
「ですがジルヴァルド、君が眠っている間に、政権が変わったことは前に伝えましたね」
「はい……」
「その時、メタレイア議員の無実が証明されました。メタレイア議員は横領なんかしていなかった、そしてそれをずっと信じていた人がいたんです。メタレイア議員の支持者でもあるブロンセ議員です。メタレイア議員の不正に加担した疑いで、拘束されていたらしいのですが。そのブロンセ議員が解放されて、君たちのことを探していたそうです。それで村で君の兄を見つけて、保護してくれたのだと。今は、病院で治療を受けているとそう聞いています」
その日から、ジルヴァルドの様子は大きく変わった。
食事をしっかりとるようになり、積極的に医師の治療も受けるようになった。
努力の甲斐あって、歩けるようになるまで数ヶ月はかかるだろうと言われていた足は、まだぎこちなく緩慢な動きではあったが、たった一ヶ月足らずで回復した。
全てを諦めていた目には、光が戻っていた。
ジルヴァルドがリハビリに勤しむ間、神父はブロンセ議員に手紙を書き、連絡を取っていたらしい。
しばらくして教会に現れた厳めしい顔つきの初老の男に、ジルヴァルドは何となく見覚えがあった。
応接室で父と話す横顔。
そっと扉の隙間から覗き見ただけの記憶の中にある姿よりも、今は幾分痩せ衰えて見えた。
無事でよかった。
彼が言ったのはそれだけだったが、不思議とその一言の中にすべての感情が詰まっているように思えた。
ジルヴァルドは彼に連れられ、慣れ親しんだ街へと戻ってきた。
幼い頃から育ってきた街並みは懐かしくもあったが、同時に恐ろしく物悲しい記憶をも呼び起こした。
ジルヴァルドは外套のフードを被り、顔を隠すと俯き加減に道を急いだ。やがて街角にそびえる大きな建物が見えてくると、複雑な感情はすっかり忘れ去られ、ジルヴァルドの意識はその一点へと集中する。
もうすぐ兄に会える。
もうすぐ。やっと。
兄はもう自分の無事を聞いているだろうか。
怪我はもう治っただろうか。いや、完治していないからこそ、まだ病院にいるのだろう。
それならばこれからは自分が兄の手となり足となろう。今度こそ兄の支えになりたい。
そんなことを考えていたら、前を歩いていたブロンセが急に足を止めた。
不思議そうに眼を瞬かせるジルヴァルドに、ブロンセが言う。
「これから目の当たりにする現実は、君にとって残酷なものかもしれない。けど、どうか兄さんの傍に。どうか力になってやってくれ。おまえはあいつにとって残されたたった一人の家族なんだ」
ブロンセの言葉の意味は、すぐにジルヴァルドの理解するところとなった。
木の緑がいっぱいに広がる大きな窓のついた、広い贅沢な部屋の片隅。車椅子に腰かけ、ぼんやりと窓の外を眺めてる小柄な青年。
淡い金色の柔らかそうな髪と同色の瞳の、以前にも増してやつれたその横顔。
胸の内がざわつく。
一気に溢れ出た感情がじわりと頭の先まで広がるような感覚。
「兄さん……」
ふらつきながら、部屋に足を踏み入れる。
「兄さん!」
思わず漏れ出た呟きは、今度こそ呼び声に変わる。
ところが目の前にいるはずの青年はまるでジルヴァルドの声が聞こえていないかのように、窓の外を見つめ続けている。
「兄さん、おれです。兄さん?」
ジルヴァルドは車椅子の前に回ると、痩せた腕を掴み必死になって呼びかける。
そこで青年の目はようやくジルヴァルドを捕えた。ほんの僅かな動きだったが、ひどく緩慢だった。
茫洋とした瞳がジルヴァルドの不安げな顔を映し出す。
薄く開いた唇から自分の名前が紡がれることを一瞬期待したが、彼は薄く微笑むだけであった。
ジルヴァルドは衝撃のあまり表情を失い、兄の肩越しにブロンセを見やる。
「我々が君の兄を見つけた時、彼は既にその状態だった。いや、それ以上に酷い状態だったと言ってもいい。傷と、痣だらけで……呼び掛けても揺さぶっても何の反応もない。まるで、ただ息をしているだけの、人形のような」
ジルヴァルドは再び兄に視線を戻す。
兄はにこにこと自分に笑顔を向けている。ジルヴァルドには、その笑顔の裏に何の感情もないように思えた。
「彼の眼は何も映さず、何も感じ取らず、そして実の弟である君のことすら恐らく認識していない」
「兄さん、なんで、こんな……」
無意識に漏れた呟きに、ブロンセは答えを寄越してくる。
「よほど酷い目にあったんだろう……医師が言うには、恐怖や嫌悪や絶望や、そういった様々な感情に押し潰されそうになって、自身を守るために自ら心を閉ざしたのではないかと」
それから、ブロンセは僅かに間を置いて言う。
明確な治療法は今のところない、と。
ややあって、ジルヴァルドは重い口を開いた。
「……すみません、少しだけ二人にしてもらえませんか?」
ブロンセは頷き、部屋を出て行く。
扉が閉まり、足音が遠ざかると、ジルヴァルドはもう一度兄の顔を見上げた。
兄は、初め部屋を訪れた時と同じように、窓の外を見ていた。
若葉生い茂る木々の枝。その隙間から零れる白いこもれび。時折風が吹いて、葉を揺らす。どこかから鳥の鳴き声は聞こえるが、その姿は見えない。
穏やかだが、特段変化もなく面白みのない光景だ。
けれど、兄の視線は先程からずっとその光景に注がれ続けている。
ジルヴァルドは再び兄を呼ぶ。
「兄さん」
もちろん兄は無反応だったが、構わずジルヴァルドは話し続けた。
「兄さん、おれは無事です。兄さんのおかげで、あの後親切な神父様とシスターに助けてもらって、それで……おれ、最初は兄さんはもうあいつらに殺されたんだって、死んでしまったんだって思い込んでて、それならおれは生きてても仕方ない、早く兄さんや父さん母さんのところに逝きたいって思ったりもしたけれど。でも、兄さんが生きてるってわかって嬉しかったんです」
ジルヴァルドの声はきっと、兄に届いていないだろう。
そんなことはわかっている。
わかっていながら、それでもジルヴァルドは声を発する。
「おれはただ、兄さんが生きてることが嬉しくって、でもまさか、こんなことになっているなんて思いもしませんでした」
あの後一体どんな酷い目にあったのだろう。
どれほど恐ろしい思いをしたのだろう。痛い思いをしたのだろう。辛く、苦しい時を過ごしたのだろう。
車椅子の肘掛けに乗せられた手を取り握る。
うっすら残る傷痕を見つけて、指でなぞる。傷自体すっかり塞がってはいるが、皮膚が僅かに膨らんでいた。
「あの日、あの大きな川を前にしておれは一瞬でも諦めてしまいました。その結果、兄さんから手を離してしまった。どうして最後の最後まで諦めずにいられなかったのか、どうして、兄さんの手をしっかり握っていなかったのか。悔やんだところで、何も変わらないって、どうしようもないことなんだってわかってます」
頭ではわかっているが、気持ちだけはどうしようもなかった。
ジルヴァルドの頬を、熱い涙が一筋伝い落ちていく。
一度溢れ出すと止まらなかった。
ぼろぼろと大粒の雫が零れて、兄の膝を濡らす。
泣くなんていつ以来だろう。死にたいって思ったあの時も、両親が目の前で殺された時でさえ涙なんて出なかったのに。
小さな頃は、よく泣いていた気がする。
転んで膝をすりむいた時。父の仕事で母が共に出かけることになった時。いたずらをして叱られた時。
その度に手を差し出してくれる人がいた。
――――泣くなジル。
そう言って頭を撫でてくれて。
――――俺が一緒にいるからな。
ふと、握っていたか細い手が、ジルヴァルドの手の中から逃げ出す。
その手が蝶のようにふわりとジルヴァルドの頭に添えられて、ゆっくりと髪を撫でるように動かされる。
「に、いさん……?」
驚いたジルヴァルドが、兄を振り仰ぐ。
彼は窓に向けていた視線をジルヴァルドに移し、やはり微笑を浮かべるばかりだ。
どこか虚無を抱えたような笑み。
だが。
昔と同じ手つきで、優しくて温かくて、思い出す。
幼い日のことを。
冒険と称してこっそり屋敷を抜けだしたことがある。迷ううち夜になり、見知らぬ場所で暗闇で、兄の方こそ不安だっただろうに、そんな中でもジルヴァルドを励まし、庇い続けてくれた。
兄はずっとジルヴァルドを守ってくれていた。
ずっと。
それは、成長しジルヴァルドが兄よりも大きくなってからも。全てを奪われ、貧しい生活を強いられるようにようになってからも。
そうして今も。
ジルヴァルドはぐいっと拳で頬を拭う。
頭を撫でる手を取り、両手で握りしめて、ジルヴァルドは兄をまっすぐに見た。
「兄さん、一人にしてごめんなさい。でもこれからはずっとおれが傍にいます。おれが、兄さんを守りますから」
✴︎✴︎✴︎
兄、アウルムと再会してから、早くも一年が経とうとしていた。
状況は何も変わらない。
アウルムは今も自我を失ったままで、今はジルヴァルドが身の周りの世話をしている。
顔の前にスプーンを持って行けば、アウルムは口を開く。そうしてゆっくりと咀嚼し、飲み下す。
相変わらず表情は変化に乏しく反応も少ないが、時折笑顔を見せてくれるし、窓の外を眺めるのが好きらしい。
季節は春。
病室から見える木の花の蕾も膨らみ、あと少しで開きそうだ。
「少し散歩でもしましょうか」
車椅子を押し、庭に出る。
暖かい陽気の中を蝶が舞い、花の香りが風に運ばれてくる。
庭の木々や草花は手入れされて美しい。
鳥のさえずりが聞こえる。離れた場所で地面を啄む小鳥の姿にジルヴァルドは目を細める。
「兄さん、わかりますか? ツグミです。うちの庭にも良く来てましたね」
返答などないことを知りながら、ジルヴァルドはこれまで何度も根気強く語りかけてきた。
いつか自分の声が届くのではないかと。何か心に響く言葉があるのではないかと。
そして、今回もアウルムはジルヴァルドの言葉に何の反応も示さない。
ところが兄の様子は普段とやや異なっていて、ジルヴァルドはそれに気が付いた。
「どうかしましたか?」
何かに気を取られているかのように、アウルムの目はただ一点に据えられたまま動かない。
視線の先を追ってみると、そこには花壇を手入れする庭師の姿があった。しかし日よけの帽子を被り、作業に勤しむ老爺に見覚えはない。
「あの人のことが気になるんですか?」
ちょっと待っててくださいねと言い置いて、ジルヴァルドは庭師の元へ走る。
「あの、すみません」
庭師は作業の手を止め、顔を上げると、はてと首を傾げる。
それからジルヴァルドの背後にある車椅子を見つけて、納得したように頷いた。
「ここの患者さんのご家族さんじゃな、ちょっと待っとけ」
彼は先程まで手入れしていた白い花をハサミで切って、ジルヴァルドに寄越した。
「え、あ、いいんですか?」
「少し間引いてやらんとな、ええから病室に飾ってやりな」
ひらひらと手を振ると、庭師は道具を抱えて立ち去る。
やはり知り合いではないようだ。
何が気になったのだろうと首を捻りつつ、ジルヴァルドはアウルムの元に戻る。
「お待たせしました、兄さん?」
見ればアウルムはうとうとと船を漕いでいて、ジルヴァルドは微笑むと、車椅子の後ろに回った。
「今日は暖かくて気持ちが良いですもんね。そろそろ部屋に戻りましょう」
病室に戻って、アウルムの体をベッドに移動させると、ややあって静かな寝息が聞こえてくる。
先刻分けてもらった花は花瓶に活けて、枕元の棚の上に置き、ジルヴァルドは傍らの椅子に腰かける。
穏やかな寝顔だ。
一体どんな夢を見ているのだろう。
「おやすみなさい……」
そう呟いて、椅子から立ち上がる。
今の間に洗濯を済ませてしまおう。
今日は朝から晴れで、綺麗な青空が広がっている。心地よい風と日差しに布団のシーツも良く乾くだろう。
***
甘い匂いがする。
花の匂いだ。
アウルムはこの匂いが好きだ。
ずっと前からそうだった気がする。
どうしてだったか、何の花なのか、それはわからない。覚えていない。
だけどふわりと優しくて、安心する。
「おやすみなさい……」
静かな声。
これもまたずっと前から知っている。
今、自分はとてもしあわせだ。
やさしいものばかり。
あたたかいものばかり。
とてもしあわせで、うれしい。
瞼を閉じれば、意識はすぐに眠りの中へと沈んでゆく。
ああ、またこの夢だ。
手入れの行き届いた広い庭。
大きな木の根元、アウルムは若い緑の草の上に寝そべって伸びをする。
太陽の光は伸びた枝葉で遮られて眩しさはない。さわさわと葉が風に擦れる音。頭上を蝶が舞う。
静かで穏やかで美しい花が咲き乱れていて。自分の他には誰もいない。誰に咎められることもなく、好きなだけこうしてのんびりしていられる場所だ。
まるで物語に出てくる楽園のようだと思う。
ふと、赤い小さなテントウムシがアウルムの鼻の頭に止まった。くすぐったさに身体を起こして、頭を振る。
テントウムシはまたどこかへ飛んでいき、アウルムはそこで初めて耳慣れない声に気が付いた。
それは遠く聞こえてくる、誰かの泣き声のようだった。
いつもは鳥の声と風の音、それに木のざわめきくらいしか聞こえないのに。一体、自分以外の誰がこの庭にいると言うのだろう。
ここはアウルムだけの場所なのに。
大事な大事な、秘密の場所なのに。
文句を言ってやろうと、立ち上がる。
スズラン、モクレン、クチナシ、ハナミズキ、マーガレット。
白い花々に彩られた道の真ん中を、アウルムは憤然と歩いて行く。
そうして突き当たりに見えてきたのは、ノイバラの木とその手前で座り込んで泣いている小さな子ども。
短い銀髪の少しふっくらとした男の子だ。二、三歳くらいだろうか。自分よりもずいぶん年下のように見える。
アウルムは男の子の前に立つと、腕組みをし、腹立ちを声に含めて呼びかけてみた。
「おいチビ」
男の子は吃驚したように泣くのを止め、きょとんとしてアウルムを見上げてくる。
「おまえどこから入った。ここは俺の庭だぞ」
「ぷれぜと……」
「ぷれぜと?」
「おはな、にーちゃんにあげるの……」
「ああ、兄ちゃんへのプレゼントに花をあげたいってことか?」
男の子はこくりと首を縦に振ってみせる。
アウルムはその場にしゃがみこみ、視線を合わせると更に問いかけた。
「それで、お前はなんで泣いていたんだ?」
「……」
男の子は黙って、指で指し示す。
そこにはノイバラの木があった。
アウルムの背丈よりも高く伸びたその木は、可憐な白い花をいくつも咲かせている。
「ああ、これが欲しかったのか? ちょっとくらいなら取っても、ッ!?」
言ってアウルムは細い枝に手を伸ばすが、指先に痛みを感じてすぐに引っ込める。指先には丸く小さく血が滲んでいた。
そうか、バラには棘があるんだったなと思って、今度は慎重に枝に触れる。
それでも無数の棘はアウルムの手の甲や指を傷つけたが、我慢して手首を僅かに捻って枝を一本折り取ってやる。
「怪我しないように気をつけろよ」
差し出されたノイバラの枝を受けとると、男の子はぱっと顔を輝かせ、少しだけ笑った。
さて、もう一度昼寝でもするかと来た道を戻ろうとした時だ。
くいっとズボンの裾を引く手があった。振り返ると、男の子がアウルムのズボンを掴んでいて、丸くて可愛らしい目でじっと見つめてくる。
「……おい、もっと欲しいなんて言うなよ」
男の子は、今度は首を横に振る。
「そしたら何、まさか帰り方がわからんなんてことは……」
困ったことに、そのまさかであった。
今度は頭を縦に振る姿に、アウルムは長く仰々しい溜息を吐く。
それから男の子に向かって手を差し出してやる。
「ほら。俺も一緒に兄ちゃん探してやる」
どこの誰かもしれぬ子どもの守りなんて面倒くさいが、どうしてだかこのまま放っておくことはできなかった。
男の子は花を持った方とは反対の手でアウルムの手を握ってくる。
不安の表れなのか妙に強い力だった。
庭の傍には白い壁の大きな屋敷がある。多分そこの子どもだろうと思って、アウルムは男の子の手を引きながら屋敷の入り口を探した。
壁沿いにぐるりと歩いていくと、玄関の扉はすぐに見つかった。
扉を叩いても、呼びかけても応じる者は誰もいない。仕方なくそっと押してみると、鍵はかかっておらず、扉は簡単に開いた。
中は赤い絨毯が敷かれて、真正面には左右に伸びる階段が見える。
そこへ来てようやく、男の子の顔から不安が取り除かれた。見覚えのある場所まで戻ってこられたということかもしれない。
やれやれとばかりにアウルムは手を離そうとしたが、小さな指はしっかりとアウルムの手を握って離れない。それどころか今度は男の子がアウルムの手を引いて、屋敷の中へと入ってゆく。
「こら! もう一人で帰れんだろ!? 手ぇ離せって!」
困惑してアウルムは言うが、男の子は小走り気味にエントランスを抜けて、唯一大きく開かれた扉の部屋へとまっすぐに向かう。
繋がれた手を振り払おうとするが、どういうわけか敵わない。
そして―――
華美な装飾がなされたエントランスと比べると、調度品が少なく簡素な印象の部屋。
窓から吹きこむ風に、ふわりふわりと揺れるレースのカーテン。
その手前には小さな木の椅子と大きなベッド。そしてベッドの上には、目を閉じて動かない青年の姿。
男の子はやっとアウルムから手を離して、ベッドの方へと駆けて行く。
アウルムはその光景に一瞬目を疑う。
男の子が瞬きの間に、眠る青年と同じ年頃の姿に変わったのだ。
銀の短い髪と凛々しい眉、丸い目はそのままで、けれどたくましく成長した幅のある身体。
彼は木の椅子に座り、ベッドの上を見つめる。
「兄さん……」
呟く声は切なく、そしてどこか悲しげだった。
眉根が寄って、瞳が揺れて、今にも泣きだしそうに表情を歪ませている。
青年に目覚める気配はない。
何だろう。
胸がずきずきする。
一体あれは誰なんだろう。
どうしてこんなに胸が痛いんだろう。
自分はあの銀髪の男を知っている気がする。
とても気になる。
それなのに思い出そうとすると、頭がひどく痛んだ。
やめろ。考えてはいけない。やめろ。やめろ。
やめろ。
全て忘れたままでいる方がいい。
何も思い出さず、何も理解せず、何も感じず。
そうすれば何も恐ろしくない。
悲しむこともない。
苦しいばかりの過去なんて捨ててしまえ。
そうすれば解放される。
楽になれる。
頭を抱えるアウルムの耳に、再びあの囁くような声が聞こえてきた。
「兄さん」
男はずっと大事そうに持っていたノイバラの花を枕元に静かに置く。
途端に窓から強烈な風が吹き込んできて、アウルムは思わず腕で顔を庇う。
風が治まり、次に目を開けると、先程まで部屋であったその場所はがらりと変わっていた。
一面の星空。
黒いヴェールに散りばめられたビーズ飾りのように、強く、弱く輝きを放つ星々。
足元が何だかふわふわしていて、見てみると白い靄みたいなところに足首まで沈んでいる。まるで雲の上にいるようだと、アウルムは思う。
「すげぇだろ?」
突然、背後から声を投げかけられて驚く。
「これ、今雲の上にいるんだぞ」
得意げな顔で言ったのは、金色の髪の少年だ。
少年は後ろに倒れ込むようにして、雲の上に寝そべると、アウルムにも隣に来るよう促してくる。
「見ろよ。すげえ近くに星があるんだ」
アウルムは少年の隣に足を抱えて座ると、天を振り仰ぐ。
彼の言うとおり、地上で見るよりもずっと星が大きく間近に感じられた。
「綺麗だろ?」
少年の言葉に、アウルムは無言で頷く。
「ここにはなんでもあって、なんでもできる。好きなことを好きなだけしていていいんだ」
少年は言って、目元を笑ませる。
その顔を不思議な気分で眺めながら、アウルムは口を開いた。
「訊いてもいいか?」
「ん?」
「ここは、どういう場所だ?」
少年は勢いをつけて跳ねるように起き上がると、ゆっくりと前方に歩いていく。
「うーん、そうだなあ……ここはまあ、言うなれば卵の殻の中みたいなもんかな」
「卵?」
「そう、ここにいれば安全。色んな怖いことから守ってくれて、あたたかくて安心できる。そんなとこ」
「殻の外は、どうなってる?」
「怖いことがたくさんある。辛いことも」
少年は足を止めて、くるりと身体ごと振り返った。
「けど、ここにいればそんな心配はいらない。考える必要もない」
彼は芝居じみた仕草で両手を広げてみせる。
アウルムは立ち上がり、数歩進んで少年に近づいた。
「ほんとに、ここは楽園みたいなとこだよな……苦しいことも悲しいこともなくて、好きなことばかりしていられて居心地良くて」
まっすぐに向けた視線の先には、髪と同じ色の瞳がある。その中を覗き込みながら、アウルムは言う。
「俺は初めここに来た時、すげえ疲れてた。何もしたくなくて、何も考えたくなくて、だからこの場所に逃げ込んだ。嫌なこと全部、ぜんぶ投げ出して、この中に閉じこもって、それで何もかも忘れられて。お前の言うとおり、ここは安全だ。ここにいれば、何も心配はいらない。けどな何か、」
アウルムは服の胸の辺りを掴んで、ぎゅっと拳を握る。
「何か物足りんなって思ってた」
ぽっかりと胸に穴が空いたような感覚。
それが何なのかずっとわからなかった。
「嫌なことと一緒に、何か大事なことまで忘れてしまってるような、ずっとそんな気がしてた……そして、やっとわかったんだ」
少年は短く吐息し、肩を竦める。
「さっきのあれ。あれはお前見せたものだろう?」
「さあ、なんのことやら。わからねぇな」
少年の空々しい言葉に、アウルムは苦笑する。
また少し、少年に近づいてアウルムが言う。手を伸ばせば触れる距離。
「俺、そろそろ帰らなきゃだ」
「せっかくこんな楽園みたいな場所にいるのに? わざわざ嫌な思いをしにいくって言うのか?」
少年は口元に意地の悪い笑みを刻む。
アウルムの意思も今から答える内容も何もかも、きっとわかっているんだろう。
だって彼は、他ならぬアウルム自身なのだ。
「でも、ジルが待ってる」
腕を組んでもう一度短い溜息を吐きだして、もう一人の自分は手を差し伸べてくる。
ここを出れば、これまで避け続けてきたすべてものがそこにある。
大丈夫という自信があるわけではない。不安は重く胸に圧し掛かる。
でも泣いている弟を、放ってはおけない。
何せアウルムはジルヴァルドのただ一人の兄だ。
差し出された手を取って、アウルムは目を閉じる。
脳裏をよぎるのはこれまで起こったすべての出来事。
アウルムの中で時間が一気に進んでいく。
***
甘い花の香り。
カーテン越しに差し込む、柔らかな午後の陽光。
途切れがちに聞こえる誰かの話し声。
真っ白なシーツの中に沈む重い身体。
アウルムはゆっくりと瞼を持ち上げる。
寝覚めにぼんやりする頭で、ゆっくりと目だけを動かし周囲を見回す。
部屋の扉近くに見える背中。誰かと何やら話しているらしい。
軽く頭を下げるその後ろ姿。
大きなその背中。
知っている。
そうだ、あれはたった一人の。
急激にこみ上げてきた感情が喉元でつかえる。
アウルムは震える声にその想いを全てのせ、その名を呼んだ。
「ジル……!」