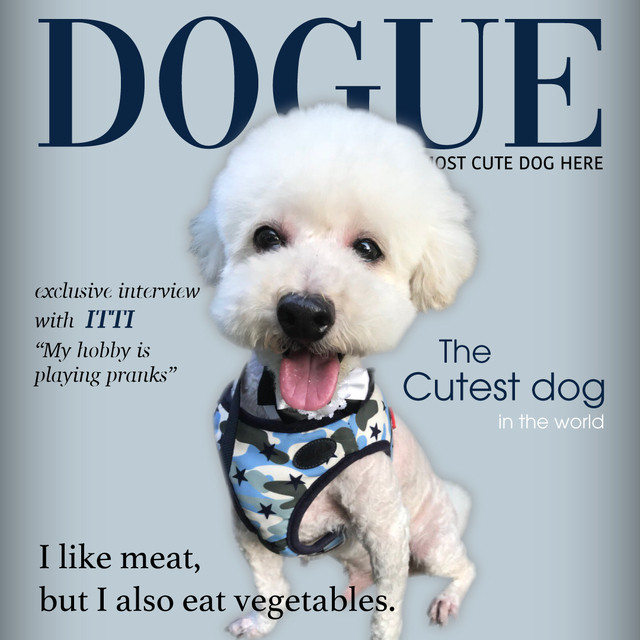初めて飲んだドリップコーヒー
文字数 1,814文字
荘重なクラシック音楽とコーヒーの香りに包まれた小さなコーヒースタンド。
6月半ばだというのにまだ降り続く五月雨が染み込んで、いつもよりやけにしっとりとした空気の店内は普段よりもっと小洒落た雰囲気が増していた。
カウンターだけの手狭な店内に、身の丈に合わないような高めの椅子が、ちっぽけな女子高生の私を少し気恥ずかしい気分にさせていた。
「先輩、いつものハニーカフェオレ!」
「また?たまにはドリップコーヒーは?」
「あんなのただの苦い焦げ汁じゃないですか…」
変わらないいつものやりとり。
先輩は高校の文芸部部長だったんだけど、今は客と大学生のアルバイト店員。下剋上だ。
高校からも程近いこのコーヒースタンドを憩いの場として通い詰めすぎて、もはやここの店員の先輩の方が目に馴染んでいる。
今日は珍しくマスターがいない。勇気を出して、気になっていたことを初めて聞いてみることにした。
「せっかく大学生になったのに、なんでこんなにずっとバイトばっかりしてるんです?」
「…実は俺、将来バリスタになりたいの。でも部員のみんなには内緒な。」
予期せぬ2人だけの秘密を急に抱えることになって、ハニーカフェオレが喉に突っかかりそうになった。
でも内緒にしたくなるのもわかる。
先輩は多才だからだ。高校卒業の記念にと、講談社の新人賞に応募してあっさりと最優秀賞を受賞してしまうくらいの文才の持ち主で、もちろん頭も良い。高校を卒業後はすんなり国立大学に合格。おまけにモテる。いわば我が高校の文芸部希望の星だった。
そのマルチな才能に嫉妬する輩は数知れず。まぁ私もそのうちの1人なんだけど。
ちりんとマスターが入り口の鈴を鳴らして帰ってきた。
「あぁ、後輩ちゃん来てたのね。やっぱり、先輩がいなくなるのって寂しい?」
「いなくなる…?」
「あ、えっと、そのマスター、まだ…言えてなくって」
喉の奥がぎゅっとなった。
はちみつの甘ったるさが突っ掛かったみたいだ。
「…どこか、行っちゃうんですか?」
「いや…まぁ、さっきの話の続きなんだけど、やっぱりバリスタになりたくてさ。本場のオーストラリアに行こうかなって。ちょうどうちの大学の姉妹校があるから。」
そんなの聞いてない。なんでこの人はいつもこう突然なんだろう。高校の時もそうだった。大学なんて適当なところでいいし、という雰囲気を醸し出しながら、ちゃっかり自分の学力にあった大学に我先にと合格する。
私なんて、高校の文芸部の中ですらなんの役割も担えていないのに。
同じ場所にいるのに、なんだかとても遠くにいるような気がした。
それがどうにも悔しくなって、飲めないドリップコーヒーをおかわりで頼んでみた。
「先輩が淹れたドリップコーヒー、美味しいですね。もっと早く飲めばよかった。」
先輩は何も言わずに、ただはにかんだだけだった。
初めて飲んだドリップコーヒーはやっぱり苦くて、私はこれからコーヒーを飲むたびに先輩を思い出すのかなと思うとなんだかやっぱりずるい人だなと思った。
先輩がオーストラリアに飛んでから、私は初めて何かに打ち込んでみようと思えた。
先輩を頭から追い出したかったという気持ちもなかったわけではないけれど。
とりあえず本をたくさん読んでみることにした。今まで読んだことのなかった純文学、苦手かもしれないと思っていた著名人の小説やエッセイ、偉人の軌跡など。おまけにオーストラリアの旅行本まで。いつの間にか文芸部でも随一の本の虫になり、知らぬ間に部長になって後輩たちに文章の添削ができるまでになっていた。
軽やかなジャズとコーヒー豆の華やかな香りが広がる大きなコーヒーショップ。
カラッとして青空によく似合う爽やかな白いシャツを着た先輩が私を迎えた。
広々とした店内にはさまざまな本が所狭しと並べられていて、そのどれもが秀逸なセンスが光っていて、やっぱり希望の星はずるいと思ってしまう。
小説好きなお客さん、著名な作家も集うお店として、立派に賑わっている。今度大きなメディアにも掲載されるらしい。
「本当、なんでも手に入れちゃうんですね。」
「何を?」
「なんでもです。なあんでも。富も夢も名声も全部!」
「でもまだ手に入れられてないけど、文芸部の部長の彼女もいないしね。」
驚いて振り向くと、もう別のお客さんのところで接客を始めている。
こんなに待たせておいて、結局私を動かすんだもんなぁ。
本当に、ずるい人だ。
「先輩!こっちにもドリップコーヒーを1杯お願いします!」
6月半ばだというのにまだ降り続く五月雨が染み込んで、いつもよりやけにしっとりとした空気の店内は普段よりもっと小洒落た雰囲気が増していた。
カウンターだけの手狭な店内に、身の丈に合わないような高めの椅子が、ちっぽけな女子高生の私を少し気恥ずかしい気分にさせていた。
「先輩、いつものハニーカフェオレ!」
「また?たまにはドリップコーヒーは?」
「あんなのただの苦い焦げ汁じゃないですか…」
変わらないいつものやりとり。
先輩は高校の文芸部部長だったんだけど、今は客と大学生のアルバイト店員。下剋上だ。
高校からも程近いこのコーヒースタンドを憩いの場として通い詰めすぎて、もはやここの店員の先輩の方が目に馴染んでいる。
今日は珍しくマスターがいない。勇気を出して、気になっていたことを初めて聞いてみることにした。
「せっかく大学生になったのに、なんでこんなにずっとバイトばっかりしてるんです?」
「…実は俺、将来バリスタになりたいの。でも部員のみんなには内緒な。」
予期せぬ2人だけの秘密を急に抱えることになって、ハニーカフェオレが喉に突っかかりそうになった。
でも内緒にしたくなるのもわかる。
先輩は多才だからだ。高校卒業の記念にと、講談社の新人賞に応募してあっさりと最優秀賞を受賞してしまうくらいの文才の持ち主で、もちろん頭も良い。高校を卒業後はすんなり国立大学に合格。おまけにモテる。いわば我が高校の文芸部希望の星だった。
そのマルチな才能に嫉妬する輩は数知れず。まぁ私もそのうちの1人なんだけど。
ちりんとマスターが入り口の鈴を鳴らして帰ってきた。
「あぁ、後輩ちゃん来てたのね。やっぱり、先輩がいなくなるのって寂しい?」
「いなくなる…?」
「あ、えっと、そのマスター、まだ…言えてなくって」
喉の奥がぎゅっとなった。
はちみつの甘ったるさが突っ掛かったみたいだ。
「…どこか、行っちゃうんですか?」
「いや…まぁ、さっきの話の続きなんだけど、やっぱりバリスタになりたくてさ。本場のオーストラリアに行こうかなって。ちょうどうちの大学の姉妹校があるから。」
そんなの聞いてない。なんでこの人はいつもこう突然なんだろう。高校の時もそうだった。大学なんて適当なところでいいし、という雰囲気を醸し出しながら、ちゃっかり自分の学力にあった大学に我先にと合格する。
私なんて、高校の文芸部の中ですらなんの役割も担えていないのに。
同じ場所にいるのに、なんだかとても遠くにいるような気がした。
それがどうにも悔しくなって、飲めないドリップコーヒーをおかわりで頼んでみた。
「先輩が淹れたドリップコーヒー、美味しいですね。もっと早く飲めばよかった。」
先輩は何も言わずに、ただはにかんだだけだった。
初めて飲んだドリップコーヒーはやっぱり苦くて、私はこれからコーヒーを飲むたびに先輩を思い出すのかなと思うとなんだかやっぱりずるい人だなと思った。
先輩がオーストラリアに飛んでから、私は初めて何かに打ち込んでみようと思えた。
先輩を頭から追い出したかったという気持ちもなかったわけではないけれど。
とりあえず本をたくさん読んでみることにした。今まで読んだことのなかった純文学、苦手かもしれないと思っていた著名人の小説やエッセイ、偉人の軌跡など。おまけにオーストラリアの旅行本まで。いつの間にか文芸部でも随一の本の虫になり、知らぬ間に部長になって後輩たちに文章の添削ができるまでになっていた。
軽やかなジャズとコーヒー豆の華やかな香りが広がる大きなコーヒーショップ。
カラッとして青空によく似合う爽やかな白いシャツを着た先輩が私を迎えた。
広々とした店内にはさまざまな本が所狭しと並べられていて、そのどれもが秀逸なセンスが光っていて、やっぱり希望の星はずるいと思ってしまう。
小説好きなお客さん、著名な作家も集うお店として、立派に賑わっている。今度大きなメディアにも掲載されるらしい。
「本当、なんでも手に入れちゃうんですね。」
「何を?」
「なんでもです。なあんでも。富も夢も名声も全部!」
「でもまだ手に入れられてないけど、文芸部の部長の彼女もいないしね。」
驚いて振り向くと、もう別のお客さんのところで接客を始めている。
こんなに待たせておいて、結局私を動かすんだもんなぁ。
本当に、ずるい人だ。
「先輩!こっちにもドリップコーヒーを1杯お願いします!」