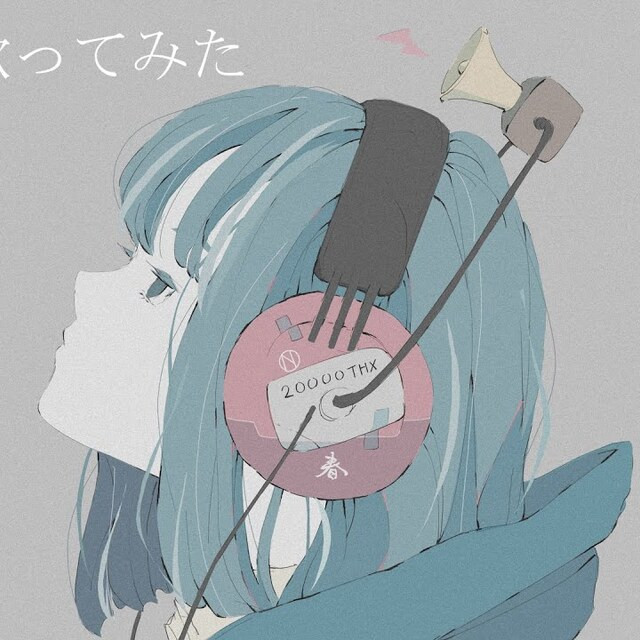第1話
文字数 3,815文字
私には、ずっと恋い焦がれている景色がある。
山道をやっとの思いでくぐりぬけ、私は車を路肩に停めて降り、大きく息を吐く。なかなかややこしい道だった上に、道がぐねぐねとしていたこともあり、しっかりと車酔いしてしまった。
水を一口含み、今まで自分の登ってきた道を眺める。
もうここまできたか、と思う。あれから十年近くの月日が流れた。あれ以来、あの村はどうなっているだろう。あの祭りはどうなっているだろう。――あの人はどうしているだろう。
また大きく息を吐く。
「行くか」
車酔いも心配だし、祖父から譲ってもらったこの軽自動車も山道を酷使して走らせたせいか、機嫌が悪い。状況はよくはない。
だがそれも、あの景色を目に収めるまでの辛抱だ。
私は山道を登るほうの車線へ、ハンドルをきった。
私があの景色に出会ったのは、小学校高学年の時の林間学校でのことだった。
就寝時刻が過ぎて騒いでいたのを当時の担任の先生に怒られ、私のグループのメンバーは、就寝時刻から一時間を過ぎたころには、皆ぐっすりと眠っていた。
そんななか私だけは、初めての友達との宿泊というのが緊張したのか、目が冴えてなかなか寝付けなかった。することもなく、暇で仕方ない。そこでふと、私は外に出てみようかな、と思った。
このまま寝るなんて面白くないというそれだけの理由だった。怖さよりも、夜の中を歩いてみたかったのと、それを同じグループのメンバーに自慢したいという気持ちがあっさり勝った。
私たちが泊まっていたのは一グループ一つのコテージだった。外に出たのを先生たちに見つかっても、外にあるトイレに行くところだ、と言えば、誤魔化せるだろう。
林間学校に行った季節は、初夏とはいえ、夜の空気はひんやりしていたし、怖さよりも好奇心が勝ったと言えど、やはり少しは怖かったのもあり、さっとトイレのあるコテージまで行って戻ってくるつもりだった。
私たちが泊まっていたのは山奥で、携帯も繋がらないようなところだった。もちろん、外灯などはついておらず、移動するときは、コテージに備え付けられた懐中電灯を使うよう言われていた。
さすがに懐中電灯を持たずに外に出る勇気はなく、それを持ちつつ、外へ出た。電源を入れ、あたりを照らしてみるも、何がどこにあるかがよくわからなかったので、私は昼間の記憶を頼りに、多分こっちだろうという方に進み始めた。
しかし、それは間違いで、私は全くの逆方向、山奥に向けて歩き始めていた。
五分ほど歩いたところで、さすがに自分が正しい方向に進んでいないことは分かった。だが、あたりは暗闇、懐中電灯で照らすが、あたりは木と草だけ。とりあえず進んでみることを決めた。民家の一つくらいは見つかるのではないかと思ったのだ。
そこからさらに十分ほど歩いた。辺りは暗闇のまま、進んできた道も道でなくなってきた。ここまでくると引き返すこともできず、私は地面に座り込み、ついに泣き出してしまった。
どのくらいの間そうしていたのかは分からない。結構長い間だったように思う。涙をぬぐいながら鼻をすすっていた。先生や、グループの人は気づいてくれただろうか、このまま気づかれなかったらどうしよう、私死んでしまうかもしれない、と、本気で思い始めたころ、
「何してんの?」
と、声がふってきた。
顔をあげると、そこには私の大して年が変わらないであろう、男の子の姿が見えた。怪我でもしたのか、頬に絆創膏が貼ってある。
「お前、誰? この辺のやつじゃないよな」
彼は、私に話しかけてきた。私は泣いていたから、ヒックヒックと言いながら大きく頷いた。
「で、一人で何してんの?」
男の子は私の顔を覗き込んでくる。私はヒックヒックと声をあげ、鼻水をすすりながら、迷子になったことを伝えた。どーすんのタイヘンじゃん! と男の子はひとしきり騒いだ後、言った。
「とりあえず、ばあちゃんとこ行こ。ばあちゃんこのへんに詳しいから、ほら」
男の子は私に手を差し出した。私がその手を取ると、私の歩くスピードに合わせて、男の子は歩いてくれた。
男の子は沈黙を紛らわすように、歩きながらいろんなことをしゃべってくれた。自分の家族のこと、友達のこと、自分の住んでいる村のこと、最近あった面白いできごとなんかを。そのおかげで、私は彼の過ごしている環境をほとんど把握できた。それらを語る男の子はとても楽しそうだった。人見知りなせいもあり、友達の少なかった私にとって、彼の過ごしている状況がうらやましかった。
そのなかで、彼は思い出したように言った。
「あ、そうだ! 今日はトクベツな日なんだぜ」
「トクベツ?」
私は泣くのも落ち着き、彼と普通に話していた。
「そう、トクベツ! 年に一度な、カミサマにお祈りする日があるんだ。なんか、ゴコクホ―ジョー? とかを祈るんだって! おれはその準備がめんどくさくて逃げてきたんだけど・・・・・・そろそろ準備が終わるころだと思うんだ! だからお前も見れるぞ!」
男の子はそういってニッと笑った。素敵な笑顔だった。
少し開けたところに出てきたところで、彼は歩くのをやめた。
「あれだ!」
と、男の子は指さした。
その先では、大きな、何百年もたっているであろう大木に、灯篭がつるされて、その灯篭一つ一つが光っていた。
なんて幻想的な風景だろう。
――まるで、灯篭の咲く樹を見ているようだ。
「すごいだろ?」
ときかれ、私は首がもげそうなくらい、大きく頷いた。
この素晴らしい光景は、いつまでも見ていられると思った。この景色を絶対に忘れないように、私は目を見開いて、灯篭の咲いている樹を見た。
心の底から、こんなにも感動したのは、いつまでもこの景色を見たいと思ったのは、初めてのことだった。
「ほんとは村の人のヒミツらしいんだけど、お前はトクベツな!」
そう言って、男の子はまた、ニッと笑った。私みたいなよそ者も包み込んでくれる無邪気な笑顔だった。その笑顔に惹かれなかったといえば嘘になる。
そしてその笑顔を今も忘れられないなど、重い女だと自分でも思う。
ここから先のことはよく覚えていない。村の人たちが私を見つけて、コテージまで連れて帰ってくれ、その後先生にこっぴどく叱られたと記憶している。
あれから十年近い月日が流れた。
今でも、私はあの景色を鮮明に思い出すことができる。
今でも、私はあの景色にとらわれ続けている。
キーッとブレーキが音を立てて、車がとまった。
降りると、そこにはあの日泊まったコテージが並んでいる。
「ふぅ」
息を吐く。心臓の鼓動が早まり、中々収まらない。もうすぐ、あの景色が見られるかもしれないという思いからだ。
「行こう」
もう一度息を吐いてから、私は小さな山道を進みはじめた。
どの道をどう進んだかなんて覚えていないから、適当に歩き始める。小一時間ほど、いろんな道とは言えない道を歩きまわり、やっと開けたところに出た。
それはいいものの、あの時と出てきた場所が違うのか、あの樹は見えなかった。
あたりを見渡すと、一軒の小さな家のようなものが見えた。あの日もこんな建物があったのかの記憶はない。きっと、素敵な村だったのだろうから灯篭の咲く樹しか見ていなかったのを、今頃少し後悔するが、遅い。
近寄って行ってみると、村役場、と掠れた墨でかかれているのを見つけた。
「すみません」
私は扉を押して入った。中には穏やかそうな、おばあさんが座っていた。
「若い人か、珍しいね。この村に何の御用だい?」
村の人のヒミツね、という言葉が頭をよぎり、言うかどうか少し迷ったが、この人しか今頼みの綱はない。
「あの、灯篭を飾る樹を探していて――」
私がそう言うと、おばあさんは、心なしか悲しそうな顔をして笑った。
「連れていってあげよう、ついておいで」
その樹にたどり着くまでの間に、おばあさんは私に話をしてくれた。
八年ほど前。今までと同じように灯篭の準備をしていたら、灯篭にともしていた灯が、樹に燃えうつり、大規模な山火事が起こってしまったこと。その山火事で、たくさんのひとが巻き込まれ、亡くなってしまったこと。小さな村だったこともあり、あまり大きなニュースにはならなかったこと。また、村の民家もほとんど焼けてしまい、皆、どんどんといなくなってしまったこと。人もいなくなり、樹もなくなり、灯篭を樹に咲かすことはできなくなってしまったこと。
「ここが、灯篭の樹があったとこだよ」
そう言われた場所に、あの日の面影は全くなかった。
燃えてしまい、幹も少ししか残っていない樹。
そして、その樹の下には、お墓が並んでいる。きっと、あの山火事で亡くなってしまった人のものだろう。そして、一つだけ小さな灯篭が灯っている。
「灯篭は死者の魂をしずめるためのものでもあるんだよ」
おばあさんは遠くを見つめて言った。村に住んでいる人は少ないというのに、お墓はどれも綺麗だった。――彼女もここで、何かを失くした一人なのかもしれなかった。
「あたしは役場へ帰るよ。一人なもんでね、この間に他の人が着たら大変だ。あんたも好きな時に帰りな」
そう言って、おばあさんはきた道を引きかえしていく。
おばあさんの気遣いが胸に深く沈む。
もう一度、私は並んだ墓を見渡した。
私は、あの男の子の名前を知らないのだった。
終
山道をやっとの思いでくぐりぬけ、私は車を路肩に停めて降り、大きく息を吐く。なかなかややこしい道だった上に、道がぐねぐねとしていたこともあり、しっかりと車酔いしてしまった。
水を一口含み、今まで自分の登ってきた道を眺める。
もうここまできたか、と思う。あれから十年近くの月日が流れた。あれ以来、あの村はどうなっているだろう。あの祭りはどうなっているだろう。――あの人はどうしているだろう。
また大きく息を吐く。
「行くか」
車酔いも心配だし、祖父から譲ってもらったこの軽自動車も山道を酷使して走らせたせいか、機嫌が悪い。状況はよくはない。
だがそれも、あの景色を目に収めるまでの辛抱だ。
私は山道を登るほうの車線へ、ハンドルをきった。
私があの景色に出会ったのは、小学校高学年の時の林間学校でのことだった。
就寝時刻が過ぎて騒いでいたのを当時の担任の先生に怒られ、私のグループのメンバーは、就寝時刻から一時間を過ぎたころには、皆ぐっすりと眠っていた。
そんななか私だけは、初めての友達との宿泊というのが緊張したのか、目が冴えてなかなか寝付けなかった。することもなく、暇で仕方ない。そこでふと、私は外に出てみようかな、と思った。
このまま寝るなんて面白くないというそれだけの理由だった。怖さよりも、夜の中を歩いてみたかったのと、それを同じグループのメンバーに自慢したいという気持ちがあっさり勝った。
私たちが泊まっていたのは一グループ一つのコテージだった。外に出たのを先生たちに見つかっても、外にあるトイレに行くところだ、と言えば、誤魔化せるだろう。
林間学校に行った季節は、初夏とはいえ、夜の空気はひんやりしていたし、怖さよりも好奇心が勝ったと言えど、やはり少しは怖かったのもあり、さっとトイレのあるコテージまで行って戻ってくるつもりだった。
私たちが泊まっていたのは山奥で、携帯も繋がらないようなところだった。もちろん、外灯などはついておらず、移動するときは、コテージに備え付けられた懐中電灯を使うよう言われていた。
さすがに懐中電灯を持たずに外に出る勇気はなく、それを持ちつつ、外へ出た。電源を入れ、あたりを照らしてみるも、何がどこにあるかがよくわからなかったので、私は昼間の記憶を頼りに、多分こっちだろうという方に進み始めた。
しかし、それは間違いで、私は全くの逆方向、山奥に向けて歩き始めていた。
五分ほど歩いたところで、さすがに自分が正しい方向に進んでいないことは分かった。だが、あたりは暗闇、懐中電灯で照らすが、あたりは木と草だけ。とりあえず進んでみることを決めた。民家の一つくらいは見つかるのではないかと思ったのだ。
そこからさらに十分ほど歩いた。辺りは暗闇のまま、進んできた道も道でなくなってきた。ここまでくると引き返すこともできず、私は地面に座り込み、ついに泣き出してしまった。
どのくらいの間そうしていたのかは分からない。結構長い間だったように思う。涙をぬぐいながら鼻をすすっていた。先生や、グループの人は気づいてくれただろうか、このまま気づかれなかったらどうしよう、私死んでしまうかもしれない、と、本気で思い始めたころ、
「何してんの?」
と、声がふってきた。
顔をあげると、そこには私の大して年が変わらないであろう、男の子の姿が見えた。怪我でもしたのか、頬に絆創膏が貼ってある。
「お前、誰? この辺のやつじゃないよな」
彼は、私に話しかけてきた。私は泣いていたから、ヒックヒックと言いながら大きく頷いた。
「で、一人で何してんの?」
男の子は私の顔を覗き込んでくる。私はヒックヒックと声をあげ、鼻水をすすりながら、迷子になったことを伝えた。どーすんのタイヘンじゃん! と男の子はひとしきり騒いだ後、言った。
「とりあえず、ばあちゃんとこ行こ。ばあちゃんこのへんに詳しいから、ほら」
男の子は私に手を差し出した。私がその手を取ると、私の歩くスピードに合わせて、男の子は歩いてくれた。
男の子は沈黙を紛らわすように、歩きながらいろんなことをしゃべってくれた。自分の家族のこと、友達のこと、自分の住んでいる村のこと、最近あった面白いできごとなんかを。そのおかげで、私は彼の過ごしている環境をほとんど把握できた。それらを語る男の子はとても楽しそうだった。人見知りなせいもあり、友達の少なかった私にとって、彼の過ごしている状況がうらやましかった。
そのなかで、彼は思い出したように言った。
「あ、そうだ! 今日はトクベツな日なんだぜ」
「トクベツ?」
私は泣くのも落ち着き、彼と普通に話していた。
「そう、トクベツ! 年に一度な、カミサマにお祈りする日があるんだ。なんか、ゴコクホ―ジョー? とかを祈るんだって! おれはその準備がめんどくさくて逃げてきたんだけど・・・・・・そろそろ準備が終わるころだと思うんだ! だからお前も見れるぞ!」
男の子はそういってニッと笑った。素敵な笑顔だった。
少し開けたところに出てきたところで、彼は歩くのをやめた。
「あれだ!」
と、男の子は指さした。
その先では、大きな、何百年もたっているであろう大木に、灯篭がつるされて、その灯篭一つ一つが光っていた。
なんて幻想的な風景だろう。
――まるで、灯篭の咲く樹を見ているようだ。
「すごいだろ?」
ときかれ、私は首がもげそうなくらい、大きく頷いた。
この素晴らしい光景は、いつまでも見ていられると思った。この景色を絶対に忘れないように、私は目を見開いて、灯篭の咲いている樹を見た。
心の底から、こんなにも感動したのは、いつまでもこの景色を見たいと思ったのは、初めてのことだった。
「ほんとは村の人のヒミツらしいんだけど、お前はトクベツな!」
そう言って、男の子はまた、ニッと笑った。私みたいなよそ者も包み込んでくれる無邪気な笑顔だった。その笑顔に惹かれなかったといえば嘘になる。
そしてその笑顔を今も忘れられないなど、重い女だと自分でも思う。
ここから先のことはよく覚えていない。村の人たちが私を見つけて、コテージまで連れて帰ってくれ、その後先生にこっぴどく叱られたと記憶している。
あれから十年近い月日が流れた。
今でも、私はあの景色を鮮明に思い出すことができる。
今でも、私はあの景色にとらわれ続けている。
キーッとブレーキが音を立てて、車がとまった。
降りると、そこにはあの日泊まったコテージが並んでいる。
「ふぅ」
息を吐く。心臓の鼓動が早まり、中々収まらない。もうすぐ、あの景色が見られるかもしれないという思いからだ。
「行こう」
もう一度息を吐いてから、私は小さな山道を進みはじめた。
どの道をどう進んだかなんて覚えていないから、適当に歩き始める。小一時間ほど、いろんな道とは言えない道を歩きまわり、やっと開けたところに出た。
それはいいものの、あの時と出てきた場所が違うのか、あの樹は見えなかった。
あたりを見渡すと、一軒の小さな家のようなものが見えた。あの日もこんな建物があったのかの記憶はない。きっと、素敵な村だったのだろうから灯篭の咲く樹しか見ていなかったのを、今頃少し後悔するが、遅い。
近寄って行ってみると、村役場、と掠れた墨でかかれているのを見つけた。
「すみません」
私は扉を押して入った。中には穏やかそうな、おばあさんが座っていた。
「若い人か、珍しいね。この村に何の御用だい?」
村の人のヒミツね、という言葉が頭をよぎり、言うかどうか少し迷ったが、この人しか今頼みの綱はない。
「あの、灯篭を飾る樹を探していて――」
私がそう言うと、おばあさんは、心なしか悲しそうな顔をして笑った。
「連れていってあげよう、ついておいで」
その樹にたどり着くまでの間に、おばあさんは私に話をしてくれた。
八年ほど前。今までと同じように灯篭の準備をしていたら、灯篭にともしていた灯が、樹に燃えうつり、大規模な山火事が起こってしまったこと。その山火事で、たくさんのひとが巻き込まれ、亡くなってしまったこと。小さな村だったこともあり、あまり大きなニュースにはならなかったこと。また、村の民家もほとんど焼けてしまい、皆、どんどんといなくなってしまったこと。人もいなくなり、樹もなくなり、灯篭を樹に咲かすことはできなくなってしまったこと。
「ここが、灯篭の樹があったとこだよ」
そう言われた場所に、あの日の面影は全くなかった。
燃えてしまい、幹も少ししか残っていない樹。
そして、その樹の下には、お墓が並んでいる。きっと、あの山火事で亡くなってしまった人のものだろう。そして、一つだけ小さな灯篭が灯っている。
「灯篭は死者の魂をしずめるためのものでもあるんだよ」
おばあさんは遠くを見つめて言った。村に住んでいる人は少ないというのに、お墓はどれも綺麗だった。――彼女もここで、何かを失くした一人なのかもしれなかった。
「あたしは役場へ帰るよ。一人なもんでね、この間に他の人が着たら大変だ。あんたも好きな時に帰りな」
そう言って、おばあさんはきた道を引きかえしていく。
おばあさんの気遣いが胸に深く沈む。
もう一度、私は並んだ墓を見渡した。
私は、あの男の子の名前を知らないのだった。
終