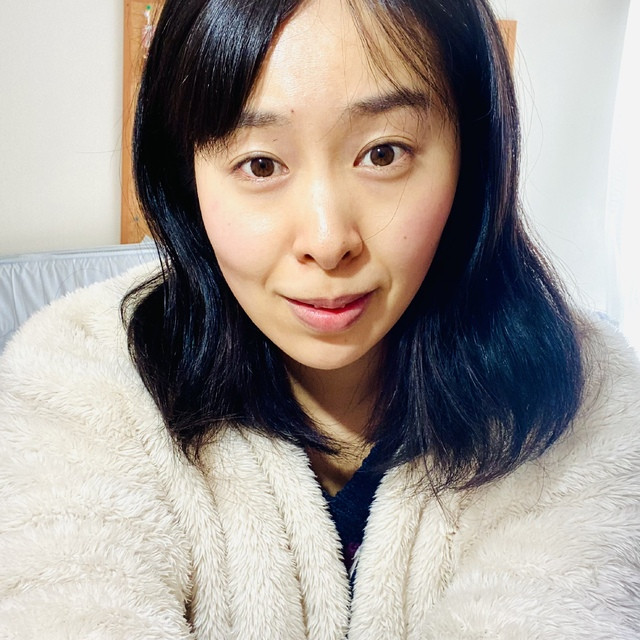第1話
文字数 23,385文字
Ball
「いらっしゃいませ。」
ロシアのコンビニでは、店員のセラフィム・アガファニコフがレジを売っていた。
「お願い。」
高級毛皮の女性が、レジに商品を置いた。
「780円です。」
「ふん。」
「こちら。」
セラフィムは袋に入れた商品を、女性の前に置いた。
「ちょっとぉ‥。」
女性は袋の中身を見て、顔をしかめた。
「なんで、ボールペンと食べ物を一緒に入れるのよ!!」
「え‥。」
「あんた名前は?」
とっさに、セラフィムは名札を手で隠した。
「見せなさいよ!!」
「ああ‥。」
「セラフィム・アガファニコフさんね。よく覚えておく。」
セラフィムは悲しくなり、少し赤くなった。
友達のヤコフ・ガルギナが、コンビニに入ってきた。
「大丈夫?」
「うん。」
セラフィムはついに涙をぬぐった。
中国広東省の刑務所で、ジエン・チョウと、シュエン・ソンは話していた。
「今日で終わりやな。」
「ええ。やっと出られますよ。11カ月は長かったですわ。」
「俺は10カ月やけど、もうすぐ死ぬ所やったわ。」
若い刑務官が来て、叫んだ。
「1105番!1104番!外へ出ろ。」
「いや、順番が逆やろう。」
「ついに死刑ですか。」
ジハンとシュエンがつぶやいた。
「いいから、早く出てこい!!今日でようやく外へ出られるぞ。」
2人が部屋から出ると、手を後ろにされ、手錠をされそうになった。
「おい、俺たちは今日で終わりやぞ。もういいやないか!!」
「まぁまぁ、兄さん。言う事、聞いておきましょうや。」
結局、2人は手錠をされずに済んだ。
釈放前に、2人は刑務官と面談しなければいけない。
シュエンは言った。
「ほんまに、反省しております。盗みをして、その店の店長を殴るなんて、悪い事をしました。家に帰ったらまず、母の肩をもむつもりです。」
シュエンは嘘笑いで刑務官に話した。
ジエンは泣きながら、刑務官と話した。
「いや、ヤクをやったくらいでね、10カ月も盗られましたわ。俺の10カ月を返してくださいよ。」
「いやいや、君はもう罪をつぐなってくれた。今日で釈放出来るよ。」
「この阿呆!ヤクをやったヤツを10カ月で出すんなら、殺人者も出してやれ!!」
ジエンが大声で言ったので、刑務官はひるんでしまった。
「あのな、殺人者を出したからって、また殺人するとは限らんやろうが。
世の中にはな、殺人者の因子なんて、ぎょうさんおるんや。信じられないほどにな!!」
結局2人は外に出た。
シュエンは両親、ジエンは従兄が迎えに来ていた。
ジエンは言った。
「シュエン、また会いましょうや。」
「はい。じゃ、兄貴これ。」
「ありがと。」
シュエンは、ジエンに連絡先の書かれたメモを渡した。
セラフィムの仕事の後、セラフィムとヤコフは、バルで話した。
このバルはなかなか安い。味はそこそこだし、飲み放題は700円だ。
ヤコフは酒を飲み、バルの中を少し見ながら言った。
「俺はまだ奨学金が残っている。」
「まだ返済を?」
「うん、そうだ。だから、全然貯金出来ていない。」
「そうかい。でも、僕もだよ。両親に毎月5万取られる。」
「ああ。お互い様だな。」
「うん。」
「こんばんは、お二人さん。」
「アルビナ。来ていたんだね。誰かと?」
セラフィムが言った。
「いえ、1人よ。」
「1人?バルに、28歳の女の人が1人で来るなんて。」
ヤコフが言った。
「そう?普通でしょう。」
セラフィムは言った。
「よければ、一緒に飲む?」
「いえ、結構よ。もう食べ終わって、帰る所だから。」
「ああ、そうかい‥。僕たちはまだ来たばかりだ。また一緒に‥。」
ヤコフは言った。
「ええ、ありがとう。さよなら。」
「またね。」
ヤコフは言った。
ヤコフは少し笑って、セラフィムを見た。
「好きなの?」
「別にそうじゃないよ。」
「じゃあ、そろそろ他の誰かと付き合えよ。」
「金があればな。」
セラフィムは照れ隠しに言った。
「愛にお金は関係ない。」
ブルル
ジエンの従兄の車が、ジエンの実家の団地に着いた。
「家についたな。しばらくゆっくりしたら?」
従兄のハオミンが言った。
「いや‥でも、働かないと、金に困るだろうし。」
「うん‥、ジエンはえらいな。」
「いや‥兄さんほどじゃないよ。」
ジエンはハオミンが好きだった。
もしもの時は、仕事を紹介してくれそうだ。
「ただいま。」
「兄ちゃん?」
「お母さん、兄ちゃんが帰ってきたよー!!」
2人の妹チェンシーとルーシーが顔を出した。
「あらあら、おかえりなさい。」
お母さんがエプロンで手を拭きながら出て来て、ジエンの手を握った。
「あ、うん。」
ジエンが台所に入ると、高校教師をしている父親が新聞を読んでいた。
「父ちゃん、帰ったで。」
「よく戻ってきてくれたな。」
「うん。」
妹2人が言った。
「兄ちゃん、バカだよねー。」
「麻薬はやっちゃいけないって、自分が言ったんじゃん。」
「ああ、すまんな。可愛い妹たちを、裏切ってしもうて。」
「きらい。」「兄ちゃん、やだ。」
お母さんは言った。
「仕方ないでしょう。」
「母ちゃん、今日の晩飯なに?」
ジエンは聞いた。
両親は目を合わせた。
「今日、家はからあげなんだけど、隣のムォンちゃんが、あんたにご飯を作ってくれたっていうのよ。」
「ええ?!」
「えええっ!」
妹たちも口を抑えた。
ムォン・ヨウは、28歳の聡明な女性で、家族と一緒に、隣の部屋に住んでいる。
「マジか、それ。」
「マジや。あのなぁ、やっぱり罪をつぐなってきたでな、良い事がおこるんや。」
父親が答えた。
「はああ。」
ジエンは軽くシャワーを浴び、髪を整えた。
隣の部屋のドアの前に立ち、軽く咳払いをした。
チャイムをちらりと見た。チャイムは汚れている。
あんなに美しくて綺麗な女性が、自分と同じ、汚くて古い団地に住んでいる事が、信じられない。
カチャ
ムォンはドアを開けた。
「あっ。」
「ジエンさん。来てくれたのね。嬉しいわ。」
「いやいや。今日はありがとな。わざわざ俺のために。」
「とんでもないことよ。さぁ、入って。」
「うん。」
ムォンは少し走って、おかってに向かった。
床にはぬいぐるみが置かれていて、チョウ家より綺麗だし、お洒落だ。
どことなく、太陽の香りがする。
ムォンのお父さんは大工で、お母さんは工場にパートに出ている。
お姉さんは、万里の長城でガイドをしているので、今は住んでいない。
「座って。水餃子を作ったの。」
「ああ、美味しそうや。今日、おばさんとおじさんは?」
「出かけているわ。パパが関わったお家が完成したので、今日はお祝いがあるの。」
「そうか。よかったな。」
「ええ。」
「美味い!!」
ジエンは音を立てて食べた。
「本当?よかった。」
ムォンも水餃子を女性らしく食べながら、微笑んだ。
ブルルル
高級車の中で、シュエンの母リンナが聞いた。
「酷いことされたでしょう?」
リンナは綺麗だ。
「いいえ。ジエン兄貴とも知り合いになれたし、貴重な11カ月でした。」
シュエンは答え、父ズォンが言った。
「だけど、店の店長を殴っただけで捕まるなんて、おかしいよ。」
「いえ、僕が悪いんです。仲間と一緒に店に押し入ったんです。」
リンナが聞いた。
「じゃあ、仲間はまだムショに?」
「ええ。奴らには前科がありましたから。僕にはなかったので、早く出られました。
お母さん、お父さん、僕を11兄弟の最後の養子に迎え、大切に育てていただき、ありがとうございました。」
シュエンが言うと、ズォンは運転をしながら、涙をこらえた。
リンナは言った。
「まだ孫家にいていいのよ。お前は大事な子だから。」
車は屋敷の前についた。
門番がドアを開く。
車は屋敷の敷地に入った。
家来がドラを鳴らし、玄関の前の廊下の両側に並んだメイド達が、手をついて挨拶をした。
「おかえりなさいませ、シュエン様!!」
「ありがとう、みんな。」
「宴の準備は出来ております。」
一番上のメイドが言った。
「いつもありがとう。」
ズォンは言った。
「さぁ、行きましょう。」
リンナはシュエンの肩にさわり、歩き出した。
広間につくと、兄妹達が勢ぞろいしていた。
孫家は11人の養子をとっている。
一番末がシュエンで、男と女が5人ずついた。
双子は男に一組、三つ子は女に一組いる。
宴は始まった。
双子の兄さん、イーヌォとユイルイが言った。
「お前が帰ってこなければ、よかった。」
「なぜだ?俺は兄さん達のことが好きだよ。」
「俺達はそうじゃないから。」
長女のイーイーが聞いた。
「シュエン、刑務所で、友達が出来たって本当?」
「はい、本当です。」
「気をつけなさいね。犯罪者は繰り返すものよ。」
「ジエン兄貴なら大丈夫です。ムショで俺にいい話をたくさんしてくれましたから。」
三つ子は笑いあっている。
次女のメイジィが言った。
「アンタさぁ、ちょっと痩せたんじゃない。」
「そうかな‥。」
長男のトンデルが言った。
「そうだよ、少し鍛えた方がいい。」
次男のヒューデルが言った。
「お前がいない間にな、男専用のトレーニングルームを作ったんだ。」
「風呂から出たら、やってみろ!」
三男のフロルが最後に言った。
ロシア‥アルビナは落ち込んでいた。
本当は帰る気分でなかったが、帰るしかない。
雪が残った道を、一歩一歩踏みしめて帰る。
両親もおばあちゃんも何も言ってこないが、家に帰るたびに、何か言われそうに思ってしまう。
アルビナはドアの前で目を閉じ、深呼吸した。
「ただいま。」
「あら。おかえりなさい。ご飯は?」
「食べた。」
「どうして元気がないの?」
「なんでもない!」
「もう‥。」
お母さんは最近傷つきやすい。
太って裕福そうなお父さんは、暖炉の前で心配した表情をした。
アルビナの家は、同じ家が並ぶ住宅街のうちの一軒で、貧乏ではないが、特別お金持ちというわけではなかった。
妹はモスクワに出たまま、帰ってこない。
アルビナはそれが辛かった。
「アルビナ、お風呂は?」
「もう少し待って。」
「分かった。」
「でも‥。」
アルビナはお風呂に入ることにした。
仕度をして、風呂から出た。
髪は少し濡れている。
「ゲームするか?」
お父さんが聞いた。
「いい。」
「ふん、そうか。」
アルビナは部屋で、お気に入りのテディベアを抱いて、考えた。
今日は失敗をした。友達に誘われて、イーゴルのバスケの練習を見に行ったのだ。
アルビナを誘った友達は、別の子と仲良く話しだしたし、なんとなくイーゴルの機嫌が悪くなって、アルビナ座っている壁の近くにボールを当てたのだ。
アルビナがよそ見をしているすきだった。
「ああ‥。」
「やめろよー。」
他のチームメイトが声をかけ、イーゴルは向こうに行ってしまった。
アルビナは立ち上がった。
「帰るの?」
誘った友達が聞いた。
「うん、もういいから。」
「えー。変なの。」
「うん、ごめんね。」
「いいよ。じゃあね。」
「じゃ。」
誘った友達の友達も、アルビナに微笑んだ。
アルビナは雪が舞う中、走って明るい場所に向かった。
「なんて馬鹿なことをしたのかしら。」
私服姿のイーゴルの姿が浮かび、アルビナは少し泣いてしまった。
イーゴルは黒髪で、ずっと好きだった相手だった。
28歳なのだから、イーゴルにも恋人くらいいるはずだ。
アルビナはテディベアを抱きしめた。
今この場で、テディベアを引き裂くことだって、自分の体を傷つけることだってできる。
でも、アルビナはしなかった。それは28歳の大人だからだ。
若い頃にそんな経験をするよりも、大人になってからの方が、良かったかもしれない。
それと、今、セラフィムは自分の部屋の鏡の前で、ブロンドをとかしながら、アルビナを想っていた。
「別にアルビナの事は好きじゃないけど、良い子だよな。」
セラフィムの給料は少ないが、少しだけいいアパートの上階に家族と住んでいて、
部屋には、昔の貴族が使っていたような鏡を置いていた。骨董市で見つけたのだ。
「はぁぁ、俺ってハンサムだよなぁ。」
セラフィムは左右に顔を動かし、決め顔をした。
「ん?」
セラフィムは後ろを向いた。
「何もないか。」
セラフィムは鏡に布をかけた。
時々、この鏡は怖いので、布をかけるようにしている。
この前、帰宅すると布が鏡から落ちていたので、怖くなった。
母さんが掃除をしたせいだ。
「母さん、勝手に掃除をするのはやめてくれ!」
セラフィムは怒った。
「ただいま。」
ジエンは家に戻った。
台所で両親は、うれしそうにお茶を飲んでいる。
「どうだった?」
「ああ、ムォンちゃんが、水餃子を作ってくれてなぁ。とても美味かったわ。」
「はは。よかったなぁ。」
「それでな、ムォンちゃんは、今、彼氏募集中なんやて。」
「えええ?!」
聞き耳を立てていた妹たちが部屋から顔を出した。
「ああ、もうお前達、うるさいわ。」
妹たちも台所に来た。
「お兄ちゃんがムォンちゃんと付き合うってこと?!」
「いや、まだ決まったことじゃないよ。俺はムショから出たばかりやし。」
お父さんが言った。
「でもな、やっぱり、罪をつぐなってきたから、良い事が起こるんや。」
「そうやな。親父、ありがとう。」
ムォンは夢を見ていた。
ムォンは離れて暮らしている祖父母からもらったお金を、北京の料理専門学校に通っているうちに、使いはたしてしまった。
ムォンのアパートは今よりも部屋は広いが、雑踏の中にあった。
ジエンのようなお兄もいないし、少しだけ治安が悪く、落書きだらけだ。
部屋の郵便受けに、借金の取り立て書が入っており、
ムォンは、寂しさもあいまって、大声で叫んで泣いてしまった。
「あああああ!あああああ!」
「え?」
1人の男が叫び声に気づいた。
ドンドン、ドンドン
「ムォン!大丈夫か!」
「え‥。」
ムォンは恥ずかしくなり、布団を上からかぶり電気を消し、その人が去るのを待った。
足音がしたので、ムォンはベランダから姿を確認すると、幼稚園の時に知り合いだったレフ・リーだった。
レフは北京のレストランで働いていた。
「レフ‥。」
レフは笑い、ムォンもレフに手を振った。
「でも‥。」
ムォンは、豆電球が飾り付けられた今の部屋の布団の上でゴロゴロした。
ムォンは思い出した。
「お母さん!!恥ずかしいからやめてよ!!」
ムォンが大声を出したので、まわりの人達がじろじろと見ている。
普段、北京でかっこつけていたのに、ダサいお母さんと一緒にいる所を見られたくなかった。
その場を、またレフに見られてしまった。
レフはムォンが好きだったので、心配して、よく見に行っていた。
「やっぱり、レフとは無理。」
ムォンは起き上がり、壁を見た。
壁の向こうの部屋では、ジエンが寝ている事を分かっていた。
ジエンはいびきをかいて寝ていた。
キキッ
「おはよう。」
ヤコフの自転車が、セラフィムの前で止まった。
「おはよっ。」
「仕事終わりか?」
「うん。昨日から夜番なんだ。」
「そう。俺は、今から仕事。マヨネーズ工場は退屈だが、楽でいい。」
「そうか。頑張って。」
「ありがとう。」
セラフィムとヤコフは握手をした。
家についたセラフィムは、昨日の晩御飯の残りを食べ、シャワーを浴び、眠りについた。
しばらくして、母親の声で目覚めた。
「ロディオン、よく帰ってきてくれたわね。子供たちは?」
「今日はいない。僕一人だ。」
セラフィムが見に行くと、兄のロディオンが来ていた。
「やぁ、ただいま。セラフィム。」
「兄さん。おかえり。」
コーヒーを飲みながら、母親のナナロが聞いた。
「なぜ、アンジェリーナと別れるの?あんなに可愛い子供たちがいるのに。」
「アンジェリーナは最初から、僕を愛していなかった。」
「そんなことないわ。2人の結婚式だって、あんなに楽しかったじゃない。」
「そうだよ、兄さん。彼女と別れるべきじゃない。」
「いや、別れるべきなんだ。2人の子供は、僕と、DNAが一致しなかったんだよ。」
「ええ?」
帰ろうとしながら、ロディオンが言った。
「もっと早く気づくべきだったんだ。」
「ダーリン、可哀想に。」
「母さん。」
2人はハグをかわし、セラフィムは少し泣き、背を向けた。
「ああ、兄さん。可哀想に。」
セラフィムはまた眠りについた。
ジエンは、ハオミンが働く工場に雇ってもらうことになった。
給料は安いが、ジエンが予想していたよりも、悪くなかった。
ハオミンは工場内を、あれこれ説明しながら、歩く。
「はぁぁ。」
ジエンは、大好きな兄貴の手前、しっかり働きたいと思っていたが、
こんな仕事では、毎日飽きるだろうと感じた。
夢がない。
「こちらは、勤続40年のチインさん。」
「はああ…。」
「よろしく。」
チインさんは、歯がかけていたが、ニッコリと笑った。
『こんな場所で、勤続40年か‥。バカだな。』
ハオミンはニコニコとして、あれこれ説明している。
『はああ。兄貴のために頑張りたいけど、俺はそんなに続けるのは無理だ。』
「辞めたくなったら、辞めていいからな。」
ハオミンは言った。ハオミンは街のオーケストラ団員で、登山を趣味にしている。
「いや、俺は‥、兄貴がいるこの工場で、働きたいです。」
ジエンは言った。
「そうか。」
ハオミンはにっこりと笑った。
「この毎日は退屈だからな、お前は何か趣味を持てばいい。
俺だって、オーケストラに入っているし、暇があれば登山に行っている。」
「はああ。」
ジエンは、ハオミンの優しさに少しぼんやりとしてしまった。
シュエンはしばらくの間、新聞配達をすることになった。
近所の人達はシュエンが来ると笑って、挨拶をし、シュエンも走りながら手を振ったりした。
夜。屋敷のトレーニングルームでは、双子のイーヌォとユイルイが空手の型の練習をしていた。
息はピッタリだ。
トンデルとヒューデルは背が高く、200センチくらいある。
フロウも190センチくらいあるが、低く見えてしまうくらいだ。
シュエンの身長は170センチくらい。
みんなトレーニングをしていた。
「シュエン、何かやってみろ。」
トンデルがシュエンに言った。
「何かって?」
「アクロバットだよ。」
「ええ‥。」
双子が手をこきこきさせ、こちらに来た。
この2人は何かと、シュエンに文句をつけたがる。
「でも、俺、前にやってみたけど、上手くいかなくて。」
シュエンは言った。
「ああ。アクロができないチビなど意味がない。」
「努力せずにあきらめるヤツは、カスだ。」
双子が言った。
「まぁまぁ。シュエンだって、あきらめているわけじゃないさ。」
ヒューデルが出てきた。
「ほら。」
フロウは簡単な技を見せた。
「だけど、こいつには無理だ。」
双子は言った。
「そんなことない。シュエン、やってみろよ。」
トンデルが言った。
双子以外の兄弟は、シュエンに期待をしていた。
アクロが出来るチビは、国宝とも言える。
「うん‥。」
セラフィムは午後6時に起きた。
高級毛皮の変な女性を思い浮かべた。
「うん。もしも、あの女性が来ても、優しくしてあげよう。
きっと、高級マンションに住みすぎて、普通の会社では、働けなくなった人だ。」
セラフィムはベッドから起き上がった。
ベッドは窓際に置いてある。
真冬は寒いので、窓もカーテンも二重にしてある。
晩御飯を食べ、「行ってきます。」
「おお、セラフィム。」
「こんばんは、父さん。行ってきます。」
「気をつけて。」
「はい。」
セラフィムは階段を降りた。
ふいに、昔のことを思い出した。
中学ではバレーをしていた。
中学でかなり背が高いヤツもいるが、身長がどうなるかなんて、まだ分からない。
その男のパパは、身長が200センチあった。
ママは小さい。
その男アデルは、自分は体育が出来ると思い込んでいた。
小中学校では、体育が出来る子だと、信じ込まない方がいい。
信じこんでいいのは、高校からだ。
セラフィムの方が、各段にバレーがうまかったが、アデルは、「下手だから。」と言った。
セラフィムの幼馴染ナアが、アデルのことが好きだったため、許してあげた。
アデルは、高校はスポーツ推薦でいけると思った。
でも、アデルの身長は伸びない。ママが小さいからかもしれない。
強豪校が声をかけたのは、セラフィムにだった。
セラフィムは遠慮した。
そして、アデルの第一希望高校を、念入りに調べ、アデルと別の高校に入学することに成功したのだ。
アデルが馬鹿にしていたヤツで、プロスポーツ選手になった者もいる。
アデルは焦ってしまった。心はまだ、自分は体育が出来る男の子だったからだ。
だから、子供時代は才能があると、信じない方がいい。
大人になって、自分に才能に気づくのがちょうどいいのだ。
スポーツの才能なら、高校でもいい。
「はああ。」
セラフィムは歩いて、コンビニに向かう。
ずっと勤める気はないが、近所の職場なので、ありがたい。
「いらっしゃいませ。」
セラフィムは顔を上げると、また、あの女の人が来ていた。
「ああ‥。」
セラフィムが笑うと、
「何よ!!」
女の人が突然コーヒーをセラフィムにかけた。
「ああ。」
「ちょっと‥。」
店長が奥から出て来て、女の人をなだめた。
女の人は怒って立って聞いていたが、店長に殴りかかったので、店長は警察を呼び、
女の人は、警察に連行された。
店長はコンビニに戻り、セラフィムに聞いた。
「大丈夫?」
「はい、すみません。」
「いや。アガファニコフ君が謝ることじゃないよ。」
店長はおでんを見て言った。
「ああ、こりゃダメだな。もうこれは、捨てようか?」
「はい。」
セラフィムはおでんを捨てるために、具を皿に盛った。
ジエンは部屋で座布団に座り、考えていた。
「これ、嘘かのぉ‥。」
シュエンのメモだ。
パソコンで調べると、大金持ちの家が出てくる。
ジエンは困った顔をした。
「困るのぉ。こんな大金持ちと関わるなんて、わし、嫌や!」
ムォンは、レフが広東省のレストランに転職したので、見に行っていた。
ムォンは大衆食堂で働いている。お父さんの大工仲間や弟子が来るので、とても楽しい。
ムォンは髪を七三分けにして、タートルネック、ミニスカートに黒のストッキングをはいて、お洒落をした。
レストランは一軒家で落ち着いた感じだ。
ムォンはうきうきして、肘を両サイドに振った。
「ムォン。」
「え‥。」
そこにいたのは、コック姿のレフだった。
「来てくれたの?」
「いえ‥。」
ムォンは恥ずかしくなり、答えられなかった。
ムォンは気が動転してしまい、歩いては、肘を両サイドに振った。
ジエンは、ベランダに立って、景色を見た。
綺麗とは言えないが、悪くない。
海が見えたらいいのにと、よく思う。
「あ‥ムォンちゃんや。」
「ムォンちゃーん‥ん?」
ムォンは、歩いては、肘を両サイドに振っている。
「なんか、うれしそうやな。よかった。」
ジエンはニッコリと笑った。
「まだ俺は、ムォンちゃんとつり合うような男じゃない。早く、一人前になりたいわ。」
シュエンは、アクロの練習をしていた。フロウは腕組みをして、見ている。
双子も様子を見に来ていて、シュエンが技に失敗して尻もちをついたところに、歩み寄った。
「お前、バカだなー。」
「不可能なことに時間をさくヤツは、落ちこぼれだ。」
「いいか?こうだ。」
フロウは分かりやすく説明しながら、ハンドスプリング等の簡単な技を見せた。
「俺も、雑技団ほどは、アクロはうまくない。でも、お前もきっとできるはずだよ。」
「うん‥。」
双子は言った。
「兄さん、でもこいつは、アホだから。」
「ドジでまぬけで、犯罪もしたし、勉強もできない。」
シュエンは下を向いた。
フロウは言った。
「でも、シュエンは足が速い。だからきっとアクロバットだって出来る。」
双子は顔を見合わせ、気に食わない感じにしている。
シュエンはまた少し落ち込んだ。
元気をもらうために、女子の部屋の方に行く事にした。
イーイーとメイズィは化粧鏡の前で、何かやっている。
シュエンは言った。
「ほぉぉ。男はトレーニング、女は化粧やな。」
メイズィは少し舌打ちをした。
「化粧じゃないわよ。今は保湿をしているの。」
「ふん‥。見た目は化粧やから、よくわからんわ。」
イーイーは言った。
「これはお化粧じゃないのよ。ほら。透明になるでしょう。」
イーイーは、白いクリームを、手の甲に塗ってみせた。
「あんた、なんで来たの?」
メイズィは聞いた。
「いや‥俺、兄さん達から勧められたアクロがうまくできなくて。姉さん達に会えば、元気でるかなと思って来たんだよ。」
「元気が出るですって?まさか、私達に興味があるってこと?」
「いやいや。お二人には、トンデル兄さんとヒューデル兄さんがいるということを、俺はよくわかっている。」
「ふん。」
イーイーは安心したように、リップクリームを塗り始めた。
メイズィは聞いた。
「じゃあ、あんたは、ラナデルレイに興味があるの?」
「いや、俺は、ラナデルレイにも興味はない。ただ、女と話せば、元気が出るかなと思っただけで‥。」
「ラナデルレイ、来なさい!!」
メイズィはシュエンの言葉を聞かずに、ラナデルレイを呼んだ。
「はーい。」
ラナデルレイは三つ子の名前だ。ラナ、デル、レイである。
「シュエン。」
「どうしてここに?」
「1人で来たの?」
「ええ、そうよ。」
イーイーが答えた。
ラナデルレイはニヤニヤと笑ってシュエンを見た。
3人は、孫家の養子兄妹同士で付き合うなら、イーヌォとユイルイの双子とシュエンだと思っていたのだ。
シュエンは11人の養子の末っ子だ。誰がシュエンと付き合うのか、よく話していた。
「どうしてここに?」
デルがもう一度聞いた。
「俺な、アクロがうまくできなくて、女と話せば、元気が出るかと思って来たんだよ。」
シュエンは答え、姉妹は笑った。
「分かった。俺はお前たちに興味はない。だからもう、行くわ。」
「もう行っちゃうのぉ?」
「ああ。」
シュエンは、棒をすべり、下に降りた。
下では、トンデルとヒューデルが待っていた。
「女部屋に行っていたのか?うらやましい。」
「ああ。ちょっと話しただけだよ。」
「俺達が行くと、すぐに母さんに疑われるから。」
「姉さんたちに本気なのか?」
「ああ。俺はイーイーとの子供がほしい。俺ももうすぐ36歳になってしまう。」
トンデルは言った。
「兄さんと姉さんなら、子供くらい、きっとすぐにできるさ。」
「どうかな。」
シュエンが言うと、トンデルはニヤニヤと笑って、首をかしげた。
ヤコフは、単調な仕事の休憩中に、白いテーブルの上にマーブルチョコを並べた。
それを1つずつ口に入れる。
顔は全身覆われているので見えないが、ヤコフの身長は高い。200センチあるが、ロシアではそんなの普通である。
日本なら、そんなヤツはすぐに正社員になれるが、ロシアではなれない。
ヤコフは、日本のバレーボールのチビを見て、口をへの字にした。
もしかしたら、日本でならうまくいくかもしれない。
でも、自分は白人だからきっと無理だ。
ヤコフは手で顔をおおった。
東京五輪は2年後にある。
なんとかして出たいものだ。そう思うと、ヤコフはニヤニヤとした。
事実を事実として受け止めると不可能に感じるが、まだ何が起こるか分からない。
時々、セラフィムや仲間たちとバレーボールをして遊んでいる。
次の予定は、日曜日だ。
マーブルチョコレートを食べ終えると、ヤコフは青いサプリメントを二粒、楕円のオレンジのサプリメントを一粒取り出し、テーブルに置いた。
なんとなく、顔を作ったりして遊ぶ。
派遣社員の親父が上からジロリと見たので、ヤコフはサプリメントを飲むのをやめた。
親父がどんな経歴の持ち主なのか、ヤコフは知らない。
親父はマヨネーズをパンにかけて、食べ始めた。うまそうだ。
ヤコフはにっこりと笑った。
ヤコフは高校の頃を思い出した。
背の高いセラフィムは、ミニスカートの女子を連れて階段を上がっている。
今日は、高校の行事で、プロのサッカー観戦にスタジアムに来た。
「ヤコフ。」
セラフィムはヤコフに声をかけた。
「やぁ、セラフィム。君は‥?」
「ナァよ。よろしくね。」
「まぁ、そうだな。友達の彼女なら‥。」
「彼女ってわけじゃないわ。」
「ああ。同じ班なんだよ。」
セラフィムとヤコフは別のクラスだ。
この後は、高校に戻ってバレーボール部の練習がある。
最初、先輩達は嫌な感じがしたが、優しくしてくれた。
ヤコフとセラフィムは、いつか、バレーボールのプロ選手になれる気がした。
だから、先輩には、「先輩はプロを目指さないんですか?」と必ず聞いた。
「うん‥、俺たちの高校からじゃ、無理っしょ。」
先輩は大体そう言う。
「でも、大学でもやったらどうでしょうか?」
「いや~、俺‥パイロットを目指したいんだよ。」
「ああ‥。」
ヤコフとセラフィムにとっては、パイロットの方が狭き門だった。
勉強もしっかりしていたので、目がだんだん見えなくなっていた。
裸眼にこだわったせいだ。友人のイーゴルは、裸眼でもいけるくせに、中学生のころから勉強する時は時々眼鏡をかけていたので、視力がとても良い。
でも、さすがのイーゴルも、現在では視力が少し落ちた。
イーゴルにとっては、大変な異常事態だった。
ヤコフとセラフィムは、大学に行かなかった。
モスクワのアマチュアチームに入ってバレーボールをした。
でも、だんだんと、まわりに差をつけられた気がした。
イーゴルはモスクワ大学のバスケットボールチームでプレーしていたし、自分たちには将来性がないように感じたが、イーゴルはプロになれなかった。
28歳のヤコフは、休憩室でため息をついた。
親父になって派遣社員をやるのは、大変そうだ。
だから偉いのか?分からない。
ヤコフには、好きだった子いる。レレイのブログを読んだ。
レレイはとても可愛い。レレイは一度変な男と結婚したが、離婚した。
その時は頭にきて、レレイのことを嫌いにもなったが、
今は許している。まだ付き合ってはいないが、仕事がもう少しうまくいったら、
好きだという気持ちを伝えたいと思っている。
「ううっ。」
シュエンは、アクロの練習中、腰をうった。
「大丈夫か!?」
双子は、シュエンの下にかけよった。
「無理なら、もうやめろ。」
「うん。」
フロウに向かって、シュエンは言った。
「兄さん、俺、もう無理やわ。」
「わかった。別のスポーツをやろう。」
フロウは提案した。
「別のスポーツってなんだい?」
「バレーボールさ。お前はバレーボール部だっただろう?それに、昔はよく、兄妹みんなでバレーボールをしたじゃないか。」
「海南島でのビーチバレー!」
「ああ、そうだ。」
双子はバレーボールを撃つ真似をして、ジャンプをした。
ちょうど男は6人いるので、3対3になる。
女子5人は、その姿を見守った。
トンデルがサーブをして、試合が始まった。
それはボールがなかなか床に落ちない、面白い試合だった。
体育館に社会人チームが入ってきた。パパさんバレーってやつだ。
「あれ?」
「すみません、ここ使いますか?」
「いえ、こちらのコートを使いますから。」
「そうですか。よかった。」
パパさんバレーチームの練習はハードそうなものだった。
兄弟はまた、試合を始めた。
「ふーん。」
パパさんチームのキャプテンはこちらを見た。
「よければ、一緒にやりませんか?」
「え‥。」
妹たちは、『やりなさいよ。』手で合図したので、兄弟は、一緒にやらせてもらうことにした。
やっぱり、パパさんチームと兄弟では、速さが違っていた。
一番うまいトンデルでさえ、遅れてしまう。
キャプテンは言った。
「大丈夫さ。すぐに慣れる。」
「はい。」
「よければ、君たちは、僕らのチームに入らないか?」
「ええ、いいんですか?」
夜、向き合ったソファーで、6人の兄弟は話した。
「よかったなぁ、良い人達に出会えてさ。」
「うん。父さんも、金を出してくれるっていうから、ちょうどいいよ。」
トンデルとヒューデルが言った。
「予想外の展開だ。」「こわいくらいに。」
双子も言った。
シュエンは、刑務所でのジエンとの会話を思い出した。
『兄さん、なにかスポーツをやっていましたか?』
『俺?俺は、バリーをやっていたよ。』
『バリー?』
『バリーボールさ。』
シュエンは言った。
「兄さん、俺、友達を誘ってもいい?」
「ああ、いいよ。ちなみに、誰だ?」
「刑務所で出会った人だよ。俺に、一寸法師の話をしてくれた。」
「一寸法師?」
フロウは聞いた。
「あのな、昔々ある所に、おじいさんとおばあさんがおった。
それでな、60歳になって、ようやく子供が生まれたんや。
でも、生まれてきた子供は、大人の小指ほどの大きさしかなかったんや。」
「ああ‥。両親が、年だったからやな。」
「うん。それでな、おじいさんとおばあさんは、その子を一寸法師と名付けたんや。
大切に育てたけど、何年たっても、大きくならんかった。
でも、気はしっかりしたいい男になってな、都でサムライになると言い出したんや。
おじいさんとおばあさんはもちろん止めた。でも、聞かんのでな、仕方なく、
針の刀とお椀の船を用意して、息子を送り出したんや。」
「それでな、都で大臣に気に入られて、大臣の一人娘の春姫に仕えることになったんや。」
「はぁぁ。男なのに、姫の世話をすることになったんやな。」
「そうや。それである日な、赤鬼が現れて、春姫がさらわれそうになったんや。
一寸法師は、針の刀で一生懸命に戦ったんやけど、赤鬼に食われてしまったんや。
でも、一寸法師はな、赤鬼の腹の中を、針の刀でつつきまわして、ついに、赤鬼を倒したんや。」
「ああ~。」
「一度負けても、それで終わりやないっていう話やな。」
「そうや。その後にな、赤鬼は逃げたんやけど、打ち出の小槌を忘れていったんや。
それが魔法の小槌でな、一寸法師の体を、大きくしてくれたんや。」
「はああ。」
「いい話や。」
「お前にピッタリの話だな。」
「な、いい話やろう?兄貴は他にもたくさんいい話をしてくれたんや。」
「ふーん。俺たちもその兄貴と仲良くなれるんかいな。」
「仲良くなれるに決まっている!」
ジエンは会社から家に戻った。家に戻るのは7時くらいである。
「おかえり、ご飯、ちょっと待ってね。」
「ジエン、医師会から封筒がきてたぞ。」
「医師会から?」
ジエンは、父親から封筒を受け取った。
「なんだろう‥。ああ、免許の更新やて。」
「更新しておけ。きっと、いつか使う日がくる。」
「そうやな。今はムショから出たばかりやけん。また何年かしたら、病院で働きたいわ。」
「あんたが、医師免許証を持っているなんて、嘘みたいやねぇ。」
お母さんが言った。
「医師くらい、簡単になれましたわ。」
「まぁ‥そうやなぁ。」
父親も面白そうにジエンを見た。
ジエンは、医師免許を持っている。
中学でジエンはバスケ部だった。
それは、ムォンがバスケ部だったからである。
ムォンとは関わらないようにしていたが、同じ中学に通っていた。
ムォンはバスケを一生懸命にやるが、とても下手くそだった。
「ふん、くぁわいい。」
中学生のジエンは、ニヤニヤしてムォンを見た。
ジエンはバスケの試合で疲れてくると、時々、足が痛いフリをした。
「え‥どうしよう。俺、準備してねぇよ。」
まだそこまで強くない部員は、不安そうにジャージを脱いだ。
「だ‥大丈夫だ。敵がいない場所にいって、はいと言えば、ボールを回してもらえる。
狙えそうなら、シュートしろ。」
「わ、わかった。」
そのおかげで、中学はとても楽しかった。
ジエンは、ムォンと同じ高校に行くことにした。
ジエンは頭がよかったので、実際の実力より下の学校に行く事になったが、気にしなかった。
ムォンの隣の家に住み、小中高と同じ学校に通ったのに、ムォンについては、知らない事がたくさんある。
高1の春の、部活見学では、バスケ部も見学したが、
「俺、もうバスケはいいわ。」
ジエンはボールを落としてしまった。
野球部もサッカー部も見た。でも、先輩が大人っぽいので嫌だった。
なので、先輩が一番弱そうで優しそうだったバレーボール部を選ぶことにした。
やってみると、バレーボールは難しかった。
ひょろひょろと思えた先輩に、尊敬のまなざしを向けてしまった。
先輩は丁寧に教えてくれて、ジエンはバスケより、バレーボールが好きになった。
ジエンは、優しい先輩に、おかしな事を聞いてみた。
「先輩、ボールってなんやと思います?」
優しくて、大人びた先輩は、少し笑って答えた。
「何?普通に、遊ぶものだと思うけど。」
「ふーん。なら、先輩、プロになれますわ。」
「プロ‥?いや、なんないよ。俺は。」
優しくて大人びた先輩は笑ったが、大学で活躍したので、何度か、テレビのバレーボールの試合に出た。
今は、高校の先生になっているらしい。きっといい先生だ。
ジエンは医学部に進学した。
本気でスポーツをしていたヤツらは、そんな学力はない。
嫌な視線を向けてきたが、ジエンは気にしなかった。
「だって俺は、高校時代、雑誌にも、テレビにも、ネットにも、出なかったんだぞ。」
ジエンは言った。それは大切なことである。
「それにな、デートもしなかったんや。でも、エッチはした。」
「誰とや?」
「言えない。」
ジエンは赤くなった。
夜、ジエンは布団に仰向けになり、イヤホンをつけ、ジャズを聴く。
枕元に置いた医学誌をパラパラとめくったり、ゲームをしたりする。
たわいのない時間である。真っ暗にして、目を閉じ、宇宙に行くのもいい。
プルルル
「はい。‥ああ~、ちょっと待ってね。」
「ジエン、シュエンさんという人から電話。」
「ええ?」
「もしもし?」
「兄貴。俺です。シュエンですわ。」
「ああ~久しぶりやな。ごめんな、連絡できなくて。」
「いや、いいんですよ。」
「久しぶりに声聞けてうれしいわ。」
「俺もです。ところで、兄貴、また会いませんか?俺ね、兄弟たちと一緒に、パパさんバレーボールチームに入ったんですわ。よければ、兄貴も一緒にどうですか?」
「おお、わかった。いいよ。」
「よかった。兄貴は医者だと聞いていたので、忙しいかと心配していたんですよ。」
「俺は、仕事以外は暇やで。」
さっそく、土曜日に、チームの練習に参加することになった。
「うう‥。」
セラフィムは、あの夜のコーヒー事件を思い出して、家で泣いた。
「大丈夫か?」
お父さんはセラフィムの前にコーヒーを出した。
「コーヒーなんかいらない。」
「飲みなさい。コーヒーは体にいいから。」
お父さんはセラフィムの前に座った。
「いいか。良い方向に変化する時、人間は必ず泣くものだ。」
「なぜそんな事が言える?」
「経験だよ。父さんにもそんな事が昔、何度かあったんだ。
人は、何度も涙を流して、良い人間になっていく。」
「涙は体にいいのか?」
「悪いとは聞いた事がないな。それに、泣いた後の顔は、老けては見えないだろう?
きっと、涙には若返りの効果があるんだ。」
「ああ‥。」
セラフィムは、自分の部屋の鏡で、自分の顔をまじまじと見た。
「でも、やっぱり泣ける。」
セラフィムはまた泣いてしまった。
少し眠ることにした。
午後3時。曇りだった空は晴れていた。
ピンポーン
チャイムの少し前に目覚めていた。時々、自分は、タイミングがいいなと思う。
きっと神様への信仰心のおかげだ。
「あら、ナァちゃん。」
「こんにちは。あの‥セラフィムは?」
「今ね、寝ているの。起こしましょうか‥。」
「なんだい?」
セラフィムは起きて、玄関に向かった。
「ナァ。なんの用?」
「ああ‥。この前、コンビニで大変な目に遭ったって聞いたから。これ‥。」
ナァは小さな紙袋を渡した。
「なんだいこれ?」
「私、今、パティスリーで働いていてこで売っているものなの。」
「そうか。ありがとう。」
「いいの。」
ナァはニコニコと笑い、母親はナァを家に入れるように合図をした。
「あの、よかったら上がる?」
「うん。」
「お邪魔します。」
セラフィムはリビングに入れようとしたが、母親は慌てて合図をしたので、自分の部屋に入れた。
「そこに、かけていいよ。」
「ありがとう。綺麗にしているのね。」
ナァはデスクの椅子に座り、セラフィムはベッドに座った。
「それは‥?」
「ああ。鏡さ。」
セラフィムは布をとった。
「まぁ、素敵な鏡。」
「骨董市で見つけたんだよ。」
「きっといい物だわ。」
母親が紅茶を淹れてきた。
クッキーも添えてある。
「ごめんね、ナァちゃん。こんなもので‥。」
「いえ。お気遣いいただきありがとうございます。」
母親がだしたのは、コンビニの袋のクッキーだ。
「あとで、セラフィムがナァちゃんのクッキーを食べますからね。」
「はい、ありがとうございます。」
母親は出て行った。
「お母さん、優しいのね。」
「うん。でも、時々やかましいんだ。」
「その方がいいわよ。私のお母さん、最近、すごく元気がないの。」
「ああ‥。」
「きっと年のせいだわ。それに、兄さんと姉さんが、どちらも離婚したの。信じられる?」
「ああ‥。2人とも、パートナーとあんなに仲が良かったから、信じられないな。」
「私も。何があったのか気になっちゃう。」
ナァは紅茶を飲んだ。
「俺の兄貴も離婚するって。」
「どうして?」
「子供と血がつながってなかったんだ。」
「なんてこと。あっちでもこっちでも離婚ね。一度も結婚していないのは、幸いだったわ。」
「ナァは彼氏がいるの?」
「いないの。だから、会いに来たのよ。」
ナァはにっこりと笑った。
「ええ‥?」
「セラフィムとは幼馴染だし、気も会うわ。お互い好きになれるかもしれない。」
「いや、突然そんなこと、できるわけないだろ。」
セラフィムは赤くなった。
「今すぐじゃなくていいの。」
ナァは上品にニッコリと笑った。
仕事に出かけるアルビナに、母親が声をかけた。
「今日、ララビが帰ってくるからね。」
「ええ、ララビが?」
「そう。」
「はぁ‥。」
アルビナはお金がなくて、家を出られないのに、ララビは親からお金をもらい、モスクワで暮らしている。
おばあちゃんにボケてきているので、嫌みたいだ。
夕方、アルビナは家に戻った。
「ただいま。」
「お姉ちゃん、おかえり。」
「うん。」
ララビは少し太ったようだ。
お父さんがララビに言った。
「ララビ、明日、晴れたら一緒にフリスビーするか?」
「いいわよ。パパとフリスビーなんて、何年ぶりかしら?」
「お姉ちゃんもやるー?」
「いい。」
ララビはぺらぺらと一人暮らしのことを話している。
アルビナは腹がたってきてしまった。
「ふん。」
Facebookを開く。
Facebookではいろいろあったが、経験を積んで、慣れてきた。
あまり更新はしないが、時々通知があるので、見て、楽しんでいる。
一件のメッセージが入っている。
『この前はごめん。』
「え?」
「イーゴルからだ‥。」
『今度、セラフィムたちとバレーボールをするから、見に来ない?』
写真が貼られているので、嘘ではなさそうだ。
「ええ。行ってもいいなら。」
『ありがとう(‘ω’)ノ』
アルビナはニッコリした。
土曜日、アルビナは本当に体育館に行ってみた。
イーゴルはアルビナを見つけ、大きく手を振ってきたので、アルビナも可愛く手を振った。
セラフィムとヤコフもこちらを見て、笑った。
アルビナの下に、金髪の女の子が寄ってきた。ちなみにアルビナの髪の毛は、茶髪とブロンドが混ざったような色で、とても綺麗である。
女の子は言った。
「こんにちは。この中の誰かと知り合いですか?」
「イーゴル。セラフィムとヤコフも、高校の時の知り合いよ。」
「そうでしたか。私はセラフィムと幼馴染なんです。」
「幼馴染?なんて素敵なの。」
「はい‥。」
「私の名前はアルビナ。あなたの名前は?」
「ナァです。」
「よろしくね。」
「よろしくお願いします。」
イーゴルが本気を出し、ついにリベロのヤコフは取れなかった。
「すごいな‥。」
ヤコフは言った。
「これくらい普通だよ。」
イーゴルはバレーボールを指でくるくると回した。
ガラガラガラッ
みんなが振り向いた。
そこにいたのは、ヤコフの叔母で歌手のリリオネット・アディオラである。
「おばさん!」
ヤコフが言った。
「私のことは、オバサンと呼ぶなと何度言ったら分かるの?」
「すみません‥。」
「ふん。あんた達、次の試合に出なさい。スポンサーなら、私がなんとかする。」
「試合に?」
「オリンピックを目指すの。」
観客席にいたアルビナ達も、心配そうに見た。
「オリンピックを?今からじゃ、無理に決まっている。」
セラフィムが言い、他のメンバーは下を向いたりした。
「この写真を見て。」
リリオネットが見せたのは、ロシア代表のキャプテンが、体育館で、四つん這いになり、ゲロをしている写真だった。
「ええ‥なんだ、これ。」
「覚せい剤が原因よ。奴らはそれを、シロップと呼んで、楽しんでいるわ。」
「だけど、吐いている写真を見て、楽しそうとは言えないな。」
マイティが言った。
「もうこいつに、感覚はないわ。」
「だけど、僕たちには仕事があるから、あまり練習の時間がとれないんです。」
「大事なのは、練習量じゃないわ。練習の質よ。」
「そうか‥。」
リリオネットはイーゴルに言った。
「それから、あなたも、チームに入りなさい。」
「ええ、俺も?」
「あなたのような男は、チームに必要だわ。」
アルビナ達も、観客席から見守った。
「最後に、私の歌を聴きなさい。」
リリオネットはロシア民謡を歌って帰って行った。
日曜日。
「うわぁ‥。でかい。」
孫家についたジエンは見上げてしまった。
「兄貴や。」
屋敷の上階から望遠鏡でジエンの姿を見つけたシュエンは、下に降りた。
ジエンの前に、トンデルとヒューデルが現れたので、ジエンは会釈をした。
「兄貴!」
「シュエン。久しぶりやな!」
「はい。兄貴、お元気でしたか?」
「おお、俺は元気やったぞ。」
「兄貴、こちらが俺の兄弟です。」
「トンデルです。」「ヒューデルです。」
「ああ‥。」
いつのまにか、シュエンのファミリーが勢ぞろいしていた。
「俺は孫家に迎えられた11人の養子の末息子なんですよ。」
「お前、そうやったんか!」
「はい。」
「ジエンさん、ムショでシュエンに好くして頂いて、ほんまにありがとうございました。」
「シュエンが改心できたのは、ジエンさんのおかげです。」
両親がジエンに礼を言った。
「いえ、俺の方こそ、シュエンに助けられましたわ。とてもいい息子さんで。」
「あはは、ありがとうございますぅ。」
両親は笑った。
「兄貴、さっそく行きましょうや。」
黒いロールスロイスのそばで、シュエンが声をかけた。
妹たちが見送りをし、ジエンは赤くなってしまった。
「あ、シートベルトを‥。」
「いいんや。シートベルトなんか必要ない。」
イーヌォが言った。
「え、でも‥。」
「今日はロールスロイスやけん。心配するな。」
ユイルイも言った。
シュエンは兄弟を説明した。
「トンデル兄さん、ヒューデル兄さん、フロウ兄さん、イーヌォ、ユイルイだ。」
「よろしく。」
フロウは言った。
シュエンはまた言った。
「トンデル、ヒューデル、フロウ、イーヌォ、ユイルイ。」
「よしっ、もう覚えたわ。」
ジエンは言った。
「ああ~覚えがいい~。」
兄弟たちはニヤニヤと笑った。
「兄さんたち、聞いてくれ。ジエン兄貴はな、医者なんや。」
「へええ、医者?」
「はい。一応、医師免許をとりましたわ。」
「はは、すごい。俺なんか、35歳でようやく弁護士になれたというのに。」
トンデルが言った。
「弁護士?すごいじゃないですか。」
「全然すごくないよ。ここ3人はみんな弁護士なんだ。」
「うわぁ、何それ!」
「兄貴に習って、俺も34歳で弁護士になりましたわ。」
「やってみれば、簡単でしたよ。」
ヒューデルとフロウも言った。
トンデルとヒューデルが言った。
「まだシュエンだけが、何の資格も持っていないんです。」
「今は新聞配達をしておりますわ。」
「そうなんか?」
「そうなんや。俺は勉強が苦手で‥。」
「じゃあ、バレーを頑張るしかないな。」
「よしっ、いくぞー!」
ジエンはサーブをした。
さっき話し合って、ポジションを決めた。
シュエンはリベロだ。
ジエンはかなりうまくて、シュエンはなかなか取れなかった。
そのうちに、パパさんチームの奴らが来た。
キャプテンの名前は、ランウィー・ハンという。
「今日は、知り合いのジエン兄貴を連れてきました。」
「お、頼もしい。」
ランウィーは笑った。
ジエンは言った。
「よろしくお願いします。」
「こちらこそ、よろしく。」
2人は握手をした。
「さっそくなんだけど、来週もう、チームで試合に出ようと思います。」
「ええ~!!」
「わかった。じゃあ、今日本気で練習しような。」
トンデルが言った。
「おおう!!」
休憩時間、ジエンとシュエンは、マネージャーをしているヨシフに聞いた。
「ところで、君は、マネージャーでいいんか?」
「はい。今まで日本にいたので、バレーボールから離れていたんですよ。」
「日本に?」
「食品工場の研修です。でも、あまりためになりませんでした。古い工場でコキ使われただけです。何も教わっていない。」
「そうか‥、大変だったんですねぇ。」
「僕たちは刑務所に入っていたんです。」
「刑務所に?」
「はい。とても軽い罪でしたけどね。バレーボールの試合に出られれば、ばん回できます。」
午後の練習は、念のため、ヨシフも参加した。
みんな素質があったので、ランウィーの速さにもすぐに慣れた。
ロシア‥
セラフィムはバレーボールに本気になり、未来が明るくなってきたと感じていた。
水曜日。セラフィムはナァと会うことになっていた。
約束のスタバの前で待っていると、ナァが来た。
「こんにちは。」
ナァはとても可愛い。
2人はスタバに入り、それぞれ飲み物を買った。
ナァが買ったのは、フラペチーノだ。
「なんだい、それ。」
セラフィムは聞いた。
「フラペチーノよ。わからない?とても甘くておいしいの。」
「ふーん、そうか。僕はカプチーノだ。甘い物は控えている。」
「甘い物は、頭の栄養になるらしいわよ。」
「そうなんだ。」
2人は少し黙った。
ナァはニヤニヤと笑った。
「どうしたの?」
「なんでもないわ。‥バレーボールのユニフォームって、どうしてあんなに短いのかしら?」
「多分、サポーターをつけるからじゃないか?」
「ふん。スポーツ選手は露出が多すぎるわ。だから、嫌われるのよ。」
「ええ、俺達が、嫌われているの?」
「あなた達のことじゃないわ。」
ナァは笑った。
ナァの顔には、少しだけ大きなシミがある。
セラフィムは聞いた。
「君って今までに、悲しいことあった?」
「まぁ、いろいろとあったわよ。もう28歳ですもの。28歳って、仕事がうまくいかなくなる時期だわ。」
「そうなのか?」
「ええ。でもそれを経験して、強くなるんじゃないかしら。
‥年齢に合わせて、周りの人から見たら、カッコいい事を選んでやっていくべきだわ。」
「そうなんだ。」
「うん。」
「27歳の頃は、血気盛んだった。」
「血気盛ん?」
「そうよ。あなたはちがったの?」
「いや‥俺は特に何もなかった。」
「かわいそうに。でも、人生はこれからだわ。友達のベルもエイズなのよ。でも頑張って生きているの。」
「ええ?エイズ?君もエイズなのか?」
「いえ、私はちがうわ。神様のお導きのおかげでね。」
「はああ。」
セラフィムは赤くなった。もしもナァがエイズなら、本気で将来のことを考えなければいけない所だったからだ。エイズにはならない方がいい。
日曜日。ジエンたちは試合の日だ。
孫家のロールスロイスが、孫家のメンバーを乗せてきた。
ジエンは親父の車で来ていた。
社会人チームのメンバーたちも笑って、手を振った。
ランウィーは言った。
「最初から、ヤバい奴らが相手だ。中でも、エースのゴルゴは、北京一の荒くれ者と呼ばれている。」
「ええ~‥大丈夫ですかいな。」
「僕たちならきっと大丈夫だ。ヤツの武器である、炎のアタックとドラゴンのスパイクを抑えれば、負けることはないだろう。シュエン、君にかかえっている。」
ランウィーが言い、みんなシュエンを見た。
「できるな?」
「がんばります。」
もうすぐ試合が始まる時、他のメンバーは緊張して、目を閉じたりしている中、シュエンは全く緊張していなかった。
試合の前、緊張しすぎるのもよくないが、全く緊張しないのはよくない。
少しだけ緊張しているジエンに、シュエンが声をかけた。
「兄貴、何かいい話、聞かせてくださいよ。」
「話?うーん、何かあったかのぉ‥。あ、あの話がある!」
「ええっ。」
シュエンは目を輝かせた。
「何年か前のことや。日本に、天才リベロと呼ばれた、身長153センチの女子選手がおったそうや。」
「うん‥。」
「その人は、どんな強くて速い球でも、落とさなかった。みんな最初は、すごいと言うたんやけどな、だんだん、それがうっとうしく思えてきてしまったんや。」
「ええ‥。」
「あんまりできすぎるのはよくない。だいたい、身長153センチというのは、普通はバレーボールのトップの世界には入っちゃいけない身長なんや。」
「でも、なぜ、そんなに強かったんですか?」
「強制避妊手術だよ。なぜかその子は、それを受けとった。子供が産めないことが悔しくて、強くなったんやな。」
「強制避妊手術‥?」
「日本で昔、行われていたんや。」
「ああ‥。」
「その子は女子の球なら大体とれる。ある日、男子から、勝負の声がかかったんや。」
「男子選手から‥?」
「そうや。それでな、その子はその日、生理でな、全然球がとれなかった。」
「ええ‥。」
「でな、本気になった男のバレーボールでな、腕を骨折してしまったんや。」
「医者の話によるとな、その子の腕はもうダメやということやった。もうリベロに戻れん。」
シュエンは下を向いた。
「最後にその子は、変な男と付き合ってしまってな、崖から落とされて殺されたんや。」
「そんな。」
「栄光と名声にしか興味がない男と付き合ってしまった仇ってもんやな。」
「かわいそうに。」
シュエンは泣いた。
「どうや?少しは緊張できたか?」
ジエンは聞いた。
「うん。」
ジエンはシュエンの腕をさわり、言った。
「シュエンの腕なら、どんなに速いバレーボールが当たっても大丈夫や。俺は医者やから、保証する。」
「今までお前が、両親と兄弟から大事にされてきたおかげやと思う。」
ジエンは言った。
「そろそろ円陣を組もうか。」
トンデルが言った。
「おお。」
「行くぞ!!」
「おおす!!」
シュエンは、ゴルゴの強い球をとったが、僅差でチームは負けてしまった。
シュエンは言った。
「最後の球、とれなくてすみません。」
「シュエンだけのせいじゃない。最初から、そんなにうまくいくとは思ってなかった。」
ランウィーは言った。
ジエンは片付けをしながら、体育館の反対側にいるシュエンをちらりと見たが、ランウィーと話しながら、可愛らしく笑っていたので、安心した。
ロシアでも、試合が行われて、いろいろなチームと対戦したセラフィム達は、だんだんと強くなっていた。
数年後、中国1次リーグのバレーボールチームに入る事ができたジエンとシュエン。ロシアのイーゴルとヤコフとセラフィムも同じだった。
中国の対戦相手は日本で、とても弱そうに思えたが、なんとなく苦悩だとかそういう困難を感じさせるチームだった。
手加減しているのかどうかは分からないか、時々、タイミングがずれている。
それがとてもやりずらい。それが技なのかどうか分からないが、難しく感じる。
中国のチームは、直球勝負だった。なんといってもゴルゴがいるので、安心だ。
勝てそうだったので、ゴルゴがシュエンに聞いた。
「出てみるか?」
「はい。」
シュエンは上着を脱いで、着替えた。
日本選手たちはそれを見て、こそこそ話した。
試合は中国が勝利し、試合終了後は、日本選手が足を引きずっていた。
ジエンは笑った。
「あいつ、足を引きずっている。俺なら、どんなに痛くてもこうだぜ。」
ジエンは足を床にドンとし、中国選手は笑った。
だけど、午後の試合で、ジエンの足も痛くなってしまった。
「ああ‥。」
「兄貴、大丈夫か?」
「すまん、ちょっと休むわ。ジャンプ痛がどんなに痛いか、これで分かったわ。」
「人を笑うと、自分も笑われるんや。」
ゴルゴが言った。
「ああ、そうやな。」
ロシアのセラフィムのチームは、パリでの国際試合に出た。
最初の相手はイギリスで、紳士的なプレーだったが、とても速かった。
一回は速くて、止まってしまったが、ワンセット終える頃にはすぐに慣れた。
そういう時に、自分のバレーボールの才能を感じる。
パリの赤ワインは特にうまかった。ロシアにもワイナリーがあるが、風味が違う感じがする。
ロシアのワインも厳しい冬を乗り越えているので、なかなか美味しいが、ヨーロッパのワインは格別だ。しかし、ロシアには、もっといい酒がある。
いろいろな試合を乗り越えた中国とロシアのチームは、オリンピックに出ることになった。
新体操の人が、選手村で技を見せようとして、腰を打ってしまった。
ロシアのセラフィムとヤコフは、見なかったことにした。
いよいよオリンピックの日。
3回勝ったロシアと中国は、あたることになった。
入場のため、男達は歩き出した。
ロシア対中国
背が高いジハンと背が低いシュエンは、2人並んで、観客に手を振ったので、
ロシアの選手は立ち止まってしまった。
ジェントルマンなロシア選手は、仕方なさそうに再び歩き出した。
ロシア選手のセラフィムとヤコフも真似をしようとしたが、
黒髪が舌打ちをしたので、再び後ろに並んだ。
試合前、CMの時間だと思う。
選手たちは、ベンチに座った。
なんとなく、試合前は、見えないはずの景色が見えてしまう。
ゴルゴは座り、指を組んで、うなだれた。
シュエンがジエンに言った。
「兄さん、何かいい話をしてくださいよ。」
「ああ、いいよ。」
ゴルゴが立ち上がったので、シュエンが言った。
「聞いとけ。」
「いや、俺はいいよ。」
「いいから、聞いとけや。」
みんなジエンのまわりに集まった。
「昔、俺にバレーを教えてくれた先輩に、聞いてみた事がある。ボールはなんやと思いますかって。」
「そしたら、先輩はこう言った。ボールはただ遊ぶもんやって。」
「いいか?これはただのゲームや。誰の命もかかっていない、ただのゲームなんや。」
ジエンは言った。
「今日は、国のために戦おう。」
円陣を組んだセラフィムは言った。
「FIGHT!!」
中国の客席にも、ムォンや、姉妹たちが来ていた。
シュエンが言った。
「遊びや言うたけど、今日は勝たないと。」
「まぁ、遊びで勝つんやな。」
中国も円陣を組んだ。
「なんて言えばいい?」
ゴルゴが聞いた。
「さぁ、兄貴決めろや。」
シュエンが言った。
ジエンは言った。
「じゃあ、これや。‥オーケー!!」
勝負の行方はまだである。
End
By Song River
「いらっしゃいませ。」
ロシアのコンビニでは、店員のセラフィム・アガファニコフがレジを売っていた。
「お願い。」
高級毛皮の女性が、レジに商品を置いた。
「780円です。」
「ふん。」
「こちら。」
セラフィムは袋に入れた商品を、女性の前に置いた。
「ちょっとぉ‥。」
女性は袋の中身を見て、顔をしかめた。
「なんで、ボールペンと食べ物を一緒に入れるのよ!!」
「え‥。」
「あんた名前は?」
とっさに、セラフィムは名札を手で隠した。
「見せなさいよ!!」
「ああ‥。」
「セラフィム・アガファニコフさんね。よく覚えておく。」
セラフィムは悲しくなり、少し赤くなった。
友達のヤコフ・ガルギナが、コンビニに入ってきた。
「大丈夫?」
「うん。」
セラフィムはついに涙をぬぐった。
中国広東省の刑務所で、ジエン・チョウと、シュエン・ソンは話していた。
「今日で終わりやな。」
「ええ。やっと出られますよ。11カ月は長かったですわ。」
「俺は10カ月やけど、もうすぐ死ぬ所やったわ。」
若い刑務官が来て、叫んだ。
「1105番!1104番!外へ出ろ。」
「いや、順番が逆やろう。」
「ついに死刑ですか。」
ジハンとシュエンがつぶやいた。
「いいから、早く出てこい!!今日でようやく外へ出られるぞ。」
2人が部屋から出ると、手を後ろにされ、手錠をされそうになった。
「おい、俺たちは今日で終わりやぞ。もういいやないか!!」
「まぁまぁ、兄さん。言う事、聞いておきましょうや。」
結局、2人は手錠をされずに済んだ。
釈放前に、2人は刑務官と面談しなければいけない。
シュエンは言った。
「ほんまに、反省しております。盗みをして、その店の店長を殴るなんて、悪い事をしました。家に帰ったらまず、母の肩をもむつもりです。」
シュエンは嘘笑いで刑務官に話した。
ジエンは泣きながら、刑務官と話した。
「いや、ヤクをやったくらいでね、10カ月も盗られましたわ。俺の10カ月を返してくださいよ。」
「いやいや、君はもう罪をつぐなってくれた。今日で釈放出来るよ。」
「この阿呆!ヤクをやったヤツを10カ月で出すんなら、殺人者も出してやれ!!」
ジエンが大声で言ったので、刑務官はひるんでしまった。
「あのな、殺人者を出したからって、また殺人するとは限らんやろうが。
世の中にはな、殺人者の因子なんて、ぎょうさんおるんや。信じられないほどにな!!」
結局2人は外に出た。
シュエンは両親、ジエンは従兄が迎えに来ていた。
ジエンは言った。
「シュエン、また会いましょうや。」
「はい。じゃ、兄貴これ。」
「ありがと。」
シュエンは、ジエンに連絡先の書かれたメモを渡した。
セラフィムの仕事の後、セラフィムとヤコフは、バルで話した。
このバルはなかなか安い。味はそこそこだし、飲み放題は700円だ。
ヤコフは酒を飲み、バルの中を少し見ながら言った。
「俺はまだ奨学金が残っている。」
「まだ返済を?」
「うん、そうだ。だから、全然貯金出来ていない。」
「そうかい。でも、僕もだよ。両親に毎月5万取られる。」
「ああ。お互い様だな。」
「うん。」
「こんばんは、お二人さん。」
「アルビナ。来ていたんだね。誰かと?」
セラフィムが言った。
「いえ、1人よ。」
「1人?バルに、28歳の女の人が1人で来るなんて。」
ヤコフが言った。
「そう?普通でしょう。」
セラフィムは言った。
「よければ、一緒に飲む?」
「いえ、結構よ。もう食べ終わって、帰る所だから。」
「ああ、そうかい‥。僕たちはまだ来たばかりだ。また一緒に‥。」
ヤコフは言った。
「ええ、ありがとう。さよなら。」
「またね。」
ヤコフは言った。
ヤコフは少し笑って、セラフィムを見た。
「好きなの?」
「別にそうじゃないよ。」
「じゃあ、そろそろ他の誰かと付き合えよ。」
「金があればな。」
セラフィムは照れ隠しに言った。
「愛にお金は関係ない。」
ブルル
ジエンの従兄の車が、ジエンの実家の団地に着いた。
「家についたな。しばらくゆっくりしたら?」
従兄のハオミンが言った。
「いや‥でも、働かないと、金に困るだろうし。」
「うん‥、ジエンはえらいな。」
「いや‥兄さんほどじゃないよ。」
ジエンはハオミンが好きだった。
もしもの時は、仕事を紹介してくれそうだ。
「ただいま。」
「兄ちゃん?」
「お母さん、兄ちゃんが帰ってきたよー!!」
2人の妹チェンシーとルーシーが顔を出した。
「あらあら、おかえりなさい。」
お母さんがエプロンで手を拭きながら出て来て、ジエンの手を握った。
「あ、うん。」
ジエンが台所に入ると、高校教師をしている父親が新聞を読んでいた。
「父ちゃん、帰ったで。」
「よく戻ってきてくれたな。」
「うん。」
妹2人が言った。
「兄ちゃん、バカだよねー。」
「麻薬はやっちゃいけないって、自分が言ったんじゃん。」
「ああ、すまんな。可愛い妹たちを、裏切ってしもうて。」
「きらい。」「兄ちゃん、やだ。」
お母さんは言った。
「仕方ないでしょう。」
「母ちゃん、今日の晩飯なに?」
ジエンは聞いた。
両親は目を合わせた。
「今日、家はからあげなんだけど、隣のムォンちゃんが、あんたにご飯を作ってくれたっていうのよ。」
「ええ?!」
「えええっ!」
妹たちも口を抑えた。
ムォン・ヨウは、28歳の聡明な女性で、家族と一緒に、隣の部屋に住んでいる。
「マジか、それ。」
「マジや。あのなぁ、やっぱり罪をつぐなってきたでな、良い事がおこるんや。」
父親が答えた。
「はああ。」
ジエンは軽くシャワーを浴び、髪を整えた。
隣の部屋のドアの前に立ち、軽く咳払いをした。
チャイムをちらりと見た。チャイムは汚れている。
あんなに美しくて綺麗な女性が、自分と同じ、汚くて古い団地に住んでいる事が、信じられない。
カチャ
ムォンはドアを開けた。
「あっ。」
「ジエンさん。来てくれたのね。嬉しいわ。」
「いやいや。今日はありがとな。わざわざ俺のために。」
「とんでもないことよ。さぁ、入って。」
「うん。」
ムォンは少し走って、おかってに向かった。
床にはぬいぐるみが置かれていて、チョウ家より綺麗だし、お洒落だ。
どことなく、太陽の香りがする。
ムォンのお父さんは大工で、お母さんは工場にパートに出ている。
お姉さんは、万里の長城でガイドをしているので、今は住んでいない。
「座って。水餃子を作ったの。」
「ああ、美味しそうや。今日、おばさんとおじさんは?」
「出かけているわ。パパが関わったお家が完成したので、今日はお祝いがあるの。」
「そうか。よかったな。」
「ええ。」
「美味い!!」
ジエンは音を立てて食べた。
「本当?よかった。」
ムォンも水餃子を女性らしく食べながら、微笑んだ。
ブルルル
高級車の中で、シュエンの母リンナが聞いた。
「酷いことされたでしょう?」
リンナは綺麗だ。
「いいえ。ジエン兄貴とも知り合いになれたし、貴重な11カ月でした。」
シュエンは答え、父ズォンが言った。
「だけど、店の店長を殴っただけで捕まるなんて、おかしいよ。」
「いえ、僕が悪いんです。仲間と一緒に店に押し入ったんです。」
リンナが聞いた。
「じゃあ、仲間はまだムショに?」
「ええ。奴らには前科がありましたから。僕にはなかったので、早く出られました。
お母さん、お父さん、僕を11兄弟の最後の養子に迎え、大切に育てていただき、ありがとうございました。」
シュエンが言うと、ズォンは運転をしながら、涙をこらえた。
リンナは言った。
「まだ孫家にいていいのよ。お前は大事な子だから。」
車は屋敷の前についた。
門番がドアを開く。
車は屋敷の敷地に入った。
家来がドラを鳴らし、玄関の前の廊下の両側に並んだメイド達が、手をついて挨拶をした。
「おかえりなさいませ、シュエン様!!」
「ありがとう、みんな。」
「宴の準備は出来ております。」
一番上のメイドが言った。
「いつもありがとう。」
ズォンは言った。
「さぁ、行きましょう。」
リンナはシュエンの肩にさわり、歩き出した。
広間につくと、兄妹達が勢ぞろいしていた。
孫家は11人の養子をとっている。
一番末がシュエンで、男と女が5人ずついた。
双子は男に一組、三つ子は女に一組いる。
宴は始まった。
双子の兄さん、イーヌォとユイルイが言った。
「お前が帰ってこなければ、よかった。」
「なぜだ?俺は兄さん達のことが好きだよ。」
「俺達はそうじゃないから。」
長女のイーイーが聞いた。
「シュエン、刑務所で、友達が出来たって本当?」
「はい、本当です。」
「気をつけなさいね。犯罪者は繰り返すものよ。」
「ジエン兄貴なら大丈夫です。ムショで俺にいい話をたくさんしてくれましたから。」
三つ子は笑いあっている。
次女のメイジィが言った。
「アンタさぁ、ちょっと痩せたんじゃない。」
「そうかな‥。」
長男のトンデルが言った。
「そうだよ、少し鍛えた方がいい。」
次男のヒューデルが言った。
「お前がいない間にな、男専用のトレーニングルームを作ったんだ。」
「風呂から出たら、やってみろ!」
三男のフロルが最後に言った。
ロシア‥アルビナは落ち込んでいた。
本当は帰る気分でなかったが、帰るしかない。
雪が残った道を、一歩一歩踏みしめて帰る。
両親もおばあちゃんも何も言ってこないが、家に帰るたびに、何か言われそうに思ってしまう。
アルビナはドアの前で目を閉じ、深呼吸した。
「ただいま。」
「あら。おかえりなさい。ご飯は?」
「食べた。」
「どうして元気がないの?」
「なんでもない!」
「もう‥。」
お母さんは最近傷つきやすい。
太って裕福そうなお父さんは、暖炉の前で心配した表情をした。
アルビナの家は、同じ家が並ぶ住宅街のうちの一軒で、貧乏ではないが、特別お金持ちというわけではなかった。
妹はモスクワに出たまま、帰ってこない。
アルビナはそれが辛かった。
「アルビナ、お風呂は?」
「もう少し待って。」
「分かった。」
「でも‥。」
アルビナはお風呂に入ることにした。
仕度をして、風呂から出た。
髪は少し濡れている。
「ゲームするか?」
お父さんが聞いた。
「いい。」
「ふん、そうか。」
アルビナは部屋で、お気に入りのテディベアを抱いて、考えた。
今日は失敗をした。友達に誘われて、イーゴルのバスケの練習を見に行ったのだ。
アルビナを誘った友達は、別の子と仲良く話しだしたし、なんとなくイーゴルの機嫌が悪くなって、アルビナ座っている壁の近くにボールを当てたのだ。
アルビナがよそ見をしているすきだった。
「ああ‥。」
「やめろよー。」
他のチームメイトが声をかけ、イーゴルは向こうに行ってしまった。
アルビナは立ち上がった。
「帰るの?」
誘った友達が聞いた。
「うん、もういいから。」
「えー。変なの。」
「うん、ごめんね。」
「いいよ。じゃあね。」
「じゃ。」
誘った友達の友達も、アルビナに微笑んだ。
アルビナは雪が舞う中、走って明るい場所に向かった。
「なんて馬鹿なことをしたのかしら。」
私服姿のイーゴルの姿が浮かび、アルビナは少し泣いてしまった。
イーゴルは黒髪で、ずっと好きだった相手だった。
28歳なのだから、イーゴルにも恋人くらいいるはずだ。
アルビナはテディベアを抱きしめた。
今この場で、テディベアを引き裂くことだって、自分の体を傷つけることだってできる。
でも、アルビナはしなかった。それは28歳の大人だからだ。
若い頃にそんな経験をするよりも、大人になってからの方が、良かったかもしれない。
それと、今、セラフィムは自分の部屋の鏡の前で、ブロンドをとかしながら、アルビナを想っていた。
「別にアルビナの事は好きじゃないけど、良い子だよな。」
セラフィムの給料は少ないが、少しだけいいアパートの上階に家族と住んでいて、
部屋には、昔の貴族が使っていたような鏡を置いていた。骨董市で見つけたのだ。
「はぁぁ、俺ってハンサムだよなぁ。」
セラフィムは左右に顔を動かし、決め顔をした。
「ん?」
セラフィムは後ろを向いた。
「何もないか。」
セラフィムは鏡に布をかけた。
時々、この鏡は怖いので、布をかけるようにしている。
この前、帰宅すると布が鏡から落ちていたので、怖くなった。
母さんが掃除をしたせいだ。
「母さん、勝手に掃除をするのはやめてくれ!」
セラフィムは怒った。
「ただいま。」
ジエンは家に戻った。
台所で両親は、うれしそうにお茶を飲んでいる。
「どうだった?」
「ああ、ムォンちゃんが、水餃子を作ってくれてなぁ。とても美味かったわ。」
「はは。よかったなぁ。」
「それでな、ムォンちゃんは、今、彼氏募集中なんやて。」
「えええ?!」
聞き耳を立てていた妹たちが部屋から顔を出した。
「ああ、もうお前達、うるさいわ。」
妹たちも台所に来た。
「お兄ちゃんがムォンちゃんと付き合うってこと?!」
「いや、まだ決まったことじゃないよ。俺はムショから出たばかりやし。」
お父さんが言った。
「でもな、やっぱり、罪をつぐなってきたから、良い事が起こるんや。」
「そうやな。親父、ありがとう。」
ムォンは夢を見ていた。
ムォンは離れて暮らしている祖父母からもらったお金を、北京の料理専門学校に通っているうちに、使いはたしてしまった。
ムォンのアパートは今よりも部屋は広いが、雑踏の中にあった。
ジエンのようなお兄もいないし、少しだけ治安が悪く、落書きだらけだ。
部屋の郵便受けに、借金の取り立て書が入っており、
ムォンは、寂しさもあいまって、大声で叫んで泣いてしまった。
「あああああ!あああああ!」
「え?」
1人の男が叫び声に気づいた。
ドンドン、ドンドン
「ムォン!大丈夫か!」
「え‥。」
ムォンは恥ずかしくなり、布団を上からかぶり電気を消し、その人が去るのを待った。
足音がしたので、ムォンはベランダから姿を確認すると、幼稚園の時に知り合いだったレフ・リーだった。
レフは北京のレストランで働いていた。
「レフ‥。」
レフは笑い、ムォンもレフに手を振った。
「でも‥。」
ムォンは、豆電球が飾り付けられた今の部屋の布団の上でゴロゴロした。
ムォンは思い出した。
「お母さん!!恥ずかしいからやめてよ!!」
ムォンが大声を出したので、まわりの人達がじろじろと見ている。
普段、北京でかっこつけていたのに、ダサいお母さんと一緒にいる所を見られたくなかった。
その場を、またレフに見られてしまった。
レフはムォンが好きだったので、心配して、よく見に行っていた。
「やっぱり、レフとは無理。」
ムォンは起き上がり、壁を見た。
壁の向こうの部屋では、ジエンが寝ている事を分かっていた。
ジエンはいびきをかいて寝ていた。
キキッ
「おはよう。」
ヤコフの自転車が、セラフィムの前で止まった。
「おはよっ。」
「仕事終わりか?」
「うん。昨日から夜番なんだ。」
「そう。俺は、今から仕事。マヨネーズ工場は退屈だが、楽でいい。」
「そうか。頑張って。」
「ありがとう。」
セラフィムとヤコフは握手をした。
家についたセラフィムは、昨日の晩御飯の残りを食べ、シャワーを浴び、眠りについた。
しばらくして、母親の声で目覚めた。
「ロディオン、よく帰ってきてくれたわね。子供たちは?」
「今日はいない。僕一人だ。」
セラフィムが見に行くと、兄のロディオンが来ていた。
「やぁ、ただいま。セラフィム。」
「兄さん。おかえり。」
コーヒーを飲みながら、母親のナナロが聞いた。
「なぜ、アンジェリーナと別れるの?あんなに可愛い子供たちがいるのに。」
「アンジェリーナは最初から、僕を愛していなかった。」
「そんなことないわ。2人の結婚式だって、あんなに楽しかったじゃない。」
「そうだよ、兄さん。彼女と別れるべきじゃない。」
「いや、別れるべきなんだ。2人の子供は、僕と、DNAが一致しなかったんだよ。」
「ええ?」
帰ろうとしながら、ロディオンが言った。
「もっと早く気づくべきだったんだ。」
「ダーリン、可哀想に。」
「母さん。」
2人はハグをかわし、セラフィムは少し泣き、背を向けた。
「ああ、兄さん。可哀想に。」
セラフィムはまた眠りについた。
ジエンは、ハオミンが働く工場に雇ってもらうことになった。
給料は安いが、ジエンが予想していたよりも、悪くなかった。
ハオミンは工場内を、あれこれ説明しながら、歩く。
「はぁぁ。」
ジエンは、大好きな兄貴の手前、しっかり働きたいと思っていたが、
こんな仕事では、毎日飽きるだろうと感じた。
夢がない。
「こちらは、勤続40年のチインさん。」
「はああ…。」
「よろしく。」
チインさんは、歯がかけていたが、ニッコリと笑った。
『こんな場所で、勤続40年か‥。バカだな。』
ハオミンはニコニコとして、あれこれ説明している。
『はああ。兄貴のために頑張りたいけど、俺はそんなに続けるのは無理だ。』
「辞めたくなったら、辞めていいからな。」
ハオミンは言った。ハオミンは街のオーケストラ団員で、登山を趣味にしている。
「いや、俺は‥、兄貴がいるこの工場で、働きたいです。」
ジエンは言った。
「そうか。」
ハオミンはにっこりと笑った。
「この毎日は退屈だからな、お前は何か趣味を持てばいい。
俺だって、オーケストラに入っているし、暇があれば登山に行っている。」
「はああ。」
ジエンは、ハオミンの優しさに少しぼんやりとしてしまった。
シュエンはしばらくの間、新聞配達をすることになった。
近所の人達はシュエンが来ると笑って、挨拶をし、シュエンも走りながら手を振ったりした。
夜。屋敷のトレーニングルームでは、双子のイーヌォとユイルイが空手の型の練習をしていた。
息はピッタリだ。
トンデルとヒューデルは背が高く、200センチくらいある。
フロウも190センチくらいあるが、低く見えてしまうくらいだ。
シュエンの身長は170センチくらい。
みんなトレーニングをしていた。
「シュエン、何かやってみろ。」
トンデルがシュエンに言った。
「何かって?」
「アクロバットだよ。」
「ええ‥。」
双子が手をこきこきさせ、こちらに来た。
この2人は何かと、シュエンに文句をつけたがる。
「でも、俺、前にやってみたけど、上手くいかなくて。」
シュエンは言った。
「ああ。アクロができないチビなど意味がない。」
「努力せずにあきらめるヤツは、カスだ。」
双子が言った。
「まぁまぁ。シュエンだって、あきらめているわけじゃないさ。」
ヒューデルが出てきた。
「ほら。」
フロウは簡単な技を見せた。
「だけど、こいつには無理だ。」
双子は言った。
「そんなことない。シュエン、やってみろよ。」
トンデルが言った。
双子以外の兄弟は、シュエンに期待をしていた。
アクロが出来るチビは、国宝とも言える。
「うん‥。」
セラフィムは午後6時に起きた。
高級毛皮の変な女性を思い浮かべた。
「うん。もしも、あの女性が来ても、優しくしてあげよう。
きっと、高級マンションに住みすぎて、普通の会社では、働けなくなった人だ。」
セラフィムはベッドから起き上がった。
ベッドは窓際に置いてある。
真冬は寒いので、窓もカーテンも二重にしてある。
晩御飯を食べ、「行ってきます。」
「おお、セラフィム。」
「こんばんは、父さん。行ってきます。」
「気をつけて。」
「はい。」
セラフィムは階段を降りた。
ふいに、昔のことを思い出した。
中学ではバレーをしていた。
中学でかなり背が高いヤツもいるが、身長がどうなるかなんて、まだ分からない。
その男のパパは、身長が200センチあった。
ママは小さい。
その男アデルは、自分は体育が出来ると思い込んでいた。
小中学校では、体育が出来る子だと、信じ込まない方がいい。
信じこんでいいのは、高校からだ。
セラフィムの方が、各段にバレーがうまかったが、アデルは、「下手だから。」と言った。
セラフィムの幼馴染ナアが、アデルのことが好きだったため、許してあげた。
アデルは、高校はスポーツ推薦でいけると思った。
でも、アデルの身長は伸びない。ママが小さいからかもしれない。
強豪校が声をかけたのは、セラフィムにだった。
セラフィムは遠慮した。
そして、アデルの第一希望高校を、念入りに調べ、アデルと別の高校に入学することに成功したのだ。
アデルが馬鹿にしていたヤツで、プロスポーツ選手になった者もいる。
アデルは焦ってしまった。心はまだ、自分は体育が出来る男の子だったからだ。
だから、子供時代は才能があると、信じない方がいい。
大人になって、自分に才能に気づくのがちょうどいいのだ。
スポーツの才能なら、高校でもいい。
「はああ。」
セラフィムは歩いて、コンビニに向かう。
ずっと勤める気はないが、近所の職場なので、ありがたい。
「いらっしゃいませ。」
セラフィムは顔を上げると、また、あの女の人が来ていた。
「ああ‥。」
セラフィムが笑うと、
「何よ!!」
女の人が突然コーヒーをセラフィムにかけた。
「ああ。」
「ちょっと‥。」
店長が奥から出て来て、女の人をなだめた。
女の人は怒って立って聞いていたが、店長に殴りかかったので、店長は警察を呼び、
女の人は、警察に連行された。
店長はコンビニに戻り、セラフィムに聞いた。
「大丈夫?」
「はい、すみません。」
「いや。アガファニコフ君が謝ることじゃないよ。」
店長はおでんを見て言った。
「ああ、こりゃダメだな。もうこれは、捨てようか?」
「はい。」
セラフィムはおでんを捨てるために、具を皿に盛った。
ジエンは部屋で座布団に座り、考えていた。
「これ、嘘かのぉ‥。」
シュエンのメモだ。
パソコンで調べると、大金持ちの家が出てくる。
ジエンは困った顔をした。
「困るのぉ。こんな大金持ちと関わるなんて、わし、嫌や!」
ムォンは、レフが広東省のレストランに転職したので、見に行っていた。
ムォンは大衆食堂で働いている。お父さんの大工仲間や弟子が来るので、とても楽しい。
ムォンは髪を七三分けにして、タートルネック、ミニスカートに黒のストッキングをはいて、お洒落をした。
レストランは一軒家で落ち着いた感じだ。
ムォンはうきうきして、肘を両サイドに振った。
「ムォン。」
「え‥。」
そこにいたのは、コック姿のレフだった。
「来てくれたの?」
「いえ‥。」
ムォンは恥ずかしくなり、答えられなかった。
ムォンは気が動転してしまい、歩いては、肘を両サイドに振った。
ジエンは、ベランダに立って、景色を見た。
綺麗とは言えないが、悪くない。
海が見えたらいいのにと、よく思う。
「あ‥ムォンちゃんや。」
「ムォンちゃーん‥ん?」
ムォンは、歩いては、肘を両サイドに振っている。
「なんか、うれしそうやな。よかった。」
ジエンはニッコリと笑った。
「まだ俺は、ムォンちゃんとつり合うような男じゃない。早く、一人前になりたいわ。」
シュエンは、アクロの練習をしていた。フロウは腕組みをして、見ている。
双子も様子を見に来ていて、シュエンが技に失敗して尻もちをついたところに、歩み寄った。
「お前、バカだなー。」
「不可能なことに時間をさくヤツは、落ちこぼれだ。」
「いいか?こうだ。」
フロウは分かりやすく説明しながら、ハンドスプリング等の簡単な技を見せた。
「俺も、雑技団ほどは、アクロはうまくない。でも、お前もきっとできるはずだよ。」
「うん‥。」
双子は言った。
「兄さん、でもこいつは、アホだから。」
「ドジでまぬけで、犯罪もしたし、勉強もできない。」
シュエンは下を向いた。
フロウは言った。
「でも、シュエンは足が速い。だからきっとアクロバットだって出来る。」
双子は顔を見合わせ、気に食わない感じにしている。
シュエンはまた少し落ち込んだ。
元気をもらうために、女子の部屋の方に行く事にした。
イーイーとメイズィは化粧鏡の前で、何かやっている。
シュエンは言った。
「ほぉぉ。男はトレーニング、女は化粧やな。」
メイズィは少し舌打ちをした。
「化粧じゃないわよ。今は保湿をしているの。」
「ふん‥。見た目は化粧やから、よくわからんわ。」
イーイーは言った。
「これはお化粧じゃないのよ。ほら。透明になるでしょう。」
イーイーは、白いクリームを、手の甲に塗ってみせた。
「あんた、なんで来たの?」
メイズィは聞いた。
「いや‥俺、兄さん達から勧められたアクロがうまくできなくて。姉さん達に会えば、元気でるかなと思って来たんだよ。」
「元気が出るですって?まさか、私達に興味があるってこと?」
「いやいや。お二人には、トンデル兄さんとヒューデル兄さんがいるということを、俺はよくわかっている。」
「ふん。」
イーイーは安心したように、リップクリームを塗り始めた。
メイズィは聞いた。
「じゃあ、あんたは、ラナデルレイに興味があるの?」
「いや、俺は、ラナデルレイにも興味はない。ただ、女と話せば、元気が出るかなと思っただけで‥。」
「ラナデルレイ、来なさい!!」
メイズィはシュエンの言葉を聞かずに、ラナデルレイを呼んだ。
「はーい。」
ラナデルレイは三つ子の名前だ。ラナ、デル、レイである。
「シュエン。」
「どうしてここに?」
「1人で来たの?」
「ええ、そうよ。」
イーイーが答えた。
ラナデルレイはニヤニヤと笑ってシュエンを見た。
3人は、孫家の養子兄妹同士で付き合うなら、イーヌォとユイルイの双子とシュエンだと思っていたのだ。
シュエンは11人の養子の末っ子だ。誰がシュエンと付き合うのか、よく話していた。
「どうしてここに?」
デルがもう一度聞いた。
「俺な、アクロがうまくできなくて、女と話せば、元気が出るかと思って来たんだよ。」
シュエンは答え、姉妹は笑った。
「分かった。俺はお前たちに興味はない。だからもう、行くわ。」
「もう行っちゃうのぉ?」
「ああ。」
シュエンは、棒をすべり、下に降りた。
下では、トンデルとヒューデルが待っていた。
「女部屋に行っていたのか?うらやましい。」
「ああ。ちょっと話しただけだよ。」
「俺達が行くと、すぐに母さんに疑われるから。」
「姉さんたちに本気なのか?」
「ああ。俺はイーイーとの子供がほしい。俺ももうすぐ36歳になってしまう。」
トンデルは言った。
「兄さんと姉さんなら、子供くらい、きっとすぐにできるさ。」
「どうかな。」
シュエンが言うと、トンデルはニヤニヤと笑って、首をかしげた。
ヤコフは、単調な仕事の休憩中に、白いテーブルの上にマーブルチョコを並べた。
それを1つずつ口に入れる。
顔は全身覆われているので見えないが、ヤコフの身長は高い。200センチあるが、ロシアではそんなの普通である。
日本なら、そんなヤツはすぐに正社員になれるが、ロシアではなれない。
ヤコフは、日本のバレーボールのチビを見て、口をへの字にした。
もしかしたら、日本でならうまくいくかもしれない。
でも、自分は白人だからきっと無理だ。
ヤコフは手で顔をおおった。
東京五輪は2年後にある。
なんとかして出たいものだ。そう思うと、ヤコフはニヤニヤとした。
事実を事実として受け止めると不可能に感じるが、まだ何が起こるか分からない。
時々、セラフィムや仲間たちとバレーボールをして遊んでいる。
次の予定は、日曜日だ。
マーブルチョコレートを食べ終えると、ヤコフは青いサプリメントを二粒、楕円のオレンジのサプリメントを一粒取り出し、テーブルに置いた。
なんとなく、顔を作ったりして遊ぶ。
派遣社員の親父が上からジロリと見たので、ヤコフはサプリメントを飲むのをやめた。
親父がどんな経歴の持ち主なのか、ヤコフは知らない。
親父はマヨネーズをパンにかけて、食べ始めた。うまそうだ。
ヤコフはにっこりと笑った。
ヤコフは高校の頃を思い出した。
背の高いセラフィムは、ミニスカートの女子を連れて階段を上がっている。
今日は、高校の行事で、プロのサッカー観戦にスタジアムに来た。
「ヤコフ。」
セラフィムはヤコフに声をかけた。
「やぁ、セラフィム。君は‥?」
「ナァよ。よろしくね。」
「まぁ、そうだな。友達の彼女なら‥。」
「彼女ってわけじゃないわ。」
「ああ。同じ班なんだよ。」
セラフィムとヤコフは別のクラスだ。
この後は、高校に戻ってバレーボール部の練習がある。
最初、先輩達は嫌な感じがしたが、優しくしてくれた。
ヤコフとセラフィムは、いつか、バレーボールのプロ選手になれる気がした。
だから、先輩には、「先輩はプロを目指さないんですか?」と必ず聞いた。
「うん‥、俺たちの高校からじゃ、無理っしょ。」
先輩は大体そう言う。
「でも、大学でもやったらどうでしょうか?」
「いや~、俺‥パイロットを目指したいんだよ。」
「ああ‥。」
ヤコフとセラフィムにとっては、パイロットの方が狭き門だった。
勉強もしっかりしていたので、目がだんだん見えなくなっていた。
裸眼にこだわったせいだ。友人のイーゴルは、裸眼でもいけるくせに、中学生のころから勉強する時は時々眼鏡をかけていたので、視力がとても良い。
でも、さすがのイーゴルも、現在では視力が少し落ちた。
イーゴルにとっては、大変な異常事態だった。
ヤコフとセラフィムは、大学に行かなかった。
モスクワのアマチュアチームに入ってバレーボールをした。
でも、だんだんと、まわりに差をつけられた気がした。
イーゴルはモスクワ大学のバスケットボールチームでプレーしていたし、自分たちには将来性がないように感じたが、イーゴルはプロになれなかった。
28歳のヤコフは、休憩室でため息をついた。
親父になって派遣社員をやるのは、大変そうだ。
だから偉いのか?分からない。
ヤコフには、好きだった子いる。レレイのブログを読んだ。
レレイはとても可愛い。レレイは一度変な男と結婚したが、離婚した。
その時は頭にきて、レレイのことを嫌いにもなったが、
今は許している。まだ付き合ってはいないが、仕事がもう少しうまくいったら、
好きだという気持ちを伝えたいと思っている。
「ううっ。」
シュエンは、アクロの練習中、腰をうった。
「大丈夫か!?」
双子は、シュエンの下にかけよった。
「無理なら、もうやめろ。」
「うん。」
フロウに向かって、シュエンは言った。
「兄さん、俺、もう無理やわ。」
「わかった。別のスポーツをやろう。」
フロウは提案した。
「別のスポーツってなんだい?」
「バレーボールさ。お前はバレーボール部だっただろう?それに、昔はよく、兄妹みんなでバレーボールをしたじゃないか。」
「海南島でのビーチバレー!」
「ああ、そうだ。」
双子はバレーボールを撃つ真似をして、ジャンプをした。
ちょうど男は6人いるので、3対3になる。
女子5人は、その姿を見守った。
トンデルがサーブをして、試合が始まった。
それはボールがなかなか床に落ちない、面白い試合だった。
体育館に社会人チームが入ってきた。パパさんバレーってやつだ。
「あれ?」
「すみません、ここ使いますか?」
「いえ、こちらのコートを使いますから。」
「そうですか。よかった。」
パパさんバレーチームの練習はハードそうなものだった。
兄弟はまた、試合を始めた。
「ふーん。」
パパさんチームのキャプテンはこちらを見た。
「よければ、一緒にやりませんか?」
「え‥。」
妹たちは、『やりなさいよ。』手で合図したので、兄弟は、一緒にやらせてもらうことにした。
やっぱり、パパさんチームと兄弟では、速さが違っていた。
一番うまいトンデルでさえ、遅れてしまう。
キャプテンは言った。
「大丈夫さ。すぐに慣れる。」
「はい。」
「よければ、君たちは、僕らのチームに入らないか?」
「ええ、いいんですか?」
夜、向き合ったソファーで、6人の兄弟は話した。
「よかったなぁ、良い人達に出会えてさ。」
「うん。父さんも、金を出してくれるっていうから、ちょうどいいよ。」
トンデルとヒューデルが言った。
「予想外の展開だ。」「こわいくらいに。」
双子も言った。
シュエンは、刑務所でのジエンとの会話を思い出した。
『兄さん、なにかスポーツをやっていましたか?』
『俺?俺は、バリーをやっていたよ。』
『バリー?』
『バリーボールさ。』
シュエンは言った。
「兄さん、俺、友達を誘ってもいい?」
「ああ、いいよ。ちなみに、誰だ?」
「刑務所で出会った人だよ。俺に、一寸法師の話をしてくれた。」
「一寸法師?」
フロウは聞いた。
「あのな、昔々ある所に、おじいさんとおばあさんがおった。
それでな、60歳になって、ようやく子供が生まれたんや。
でも、生まれてきた子供は、大人の小指ほどの大きさしかなかったんや。」
「ああ‥。両親が、年だったからやな。」
「うん。それでな、おじいさんとおばあさんは、その子を一寸法師と名付けたんや。
大切に育てたけど、何年たっても、大きくならんかった。
でも、気はしっかりしたいい男になってな、都でサムライになると言い出したんや。
おじいさんとおばあさんはもちろん止めた。でも、聞かんのでな、仕方なく、
針の刀とお椀の船を用意して、息子を送り出したんや。」
「それでな、都で大臣に気に入られて、大臣の一人娘の春姫に仕えることになったんや。」
「はぁぁ。男なのに、姫の世話をすることになったんやな。」
「そうや。それである日な、赤鬼が現れて、春姫がさらわれそうになったんや。
一寸法師は、針の刀で一生懸命に戦ったんやけど、赤鬼に食われてしまったんや。
でも、一寸法師はな、赤鬼の腹の中を、針の刀でつつきまわして、ついに、赤鬼を倒したんや。」
「ああ~。」
「一度負けても、それで終わりやないっていう話やな。」
「そうや。その後にな、赤鬼は逃げたんやけど、打ち出の小槌を忘れていったんや。
それが魔法の小槌でな、一寸法師の体を、大きくしてくれたんや。」
「はああ。」
「いい話や。」
「お前にピッタリの話だな。」
「な、いい話やろう?兄貴は他にもたくさんいい話をしてくれたんや。」
「ふーん。俺たちもその兄貴と仲良くなれるんかいな。」
「仲良くなれるに決まっている!」
ジエンは会社から家に戻った。家に戻るのは7時くらいである。
「おかえり、ご飯、ちょっと待ってね。」
「ジエン、医師会から封筒がきてたぞ。」
「医師会から?」
ジエンは、父親から封筒を受け取った。
「なんだろう‥。ああ、免許の更新やて。」
「更新しておけ。きっと、いつか使う日がくる。」
「そうやな。今はムショから出たばかりやけん。また何年かしたら、病院で働きたいわ。」
「あんたが、医師免許証を持っているなんて、嘘みたいやねぇ。」
お母さんが言った。
「医師くらい、簡単になれましたわ。」
「まぁ‥そうやなぁ。」
父親も面白そうにジエンを見た。
ジエンは、医師免許を持っている。
中学でジエンはバスケ部だった。
それは、ムォンがバスケ部だったからである。
ムォンとは関わらないようにしていたが、同じ中学に通っていた。
ムォンはバスケを一生懸命にやるが、とても下手くそだった。
「ふん、くぁわいい。」
中学生のジエンは、ニヤニヤしてムォンを見た。
ジエンはバスケの試合で疲れてくると、時々、足が痛いフリをした。
「え‥どうしよう。俺、準備してねぇよ。」
まだそこまで強くない部員は、不安そうにジャージを脱いだ。
「だ‥大丈夫だ。敵がいない場所にいって、はいと言えば、ボールを回してもらえる。
狙えそうなら、シュートしろ。」
「わ、わかった。」
そのおかげで、中学はとても楽しかった。
ジエンは、ムォンと同じ高校に行くことにした。
ジエンは頭がよかったので、実際の実力より下の学校に行く事になったが、気にしなかった。
ムォンの隣の家に住み、小中高と同じ学校に通ったのに、ムォンについては、知らない事がたくさんある。
高1の春の、部活見学では、バスケ部も見学したが、
「俺、もうバスケはいいわ。」
ジエンはボールを落としてしまった。
野球部もサッカー部も見た。でも、先輩が大人っぽいので嫌だった。
なので、先輩が一番弱そうで優しそうだったバレーボール部を選ぶことにした。
やってみると、バレーボールは難しかった。
ひょろひょろと思えた先輩に、尊敬のまなざしを向けてしまった。
先輩は丁寧に教えてくれて、ジエンはバスケより、バレーボールが好きになった。
ジエンは、優しい先輩に、おかしな事を聞いてみた。
「先輩、ボールってなんやと思います?」
優しくて、大人びた先輩は、少し笑って答えた。
「何?普通に、遊ぶものだと思うけど。」
「ふーん。なら、先輩、プロになれますわ。」
「プロ‥?いや、なんないよ。俺は。」
優しくて大人びた先輩は笑ったが、大学で活躍したので、何度か、テレビのバレーボールの試合に出た。
今は、高校の先生になっているらしい。きっといい先生だ。
ジエンは医学部に進学した。
本気でスポーツをしていたヤツらは、そんな学力はない。
嫌な視線を向けてきたが、ジエンは気にしなかった。
「だって俺は、高校時代、雑誌にも、テレビにも、ネットにも、出なかったんだぞ。」
ジエンは言った。それは大切なことである。
「それにな、デートもしなかったんや。でも、エッチはした。」
「誰とや?」
「言えない。」
ジエンは赤くなった。
夜、ジエンは布団に仰向けになり、イヤホンをつけ、ジャズを聴く。
枕元に置いた医学誌をパラパラとめくったり、ゲームをしたりする。
たわいのない時間である。真っ暗にして、目を閉じ、宇宙に行くのもいい。
プルルル
「はい。‥ああ~、ちょっと待ってね。」
「ジエン、シュエンさんという人から電話。」
「ええ?」
「もしもし?」
「兄貴。俺です。シュエンですわ。」
「ああ~久しぶりやな。ごめんな、連絡できなくて。」
「いや、いいんですよ。」
「久しぶりに声聞けてうれしいわ。」
「俺もです。ところで、兄貴、また会いませんか?俺ね、兄弟たちと一緒に、パパさんバレーボールチームに入ったんですわ。よければ、兄貴も一緒にどうですか?」
「おお、わかった。いいよ。」
「よかった。兄貴は医者だと聞いていたので、忙しいかと心配していたんですよ。」
「俺は、仕事以外は暇やで。」
さっそく、土曜日に、チームの練習に参加することになった。
「うう‥。」
セラフィムは、あの夜のコーヒー事件を思い出して、家で泣いた。
「大丈夫か?」
お父さんはセラフィムの前にコーヒーを出した。
「コーヒーなんかいらない。」
「飲みなさい。コーヒーは体にいいから。」
お父さんはセラフィムの前に座った。
「いいか。良い方向に変化する時、人間は必ず泣くものだ。」
「なぜそんな事が言える?」
「経験だよ。父さんにもそんな事が昔、何度かあったんだ。
人は、何度も涙を流して、良い人間になっていく。」
「涙は体にいいのか?」
「悪いとは聞いた事がないな。それに、泣いた後の顔は、老けては見えないだろう?
きっと、涙には若返りの効果があるんだ。」
「ああ‥。」
セラフィムは、自分の部屋の鏡で、自分の顔をまじまじと見た。
「でも、やっぱり泣ける。」
セラフィムはまた泣いてしまった。
少し眠ることにした。
午後3時。曇りだった空は晴れていた。
ピンポーン
チャイムの少し前に目覚めていた。時々、自分は、タイミングがいいなと思う。
きっと神様への信仰心のおかげだ。
「あら、ナァちゃん。」
「こんにちは。あの‥セラフィムは?」
「今ね、寝ているの。起こしましょうか‥。」
「なんだい?」
セラフィムは起きて、玄関に向かった。
「ナァ。なんの用?」
「ああ‥。この前、コンビニで大変な目に遭ったって聞いたから。これ‥。」
ナァは小さな紙袋を渡した。
「なんだいこれ?」
「私、今、パティスリーで働いていてこで売っているものなの。」
「そうか。ありがとう。」
「いいの。」
ナァはニコニコと笑い、母親はナァを家に入れるように合図をした。
「あの、よかったら上がる?」
「うん。」
「お邪魔します。」
セラフィムはリビングに入れようとしたが、母親は慌てて合図をしたので、自分の部屋に入れた。
「そこに、かけていいよ。」
「ありがとう。綺麗にしているのね。」
ナァはデスクの椅子に座り、セラフィムはベッドに座った。
「それは‥?」
「ああ。鏡さ。」
セラフィムは布をとった。
「まぁ、素敵な鏡。」
「骨董市で見つけたんだよ。」
「きっといい物だわ。」
母親が紅茶を淹れてきた。
クッキーも添えてある。
「ごめんね、ナァちゃん。こんなもので‥。」
「いえ。お気遣いいただきありがとうございます。」
母親がだしたのは、コンビニの袋のクッキーだ。
「あとで、セラフィムがナァちゃんのクッキーを食べますからね。」
「はい、ありがとうございます。」
母親は出て行った。
「お母さん、優しいのね。」
「うん。でも、時々やかましいんだ。」
「その方がいいわよ。私のお母さん、最近、すごく元気がないの。」
「ああ‥。」
「きっと年のせいだわ。それに、兄さんと姉さんが、どちらも離婚したの。信じられる?」
「ああ‥。2人とも、パートナーとあんなに仲が良かったから、信じられないな。」
「私も。何があったのか気になっちゃう。」
ナァは紅茶を飲んだ。
「俺の兄貴も離婚するって。」
「どうして?」
「子供と血がつながってなかったんだ。」
「なんてこと。あっちでもこっちでも離婚ね。一度も結婚していないのは、幸いだったわ。」
「ナァは彼氏がいるの?」
「いないの。だから、会いに来たのよ。」
ナァはにっこりと笑った。
「ええ‥?」
「セラフィムとは幼馴染だし、気も会うわ。お互い好きになれるかもしれない。」
「いや、突然そんなこと、できるわけないだろ。」
セラフィムは赤くなった。
「今すぐじゃなくていいの。」
ナァは上品にニッコリと笑った。
仕事に出かけるアルビナに、母親が声をかけた。
「今日、ララビが帰ってくるからね。」
「ええ、ララビが?」
「そう。」
「はぁ‥。」
アルビナはお金がなくて、家を出られないのに、ララビは親からお金をもらい、モスクワで暮らしている。
おばあちゃんにボケてきているので、嫌みたいだ。
夕方、アルビナは家に戻った。
「ただいま。」
「お姉ちゃん、おかえり。」
「うん。」
ララビは少し太ったようだ。
お父さんがララビに言った。
「ララビ、明日、晴れたら一緒にフリスビーするか?」
「いいわよ。パパとフリスビーなんて、何年ぶりかしら?」
「お姉ちゃんもやるー?」
「いい。」
ララビはぺらぺらと一人暮らしのことを話している。
アルビナは腹がたってきてしまった。
「ふん。」
Facebookを開く。
Facebookではいろいろあったが、経験を積んで、慣れてきた。
あまり更新はしないが、時々通知があるので、見て、楽しんでいる。
一件のメッセージが入っている。
『この前はごめん。』
「え?」
「イーゴルからだ‥。」
『今度、セラフィムたちとバレーボールをするから、見に来ない?』
写真が貼られているので、嘘ではなさそうだ。
「ええ。行ってもいいなら。」
『ありがとう(‘ω’)ノ』
アルビナはニッコリした。
土曜日、アルビナは本当に体育館に行ってみた。
イーゴルはアルビナを見つけ、大きく手を振ってきたので、アルビナも可愛く手を振った。
セラフィムとヤコフもこちらを見て、笑った。
アルビナの下に、金髪の女の子が寄ってきた。ちなみにアルビナの髪の毛は、茶髪とブロンドが混ざったような色で、とても綺麗である。
女の子は言った。
「こんにちは。この中の誰かと知り合いですか?」
「イーゴル。セラフィムとヤコフも、高校の時の知り合いよ。」
「そうでしたか。私はセラフィムと幼馴染なんです。」
「幼馴染?なんて素敵なの。」
「はい‥。」
「私の名前はアルビナ。あなたの名前は?」
「ナァです。」
「よろしくね。」
「よろしくお願いします。」
イーゴルが本気を出し、ついにリベロのヤコフは取れなかった。
「すごいな‥。」
ヤコフは言った。
「これくらい普通だよ。」
イーゴルはバレーボールを指でくるくると回した。
ガラガラガラッ
みんなが振り向いた。
そこにいたのは、ヤコフの叔母で歌手のリリオネット・アディオラである。
「おばさん!」
ヤコフが言った。
「私のことは、オバサンと呼ぶなと何度言ったら分かるの?」
「すみません‥。」
「ふん。あんた達、次の試合に出なさい。スポンサーなら、私がなんとかする。」
「試合に?」
「オリンピックを目指すの。」
観客席にいたアルビナ達も、心配そうに見た。
「オリンピックを?今からじゃ、無理に決まっている。」
セラフィムが言い、他のメンバーは下を向いたりした。
「この写真を見て。」
リリオネットが見せたのは、ロシア代表のキャプテンが、体育館で、四つん這いになり、ゲロをしている写真だった。
「ええ‥なんだ、これ。」
「覚せい剤が原因よ。奴らはそれを、シロップと呼んで、楽しんでいるわ。」
「だけど、吐いている写真を見て、楽しそうとは言えないな。」
マイティが言った。
「もうこいつに、感覚はないわ。」
「だけど、僕たちには仕事があるから、あまり練習の時間がとれないんです。」
「大事なのは、練習量じゃないわ。練習の質よ。」
「そうか‥。」
リリオネットはイーゴルに言った。
「それから、あなたも、チームに入りなさい。」
「ええ、俺も?」
「あなたのような男は、チームに必要だわ。」
アルビナ達も、観客席から見守った。
「最後に、私の歌を聴きなさい。」
リリオネットはロシア民謡を歌って帰って行った。
日曜日。
「うわぁ‥。でかい。」
孫家についたジエンは見上げてしまった。
「兄貴や。」
屋敷の上階から望遠鏡でジエンの姿を見つけたシュエンは、下に降りた。
ジエンの前に、トンデルとヒューデルが現れたので、ジエンは会釈をした。
「兄貴!」
「シュエン。久しぶりやな!」
「はい。兄貴、お元気でしたか?」
「おお、俺は元気やったぞ。」
「兄貴、こちらが俺の兄弟です。」
「トンデルです。」「ヒューデルです。」
「ああ‥。」
いつのまにか、シュエンのファミリーが勢ぞろいしていた。
「俺は孫家に迎えられた11人の養子の末息子なんですよ。」
「お前、そうやったんか!」
「はい。」
「ジエンさん、ムショでシュエンに好くして頂いて、ほんまにありがとうございました。」
「シュエンが改心できたのは、ジエンさんのおかげです。」
両親がジエンに礼を言った。
「いえ、俺の方こそ、シュエンに助けられましたわ。とてもいい息子さんで。」
「あはは、ありがとうございますぅ。」
両親は笑った。
「兄貴、さっそく行きましょうや。」
黒いロールスロイスのそばで、シュエンが声をかけた。
妹たちが見送りをし、ジエンは赤くなってしまった。
「あ、シートベルトを‥。」
「いいんや。シートベルトなんか必要ない。」
イーヌォが言った。
「え、でも‥。」
「今日はロールスロイスやけん。心配するな。」
ユイルイも言った。
シュエンは兄弟を説明した。
「トンデル兄さん、ヒューデル兄さん、フロウ兄さん、イーヌォ、ユイルイだ。」
「よろしく。」
フロウは言った。
シュエンはまた言った。
「トンデル、ヒューデル、フロウ、イーヌォ、ユイルイ。」
「よしっ、もう覚えたわ。」
ジエンは言った。
「ああ~覚えがいい~。」
兄弟たちはニヤニヤと笑った。
「兄さんたち、聞いてくれ。ジエン兄貴はな、医者なんや。」
「へええ、医者?」
「はい。一応、医師免許をとりましたわ。」
「はは、すごい。俺なんか、35歳でようやく弁護士になれたというのに。」
トンデルが言った。
「弁護士?すごいじゃないですか。」
「全然すごくないよ。ここ3人はみんな弁護士なんだ。」
「うわぁ、何それ!」
「兄貴に習って、俺も34歳で弁護士になりましたわ。」
「やってみれば、簡単でしたよ。」
ヒューデルとフロウも言った。
トンデルとヒューデルが言った。
「まだシュエンだけが、何の資格も持っていないんです。」
「今は新聞配達をしておりますわ。」
「そうなんか?」
「そうなんや。俺は勉強が苦手で‥。」
「じゃあ、バレーを頑張るしかないな。」
「よしっ、いくぞー!」
ジエンはサーブをした。
さっき話し合って、ポジションを決めた。
シュエンはリベロだ。
ジエンはかなりうまくて、シュエンはなかなか取れなかった。
そのうちに、パパさんチームの奴らが来た。
キャプテンの名前は、ランウィー・ハンという。
「今日は、知り合いのジエン兄貴を連れてきました。」
「お、頼もしい。」
ランウィーは笑った。
ジエンは言った。
「よろしくお願いします。」
「こちらこそ、よろしく。」
2人は握手をした。
「さっそくなんだけど、来週もう、チームで試合に出ようと思います。」
「ええ~!!」
「わかった。じゃあ、今日本気で練習しような。」
トンデルが言った。
「おおう!!」
休憩時間、ジエンとシュエンは、マネージャーをしているヨシフに聞いた。
「ところで、君は、マネージャーでいいんか?」
「はい。今まで日本にいたので、バレーボールから離れていたんですよ。」
「日本に?」
「食品工場の研修です。でも、あまりためになりませんでした。古い工場でコキ使われただけです。何も教わっていない。」
「そうか‥、大変だったんですねぇ。」
「僕たちは刑務所に入っていたんです。」
「刑務所に?」
「はい。とても軽い罪でしたけどね。バレーボールの試合に出られれば、ばん回できます。」
午後の練習は、念のため、ヨシフも参加した。
みんな素質があったので、ランウィーの速さにもすぐに慣れた。
ロシア‥
セラフィムはバレーボールに本気になり、未来が明るくなってきたと感じていた。
水曜日。セラフィムはナァと会うことになっていた。
約束のスタバの前で待っていると、ナァが来た。
「こんにちは。」
ナァはとても可愛い。
2人はスタバに入り、それぞれ飲み物を買った。
ナァが買ったのは、フラペチーノだ。
「なんだい、それ。」
セラフィムは聞いた。
「フラペチーノよ。わからない?とても甘くておいしいの。」
「ふーん、そうか。僕はカプチーノだ。甘い物は控えている。」
「甘い物は、頭の栄養になるらしいわよ。」
「そうなんだ。」
2人は少し黙った。
ナァはニヤニヤと笑った。
「どうしたの?」
「なんでもないわ。‥バレーボールのユニフォームって、どうしてあんなに短いのかしら?」
「多分、サポーターをつけるからじゃないか?」
「ふん。スポーツ選手は露出が多すぎるわ。だから、嫌われるのよ。」
「ええ、俺達が、嫌われているの?」
「あなた達のことじゃないわ。」
ナァは笑った。
ナァの顔には、少しだけ大きなシミがある。
セラフィムは聞いた。
「君って今までに、悲しいことあった?」
「まぁ、いろいろとあったわよ。もう28歳ですもの。28歳って、仕事がうまくいかなくなる時期だわ。」
「そうなのか?」
「ええ。でもそれを経験して、強くなるんじゃないかしら。
‥年齢に合わせて、周りの人から見たら、カッコいい事を選んでやっていくべきだわ。」
「そうなんだ。」
「うん。」
「27歳の頃は、血気盛んだった。」
「血気盛ん?」
「そうよ。あなたはちがったの?」
「いや‥俺は特に何もなかった。」
「かわいそうに。でも、人生はこれからだわ。友達のベルもエイズなのよ。でも頑張って生きているの。」
「ええ?エイズ?君もエイズなのか?」
「いえ、私はちがうわ。神様のお導きのおかげでね。」
「はああ。」
セラフィムは赤くなった。もしもナァがエイズなら、本気で将来のことを考えなければいけない所だったからだ。エイズにはならない方がいい。
日曜日。ジエンたちは試合の日だ。
孫家のロールスロイスが、孫家のメンバーを乗せてきた。
ジエンは親父の車で来ていた。
社会人チームのメンバーたちも笑って、手を振った。
ランウィーは言った。
「最初から、ヤバい奴らが相手だ。中でも、エースのゴルゴは、北京一の荒くれ者と呼ばれている。」
「ええ~‥大丈夫ですかいな。」
「僕たちならきっと大丈夫だ。ヤツの武器である、炎のアタックとドラゴンのスパイクを抑えれば、負けることはないだろう。シュエン、君にかかえっている。」
ランウィーが言い、みんなシュエンを見た。
「できるな?」
「がんばります。」
もうすぐ試合が始まる時、他のメンバーは緊張して、目を閉じたりしている中、シュエンは全く緊張していなかった。
試合の前、緊張しすぎるのもよくないが、全く緊張しないのはよくない。
少しだけ緊張しているジエンに、シュエンが声をかけた。
「兄貴、何かいい話、聞かせてくださいよ。」
「話?うーん、何かあったかのぉ‥。あ、あの話がある!」
「ええっ。」
シュエンは目を輝かせた。
「何年か前のことや。日本に、天才リベロと呼ばれた、身長153センチの女子選手がおったそうや。」
「うん‥。」
「その人は、どんな強くて速い球でも、落とさなかった。みんな最初は、すごいと言うたんやけどな、だんだん、それがうっとうしく思えてきてしまったんや。」
「ええ‥。」
「あんまりできすぎるのはよくない。だいたい、身長153センチというのは、普通はバレーボールのトップの世界には入っちゃいけない身長なんや。」
「でも、なぜ、そんなに強かったんですか?」
「強制避妊手術だよ。なぜかその子は、それを受けとった。子供が産めないことが悔しくて、強くなったんやな。」
「強制避妊手術‥?」
「日本で昔、行われていたんや。」
「ああ‥。」
「その子は女子の球なら大体とれる。ある日、男子から、勝負の声がかかったんや。」
「男子選手から‥?」
「そうや。それでな、その子はその日、生理でな、全然球がとれなかった。」
「ええ‥。」
「でな、本気になった男のバレーボールでな、腕を骨折してしまったんや。」
「医者の話によるとな、その子の腕はもうダメやということやった。もうリベロに戻れん。」
シュエンは下を向いた。
「最後にその子は、変な男と付き合ってしまってな、崖から落とされて殺されたんや。」
「そんな。」
「栄光と名声にしか興味がない男と付き合ってしまった仇ってもんやな。」
「かわいそうに。」
シュエンは泣いた。
「どうや?少しは緊張できたか?」
ジエンは聞いた。
「うん。」
ジエンはシュエンの腕をさわり、言った。
「シュエンの腕なら、どんなに速いバレーボールが当たっても大丈夫や。俺は医者やから、保証する。」
「今までお前が、両親と兄弟から大事にされてきたおかげやと思う。」
ジエンは言った。
「そろそろ円陣を組もうか。」
トンデルが言った。
「おお。」
「行くぞ!!」
「おおす!!」
シュエンは、ゴルゴの強い球をとったが、僅差でチームは負けてしまった。
シュエンは言った。
「最後の球、とれなくてすみません。」
「シュエンだけのせいじゃない。最初から、そんなにうまくいくとは思ってなかった。」
ランウィーは言った。
ジエンは片付けをしながら、体育館の反対側にいるシュエンをちらりと見たが、ランウィーと話しながら、可愛らしく笑っていたので、安心した。
ロシアでも、試合が行われて、いろいろなチームと対戦したセラフィム達は、だんだんと強くなっていた。
数年後、中国1次リーグのバレーボールチームに入る事ができたジエンとシュエン。ロシアのイーゴルとヤコフとセラフィムも同じだった。
中国の対戦相手は日本で、とても弱そうに思えたが、なんとなく苦悩だとかそういう困難を感じさせるチームだった。
手加減しているのかどうかは分からないか、時々、タイミングがずれている。
それがとてもやりずらい。それが技なのかどうか分からないが、難しく感じる。
中国のチームは、直球勝負だった。なんといってもゴルゴがいるので、安心だ。
勝てそうだったので、ゴルゴがシュエンに聞いた。
「出てみるか?」
「はい。」
シュエンは上着を脱いで、着替えた。
日本選手たちはそれを見て、こそこそ話した。
試合は中国が勝利し、試合終了後は、日本選手が足を引きずっていた。
ジエンは笑った。
「あいつ、足を引きずっている。俺なら、どんなに痛くてもこうだぜ。」
ジエンは足を床にドンとし、中国選手は笑った。
だけど、午後の試合で、ジエンの足も痛くなってしまった。
「ああ‥。」
「兄貴、大丈夫か?」
「すまん、ちょっと休むわ。ジャンプ痛がどんなに痛いか、これで分かったわ。」
「人を笑うと、自分も笑われるんや。」
ゴルゴが言った。
「ああ、そうやな。」
ロシアのセラフィムのチームは、パリでの国際試合に出た。
最初の相手はイギリスで、紳士的なプレーだったが、とても速かった。
一回は速くて、止まってしまったが、ワンセット終える頃にはすぐに慣れた。
そういう時に、自分のバレーボールの才能を感じる。
パリの赤ワインは特にうまかった。ロシアにもワイナリーがあるが、風味が違う感じがする。
ロシアのワインも厳しい冬を乗り越えているので、なかなか美味しいが、ヨーロッパのワインは格別だ。しかし、ロシアには、もっといい酒がある。
いろいろな試合を乗り越えた中国とロシアのチームは、オリンピックに出ることになった。
新体操の人が、選手村で技を見せようとして、腰を打ってしまった。
ロシアのセラフィムとヤコフは、見なかったことにした。
いよいよオリンピックの日。
3回勝ったロシアと中国は、あたることになった。
入場のため、男達は歩き出した。
ロシア対中国
背が高いジハンと背が低いシュエンは、2人並んで、観客に手を振ったので、
ロシアの選手は立ち止まってしまった。
ジェントルマンなロシア選手は、仕方なさそうに再び歩き出した。
ロシア選手のセラフィムとヤコフも真似をしようとしたが、
黒髪が舌打ちをしたので、再び後ろに並んだ。
試合前、CMの時間だと思う。
選手たちは、ベンチに座った。
なんとなく、試合前は、見えないはずの景色が見えてしまう。
ゴルゴは座り、指を組んで、うなだれた。
シュエンがジエンに言った。
「兄さん、何かいい話をしてくださいよ。」
「ああ、いいよ。」
ゴルゴが立ち上がったので、シュエンが言った。
「聞いとけ。」
「いや、俺はいいよ。」
「いいから、聞いとけや。」
みんなジエンのまわりに集まった。
「昔、俺にバレーを教えてくれた先輩に、聞いてみた事がある。ボールはなんやと思いますかって。」
「そしたら、先輩はこう言った。ボールはただ遊ぶもんやって。」
「いいか?これはただのゲームや。誰の命もかかっていない、ただのゲームなんや。」
ジエンは言った。
「今日は、国のために戦おう。」
円陣を組んだセラフィムは言った。
「FIGHT!!」
中国の客席にも、ムォンや、姉妹たちが来ていた。
シュエンが言った。
「遊びや言うたけど、今日は勝たないと。」
「まぁ、遊びで勝つんやな。」
中国も円陣を組んだ。
「なんて言えばいい?」
ゴルゴが聞いた。
「さぁ、兄貴決めろや。」
シュエンが言った。
ジエンは言った。
「じゃあ、これや。‥オーケー!!」
勝負の行方はまだである。
End
By Song River
ワンクリックで応援できます。
(ログインが必要です)
(ログインが必要です)