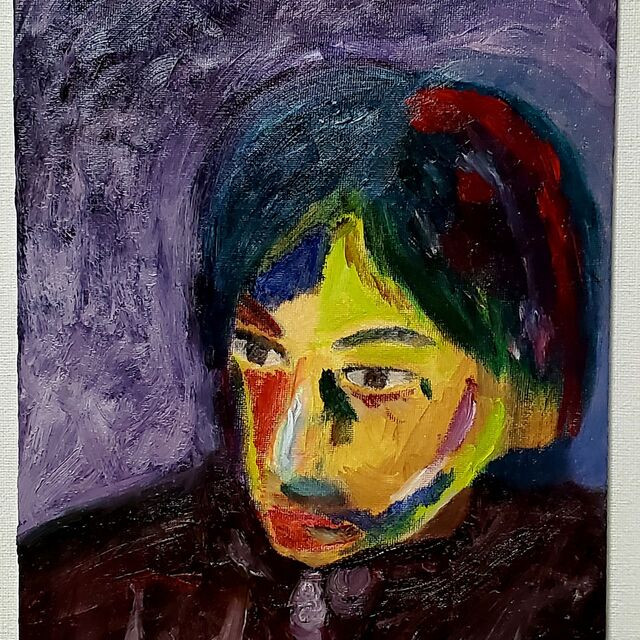彼ひとり
文字数 1,802文字
山の雨は空を白くする。窓の向こう側はもはや別世界だった。彼は煙草を吸いながら思案する。大学生活も残り一年に差し掛かり、そろそろ就活がはじまってしまう。それなのに彼はなにをすればいいのか、なにがしたいのかよく分かっていなかった。それは孤独のときに感じる窮屈な苦しさに似ていた。彼は煙を窓に向かって吐き出す。目の前がさらに白くなっていく。雨はまだやみそうにない。
コーヒーを淹れているときの、湯気に乗って漂う香りが好きだった。だから彼は大学に入ってからずっと同じ喫茶店でバイトをしていた。いつしか彼は仕事にもなれ、友達もでき、ある程度の仕事を任されるようになった。ある日、新しいバイトの子が入ってきた。その子は彼と同じ苗字だった。ただそれだけだったはずなのに。
彼は人を愛するということに懐疑的だった。両親が離婚したとか虐待されていたとかそんな具体的な理由からではなく、自分は他の人とは違う特殊な人間だからだと信じていたからだった。実際に彼は孤独になることが多かった。
「この前ね、山に行ってきたんだ」
バイト先の休憩室でその子は独り言のようにつぶやいた。彼はその言葉が自分に向けられたものか確信がないままそうなんだ、と小さく言った。返事はなかった。彼はスマホに目を落として、山について検索した。
見下していたのかもしれない。または過信か。先日、彼はその子が別のバイトの男と店の裏のゴミ捨て場でキスをしているのを目撃してしまった。翌日、それを店長に告げ口した。店長は面倒くさそうに「そうか」と言った。それだけだった。俺は間違っていない。正しいのは俺で、間違っているのはアイツらだ。それでも彼はバイトを辞めなかった。他の世界に飛び込んでいけるほどの度胸もなかった。それから彼はいつもの孤独をより強く感じるようになった。もしかしたら間違っているのは俺だったのかもしれない。その考えが脳裏に浮かぶたびに、彼は頭の中で昨夜見たAVを思い出した。それはその子に似た女性が山に登っている最中、縄で縛られて犯されるという企画ものだった。
二人が公然として付き合っていることを彼だけが知らなかったということを知ったのはキスを目撃してから半年が過ぎた頃だった。世間はクリスマスカラーで染まり、店では十二月後半のシフトをどうするかでにぎわっていた。
「申し訳ないけど、この二日間通しで出てもらえないかな?」
24日と25日だった。彼は去年もその二日間を通しで出勤した。確かに用事はない。なにもない。それでも彼は素直にうなずくことができなかった。なぜ俺が働かないといけない。なぜ。
「すみません、その日は用事があって」
とっさに出た嘘に彼は少しばかりの罪悪感を覚えたが、長の驚いた顔を見て、かすかな快感を覚えた。
「山に行くんです。彼女と」
悪いのはアイツらで、俺は悪くない。悪いのはこの無能な店長と見る目のないアイツで、俺は悪くない。彼は店長の驚いた顔を思い出すたびに、自然と口角があがる自分を好きになろうと思った。
クリスマスの二日間、彼は家にいた。一人暮らしだったから、気兼ねなく好きなことに没頭しようと思った。彼はスマホに「中世 魔女狩り」最後に「拷問」の文字を入れようか悩んで、やっぱり辞めた。布団に寝転んで中学生のときにはじめて見た動画を二時間かけて調べてから、あきらめていつもと同じ動画で射精した。そのまま眠りこけて、自分は友達がいないということをようやく知った。
山に行こうと思ったのは、そんな自分を変えたかったからかもしれない。彼は年末、田舎の実家に帰省し、近所にあった小さな山に登ろうと思った。小さいとは言っても山は山で、たいした装備もない彼は登山道に雪がちらついているのを見て辞めた。その足で昔よく通った喫茶店に寄った。
「タバコ、吸うようになったんだねえ」
おばちゃんはそう言って笑った。彼は外を眺めていた。雨が降ってきて、室内にいても寒さを感じた。昔ながらの灯油ストーブがパキパキと鳴って、もはやそこには彼ひとりだった。
彼は三が日を経てバイトに戻った。あの二人は年末で辞めたことをそこで知った。彼は少し考えてから、店長に言った。
「来月、実家に帰ることになったので今月いっぱいで辞めたいと思います」
外は晴れていた。店長は分かった、と簡単に言った。彼は店長の目を真っすぐに見つめて、翌日、店に現れず連絡を絶った。
コーヒーを淹れているときの、湯気に乗って漂う香りが好きだった。だから彼は大学に入ってからずっと同じ喫茶店でバイトをしていた。いつしか彼は仕事にもなれ、友達もでき、ある程度の仕事を任されるようになった。ある日、新しいバイトの子が入ってきた。その子は彼と同じ苗字だった。ただそれだけだったはずなのに。
彼は人を愛するということに懐疑的だった。両親が離婚したとか虐待されていたとかそんな具体的な理由からではなく、自分は他の人とは違う特殊な人間だからだと信じていたからだった。実際に彼は孤独になることが多かった。
「この前ね、山に行ってきたんだ」
バイト先の休憩室でその子は独り言のようにつぶやいた。彼はその言葉が自分に向けられたものか確信がないままそうなんだ、と小さく言った。返事はなかった。彼はスマホに目を落として、山について検索した。
見下していたのかもしれない。または過信か。先日、彼はその子が別のバイトの男と店の裏のゴミ捨て場でキスをしているのを目撃してしまった。翌日、それを店長に告げ口した。店長は面倒くさそうに「そうか」と言った。それだけだった。俺は間違っていない。正しいのは俺で、間違っているのはアイツらだ。それでも彼はバイトを辞めなかった。他の世界に飛び込んでいけるほどの度胸もなかった。それから彼はいつもの孤独をより強く感じるようになった。もしかしたら間違っているのは俺だったのかもしれない。その考えが脳裏に浮かぶたびに、彼は頭の中で昨夜見たAVを思い出した。それはその子に似た女性が山に登っている最中、縄で縛られて犯されるという企画ものだった。
二人が公然として付き合っていることを彼だけが知らなかったということを知ったのはキスを目撃してから半年が過ぎた頃だった。世間はクリスマスカラーで染まり、店では十二月後半のシフトをどうするかでにぎわっていた。
「申し訳ないけど、この二日間通しで出てもらえないかな?」
24日と25日だった。彼は去年もその二日間を通しで出勤した。確かに用事はない。なにもない。それでも彼は素直にうなずくことができなかった。なぜ俺が働かないといけない。なぜ。
「すみません、その日は用事があって」
とっさに出た嘘に彼は少しばかりの罪悪感を覚えたが、長の驚いた顔を見て、かすかな快感を覚えた。
「山に行くんです。彼女と」
悪いのはアイツらで、俺は悪くない。悪いのはこの無能な店長と見る目のないアイツで、俺は悪くない。彼は店長の驚いた顔を思い出すたびに、自然と口角があがる自分を好きになろうと思った。
クリスマスの二日間、彼は家にいた。一人暮らしだったから、気兼ねなく好きなことに没頭しようと思った。彼はスマホに「中世 魔女狩り」最後に「拷問」の文字を入れようか悩んで、やっぱり辞めた。布団に寝転んで中学生のときにはじめて見た動画を二時間かけて調べてから、あきらめていつもと同じ動画で射精した。そのまま眠りこけて、自分は友達がいないということをようやく知った。
山に行こうと思ったのは、そんな自分を変えたかったからかもしれない。彼は年末、田舎の実家に帰省し、近所にあった小さな山に登ろうと思った。小さいとは言っても山は山で、たいした装備もない彼は登山道に雪がちらついているのを見て辞めた。その足で昔よく通った喫茶店に寄った。
「タバコ、吸うようになったんだねえ」
おばちゃんはそう言って笑った。彼は外を眺めていた。雨が降ってきて、室内にいても寒さを感じた。昔ながらの灯油ストーブがパキパキと鳴って、もはやそこには彼ひとりだった。
彼は三が日を経てバイトに戻った。あの二人は年末で辞めたことをそこで知った。彼は少し考えてから、店長に言った。
「来月、実家に帰ることになったので今月いっぱいで辞めたいと思います」
外は晴れていた。店長は分かった、と簡単に言った。彼は店長の目を真っすぐに見つめて、翌日、店に現れず連絡を絶った。