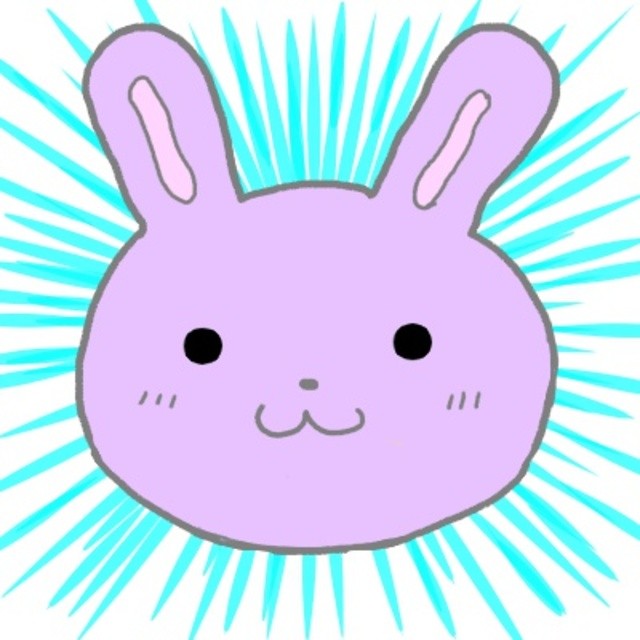第5話 彼女の恋人
文字数 1,628文字
『れむ』は僕にとって、なくてはならない居心地の良い場所になりつつある。通う回数も、週に三回だったのが五回になっていた。
課長はようやくあきらめたのか、定時に退勤する僕を放置している。
一日働いて、通勤電車に揺られ、ほっとできる時間は『れむ』のドアを開ける瞬間だった。
気和さんとおしゃべりして、美味い食事をして、気和さんの淹れてくれるブレンドコーヒーを飲みながら、読書をする。
そのひと時が一番安らいでいた。
「久我さん、お寛ぎのところ失礼します」
気和さんがテーブルの脇に立っていた。コーヒーは注いでくれたばかりなのに、どうしたんだろうと顔を上げると、その傍らには長身の男性が立っていた。
「紹介が遅れてごめんなさい。この店のオーナー兼シェフの、叔父です」
僕は男性を見上げた。
三十代後半ぐらいの年齢。普段厨房にこもっている人物とは思えないほど、野性味あふれる精悍な顔立ちの男だ。
「常連さんだそうですね。いつもありがとうございます。これからも御ひいきに、よろしくお願いします」
低く落ち着いた声は大人の男そのもので、しかも感じがいい。笑顔になると、目尻に皺を刻むのがなんともさわやかだ。
――これが、気和さんの好きな男。
あの日。初めてここへ訪れた晩。暗闇の中で、彼女の体を抱きしめたのは、間違いなくこの男だ。
あの男が、彼女の叔父だったとは。
どう受け答えをして店を出たのだろう。会計を済ませたのも覚えていなかった。ぼんやり歩いていたら、いつのまにか自宅マンションが視界に映った。
鍵を開けて部屋に入ると、浴室へ直行した。バスタブを簡単に洗い、熱い湯を出す。リビングへ行きネクタイをゆるめて、ソファーへ崩れるように座った。
気和さんの恋は、成就することはないだろう。たとえ二人が互いに想い合っていても、この先どうなる? 従兄なら結婚できるが、相手が叔父ではどうにもならない。
仕事の休みはないと答えた、気和さんの顔が浮かぶ。強い意志を感じさせる表情、眼差し。
あのとき僕は、きっと彼女は純粋に叔父の店のためにがんばりたいのだと勝手に解釈していた。けれど、それは肉親の情愛ではなく、ただ、少しでも好きな男の傍にいたいという気持ちの表れだったのだ。
――あの男は、叔父という自分の立場がわかっているのか? 本当に気和さんのことを大事に思っているのか? 気和さんが辛い思いをしなくて済むように、守れるのか……。
ドンッと大きな音にはっと顔を上げる。ローテーブルに自分の拳が叩きつけられたのだ。
しん……と静まり返ったリビングに、荒い呼吸音だけが聞こえる。遅れて、右手がじんじんと痛んだ。
「ふ……ふふ……はは……」
自虐的な笑いが口から漏れる。ひとしきり体を揺すって笑ったあと、長く息を吐き出した。
――何を言ってるんだ、それをおまえが言うのか。妻を何年も笑顔にできずに、置いていかれたお前が……
妻を、娘を、幸せにできない自分に、あの男を責める資格はこれっぽっちもない。
気和さんの闇と、僕の闇は、どちらが深いのだろうか。
――現実は、残酷だな
タイマーの高い音が、僕を現実に引き戻した。浴槽の湯が適量になったようだ。僕は立ち上がると、Yシャツのボタンを外した。
『パパ! ひなも入る!』
何の前触れもなく発作のように、突然比奈の声は聞こえてくる。
「比奈…………」
僕の帰宅が遅い日、たとえ入浴済みでも、比奈は僕と入りたがる。僕はどんなに疲れていても、彼女のお気に入りのおもちゃを沢山持ち込んで、一緒に風呂で遊んだ。きゃっきゃっとはしゃぐ比奈の声が、頭の中でこだまする。
――比奈、比奈……ごめんな、ごめん……
僕は胸を押さえてその場でうずくまり、自分の体を抱きしめながら、その波が引くのをじっと待った。
課長はようやくあきらめたのか、定時に退勤する僕を放置している。
一日働いて、通勤電車に揺られ、ほっとできる時間は『れむ』のドアを開ける瞬間だった。
気和さんとおしゃべりして、美味い食事をして、気和さんの淹れてくれるブレンドコーヒーを飲みながら、読書をする。
そのひと時が一番安らいでいた。
「久我さん、お寛ぎのところ失礼します」
気和さんがテーブルの脇に立っていた。コーヒーは注いでくれたばかりなのに、どうしたんだろうと顔を上げると、その傍らには長身の男性が立っていた。
「紹介が遅れてごめんなさい。この店のオーナー兼シェフの、叔父です」
僕は男性を見上げた。
三十代後半ぐらいの年齢。普段厨房にこもっている人物とは思えないほど、野性味あふれる精悍な顔立ちの男だ。
「常連さんだそうですね。いつもありがとうございます。これからも御ひいきに、よろしくお願いします」
低く落ち着いた声は大人の男そのもので、しかも感じがいい。笑顔になると、目尻に皺を刻むのがなんともさわやかだ。
――これが、気和さんの好きな男。
あの日。初めてここへ訪れた晩。暗闇の中で、彼女の体を抱きしめたのは、間違いなくこの男だ。
あの男が、彼女の叔父だったとは。
どう受け答えをして店を出たのだろう。会計を済ませたのも覚えていなかった。ぼんやり歩いていたら、いつのまにか自宅マンションが視界に映った。
鍵を開けて部屋に入ると、浴室へ直行した。バスタブを簡単に洗い、熱い湯を出す。リビングへ行きネクタイをゆるめて、ソファーへ崩れるように座った。
気和さんの恋は、成就することはないだろう。たとえ二人が互いに想い合っていても、この先どうなる? 従兄なら結婚できるが、相手が叔父ではどうにもならない。
仕事の休みはないと答えた、気和さんの顔が浮かぶ。強い意志を感じさせる表情、眼差し。
あのとき僕は、きっと彼女は純粋に叔父の店のためにがんばりたいのだと勝手に解釈していた。けれど、それは肉親の情愛ではなく、ただ、少しでも好きな男の傍にいたいという気持ちの表れだったのだ。
――あの男は、叔父という自分の立場がわかっているのか? 本当に気和さんのことを大事に思っているのか? 気和さんが辛い思いをしなくて済むように、守れるのか……。
ドンッと大きな音にはっと顔を上げる。ローテーブルに自分の拳が叩きつけられたのだ。
しん……と静まり返ったリビングに、荒い呼吸音だけが聞こえる。遅れて、右手がじんじんと痛んだ。
「ふ……ふふ……はは……」
自虐的な笑いが口から漏れる。ひとしきり体を揺すって笑ったあと、長く息を吐き出した。
――何を言ってるんだ、それをおまえが言うのか。妻を何年も笑顔にできずに、置いていかれたお前が……
妻を、娘を、幸せにできない自分に、あの男を責める資格はこれっぽっちもない。
気和さんの闇と、僕の闇は、どちらが深いのだろうか。
――現実は、残酷だな
タイマーの高い音が、僕を現実に引き戻した。浴槽の湯が適量になったようだ。僕は立ち上がると、Yシャツのボタンを外した。
『パパ! ひなも入る!』
何の前触れもなく発作のように、突然比奈の声は聞こえてくる。
「比奈…………」
僕の帰宅が遅い日、たとえ入浴済みでも、比奈は僕と入りたがる。僕はどんなに疲れていても、彼女のお気に入りのおもちゃを沢山持ち込んで、一緒に風呂で遊んだ。きゃっきゃっとはしゃぐ比奈の声が、頭の中でこだまする。
――比奈、比奈……ごめんな、ごめん……
僕は胸を押さえてその場でうずくまり、自分の体を抱きしめながら、その波が引くのをじっと待った。