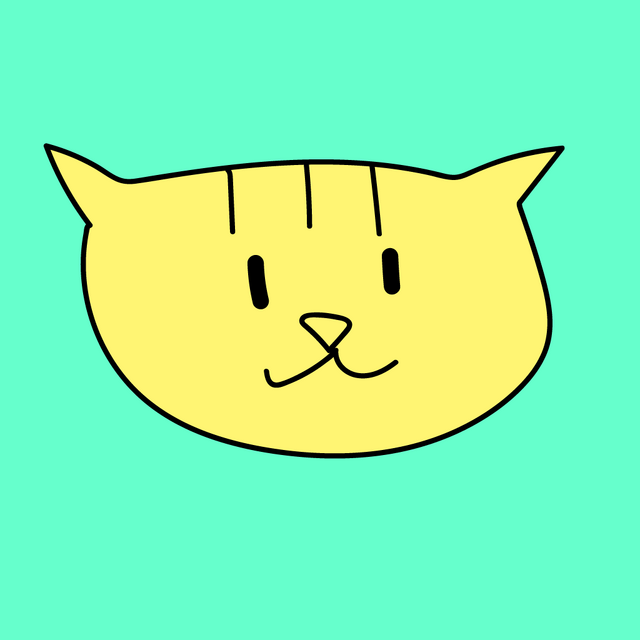第1話
文字数 11,494文字
辺り一面が闇色に染まっている中、私は校門の前に立っていた。
校舎には明かりが一つもなく、教師は全員帰宅したものと思われる。
そろそろ夏は終わってもいい頃であるがまだ秋はやってきていないため、夜風が少ない。もっと涼しいものだと思っていたが期待外れだ。
携帯の明かりを点けて時間を確認すると午前一時。丁度待ち合わせの時間だった。
周囲を見渡すと、強い光を放ちながら人影がこちらに近づいてくる。
シルエットから若い女性だと判別でき、徐々に距離が詰められると、待ち合わせ相手であるアイリだと分かった。
「麻衣、来るの早いね」
「アイリは丁度だね」
アイリは携帯をフラッシュライトモードにし、懐中電灯として使っていた。
互いに夜の学校は初めてで、闇の中でそびえたつ学校を眺める。
どうやって入ろうかと悩んでいると、アイリは閉まっている門に掴まり、手足を上手に使って越えてみせた。私も後に続き、学校の敷地内に侵入した。
アイリの携帯が放つ光を頼りに歩く。
校舎は無視し、一直線に向かった先はプールだった。
夏の終わりではあるが、まだプールの授業はある。
年々、夏は暑さが増しているため、プールの授業は数年前と比べて長くなっている。と、先生が言っていた。
プールの授業日数が以前より増えた、と聞いて喜んでいるのは男子だけだ。
女子は当然ながら文句しか出ない。太い手足、脂肪で膨らんでいる腹、日焼け、落ちる化粧、濡れる髪。特に嫌なのが生理の日だ。体操服に着替えてプール見学をしている姿は、私は生理中なんですと言っているようなもの。もし男子に見られでもしたら、あいつ今生理なんだと陰でこそこそ言われるに違いない。
だから女子は一人で見学をしない。仲の良い友達数人に頼んで、一緒に見学するのだ。
女子が集団でトイレに行く感覚と似ている。
「夜だから怖いけど、わくわくするね」
アイリは楽しそうに言いながらプールサイドに座った。
靴と靴下を脱いで足を水に入れるアイリを真似て私も靴下に手をかけた。
水中に足を入れると、冷たくて一瞬躊躇ってしまうがゆっくりと両足を水に入れる。鞄から飲み物を二つ取り出し、一つをアイリに渡すと「ありがと」と言って受取り、隣に置いた。
ちゃぽちゃぽとアイリの足が奏でる水音だけが聞こえる。
「あー、本当に、死にたい」
揺れる水面を眺めながらアイリは言った。
「死にたいの?」
「もう何もかもが嫌なんだよね」
はぁ、と露骨な溜息を吐いてアイリは上を向いた。
視線の先を追うと、ただ黒いだけで星一つない空がそこにある。
星はない、月もない。
黒くて大きな画用紙が空に張り付いているようだった。
ちらっとアイリを見ると、変わらず上を見ている。
何も面白いものはないのに、何故そんなにじっと空を見ているのだろうか。
もう一度空を見るが、やはり何もない。
趣を感じるような要素は何一つないのに、満天の星を眺めているような顔をしている。
「家に居ると母さんから暴力を振るわれるし、学校にいても居場所はないし、もうこのまま死んでしまいたい」
「そっか」
「麻衣とはさ、学校でずっと一緒にいるわけじゃないじゃん。選択科目は別だし、麻衣には他にも友達がいる。あたしは麻衣しかいないのに」
「友達つくればいいよ」
「今更無理でしょ。もう輪はできてるんだから。麻衣だけなんだよ、小学生の頃から一緒で気を許せる友達は」
何回聞いただろう。
私だって小学生の頃から一緒なのはアイリだけだ。だけど私は他にも友達がいる。それは私が友達をつくろうと思って色んな人に声をかけたり、話しかけられた時は愛想よく返したり社交性ある行動をとったからだ。
友達は簡単につくれる。
にこにこ笑って挨拶をしたり答えたりするだけで好感を持ってもらえる。アイリはそれをしないから、いつまでたっても私以外の友達がつくれない。
「まあ、別に、友達なんていらないけどね。だって馬鹿ばっかりだし。話を聞いてても、レベルが低いんだよ。あたしとは合わない」
「ふうん」
「この前、席替えしたじゃん。班の人間が最悪で、理科室の掃除当番のときに誰一人掃除しないの。あたしだけが掃除してるの。掃除の時間なのに喋ってばっかり。あたしだけがほうきとちりとり持って動いて、終わっても皆お礼すら言わないんだよ」
「そうなんだ」
「教室掃除と違って理科室は先生が監視してないから、喋りたい放題だよ。理科室も監視してほしい。じゃなきゃ不公平だよ。あたしだけ真面目に掃除して、皆は楽しく話してさ。あたしが皆の分も掃除してるなんておかしいじゃん」
じゃあアイリもサボればいいじゃん。
その言葉を呑み込むためにペットボトルの蓋を開けて水を飲む。
「英語の読み合いでペアになった橋本はもっと最悪。会話の読み合いだから二人でやらないといけないのに、あいつずっと後ろの席の二人とふざけててあたしの方なんて見やしない。仕方ないから一人で読んだけど、あいつ何のために授業出てんだろ。真面目にやらないなら学校に来なければいいのに」
小学生の頃はアイリのこういう話を真剣に聞いていた。「そうだそうだ」と同調することでアイリがすっきりすると思っていたからだ。
けれどそれも最初だけ。私には向いてなかった。
英語の件は「橋本はそういう奴なんだから怒るだけ無駄」と、私は思っている。クラスに一人はいるだろう、自分は他と違うとアピールしたい人間。それが橋本なのだ。ムードメーカーを気取って、はっちゃけキャラを確立していると自身で認識している橋本だが、そう思っているのは本人だけで、周りは「頑張ってる感がキツい」と冷めた目で見ているのだ。
アイリは私以外に友達がいないから、橋本がどういう目でクラスメイトに見られているか分かっていない。分かっていれば、怒ることもないのだ。
注目を浴びたくて頑張ってる奴。そう思えば橋本のやることすべてに「あー、はいはい」で片付く。
見ていれば分かりそうなものだが、アイリの観察力では無理か。
「お腹が痛くて保健室に行った時はまたあの一年生がいたし。ほら、あのイケメンの、吉岡だっけ。保健室通いしてる吉岡、顔が良いよね。保健室の先生は吉岡が気に入ってるから頻繁に来させてるみたいだよ。いい歳したおばさんが、ワンチャンあると思ってるのかな?」
どこから仕入れた情報か分からないが、それは大きな誤解だ。
一年生の吉岡といえば、顔が整っていることで少しだけ有名だ。何故少しだけかというと、吉岡は主に保健室登校をしているからだ。だから吉岡の存在を知る人は少ないし、クラスメイトだけど吉岡の顔が分からないという人もいる。
私は保健室に絆創膏を貰いに行った際、偶然吉岡に出会った。確かに顔は整っていて、目を引く容姿だった。
そこから何度か保健室の近くを通ると、鞄を持った吉岡を目にすることがあったので気づいただけだ。
保健室登校をしていることは知られたくないだろうから、誰にもこの話題を出したことはない。彼のクラスメイトならば知っているだろうが、大きな噂になっていないということはクラスメイトも積極的に吹聴していないのだろう。
学年が違うからかもしれないが。
だから一年生の吉岡と、保健室の先生の間に色っぽいものはない。ワンチャンを狙うだとか、そんな話ではない。
しかしここで訂正するつもりはない。
その話は違うよ、と言ったところで今度は違う愚痴を展開させて熱く長く語るのだ。
余計なことは言わないのが吉。
「他の教師たちは見て見ぬ振りでしょ。細川なんて教え子に手を出したって有名じゃん。教え子ってことはきっと十歳以上離れてるってことだよね。キモい」
これも歪曲された話だ。体育の細川先生は確かに教え子と結婚したが、その教え子が社会人になってから籍を入れたのだ。きっかけは同窓会と言っていたから、先生と生徒の関係性の時に交際したのではない。
「馴れ初めが気になるから本人に突撃しよう」と友達が言うので、先生に聞きに行って知ったことだ。
先生に直接聞いていない人が憶測で話をし、そんなねじ曲がった噂が囁かれるようになったのだろう。
「この学校の教師は終わってるよ。どうしてあんな大人たちが教師になれたんだろうね」
「そうだね」
「まあ、生徒も終わってるけど。麻衣はさ、いつまで道宮たちとつるんでるの?」
不満を見せまいとしているが、声色と下手な表情から「道宮たちと友達をやめろ」と言いたいのだと察する。
私が普段一緒にいる友達は道宮鏡花を筆頭とする派手な集団だ。周囲からはギャルだと言われるような、目立つ女子生徒たちだ。派手な頭髪は校則で厳しく禁じられているため、金髪にはしていないが、赤に近い茶髪やピアスが目立ち、学年で一番派手なグループだった。
一番派手ということは、一番影響力があるということ。クラスで彼女たちの意見は必ず通るし、先生たちとも仲が良い。見た目によらず成績は悪くなく、テスト期間は放課後集まって勉強をしている。
「麻衣は大人しいのに、何であんな奴等と仲良くしてるの? はっきり言って、あの中で麻衣は浮いてるよ」
「そうかな」
「そうだよ。麻衣とあいつ等は住む世界が違うんだよ」
この話は何十回と聞いた。もしかしたら百回を超えたかもしれない。
「麻衣はさ、あんな奴等じゃなくてあたしと居る方が良いと思うな。ほら、あたしたち好み似てるし、大人しめじゃん?」
「そうかな」
「そうだよ」
私が道宮たちと仲良くしているのは、一緒にいて気楽だから。それと、権力がある人間と仲良くする方がどう考えても今後の役に立つ。
友達が多く、先生と仲が良く、自己主張がはっきりしていて、仲間意識が強い道宮たち。それに比べてアイリは友達がいないし、成績は中の下。
どちらと仲良くするかなんて馬鹿でも分かる。
目立つグループに所属している私と、友達がいないアイリ。互いの立っている場所に上下ができている。それが気に入らないのだろう。アイリがいる場所まで堕ちて来いと、そう言いたいのだろう。
当然、それはできない。
道宮たちの場所は居心地が良いし、都合も良い。
私たちは小学生の頃から通っている学校が同じなだけで、それ以上ではない。
アイリは私のことを親友だと思っているかもしれないが、私は違う。知り合ってから結構な時間が経ったので取り敢えず友達と認識しているが、親友ではない。
私しか友達がいないアイリとしては、私を親友だと思うのも無理はないが、それは一方通行だ。
「先週、道宮に話しかけられたんだけど、絶対あたしのこと馬鹿にしてるよね。ねぇ、道宮何か言ってたでしょ?」
「何かって?」
「あたしのこと、言ってたでしょ。きっとブスとか根暗とかそんなこと言ってたんじゃないの?」
「何も言ってなかったよ」
「絶対嘘だ。絶対何か言ってるよ。気を遣わなくていいから、本当のことを教えて」
「本当に何も言ってないよ」
「はぁ。麻衣は優しいから、言えないんだよね。それが麻衣の長所だけどさ。でも言ってくれた方がすっきりするんだよね」
はぁ、と再びため息を吐くアイリは自分の立ち位置をやはり理解していない。
クラスの隅でぽつんと座っているアイリに、道宮が興味を示すはずがない。道宮が「今日愛利栖ちゃんと喋ったんだよ」などと話題に出す程アイリのことを気にしていない。
道宮に話しかけられたといっても、どうせ「次の授業なんだっけ?」「そこ退いてくれる?」「これ落としたよ」のような一言に決まっている。道宮に何を言われたのかを話さないのがその証拠だ。
道宮の立場になって考えてほしい。自分が学年で目立つ存在だとして、教室で誰とも喋らず独りでいる人間に興味を持って話しかけるだろうか。
独りは可哀想だ。話しかけてあげよう。そんな善意があれば少しくらいは話してあげるのかもしれないが、そんな善意を施す暇があるなら友達と楽しくはしゃぐ方を選ぶのが道宮だ。小学生ではないのだから会話をしたいなら自分から話しかけるはずなので、独りでいるのは独りが好きだからだ。道宮ならきっとそう思っているだろう。
好きで独りになっている人間と絡もうとしない。
これまでも道宮からアイリの話題は出なかったし、私も出したことはない。
他愛もないやりとりをしたくらいで道宮の気を引けるなんて思わないことだ。
「麻衣は大人しめな子と一緒にいることが多かったのに、どうして道宮たちと友達になったの?」
「一緒にいて楽しいからだよ」
「……ふうん。でも麻衣、浮いてるよ。あの中で麻衣だけ大人しいじゃん。なんかいじめられてるみたいに見えるよ」
「そう? 私は楽しくやってるよ」
「本当に? でも道宮たちのために自動販売機で大量のペットボトル買ってるよね?」
「じゃんけんで負けたからだよ」
「それ、いじめじゃないの?」
「違うよ」
「麻衣は優しいからなぁ」
大量のペットボトルではなく、私含めた四人の飲み物だ。
四本のペットボトルを抱えていただけでいじめに遭っていると指摘されるとは、道宮も驚きだろう。
友達がいないアイリには分からないかもしれないが、これは普通のことだ。
私たちの教室があるのは校舎の四階で、自動販売機は一階にある。校内に自動販売機は二台のみで、しかも並べて設置されている。
昼休憩に自動販売機が混みあうことは毎日のことであり、四人でぞろぞろ買いに行くよりも一人で四人分を買う方が迷惑にならない。
例えば私が二日連続でじゃんけんに負けたら、三日目からは配慮してくれて私以外がじゃんけんをする。
さすがに六本も七本も一人で持てないので、昼ご飯を一緒に食べるメンバー内で飲み物係として二人選出するのだ。
私一人が飲み物を買いに行っているのではないし、いじめでもない。
「麻衣が道宮たちと一緒にいると、いじめられてるのか心配になるんだよね」
「大丈夫だよ」
「心配で心配で死にそうになる」
「そっか」
「あー、死にたい」
アイリは隣に置いていたペットボトルのキャップを開け、ごくごくと喉を鳴らして水を飲む。
飲み終えると「ぷはっ」と声を出し、軽く口元を親指で拭っていた。
「はぁ」
ペットボトルを置くと、今日何度目かの溜息を吐いた。
特に反応をしないでいると、今度は先程に比べて長い溜息を吐いた。
「どうしたの?」
そう言うと、また溜息を吐き、神妙な面持ちで「実はね」とちらちら視線を私に寄こし、言おうかどうか躊躇っている様子だった。
催促せずに黙っていると、アイリは小さく深呼吸した。
「実は、母さんからの暴力が絶えなくてさ」
先程とは打って変わって弱々しそうに笑った。
「あたしが良い子に育てばよかったんだけどね」
アイリは足をつうっと動かして水面に静かな波紋をつくる。
その仕草がか弱い女子を演出していた。
アイリの母親は早くに離婚し、女手一つで今までやってきた。
昔、一度だけアイリにしつこく誘われて家まで遊びに行ったことがある。どこからどう見ても、お金に困っている人たちが住む外観のアパートだった。
隣の部屋からは髪も髭も手入れなんてしていないような中年のおじさんが、茶色く汚れた服を着て左右で色が違うスリッパをずりずりと音を立てながら出てきたのは印象深い。
家の中は上手く表現できない匂いが充満していた。田舎のおばあちゃん家の匂いと似たものだった。
その時、アイリの母はいなくて二人で過ごしたけど、ゲームがないしテレビもない。特にすることなく、ただ喋っていただけだ。喋るだけならアイリの家じゃなくてもできるのに、と幼いながらに思ったものだ。
朝から晩まで娘のために働いていれば、過労で八つ当たりもしたくなるのかもしれない。私は働いたことがないから想像できないけど、育児放棄のニュースは度々見かける。綺麗な服を着て、学校に通えて、ご飯を食べることができているのだから、アイリはまだマシだと思う。私は両親から暴力を振るわれたことはないし、恵まれた環境にいる。
プールの授業でアイリの肌を見たことがあるけど、傷も痣もなかった。見えないところにあるのかもしれないが、アイリを可哀想だと思ったことはない。
「この名前だってさ、おかしいでしょ。普通子どもに愛利栖って付ける? 外国っぽい名前を無理やり漢字にしてさぁ」
「良い名前だと思うけどね」
「愛利栖が? じゃあ麻衣がこの名前貰ってよ。あたしは麻衣みたいな普通の名前がよかった」
そう言って俯きながらまた「死にたい」と呟く。
私だったら愛利栖という名前を付けられてもいい。変わった名前で覚えやすいし、他の人とは違うから被らなくていいと思う。漢字を見てアイリスと読めないこともない。
アイリの心まで読み取ることはできないが、アイリが嫌なのは名前ではなく名前による周囲の反応ではないだろうか。
自己紹介で自分の名前を言った時、「え? 何て?」「日本人?」「キラキラネームじゃん」という反応が多数だろう。しかし名前が麻衣であったなら「へえ」で終わるのだ。
もしもアイリにもっと社交性があれば名前をきっかけにして友達をつくれただろう。私だったらそうする。名前にインパクトがあるからその場で覚えてもらえる。それを利用しない手はない。そうやって徐々に輪を広げていけばいいだけなのに、アイリにはその能力がない。
それ故に皆最初に興味を持つものの、アイリが控え目な人だと知ると興味が失せたとばかりに目を離す。
小学校高学年の頃。放課後、忘れ物を取りに教室へ行くと男子たちが「クラスで一番可愛い子」と大きく黒板に書き、ランキングをつくって遊んでいた。一位はクラスの中で最も可愛い子だったので納得した。教室に入るのを躊躇っていると、とある男子がにやにやと「アイリスちゃんはー?」と声を出し、その場の男子は全員笑い始めた。「アイリスちゃんは圏外でーす」「名前負けだしな」「アイリスっち、暗すぎて名前と合ってないわー」ぎゃはぎゃはと嫌な笑い方で楽しんでいた彼等の気持ちは、分からなくもない。
目立ったいじめはなかったものの、陰で笑われていたことは事実だ。それは恐らく、私だけでなく他のクラスメイトも気づいていたことだろう。
彼等の会話の節々に、名前こそ出さないものの、アイリを嘲笑するような発言があった。
アイリの耳には入っていないだろうが、皆なんとなくアイリの立ち位置を理解していた。
しかしそれは小学生で終了した。小学校では学年に三組しかなかったのが、中学生になると七組もあった。通う生徒数が増えると、小学生の頃にはアイリしかいなかったキラキラネームの子がちらほらと現れたのだ。アイリよりも印象に残る名前を持つ子がいることで、アイリの存在は霞んでいった。そこからは陰で話題にすらされなくなった。
アイリが思っている以上に、誰もアイリを気にしていない。アイリは自意識過剰と被害妄想を兼ね備えているのだ。
「ご飯の準備をしておけだの、掃除をしろだの、買い出しに行けだの、洗濯しろだの、あたしのこと召使だと思ってるの」
「でも、お母さんは働いてるんでしょう?」
「娘に家事をさせる親ってどうなの? 普通なの? 麻衣は毎日ご飯つくったり掃除したり、家事やってる?」
「やってないよ」
「ほらね、普通はやらないよ。だって娘は召使じゃないもん」
私は父がサラリーマンで母が専業主婦であるため、母が家事をしている。娘の私は学校に通うだけ。しかしアイリの家庭は違う。母一人が働きに出ているのだから、家事全般を娘に託したいと思うのはごく自然のことなのかもしれない。
労働も家事も母一人でやればいい、と聞こえ、私は「んー」と微妙な相槌しか返せなかった。
「麻衣には分からないか」
「そうかも」
「麻衣のとこは幸せな家庭だもんね、あたしの家とは違って。あぁ、死にたい。変な名前を付けられて、家事を強要されて。家でも学校でも、あたしの居場所なんてないんだ」
毎度思うが、私はその言葉に何と返すのが正解なのだろう。
肯定しても否定しても「あたしの気持ちなんて分からないくせに」と言われそうだ。
だからいつも私は黙る。慰めると話は長引くし、助言すると顔を顰める。
恐らく何も返さないのが無難なのだ。
がぶがぶと水を飲み、「ぷっはぁ」と飲み終えた後に息を吐くアイリは、水に浸けていた足を引き抜き、三角座りをして腕に顎を乗せ「死にたい」と小さく呟く。
「大丈夫だよアイリ」
「何が?」
「きっと大丈夫」
「何が大丈夫なのよ。あたしはもうボロボロなんだよ」
「大丈夫だよ」
「麻衣には分からないよ」
大丈夫、と言ってみたがやはりお気に召さないようだ。大丈夫と言ったことがスイッチを押してしまったようで、アイリはいかに自分が恵まれていないのかを語り始めた。
こうなるともう止まらない。次から次へと漏れ出る負の言葉たち。私は耳を塞いでいるわけでもないのに、何故かアイリの話していることが耳に入ってこない。完全なシャットアウトだった。
アイリの声をBGMに、夜のプールを眺める。
昼間は綺麗な水色を映しているのに、今はまるで沼のように黒ずんでいる。ぽつんと道路脇にある灯りが水の波紋を浮かび上がらせている。
貧乏ゆすりをすると、私の足を中心に水面が揺れる。
暫く視線を足元にやっていると、BGMが止んだ。
ふと隣を見ると、アイリはこくりこくりと眠りの舟を漕いでいた。瞼は閉じられていて、数秒もすれば意識を持っていかれるだろう。
アイリの頭に軽く手を当てて、私の膝の上に倒れるように誘導すると、抵抗なくゆっくりと私の太腿に頭が乗った。
やっと眠った。
入れる量を間違えたのかと思っていたが、杞憂だった。
アイリに渡したペットボトルは空になっており、水に溶けた睡眠薬はすべて摂取されている。
睡眠薬なんて初めて購入したから効き目がどの程度か、いつ眠るのか疑問ではあったが今こうして夢の中にいるアイリを見ると、薬としての役割は果たしているようだ。
決断するのに、長い時間がかかった。
いつかいつか、と思って実行するのに時間がかかってしまった。
アイリは私を優しいと言うが、道宮に言わせれば私は人に関心を持たない女らしい。愉快な話に花を咲かせている中で道宮から突然落とされた発言に、あの時の私は反応が遅れた。
「麻衣はさ、人に興味ないよね」
「そんなことないよ」
「あ、そっか。間違えた。仲が良い人間には半分興味を持つけど半分無関心なんだよ」
否定はできなかった。
道宮と仲良くしているのは楽しいという感情と使えるという感情の二つが混ざっているからだった。
それが道宮の言う半分なのだろう。
「仲良くない奴に興味ないのは皆同じだけど、麻衣は仲良い子に対しても半分は興味ないんだよ」
言い返さない私を道宮は笑った。
「うちらは楽しいから麻衣といるんだから、別に責めてないよ」
「そう」
一緒にいると伝わってしまうものなのか。
罪悪感がちくりと胸を刺した。
登校して下校するまでの間ほとんど一緒にいるのだから、それが毎日続けば薄々感づいても不思議ではない。
知ってもなお道宮は今まで通りに接してくれ、これが友達というものかとじんわりと温かくなった。
アイリは道宮よりも長い間知っている。アイリに対して愛想のない言動をしていた自覚はあるが、アイリがそれを指摘することはなかった。
それもそのはず、アイリは私を友達として扱っていなかった。
母に暴力を振るわれた、クラスメイトが悪口を言っていた、笑っていた、嫌なことがあった、と私にぶつけるだけ。私が何か言おうものなら「でも」「だって」「麻衣には分からない」と言って、また話が元に戻る。私を人形だとでも思っているのだろう。黙って聞く、相槌を打つ。これ以外求められていないのだ。
私が道宮たちと仲良くしているのを嫌がるのは、唯一友達である私が他の友達と仲良くしているのが気に食わないだけだ。独占欲が顔を覗かせているのだ。
自分は独りなのに、どうして麻衣は目立つ人たちと仲良くしているのか。独占欲、嫉妬、羨望が入り混じった眼差しを向けられていた。
痛い視線を背中に感じながら、私は無視し続けた。
学校で話しかけられたくはなかった。誰とも喋らない根暗なクラスメイトと友達だと思われたら面倒だからだ。アイリと話しながら道宮たちと話すことなんてできない。アイリと道宮たちは性格から何もかもが真逆なのだから、合うはずがない。私の学校生活の足を引っ張ることしかできないのだから、アイリに話しかけられないよう無視を続けていた。
アイリから私に話しかけることはなく、私から話しかけることもなかったため、アイリとも道宮とも丁度良い距離感を保つことができた。
けれどそれももう終わり。
やっと終わるのだ。
アイリは長年、私の心に引っかかる異物だった。この異物が除去されたら楽なのに、と思っていた。
それが今日、やっと取り出せそうだ。
耳にたこができる程聞いたアイリの言葉。
「死にたい」
その度に、じゃあ死ねばいいのにと呆れた。
死にたいのなら死ねばいい。友達をつくりたいのならつくればいい。そうしないのは、アイリに実行する気がないからだ。
面倒な性格。
だから友達がいない。
近くの蛇口で水を出し、アイリのペットボトルを洗う。
プールサイドに置いたままのアイリを引っ張り、ちゃぽ、と可愛らしい水音を立てながらプールに入水させた。
私は座ったまま、両足でアイリの後頭部を踏みつける。
その恰好のまま時間が過ぎると、呼吸ができないことに気づいたのか、アイリが急に動き始めた。
ばしゃばしゃ、ばたばた、ばしゃばしゃ。
両手両足を使いぐっとアイリを押さえつける。
どのくらいそうしていたか分からないが、徐々に力が抜けていくアイリは、ついに動きを止めた。
でも、まだ生きているのかもしれない。
死んだ振りをしているのかもしれないから、手も足もアイリから離さずにいた。
「もういいかな?」
ゆっくりとアイリを放し、両足で体を蹴ると、アイリはぷかぷか浮かんだままプールを漂う。
私は持ってきたタオルで濡れた部分を拭き、靴下と靴を履いた。
帰ろうかと体の向きを変えると、アイリのペットボトルが目に入った。
そうだった、忘れていた。
そのペットボトルにほんの少しプールの水を入れて、アイリの死体近くに投げた。
自分のペットボトルを持って、学校を去った。
死にたいというから殺してあげた。
アイリの言う通り、確かに私は優しい。
死にたい、死にたい、と幾度となく口にしながら実行できないでいるアイリのためを思って息の根を止めてあげたのだから。
そして明日か明後日にはアイリを思ってクラスメイトはホームルームにでも黙祷するだろう。
友達でもなかった人たちがアイリのために目を閉じて祈る時間を共にするのだ。きっとアイリも喜ぶだろう。
数日経てばアイリの存在を忘れ、楽しい日々を送るだろうが、一時でもアイリのための時間が確保されて良かったね。
アイリの母も不出来な娘がいなくなって肩の荷が下りるもしれない。
私も心のつっかえがなくなって、清々しい気持ちだ。
以前から「死にたいなら死ねばいいのに。私が殺してあげようかな」と考えていたのだが、方法が決まらずなかなか行動に移すことができなかった。
何故今日だったのか、特に意味はない。
昨日ふと思いついたのだ。そろそろなんじゃないか、と。
アイリが死んで悲しい、とは思わないが安らかに眠ってほしい。
ドラマでよく見かけるやつをやってあげた方がいいかな。
アイリの席に花瓶を置いて、花を一本供えよう。
供え物の花はどんなのが一般的だろう。葬式なんてまだ一回しか経験していない。墓参りの際に花なんて気にしたことがないから分からない。
薔薇は駄目だろう。華やか過ぎて先生に怒られる。
道端に咲いている花はすぐにバレそうだから、これも駄目だ。
供えるのだから、花弁の色も気をつけないといけないのかな。
棺に入るときは白い服だろうから、白い花がいいだろうか。
そうだ、百合にしよう。
決まりだ。
帰宅後、学校に持って行く財布の中に五千円札を入れて鞄にしまった。百合の花がいくらなのか分からないけれど、五千円もあれば足りるだろう。
明日、学校の帰りにでも花屋へ寄ろう。
学校で仲良くしているわけでもないクラスメイトのために花を供えるなんて、やっぱり私は優しいのかもしれない。
校舎には明かりが一つもなく、教師は全員帰宅したものと思われる。
そろそろ夏は終わってもいい頃であるがまだ秋はやってきていないため、夜風が少ない。もっと涼しいものだと思っていたが期待外れだ。
携帯の明かりを点けて時間を確認すると午前一時。丁度待ち合わせの時間だった。
周囲を見渡すと、強い光を放ちながら人影がこちらに近づいてくる。
シルエットから若い女性だと判別でき、徐々に距離が詰められると、待ち合わせ相手であるアイリだと分かった。
「麻衣、来るの早いね」
「アイリは丁度だね」
アイリは携帯をフラッシュライトモードにし、懐中電灯として使っていた。
互いに夜の学校は初めてで、闇の中でそびえたつ学校を眺める。
どうやって入ろうかと悩んでいると、アイリは閉まっている門に掴まり、手足を上手に使って越えてみせた。私も後に続き、学校の敷地内に侵入した。
アイリの携帯が放つ光を頼りに歩く。
校舎は無視し、一直線に向かった先はプールだった。
夏の終わりではあるが、まだプールの授業はある。
年々、夏は暑さが増しているため、プールの授業は数年前と比べて長くなっている。と、先生が言っていた。
プールの授業日数が以前より増えた、と聞いて喜んでいるのは男子だけだ。
女子は当然ながら文句しか出ない。太い手足、脂肪で膨らんでいる腹、日焼け、落ちる化粧、濡れる髪。特に嫌なのが生理の日だ。体操服に着替えてプール見学をしている姿は、私は生理中なんですと言っているようなもの。もし男子に見られでもしたら、あいつ今生理なんだと陰でこそこそ言われるに違いない。
だから女子は一人で見学をしない。仲の良い友達数人に頼んで、一緒に見学するのだ。
女子が集団でトイレに行く感覚と似ている。
「夜だから怖いけど、わくわくするね」
アイリは楽しそうに言いながらプールサイドに座った。
靴と靴下を脱いで足を水に入れるアイリを真似て私も靴下に手をかけた。
水中に足を入れると、冷たくて一瞬躊躇ってしまうがゆっくりと両足を水に入れる。鞄から飲み物を二つ取り出し、一つをアイリに渡すと「ありがと」と言って受取り、隣に置いた。
ちゃぽちゃぽとアイリの足が奏でる水音だけが聞こえる。
「あー、本当に、死にたい」
揺れる水面を眺めながらアイリは言った。
「死にたいの?」
「もう何もかもが嫌なんだよね」
はぁ、と露骨な溜息を吐いてアイリは上を向いた。
視線の先を追うと、ただ黒いだけで星一つない空がそこにある。
星はない、月もない。
黒くて大きな画用紙が空に張り付いているようだった。
ちらっとアイリを見ると、変わらず上を見ている。
何も面白いものはないのに、何故そんなにじっと空を見ているのだろうか。
もう一度空を見るが、やはり何もない。
趣を感じるような要素は何一つないのに、満天の星を眺めているような顔をしている。
「家に居ると母さんから暴力を振るわれるし、学校にいても居場所はないし、もうこのまま死んでしまいたい」
「そっか」
「麻衣とはさ、学校でずっと一緒にいるわけじゃないじゃん。選択科目は別だし、麻衣には他にも友達がいる。あたしは麻衣しかいないのに」
「友達つくればいいよ」
「今更無理でしょ。もう輪はできてるんだから。麻衣だけなんだよ、小学生の頃から一緒で気を許せる友達は」
何回聞いただろう。
私だって小学生の頃から一緒なのはアイリだけだ。だけど私は他にも友達がいる。それは私が友達をつくろうと思って色んな人に声をかけたり、話しかけられた時は愛想よく返したり社交性ある行動をとったからだ。
友達は簡単につくれる。
にこにこ笑って挨拶をしたり答えたりするだけで好感を持ってもらえる。アイリはそれをしないから、いつまでたっても私以外の友達がつくれない。
「まあ、別に、友達なんていらないけどね。だって馬鹿ばっかりだし。話を聞いてても、レベルが低いんだよ。あたしとは合わない」
「ふうん」
「この前、席替えしたじゃん。班の人間が最悪で、理科室の掃除当番のときに誰一人掃除しないの。あたしだけが掃除してるの。掃除の時間なのに喋ってばっかり。あたしだけがほうきとちりとり持って動いて、終わっても皆お礼すら言わないんだよ」
「そうなんだ」
「教室掃除と違って理科室は先生が監視してないから、喋りたい放題だよ。理科室も監視してほしい。じゃなきゃ不公平だよ。あたしだけ真面目に掃除して、皆は楽しく話してさ。あたしが皆の分も掃除してるなんておかしいじゃん」
じゃあアイリもサボればいいじゃん。
その言葉を呑み込むためにペットボトルの蓋を開けて水を飲む。
「英語の読み合いでペアになった橋本はもっと最悪。会話の読み合いだから二人でやらないといけないのに、あいつずっと後ろの席の二人とふざけててあたしの方なんて見やしない。仕方ないから一人で読んだけど、あいつ何のために授業出てんだろ。真面目にやらないなら学校に来なければいいのに」
小学生の頃はアイリのこういう話を真剣に聞いていた。「そうだそうだ」と同調することでアイリがすっきりすると思っていたからだ。
けれどそれも最初だけ。私には向いてなかった。
英語の件は「橋本はそういう奴なんだから怒るだけ無駄」と、私は思っている。クラスに一人はいるだろう、自分は他と違うとアピールしたい人間。それが橋本なのだ。ムードメーカーを気取って、はっちゃけキャラを確立していると自身で認識している橋本だが、そう思っているのは本人だけで、周りは「頑張ってる感がキツい」と冷めた目で見ているのだ。
アイリは私以外に友達がいないから、橋本がどういう目でクラスメイトに見られているか分かっていない。分かっていれば、怒ることもないのだ。
注目を浴びたくて頑張ってる奴。そう思えば橋本のやることすべてに「あー、はいはい」で片付く。
見ていれば分かりそうなものだが、アイリの観察力では無理か。
「お腹が痛くて保健室に行った時はまたあの一年生がいたし。ほら、あのイケメンの、吉岡だっけ。保健室通いしてる吉岡、顔が良いよね。保健室の先生は吉岡が気に入ってるから頻繁に来させてるみたいだよ。いい歳したおばさんが、ワンチャンあると思ってるのかな?」
どこから仕入れた情報か分からないが、それは大きな誤解だ。
一年生の吉岡といえば、顔が整っていることで少しだけ有名だ。何故少しだけかというと、吉岡は主に保健室登校をしているからだ。だから吉岡の存在を知る人は少ないし、クラスメイトだけど吉岡の顔が分からないという人もいる。
私は保健室に絆創膏を貰いに行った際、偶然吉岡に出会った。確かに顔は整っていて、目を引く容姿だった。
そこから何度か保健室の近くを通ると、鞄を持った吉岡を目にすることがあったので気づいただけだ。
保健室登校をしていることは知られたくないだろうから、誰にもこの話題を出したことはない。彼のクラスメイトならば知っているだろうが、大きな噂になっていないということはクラスメイトも積極的に吹聴していないのだろう。
学年が違うからかもしれないが。
だから一年生の吉岡と、保健室の先生の間に色っぽいものはない。ワンチャンを狙うだとか、そんな話ではない。
しかしここで訂正するつもりはない。
その話は違うよ、と言ったところで今度は違う愚痴を展開させて熱く長く語るのだ。
余計なことは言わないのが吉。
「他の教師たちは見て見ぬ振りでしょ。細川なんて教え子に手を出したって有名じゃん。教え子ってことはきっと十歳以上離れてるってことだよね。キモい」
これも歪曲された話だ。体育の細川先生は確かに教え子と結婚したが、その教え子が社会人になってから籍を入れたのだ。きっかけは同窓会と言っていたから、先生と生徒の関係性の時に交際したのではない。
「馴れ初めが気になるから本人に突撃しよう」と友達が言うので、先生に聞きに行って知ったことだ。
先生に直接聞いていない人が憶測で話をし、そんなねじ曲がった噂が囁かれるようになったのだろう。
「この学校の教師は終わってるよ。どうしてあんな大人たちが教師になれたんだろうね」
「そうだね」
「まあ、生徒も終わってるけど。麻衣はさ、いつまで道宮たちとつるんでるの?」
不満を見せまいとしているが、声色と下手な表情から「道宮たちと友達をやめろ」と言いたいのだと察する。
私が普段一緒にいる友達は道宮鏡花を筆頭とする派手な集団だ。周囲からはギャルだと言われるような、目立つ女子生徒たちだ。派手な頭髪は校則で厳しく禁じられているため、金髪にはしていないが、赤に近い茶髪やピアスが目立ち、学年で一番派手なグループだった。
一番派手ということは、一番影響力があるということ。クラスで彼女たちの意見は必ず通るし、先生たちとも仲が良い。見た目によらず成績は悪くなく、テスト期間は放課後集まって勉強をしている。
「麻衣は大人しいのに、何であんな奴等と仲良くしてるの? はっきり言って、あの中で麻衣は浮いてるよ」
「そうかな」
「そうだよ。麻衣とあいつ等は住む世界が違うんだよ」
この話は何十回と聞いた。もしかしたら百回を超えたかもしれない。
「麻衣はさ、あんな奴等じゃなくてあたしと居る方が良いと思うな。ほら、あたしたち好み似てるし、大人しめじゃん?」
「そうかな」
「そうだよ」
私が道宮たちと仲良くしているのは、一緒にいて気楽だから。それと、権力がある人間と仲良くする方がどう考えても今後の役に立つ。
友達が多く、先生と仲が良く、自己主張がはっきりしていて、仲間意識が強い道宮たち。それに比べてアイリは友達がいないし、成績は中の下。
どちらと仲良くするかなんて馬鹿でも分かる。
目立つグループに所属している私と、友達がいないアイリ。互いの立っている場所に上下ができている。それが気に入らないのだろう。アイリがいる場所まで堕ちて来いと、そう言いたいのだろう。
当然、それはできない。
道宮たちの場所は居心地が良いし、都合も良い。
私たちは小学生の頃から通っている学校が同じなだけで、それ以上ではない。
アイリは私のことを親友だと思っているかもしれないが、私は違う。知り合ってから結構な時間が経ったので取り敢えず友達と認識しているが、親友ではない。
私しか友達がいないアイリとしては、私を親友だと思うのも無理はないが、それは一方通行だ。
「先週、道宮に話しかけられたんだけど、絶対あたしのこと馬鹿にしてるよね。ねぇ、道宮何か言ってたでしょ?」
「何かって?」
「あたしのこと、言ってたでしょ。きっとブスとか根暗とかそんなこと言ってたんじゃないの?」
「何も言ってなかったよ」
「絶対嘘だ。絶対何か言ってるよ。気を遣わなくていいから、本当のことを教えて」
「本当に何も言ってないよ」
「はぁ。麻衣は優しいから、言えないんだよね。それが麻衣の長所だけどさ。でも言ってくれた方がすっきりするんだよね」
はぁ、と再びため息を吐くアイリは自分の立ち位置をやはり理解していない。
クラスの隅でぽつんと座っているアイリに、道宮が興味を示すはずがない。道宮が「今日愛利栖ちゃんと喋ったんだよ」などと話題に出す程アイリのことを気にしていない。
道宮に話しかけられたといっても、どうせ「次の授業なんだっけ?」「そこ退いてくれる?」「これ落としたよ」のような一言に決まっている。道宮に何を言われたのかを話さないのがその証拠だ。
道宮の立場になって考えてほしい。自分が学年で目立つ存在だとして、教室で誰とも喋らず独りでいる人間に興味を持って話しかけるだろうか。
独りは可哀想だ。話しかけてあげよう。そんな善意があれば少しくらいは話してあげるのかもしれないが、そんな善意を施す暇があるなら友達と楽しくはしゃぐ方を選ぶのが道宮だ。小学生ではないのだから会話をしたいなら自分から話しかけるはずなので、独りでいるのは独りが好きだからだ。道宮ならきっとそう思っているだろう。
好きで独りになっている人間と絡もうとしない。
これまでも道宮からアイリの話題は出なかったし、私も出したことはない。
他愛もないやりとりをしたくらいで道宮の気を引けるなんて思わないことだ。
「麻衣は大人しめな子と一緒にいることが多かったのに、どうして道宮たちと友達になったの?」
「一緒にいて楽しいからだよ」
「……ふうん。でも麻衣、浮いてるよ。あの中で麻衣だけ大人しいじゃん。なんかいじめられてるみたいに見えるよ」
「そう? 私は楽しくやってるよ」
「本当に? でも道宮たちのために自動販売機で大量のペットボトル買ってるよね?」
「じゃんけんで負けたからだよ」
「それ、いじめじゃないの?」
「違うよ」
「麻衣は優しいからなぁ」
大量のペットボトルではなく、私含めた四人の飲み物だ。
四本のペットボトルを抱えていただけでいじめに遭っていると指摘されるとは、道宮も驚きだろう。
友達がいないアイリには分からないかもしれないが、これは普通のことだ。
私たちの教室があるのは校舎の四階で、自動販売機は一階にある。校内に自動販売機は二台のみで、しかも並べて設置されている。
昼休憩に自動販売機が混みあうことは毎日のことであり、四人でぞろぞろ買いに行くよりも一人で四人分を買う方が迷惑にならない。
例えば私が二日連続でじゃんけんに負けたら、三日目からは配慮してくれて私以外がじゃんけんをする。
さすがに六本も七本も一人で持てないので、昼ご飯を一緒に食べるメンバー内で飲み物係として二人選出するのだ。
私一人が飲み物を買いに行っているのではないし、いじめでもない。
「麻衣が道宮たちと一緒にいると、いじめられてるのか心配になるんだよね」
「大丈夫だよ」
「心配で心配で死にそうになる」
「そっか」
「あー、死にたい」
アイリは隣に置いていたペットボトルのキャップを開け、ごくごくと喉を鳴らして水を飲む。
飲み終えると「ぷはっ」と声を出し、軽く口元を親指で拭っていた。
「はぁ」
ペットボトルを置くと、今日何度目かの溜息を吐いた。
特に反応をしないでいると、今度は先程に比べて長い溜息を吐いた。
「どうしたの?」
そう言うと、また溜息を吐き、神妙な面持ちで「実はね」とちらちら視線を私に寄こし、言おうかどうか躊躇っている様子だった。
催促せずに黙っていると、アイリは小さく深呼吸した。
「実は、母さんからの暴力が絶えなくてさ」
先程とは打って変わって弱々しそうに笑った。
「あたしが良い子に育てばよかったんだけどね」
アイリは足をつうっと動かして水面に静かな波紋をつくる。
その仕草がか弱い女子を演出していた。
アイリの母親は早くに離婚し、女手一つで今までやってきた。
昔、一度だけアイリにしつこく誘われて家まで遊びに行ったことがある。どこからどう見ても、お金に困っている人たちが住む外観のアパートだった。
隣の部屋からは髪も髭も手入れなんてしていないような中年のおじさんが、茶色く汚れた服を着て左右で色が違うスリッパをずりずりと音を立てながら出てきたのは印象深い。
家の中は上手く表現できない匂いが充満していた。田舎のおばあちゃん家の匂いと似たものだった。
その時、アイリの母はいなくて二人で過ごしたけど、ゲームがないしテレビもない。特にすることなく、ただ喋っていただけだ。喋るだけならアイリの家じゃなくてもできるのに、と幼いながらに思ったものだ。
朝から晩まで娘のために働いていれば、過労で八つ当たりもしたくなるのかもしれない。私は働いたことがないから想像できないけど、育児放棄のニュースは度々見かける。綺麗な服を着て、学校に通えて、ご飯を食べることができているのだから、アイリはまだマシだと思う。私は両親から暴力を振るわれたことはないし、恵まれた環境にいる。
プールの授業でアイリの肌を見たことがあるけど、傷も痣もなかった。見えないところにあるのかもしれないが、アイリを可哀想だと思ったことはない。
「この名前だってさ、おかしいでしょ。普通子どもに愛利栖って付ける? 外国っぽい名前を無理やり漢字にしてさぁ」
「良い名前だと思うけどね」
「愛利栖が? じゃあ麻衣がこの名前貰ってよ。あたしは麻衣みたいな普通の名前がよかった」
そう言って俯きながらまた「死にたい」と呟く。
私だったら愛利栖という名前を付けられてもいい。変わった名前で覚えやすいし、他の人とは違うから被らなくていいと思う。漢字を見てアイリスと読めないこともない。
アイリの心まで読み取ることはできないが、アイリが嫌なのは名前ではなく名前による周囲の反応ではないだろうか。
自己紹介で自分の名前を言った時、「え? 何て?」「日本人?」「キラキラネームじゃん」という反応が多数だろう。しかし名前が麻衣であったなら「へえ」で終わるのだ。
もしもアイリにもっと社交性があれば名前をきっかけにして友達をつくれただろう。私だったらそうする。名前にインパクトがあるからその場で覚えてもらえる。それを利用しない手はない。そうやって徐々に輪を広げていけばいいだけなのに、アイリにはその能力がない。
それ故に皆最初に興味を持つものの、アイリが控え目な人だと知ると興味が失せたとばかりに目を離す。
小学校高学年の頃。放課後、忘れ物を取りに教室へ行くと男子たちが「クラスで一番可愛い子」と大きく黒板に書き、ランキングをつくって遊んでいた。一位はクラスの中で最も可愛い子だったので納得した。教室に入るのを躊躇っていると、とある男子がにやにやと「アイリスちゃんはー?」と声を出し、その場の男子は全員笑い始めた。「アイリスちゃんは圏外でーす」「名前負けだしな」「アイリスっち、暗すぎて名前と合ってないわー」ぎゃはぎゃはと嫌な笑い方で楽しんでいた彼等の気持ちは、分からなくもない。
目立ったいじめはなかったものの、陰で笑われていたことは事実だ。それは恐らく、私だけでなく他のクラスメイトも気づいていたことだろう。
彼等の会話の節々に、名前こそ出さないものの、アイリを嘲笑するような発言があった。
アイリの耳には入っていないだろうが、皆なんとなくアイリの立ち位置を理解していた。
しかしそれは小学生で終了した。小学校では学年に三組しかなかったのが、中学生になると七組もあった。通う生徒数が増えると、小学生の頃にはアイリしかいなかったキラキラネームの子がちらほらと現れたのだ。アイリよりも印象に残る名前を持つ子がいることで、アイリの存在は霞んでいった。そこからは陰で話題にすらされなくなった。
アイリが思っている以上に、誰もアイリを気にしていない。アイリは自意識過剰と被害妄想を兼ね備えているのだ。
「ご飯の準備をしておけだの、掃除をしろだの、買い出しに行けだの、洗濯しろだの、あたしのこと召使だと思ってるの」
「でも、お母さんは働いてるんでしょう?」
「娘に家事をさせる親ってどうなの? 普通なの? 麻衣は毎日ご飯つくったり掃除したり、家事やってる?」
「やってないよ」
「ほらね、普通はやらないよ。だって娘は召使じゃないもん」
私は父がサラリーマンで母が専業主婦であるため、母が家事をしている。娘の私は学校に通うだけ。しかしアイリの家庭は違う。母一人が働きに出ているのだから、家事全般を娘に託したいと思うのはごく自然のことなのかもしれない。
労働も家事も母一人でやればいい、と聞こえ、私は「んー」と微妙な相槌しか返せなかった。
「麻衣には分からないか」
「そうかも」
「麻衣のとこは幸せな家庭だもんね、あたしの家とは違って。あぁ、死にたい。変な名前を付けられて、家事を強要されて。家でも学校でも、あたしの居場所なんてないんだ」
毎度思うが、私はその言葉に何と返すのが正解なのだろう。
肯定しても否定しても「あたしの気持ちなんて分からないくせに」と言われそうだ。
だからいつも私は黙る。慰めると話は長引くし、助言すると顔を顰める。
恐らく何も返さないのが無難なのだ。
がぶがぶと水を飲み、「ぷっはぁ」と飲み終えた後に息を吐くアイリは、水に浸けていた足を引き抜き、三角座りをして腕に顎を乗せ「死にたい」と小さく呟く。
「大丈夫だよアイリ」
「何が?」
「きっと大丈夫」
「何が大丈夫なのよ。あたしはもうボロボロなんだよ」
「大丈夫だよ」
「麻衣には分からないよ」
大丈夫、と言ってみたがやはりお気に召さないようだ。大丈夫と言ったことがスイッチを押してしまったようで、アイリはいかに自分が恵まれていないのかを語り始めた。
こうなるともう止まらない。次から次へと漏れ出る負の言葉たち。私は耳を塞いでいるわけでもないのに、何故かアイリの話していることが耳に入ってこない。完全なシャットアウトだった。
アイリの声をBGMに、夜のプールを眺める。
昼間は綺麗な水色を映しているのに、今はまるで沼のように黒ずんでいる。ぽつんと道路脇にある灯りが水の波紋を浮かび上がらせている。
貧乏ゆすりをすると、私の足を中心に水面が揺れる。
暫く視線を足元にやっていると、BGMが止んだ。
ふと隣を見ると、アイリはこくりこくりと眠りの舟を漕いでいた。瞼は閉じられていて、数秒もすれば意識を持っていかれるだろう。
アイリの頭に軽く手を当てて、私の膝の上に倒れるように誘導すると、抵抗なくゆっくりと私の太腿に頭が乗った。
やっと眠った。
入れる量を間違えたのかと思っていたが、杞憂だった。
アイリに渡したペットボトルは空になっており、水に溶けた睡眠薬はすべて摂取されている。
睡眠薬なんて初めて購入したから効き目がどの程度か、いつ眠るのか疑問ではあったが今こうして夢の中にいるアイリを見ると、薬としての役割は果たしているようだ。
決断するのに、長い時間がかかった。
いつかいつか、と思って実行するのに時間がかかってしまった。
アイリは私を優しいと言うが、道宮に言わせれば私は人に関心を持たない女らしい。愉快な話に花を咲かせている中で道宮から突然落とされた発言に、あの時の私は反応が遅れた。
「麻衣はさ、人に興味ないよね」
「そんなことないよ」
「あ、そっか。間違えた。仲が良い人間には半分興味を持つけど半分無関心なんだよ」
否定はできなかった。
道宮と仲良くしているのは楽しいという感情と使えるという感情の二つが混ざっているからだった。
それが道宮の言う半分なのだろう。
「仲良くない奴に興味ないのは皆同じだけど、麻衣は仲良い子に対しても半分は興味ないんだよ」
言い返さない私を道宮は笑った。
「うちらは楽しいから麻衣といるんだから、別に責めてないよ」
「そう」
一緒にいると伝わってしまうものなのか。
罪悪感がちくりと胸を刺した。
登校して下校するまでの間ほとんど一緒にいるのだから、それが毎日続けば薄々感づいても不思議ではない。
知ってもなお道宮は今まで通りに接してくれ、これが友達というものかとじんわりと温かくなった。
アイリは道宮よりも長い間知っている。アイリに対して愛想のない言動をしていた自覚はあるが、アイリがそれを指摘することはなかった。
それもそのはず、アイリは私を友達として扱っていなかった。
母に暴力を振るわれた、クラスメイトが悪口を言っていた、笑っていた、嫌なことがあった、と私にぶつけるだけ。私が何か言おうものなら「でも」「だって」「麻衣には分からない」と言って、また話が元に戻る。私を人形だとでも思っているのだろう。黙って聞く、相槌を打つ。これ以外求められていないのだ。
私が道宮たちと仲良くしているのを嫌がるのは、唯一友達である私が他の友達と仲良くしているのが気に食わないだけだ。独占欲が顔を覗かせているのだ。
自分は独りなのに、どうして麻衣は目立つ人たちと仲良くしているのか。独占欲、嫉妬、羨望が入り混じった眼差しを向けられていた。
痛い視線を背中に感じながら、私は無視し続けた。
学校で話しかけられたくはなかった。誰とも喋らない根暗なクラスメイトと友達だと思われたら面倒だからだ。アイリと話しながら道宮たちと話すことなんてできない。アイリと道宮たちは性格から何もかもが真逆なのだから、合うはずがない。私の学校生活の足を引っ張ることしかできないのだから、アイリに話しかけられないよう無視を続けていた。
アイリから私に話しかけることはなく、私から話しかけることもなかったため、アイリとも道宮とも丁度良い距離感を保つことができた。
けれどそれももう終わり。
やっと終わるのだ。
アイリは長年、私の心に引っかかる異物だった。この異物が除去されたら楽なのに、と思っていた。
それが今日、やっと取り出せそうだ。
耳にたこができる程聞いたアイリの言葉。
「死にたい」
その度に、じゃあ死ねばいいのにと呆れた。
死にたいのなら死ねばいい。友達をつくりたいのならつくればいい。そうしないのは、アイリに実行する気がないからだ。
面倒な性格。
だから友達がいない。
近くの蛇口で水を出し、アイリのペットボトルを洗う。
プールサイドに置いたままのアイリを引っ張り、ちゃぽ、と可愛らしい水音を立てながらプールに入水させた。
私は座ったまま、両足でアイリの後頭部を踏みつける。
その恰好のまま時間が過ぎると、呼吸ができないことに気づいたのか、アイリが急に動き始めた。
ばしゃばしゃ、ばたばた、ばしゃばしゃ。
両手両足を使いぐっとアイリを押さえつける。
どのくらいそうしていたか分からないが、徐々に力が抜けていくアイリは、ついに動きを止めた。
でも、まだ生きているのかもしれない。
死んだ振りをしているのかもしれないから、手も足もアイリから離さずにいた。
「もういいかな?」
ゆっくりとアイリを放し、両足で体を蹴ると、アイリはぷかぷか浮かんだままプールを漂う。
私は持ってきたタオルで濡れた部分を拭き、靴下と靴を履いた。
帰ろうかと体の向きを変えると、アイリのペットボトルが目に入った。
そうだった、忘れていた。
そのペットボトルにほんの少しプールの水を入れて、アイリの死体近くに投げた。
自分のペットボトルを持って、学校を去った。
死にたいというから殺してあげた。
アイリの言う通り、確かに私は優しい。
死にたい、死にたい、と幾度となく口にしながら実行できないでいるアイリのためを思って息の根を止めてあげたのだから。
そして明日か明後日にはアイリを思ってクラスメイトはホームルームにでも黙祷するだろう。
友達でもなかった人たちがアイリのために目を閉じて祈る時間を共にするのだ。きっとアイリも喜ぶだろう。
数日経てばアイリの存在を忘れ、楽しい日々を送るだろうが、一時でもアイリのための時間が確保されて良かったね。
アイリの母も不出来な娘がいなくなって肩の荷が下りるもしれない。
私も心のつっかえがなくなって、清々しい気持ちだ。
以前から「死にたいなら死ねばいいのに。私が殺してあげようかな」と考えていたのだが、方法が決まらずなかなか行動に移すことができなかった。
何故今日だったのか、特に意味はない。
昨日ふと思いついたのだ。そろそろなんじゃないか、と。
アイリが死んで悲しい、とは思わないが安らかに眠ってほしい。
ドラマでよく見かけるやつをやってあげた方がいいかな。
アイリの席に花瓶を置いて、花を一本供えよう。
供え物の花はどんなのが一般的だろう。葬式なんてまだ一回しか経験していない。墓参りの際に花なんて気にしたことがないから分からない。
薔薇は駄目だろう。華やか過ぎて先生に怒られる。
道端に咲いている花はすぐにバレそうだから、これも駄目だ。
供えるのだから、花弁の色も気をつけないといけないのかな。
棺に入るときは白い服だろうから、白い花がいいだろうか。
そうだ、百合にしよう。
決まりだ。
帰宅後、学校に持って行く財布の中に五千円札を入れて鞄にしまった。百合の花がいくらなのか分からないけれど、五千円もあれば足りるだろう。
明日、学校の帰りにでも花屋へ寄ろう。
学校で仲良くしているわけでもないクラスメイトのために花を供えるなんて、やっぱり私は優しいのかもしれない。