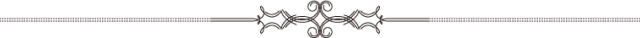第1章 男娼
文字数 2,726文字
[彼]は全身傷だらけで、包帯にくるまれて、硬いベッドに横たわっていた。
二人の男が、意識を取り戻した[彼]を見下ろしていた。明らかに医者と知れる、白衣を着た初老の男が、驚いた様子で叫んだ。
「気がついたか。運の良い坊やだ」
[彼]は両腕と両脚の骨を叩き折られ、全身に無数の切り傷、刺し傷、打撲傷を受け、血まみれでマルセイユの裏路地に倒れていたのだった。奇跡的に傷はすべて急所を外れていたが、失血はおびただしい量だった。死にかけているところを、モノリスというこの部屋の持ち主に拾われたのだ。
[彼]は何も覚えていなかった。過去の記憶を完全に失っていた。自分が何者でどこから来たのか、なぜそんな重傷を負う羽目になったのか、何一つ思い出せなかった。
身元など、わかるはずもなかった。
記憶を持たない[彼]に、モノリスはセシルという名を与えた。
特に異存はなかったので、[彼]はうなずいて承諾した。こうして[彼]はセシルとなった。
モノリスがセシルを拾って医師の手当てまで受けさせたのは善意からではなかった。セシルの顔が美しいのを見て、「商品」になると判断したからだった。
セシルは昼も夜もじっと横たわり、薄汚い天井を眺めていた。茶色い埃のこびりついた窓ガラスの向こうを、色あせた太陽が横切り、夜の闇が覆い尽くし、再び太陽が横切った。セシルは日数を数えていなかったが、傷がふさがり、ベッドから体を起こせるほど体力が回復するまで、一か月以上は経っていただろう。
「今日から仕事だ、セシル。今までかかった医者代や薬代、食費を返してもらわなきゃならんからな。しっかり稼いでもらうぞ」
モノリスは、いつもきまって黒のシャツを着ている四十過ぎの中肉中背の男だった。薄くなりかかった茶髪が頭皮にばらばらに貼りついている。眠そうに瞼の落ちかかった目は、表情を読ませない。
「……まずは、おまえを店に出せる状態にする」
そう言われて、セシルは素直にうなずいた。モノリスの言う「仕事」や「店」とは何なのか、さっぱりわかっていなかったが。
皆に〔鉤鼻〕と呼ばれている筋骨たくましい中年男が、セシルを地下室へ連れて行った。天井から長めのコードでぶら下がった白熱電球が、むき出しのコンクリートの壁に囲まれた部屋を、いっそう殺風景なものに見せていた。室内にあるのは、みすぼらしいベッドと、引き出し付きの飴色の机だ。机の上には古ぼけた蓄音機が置かれている。
ベッドの上におざなりに掛けられただけのシーツは、初めからすでに斜めになっている。そのため、シーツの隅に縫いつけられたラベルがセシルの視界に入った。〔セシル・ブランシュ〕というブランド名が書かれていた。
――もしかするとモノリスは、このラベルを見てセシルという名前を思いついたのかもしれない。
そう気づいた瞬間、ワセリンをまぶした太い指があり得ない場所に押し入ってきたので、セシルは痛みと驚きで「うっ」と声を漏らした。
「今日からこれがおまえの仕事だ。ここを使って、客を悦ばせるんだ」
背後から〔鉤鼻〕の重々しい声が響いた。
長い時間をかけて、セシルは体を
「
感情は何も湧いてこなかった。羞恥も屈辱も。
ただ、突き上げられる痛みと、ずるりと抜かれる時に自分の内臓まで持っていかれるみたいな違和感が不快なだけだった。
セシルの中身は空っぽで、モノリスたちから与えられる言葉が唯一の指針だった。これが彼の仕事だとモノリスたちが言うのなら、きっとそうなのだろう。
〔鉤鼻〕は地下室で、一週間かけてセシルを仕込んだ。何度も犯されているうちに体が慣れたので、それ以降セシルは本当に何も感じなくなった。どうってことはない。少しわずらわしいだけだ。
地下室にはずっと音楽が流れていた。〔鉤鼻〕がサロンで使われなくなった古いレコード盤を持ちこみ、蓄音機で再生していたからだ。大男のお気に入りはミスタンゲットの歌だった。
この地上で、私のたった一つの楽しみ、たった一つの喜び
それは私の男。
私の持っているものをすべてあげる、私の愛、私の心を
私の男に。
夜になっても、
夢を見るの、彼のことを、
私の男のことを。
埃がこびりついたどす黒い天井。激しく腰を使う〔鉤鼻〕の顔から飛び散る汗。内奥の肉をえぐられる衝撃。レコード盤の傷のせいで何度も繰り返し再生される、同じフレーズ。
〔鉤鼻〕はセシルを「抱かれる体」に作り替えただけでなく、男娼として働くために必要な一通りの技術を教えた。抱かれるための体の準備と、抱かれた後の処理の方法。客の悦ばせ方。無体な客のいなし方。
セシルは黙ってそれらを学び、一週間後には地下室を出て、慣れきった男娼のように事務的な態度で客を取り始めた。仕事と割り切ることができれば、セックスはそれほど難しい稼業ではなかった。単純作業と呼んでもいい。要するに客を射精させればいいのだから。
羞恥心というものを知らず、また、苦痛にも耐性があるセシルは、客のどんな要望にも平然と応じた。容姿の美しさも手伝って、モノリスの男娼窟でナンバーワンの売れっ子になるのに時間はかからなかった。