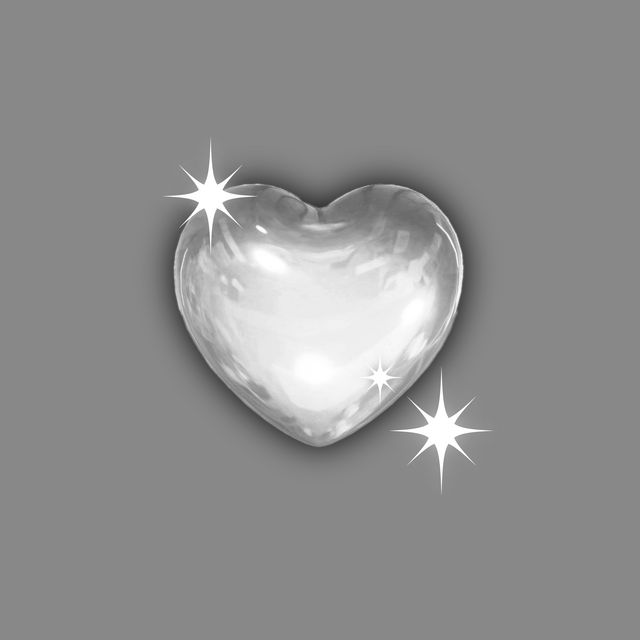第7話
文字数 3,413文字
人の流れに乗って今日も都会の雑踏を歩く。この街が初めから自分の持ち物であるかのように。他人がすべて名前のないキャラクターであるかのように。平日の昼間とはいえ、地元に比べれば嘘みたいな人の量だと芽里は思う。自分が知っている物事よりもずっと多くの何かが、日々、お金に変えられているのだとも。耳に流れ込んでくるのは環境音と化された他人の声、歩行者用信号の青を伝える音、ハイテンションな広告、買い物気分を盛り上げようとするBGM。「てかさ、今日のテスト最悪だったんだけどまじで」芽里の耳は菜子の声だけを選び取っては意味を伝える。
「私も点数下がった」
「芽里も? 私ママにさすがに何か言われそう。バイトのシフト減らしたくないんだけどなー」
たくさんの音に負けない声で話しかけてくる菜子に芽里は微笑む。放課後。普段どおり、何か買いに行こうと芽里は菜子を誘った。それからノートパソコンに貼る用のプリクラを撮って、時間があれば適当にふらつこうと。「行く行く!」と菜子は喜んでついてきてくれた。2人でこうして街中を歩くのは久しぶりだった。少しの間、バイトと勉強に明け暮れていたからだ。
菜子は待ち切れないといった感じで言った。
「先にプリクラ撮っちゃう?」
「いいよ」
芽里はそう答えつつも、笑ってと機械に言われて笑えるのか不安になる。ふと横を見るとハイブランドのショーケースがあった。そこには攻めすぎたデザインのバッグやコーディネート一式、そして制服を着たありきたりな自分たちが映り込んでいる。何かを打ち明けようとする決意も、何かを受け止める深刻な気配も特に感じられない。だけど芽里は今日、伝えに来たのだった。叶人に好きと言われたこと、キスをしたこと、そして──自分が好きと言ったこと。付き合おうと思っていること。それらをすべて、菜子に。
直後、スーツを着た女の人が足早に2人を追い越していった。名前も声も知らない他人の、さらに目には見えない内側の部分を芽里はイメージした。よくある後ろ姿。ただ歩いている振りをしている人は自分以外にどれくらいいるんだろう。 そんなことを考えながら、キャッチの男をあしらい前へ進む。なるべく大きな声で菜子と笑う。悩みなんて一度も感じたことのなさそうな軽い足取りで。
芽里が気付かれないように深呼吸をすると、菜子は言った。
「なんかさ、毎日楽しいんだけどつまんないよね?」
「わかる。でも菜子といるときは楽しいよ」
「本当にー?」
菜子は芽里と目を合わせると心からうれしそうに笑った。大きな交差点の赤信号で彼女は続けた。
「芽里。なんかさ、言いたいことあるなら言ってよ。……なんでもいいよ」
芽里は溜め息をついた。取り調べられているわけでもないのに白状しなきゃなんない。そんな意味不明の気分だった。追い打ちをかけるように「さっきからちょくちょく溜め息ついてるよね?」とも言われた。芽里はスクールバッグのショルダーを握り締めた。友情が壊れるのは怖い。だけど不自然な自分がバレている以上、失うものなんてない。
「話があるんだ。菜子に」
「うん」
「あのさ。叶人のことなんだけど」
「叶人がどうしたの?」
「私、叶人のことが……」
芽里は言葉に詰まった。誰も傷付けない都合のいい言語があればいいのに。そう本気で思いながら、半ば投げやりな気持ちで飛び込んだ。おそらく菜子の言う、前へ。
「好き」
直後、魔法みたいに信号が青に変わった。周りの人たちは動き出した一方、少しの間、芽里と菜子は見つめ合ったまま動けずに迷惑な都会のオブジェだった。歩き出すタイミングを失った芽里の制服の袖を菜子は引っ張ってくれた。
「叶人が好きなんだ。こないだキスされた」
それは、叶人に言った「好き」よりずっと重い「好き」だった。渡り終えた横断歩道の先で、芽里は思わず菜子の指を子どもみたいに掴んだ。冷たくて細い指。ここだよ、と伝えるかのように菜子は手を繋ぎ返してくれた。2人は歩き続ける。目的地を過ぎても、口を閉ざしたまま。
「芽里。私も言えなかったことがあるの」
やがて人の少ない路地で菜子は足を止めた。長い髪の中でうつむいていて表情はよく見えない。
「私、知ってたよ」
「え?」
「叶人が芽里を好きなのも、きっと2人の間に私の入れない何かがあるんだってことも」
「菜子……」
「だってそうでしょ? 叶人に特別な人がいるなら、芽里以外に考えつかないもん」
菜子は顔を上げて笑った。
「好きな人が誰を見てるかって、恋してるとわかるんだよ」
芽里の手は菜子から滑り落ちた。ごめんね。反射的に言いかけたその言葉を、芽里は飲み込んだ。謝ることで相手を少しも惨めな存在にしたくない。そう思うのは相手が菜子だから以外の何物でもなかった。
「私も叶人が好きなんだ。本当に」
そして菜子のことも同じように。そのことが伝わってほしくて下唇を噛む。友情か恋愛。どちらかを選べと言われたら、どちらもいらないと言える人間になりたかった。だけどそんなに強くもなければ、どちらも欲しいと思えるくらいの人しか欲しくない。弱虫で欲張りな人間だと、芽里は恋に暴かれた自分を思う。
「芽里。知ってる?」
菜子はそう言うと、長い髪を耳にかけた。
「叶人はね、顔もなんだけど……。周りに流されない自分を持っててかっこいいの」
「うん」
「それで、誰にでも優しいところが、今は好きじゃないけど好きだった」
「……うん」
芽里は目を逸らさなかった。全部、進行形で知っていることだ。これから先、菜子がいくら過去形で彼を語っても。
「でも結局、勝手にどっか行っちゃうんだよね。ねぇ芽里、叶人は留学しちゃうけどいいの?」
「やだけど……。いい。別に」
そう言うと菜子は、諦めたように笑った。
「なんか、今やっと本当の意味で吹っ切れたのかも」
遠距離恋愛とか私は無理だしね。そう続ける彼女に芽里は言わずにはいられなかった。
「ねぇ菜子。あのさ……。大好き」
「何? どしたの急に」
一瞬の空白を置いて、菜子は言った。「そんなの私もだよ」。あの日とは反対に、今度は彼女のほうから腕を回してくれた。「幸せになってほしいって、芽里にはめっちゃ思ってる」芽里の耳元で菜子はそう言った。大人びた甘い香りの中で芽里は泣きそうなほど安心した。きっともう自分は迷子にはならない。そして誰かを迷子にさせたくないとも思う。
身体を離すと、菜子はスマートフォンを取り出し、誰かに短いメッセージを送った後で言った。
「で、芽里たちいつから付き合ってんの?」
「え? まだだけど……」
「好きって言ったんだよね?」
「うん」
「じゃあなんで? ありえなくない!?」
菜子は信じられない、といった声で言った。
「スマホ出して。今から叶人に送ろうよ」
「え? 今?」
「いいから送っちゃいな」
刺すような菜子の視線を感じながら、芽里はスマートフォンに打ち込む。「ずっと言えなくてごめん。好き」そして「これからよろしく」というメッセージを彼に。菜子と顔を見合わせ、頷いた後で送信した。芽里は不思議な解放感に包まれていた。好き。なんでこんなたった2文字に苦労したのかわからない。大人になるにつれて簡単な言葉ほど簡単には言えなくなるのかもしれない。今はまだ、なんとか言える程度の年齢だ。
2人はもう一度、歩き出した。菜子いわく「ぼーっとしてたら通り過ぎちゃった」家電量販店へ、ひとまず戻るために。どの瞬間を切り取られても今なら自然に笑えると芽里は思う。菜子の言うとおり、たしかに毎日はつまらないことを連続させている。だけど時々こういう瞬間は確実に訪れる。硬く平らなアスファルトの地面が、空へ繋がる雲の階段のように思える瞬間が。
「そういえば、芽里のクラスの高橋いるでしょ?」
菜子の声は今、完全に明るい。
「今度遊ぼって言われたんだよね。2人で」
「いいじゃん。行ってみなよ」
「付き合ってみたら、叶人よりいい男かもしれないし?」
そうだね。芽里はそう言うと笑った。制服のポケットでスマートフォンが震え、叶人からのメッセージかもしれないと芽里は思う。だけど確認するのは後でいい。2人の足取りはスキップに近い。胸元では今日も制服のリボンが揺れる。気付けば街は少しずつ夕方の気配を帯び始めた。楽しい何かが待っていると感じさせるには充分な人のざわめきと街の明かり。菜子と芽里、2人は歩けば歩くほど人混みに溶け込んでいく。
「私も点数下がった」
「芽里も? 私ママにさすがに何か言われそう。バイトのシフト減らしたくないんだけどなー」
たくさんの音に負けない声で話しかけてくる菜子に芽里は微笑む。放課後。普段どおり、何か買いに行こうと芽里は菜子を誘った。それからノートパソコンに貼る用のプリクラを撮って、時間があれば適当にふらつこうと。「行く行く!」と菜子は喜んでついてきてくれた。2人でこうして街中を歩くのは久しぶりだった。少しの間、バイトと勉強に明け暮れていたからだ。
菜子は待ち切れないといった感じで言った。
「先にプリクラ撮っちゃう?」
「いいよ」
芽里はそう答えつつも、笑ってと機械に言われて笑えるのか不安になる。ふと横を見るとハイブランドのショーケースがあった。そこには攻めすぎたデザインのバッグやコーディネート一式、そして制服を着たありきたりな自分たちが映り込んでいる。何かを打ち明けようとする決意も、何かを受け止める深刻な気配も特に感じられない。だけど芽里は今日、伝えに来たのだった。叶人に好きと言われたこと、キスをしたこと、そして──自分が好きと言ったこと。付き合おうと思っていること。それらをすべて、菜子に。
直後、スーツを着た女の人が足早に2人を追い越していった。名前も声も知らない他人の、さらに目には見えない内側の部分を芽里はイメージした。よくある後ろ姿。ただ歩いている振りをしている人は自分以外にどれくらいいるんだろう。 そんなことを考えながら、キャッチの男をあしらい前へ進む。なるべく大きな声で菜子と笑う。悩みなんて一度も感じたことのなさそうな軽い足取りで。
芽里が気付かれないように深呼吸をすると、菜子は言った。
「なんかさ、毎日楽しいんだけどつまんないよね?」
「わかる。でも菜子といるときは楽しいよ」
「本当にー?」
菜子は芽里と目を合わせると心からうれしそうに笑った。大きな交差点の赤信号で彼女は続けた。
「芽里。なんかさ、言いたいことあるなら言ってよ。……なんでもいいよ」
芽里は溜め息をついた。取り調べられているわけでもないのに白状しなきゃなんない。そんな意味不明の気分だった。追い打ちをかけるように「さっきからちょくちょく溜め息ついてるよね?」とも言われた。芽里はスクールバッグのショルダーを握り締めた。友情が壊れるのは怖い。だけど不自然な自分がバレている以上、失うものなんてない。
「話があるんだ。菜子に」
「うん」
「あのさ。叶人のことなんだけど」
「叶人がどうしたの?」
「私、叶人のことが……」
芽里は言葉に詰まった。誰も傷付けない都合のいい言語があればいいのに。そう本気で思いながら、半ば投げやりな気持ちで飛び込んだ。おそらく菜子の言う、前へ。
「好き」
直後、魔法みたいに信号が青に変わった。周りの人たちは動き出した一方、少しの間、芽里と菜子は見つめ合ったまま動けずに迷惑な都会のオブジェだった。歩き出すタイミングを失った芽里の制服の袖を菜子は引っ張ってくれた。
「叶人が好きなんだ。こないだキスされた」
それは、叶人に言った「好き」よりずっと重い「好き」だった。渡り終えた横断歩道の先で、芽里は思わず菜子の指を子どもみたいに掴んだ。冷たくて細い指。ここだよ、と伝えるかのように菜子は手を繋ぎ返してくれた。2人は歩き続ける。目的地を過ぎても、口を閉ざしたまま。
「芽里。私も言えなかったことがあるの」
やがて人の少ない路地で菜子は足を止めた。長い髪の中でうつむいていて表情はよく見えない。
「私、知ってたよ」
「え?」
「叶人が芽里を好きなのも、きっと2人の間に私の入れない何かがあるんだってことも」
「菜子……」
「だってそうでしょ? 叶人に特別な人がいるなら、芽里以外に考えつかないもん」
菜子は顔を上げて笑った。
「好きな人が誰を見てるかって、恋してるとわかるんだよ」
芽里の手は菜子から滑り落ちた。ごめんね。反射的に言いかけたその言葉を、芽里は飲み込んだ。謝ることで相手を少しも惨めな存在にしたくない。そう思うのは相手が菜子だから以外の何物でもなかった。
「私も叶人が好きなんだ。本当に」
そして菜子のことも同じように。そのことが伝わってほしくて下唇を噛む。友情か恋愛。どちらかを選べと言われたら、どちらもいらないと言える人間になりたかった。だけどそんなに強くもなければ、どちらも欲しいと思えるくらいの人しか欲しくない。弱虫で欲張りな人間だと、芽里は恋に暴かれた自分を思う。
「芽里。知ってる?」
菜子はそう言うと、長い髪を耳にかけた。
「叶人はね、顔もなんだけど……。周りに流されない自分を持っててかっこいいの」
「うん」
「それで、誰にでも優しいところが、今は好きじゃないけど好きだった」
「……うん」
芽里は目を逸らさなかった。全部、進行形で知っていることだ。これから先、菜子がいくら過去形で彼を語っても。
「でも結局、勝手にどっか行っちゃうんだよね。ねぇ芽里、叶人は留学しちゃうけどいいの?」
「やだけど……。いい。別に」
そう言うと菜子は、諦めたように笑った。
「なんか、今やっと本当の意味で吹っ切れたのかも」
遠距離恋愛とか私は無理だしね。そう続ける彼女に芽里は言わずにはいられなかった。
「ねぇ菜子。あのさ……。大好き」
「何? どしたの急に」
一瞬の空白を置いて、菜子は言った。「そんなの私もだよ」。あの日とは反対に、今度は彼女のほうから腕を回してくれた。「幸せになってほしいって、芽里にはめっちゃ思ってる」芽里の耳元で菜子はそう言った。大人びた甘い香りの中で芽里は泣きそうなほど安心した。きっともう自分は迷子にはならない。そして誰かを迷子にさせたくないとも思う。
身体を離すと、菜子はスマートフォンを取り出し、誰かに短いメッセージを送った後で言った。
「で、芽里たちいつから付き合ってんの?」
「え? まだだけど……」
「好きって言ったんだよね?」
「うん」
「じゃあなんで? ありえなくない!?」
菜子は信じられない、といった声で言った。
「スマホ出して。今から叶人に送ろうよ」
「え? 今?」
「いいから送っちゃいな」
刺すような菜子の視線を感じながら、芽里はスマートフォンに打ち込む。「ずっと言えなくてごめん。好き」そして「これからよろしく」というメッセージを彼に。菜子と顔を見合わせ、頷いた後で送信した。芽里は不思議な解放感に包まれていた。好き。なんでこんなたった2文字に苦労したのかわからない。大人になるにつれて簡単な言葉ほど簡単には言えなくなるのかもしれない。今はまだ、なんとか言える程度の年齢だ。
2人はもう一度、歩き出した。菜子いわく「ぼーっとしてたら通り過ぎちゃった」家電量販店へ、ひとまず戻るために。どの瞬間を切り取られても今なら自然に笑えると芽里は思う。菜子の言うとおり、たしかに毎日はつまらないことを連続させている。だけど時々こういう瞬間は確実に訪れる。硬く平らなアスファルトの地面が、空へ繋がる雲の階段のように思える瞬間が。
「そういえば、芽里のクラスの高橋いるでしょ?」
菜子の声は今、完全に明るい。
「今度遊ぼって言われたんだよね。2人で」
「いいじゃん。行ってみなよ」
「付き合ってみたら、叶人よりいい男かもしれないし?」
そうだね。芽里はそう言うと笑った。制服のポケットでスマートフォンが震え、叶人からのメッセージかもしれないと芽里は思う。だけど確認するのは後でいい。2人の足取りはスキップに近い。胸元では今日も制服のリボンが揺れる。気付けば街は少しずつ夕方の気配を帯び始めた。楽しい何かが待っていると感じさせるには充分な人のざわめきと街の明かり。菜子と芽里、2人は歩けば歩くほど人混みに溶け込んでいく。