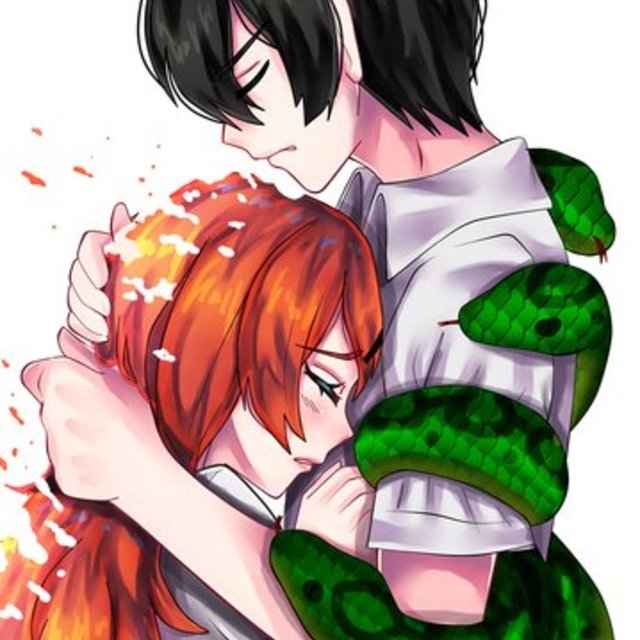1
文字数 11,047文字
ライド
プロローグ
Radicibus
[第一部]
この物語では、人類の始まりへ遡ります。まだ何も存在しない時代 です。
何もない、ただ、若い3羽のゴシキヒワだけが、翼を広げて,
自分自身を発見するために羽ばたく瞬間を熱心に待っています。
これは、運命がいかに彼らを巡りあわせ、
それぞれの人生が驚くほど変わってしまったかについての物語です。
文章:ミツアキ・セイジ (ティアーゴ・マルケス)
軽くて柔らかい風が、『科学の木』の赤い葉をはためかせた。それは、世界の中心、『エデンの園』にある『神』によって作られた2本の特別な樹木の1つである。
この巨大な樹木(高さ約115メートル)の下、自然の創造の中で最も美しいとされる庭園の広大で美しい景観に囲まれながら、一人の12歳の少年が幹に寄りかかって昼寝をしていた。
「アダム、気をつけて!」
アダムの横には、同じ年齢のイブと呼ばれる一人の少女が休んでいた。静かな一時を起きたまま、そこに生えているアマランサスを集めて遊んでいた。
女の子は突然、悪意の気配を感じた。
茂みから何かが アダムをじっと見ている。
捕食者は獲物に襲いかかり、その有毒な牙で犠牲者の人生をひとかじりで終わらせようとした。
アダムは弱い立場におかれた。
死を意味するであろう。
終わりを避けるのには、もう遅すぎるのだろうか...?
「捕まえたぞ、『喋る蛇』! 」
「シュー!いつも他人に頼ってばかり!」
アダムがイブの直覚に頼りすぎることを指していた。
本当は、少年は『喋る蛇』の攻撃への準備ができていて、それに反撃する瞬間を待っていたのだ。
蛇は少年の手から抜け出した。
再攻撃するつもりだ。
アダムの腕を素早い動きで滑り抜け、今度は敵の顔に狙いを付けた。
しかし、攻撃するその瞬間、蛇は自分の体のほぼ3分の1を持ち上げ、大きな円を描いて、アダムの頭上を完全に跳び越した。
結局、蛇には二度目の攻撃の意図はなかったのだ。
蛇は素晴らしい動きで着地した。
少年と向かい合い、数メートルの距離が2つの視線を隔てた。
「 おい、準備はできている。 早く来い!」
右足でしっかり地面に支えて、手を位置に構え、少年は『戦闘モード』に入った。
イブは心配しながら、ただ、見守っている。
蛇はアダムに背を向け、挑戦を断った。
その態度は 赤毛の少年を驚かせた。彼は蛇を逃がすつもりはあまり無かった。
「何だ? 逃げるのか? そっちが始めたんだろう? なんて臆病なんだ!」
蛇の限界を試そうと、腰に手を当ててさらに挑発した。
アダムの挑発に反応して、『喋る蛇』は首をひねり舌を出した。
「笑っていられるのも今のうちだ。もし、貴様がガードを緩めたら...忘れかけたときに、その哀れな命を取れるよう、俺ははいつも傍にいるぞ...バカヤロー!」
「な... 何だと?! このヤロー、今度こそ! 」
イブの腕の中アダムは叫んだ。イブは怒り狂う少年が蛇の後を追わないように押さえていたのだ。
「ここへ戻れ! これからが第2ラウンドだ!」
「落ち着いて。もう行ってしまったわ。」
イブは、ため息をつきながらも、新たな喧嘩を防ごうと必死だった。
少年は頭を上げて遠くを見た。蛇は逃げたのだろうか、その姿はもうどこにも無かった。
「5日間も同じことが続いている... 蛇は一体、何を望んでいるの?」
イブは疑問に思っていることを声に出して自問した。そして、ふと、頭に浮かんだ。
「まさか... ね?」
...
それ以来、 『喋る蛇』は、毎日ように現れては、アダムの命を狙いました。
こうして、5日間が過ぎていきました。
捕食者も獲物も妥協しないまま、
とうとうどちらが最後まで生き残るかに決着をつける時がやって来ました。
...
彼らは再び、目と目を合わせて、対峙している。
闘いの十日目。
「おい、お前は本当にしつこいな」
アダムは微笑んだ。
彼の下唇からは 血が大量に出ている。顔にあるたくさんの傷跡は、両者の闘いがどれほど激しいものかを示していた。
「ふん、バカバカしい!」
「何だと?!」
『喋る蛇』は一瞬、黙った。
その閉じた目と穏やかな呼吸は、これから言うことを深く考えている印だ。
「決着をつけよう。 明日の午後が、最後の闘いだ。」
この発言は、アダムとイブを驚ろかせた。
まさかこんなにも早くに決着の日が来るとは、アダムは思ってもいなかった。
“いや、もしかしたら、この問題を解決する最高の時なのかもしれない。”
闘いへの興奮を抑えられず、アダムはかすかな笑みを浮かべた。
「いいだろう。終わりにしよう。」
『喋る蛇』がその場を去った直後、イブがアダムに近づいた。何かで真剣に悩んでいる様子だ。
「イブ、どうした?」
たった今、死を賭けた決闘を受け入れたことを思えば、アダムの表情は意外と平静だった。
「なぜ蛇がこんなことをやっているのか... 私は本当の理由を知っているわ」
アダムは不意打ちを食らった。
少女の言葉を真に受けず、皮肉な笑みを浮かべた。
「イブ、何を言っているんだ?あいつは、ただの災い...」
「良く考えてみて!蛇の本当の目的は、あなたと言い合ったり、闘いを始めたりすることじゃない。それは、おそらく、他人と触れ合う方法を他に知らないから。そうよ...今までの間ずっと、蛇は私達に近づこうとしていた。あなたに近づこうとしていた! 」
明らかにされた真実に、アダムは動揺した。イブの言葉に全身が震えるのを感じた。
「私には理解できる...私は運良く、アダム、あなた出会えた 。でも、もし会えていなかったら、私もおそらく同じように...孤独を感じていたでしょう。 だって、結局は...私達もまったくのひとりぼっちよ...
この世界には他に誰もいないのだから!」
込み上がる感情を抑えきれず、イブの最後の言葉は必死だった 。
衝撃を受けたアダムは、どう反応すればいいのかが、わからなかった。
いや、反応できなかった。
今まで、全く気が付かなかった。
あんなにも、はっきりしていたのに。
あんなにも、すぐ目の前にあったのに。
次の瞬間、アダムはあまりの考えの浅さに、自分自身を責めた。
少年は決心した。
これから先、もう間違いは犯したくない。
イブの気持ちが少年の心を動かしたのだ。
少年はそれを認識した。
「ありがとう、イブ。それから、ごめん。これは、僕が必ず終わらせてみせる。約束だ! 」
通り過ぎる時、決然とした表情をイブに見せた。
...
闘いの最終日は...今日
太陽の日差しはまだ強く、午後の穏やかな気候はこの場にぴったりだった。
アダムとイブが、最初にその場所(いつも彼らの争いが起こった)に到着した 。今、これが最後の対決になるだろう。
アダムは、前日にイブに見せた、決然とした表情を維持したままだ。
彼の決心は変わっていない。
数分後、第三者が彼らの前に現れた。
ところが驚いたことに、『喋る蛇』ではなく、今まで見たことのない顔をした少年だった。年齢は彼らと同じくらいで、背はアダムよりやや高かった。
しかしながら、イブにはこの少年の冷たい視線には見覚えがあった。暗緑色の目と奇妙な虹彩、確かに以前、どこかで見たことがある気がした。
「ええっと... もしかして、道に迷ったのかな?」
アダムは、少し混乱しつつも、穏やかな笑顔で尋ねた。
イブはこの見知らぬ少年から目が離せなかった。以前、彼らが出会っていることは、ほぼ確かなはずだ。
“ええ、あの視線、あの目...まさか、彼が...?!”
「もしかして、あなたは...?」
「これは俺の人間の姿 — 真の姿だ。 問題あるのか?」
イブの仮説を証明し、アダムが彼の正体を理解するには、その言葉は充分だった。
「男の子?! 」
アダムの言葉にイブが反応した。
「こんなことで驚いているの?!」
「さあ... これで終わりにしよう。 」
アダムはしっかりと頷く。
「うん。」
まず、蛇少年が『科学の木』の根元まで先に歩き始めた。
そこで止まった。
彼は 足で強く地面を支え、その足を完全に地中まで突き刺した。
その支えを反動として利用し、 木の上を目掛け、大きく飛び跳ねた。
信じられないほどのスピードで、数秒の間に高さ115メートルの木の頂点まで登った。疑う余地もないほど素晴らしい、蛇の能力を持つ人間だけが可能な行動だった。
“すごい... 何というジャンプ!...”、イブは思った。
イブとは違って、アダムは驚かず、ただ後を追った。
今度は赤毛の少年が驚きを与える番だ。すばらしい左右の動きで、『喋る蛇』に負けないスピードで木の根元から頂きまで登った。
二人は木の頂上に達した。そこは闘いには申し分のない競技場であった。
沈黙が天までを支配していた。
「まず初めに... お前に聞きたいことがある。何で僕なんだ?」
蛇人間は唇を軽く噛んだ。
「そのお前のうっとおしい態度のせいだ。お前は...甘えすぎている。俺はそれが我慢できない!」
イニシアティブをとるのは、常に、様々な打撃をアダムに与えていた『喋る蛇』だった。
最初の間は、アダムは反射神経をうまく使って防御し、執拗な攻撃に耐えていた。だが、能力と強さの差が少しずつ見え始め、次第に不平等な闘いになっていった。
アダムは対戦相手に完全に圧倒された。爬虫類の姿の時とは、レベルが全く違っていた。
「お前は、本当は自分自身が誰なのかを知らなくても... 」
アダムの顔にパンチ。
「お前は、本当は今どこにいるのかを知らなくても... 」
顔面に、パンチをもう一発。
「お前は、なぜ自分が存在するのかを知らなくても... 」
三発目は腹へ。
「お前は、全く何も知らなくても... !」
膝蹴りを、再び腹部へ。
怒り狂った蛇は、感情を抑えられずに、自分の人生の重荷を全部ぶちまけた。
少し間があいた。
『喋る蛇』は息を切らしている。それに対し、アダムは体の何箇所、特に顔から、血を流しながら、これまで通りのキリッとした目付きと朱色に光る目玉で敵の姿をじっと見ている。
怒り、悲しみ、痛み、更に妬みまで、全てを身体で受け入れる覚悟でいた。
《妬み?》
そう、いかなる状況でも、いつもあの朗らかな精神状態を保っている、無邪気な子供に対する蛇の妬み。
「それでも...それでも...なぜだ...?なぜ、お前はそんなに気楽に生きていられるんだ?!目的も理由も無いこの人生を?!」
蛇は再び攻撃した。この一撃に大きな意思を込めて。
しかし、『喋る蛇』の動きが鈍くなっているのか、それとも、アダムの動きがかなり良くなっているのか。
今回のパンチをアダムは避け、驚いた蛇は、何かが変わってきていることに気付き始めた。
だが、この足場の悪い場所で移動する唯一の手段は、枝から枝へ飛び移ることのみ、一歩でも踏み外せば、それが最後を意味する。
それがまさに起こった。
アダムが蛇の攻撃を上手にかわした動きは、枝と枝の隙間に気が付かなかった少年の不注意だけではなく、攻撃を失敗した瞬間に引き起こされた『喋る蛇』の不注意でもあった。
115メートルの落下が今、彼らを待っていた。
闘いを下からみていたイブは、彼らが陥った状況を信じたくなくて、手で口を覆った。
落下は、闘いを止めるには充分ではなかった。
空気のかたまりが圧縮されて、気圧が高まった。
地面に近づくほど、彼らの呼吸は困難になった。
80メートル。
連続打撃のやり取りが続く中、ますますアダムに有利な方向へ闘いの流れは傾き、すでに互角に戦っていた。
60メートル。
『喋る蛇』は、アダムに征服され、これまで保持していた闘いの支配権を失った。
50メートル。
闘いの流れを覆そうと、蛇は、油断しているアダムを捉え、屈服させようと体を締め付けた。これは、ある種の蛇が餌食を殺すために使う方法だ。
アダムは、あらゆる手段で蛇の締め付けから逃れようとした。
「自分自身が誰なのか、知らないかもしれない。今どこにいるのか、知らないかもしれない。なぜ自分が存在するのか、知らないかもしれない。けれども...信じている...生きる意味は、誰かに与えられるものではないと...お前が、自分自身の力で探すべきだ...お前の人生を、一生懸命に生きながら...」
『喋る蛇』は震え、アダムの言葉が心で響くのを感じていた。
40メートル。
「それは... その話はまったくのデタラメだ!」
「違う!」
30メートル。
「言いたいのは...ほら、お前の周りを見てみろ。この、まばゆい太陽... 」
太陽が遠くへ沈んでいく。その光が屈折して、赤とオレンジの色合いが二人の少年の瞳に映る。
「この大きな海... 」
その澄んだ水にも、光が屈折して見える。
「この世界の全て...」
太陽、海、木や草花が、最高に美しい景色を作り出していた。
「僕は恵まれている...この命に!だから、僕は自分自身に誓ったんだ。まるで今日が最後の日であるかのように、毎日を楽しんで生きて、その間に自分の人生の目的を見つけ出すと...後で後悔しないために!」
20メートル。
その瞬間、『喋る蛇』は、アダムのその『一撃』が深く心を貫いたのを感じた。敗北感に包まれた。
「これを、終わらせろ...」
「うん...」
アダムは、彼の襟元を掴んだ。
「僕は、終わらせるつもりだ...お前の中にある、その孤独をな!」
蛇に、新たな『一撃』が入れられた。
しかし、今回受けた攻撃の感覚は、今までとは違っていた。空っぽだったその胸の中が、アダムが放つポジティブなエネルギーとその言葉で、一瞬、満たされたようだった。
もう一度、彼はアダムを見た。
アダムが首に吊るしていた十字架が、持ち主の感情に反応して、ブルブルと震えている。
人間の目にはほとんど見えないくらい透き通った、神秘的な白いオーラが、アダムを包んだ。
アダムの目も同じく、透き通っていた。
その時、『喋る蛇』は気が付いた。
この少年が持っている力が、自分に欠けているものだと...
それは、信じる...力。
もしかしたら、運命の仕業だったのだろうか。
あるいは、ただの偶然が、結果として重要な役割を果たしたのか。
運命と偶然、どちらの仕業にしても、確かなことは、樹木の下の枝が落下を遅らせて衝撃を和らげ、最終的に二人の命を救ったことだった。
二人の少年はひっくり返った。あまりの痛さに、泣き言をこぼした。
特にアダムは唸り続け、その「小さいお尻」がどれだけ痛むかを訴えた。
イブは,上空で何が起こったのかと不安を感じて、彼らに駆け寄った。
まず始めに、緑色の髪の少年へ近づいた。目を合わせようとかがみ込み、穏やかに微笑んだ。
「大丈夫?」
少年は目を合わせるのを避けた。負けてしまった今、どんな反応をすればいいのか分からなかった。
「ねえ、あなたには名前があるの?」
「いや... 」
イブはますます笑顔を浮かべた。
「じゃ... わたし、あなたにぴったりの名前を思い付いたの」
「え...?」
少年は目を上へ向けた。
やっと、イブを見た。
「ナーハーシュ 」
「『ナーハーシュ』...?」
「『輝く者』。」
ナーハーシュは顔を赤らめた。
枝だらけのズボンをはたき落としながら、アダムは立ち上がった。
顔、髪、服は、木の枝でまだ汚れている。
振り返り、今は『ナーハーシュ』と言う名の少年に、友情のしるしとして、手を差し出した。
「勝利は僕のものだ。さっさと一緒に来いよ、このバカ!」
ナーハーシュはこの振る舞いを受け入れ、アダムに起こしてもらった。
この幸福という誘惑には、抵抗できなかった。
立ち上がりながら、微かな頬笑みを浮かべた。
「『ナーハーシュ』...」
自分自身に、この名前を繰り返して言った。
不覚にも涙が目から溢れたが、少年はそれを素早く振り払った。
ゴシキヒワは翼を羽ばたかせ、自分がいるべき場所へと飛んでいきました。
こうして、ナーハーシュは旅立ったのでした...
新たな自分、新たな友人達と共に。
しかし、これが物語の終わりではありませんでした。
少年とヘビとの喧嘩、その結果は、アダムと『喋る蛇』、両者を限界まで行かせた戦い。そして、二人の和解、ナーハーシュのグループへの受け入れ。
これらの出来事は、まだ物語が途中である一冊の本の数ページに過ぎません。
我々が今なすべきことは、一枚ずつ、1ページずつ、めくっていくこと...
変えようがない...エンディングに...最終的にたどり着くまで。
これは...彼らの物語の続きです...
--前回の出来事から10日後--
アダム、イブ、ナーハーシュの三人組は、それから「くつろぎ」の日々を過ごした。(アダムとナーハーシュが絶えず言い争ったり、喧嘩したりすることも、一応「くつろぎ」ということにしておこう。)
しかし、その日常に飽きる日が、とうとうやって来た...その時、アダムが一つのアイディアを思い付いた。
「なあ...もう一回、あれ、試してみないか?」
『科学の木』の下で、少年は、その幹に寄りかかりながら、くつろいでいた。ちょうどその時、そこにイブはいなかった。
アダムのやや上、木の枝にいたナーハーシュにとっては、赤毛の少年の提案は思いがけないものだった。
「試す...って、何を?」
少年は首をひねり、下からナーハーシュを見上げた。
「あ、そうだった...ナーハーシュはその時まだ一緒じゃなかったんだっけ。」
イブが戻ってきたので、会話が止まる。かなり遠い場所まで花へ摘みに行っていたのだ。
両手に12輪のクチナシの花(その場所だけに生えている)、片手に半分ずつ持っている。
「ただいま」
イブはいつもどおりの優しい笑顔で、帰ってきたことを知らせた。
それから、花を置くためにしゃがみ、前に摘んでいたアマランサスと一緒にした。
「なあ、イブ。もう一度、『あそこ』へ行こうよ。今すぐ!」
「『あそこ』へ... 『あの』場所?」
『試す』、『あそこ』、『あの』。
ナーハーシュは、もう、何だかイライラしていた。どうやら、緑色の髪の少年だけが、会話が理解できないようだ。地面へ飛び降り、イブとアダムの間に割り込んだ。
「もう一度聞く。何のことを言ってるんだ?」
アダムは、わざとナーハーシュに答えず、ふざけて顔をしかめた。
「そこに行けば分かるさ。」
...
茂みに覆われた、狭いスペースにぎゅうぎゅう詰めの、あまり心地良くない体制で、3人はそこでじっとしている。まるで葉の海の中で溺れているかのようだ。真ん中にいるナーハーシュが、一番ソワソワしている。
「で...俺たちは何で隠れているんだ?」
ナーハーシュが、 やや大きな声で問いかけた。質問している内容とは、かなり、逆の行動である。
「シーッ...もう少し、近づいて見ろ。」
『喋る蛇』は言われたとおり、雨で濡れた地面を這いながら、真っ直ぐ進んだ。
茂みの裏側で、隙間から覗いた。
『生命の木』と呼ばれる、『科学の木』と同じくらいの大きさの巨大な樹木がそびえていた。その木を囲んで、12人が動かず、じっと立っている。そして、その全員がグレーのマントと頭巾をまとっている。
それらの姿からは、身長も、体重も全く同じ、要するに、身体的な特徴の全てが、同じに見えた。
まるでクローンのように、全てが同じだ。
第二の木...? そして...人間...?!
ナーハーシュは、驚きが見え見えの表情をした。
実際、彼が知っていた木は『科学の木』だけであり、この世にはアダムとイブと自分以外には誰もいないと本気で信じていたのだ。
「そうなんだ...実は、本当に人間なのかどうか、分からない。最初に彼らを見た時、僕らは彫刻じゃないかと思ったんだ。それ以来、何度かここへ来ているけれど、今まで指一本動かすところを見た事がない」
イブも頷く。自分の周りの世界についてどれだけ無知なのか、今でもまだ、誰かがそこに彫った像、もしくは、自然が創り上げたものだと、信じ込んでいる。
「でも、そんなことのために来たんじゃない。よく見ろ、木の上を。」
アダムは上を見上げて、その物体を小指で差した。
ナーハーシュは、アダムの指示通りの方角へ目を向けた。
『生命の木』の枝の先に、リンゴが一つ実っているのが見える。
「一つの...リンゴ?あれのどこが、そんなに特別なんだ?普通のリンゴにしか見えないけど...」
後方にいたアダムとイブも、ナーハーシュに合流しようと、地面を這いずっている。
「正直のところ、僕も知らない。」
「はぁ?」
これまでは黙って話を聞いているだけだったイブが、一瞬笑い声を上げ、二人の注目を浴びた。
「あんな多くの『見張り』に守られているからこそ、アダムはあのリンゴが特別に思えるんでしょ?違う?」
「うん、そうだ。」
その『謎解き』に、ナーハーシュはため息をつく。
「はぁ、ただの勘かよ...」
ガッカリすることでもない。だって、それはアダムがいつもやっている事だ。
それでも、目を一瞬でも離さないところを見ると、やはり、あれはただの果物ではないのだろう。
“うわべは人を欺く”―その時、ちょうどそんな考えが頭をよぎっていた。
「それで?あのリンゴ、どうする?」
何かイタズラを企んでいるのか、アダムは小悪魔のような笑みを浮かべた。
「簡単なことさ。僕らが盗むんだよ。」
...
全員、準備は出来ている。それぞれが、自分の配置についた。
『リンゴ強奪』作戦の開始には、第一幕担当アダムの合図を待つのみ。
5分前。話し合いと作戦の計画。
アダムは腕を組み、すでにリーダー気取りで作戦を立て始めた。
「よし、僕の作戦はこうだ。ナーハーシュが奴らの気を引いている間に、 僕がこっそりとリンゴを盗む。イブ、お前は茂みに隠れている方がいい、その方が安全だ。どう思う?」
アダムの単純さに呆れたナーハーシュは、この作戦全体に納得できなかった。特に、自分の役目に対しての不満は、ハッキリと表情と出ている。
しかし、 不満を本当に抱いていたのはイブだった。
結局、彼らはそれに気が付かなかった。
「言い換えれば、俺はお前の名誉のために囮になる、と言うことだ。賛成できない。」
「えっ?!なんてわがままなんだ!」
「わがままなのは、お前だろ!」
この件に関して無関心な態度を装っていたイブが、自分の意見を述べた。
「うーん... 計画自体はいいんだけど、作戦での役割が間違っている気がする。ほら、こっそりと行きたいのなら、蛇の姿のナーハーシュが一番の選択肢でしょ。ごめんね、アダム、でも、あなたが一番囮には向いているわ。」
少年に同情して笑いかけながら、話し終えた。
「えっ?それはないだろ!」
それに対し、ナーハーシュはすでに言い争いに勝った気でいる。
「へっへっへっ。俺も同感。」
アダムは反論できなかった。主役を取られて残念に思ったが、すぐに立ち直った。(本心では、この新しい役目も意外と立派だと思っている。)
「始める前に、お前らは何度もここへ来たって言っていたよな。その度に盗みに挑戦して、失敗したのか?」
ナーハーシュは疑問に思っていた。
「うん。まぁ、正確には『挑戦した』とは言えないけどな。実をいうと、木に近づくことさえ出来なかった。僕らが近づこうとする瞬間、いつも妙な気分がして...とても危険な。」
その奇妙な感覚を思い出しながら、胸に手を当てて、アダムは説明した。
“アダムが何かを諦める?” ―少年の話を聞きながら、ナーハーシュはそう思った。
気丈な性格のアダムは、すぐに気を取り直した。
「けれど、今回は違う。今回はナーハーシュ、お前がいるからな!」
ナーハーシュは仲間につられて笑った。もちろん、さっきまでの心配は、忘れてしまっていた。
イブも笑顔を見せた。これで、三人の意見が一致した。
「あっ、この作戦にピッタリの名前を思い付いた。」
「えっ?何?」
ナーハーシュは知りたがっている。
「『リンゴ強奪』作戦。」
ナーハーシュとイブが大声を出して笑う。それから、蛇はため息をついた。
「まぁ、いいか、それで。成功さえしてくれるのなら、名前なんか別にどうでもいい。」
「そうね、私も賛成」― イブからしてみても、取るに足らない、ささいな一面に過ぎなかった。―「じゃ、やってみる?」
「うん、100%準備オッケー!」
アダムはやる気を更に増している...100%やる気満々だ。
「いつでもいいよ。」
ナーハーシュが開始の指示を待っている。
合図はアダムが出す事になっている。
「よし...『リンゴ強奪』作戦、スタート!」
...
全員、準備は出来ている。
それぞれが、指定されたポジションについた。アダムが頭巾を被っている生気の無い人物らの20メートルくらい手前、既に爬虫類の姿になったナーハーシュは、アダムの左の茂みに隠れ、イブは後ろで、彼らが出ていった茂みに残った。
「よう!しばらくぶりだねぇ。」
朱色の瞳の少年は挨拶するが、これらの謎の人物たちからの返事は無い。
「ヘッ。よそよそしいなぁ、相変わらず...」
アダムがもう少し前へ進む。
地面にしゃがんで石を一つ拾い、一列に並んでいる中の六人目を目掛けてそれを投げた。
ところが、ナーハーシュ(その時、木の方向へと辺りを一周していた)が驚いたことに、この石ころは、その人物の体を、まるで実体がないかのように、通り抜けた。彼だけが、この現象をまだ一度も見たことがなかったのだ。
「えっ...体を通り抜けた?!」
ナーハーシュには、たった今起こったことが信じられなかった。
初めて目撃したわけでもないアダムも、多少の驚きを隠せないでいた。以前にも何回か、同じように挑発したことがあったからだ。
イブはその瞬間、背筋に寒気がした。
今のは...恐怖? そうだとしても、何に対して?それから、なぜ、こんなに唐突に?
頭巾の人物からの明らかな反応は無く、何が何でも、じっと動かないつもりだ。
「ああ!間違ってると思ったこともあるけど、やっぱり僕の考えは当たってた。お前ら、幽霊だろ?そうだろ?でも運が悪かったな。あいにく、僕は幽霊なんか怖くないのさ!蛇だって怖くない...」―それとなく見せかけて、明らかにナーハッシュへの当て付けだ―「幽霊だって怖くない...」―更に続ける―「怖いものなんか、何もないぞ!」
嫌な予感。
何だろう?
イブは自分自身に問いかけていた。
何かが起ころうとしている。危ない。二人が...危ない。
アダムがもう一歩、前へ踏み出した。
作戦は危険にさらされている。
“やめて、アダム。”
(続く...)
プロローグ
Radicibus
[第一部]
この物語では、人類の始まりへ遡ります。まだ何も存在しない時代 です。
何もない、ただ、若い3羽のゴシキヒワだけが、翼を広げて,
自分自身を発見するために羽ばたく瞬間を熱心に待っています。
これは、運命がいかに彼らを巡りあわせ、
それぞれの人生が驚くほど変わってしまったかについての物語です。
文章:ミツアキ・セイジ (ティアーゴ・マルケス)
軽くて柔らかい風が、『科学の木』の赤い葉をはためかせた。それは、世界の中心、『エデンの園』にある『神』によって作られた2本の特別な樹木の1つである。
この巨大な樹木(高さ約115メートル)の下、自然の創造の中で最も美しいとされる庭園の広大で美しい景観に囲まれながら、一人の12歳の少年が幹に寄りかかって昼寝をしていた。
「アダム、気をつけて!」
アダムの横には、同じ年齢のイブと呼ばれる一人の少女が休んでいた。静かな一時を起きたまま、そこに生えているアマランサスを集めて遊んでいた。
女の子は突然、悪意の気配を感じた。
茂みから何かが アダムをじっと見ている。
捕食者は獲物に襲いかかり、その有毒な牙で犠牲者の人生をひとかじりで終わらせようとした。
アダムは弱い立場におかれた。
死を意味するであろう。
終わりを避けるのには、もう遅すぎるのだろうか...?
「捕まえたぞ、『喋る蛇』! 」
「シュー!いつも他人に頼ってばかり!」
アダムがイブの直覚に頼りすぎることを指していた。
本当は、少年は『喋る蛇』の攻撃への準備ができていて、それに反撃する瞬間を待っていたのだ。
蛇は少年の手から抜け出した。
再攻撃するつもりだ。
アダムの腕を素早い動きで滑り抜け、今度は敵の顔に狙いを付けた。
しかし、攻撃するその瞬間、蛇は自分の体のほぼ3分の1を持ち上げ、大きな円を描いて、アダムの頭上を完全に跳び越した。
結局、蛇には二度目の攻撃の意図はなかったのだ。
蛇は素晴らしい動きで着地した。
少年と向かい合い、数メートルの距離が2つの視線を隔てた。
「 おい、準備はできている。 早く来い!」
右足でしっかり地面に支えて、手を位置に構え、少年は『戦闘モード』に入った。
イブは心配しながら、ただ、見守っている。
蛇はアダムに背を向け、挑戦を断った。
その態度は 赤毛の少年を驚かせた。彼は蛇を逃がすつもりはあまり無かった。
「何だ? 逃げるのか? そっちが始めたんだろう? なんて臆病なんだ!」
蛇の限界を試そうと、腰に手を当ててさらに挑発した。
アダムの挑発に反応して、『喋る蛇』は首をひねり舌を出した。
「笑っていられるのも今のうちだ。もし、貴様がガードを緩めたら...忘れかけたときに、その哀れな命を取れるよう、俺ははいつも傍にいるぞ...バカヤロー!」
「な... 何だと?! このヤロー、今度こそ! 」
イブの腕の中アダムは叫んだ。イブは怒り狂う少年が蛇の後を追わないように押さえていたのだ。
「ここへ戻れ! これからが第2ラウンドだ!」
「落ち着いて。もう行ってしまったわ。」
イブは、ため息をつきながらも、新たな喧嘩を防ごうと必死だった。
少年は頭を上げて遠くを見た。蛇は逃げたのだろうか、その姿はもうどこにも無かった。
「5日間も同じことが続いている... 蛇は一体、何を望んでいるの?」
イブは疑問に思っていることを声に出して自問した。そして、ふと、頭に浮かんだ。
「まさか... ね?」
...
それ以来、 『喋る蛇』は、毎日ように現れては、アダムの命を狙いました。
こうして、5日間が過ぎていきました。
捕食者も獲物も妥協しないまま、
とうとうどちらが最後まで生き残るかに決着をつける時がやって来ました。
...
彼らは再び、目と目を合わせて、対峙している。
闘いの十日目。
「おい、お前は本当にしつこいな」
アダムは微笑んだ。
彼の下唇からは 血が大量に出ている。顔にあるたくさんの傷跡は、両者の闘いがどれほど激しいものかを示していた。
「ふん、バカバカしい!」
「何だと?!」
『喋る蛇』は一瞬、黙った。
その閉じた目と穏やかな呼吸は、これから言うことを深く考えている印だ。
「決着をつけよう。 明日の午後が、最後の闘いだ。」
この発言は、アダムとイブを驚ろかせた。
まさかこんなにも早くに決着の日が来るとは、アダムは思ってもいなかった。
“いや、もしかしたら、この問題を解決する最高の時なのかもしれない。”
闘いへの興奮を抑えられず、アダムはかすかな笑みを浮かべた。
「いいだろう。終わりにしよう。」
『喋る蛇』がその場を去った直後、イブがアダムに近づいた。何かで真剣に悩んでいる様子だ。
「イブ、どうした?」
たった今、死を賭けた決闘を受け入れたことを思えば、アダムの表情は意外と平静だった。
「なぜ蛇がこんなことをやっているのか... 私は本当の理由を知っているわ」
アダムは不意打ちを食らった。
少女の言葉を真に受けず、皮肉な笑みを浮かべた。
「イブ、何を言っているんだ?あいつは、ただの災い...」
「良く考えてみて!蛇の本当の目的は、あなたと言い合ったり、闘いを始めたりすることじゃない。それは、おそらく、他人と触れ合う方法を他に知らないから。そうよ...今までの間ずっと、蛇は私達に近づこうとしていた。あなたに近づこうとしていた! 」
明らかにされた真実に、アダムは動揺した。イブの言葉に全身が震えるのを感じた。
「私には理解できる...私は運良く、アダム、あなた出会えた 。でも、もし会えていなかったら、私もおそらく同じように...孤独を感じていたでしょう。 だって、結局は...私達もまったくのひとりぼっちよ...
この世界には他に誰もいないのだから!」
込み上がる感情を抑えきれず、イブの最後の言葉は必死だった 。
衝撃を受けたアダムは、どう反応すればいいのかが、わからなかった。
いや、反応できなかった。
今まで、全く気が付かなかった。
あんなにも、はっきりしていたのに。
あんなにも、すぐ目の前にあったのに。
次の瞬間、アダムはあまりの考えの浅さに、自分自身を責めた。
少年は決心した。
これから先、もう間違いは犯したくない。
イブの気持ちが少年の心を動かしたのだ。
少年はそれを認識した。
「ありがとう、イブ。それから、ごめん。これは、僕が必ず終わらせてみせる。約束だ! 」
通り過ぎる時、決然とした表情をイブに見せた。
...
闘いの最終日は...今日
太陽の日差しはまだ強く、午後の穏やかな気候はこの場にぴったりだった。
アダムとイブが、最初にその場所(いつも彼らの争いが起こった)に到着した 。今、これが最後の対決になるだろう。
アダムは、前日にイブに見せた、決然とした表情を維持したままだ。
彼の決心は変わっていない。
数分後、第三者が彼らの前に現れた。
ところが驚いたことに、『喋る蛇』ではなく、今まで見たことのない顔をした少年だった。年齢は彼らと同じくらいで、背はアダムよりやや高かった。
しかしながら、イブにはこの少年の冷たい視線には見覚えがあった。暗緑色の目と奇妙な虹彩、確かに以前、どこかで見たことがある気がした。
「ええっと... もしかして、道に迷ったのかな?」
アダムは、少し混乱しつつも、穏やかな笑顔で尋ねた。
イブはこの見知らぬ少年から目が離せなかった。以前、彼らが出会っていることは、ほぼ確かなはずだ。
“ええ、あの視線、あの目...まさか、彼が...?!”
「もしかして、あなたは...?」
「これは俺の人間の姿 — 真の姿だ。 問題あるのか?」
イブの仮説を証明し、アダムが彼の正体を理解するには、その言葉は充分だった。
「男の子?! 」
アダムの言葉にイブが反応した。
「こんなことで驚いているの?!」
「さあ... これで終わりにしよう。 」
アダムはしっかりと頷く。
「うん。」
まず、蛇少年が『科学の木』の根元まで先に歩き始めた。
そこで止まった。
彼は 足で強く地面を支え、その足を完全に地中まで突き刺した。
その支えを反動として利用し、 木の上を目掛け、大きく飛び跳ねた。
信じられないほどのスピードで、数秒の間に高さ115メートルの木の頂点まで登った。疑う余地もないほど素晴らしい、蛇の能力を持つ人間だけが可能な行動だった。
“すごい... 何というジャンプ!...”、イブは思った。
イブとは違って、アダムは驚かず、ただ後を追った。
今度は赤毛の少年が驚きを与える番だ。すばらしい左右の動きで、『喋る蛇』に負けないスピードで木の根元から頂きまで登った。
二人は木の頂上に達した。そこは闘いには申し分のない競技場であった。
沈黙が天までを支配していた。
「まず初めに... お前に聞きたいことがある。何で僕なんだ?」
蛇人間は唇を軽く噛んだ。
「そのお前のうっとおしい態度のせいだ。お前は...甘えすぎている。俺はそれが我慢できない!」
イニシアティブをとるのは、常に、様々な打撃をアダムに与えていた『喋る蛇』だった。
最初の間は、アダムは反射神経をうまく使って防御し、執拗な攻撃に耐えていた。だが、能力と強さの差が少しずつ見え始め、次第に不平等な闘いになっていった。
アダムは対戦相手に完全に圧倒された。爬虫類の姿の時とは、レベルが全く違っていた。
「お前は、本当は自分自身が誰なのかを知らなくても... 」
アダムの顔にパンチ。
「お前は、本当は今どこにいるのかを知らなくても... 」
顔面に、パンチをもう一発。
「お前は、なぜ自分が存在するのかを知らなくても... 」
三発目は腹へ。
「お前は、全く何も知らなくても... !」
膝蹴りを、再び腹部へ。
怒り狂った蛇は、感情を抑えられずに、自分の人生の重荷を全部ぶちまけた。
少し間があいた。
『喋る蛇』は息を切らしている。それに対し、アダムは体の何箇所、特に顔から、血を流しながら、これまで通りのキリッとした目付きと朱色に光る目玉で敵の姿をじっと見ている。
怒り、悲しみ、痛み、更に妬みまで、全てを身体で受け入れる覚悟でいた。
《妬み?》
そう、いかなる状況でも、いつもあの朗らかな精神状態を保っている、無邪気な子供に対する蛇の妬み。
「それでも...それでも...なぜだ...?なぜ、お前はそんなに気楽に生きていられるんだ?!目的も理由も無いこの人生を?!」
蛇は再び攻撃した。この一撃に大きな意思を込めて。
しかし、『喋る蛇』の動きが鈍くなっているのか、それとも、アダムの動きがかなり良くなっているのか。
今回のパンチをアダムは避け、驚いた蛇は、何かが変わってきていることに気付き始めた。
だが、この足場の悪い場所で移動する唯一の手段は、枝から枝へ飛び移ることのみ、一歩でも踏み外せば、それが最後を意味する。
それがまさに起こった。
アダムが蛇の攻撃を上手にかわした動きは、枝と枝の隙間に気が付かなかった少年の不注意だけではなく、攻撃を失敗した瞬間に引き起こされた『喋る蛇』の不注意でもあった。
115メートルの落下が今、彼らを待っていた。
闘いを下からみていたイブは、彼らが陥った状況を信じたくなくて、手で口を覆った。
落下は、闘いを止めるには充分ではなかった。
空気のかたまりが圧縮されて、気圧が高まった。
地面に近づくほど、彼らの呼吸は困難になった。
80メートル。
連続打撃のやり取りが続く中、ますますアダムに有利な方向へ闘いの流れは傾き、すでに互角に戦っていた。
60メートル。
『喋る蛇』は、アダムに征服され、これまで保持していた闘いの支配権を失った。
50メートル。
闘いの流れを覆そうと、蛇は、油断しているアダムを捉え、屈服させようと体を締め付けた。これは、ある種の蛇が餌食を殺すために使う方法だ。
アダムは、あらゆる手段で蛇の締め付けから逃れようとした。
「自分自身が誰なのか、知らないかもしれない。今どこにいるのか、知らないかもしれない。なぜ自分が存在するのか、知らないかもしれない。けれども...信じている...生きる意味は、誰かに与えられるものではないと...お前が、自分自身の力で探すべきだ...お前の人生を、一生懸命に生きながら...」
『喋る蛇』は震え、アダムの言葉が心で響くのを感じていた。
40メートル。
「それは... その話はまったくのデタラメだ!」
「違う!」
30メートル。
「言いたいのは...ほら、お前の周りを見てみろ。この、まばゆい太陽... 」
太陽が遠くへ沈んでいく。その光が屈折して、赤とオレンジの色合いが二人の少年の瞳に映る。
「この大きな海... 」
その澄んだ水にも、光が屈折して見える。
「この世界の全て...」
太陽、海、木や草花が、最高に美しい景色を作り出していた。
「僕は恵まれている...この命に!だから、僕は自分自身に誓ったんだ。まるで今日が最後の日であるかのように、毎日を楽しんで生きて、その間に自分の人生の目的を見つけ出すと...後で後悔しないために!」
20メートル。
その瞬間、『喋る蛇』は、アダムのその『一撃』が深く心を貫いたのを感じた。敗北感に包まれた。
「これを、終わらせろ...」
「うん...」
アダムは、彼の襟元を掴んだ。
「僕は、終わらせるつもりだ...お前の中にある、その孤独をな!」
蛇に、新たな『一撃』が入れられた。
しかし、今回受けた攻撃の感覚は、今までとは違っていた。空っぽだったその胸の中が、アダムが放つポジティブなエネルギーとその言葉で、一瞬、満たされたようだった。
もう一度、彼はアダムを見た。
アダムが首に吊るしていた十字架が、持ち主の感情に反応して、ブルブルと震えている。
人間の目にはほとんど見えないくらい透き通った、神秘的な白いオーラが、アダムを包んだ。
アダムの目も同じく、透き通っていた。
その時、『喋る蛇』は気が付いた。
この少年が持っている力が、自分に欠けているものだと...
それは、信じる...力。
もしかしたら、運命の仕業だったのだろうか。
あるいは、ただの偶然が、結果として重要な役割を果たしたのか。
運命と偶然、どちらの仕業にしても、確かなことは、樹木の下の枝が落下を遅らせて衝撃を和らげ、最終的に二人の命を救ったことだった。
二人の少年はひっくり返った。あまりの痛さに、泣き言をこぼした。
特にアダムは唸り続け、その「小さいお尻」がどれだけ痛むかを訴えた。
イブは,上空で何が起こったのかと不安を感じて、彼らに駆け寄った。
まず始めに、緑色の髪の少年へ近づいた。目を合わせようとかがみ込み、穏やかに微笑んだ。
「大丈夫?」
少年は目を合わせるのを避けた。負けてしまった今、どんな反応をすればいいのか分からなかった。
「ねえ、あなたには名前があるの?」
「いや... 」
イブはますます笑顔を浮かべた。
「じゃ... わたし、あなたにぴったりの名前を思い付いたの」
「え...?」
少年は目を上へ向けた。
やっと、イブを見た。
「ナーハーシュ 」
「『ナーハーシュ』...?」
「『輝く者』。」
ナーハーシュは顔を赤らめた。
枝だらけのズボンをはたき落としながら、アダムは立ち上がった。
顔、髪、服は、木の枝でまだ汚れている。
振り返り、今は『ナーハーシュ』と言う名の少年に、友情のしるしとして、手を差し出した。
「勝利は僕のものだ。さっさと一緒に来いよ、このバカ!」
ナーハーシュはこの振る舞いを受け入れ、アダムに起こしてもらった。
この幸福という誘惑には、抵抗できなかった。
立ち上がりながら、微かな頬笑みを浮かべた。
「『ナーハーシュ』...」
自分自身に、この名前を繰り返して言った。
不覚にも涙が目から溢れたが、少年はそれを素早く振り払った。
ゴシキヒワは翼を羽ばたかせ、自分がいるべき場所へと飛んでいきました。
こうして、ナーハーシュは旅立ったのでした...
新たな自分、新たな友人達と共に。
しかし、これが物語の終わりではありませんでした。
少年とヘビとの喧嘩、その結果は、アダムと『喋る蛇』、両者を限界まで行かせた戦い。そして、二人の和解、ナーハーシュのグループへの受け入れ。
これらの出来事は、まだ物語が途中である一冊の本の数ページに過ぎません。
我々が今なすべきことは、一枚ずつ、1ページずつ、めくっていくこと...
変えようがない...エンディングに...最終的にたどり着くまで。
これは...彼らの物語の続きです...
--前回の出来事から10日後--
アダム、イブ、ナーハーシュの三人組は、それから「くつろぎ」の日々を過ごした。(アダムとナーハーシュが絶えず言い争ったり、喧嘩したりすることも、一応「くつろぎ」ということにしておこう。)
しかし、その日常に飽きる日が、とうとうやって来た...その時、アダムが一つのアイディアを思い付いた。
「なあ...もう一回、あれ、試してみないか?」
『科学の木』の下で、少年は、その幹に寄りかかりながら、くつろいでいた。ちょうどその時、そこにイブはいなかった。
アダムのやや上、木の枝にいたナーハーシュにとっては、赤毛の少年の提案は思いがけないものだった。
「試す...って、何を?」
少年は首をひねり、下からナーハーシュを見上げた。
「あ、そうだった...ナーハーシュはその時まだ一緒じゃなかったんだっけ。」
イブが戻ってきたので、会話が止まる。かなり遠い場所まで花へ摘みに行っていたのだ。
両手に12輪のクチナシの花(その場所だけに生えている)、片手に半分ずつ持っている。
「ただいま」
イブはいつもどおりの優しい笑顔で、帰ってきたことを知らせた。
それから、花を置くためにしゃがみ、前に摘んでいたアマランサスと一緒にした。
「なあ、イブ。もう一度、『あそこ』へ行こうよ。今すぐ!」
「『あそこ』へ... 『あの』場所?」
『試す』、『あそこ』、『あの』。
ナーハーシュは、もう、何だかイライラしていた。どうやら、緑色の髪の少年だけが、会話が理解できないようだ。地面へ飛び降り、イブとアダムの間に割り込んだ。
「もう一度聞く。何のことを言ってるんだ?」
アダムは、わざとナーハーシュに答えず、ふざけて顔をしかめた。
「そこに行けば分かるさ。」
...
茂みに覆われた、狭いスペースにぎゅうぎゅう詰めの、あまり心地良くない体制で、3人はそこでじっとしている。まるで葉の海の中で溺れているかのようだ。真ん中にいるナーハーシュが、一番ソワソワしている。
「で...俺たちは何で隠れているんだ?」
ナーハーシュが、 やや大きな声で問いかけた。質問している内容とは、かなり、逆の行動である。
「シーッ...もう少し、近づいて見ろ。」
『喋る蛇』は言われたとおり、雨で濡れた地面を這いながら、真っ直ぐ進んだ。
茂みの裏側で、隙間から覗いた。
『生命の木』と呼ばれる、『科学の木』と同じくらいの大きさの巨大な樹木がそびえていた。その木を囲んで、12人が動かず、じっと立っている。そして、その全員がグレーのマントと頭巾をまとっている。
それらの姿からは、身長も、体重も全く同じ、要するに、身体的な特徴の全てが、同じに見えた。
まるでクローンのように、全てが同じだ。
第二の木...? そして...人間...?!
ナーハーシュは、驚きが見え見えの表情をした。
実際、彼が知っていた木は『科学の木』だけであり、この世にはアダムとイブと自分以外には誰もいないと本気で信じていたのだ。
「そうなんだ...実は、本当に人間なのかどうか、分からない。最初に彼らを見た時、僕らは彫刻じゃないかと思ったんだ。それ以来、何度かここへ来ているけれど、今まで指一本動かすところを見た事がない」
イブも頷く。自分の周りの世界についてどれだけ無知なのか、今でもまだ、誰かがそこに彫った像、もしくは、自然が創り上げたものだと、信じ込んでいる。
「でも、そんなことのために来たんじゃない。よく見ろ、木の上を。」
アダムは上を見上げて、その物体を小指で差した。
ナーハーシュは、アダムの指示通りの方角へ目を向けた。
『生命の木』の枝の先に、リンゴが一つ実っているのが見える。
「一つの...リンゴ?あれのどこが、そんなに特別なんだ?普通のリンゴにしか見えないけど...」
後方にいたアダムとイブも、ナーハーシュに合流しようと、地面を這いずっている。
「正直のところ、僕も知らない。」
「はぁ?」
これまでは黙って話を聞いているだけだったイブが、一瞬笑い声を上げ、二人の注目を浴びた。
「あんな多くの『見張り』に守られているからこそ、アダムはあのリンゴが特別に思えるんでしょ?違う?」
「うん、そうだ。」
その『謎解き』に、ナーハーシュはため息をつく。
「はぁ、ただの勘かよ...」
ガッカリすることでもない。だって、それはアダムがいつもやっている事だ。
それでも、目を一瞬でも離さないところを見ると、やはり、あれはただの果物ではないのだろう。
“うわべは人を欺く”―その時、ちょうどそんな考えが頭をよぎっていた。
「それで?あのリンゴ、どうする?」
何かイタズラを企んでいるのか、アダムは小悪魔のような笑みを浮かべた。
「簡単なことさ。僕らが盗むんだよ。」
...
全員、準備は出来ている。それぞれが、自分の配置についた。
『リンゴ強奪』作戦の開始には、第一幕担当アダムの合図を待つのみ。
5分前。話し合いと作戦の計画。
アダムは腕を組み、すでにリーダー気取りで作戦を立て始めた。
「よし、僕の作戦はこうだ。ナーハーシュが奴らの気を引いている間に、 僕がこっそりとリンゴを盗む。イブ、お前は茂みに隠れている方がいい、その方が安全だ。どう思う?」
アダムの単純さに呆れたナーハーシュは、この作戦全体に納得できなかった。特に、自分の役目に対しての不満は、ハッキリと表情と出ている。
しかし、 不満を本当に抱いていたのはイブだった。
結局、彼らはそれに気が付かなかった。
「言い換えれば、俺はお前の名誉のために囮になる、と言うことだ。賛成できない。」
「えっ?!なんてわがままなんだ!」
「わがままなのは、お前だろ!」
この件に関して無関心な態度を装っていたイブが、自分の意見を述べた。
「うーん... 計画自体はいいんだけど、作戦での役割が間違っている気がする。ほら、こっそりと行きたいのなら、蛇の姿のナーハーシュが一番の選択肢でしょ。ごめんね、アダム、でも、あなたが一番囮には向いているわ。」
少年に同情して笑いかけながら、話し終えた。
「えっ?それはないだろ!」
それに対し、ナーハーシュはすでに言い争いに勝った気でいる。
「へっへっへっ。俺も同感。」
アダムは反論できなかった。主役を取られて残念に思ったが、すぐに立ち直った。(本心では、この新しい役目も意外と立派だと思っている。)
「始める前に、お前らは何度もここへ来たって言っていたよな。その度に盗みに挑戦して、失敗したのか?」
ナーハーシュは疑問に思っていた。
「うん。まぁ、正確には『挑戦した』とは言えないけどな。実をいうと、木に近づくことさえ出来なかった。僕らが近づこうとする瞬間、いつも妙な気分がして...とても危険な。」
その奇妙な感覚を思い出しながら、胸に手を当てて、アダムは説明した。
“アダムが何かを諦める?” ―少年の話を聞きながら、ナーハーシュはそう思った。
気丈な性格のアダムは、すぐに気を取り直した。
「けれど、今回は違う。今回はナーハーシュ、お前がいるからな!」
ナーハーシュは仲間につられて笑った。もちろん、さっきまでの心配は、忘れてしまっていた。
イブも笑顔を見せた。これで、三人の意見が一致した。
「あっ、この作戦にピッタリの名前を思い付いた。」
「えっ?何?」
ナーハーシュは知りたがっている。
「『リンゴ強奪』作戦。」
ナーハーシュとイブが大声を出して笑う。それから、蛇はため息をついた。
「まぁ、いいか、それで。成功さえしてくれるのなら、名前なんか別にどうでもいい。」
「そうね、私も賛成」― イブからしてみても、取るに足らない、ささいな一面に過ぎなかった。―「じゃ、やってみる?」
「うん、100%準備オッケー!」
アダムはやる気を更に増している...100%やる気満々だ。
「いつでもいいよ。」
ナーハーシュが開始の指示を待っている。
合図はアダムが出す事になっている。
「よし...『リンゴ強奪』作戦、スタート!」
...
全員、準備は出来ている。
それぞれが、指定されたポジションについた。アダムが頭巾を被っている生気の無い人物らの20メートルくらい手前、既に爬虫類の姿になったナーハーシュは、アダムの左の茂みに隠れ、イブは後ろで、彼らが出ていった茂みに残った。
「よう!しばらくぶりだねぇ。」
朱色の瞳の少年は挨拶するが、これらの謎の人物たちからの返事は無い。
「ヘッ。よそよそしいなぁ、相変わらず...」
アダムがもう少し前へ進む。
地面にしゃがんで石を一つ拾い、一列に並んでいる中の六人目を目掛けてそれを投げた。
ところが、ナーハーシュ(その時、木の方向へと辺りを一周していた)が驚いたことに、この石ころは、その人物の体を、まるで実体がないかのように、通り抜けた。彼だけが、この現象をまだ一度も見たことがなかったのだ。
「えっ...体を通り抜けた?!」
ナーハーシュには、たった今起こったことが信じられなかった。
初めて目撃したわけでもないアダムも、多少の驚きを隠せないでいた。以前にも何回か、同じように挑発したことがあったからだ。
イブはその瞬間、背筋に寒気がした。
今のは...恐怖? そうだとしても、何に対して?それから、なぜ、こんなに唐突に?
頭巾の人物からの明らかな反応は無く、何が何でも、じっと動かないつもりだ。
「ああ!間違ってると思ったこともあるけど、やっぱり僕の考えは当たってた。お前ら、幽霊だろ?そうだろ?でも運が悪かったな。あいにく、僕は幽霊なんか怖くないのさ!蛇だって怖くない...」―それとなく見せかけて、明らかにナーハッシュへの当て付けだ―「幽霊だって怖くない...」―更に続ける―「怖いものなんか、何もないぞ!」
嫌な予感。
何だろう?
イブは自分自身に問いかけていた。
何かが起ころうとしている。危ない。二人が...危ない。
アダムがもう一歩、前へ踏み出した。
作戦は危険にさらされている。
“やめて、アダム。”
(続く...)