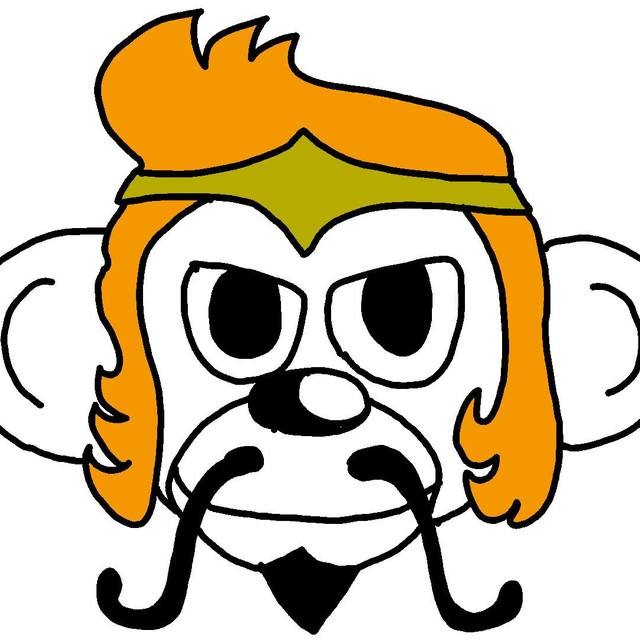第3話
文字数 19,259文字
第三章 エジプシャンストーリーテラーとの遭遇
サルバトーレの記録を読み、私、マック・デビッド・エストは、その冒険を楽しんだ。彼らの舟は、その後、約五ヶ月かけて、地球にもどった。
そしてロベルトくんたちは、その舟の推進力で宇宙に旅立った。
あれが、二〇〇八年八月十五日だった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
そうだ、あのロベルトくんたちだが、Eメールによれば、彼らは宇宙海賊に打ち勝ち、現在は地球への帰路にあるようだ。多くの旅路で、みな多くの経験をし、心を広げ、そしてまた何処かで再会する、・・・・・・・・・・それが人生の醍醐味だ。
私は、ロベルト・ディアスやサルバトーレ・メイヨーらと出会い、彼らの物語を知り、私が知らなかった世界を少し知った。人生のコネクションやリンクは計り知れない・・・・・・・・・・。
一九九七年ごろだったかな、・・・香港がもうすぐ中国に返還されようとしていた時代だった。ウォン・カーウァイという香港映画界の映画監督・脚本家が 『恋する惑星』という映画を作った。多くの熱狂的ファンを生んだ。そこでは、一瞬の出会いや人のリンクが、世界を、愛を、紡ぎ出していく事が語られ た・・・・・・・・・・。
私はこれから、どんなことを人生の旅路で経験するのか分からないが、それは私のために与えられる経験なのだと思う。何かの一瞬が、人生に大きな大切な意味を持たせることもあるかもしれない。
そんな気持ちを抱きながら私は、今回の旅路の、最後の土地を目差していたのだ・・・・・・・・・・。
それは、エジプト。
私の、これまでの、別の次元を探究するための、長い世界旅行も残すところ、あと十日だ。
多くの宇宙人との出会いが起きたと言われているエジプトに入った。
首都カイロにある国際空港から、私のエジプトでの行動は開始された。
イスラミックなサウンドが響き渡るハウジングに、私は数日の宿を取った。
ここエジプトで、私は、生命について、その神秘について、そのプレシャスさについて、短期のセッションを通して学ぶことになっていた。そこの師が、やはり出会っていたからだ。そう、宇宙人に。
何かが、ゼロに戻ったような気がした。
私の気のせいかも知れない。
人生は螺旋階段のようなものだとも聞く。
螺旋の円周の同じポイントに居るのかもしれない。
私マック・デビッドは、その一日を再考するために、ジャーナルをつけることがあるのだ。
{ジャーナル}
二〇〇九年一月九日
グローサリーで、米ドル二十八ドル分の買い物をした。
自分の部屋に戻って、食事を楽しんだ。
ミスター・ヌードルズ(ベジタブル味)と、ハンガリアン・サラミ。
わたしの好きな味なのだ。ハンガリアン・サラミが、熱いベジタブル・スープに浸り、すこし固くなった時、ヌードルと一緒に食べるのが旨い。
二〇〇九年一月十日
カイロの街中で、ふとキリスト教の伝道者に出会い、ともに、祈りを捧げた。
私は、キリストの教えを小さい頃から多く聞いたが、キリスト教会を離れたこともあった。しかし、キリストの教えは、真理だと感じることは変わらなかった。
私の欲望が、教会を離れた原因であった。
しかし、再び、教会に戻った私を教会は、温かく迎えた。
私には、一種の放浪癖があった。
長く、同じ状態に居られなかったのだ。
人間は、難しい存在だと思う。
聖書は、こういう存在である人間について、多くのインストラクションを内包している。
命について、そこから、学ぶことができる。
人間は現在、多くの自然に対し、危機的状況を作り出しているという。
しかし、人間は、テクノロジーを必要とする。それがなければ、生きられない。我々は、自然環境とテクノロジーの共存を模索していかねばならないのだ。これは『生命』に関する課題だ。
二〇〇九年一月十一日
人生、すなわち地上での生命には段階がある。時がある。
だんだん歳を重ねると、意外と幸せが身近にあったと気付く。
私の場合、フランスの片田舎の生活にも幸せを見出せるようになったのは、三十五になってからだ。
ローカルの小さな料理屋さんの、オリジナルのスープの美味しさや、麦畑の美しさ。
そうした幸せは、十代では気付かないし、気付けと言っても無理な話だ。
若さは、まだ見ぬ遠い世界を見たい心だ。
それは、大切な命の輝きだと思う。
二〇〇九年一月十二日
ユーロ系のルーツを持つ私だったが、多くのアジアを含む国々での生活経験から、アジア料理が好きだった。生活空間の中で、いくつかのアジア言語を少しず つ覚えていたが、文字によってアジア言語を読解することは、私には難しかった。こういう現象は、西洋人には、よくあることだ。我々は、ベーシックの部分で チャイニーズ・キャラクターズ(漢字)を習得していないのだ。
私がカイロを歩いていると、二人のアジア女性に出会い、日本のアニメーションについて会話の花が咲いた。西洋では、『アニメーション』は西洋産のアニメーション映画を言い、『アニメ』は日本産の独特なスタイルを持つアニメーションへの、王冠的呼称として使われる言葉だ。
アジアでは、西洋より多くの日本アニメが流入しているようで、私の知識は、そこでは、大きくはなかった。我々は、このごろ、『アメリカン・アニメーショ ン』と『アニメ』が、いろいろな所で「結婚しはじめている」(西洋では、二種の文化が混合してゆくことを、文化が結婚する、という表現を多く使用する)こ とを面白く話せた。
『アニメーション』(ANIMATION)という単語は、英語の『アニメイト』(ANIMATE)=生命を与える、から出たわけだが、まさに、芸術家たち が、絵に命を与える、絵を動かす、という夢を持っていたことが分かる。神が人を造った、その精神が、人の中にもあって、それが、こうした創造物を生み出す 原動力になっているのかもしれない。
そんな話をしながら、我々は、アジア料理のお店で、食事をし、お酒を飲んだ。私は、エジプトの現地料理であるコシャリやスパイシーチキンなども、すごく好きだったが、その日は、アジアンな1日となった。
{アジアのディッシュ}
ライス、アジアン・ポーク・スープ、アジアンビール、アジアンワイン、アジアン・スパイス・スープ、肉料理アジア風。百十米ドル。
ラウンジでデザート。十七米ドル。
その後、二人と別れて、一人、カフェで、コーヒーを飲む。四米ドル。
そして宿泊先に戻る前に、付近のグローサリーショップで水とチョコレート(ミント味)購入。七米ドル。
私は、富豪JSRから資金提供を受けていたものを、いくつかの銀行に分散して預金し出し入れ出来るようにしていた。そして部分的にSONYのようなグ ローバル企業の株に変換していた。今回の取材旅行用には、海外を大きく移動する時に比較的利便性が高いCITI系機関に現金引き出し用のアカウントを作っ ておいた。
二〇〇九年一月十三日
午前中、宿のそばのインターネットカフェに行き、必要なグローバル通信を済ませた。インターネットの時代がスタートして十数年、グローバル通信網のおかげで、仕事がやりやすくなっていると感じる。
宿は、イスラミック音楽がいつもホールで鳴っている。
午後、私は、これまでの疲れも出たのか、夕食までベッドで寝ていた。イスラミックのサウンドが、心を落ち着けてくれた。
エジプト・カイロの日射しは、強い。
のどが乾いて起きた私は、腹が少しへっている事に気付いた。昨日はかなり肉料理を食べたので、この夕食は、粗食にすることにした。宿の自室を出ると、長 い廊下があったが、ここの壁は、黄色でペイントされていた。ホールで流れるイスラミック音楽が、この黄色い廊下を吹き抜けてくるのは、気持ちがよかった。 エジプトでは、かなり安い値段で宿を取ることが出来た。しかし宿の設備の点では、こうした安宿は、問題もあった。窓を開けようとすると、窓がスライドから 外れたりした・・・。
私は、付近のグローサリーで、インスタント・ヌードルを買い込んで来た。袋には、フランス語が記載されていた。おそらく、フランス製のヌードルだ。
たしか、こうしたインスタント・ヌードルは、日本の安藤百福さんがオリジナルだと思う。いまや、世界中にインスタント・ヌードルがある。チキン味のフランス製のヌードルを、宿のキッチンでフィックスして食べた。
それから、すこし外を歩きたくなり、表へ出た。やや砂まじりの風が吹いていた。
私は、少し賑やかな通りにある『バビロニアン』というミドルイースト・クイジンに入った。風に吹かれると、お腹が空くのだ。私のルーツがユーロ圏だとしても、私はミドルイーストのスパイスにも、なかなか惚れ込んでいた。
チキンのシャワーマと、タプーリを食べた。コークと合う。
店内には中世のバグダッドの大きな絵が飾られていた。
二〇〇九年一月十四日
昨夜から、オフロードトラックに乗って、カイロから海岸地域に移動した。エジプトに来てから受けている短期のセッションのフィールドトリップで、スクー バを体験することになったからだ。地球の様々な生命を見ることで、生命の素晴らしさを知ることが目的だ。我々が普段、ほとんど目にすることのない水面下の 世界にも、神は生命を溢れさせている!
海に浮かぶボートの上での食事は最高だ。(たまに船酔いしてしまうと、きついが。)
エジプトでは、主食につく野菜サラダとして、タプーリ(トマト、パセリ、タマネギ、ニンニクの微塵切りをあえて、オリーブオイルとスパイスをかけるサラダ)をよく食べるが、これが乾燥した気候の中で食欲を増進するのに良い。
ボートから見ると、イルカが時折、水上に見える。その向こうに、黄色い大地が時々見える。
水は限り無く蒼い。
カモメの泣き声も聴こえた。
空は快晴。深い青だ。
これが、エジプトの海なのだ。
旧約聖書のモーゼの時代からの歴史がある海だが、海は多くのものを飲み込んで、そして水が全てを包んでしまった・・・。
ボートから対岸を見ていると、アジア系の女優が、何かロケーション撮影をしているようだった。私の見たところ、それは日本人女優だった。多くの日本人 が、ここエジプトに魅了されてやってくるのだ。多くのフランス人もエジプトに魅了されている。地理的にもフランスはエジプトに遠くない。フランス人は、か つてジュール・ヴェルヌがそうであったように、世界旅行が好きだ。さらに、そこにミステリアスなものがあれば、なおのこと。エジプトは、ピラミッド、ス フィンクス、古代神殿、・・・というふうに、フランス人の冒険心をかき立てるのに、十分な魅力を持っていたわけだ。
二〇〇九年一月十五日
朝、目がさめると、9時AMごろだった。
テーブルの上に置いていた、ショートブレッドとオレンジジュースで、イングリッシュ・スタイルのブレックファストをいただいた。イングランドは歴史的 に、いくつかのアジアのスタイルを、その文化に取り入れているが、シンガポール風の食事も、その一つだ。シンガポールスタイルのヌードルを少しフィックス してみた。
私は、キッチンにいるのが好きな方である。
昼、白身魚のフライ。
それから、ダイブをしたあと、ある収集家の家で三十七人の天使図を見る。これは、未公表の考古学レリックだ。
そして、この日、二度目のダイブをした。
同じボートに、何人かの日本人とフランス人が乗っていた。私たちは、写真を撮りあって楽しんだ。
ダイブの後は、用具を片付けて、塩水を落とすために真水のシャワーを浴びた。のどが渇いていたので、かなりエヴィアンを飲んだ。エジプトの陽は、まだ明るかった。
沿岸部の町に出た。コーヒーショップでチャイラテ(三米ドル)を飲んだ。ここは、エジプトに旅行に来るフランス人のためのカフェのようだった。フランス 人は、何処に行っても、カフェオレとクロワッサンを必要とする。私はアジアでの経験からチャイのような味に癒しを感じることも多いのだ。チャイを入れてく れた女性は、オルガナというフランス系カナダ人だった。私のように世界旅行をしてくると、多くの出会いがあり、また別れがある。それらの人々と再会するこ ともある。
オルガナは、私に「あの人は、おもしろい人よ」と、ちらと目で合図して教えてくれた。その人は、白髪の洒落た老齢の紳士で、窓の横のテーブルについてい た。窓からの光が、その人に荘厳な雰囲気を与えていたが、彼の表情はウィットを感じさせるものがあり、私は彼に話しかけることが出来た。
紳士は、ムッシュー・H・ウウズと云った。ムッシューは、フランス語の「ミスター」だが、彼は、自分のことをムッシューと呼ばれるのを気に入っているのだそうだ。
私は、そのように呼んだ。
「ムッシュー、はじめまして。あなたがおもしろい人だと聞きました」
「おお、若いの。わしは、ナイルの治水技術者だよ。お若いの、あんたは、旅かい?」
「そうです。信じてもらえるか分かりませんが、私は地球外の生命、宇宙の生命の神秘について、研究しながら旅を続けてきました」
「そうかい。ま、信じたって損はないし、信じるよ。私も、エジプシャンストーリーテラーだったこともある。この世界には、たくさんの、おもしろい話があるさ。うちに来なさい。あいにく、今日は車がいかれてしまって、バスだがね」
ムッシューと私はパブリックバスに乗り、ムッシューのお宅へ向かった。
私は、ムッシューのお宅で、しばらくお孫さんたちとクリケットに興じ、そして、ムッシューに、これまでの経験の中から、特にコンフィデンシャルでない話 を披露した。ムッシューは喜び、彼のコックに、スシ、ハーブチキン、スキャロップ、サラダ、ワイン、ティラミスなどを作らせ、私に御馳走してくれた。感謝 である。
ムッシューは言った、「君を見ていると、若い頃に読んだフランスの冒険小説を思い出すよ。ええと、なんだったかな、有名なやつさ、LE TOUR DU MONDE EN QUATRE-VINGTS JOURS (八十日間世界一周)だ」
私は、答えた。
「あ、それ、私も読みました。主人公、フィリアスが旅に出るとき、おとものパスパルトゥーに告げる言葉が忘れられません」
「なんだったかな」とムッシュー。
「トランクはいらない。手さげバッグひとつあればOKだ。その中に、ウール製のワイシャツを二つ、靴下を三ペアだ。君にも同じものを。あとは、旅の途中で 買おう。私のレインコート、ヒザ掛け毛布を出してくれ。靴はいいやつをね!しかし歩くことはほとんどないだろうが。さあ出発準備だ!」私は、そこを暗記し ていたのだ。
「最高の出発だ!わははは!」ムッシューは大笑いした。
「一八七〇年代に、こんな名台詞を書いたヴェルヌに乾杯です」
我々は、おもしろい話、とくにロング・ジャーニーの話がお互い大好きだと分かった。
「今日の世界旅行を愛する者たちは全て、ヴェルヌの子供じゃなあ!」ムッシューは、にこにこして言った。
ムッシューは、ちょっと席を離れると、ノートを抱えて戻ってきた。
「君に、面白い記録を見せてあげようか。これは、アメリカの古本屋で発見したノートだよ。十八夜物語と題されている。古本屋で見つけたが、とても新しいノートだ。ここにも、宇宙人の軌跡があるようだよ」
はじめのページに、『カリフォルニア州ノースビーチのカフェグレコにて、あるストーリテラーから十八夜に分けて語られた物語を記録したものである』と書かれていた。
『信じるか信じないかは君次第さ』とも。
「信じるか信じないかは君次第さ・・・か」
私はフフッと笑ってしまった。
{十八夜物語}
一日目 ジャパニーズ・ローカル・ミュージシャン・タカギ
タカギは、十九歳の青年だった。
彼は、この二千年代に、よくありがちな、音楽を志す男性。
彼の志すターゲットもまた、何万という音楽青年がフィーバーするロックワールドだった。
タカギは、大学の学園祭ではじめてロックの舞台に立った。
熱い声援!
スポットライト!
エクスタシーにのけぞるWOMEN!
タカギは、ロック・ミュージックの舞台で、あつい、こみあげる何かを感じはじめた。
二千年代は、またストリートロックの時代でもあった。
JAPANのストリートというストリートには、夜な夜な自称MUSICIANが出没!
そこから、メジャーレーベルへと昇華するものもいた!
タカギもまた、学園祭では飽き足らず、ストリートに出た。
デモテープをJAPANメジャーレーベルに何度も送付したが、その反応は今ひとつだった。
タカギは気がついた。
彼のMUSICには、源流がない、と。
ロックは、日本では表層的な文化だ。その源流の魂が欠けている。
二日目 アメリカン・トリッパー・タカギ
タカギは、エンターテインメント音楽の魂の源流をたどると決意するやいなや、ユナイテッドエアラインに乗り込んでいた。
ニューオリンズ。
ここは、古来、エンターテインメント音楽の聖地だ。
タカギはニューオリンズに、おりたっていた。
彼を、その衝動に走らせたエンターテインメントの息吹はニューオリンズの空港にさえ、すでに漂っていた。
ニューオリンズは、フランス人が入植し開発した街だ。
フレンチコロニアルと、ブラックミュージックが独特のアトモスフィアを作り出していた。
ブラックたちは、日常の生活、ささいな自然の変化、時の過ぎ行くさま、人生への感謝、神への賛美、恋人との時間、そんな全てを音楽にした。
一日のはじめ、太陽がただ昇るというだけでも、彼らはそこにエンターテインメントを見出すのだ。
モノにあふれたソサエティからやってきたタカギは、ニューオリンズの人々から、人間の生の本質にある「源流」が音楽と連動したときに生まれるフリーダムを感じた。
三日目 タカギ・ザ・ジャパニーズ・ミーツ・ザ・レジェンド
タカギは、ニューオリンズの風通しの良いフレンチコロニアル街を歩いた。
百年前からある緑と白のペンキで塗装された木造の簡素な建物に挟まれたSTREETは、アメリカの移民の歴史を感じさせる。
ふと見ると、日本人が経営しているのか、すし屋も見える・・。
タカギは、フレンチコロニアルを歩いているうちに、アメリカ音楽の源流の一つであるニューオリンズJAZZを聴かせる店(スモールホール)を見つけた。
タカギの時代はロックの一派として六十年代ビートルズや七十~八十年代VIRGINレコーズから出てきたブリティッシュ・ロックの動きが、JAPANでも盛んだったので、アメリカの音楽の源流は、一種忘れ去られた感があった。
音楽の歴史家はよくアメリカン・ロックは「風が吹き抜けるようなサウンド」だと言う。
アメリカ=風。
広大な土地を自由に吹く風、それがアメリカの音楽の伝説を作ってきた。
四日目 ブルースマスターX
タカギは、アメリカの魂、アメリカン・ブルースを自分のものにしようと、町の音楽ホールに通い、ニューオリンズのストリートで、ブルースを奏でてみた。
聴衆は、きびしく、「アメリカの魂がまだわかっちゃいないね」と去ってゆく次第。
タカギのフォーク・ギターはパワフルな音色に到達せずにいた。
タカギは、小澤征爾の音楽修行の本を読みながら、世界を求めた音楽家の魂を自分のものにしようとあがいていた。
タカギがニューオリンズの暑さのなかで、フォーク・ギターを地面に置いたまま、安いアイスクリームを舐めていると、ギターの前に「影」が止まった。ふと見上げると、そこに、不思議な東洋人が居た。
「ブルースの魂を理解したいようだね」東洋人は言った。
「アメリカ南部のブルースは、アフロ・アメリカンの歴史と共にある、それを簡単に君のようなJAPANESEが理解することはできない。すごく難しい。また、音楽は理解ではない、FEELだ」
東洋人は、地図を差し出した。
そして去っていった。
地図が示していたのは、ルイジアナの外れ、荒野の中のログハウスだった。
地図の端に「このログハウスに、八時だ」と書いてあった。
東洋人は何者なのか、彼は敵なのか、味方なのか?
去ってゆく東洋人の姿が段々小さくなる。
タカギはASKした、「ヘイ、ユー、オリエンタル・ガイ! あなたを何と呼べば?」
東洋人は答えた、
「ブルースマスターX」
五日目 ログハウス・イン・ザ・グレートフィールド
そこは、風が吹き荒れる荒野だ。
アメリカの荒野には、アメリカの魂がある。
どこまでも続いている荒野。
濃い青の空。
つぎつぎに形を変えてゆく雲。
永遠と無常の土地。
人間の存在を軽く超えてしまう大地。
それがアメリカ。
ログハウスは、そんな荒野の真っ只中にあった!
ログハウスを見つけたタカギは、TOYOTAのランドクルーザーの助手席を出た。
ランドクルーザーを運転しているのは、ネイティブアメリカンの男性だった。
「ミスター。ミスター・タカギ。この土地には、古代からのネイティブアメリカンの荒ぶる魂が吹き荒れている! アイ・フィール・イット! 気をつけて!」
ランドクルーザーの男は「じゃあ、一ヶ月後に、この場所、この時間にミスターを迎えに来るよ」そう言うと、そそくさとエンジンをかけて去っていった。
タカギのショルダーをポンと、誰かの手がたたいた。
振り返ると、さきほどまで何の気配も感じられなかったのに、黒肌の東洋人がそこにいた。
「私は、甲田忠一朗です。ニッポン人です」彼はそう言った。「マスターはアナタをまっておられます」
六日目 ブルース・レッスン
甲田忠一朗は、タカギをログハウスの中へ案内した。
ブルースマスターXは、木彫りネイティブアメリカン人形を彫りながら、甲田忠一朗が開けた扉の方をジロリと見た。
「きたかね」
ブルースマスターXは、脇に置いていたギターをつかむと、ほい、とタカギに投げた。
タカギは、とっさにそれをキャッチした。
「なにか、弾いてみな」ブルースマスターXは言った。
「では、アメリカの大地と、永遠の時間、そして、アフロの魂を一つにした新曲をいきます」そうタカギは言うと、タカギ流のブルースを奏ではじめた。
ブルースマスターXは、それを聞き終えると、「いい線いっとるな」と言った。
「しかし、君は、日本という、システムが完備された社会に毒されている部分がある。それが、君の曲の中に見えるのだ。それは、アメリカのフリーダムの魂、 NATUREの魂にうまくなじまない。君は、今から一週間、この荒野で、キャンプをするべきだな。それでは、少なすぎるかもしれんが、すばやくアメリカ大 地の魂を理解するには、荒野の夜を越えねばいかんのだよ」
ブルースマスターXはニヤリと笑い顔を浮かべた。
「私も実は、東洋の男、アメリカの魂を学んだのは、十五の時だ」
七日目 ジャパニーズソウル・フォー・ブルース
アメリカは、一見単純に見えるが、実は複雑だ。
タカギは、それを肌で感じていた。
そう、この国には、世界のあらゆる文化が集合しているのだ。
そしてアメリカの大地は、それら全てを受け入れてきた。
だからこそ、この土地は自由の土地なのだ。
ものを言う市民の国。
それがアメリカだ。
タカギは、日本に居た頃に読んだ本を思い出した。
文明開化の時代、多くの日本人たちがアメリカに学んだ。
多くの文筆家たちが、開かれた日本を模索し、この土地を旅した。
その旅は、こんにち、この国を訪れるジャパニーズソウルに繋がっている。
八日目 ソング・フォー・グレートフィールド&インサイド・ザ・ロック
アメリカン・グレートフィールド・・・・。
タカギは、アメリカの、果ての見えぬグレートフィールドを讃える歌を演奏し始めた。荒野の犬たちが、その音楽を聴いて、遠吠えをはじめた。風に舞い、賛歌はフィールドを被った。
甲田(忠一朗)氏は、そのウタに涙し、タカギの元にやってきた。
「すばらしいです、すばらしいです、あなたは、私には不可能な業をすることができる!」
甲田氏は、謎の男だ。
彼がなぜここに居るのか、タカギは疑問に思っていた。
甲田氏は語りはじめた、「私のひいおじいさんは、文明開化の頃のJAPANより、このアメリカに来たりし小説家だったのです! その名は、甲田久作。ミスター・タカギ、あなたも、その名はご存知でしょう?」
甲田久作、そうだ、あの甲田久作だ。
一八九九年、日本の神戸より出航し、アメリカの西海岸、シアトル港に到着した、あの作家だ。
甲田久作・・・、彼は、しかし謎の人物だ。
タカギは、高校時代の「文学」のクラスで、そう教えられた。
甲田久作の著作は、いくつか日本で出版されベストセラーとなった。たとえば、『うえすたん物語』などは誰もが知っている。彼は文明開化時期に、西洋的個人 主義を書いた男でもあった。しかし、当時の多くの日本国民は彼が肌で感じたものを理解しようはずもなかった。彼はいくつかの名作を文明開化時期の日本に残 し、自らは国を出た。伝説によれば、彼は自らの財産でアメリカに土地を買い、アメリカの地で、その後の生涯を過ごした。彼のいくつかの著作は知っていて も、ほとんどの日本人は、彼のアメリカ生活をトレースしなかった。この甲田忠一朗氏が、まさか、あの甲田久作の子孫だなんて! タカギは、ここで、伝説と 交差することになったのだ!
甲田氏はタカギの音楽に心打たれていた。
タカギのうたは、言葉にならない人間のサガを音にしていたのだ。言葉が全てではない。
ソウルは、言葉にならないものがある!
しかし、人は言葉にしたがる存在だ。
言葉を紡げば、それはたしかに洗練されるだろう。そうだ、洗練された言葉があるはずだ!
しかし、タカギは限界も感じていた。
「ひいおじいさんの遺した彼の全てのライティングを、いま、あなたに見せよう」甲田氏は、そうタカギに告げた。
甲田氏は、「きなさい」と言った。
彼は、タカギをグレートフィールドの中にある湖に連れて行った。
「ひいおじいさんは、じつはアメリカに莫大な財産を残しました。私どもは、その一部を使って、超近代化されたストレージを、この湖の地下に建造しました。 じつは、この建造物に使われた技術は地球のものではありません。世界の多くの人々が、伝説的に知っているように、アメリカ政府は、極秘的に、地球外の民と の接点を持っています。アメリカ人の中の、または、アメリカ永住者の中の、一部、それもごく少数の者たちだけが、彼らとアクセス可能なパスを持っていま す。基本的には、もはや世界中で伝説的にささやかれている、エリア・フィフティーワンが、そのアクセス本拠地なのです。我々は、その地球外技術を導入し て、この地下ストレージを設計・建造したわけですよ。・・・そして、そこに、ひいおじいさんの未発表のライティングが保存されています」甲田氏はそういう と、空に手をかざした。
「これは、手相認証システムです、そして、ボイスサウンド認証システムを作動させます。オープンセサミ!」
湖の中央から、巨大な岩がしぶきを上げて出てきた。そして、その岩の中央に穴が開いた。これは、まさしく、地球外のテクノロジーだ。
「さあ、あそこへ、入ります!」
そう甲田氏は言うが、タカギは唖然としている。
「どうやって、湖を渡ってゆくんだい?」
甲田氏は答えた。
「水の上を歩けます。この岸から、あの穴まで、エレクトロマグネティック・フィールドによって、橋が出来てます、目には見えませんが・・・」
甲田氏は、さっさと、見えない橋に乗り、水の上を歩き始めた。
「さあ、ミスター・タカギ、カモン! インサイド・ザ・ロックへ!」
岩の奥に二人が入ると、そこは、チタン蒸着でコーティングされた超現代型のストレージになっていた。
「ここのコンストラクションとハイテク・コンピューティングには、トーキョーの技術も導入してます」
甲田は、そう言うとホログラム・スクリーンを作動させて、彼の曾祖父の立体映像を映し出した。
甲田曾祖父のホログラム・フィギュアは、リアルだった。
甲田忠一朗は「このホログラムは、曾祖父のDNAによって作成された彼の分身なのです」とタカギに言った。
ホログラムの曾祖父は、タカギを見ると、おどろきの表情を浮かべた。
「この男、この男は百年に一人の男。世界のスーパースターになる素質の男! フェスティバル・エンターテイナー! 私は待っていたのだ、私は・・・!」
甲田忠一朗はタカギを見つめた、「やはり、キミか」
そこへ、ブルースマスターXが入ってきた。
「ふふふ、やはりキミだったのか。実は、一年前、星を読むインド人と出会った」
九日目 フレンチ・コロニアル・エリア・ワン・イヤー・アゴー
一年前のニューオリンズ・・・。
ニューオリンズは、特殊な町だ。アメリカ合衆国の建国の魂がいまだに感じられる開拓地の雰囲気を持ち続けている。
馬が引く馬車が行き交い、馬の蹄鉄が石畳を踏みつける音がこだまする。
そしてフレンチコロニアルの建物とストリートとプラザに雑踏が集まる。そこでは、ブラックたちがジャズを演奏している。ストリート・パフォーマーといっても、世界でも一流のミュージシャンのレヴェルを持つ。
フランス系移民とネイティブが混血を繰り返してきたので、女性はフレンチ風のオールドスタイル・ワンピースとフレンチスタイル・パラソルをかざして、通りをおしゃまに歩いている。本場ヨーロッパのそれとも違うが、サザンステート・パリジェンヌたちは、陽気で楽しい。
そんなフレンチ・プラザをブルースマスターXは歩いていた・・・。
プラザは、多くの人々でごったがえしていた。
ヨーロッパからの観光客、アジアからの商人、・・・様々の肌の色。
プラザの入り口に、「スターリーダー」と看板を掲げたインド人風の男がいた。
目がぱっちりしていて、麻色の肌、濃い色の髪と眉、そして濃い口ひげを蓄え、白いターバンを頭に巻いていた。
ブルースマスターXを見ると、そのインド人風の男は口を開いた。
「そこの東洋人、あなたは、さがしている。そうだ、あなたはさがしている。ブルースの星を」
「わかるのか」とブルースマスターX。
「一年後、ここへ、この場所へ、ここ、この同じ場所へまた来なさい。私はインドから来たスターリーダー、星を読む男。ここで出会いが起こることを星が示している。ここで星同士が出会うのだ」スターリーダーは答えた。
その日は、暑い日だった。ブルースマスターは、額の汗を拭いて、ギラギラに照りつける太陽を一瞬見た。
そして、インド人のスターリーダーの方へ目を下ろすと、もう、そこには誰もいなかった。
「夢、白昼夢・・・?」
十日目 ポーカーシップ・オン・ミシシッピ
荒野を流れる巨大な川・・・。
ミシシッピ。
そこにゆったりと浮かぶ、客船・・・。
客船の甲板には、三人のフエルト帽を被った男たちがいた。
そうだ、その男たちとは、ブルースマスターX、甲田忠一朗、タカギ。
三人の東洋人。
十一日目 ソウルフル・デイズ・アンド・ドリーム
マスターXは、甲板から更けてゆく夜を見ていた。
マスターXは口を開いた。
「なあ、甲田君、タカギ君、我々三人は、ひょんなことから、極東の同じ島国に生まれ、今ここにこうして三人でいる。この船はポーカーシップ。ここで、ポー カーでな、私の資本を数十倍にする。私は、生まれつきのギャンブラーでもある。ここで作った資金を使って、アミューズメント界へのりこむのだよ。アミュー ズメントとは・・・、アミューズメントとは、人々を楽しませるビジネスなのだ。私は、ショウマンだった。私も、観客を取り込み、人々に時間を忘れさせるよ うなショウを見せていたときもあった。今はすこし歳をとりすぎたよ・・」
甲田は悲しい顔を見せた。そして言った。
「マスターX、そんな悲しいことをおっしゃって・・」
マスターXは甲田に答えた、「いや、悲しいストーリーではない。私は、じょじょに、現代に響く言葉を失いつつある。それが分かる。時代はかわる。今のヤン グたちには、ヤングの言葉がある。その時代は、その時代の者によってつくられてゆく。わかるかね、甲田くん。そして、・・・タカギ君、君はいいモノをもっ ているよ。君にここで増やした資本の一部を渡そう。それで、アミューズメントの世界の扉をひらいてくれ。私は君を見守っているよ。それに、・・・タカギ 君、きみは、甲田くんの曾祖父の遺産であった奇跡のライティングも手に入れた。君の人生は、試練もあるだろうが、きっと輝く」
タカギは涙した。
「ありごとうございます、マスターX。しかし、まだまだ、あなたの力には及びません。あなたは、わたしに、多くの音楽の技をみせてくださった。その見せて くれた業に驚き、私は、吹き飛ばされそうなパワーさえ感じました。あらぶる風をも、あなたの音楽は、簡単に鎮めた。数日前の荒野のレッスンのとき・・・、 あなたは大風を鎮めた。あの、我々の前に突然吹いてきた大風、わたしは、その挑戦にすくみました。アメリカ南部のあらぶる大風は魂を持っています。あなた は、それを、すばらしい音と言葉でしずめたではないですか。ネイティブ・アメリカンの勇敢な男でも恐れる、あの、荒野のあらぶる風・・・。わたしなど、ち びりそうになりました。なんの言葉もおもいつかず、ただ、たたずみました。その大風の挑戦を、あなたは受けて立ち、音楽によって、その心と魂を鎮めまし た!」
マスターXは、すこし空を見ると、タカギに言った、「タカギ君、君は、まだ場数を踏んでいないから、そう思うのだよ。君は十分な才能、タレントを秘めてい るよ。たしか、君はJAPANのストリートで、魂の言葉を学んだ、そう言っていたね。それは、間違いではなかったのだよ。君は百年に一人の男だ。君はア ミューズメント・キングだよ。君の血がそうさせるのだ。君はできる」
タカギは困惑した。
「しかし、マスターX、私は、JAPANのストリートですこし学び、そして、このブルースの大地に来てそれほどもたちません。私はもっと、あなたに教えをいただかねばならないのでは?」
マスターXは答えた、「タカギ君。いや、君は無意識に多くのことを学んだはずだ。あとは、選択するのだ。君自身の本来の姿になるために、君は君の得たもの から選択せねばならないのだ。私は、一瞬のきっかけでしかなかった。君は、このポーカーシップに乗る前の一週間、荒野でキャンプしながら、その修行のなか で、学んでしまっている。君はそれほどの男だよ。私には分かる。だから、私は安心して去る。私は実は、ここで、資本を増やしたら、多少の社会奉仕をしたあ と、南ヨーロッパに移り住むのだ。そこで、すこしばかり引退的アミューズメントビジネスをやる。甲田君も、いままで、よく私のために仕事してくれた。あり がとう」
そんな三人を見る一人の女性がいた・・・。
十二日目 ザ・ウーマン
ポーカーシップは、ゆるやかに大河を進んでいた。
タカギはまだ甲板に居た。
タカギのそばに女性が歩いてきた。
茶色のショーカットで、印象的な目をしていた。
「私はサンセット。あなたに一目ぼれ!」
女性はそういうと、タカギに寄り添った。
タカギも彼女をかわいいとおもった。
彼女は、ポーカーシップのショウダンサーだった。
甲田は自分の船室で、天井を見ながら、すこし涙を浮かべていた。
バンドマンたちの音楽が響いていたかと思うと、とつぜん止み、大きなベルが鳴った。
「優勝者が決まりました!」
そういうアナウンスが流れた。
タカギがポーカーシップのセンターにあるポーカー会場にやってきた。
マスターXが、一億ドルの小切手を三つもらっているところだった。
マスターXは、その一つをタカギに渡した、「君のものだ」
タカギはすこし困った顔をした。
マスターXは言った、「うけとりなさい。私は君の才能、そのタレントに、これだけ出すのだ。遠い南ヨーロッパで、いつも君を見ている。私をたのしませてくれ。これは、その準備金だ」
十三日目 ワン・オブ・ア・ハンドレッド・イヤー
タカギは深く礼をし、一億ドルの小切手を受けた。
そばには、サンセットがいた。
「もう、ガールフレンドができたのか、それもいいことぢゃ」マスターXは楽しく笑った。
「タカギ君、君は、つよく歩いてゆける。君は、私が音楽と言葉で、ネイティブ・アメリカンの荒野に吹くあらぶる風を鎮めたのを見ただけで、多くを学んだ。 それにもっと深いオリジナリティをみつけることが出来れば、もっと素晴らしい創造が君のマインドにおとずれる。私は、私のサウンド、私のライティングで、 あらぶるSOULをしずめたが、君は、君自身の技を、おおくのヒントから見つけ、創造すればいい。それがとてもいい。君は、私が得たサウンドの言霊、そし てライティングからヒントを得ることもできる。アメリカ南部の旅から授かった魂の言葉のライティング、甲田曾祖父のライティングからも得られるのだ。それ に君の時代の息吹を重ねてゆけ。君は百年に一人の男。君が選択し、君の道をゆけ」
十四日目 ソウルフルブック
タカギは、自らに言った。
「・・・魂の言葉のライティング、そうだ、あのときの!」
タカギのマインドは、あの日、甲田の先祖の忘れがたみであった、あの魂の言葉が綴られたライティング本「ソウルフルブック」を得たときの光景を思い出していた。
それは、湖の中央に突然そそりたった電子岩盤の中・・・。
地球外から数世紀未来のハイテクをすでに得ていた一族の、曾祖父のSPIRITとの出会い・・。
さらにそのSPIRITを遺すことに成功した現在の甲田氏・・・。
甲田は、ハイテクにハイテクを重ね、つねに前進していたのだった・・・。
そのハイテクが、甲田曾祖父とタカギを結びつけた。
ホログラムとなった曾祖父のSPIRITは、タカギを見ると、おどろきの表情を浮かべた。そして、言葉を発した、「この男、この男は百年に一人の男。世界のスーパースターになる素質の男! フェスティバル・エンターテイナー! 私は待っていたのだ、私は・・・!」
SPIRITは究極の光を放った! タカギは光に包まれ、視界は真っ白になった。目を凝らすと、その光の中に、あらゆる「魂の言葉」が浮かび上がった。魂 の言葉、それは生命の言葉、いのちを生き生きとさせる光の言葉。音楽が聴こえはじめ、ソウルフルワードがつぎつぎに姿を現し、音となって、タカギをつらぬ いた。
タカギは、気づくと、晴天のホライゾンにいた。
そばには甲田氏が立っていた。「ソウルフルブックは君を選んだ」
魂の言葉が記されたソウルフルブックは、タカギの頭上でくるくる回っていた。
「とりなさい」甲田は言った。
タカギはパッと、ソウルフルブックをつかんだ。
中を開くと、さっき見た命のワードが無数にならんでいた。
「君のものだ」甲田は言った、「本が君を選んだのだから」
その本をつかまえることができた人間は君だけだ、そう、君だけなんだよ、タカギ君、・・・甲田はそういうと、晴天のホライゾンで空を見た。
雲がきらきら流れていた。
タカギがマインド・トリップから覚め、ハッと気づくと、ポーカーシップの甲板ではダンスパーティが始まっていた。
マスターXは言った、「ミスター・タカギ、君は、ソウルフルブックが選んだワンハンドレッド・イヤーズに一人のマンなんだよ・・。甲田曾祖父のスピリット、そして現代の甲田氏、また私、・・・この三人がそれをはっきり見た」
甲田はそれに続けて言った、「もうすぐ別れだ。君とあえてうれしかった。ありがとう。でも、いつも、おぼえている。ここで、我々ができることは終えた。君の道へとおおいなる力とともにあゆんでくれ」
十五日目 ネオホライゾン
晴天のホライゾンにタカギとサンセットがソウルフルブックを持って立っている。
とおくから砂煙をあげて、ランドクルーザーが見えてきた。
タカギたちは、クルーザーに乗り込むと、言った。
「一番近い空港にいってくれるかな」
十六日目 新生活ネオライフ
タカギとサンセットの新生活が始まった。
タカギとサンセットは、大いなる生命と愛を感じ、激しく愛し合った。
ある日、サンセットは、いなくなっていた。
タカギは、その数ヵ月後、再び戻ってきたサンセットを見た。
またすぐにサンセットは、いなくなっていた。
そして、さらに数ヵ月後、タカギのもとに戻ってきたサンセットは、小さな赤ちゃんを連れてきた。
おどろいたことに、その子は、タカギの子だということだった。
タカギは、受け入れ、しばらく三人で暮らした。
タカギには、このことで、何か気持ちの変化が芽生えていた。
それはワンダフルなことだという気がした。
ある日、サンセットはまた、いなくなった。
タカギは、残された子と、楽器を奏で楽しんだ。
タカギの子はまだ難しいことは当然わからないが、楽器から出る音を楽しんでいるようだった。
十七日目 アメリカ、北米、ジョイ
時がしばしたった。
愛がもどってきた。
そうだ、サンセットだ。
サンセットがドアをあけて、アパートメントにもどってきた。
サンセットは、しばし、まどろみ、ねむった。
あふれる愛をタカギはおもいだしていた。
タカギの子は、音楽とともに育った。
サンセットは、トランペットのテクニックをもっていた。
タカギのギター、サンセットのトランペット、そしてタカギの子ロームシーの歌。
三つがあいまって、新しいサウンド、神への賛美がうまれた。
バンドは、やがてアメリカで知られるようになり、ついに、NEW YORKのホールでのコンサートが決まった。
バンドはメジャーな存在となった。
サンフランシスコでのショウも成功した。
タカギは過去のことをおもいだしていた。
過去のあやまちに対する神の赦しを乞うた。
自らのエゴの重さからとき放たれ、サウンドはいっそうの力をおびた。
サンフランシスコでの公演が成功した後だったが、ロームシーが熱を出してしまった。
ロームシーは、ドクターとナースの熱心な治療でまた元気になった。
タカギは、ドクター、ナースたちの仕事をほんとうにすばらしいとおもった。
あるとき、タカギは聖書のページを何気なく開けた。
旧約聖書・続編、シラ書、三十八。
医者をその仕事のゆえに敬え。
主は、大地から薬をつくられた。
医者は、薬によって人をいやし、痛みをとりのぞく。
医者もまた、主に祈りもとめているのだ。
タカギは、おおくのことでまよっていた・・。
しかし、神への感謝の気持ちをもった。
この気持ちが、これまでの難局を乗り越える力になってきたのだ。
十八日目 伝承へ
「THE SHOW IN NEW YORK」は人気のショウとなった。
タカギたちのバンドは、ザ・サンセット・アンド・コーと呼ばれていた。
NEW YORKの、MUSICホールでのショウはいつも成功した。
JAPANから、タカギの両親もショウを見にきた。
二人とも、アメリカでついに成功したタカギを見てよろこんだ。
(ノート・了)
信じるも信じないも、私マック・デビッドは、タカギのものがたりに希望を与えられた。人生に立ち向かう勇気を感じた。
それから夜になり、私は海岸の宿舎までの、帰路の途中、インターネットカフェで、JSRのヘッドクオーターズに報告をした。
二〇〇九年一月十六日
その日は、師と個人的に話をする時間を持つ日だった。
師は、コプト・カルチャーの中で、マインドレッスンをしていらっしゃった。
人生の神秘は、地上での生活の最後の一瞬まで、少しずつ見てゆける、と彼は教えてくれた。私は、まだまだ若すぎて、今見えない事もいっぱいある、と。
師は、私に言った、「あなたは、芸術家だ。それは、他を幻惑の世界に連れ込む、という大きな力を持っている。しかし、その力は、あなたに預けられたもので あって、あなたのものではない。あなたが、それで慢心を持って振舞うなら、その特殊な力は、あなたを去るだろう。しかし、それが人々に夢を与え、あなたが、その働きの中で慢心を捨てるなら、そして、世界を繋げる役割の一部を果たそうとする意志があるなら、あなたは、その与えられた力によって、地上での時 間が満たされる。その仕事が終われば、天上への時さ」
二〇〇九年一月十七日
師は、私に卵料理を作ってくれた。
師は言った、「われわれ人間は、矛盾の固まりさ。しかし、それで、われわれは、うまく出来ているのだ。うまく造られているのだ。われわれが全て計算でうまくいくように出来ていたら、われわれは、慢心を捨てる事ができないだろう。慢心を捨てることが、命について分かっていく道なのだと思うな。」
二〇〇九年一月十八日
師や友たちとの食事会だった。
二〇〇九年一月十九日
帰路へ。
広大な世界旅行の間にいくつかの取り決めがなされ、富豪JSRは、彼自身のオフィスをサンフランシスコに移動させていた。
エジプト・カイロ国際空港→ギリシア・アテネ国際空港→パリ・ドゴール空港→マイアミ国際空港→サンフランシスコ国際空港、・・・かなりの距離を空路移動し、サンフランシスコに私は着いた。
旅の移動時間は、自分と向き合える時間にもなる。私はときどき、聖書を思い出すことがある。そんなときに、LOVE=LIFE=GODであると感じた。LOVEが大切。
かつて創造主はモーゼを通して人間に十のルールを与えた。それはたしか・・・、
●創造主の存在への信仰を持て。
●偶像を崇拝するな。
●神の名を空しく使用してはいけない。
●週1の休みと礼拝を持て。
●父母への敬意を持て。
●殺人はいけない。
●うその証言はいけない。
●不倫はいけない。
●盗みはいけない。
●人の妻、家を欲してはいけない。
・・・だった。
これに加えて、イエス・キリストは言った。
●神を愛しなさい。
●隣人を愛しなさい。
こういうことを今一度思い出すと、これらのルールはいいものだと思った。
こうした言葉を聞くことで、大冒険の最中でも守られる。
結局、私は宇宙人の軌跡を捜し求めながら、人生の旅路を深めていたのだ。
JSRに会ったら、それが報告の最後につける言葉だろう。 (おわり)
* おおくの方の、本を書くための心の応援を感謝します。