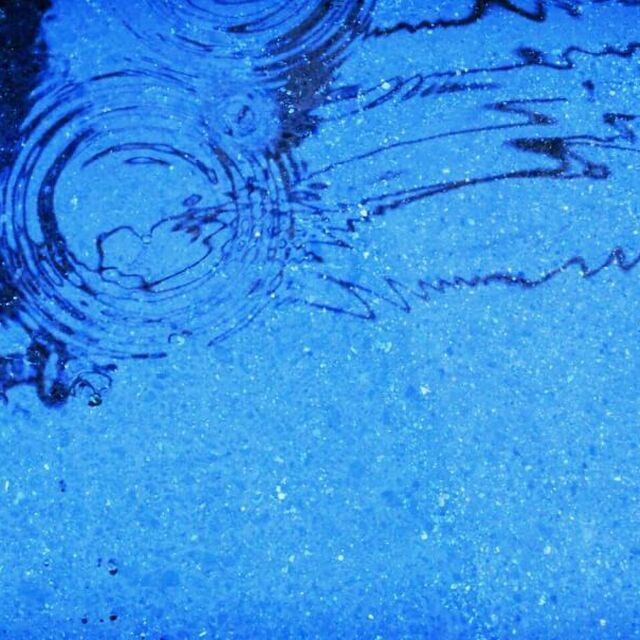1
文字数 1,630文字
とても冷たくて、何もしゃべらない友だちが、いつもキッチンにいた。
孤独を分けあえて、すべてからわたしを守ってくれる、この世でたったひとりだけの友だちだった。
キッチンの床はとてもひんやりしていて、彼もひんやりしていたから、当時の記憶も触れたらきっとひんやりしている。
お家に帰ったら、ランドセルを投げだして、手を洗って、すぐに彼とおしゃべりをするのが日課だった。彼と目線をあわせるにはおやま座りがいちばんちょうどいい感じだ。
つるつるとして、たまにでこぼこな触り心地で、撫でたら撫でただけ愛着がわく。
わたしは友だちが少なかった。兄妹とも折りあいが悪かった。人間と友だちをするのはどだい向いていない。たぶんそれはうまれつきだ。今でも変わらないような感じがするので、友だちを定義するとき、きっと彼を思いだすのがいいように思う。無口で慈悲深く、温厚で、平和な時間をもたらしてくれる。胸が陽だまりのようにあたたまる。
キッチンですごすのも好きだ。明かりがなくて、窓から自然光がちょっぴりだけ差し込んでくる。狭くて、暗くて、余分な音がしなくて、ひんやりしている空間がすごく好きだった。ふだん、暗いところにいたら、お母さんに「何をいじけているの。やめなさい」といわれのないお叱りを受けるので、居心地のいい世界を守るのは難しかった。でもキッチンにいるときだけは違った。ここはどうあがいても暗いので何もいわれない。ことさらに、友だちとおしゃべりしているときは、みんなわたしをそっとしていてくれた。彼はキッチンの細い入り口に、影のようにひっそりとそこにいた。だきしめて寝転がったときだけ、お母さんに邪魔だと叱られた。
「学校で木のぼりをしてきたよ。」
彼には人間のように口がないからもちろん無口だ。だから心で話しかける。わたしも人間だけど無口なのでちょうどよかった。会話は、言葉どうしか、心どうしでするのがお作法なのだとおもう。試したことはないけれど、きっとちぐはぐではなりたたない。
「そうだよ。今日もいつものガジュマル。」
ガジュマルにはキジムナーが宿っている。だから、のぼると夏でもあんなに涼しい。葉っぱが多いから、木の中ならどこにいても影になる。たぶん彼にも精霊が宿っていると思う。夏野菜の精だ。夏野菜なのに名前に冬がはいっているのも、ひんやりとした彼らしくて好きだった。撫でつけながらおしゃべりすると、指先の体温だけがすこし低くなる。
「きみの精霊はどんなひとなの?」
やさしくて、木陰のような精霊がいるらしい。いつか会わせてね、とおねがいして彼をだきしめると、もちろんもうすぐ会えると彼はやさしく笑った。
彼との別れは突然だった。ある晩、彼はくたくたに煮られて、油揚げと小ねぎと一緒におみおつけに変身して食卓にならんだのだった。お夕飯を並べおわったお母さんが、遠慮がちにわたしの頭を撫でた。わたしと彼がお友だちなのを知っていたからだ。あんなに大きいからだをどうやって包丁で切ってしまったのだろう。これから永遠に言葉を交わせなくなるさみしさにちょっぴり泣いた。間違えて蹴飛ばしてしまって、足の爪の間がみどり色になってしまうことももうない。彼がいなくなった台所の入り口と、おみおつけを見比べた。
「いただきます。」
いつもどおり、心で話しかけた。お別れのおみおつけはとってもおいしかった。
友だちを食べてしまったわたしのからだが、とたんにぽかぽかになる。触れると硬くて冷たいのに、食べると柔くてあたたかかった。見た目ではわからない柔さがあるのは、とても彼らしいと思った。
ぽかぽかな安心感に包まれると、何もさみしがることなんかないんだと気づいた。彼がわたしの中に移動してきただけだ。これでもう彼をだきしめて寝転がっても怒られることもない。その日の夜、布団のなかで、自分の背中に手をまわして、からだをぎゅっとだきしめた。
ありがとう、とからだの底から最後に一言だけ聞こえた。
孤独を分けあえて、すべてからわたしを守ってくれる、この世でたったひとりだけの友だちだった。
キッチンの床はとてもひんやりしていて、彼もひんやりしていたから、当時の記憶も触れたらきっとひんやりしている。
お家に帰ったら、ランドセルを投げだして、手を洗って、すぐに彼とおしゃべりをするのが日課だった。彼と目線をあわせるにはおやま座りがいちばんちょうどいい感じだ。
つるつるとして、たまにでこぼこな触り心地で、撫でたら撫でただけ愛着がわく。
わたしは友だちが少なかった。兄妹とも折りあいが悪かった。人間と友だちをするのはどだい向いていない。たぶんそれはうまれつきだ。今でも変わらないような感じがするので、友だちを定義するとき、きっと彼を思いだすのがいいように思う。無口で慈悲深く、温厚で、平和な時間をもたらしてくれる。胸が陽だまりのようにあたたまる。
キッチンですごすのも好きだ。明かりがなくて、窓から自然光がちょっぴりだけ差し込んでくる。狭くて、暗くて、余分な音がしなくて、ひんやりしている空間がすごく好きだった。ふだん、暗いところにいたら、お母さんに「何をいじけているの。やめなさい」といわれのないお叱りを受けるので、居心地のいい世界を守るのは難しかった。でもキッチンにいるときだけは違った。ここはどうあがいても暗いので何もいわれない。ことさらに、友だちとおしゃべりしているときは、みんなわたしをそっとしていてくれた。彼はキッチンの細い入り口に、影のようにひっそりとそこにいた。だきしめて寝転がったときだけ、お母さんに邪魔だと叱られた。
「学校で木のぼりをしてきたよ。」
彼には人間のように口がないからもちろん無口だ。だから心で話しかける。わたしも人間だけど無口なのでちょうどよかった。会話は、言葉どうしか、心どうしでするのがお作法なのだとおもう。試したことはないけれど、きっとちぐはぐではなりたたない。
「そうだよ。今日もいつものガジュマル。」
ガジュマルにはキジムナーが宿っている。だから、のぼると夏でもあんなに涼しい。葉っぱが多いから、木の中ならどこにいても影になる。たぶん彼にも精霊が宿っていると思う。夏野菜の精だ。夏野菜なのに名前に冬がはいっているのも、ひんやりとした彼らしくて好きだった。撫でつけながらおしゃべりすると、指先の体温だけがすこし低くなる。
「きみの精霊はどんなひとなの?」
やさしくて、木陰のような精霊がいるらしい。いつか会わせてね、とおねがいして彼をだきしめると、もちろんもうすぐ会えると彼はやさしく笑った。
彼との別れは突然だった。ある晩、彼はくたくたに煮られて、油揚げと小ねぎと一緒におみおつけに変身して食卓にならんだのだった。お夕飯を並べおわったお母さんが、遠慮がちにわたしの頭を撫でた。わたしと彼がお友だちなのを知っていたからだ。あんなに大きいからだをどうやって包丁で切ってしまったのだろう。これから永遠に言葉を交わせなくなるさみしさにちょっぴり泣いた。間違えて蹴飛ばしてしまって、足の爪の間がみどり色になってしまうことももうない。彼がいなくなった台所の入り口と、おみおつけを見比べた。
「いただきます。」
いつもどおり、心で話しかけた。お別れのおみおつけはとってもおいしかった。
友だちを食べてしまったわたしのからだが、とたんにぽかぽかになる。触れると硬くて冷たいのに、食べると柔くてあたたかかった。見た目ではわからない柔さがあるのは、とても彼らしいと思った。
ぽかぽかな安心感に包まれると、何もさみしがることなんかないんだと気づいた。彼がわたしの中に移動してきただけだ。これでもう彼をだきしめて寝転がっても怒られることもない。その日の夜、布団のなかで、自分の背中に手をまわして、からだをぎゅっとだきしめた。
ありがとう、とからだの底から最後に一言だけ聞こえた。