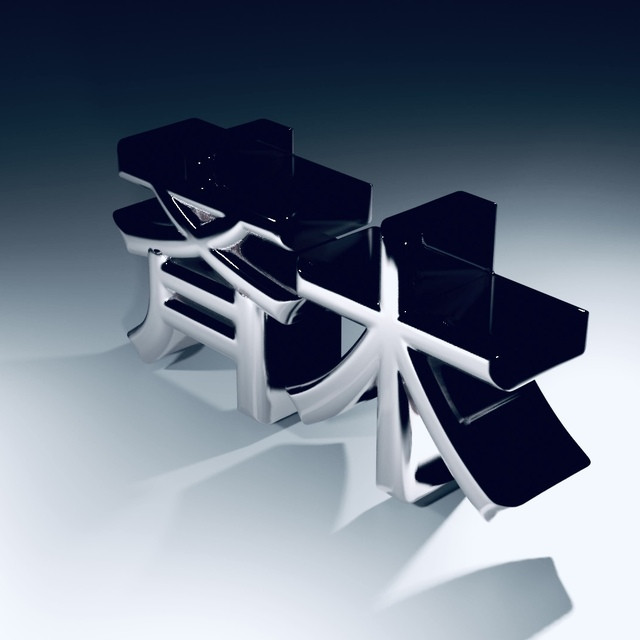野辺送りの禁忌
文字数 1,015文字
六十代の男性、小野崎さんがかつて父親から聞いた話。
父親の寛さんがまだ十代の頃で戦後すぐの事だという。
ある暑い夏、かつて住んでいた集落で若い女が亡くなった。
その集落では葬式の際に行われる、少し変わった風習があった。
死者と同世代の人間に限り、親族によって木の椀を両耳に当てられる。
椀で耳を塞ぐと親族の者はこう唱える。
「聞く耳持たぬ」
それではじめて葬列に参加出来るのだという。
一種のおまじない、俗信の類のようだが、これによって死者に道連れにされる事を防ぐ意味があるらしい。
椀は葬式が終わると川に流す。
寛さんも例に漏れず、喪服を着た親族に椀で耳を塞がれた。
続いて彼の兄の番となったが、なぜか兄は頑なに拒否した。
「今時世迷言を言うなよ」
そう言い捨てると、ひとが咎めるのも聞かず憮然として葬式に参加したという。
古めかしい仕来りが気恥ずかしかったのだろうか。
埋葬が済んで家に帰った夜中、ぐっすりと眠っていた寛さんはふと目を覚ました。
見ると横で寝ていた兄が上半身だけを起こして、蚊帳の外をぼうっと見つめている。
消灯されているので幽かな月明かりだけが屋内に差していた。
兄の見ている方に目を凝らしても何も無い。
寛さんは何度か兄の名を呼んだが気付かないので、肩を揺らしてみるとやっとこちらを振り返った。
「呼んでる声がする、ほら…」
兄は家の外を指している。
しかし、寛さんがいくら耳を済ませても蛙の啼き声以外聞こえない。
気のせいだろうと諭すと兄は虚なまま横になった。寝ぼけたのだろうと思い、寛さんは再び寝入った。
その翌朝に騒ぎが起きた。
兄が夜明け前に家から姿を消したのだ。
なんと見つかったのは墓所だった。
住職が女の墓を掘り起こそう(当時は土葬)としている兄を見つけた。
爪が剥がれるほど土を掻き分けていたらしい。
その後兄は介抱されたが床に伏せり、あっけなく衰弱死した。
兄が死んだ女に連れて行かれたとか噂が流れたが、寛さんは懐疑的だった。
どうも兄は生前の女と密かに深い関係にあったようで、そのために精神を患ったのではないかと思ったという。
ただ、寛さんは就職のために集落を出た後も葬儀に呼ばれた時は斎場に入る前に自分で両耳を塞いで小声で唱えたという。
「聞く耳持たぬ」
仕来りを信じるわけではないが、何となくやってしまう。
寛さんもすでに鬼籍に入ったが、息子の小野崎さんも密かに同じ事をしているという。
父親の寛さんがまだ十代の頃で戦後すぐの事だという。
ある暑い夏、かつて住んでいた集落で若い女が亡くなった。
その集落では葬式の際に行われる、少し変わった風習があった。
死者と同世代の人間に限り、親族によって木の椀を両耳に当てられる。
椀で耳を塞ぐと親族の者はこう唱える。
「聞く耳持たぬ」
それではじめて葬列に参加出来るのだという。
一種のおまじない、俗信の類のようだが、これによって死者に道連れにされる事を防ぐ意味があるらしい。
椀は葬式が終わると川に流す。
寛さんも例に漏れず、喪服を着た親族に椀で耳を塞がれた。
続いて彼の兄の番となったが、なぜか兄は頑なに拒否した。
「今時世迷言を言うなよ」
そう言い捨てると、ひとが咎めるのも聞かず憮然として葬式に参加したという。
古めかしい仕来りが気恥ずかしかったのだろうか。
埋葬が済んで家に帰った夜中、ぐっすりと眠っていた寛さんはふと目を覚ました。
見ると横で寝ていた兄が上半身だけを起こして、蚊帳の外をぼうっと見つめている。
消灯されているので幽かな月明かりだけが屋内に差していた。
兄の見ている方に目を凝らしても何も無い。
寛さんは何度か兄の名を呼んだが気付かないので、肩を揺らしてみるとやっとこちらを振り返った。
「呼んでる声がする、ほら…」
兄は家の外を指している。
しかし、寛さんがいくら耳を済ませても蛙の啼き声以外聞こえない。
気のせいだろうと諭すと兄は虚なまま横になった。寝ぼけたのだろうと思い、寛さんは再び寝入った。
その翌朝に騒ぎが起きた。
兄が夜明け前に家から姿を消したのだ。
なんと見つかったのは墓所だった。
住職が女の墓を掘り起こそう(当時は土葬)としている兄を見つけた。
爪が剥がれるほど土を掻き分けていたらしい。
その後兄は介抱されたが床に伏せり、あっけなく衰弱死した。
兄が死んだ女に連れて行かれたとか噂が流れたが、寛さんは懐疑的だった。
どうも兄は生前の女と密かに深い関係にあったようで、そのために精神を患ったのではないかと思ったという。
ただ、寛さんは就職のために集落を出た後も葬儀に呼ばれた時は斎場に入る前に自分で両耳を塞いで小声で唱えたという。
「聞く耳持たぬ」
仕来りを信じるわけではないが、何となくやってしまう。
寛さんもすでに鬼籍に入ったが、息子の小野崎さんも密かに同じ事をしているという。