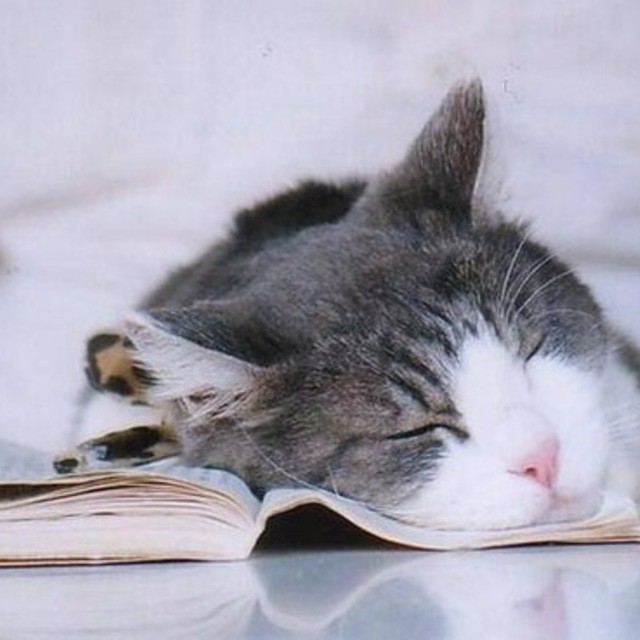僕は、髪が15cmの子としか付き合わない。
文字数 10,468文字
中学3年生の冬、卒業を間近に控えた2月14日。美希は真を呼び出した。
「僕は、髪が15センチの子としか付き合わない。ごめん。」
同じクラスだったけれど、口数も少なく馴染もうとしていなかった真と、バスケ部のキャプテンで明るく友達も多い美希とはあまり接点はなかった。休み時間も窓際の自分の席に座って外を見ているか、寝ているかのどちらかで友達もほとんどいない。なんとかきっかけをつかもうと、グループ学習で話をしたり、同じ委員会に入ってみたり、美希なりに距離を縮めようとていたが反応はいつも上の空といった感じだ。
「高橋くん、ほんと綺麗な顔してるよね。」
「そうかな。」
「ほんとほんと!モデルとかなれるんじゃない?」
「ならないよ。」
2人で委員会の当番活動をしている時、そんな話をした。
話題を広げる気のまるでないキャッチボールはすぐに終わってしまったけれど、ぼんやりと頬杖をついて何を見るでもなく、ただ見上げているその横顔に、美希は息を飲む。儚げでふっとどこかへ消えてしまいそうな透き通った空気をまとい、それでいて内に秘めた一切の妥協を許さない強い意志を感じさせる、美しい横顔。見る度にはっとして、ずっと見ていたいと思った。
きっと今日は何人もの女子が彼にチョコを渡し、想いを伝えようとあの手この手で呼び出し、告白したことだろう。もう後1ヶ月もすれば卒業してしまうのだから。
「他に好きな人がいる」
せめてそんな言葉が欲しかった。断るのが面倒くさくなってしまったのだとしても。美希は自分の髪型を初めて悔やんだ。小学校の頃から打ち込んできたバスケットボール。絶えずボールを追い、相手選手に食らいついてコートの中を縦横無尽に駆け回るのに、長い髪は邪魔だった。男子に間違われるほどのベリーショートで、試合に集中するには申し分なく、男勝りな彼女はむしろ気に入っていた。高校でもバスケは続ける気でいたし、中学の部活を引退してからは卒業式を意識して、少しは伸ばしていたけれど、十分に短髪の範囲だった。
他の子にはなんと言って断ったの?
もしかして秘密にしている彼女がいるの?
髪が短くて、何がいけないの?
美希の中で悲しさと悔しさと、そのどちらでもない何かがない交ぜになって、一気に爆発した。試合でもこんな気持ちになったことはなかった。負けた時、悔しくて涙が止まらないことは何度もあった。それでもその時やれることはやったんだと受け入れて、チームにもキャプテンとして、次を見据えていこうと鼓舞し切り替えていった。
美希が精一杯の気持ちを打ち明けた後、真はしばらくの間黙っていた。そして例の返事をし、少し申し訳なさそうに「じゃあ、ごめん。」と早々に、ふっと消えてしまった。
美希にとって、これが初めての恋らしい恋だった。女子は男子よりおませと言うが、彼女は小さい頃から兄や近所のやんちゃ坊主と走り回っていて、おままごとよりチャンバラごっこの方が好きだった。幼稚園で女の子の友達が増えると、少し可愛いものにも興味を示すようになるが、相変わらず虫や蛙を平気で捕まえて、男子はいわば良きライバルとして競い合う存在。こんなに心が揺さぶられる異性に出会ったことはなかった。
中学に入って初めて真を見た時、綺麗な顔だなとは思ったが日々新しいことを学び、部活の先輩や同級生と過ごす時間が楽しくて特に気になる存在ではなかった。しかし2年生のある日、調べ物で図書室へ行くと、真が先客として閲覧席に座っていた。椅子に浅く座り、背もたれに体を預け、腹のあたりに持った本を俯くように読んでいた。華奢だったけれど制服を上手く着崩したその姿は、整った顔立ちを引き立て、とても様になっていた。美希が思わず感心していると、窓から入った風が彼の前髪を揺らし、少し隠れていた目が露わになった。そして美希に気付くとそのまま目だけ彼女の方へ向けてきた。長いまつげが一際目を引く、切れ長の見事な流し目。
「なに?」
美希はその時、射ぬかれてしまった。
「え、いや、別に・・・」
とっさに言葉が出ずにしどろもどろになっていると、真が興味なさげにまたその視線を本へと戻した。一瞬の出来事だったけれどそのあまりに自然な仕草と、風が吹けば飛んでいってしまうような繊細さに美希は釘付けになり、捕まえてみたくなった。
彼のことを噂する女子は多く、そんな相手を自分もまた好きだということをどうしても周囲に打ち明けられなかった。さばさばした性格で姉御肌、体育会系の美希があの謎多き一匹狼を好きだとは誰も思わない。
「高橋くん、いっつも1人でいるけどモテるよね~。」
「顔は綺麗だよね。」
「でも暗そうだし、美希はああいう人タイプじゃないでしょ?」
「え、あたし?そ、そうだねー。あたしはもっとスポーツマンタイプの人がいいかな!」
「やっぱそうだよね~。」
人気者の美希が、友達もいない、なよっとした高橋を好きなはずはない。それが周りの思う正しさで、それを否定してまで自分の本心を打ち明ける勇気もなく、さらに「顔だけ」で好きになったその他大勢の女子と同じと思われたくなかったという見栄が邪魔をしていた。初めての気持ちでどうすればいいのか分からない。信頼する友達にこの気持ちを聞いて欲しい。それなのに素直に相談できないことへもどかしさと、自分のくだらない見栄のために彼を否定する自分が嫌で嫌でたまらなかった。好きなのに、その気持ちを小さな嘘で覆ってしまう。
なんで好きになっちゃったんだろう。
家に帰ると、緊張の糸がプツンと切れた。
「おかえりー。」
「ご飯いらないっ。」
「具合でも悪いの?」
「うんっ。」
美希の母はカレンダーを見て、それ以上何も言わず、台所へ戻っていった。
階段を一気に駆け上がり部屋に飛び込んだ。鞄を放り出し、制服がシワになるのも気にせずベッドに潜り込む。そして声を殺して、1人で泣いた。
初めて好きになった人に、あんな断られ方をして、いったいどう心の整理をすればいいのか美希にはさっぱり見当がつかなかった。真のことを知ろうと努力もしたし、自分のことも極力知ってもらおうと少ない機会の中で話していたという自負が美希にはあった。それなのに、という気持ちがどうしても拭えない。
「あたし、高橋くんの、外見だけじゃない・・芯の、強そうなとことか、好き、なのに・・・あたしは、好きとか、嫌いとかって、次元にすら、立てなかったの・・・?」
枕に向かって誰にも言えない想いを吐き出し、息が苦しくなるほど泣いた。
それから1ヶ月、卒業式を迎え美希と真は別々の高校へ進学した。バレンタインデーの一件で真との会話は一切なくなり、それまでも特段親しいわけではなかった2人はお互いの進学先を知らない。あの後も委員会活動はあったが、真はいつもと変わらない様子で、しばらくはその態度にも心をかき乱された。とは言え、自分だけ変に余所余所しくするのもおかしいし、誰かと付き合い始めたという噂も美希の耳には入って来ず、それ以上傷を負うこともなかった。振った振られた、ただそれだけの、少し特別な同級生の関係のままそれぞれの道へ。
高校に入ってから時折彼のことを思い出すことがあった。バスケットの強豪校へ進学した美希は部活動に明け暮れる日々。その中で熾烈なレギュラー争いに破れ、試合に出られないこともあった。そんな時、真に言われた言葉が頭をよぎる。
「僕は、髪が15センチの子としか付き合わない。」
バスケのための短髪を否定されたあの言葉。初恋の相手に振られてもこうして貫いているこの髪型を、無駄にするものかと奮い立たせていた。
「美希、髪そのままなんだ!伸ばしたいとか思わない?」
「別に、楽だし。」
中学の同級生に言われても、頑なに誘惑に耐えた。強くなりたい。上手くなりたい。上手くなって・・・。
それでも3年間、スタメンで出場した試合よりもベンチからのスタートだった試合の方が多かった。いつもレギュラーで輝いている先輩、実力を付けていく同級生達。バスケは大好きだった。続けたいと思っていた。しかし、選手生活は高校で最後にしようと決めた。美希は初めてバスケ以外の自分の将来を考えた。
そして、地元大学の教育学部へ進学しようと決めた。学校の先生になって子ども達にバスケを教えたい。こまめに切っていた髪のことも忘れて受験勉強に励んだ。いつの間にか、真のこともあまり思い出さなくなって、美希は希望する大学に合格した。
大学のバスケサークルに入り、そこで気になる人が出来た。口べたで、優しい2つ上の先輩。目が細くて、くしゃっと笑う顔にやられた。同期と恋バナをして、みんなで盛り上がった。
「京助さん、今日もカッコ良かった~。あの脹ら脛がたまんない。」
「ちーちゃん、ほんと京助さん好きだよね。」
「だってカッコ良いじゃん。そういう美希は?誰?」
「あたしは、蒼太さんかなぁ。」
「分かる~!」
友達と話す中で、憧れの先輩のことを思い出すだけで心が高揚して、ドキドキしてしまう。美希は片思いがこんなにも幸せなのだと初めて実感した。
大学の生活にも慣れた2年生の夏休み、母に連れられて近所の写真屋へ行った。成人式の振り袖を選ぶためだ。七五三も頼んだ写真屋で、明るく人懐っこいおばさんが切り盛りしている。
「あら、美希ちゃんいらっしゃい!すっかりお姉さんになったわねぇ。」
「そうなの、大学へ行ってちょっと色気付いちゃって。」
「お母さん!それに、おばさんだって卒業式の時もお願いしたじゃん!」
来る度にいつも同じ会話。まるで親戚のようで、美希はこの写真屋が好きだった。
「ねぇ、おばさん。あたし何色が似合うかな?」
「若い娘さんには何で似合うよ。」
そうは言われても今まであまり洋服に気を回していなかった美希は、大学に入って初めて私服で学校へ行くことにさへ四苦八苦している有様だった。
母やおばさんに見てもらいながら、鮮やかな緑色の振り袖にし、当日のセットもお願いすることにした。
「そうだ、美希ちゃん髪の毛どうする?面倒ならつけたりもできるよ?」
中高でのベリーショートは卒業し、今は結べるくらいまで髪を伸ばしていた。そこ
で、ふと、真のことが頭をよぎった。
あの人は、成人式でるのかな。
「せっかくだから、自分の髪でやりたいな。おばさん、この長さでもできる?」
「任せなさい!美人さんにしてあげるから。」
「あんなに小さかった美希が、成人式だなんて。」
「子どもってほんとあっと言う間に大きくなるわよね~。」
高橋くんは、髪の長いあたしを見て、どう思うんだろう。
そのことが気になって母親たちの話はまるで耳に入らなかった。
式の当日、おばさんは他の女の子たちの準備にも大忙しで、美希は眠い目をこすりながら朝早くに着付けと髪のセットをしてもらった。アップにした髪をおばさんが手際よくカールさせ、綺麗な花の髪飾りを最後に髪に差す。鏡には振り袖のカタログに出てくるような華やかな女性が写っていた。おばさんは美希を見て、満足げに頷いた。
しかし式が始まるのはお昼頃。それまで振り袖を汚さないよう家族から壊れ物のように扱われ、気崩れないようソファでじっとしていた。のどが渇いたと言えば飲み物や軽食が運ばれてくる状態で、髪も綺麗に結ってもらいまるで撮影中の女優の気分だった。
そしていよいよ車で会場へ向かう。東京へ出た友人も多く、再会が待ちきれなかった。しかし真との再会を考えると緊張で鼓動が早くなる。
会場に到着すると、花が咲き乱れたような色とりどりの袖を揺らす懐かしい顔がすでに再会を済ませていた。
「美希?えっ、もしかして美希?!」
「もしかしなくても、バスケ部の元キャプテンだよ!」
「馬子にも衣装とはよく言ったもんだ~。」
「ちょっと!」
一度顔を合わせれば、一瞬で中学時代にタイムスリップしてしまったかのように、あの頃のままの笑い声が響く。人が到着する度にどこかで歓声があがり、しばらく止むことはなかった。
一段落して、会場の中へ入ろうと移動し始めた時、美希はそっと真の姿を探した。
「美希、行かないの?」
「あ、ごめん、行く行く。」
きっともうホールの中にいて、退屈そうに座っているに違いない。美希はそう思って友人たちと中へ急いだ。
「疲れたー。」
1時間ほどの式の後、立食の懇談会で文化祭の写真や映像で盛り上がり、振り袖から洋服に着替えて居酒屋で同窓会をという怒濤の1日だった。しかしそのどこにも、真の姿はなかった。冷静に考えれば至極当然の結果だった。中学時代いつも1人でいた彼が、卒業後の進路を誰も知らない彼が、わざわざ来るはずがない。こんな簡単なことに気付かないなんて。美希が真を探していたのは、綺麗になったと言わせてやりたい、その思いだけだったのかもしれない。
「髪、切ろっかなぁ。」
美希の髪は、襟足から20センチ程度まで伸びていた。もともとベリーショートだった彼女にとってはもはや鬱陶しい長さだった。ポニーテールにしてみたり、ヘアアクセを使ってみたり、それだけでも印象がずいぶん変わる。ただ、あまりレパートリーもなければ器用でもなく、そもそも慣れていない美希は、そのまま髪を降ろしていることの方が多かった。しかしそれもバッグを肩に掛ける時はさまったり、あわてて屈んだ時に視界が遮られたりと、邪魔に感じることが増えてきた。異性の目と向き合うか、自分の感覚を優先するか、美希はまたしても髪に悩まされていた。
成人式から1週間ほど過ぎた日。大学の午後の授業が休講になったので、あまり行ったことのない、彼女にとっては少し冒険と言っていいお洒落な街を散策してみることにした。電車で30分ほどのところにあるその街は、実際行ってみると雰囲気のある古着屋からスタイリッシュな美容院まで様々な顔を持っていた。
「そういえば、蒼太さんここで一人暮らししてるって・・・かっこいい~。」
そんなことを思いながら、大通りをブラブラしていると、後ろから声をかけられた。
「すみません、今お時間ありますか?」
振り返ると、同じ年頃か少し年上にも見える青年がいた。所謂キャッチのような押しの強さもなく、服装はいたってカジュアルで、線は細いが服に着られることなく、自分に似合うものを知っていて上手に着こなしている、それが一目で分かる人だった。表情には自信と、揺るがない何かが現れていた。その整った顔に美希は一瞬身構えた。そして記憶の中に1人の少年を見つける。この目、知ってる。あたしを射抜いたあの目だ。
「・・・高橋くん?」
「え?」
「あの、人違いだったらすみません、同級生に、その、とても似ていて・・・。」
その言葉に、青年も少し考え込むような様子を見せた。
「前髪を少し、あげてもらっていいですか?」
美希は言われた通り前髪を持ち上げて、青年の反応を待った。彼は少し体を引いて、美希に向かって手のひらをかざす。人差し指から親指の線を彼女の顔の輪郭に沿わせているような、緩やかな曲線を作り、記憶の糸を手繰り寄せるように、またしばらくじっと見つめていた。そして腕を降ろすと、彼の表情がほんの少し緩んだように見えた。
「前髪、降ろして大丈夫だよ、夏川さん。」
「ほんとに、高橋くんなの?!」
「髪、伸ばしたんだね。やっぱり、その方が良い。」
「やっぱり・・・?」
美希は困惑した。成人式でも、本当に誰も卒業後真のことを知る人間がおらず、海外にでも行ってしまったのだと思っていたその人が電車で30分のところにいたのだ。さらに、中学生の頃とは言え理不尽な言葉で振った相手に穏やかな表情で「その方が良い」とまで。あの頃の気持ちがふつふつと沸き上がる。
「その方が良いって、あの時、本当に、髪の毛だけであたしのこと、振ったの?」
「そんなことないよ。ただ、15センチくらい伸ばした方が可愛いのにって思ったのは本当。」
真はたいしたことではないように、むしろ満足げに言った。美希はますます腹が立った。あの言葉が自分の心にどれだけ深く刺さり、何かあるごとに顔を出してはチクチクと締め付けていたか、まるで気にかけていない真の言い種に感情が高ぶる。
「だからって、告白してきた相手にそれだけ言って断るって、失礼だと思わなかったの?あたし、あの時、ほんとに・・!」
泣いたとか落ち込んだと、ここで言ってしまうと負けのような気がして、真に詰め寄ったまま言葉が出なくなった。
「え、あ、あの、ごめん。あの時は本当になんて言っていいか、分からなくて。その、夏川さんを傷つけてたなら、本当にごめん。」
美希の剣幕に面食らったのか、心底困った顔をして申し訳なさそうに深々と頭を下げた。その姿を見て、今度は美希は面食らった。中学の頃も悪い人間とは感じていなかったが、振られた直後は憎いとさえ思った。しかし当の真は美希の髪を否定しようとなど、当時微塵も考えていなかったのだ。それに比べて、自分の意地の悪さが、唐突にバカらしくなる。
「いや、あたしこそ勝手に蒸し返してごめん。でも、この際だから教えてよ。なんで振ったの?」
「うーん・・・。」
「別にもう怒らないから、嫌いだったならそう言ってくれて構わないから。」
「いや、むしろ逆。」
「あー、逆ねぇ・・・えっ、逆?!」
美希の声に横を通った女性が、何事かと2人を見た。
「あの頃、美容師の高専に行きたかったんだ。でも親に普通科の高校しか認めないって言われて、なんか何にも興味が持てなくて、今思い出しても恥ずかしいんだけど、一匹狼気取ってたんだよね。」
時折はにかむように笑いながら、饒舌に語る真を見て、不思議な感覚を覚えた。内に秘める芯の強さは、美容師という夢への情熱だったことは、美希の中で辻褄が合った。しかし、ぶっきらぼうで無気力な真しか知らない彼女にとって目の前にいる青年が、あの時の少年と結びつかない。かじかんだ指で紐を結んでいるような、もどかしさを感じた。
「僕の顔、なんか付いてる?髪、変?」
「ううん、違うの。なんていうか、高橋くんってこんなに喋る人だったんだなと思って。」
真は恥ずかしそうに、また話し始めた。
「中学校はほんと黒歴史だよ。普通科の高校に行って、今は良かったと思ってる。僕の目を覚まさせてくれて、視野を広げてくれた友達が出来たんだ。」
そこで一息置くと、思いがけない言葉が飛び出した。
「でも、それよりも前に僕を揺さぶってきたのが、夏川さんだったんだよ。」
美希には全く心当たりがなかった。むしろことごとく玉砕して、最後に粉砕されたとさえ思っている。
「拗ねて誰とも関わろうとしなかった僕に、あんなに話しかけてくれたのは夏川さんくらいだったから。君はいつも友達に囲まれてて、男女分け隔てなく誰にでも同じ態度でいた。自分の狭い世界に閉じこもっていた僕には眩しすぎたんだ。初めは・・・うるさい、くらいに思ってたけど、思いもしないことを聞いてきたり、いつも驚かされてた。・・・顔、赤いよ?」
真の爽やかで純粋な言葉の破壊力はすさまじかった。中学生の無垢な感情が冷凍保存されていたのではないかと疑いたくなるような、計算のない真っ直ぐな言葉。美希はただただ恥ずかしくて、爆発してしまいそうだった。
「そんなに好意的に見てくれてたのは、嬉しいんだけど、それなら尚更、なんで?」
「余裕がなかったんだと思う。誰が好きとか、付き合うとか、外に目を向ける勇気がなかった。でも、嘘はつきたくなくて・・・夏川さん、髪ちょっと伸ばした方が似合うだろうなって思ったから、あんなこと言って逃げちゃったんだ。」
美希は、心に居座っていた氷がゆっくりと溶けていくような、晴れやかな気持ちになった。自分の中でいつの間にか、あの言葉に鎧を纏わせてことあるごとに揺り起こしては一方的に戦っていただけだったのだ。自分を縛っていたのは、自分。そのことに気付いた。
「なぁーんだ、思ったより可愛い理由じゃん。」
「可愛いって・・・もう中学の話は終わり!」
今度は真が顔を赤くしていた。中学の頃とは比べ物にならないくらい喜怒哀楽をさらけ出す彼に、もう違和感はなかった。
「あっ、ところでカットモデルは?やってくれない?夏川さんの髪、何にもいじってなくて綺麗なまんまだから是非切らせて欲しい。」
美希はいたずらっぽく笑うと、言った。
「ちょうど美容院行こうと思ってたとこだし、いいよ。」
美容院に着くと真は水を得た魚のようだった。まだ見習いだけど、と少し照れながら美希を案内する彼だったが、腰にシザーケースを付けると一気に表情が引き締まる。真が準備で歩き回る度にきちんと手入れされたハサミや櫛が、小さく小気味良い音を奏で、美希を置いていった。真をチラチラ見たり、店の内装、置かれている雑誌や漫画、親しげに談笑する客と美容師にと、まるでおのぼりさんのように。
しばらくすると、いくつかの雑誌を手に先輩らしき美容師を伴って真がやってきた。
カットモデルは初めての経験だった美希は、慣れない場所ということもあり、かなり緊張していた。悟られまいと必死に平静を装っていたが、それを察してかベテラン美容師が説明を始めた。
「ご来店ありがとうございます。店長の宮内と申します。うちの高橋とはお知り合いとのことで、今回ご縁を頂いたと聞いています。現時点で高橋はまだ見習いですが、一通りのカットは出来ます。なのでカットモデルとは申しましてもお客様のご希望をお聞きした上でご要望通りのスタイルを作るという形になります。」
軽い気持ちで引き受けてしまったが、全くの他人の方が良かったのではないかと美希は少しだけ申し訳なくなった。
「あの、私あんまり詳しくないし大まかなイメージしか持ってなくて、上手く説明できるか・・・」
「そう言って頂けるだけで、こちらとしてもどこからお話すれば良いかが明確になりますので、ありがたいです。私もついておりますし、ご不明な点などございましたらどんな小さなことでもお申し付けください。高橋のためと思って。」
「よろしく、夏川さん!」
「よろしくお願いします、だろ?」
真と店長の信頼関係が伺えた。一匹狼は心許せる人に出会えたらしい。美希は驚きと、何故か自分のことのように、少し誇らしい気持ちになった。そんな思いで見つめられているとは露知らず、真は先ほどよりやや緊張した面もちで美希を見つめ返した。
「今日はどのように致しましょうか?」
「えーっと、ずっと短くしてたので今の長さでも結構鬱陶しくて、それで少し軽くしたいのと、でもせっかくだから結んだりはしたくて・・・あの、希望はそんな感じです。」
真は時折相槌を打って頷きながら、美希の髪に触れ、感触を確かめていた。その目は真剣そのもので、あらゆる可能性を描いているような鋭さを持っていた。そこから真は、長さや形など、雑誌やヘアカタログを見ながら丁寧に美希の求める髪型を絞り込んでいく。
「それでは、長さは15センチくらいまでカットして、アレンジしやすいように段はあまり付けずに軽くしていきますね。」
「はい、お願いします。」
「最初にシャンプーしちゃいますので、シャンプー台の方へどうぞ。」
同級生という関係が一時陰を潜めた。しかし、美容師として、来店してくれた美希が求め、かつ最も美しくなれるスタイルにしたいという思いが溢れた真の態度には、冷たさはまったく感じられない。自分の世界に籠もり他を寄せ付けなかった少年は、自分の世界を貫き、解放させ、外に目を向けるための一歩を踏み出している。まさにその瞬間に美希はいた。
「お疲れさまです、いかがですか?」
「おぉー。」
「後ろはこんな感じ。触ってみて、軽さも確かめてみてください。」
「すごーい。すっきりしたー。店長さん、どうです?」
宮内は施術中ほとんど見守っているだけで、口を出さなかった。
「まだすこし荒いところがあります。ただ、長さを変えずに整えられる範囲ですね。ちょっと失礼。」
そう言うと手際よくハサミを入れ始めた。真は、その隣で瞬きも惜しいと言わんばかりに宮内の手を見つめている。ほんの少しだけ、悔しさが顔に出ていた。
仕上げも終わり、せっかくだからと軽く巻いてもらった。真が荷物を取りに行っている間、宮内がしみじみと話し出した。
「あいつ腕はいいけど、まだ人と話すのに苦手意識が残ってるみたいで。美容師は技術だけじゃない。お客様との会話の中で人柄を知るのも同じくらい大事なんです。でも・・・」
「でも?」
「今日はなんだか、今までのカットモデルさんの時みたいな力みとか棘がなくて、何かを掴んだような晴れやかな顔してるんです。」
宮内と真に見送られ、店を出る。
ショーウインドウに映る自分の姿をみて、美希は思わず顔をほころばせた。
「僕は、髪が15センチの子としか付き合わない。」
あの言葉の意味を、今ならしっかりと受け止めることができる。不器用過ぎて、時間はかかってしまったけれど。
心に嘘をついて背伸びしたままに見る景色は、きっと自分が作り出した幻影で、大事なことは目の前にある。冬の透き通った風に髪を揺らしながら、美希は軽やかに歩きだした。