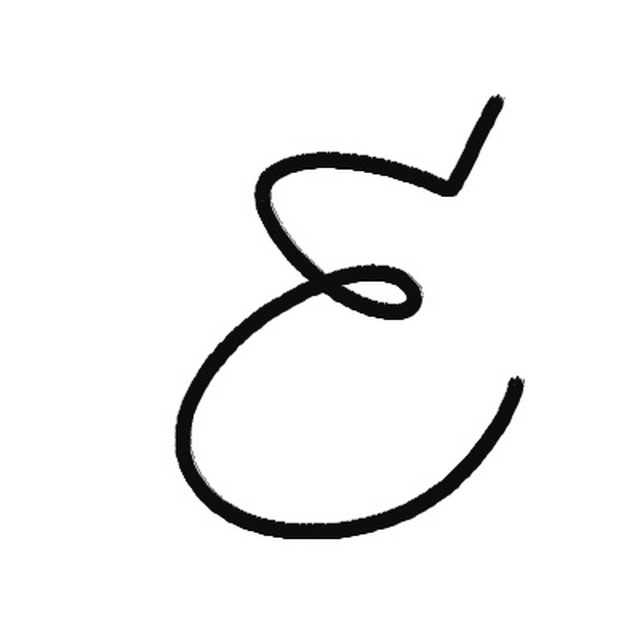第1話
文字数 8,535文字
「塔の上の少年」
永見妙
人里離れた森の奥深く、大きな湖のほとりに、それはそれは立派な塔が立っていました。大きな円柱の塔には入り口もなければ、出口もなく、なのに天辺は窓と煙突がある、石造りの家のような造形をしています。こんな辺鄙な場所も相まって、はたからみればヘンテコそのものなのは間違いないですが、こんな辺鄙な場所だからこそ、その立ち姿はどこか幻想的にも思われます。塔は誰が建てたのか、いつ建てられたのか、塔自身も知りませんが、塔にとってそんなことはどうでも良いのでした。冬から春への移り変わりを告げる温かい風や、その風の心地よさを歌う野鳥、空のように澄んだ湖の中を悠々自適に泳ぐ湖魚がそばにいてくれるだけで、塔は満足しているのです。
そしてそれらのなかでも、塔が最も大切にしているのが、塔の頂上に住む少年でした。少年は盲いた目をしており、自分の姿も、塔の身なりも、周辺の自然の顔色もわかりません。しかし、少年にとってもまた、そんなことはどうでも良いのでした。黄金色の木で作られた家具、その色に映えるように置かれた植物たち、そしてカンバスと水彩絵の具やクレヨンなどの道具を備えたアトリエ。少年にとっては、このアトリエと寝室、そしてそれらを繋ぐリビングルームが世界の全てです。そして、少年は一日中、絵を描いており、それができるだけで少年は満足しているのでした。
今日の少年はいつものように、アトリエ部屋の窓のそばに置いてある小さな丸椅子に座って、カンバスに絵を描いているのでした。窓といっても硝子も格子も付いておらず、見方によってはただ四角い穴が空いているだけとも捉えられます。塔はいつも、塔の天辺で一人寂しく暮らす少年の話し相手になってあげます。
「あのね、とうさん、僕は絵を描くのが大好きなんだ」
塔は頷きます。
「今描いているのはね、そこの窓から見える満点の星空だよ。僕はキラキラ星が大好きなんだ」
そう言うと、少年は筆を片手に握ったまま、カンバスを披露します。カンバスには杜若色の綺麗な星空と橙色の星が描かれており、稚拙ながらも力強く、そして人を惹きつける魅力をもっていました。
素敵な絵だね。
外が太陽の燦々と降り注ぐ晴天であることを確認すると、塔は返事をし、微笑ましそうに少年の話を聞いています。塔はこの時間がとても好きでした。塔にとっては、この時間が全てなのでした。そして塔はこんな生活がいつまでも続いて欲しいし、いつまでも続くと思っていました。
「あのね、とうさん、僕は目が見えないけれども、それでもいいんだ。むしろ、それで良かったと思ってる。もし僕が耳の聞こえない人だったら、きっと僕は音楽家になっているだろうし、もし読み書きができなかったら、きっと小説家になっているに違いないや。そうでしょう。とうさん」
塔は泣きたい思いでいっぱいでした。塔は少年の盲目を治せるような魔法を持ち合わせてはいません。塔が無力感に襲われていると、空は雨雲で埋まり、塔の足元のすみれには涙が降り注ぐのでした。
また次の日、少年がカンバスに向かいながら、また話しかけます。
「とうさんは優しいね。いつも黙って僕の話を聞いてくれるもの」
少年がそう言ってくれることが、塔にはとても嬉しいのです。
「僕、たまには、とうさんのお話が聞いてみたいな」
そこで、塔は今までの人間の歴史について話しました。人間がもともとは猿であったこと、道具を作って協力しながら一生懸命生きていたこと、人間が増え、文明が進むと人はどんどん協力しなくなり、果てには自分たちで殺し合うようにまで落ちぶれてしまったこと。塔は淡々と話しました。
「人間ってやっぱり変な生き物だよね。仲良しかと思ったら喧嘩したり、かと思えば喧嘩するほど仲が良いと言ったり。僕にはよくわかんないや」
わからないのは君だけではないよ、と塔は少年に笑みを投げかけます。
「あ、けれども、絵を生み出したことはすごいと思うな。こんなにも美しくて、儚くて、素晴らしくて、尊いものを作り出せるのは、それはもう奇跡としか言いようがないよね。神様だって人間が作りあげたものだし、だったら芸術は神様よりもすごいってことにもなるよね」
塔は話を遮らぬよう静かに聞いています。
「僕ね、初めて芸術をした人に会ってみたいんだ。どんなことを考えて、どんなことを表現したのか、自分の目で見てみたい。それで、僕も絵を描くんだ。その人からどんな感動だか刺激だかを受けるかわからないけど、それを形にしてみたいんだ」
いつか叶うといいね、と塔。
「昔、人生は芸術を模倣する、なんて言葉を残した人がいたけど、やっぱり僕の人生は僕の人生を芸術にするためにあるのだと思うんだ。それはきっと、僕史上、最高の作品になるんだろうなあ。それで死ねるっていうなら本望だよ」
突然、少年から一度も聞いたことのないような言葉が流れて、塔は動揺します。
「絵が描けなくなっても良いのだなんて、もちろんそうに決まってるじゃないか。人生の最大の目的は、それを通して最高傑作をつくることなんだよ。それが完成したら生きる意味なんてなくなってしまうし、僕はそうして死にたいとさえ思うんだ」
初めて聞いた少年の考えに塔は驚きを隠せません。しかし、少年の意思は断固たるもので、塔がいくら考えを改めるよう言っても、少年は聞く耳を持ちません。少年の話を聞けば聞くほど、塔は胸が締め付けられるような感覚になってきました。
この子がいなくなってしまったら、それから先はどうなるのだろう。確かに、物事には必ず終わりが来る。しかし、その現実を受け入れることができるだろうか。少年のいる生活が終わったら、この狭い部屋には何が残るのだろうか。
お喋りが終わり、少年が眠りについてからも、塔はずっと、そのことについて考えていました。夜通し考えに考え、頬の雫が乾かぬうちに塔も眠りに落ちてしまうのでした。
本日は、お花のお世話デーです。お花のお世話デーといっても、そんな日があるのではなく、朝、少年と二人で話をしていて、急遽、部屋に置いてある植木鉢をお世話しようとなっただけのことです。塔と少年は、胸を躍らせながら準備を進めました。リビングルームには、バラや、ペチュニア、シクラメンなど、たくさんのお花が置かれており、天井からは、これまたたくさんのツル性植物が吊るされています。それら全てのお世話をするとなると、一日で終わるのか怪しいほど多いのです。黄金色のテーブルに鉢を並べると、根詰まりを起こした植物を大きな鉢へと移していきます。作業をしながら、また少年はお喋りを始めます。
「僕はね、植物が大好きなんだよ。ほら見て、このサフィニア。僕が初めて育てたお花だよ。花弁についた桃色のハートがとても愛らしいでしょ。それにこのパキラなんて、僕の腕くらい大きいし、青々としてとてもたくましいよね」
作業を続けながら塔は、大きさなら負けてないよ、と冗談を一つ。
続いて、少年はペチュニアを手に取ります。
「とうさんはこの子達のこと、覚えてる? この子達はね、僕が初めて挿し芽を成功させた株だよ。あの時は大変だったなあ。一日中ずっとこの子達を抱えて、新芽が出ないかって見守ってたんだ。こんなに小さかったんだよ」
少年は、人差し指と親指を差し出して隙間を作り、片目を閉じてその隙間越しにペチュニアを覗きます。
ああ、もちろん覚えているよ、と塔は答えます。躓いて危うく落とすとこだったよね。
「結局、親株は冬を越せずに死んでしまったんだけどね。できることなら、また親子揃って濃紫色の八重を見せて欲しかったな」
塔は当時のことを鮮明に覚えていました。少年は枯らしてしまったことを気に病んで、ベッドで毛布にうずくまってしまい、夜になるとしくしくと枕を濡らしたのでした。一週間ほど籠っていた間、塔には何もしてあげられなかったという後悔だけが残っていたのです。
ふと、少年は手を止めると、目を輝かせながら言います。
「時々、想像するんだ。もし自分が植物になれたら、どんな感じなんだろうって。きっと楽しくて仕方がないだろうなあ。たんぽぽの綿毛になって空を旅したり、ひまわりの種になって誰が一番先に太陽に届くか競争したり。」
綺麗な花をつけて、みんなを魅了しちゃったりしてね、と塔は少年の調子に合わせてあげます。
でも、根ついてしまうとその場から動けないし、近くに誰かいてくれないと、きっと寂しいよ、と言いかけた途端、塔は喉の奥に何か引っかかったような感覚に襲われ、言葉が出なくなってしまいました。
「どうしたの。とうさん」
少年は気にかけますが、塔には届きません。塔は植え替えどころではなくなってしまいました。
「とうさんは、きっと疲れてしまったんだね。残りは僕が一人でやっておくよ」
少年は黙ってしまった塔に少し違和感を覚えますが、一人鼻歌を歌いながら作業を続けるのでした。
気がつくとあたりは夕暮れで茜色に染まっていて、月がその真ん丸な顔を出し始め、塔のすぐそばの森では母鼠が、もう帰る時間だよ、と小鼠の手をとって一緒に家へ帰っているのでした。塔は、何も言わず、ただ夕日を眺めていました。
今まで長い間生きてきて、一度もこんな感情を抱いたことはなかった。この感情をなんと呼べばいいのだろう。この状態を少年になんと説明したらいいだろう。
塔はまたもや頭を悩ませることとなりました。しかし、いつまで経っても答えは出ません。以前のように泣きたい気持ちになるわけではありませんでしたが、塔の心の中にはぽっかりと穴が空いてしまったようでした。それからというものの、塔は何をするにしても、心ここに在らずといった状態で、いよいよ少年が心配をし始めた頃、大きな事件が起きてしまうのでした。
それは、少年と塔が居間に現れた蜘蛛に名前をつけ、三人で一緒に遊んでいた時のことです。突然、アトリエ部屋の方から大きな物音がしたのです。あまりの大きさに塔も少年も固まってしまいました。二人の金縛りが解けるよりも先に、今度はぼそぼそと独り言のようなものが聞こえます。二人は静かに扉に近寄り、恐る恐る扉を開けると、なんとそこには少年と同じほどの背丈をした少女がカンバスをじっくりと鑑賞しているのでした。服は前に絵本で読んだ冒険家のようで、背中には大きなリュックを背負っています。少女の短くも美しく輝く金髪に少年は見惚れてしまいました。少女はカンバスに見入っていて、少年には気づいていない様子です。
「君は誰?」
少年がそう尋ねると、少女は驚いて、勢いよく顔を上げます。
「あら、勝手にごめんなさい。人がいると思わなくて」
少女は、これは予想外といったものの、あまり驚いてはいない様子。碧色の綺麗な瞳でまじまじと少年を見つめると、
「あなた、ここに住んでいるの?」
「そうだよ」
と、戸惑い混じりに答えます。。
「もしかして、この絵を描いたのもあなた?」
カンバスには、小さな町々とそれを見下ろす大きな樹木が描かれていました。
「そうだよ。つい昨日完成したんだ」
「そうなの。私、この絵大好きだわ」
少女の言葉は歯に衣着せぬまっすぐなもので、その少年を見る視線からも、一糸纏わぬ本音であることが伝わります。少年は突然の来訪に不審と驚きを禁じ得なかったのですが、その一言で少年の胸からそれらは一切消えて、代わりに喜びでいっぱいになりました
「誰かに作品を見せたことなんてなかったから、そう言ってもらえるなんて、とっても嬉しいよ。僕は絵を描くのが大好きなんだ。この絵は僕がもし植物だったらって想像しながら書いたんだよ」
少年は意気揚々と述べていましたが、ふと、先ほどまでの疑問が蘇ってきて、少女に尋ねます。
「君は一体どこから、どうやってこの部屋に来たの?」
「そんなの、簡単よ。ロープをこの穴に投げ込んで、それを伝ってきたのよ」
彼女が親指で背後を指差し、その先を追うと、ロープを巻きつけた石が窓に引っかかっていました。
さっきの大きな音は石が投げ込まれた音だったのか。
「そんなことはどうでもいいの。それよりもあなた、さっきその絵は自分で描いたって言ってたけど、あなたは目が見えないのでしょう? どうやって描いたのか、そっちの方が気になるわ」
少女はその宝石のような瞳を輝かせています。
少女のあまりの熱意にしどろもどろになりながらも、少年は
「目が見えるか、見えないかなんて絵描きには重要じゃないからね。重要なのは心の眼で見ることなんだよ。」
と答えると、
「つまり、あなたは心の眼で見た風景をモチーフに描いているってことね。なんだか、どこぞやのキツネみたいなことを言うけれど、その考え、とても素敵だわ。ねえ、他にも作品はないの?」
できあがった絵画は寝室に置いてある、と少年が言う前には、もう彼女の興味の的は変わっていて、筆や絵の具について質問してきたかと思えば、次はリビングに置いてある鉢を指差しながら「あの植物は何?」といったふうに、少年のことなどお構いなしです。少年は、あれやこれやと説明で大忙しでしたが、不思議と嫌な気持ちはしないのでした。しばらくの間、彼女とお話を続けて、次第に彼女のペースにも慣れてきます。
「君ってなんだか変な人だね。僕は自分以外の人間に会ったことがなくて。とうさんから話は聞いてたけど、君は話に聞いてた人間とはなんだか違う」
「あら、あなたにそんなこと言われる筋合いはないわよ。第一、お父さんから話は聞いているのに、人間に会ったことないって、そこでもう矛盾してるじゃない」
そう言われても、少年は意味がわからず、首を傾げて困ってしまいました。そんな少年をよそに、少女は続けます。
「それに、目が見えないのに絵描きをしているあなたの方が、よっぽど変だわ。私のほうこそ、あなたみたいな人間に出会ったことないもの」
「変じゃないよ。むしろ僕は目が見えないから絵を描いているんだ。僕は自分が盲目で良かったとさえ思ってるよ」
そう力説する少年に、今度は少女のほうが理解できない様子。
「やっぱり、あなただって変な人ね。でも話をしてて、とても面白いわ」
少女が白い歯を見せてにっと笑うと、少年もなんだか楽しくなってきて、自然と笑みがこぼれるのでした。それからも、少年と少女は会話に花を咲かせ、陽が落ちた後も部屋には楽しげな笑い声が響くのでした。
二人が部屋を駆け回ったり、床を笑い転げている間、塔はずっと静かに二人を見守っていました。そんな二人を見て、塔の気持ちは嬉しくも悲しくもあります。塔にはもう、何をどうすればいいのかもわからくなっているのでした。何について考えたらいいのか、その優先順位すらもつけられません。
塔はまた考えていました。
これからどうなるのだろう。きっと少年には素晴らしい日々が待っている。少年が得られなかった、光り輝く夢も温もりのこもった愛もきっとそこにある。けれどそこは、きっと二人だけの世界なのだ。誰も立ち入ることのできない、二人だけの世界。
塔にはどうすることもできなくて、ただじっと見守るのでした。
夜が明けて次の日、喋り疲れてリビングのテーブルで寝てしまった二人は、開けはなしのアトリエ部屋から差す朝日で目を覚まします。東の山際から指す柔らかい陽光は、森の木々を照らし、湖のほとりの草花たちを優しく包んでいます。硝子玉のように美しい朝でしたが、塔の影は濃くなるばかりなのでした。少女は寝ぼけ眼で少年に言います。
「私、ずっと遠くから歩いて旅をしてきたの。それでね、私、あなたと一緒にいてすごく楽しいし、それにあなたはこの塔から出たことないって言うから、あなたも私と一緒に外の世界へ出てみない? きっと今まで以上に素敵な旅になると思うの」
少年は少女の提案に胸が高鳴ります。少年には、恐怖がないと言えば嘘になりますが、それ以上に外の世界に対する羨望がありました。陽の光を浴びた少女の顔が一段と明るくなったような気がして、
「氷の降る砂漠や真夏のように暑い雪原、一面塩でできた湖に天国みたいにきれいなお花畑。一緒に見に行こうよ。そして、そこに行って絵を描こうよ」
最後の一言が少年の迷いを確固たるものにしました。少年は以前の塔との会話を思い出していました。自分の人生を作品にしたい。その夢を叶えるためには、この旅は必要に思われてならないのです。しかし、会話を思い出したことで、新たな迷いが生じてしまいました。
「でも、僕が出て行ったら、とうさんはどうなるの?」
「お父さん? お父さんなんて、この塔には誰もいないじゃない」
「ここにはいないけど、けれど確かにこの部屋にいるんだ。今は聞こえないだけなんだ。ねえとうさん、返事をしておくれよ」
少女はきょろきょろと部屋を見渡し、誰もいないことがわかると、少年の次の言葉を待ちます。少年はじっと返事を待ちますが、いつまで経っても返答はありません。部屋には静寂が降り落ちました。それは今までのこの部屋で交わされた塔との全てが、幻であったということを痛切に少年に告げているのでした。
少年は自分の感情を言葉にできず、俯いてしまいました。少年は今まで塔の存在があまりに当然のものだったので気が付かなかったのです。塔がどんな姿をしているのか、塔が自分に何を残してくれたのか、塔が自分をどう思い、そして自分が塔をどう思っているのか、あまりに考えていなかったのです。少年は泣きたくなって、今更になって塔の声が聞きたくなってきました。
「あなたの言う父さんが誰なのかはわからないけど、あなたにとってその人は大切な人なの?」
沈黙に耐えかねた少女が尋ねます。
「ああ、今まで考えたこともなかった。いや、本当は気づいていたけど、目を逸らしていただけなのかもしれない。僕にとっては、そこにいるのが当たり前だったんだ。けれども、もう空っぽになってしまった」
「空っぽ? 何が空っぽになったの?」
「僕とこの塔さ」
少年の目に溜まっていた涙がついに、流れ始めてしまいました。少女はなぜ泣いているのかわからなかったので、心に浮かんだことを素直に言うことにしました。
「少なくとも、あなたは空っぽなんかじゃないわ。だって、あんな素敵な絵が描けるんだもの」
少年は顔を上げ、少女を見つめます。
「出会ってたった一日だけど、私にはわかる。あなたはそんな卑下するような人間じゃないわ。あなたの絵がそう言っているもの。それでも、空っぽだって言うなら、私があなたに注いであげる。絵を描きながらでも、植物を育てながらでもいい。あなたがあなたを見つけるのを、私が手伝ってあげるわ」
少年の目にはさっきまでとは性質の違う涙が溢れてきました。
「僕にも外の世界は綺麗に映るかな?」
震える声で少年は尋ねます。
「もちろんよ」
そう言うと、少女は少年を強く抱きしめました。少年は少女の胸の中でずっと泣いていました。
「準備はできた?」
少女がアトリエから大きな声で尋ねます。外はすっかり夕暮れ刻で、部屋は赤橙色に染まっています。少女は作業を終えたところでした。泣き終えた少年は、塔に唯一の手提げバッグに筆と彩具、それから何枚かの画用紙を入れると、それを肩にかけ、準備ができたことを伝えます。少年のあまりの軽装さに
「まあ、なんとかなるわよ」
と少し呆れ声の少女。
少女はリュックと背負うと、登りと同じようにロープを伝って降り始めました。窓から顔を出してその方法を観察していましたが、いざ自分で降りるとなると、やはり足がすくんでしまいます。少女に応援され、下を見ずになんとか十数メートル降りると、ようやく地面に到着しました。
「えらく時間がかかったわね。さあ、最後の一仕事よ」
そう言うと、彼女はあらかじめ降ろしておいた鉢から植物を丁寧に掘り出し、塔のそばに埋めていきます。少年も少女に続き、穴を掘り始めます。
「案外良いところじゃない。日も当たるし、風も気持ちいいし」
最後の一つを埋め終わると、少年は心の中で唱えます。
今までありがとう。元気に育ってね。
そう言うと、今度は立ち上がって、塔を見上げます。
恐ろしく高いと思っていたけど、そうでも無いんだね。僕を守ってくれてありがとう。僕を支えてくれてありがとう
少年の心にはもう一抹の迷いもないのでした。
「行ってきます」
少年と少女は、塔を背に歩き始めました。少年の足はさくさくと大地を踏みしめていきます。塔の後ろからは夕日が覗いて、二人の背中を後押ししています。あたりには夕凪が訪れ、二人の足音だけが響いているのでした。旅立つ少年と少女を、塔はただ立ち尽くして静かに見守っているのでした。
人里離れた森の奥深く、大きな湖のほとりには、心地の良い春風が吹いています。近くの山では野うさぎが追いかけっこをし、湖の魚たちは春を揺蕩いながら満喫しています。湖のそばにはただたくさんのお花が咲き乱れていて、そこには塔の影も形もなく、ただの平野が広がっているのでした。
永見妙
人里離れた森の奥深く、大きな湖のほとりに、それはそれは立派な塔が立っていました。大きな円柱の塔には入り口もなければ、出口もなく、なのに天辺は窓と煙突がある、石造りの家のような造形をしています。こんな辺鄙な場所も相まって、はたからみればヘンテコそのものなのは間違いないですが、こんな辺鄙な場所だからこそ、その立ち姿はどこか幻想的にも思われます。塔は誰が建てたのか、いつ建てられたのか、塔自身も知りませんが、塔にとってそんなことはどうでも良いのでした。冬から春への移り変わりを告げる温かい風や、その風の心地よさを歌う野鳥、空のように澄んだ湖の中を悠々自適に泳ぐ湖魚がそばにいてくれるだけで、塔は満足しているのです。
そしてそれらのなかでも、塔が最も大切にしているのが、塔の頂上に住む少年でした。少年は盲いた目をしており、自分の姿も、塔の身なりも、周辺の自然の顔色もわかりません。しかし、少年にとってもまた、そんなことはどうでも良いのでした。黄金色の木で作られた家具、その色に映えるように置かれた植物たち、そしてカンバスと水彩絵の具やクレヨンなどの道具を備えたアトリエ。少年にとっては、このアトリエと寝室、そしてそれらを繋ぐリビングルームが世界の全てです。そして、少年は一日中、絵を描いており、それができるだけで少年は満足しているのでした。
今日の少年はいつものように、アトリエ部屋の窓のそばに置いてある小さな丸椅子に座って、カンバスに絵を描いているのでした。窓といっても硝子も格子も付いておらず、見方によってはただ四角い穴が空いているだけとも捉えられます。塔はいつも、塔の天辺で一人寂しく暮らす少年の話し相手になってあげます。
「あのね、とうさん、僕は絵を描くのが大好きなんだ」
塔は頷きます。
「今描いているのはね、そこの窓から見える満点の星空だよ。僕はキラキラ星が大好きなんだ」
そう言うと、少年は筆を片手に握ったまま、カンバスを披露します。カンバスには杜若色の綺麗な星空と橙色の星が描かれており、稚拙ながらも力強く、そして人を惹きつける魅力をもっていました。
素敵な絵だね。
外が太陽の燦々と降り注ぐ晴天であることを確認すると、塔は返事をし、微笑ましそうに少年の話を聞いています。塔はこの時間がとても好きでした。塔にとっては、この時間が全てなのでした。そして塔はこんな生活がいつまでも続いて欲しいし、いつまでも続くと思っていました。
「あのね、とうさん、僕は目が見えないけれども、それでもいいんだ。むしろ、それで良かったと思ってる。もし僕が耳の聞こえない人だったら、きっと僕は音楽家になっているだろうし、もし読み書きができなかったら、きっと小説家になっているに違いないや。そうでしょう。とうさん」
塔は泣きたい思いでいっぱいでした。塔は少年の盲目を治せるような魔法を持ち合わせてはいません。塔が無力感に襲われていると、空は雨雲で埋まり、塔の足元のすみれには涙が降り注ぐのでした。
また次の日、少年がカンバスに向かいながら、また話しかけます。
「とうさんは優しいね。いつも黙って僕の話を聞いてくれるもの」
少年がそう言ってくれることが、塔にはとても嬉しいのです。
「僕、たまには、とうさんのお話が聞いてみたいな」
そこで、塔は今までの人間の歴史について話しました。人間がもともとは猿であったこと、道具を作って協力しながら一生懸命生きていたこと、人間が増え、文明が進むと人はどんどん協力しなくなり、果てには自分たちで殺し合うようにまで落ちぶれてしまったこと。塔は淡々と話しました。
「人間ってやっぱり変な生き物だよね。仲良しかと思ったら喧嘩したり、かと思えば喧嘩するほど仲が良いと言ったり。僕にはよくわかんないや」
わからないのは君だけではないよ、と塔は少年に笑みを投げかけます。
「あ、けれども、絵を生み出したことはすごいと思うな。こんなにも美しくて、儚くて、素晴らしくて、尊いものを作り出せるのは、それはもう奇跡としか言いようがないよね。神様だって人間が作りあげたものだし、だったら芸術は神様よりもすごいってことにもなるよね」
塔は話を遮らぬよう静かに聞いています。
「僕ね、初めて芸術をした人に会ってみたいんだ。どんなことを考えて、どんなことを表現したのか、自分の目で見てみたい。それで、僕も絵を描くんだ。その人からどんな感動だか刺激だかを受けるかわからないけど、それを形にしてみたいんだ」
いつか叶うといいね、と塔。
「昔、人生は芸術を模倣する、なんて言葉を残した人がいたけど、やっぱり僕の人生は僕の人生を芸術にするためにあるのだと思うんだ。それはきっと、僕史上、最高の作品になるんだろうなあ。それで死ねるっていうなら本望だよ」
突然、少年から一度も聞いたことのないような言葉が流れて、塔は動揺します。
「絵が描けなくなっても良いのだなんて、もちろんそうに決まってるじゃないか。人生の最大の目的は、それを通して最高傑作をつくることなんだよ。それが完成したら生きる意味なんてなくなってしまうし、僕はそうして死にたいとさえ思うんだ」
初めて聞いた少年の考えに塔は驚きを隠せません。しかし、少年の意思は断固たるもので、塔がいくら考えを改めるよう言っても、少年は聞く耳を持ちません。少年の話を聞けば聞くほど、塔は胸が締め付けられるような感覚になってきました。
この子がいなくなってしまったら、それから先はどうなるのだろう。確かに、物事には必ず終わりが来る。しかし、その現実を受け入れることができるだろうか。少年のいる生活が終わったら、この狭い部屋には何が残るのだろうか。
お喋りが終わり、少年が眠りについてからも、塔はずっと、そのことについて考えていました。夜通し考えに考え、頬の雫が乾かぬうちに塔も眠りに落ちてしまうのでした。
本日は、お花のお世話デーです。お花のお世話デーといっても、そんな日があるのではなく、朝、少年と二人で話をしていて、急遽、部屋に置いてある植木鉢をお世話しようとなっただけのことです。塔と少年は、胸を躍らせながら準備を進めました。リビングルームには、バラや、ペチュニア、シクラメンなど、たくさんのお花が置かれており、天井からは、これまたたくさんのツル性植物が吊るされています。それら全てのお世話をするとなると、一日で終わるのか怪しいほど多いのです。黄金色のテーブルに鉢を並べると、根詰まりを起こした植物を大きな鉢へと移していきます。作業をしながら、また少年はお喋りを始めます。
「僕はね、植物が大好きなんだよ。ほら見て、このサフィニア。僕が初めて育てたお花だよ。花弁についた桃色のハートがとても愛らしいでしょ。それにこのパキラなんて、僕の腕くらい大きいし、青々としてとてもたくましいよね」
作業を続けながら塔は、大きさなら負けてないよ、と冗談を一つ。
続いて、少年はペチュニアを手に取ります。
「とうさんはこの子達のこと、覚えてる? この子達はね、僕が初めて挿し芽を成功させた株だよ。あの時は大変だったなあ。一日中ずっとこの子達を抱えて、新芽が出ないかって見守ってたんだ。こんなに小さかったんだよ」
少年は、人差し指と親指を差し出して隙間を作り、片目を閉じてその隙間越しにペチュニアを覗きます。
ああ、もちろん覚えているよ、と塔は答えます。躓いて危うく落とすとこだったよね。
「結局、親株は冬を越せずに死んでしまったんだけどね。できることなら、また親子揃って濃紫色の八重を見せて欲しかったな」
塔は当時のことを鮮明に覚えていました。少年は枯らしてしまったことを気に病んで、ベッドで毛布にうずくまってしまい、夜になるとしくしくと枕を濡らしたのでした。一週間ほど籠っていた間、塔には何もしてあげられなかったという後悔だけが残っていたのです。
ふと、少年は手を止めると、目を輝かせながら言います。
「時々、想像するんだ。もし自分が植物になれたら、どんな感じなんだろうって。きっと楽しくて仕方がないだろうなあ。たんぽぽの綿毛になって空を旅したり、ひまわりの種になって誰が一番先に太陽に届くか競争したり。」
綺麗な花をつけて、みんなを魅了しちゃったりしてね、と塔は少年の調子に合わせてあげます。
でも、根ついてしまうとその場から動けないし、近くに誰かいてくれないと、きっと寂しいよ、と言いかけた途端、塔は喉の奥に何か引っかかったような感覚に襲われ、言葉が出なくなってしまいました。
「どうしたの。とうさん」
少年は気にかけますが、塔には届きません。塔は植え替えどころではなくなってしまいました。
「とうさんは、きっと疲れてしまったんだね。残りは僕が一人でやっておくよ」
少年は黙ってしまった塔に少し違和感を覚えますが、一人鼻歌を歌いながら作業を続けるのでした。
気がつくとあたりは夕暮れで茜色に染まっていて、月がその真ん丸な顔を出し始め、塔のすぐそばの森では母鼠が、もう帰る時間だよ、と小鼠の手をとって一緒に家へ帰っているのでした。塔は、何も言わず、ただ夕日を眺めていました。
今まで長い間生きてきて、一度もこんな感情を抱いたことはなかった。この感情をなんと呼べばいいのだろう。この状態を少年になんと説明したらいいだろう。
塔はまたもや頭を悩ませることとなりました。しかし、いつまで経っても答えは出ません。以前のように泣きたい気持ちになるわけではありませんでしたが、塔の心の中にはぽっかりと穴が空いてしまったようでした。それからというものの、塔は何をするにしても、心ここに在らずといった状態で、いよいよ少年が心配をし始めた頃、大きな事件が起きてしまうのでした。
それは、少年と塔が居間に現れた蜘蛛に名前をつけ、三人で一緒に遊んでいた時のことです。突然、アトリエ部屋の方から大きな物音がしたのです。あまりの大きさに塔も少年も固まってしまいました。二人の金縛りが解けるよりも先に、今度はぼそぼそと独り言のようなものが聞こえます。二人は静かに扉に近寄り、恐る恐る扉を開けると、なんとそこには少年と同じほどの背丈をした少女がカンバスをじっくりと鑑賞しているのでした。服は前に絵本で読んだ冒険家のようで、背中には大きなリュックを背負っています。少女の短くも美しく輝く金髪に少年は見惚れてしまいました。少女はカンバスに見入っていて、少年には気づいていない様子です。
「君は誰?」
少年がそう尋ねると、少女は驚いて、勢いよく顔を上げます。
「あら、勝手にごめんなさい。人がいると思わなくて」
少女は、これは予想外といったものの、あまり驚いてはいない様子。碧色の綺麗な瞳でまじまじと少年を見つめると、
「あなた、ここに住んでいるの?」
「そうだよ」
と、戸惑い混じりに答えます。。
「もしかして、この絵を描いたのもあなた?」
カンバスには、小さな町々とそれを見下ろす大きな樹木が描かれていました。
「そうだよ。つい昨日完成したんだ」
「そうなの。私、この絵大好きだわ」
少女の言葉は歯に衣着せぬまっすぐなもので、その少年を見る視線からも、一糸纏わぬ本音であることが伝わります。少年は突然の来訪に不審と驚きを禁じ得なかったのですが、その一言で少年の胸からそれらは一切消えて、代わりに喜びでいっぱいになりました
「誰かに作品を見せたことなんてなかったから、そう言ってもらえるなんて、とっても嬉しいよ。僕は絵を描くのが大好きなんだ。この絵は僕がもし植物だったらって想像しながら書いたんだよ」
少年は意気揚々と述べていましたが、ふと、先ほどまでの疑問が蘇ってきて、少女に尋ねます。
「君は一体どこから、どうやってこの部屋に来たの?」
「そんなの、簡単よ。ロープをこの穴に投げ込んで、それを伝ってきたのよ」
彼女が親指で背後を指差し、その先を追うと、ロープを巻きつけた石が窓に引っかかっていました。
さっきの大きな音は石が投げ込まれた音だったのか。
「そんなことはどうでもいいの。それよりもあなた、さっきその絵は自分で描いたって言ってたけど、あなたは目が見えないのでしょう? どうやって描いたのか、そっちの方が気になるわ」
少女はその宝石のような瞳を輝かせています。
少女のあまりの熱意にしどろもどろになりながらも、少年は
「目が見えるか、見えないかなんて絵描きには重要じゃないからね。重要なのは心の眼で見ることなんだよ。」
と答えると、
「つまり、あなたは心の眼で見た風景をモチーフに描いているってことね。なんだか、どこぞやのキツネみたいなことを言うけれど、その考え、とても素敵だわ。ねえ、他にも作品はないの?」
できあがった絵画は寝室に置いてある、と少年が言う前には、もう彼女の興味の的は変わっていて、筆や絵の具について質問してきたかと思えば、次はリビングに置いてある鉢を指差しながら「あの植物は何?」といったふうに、少年のことなどお構いなしです。少年は、あれやこれやと説明で大忙しでしたが、不思議と嫌な気持ちはしないのでした。しばらくの間、彼女とお話を続けて、次第に彼女のペースにも慣れてきます。
「君ってなんだか変な人だね。僕は自分以外の人間に会ったことがなくて。とうさんから話は聞いてたけど、君は話に聞いてた人間とはなんだか違う」
「あら、あなたにそんなこと言われる筋合いはないわよ。第一、お父さんから話は聞いているのに、人間に会ったことないって、そこでもう矛盾してるじゃない」
そう言われても、少年は意味がわからず、首を傾げて困ってしまいました。そんな少年をよそに、少女は続けます。
「それに、目が見えないのに絵描きをしているあなたの方が、よっぽど変だわ。私のほうこそ、あなたみたいな人間に出会ったことないもの」
「変じゃないよ。むしろ僕は目が見えないから絵を描いているんだ。僕は自分が盲目で良かったとさえ思ってるよ」
そう力説する少年に、今度は少女のほうが理解できない様子。
「やっぱり、あなただって変な人ね。でも話をしてて、とても面白いわ」
少女が白い歯を見せてにっと笑うと、少年もなんだか楽しくなってきて、自然と笑みがこぼれるのでした。それからも、少年と少女は会話に花を咲かせ、陽が落ちた後も部屋には楽しげな笑い声が響くのでした。
二人が部屋を駆け回ったり、床を笑い転げている間、塔はずっと静かに二人を見守っていました。そんな二人を見て、塔の気持ちは嬉しくも悲しくもあります。塔にはもう、何をどうすればいいのかもわからくなっているのでした。何について考えたらいいのか、その優先順位すらもつけられません。
塔はまた考えていました。
これからどうなるのだろう。きっと少年には素晴らしい日々が待っている。少年が得られなかった、光り輝く夢も温もりのこもった愛もきっとそこにある。けれどそこは、きっと二人だけの世界なのだ。誰も立ち入ることのできない、二人だけの世界。
塔にはどうすることもできなくて、ただじっと見守るのでした。
夜が明けて次の日、喋り疲れてリビングのテーブルで寝てしまった二人は、開けはなしのアトリエ部屋から差す朝日で目を覚まします。東の山際から指す柔らかい陽光は、森の木々を照らし、湖のほとりの草花たちを優しく包んでいます。硝子玉のように美しい朝でしたが、塔の影は濃くなるばかりなのでした。少女は寝ぼけ眼で少年に言います。
「私、ずっと遠くから歩いて旅をしてきたの。それでね、私、あなたと一緒にいてすごく楽しいし、それにあなたはこの塔から出たことないって言うから、あなたも私と一緒に外の世界へ出てみない? きっと今まで以上に素敵な旅になると思うの」
少年は少女の提案に胸が高鳴ります。少年には、恐怖がないと言えば嘘になりますが、それ以上に外の世界に対する羨望がありました。陽の光を浴びた少女の顔が一段と明るくなったような気がして、
「氷の降る砂漠や真夏のように暑い雪原、一面塩でできた湖に天国みたいにきれいなお花畑。一緒に見に行こうよ。そして、そこに行って絵を描こうよ」
最後の一言が少年の迷いを確固たるものにしました。少年は以前の塔との会話を思い出していました。自分の人生を作品にしたい。その夢を叶えるためには、この旅は必要に思われてならないのです。しかし、会話を思い出したことで、新たな迷いが生じてしまいました。
「でも、僕が出て行ったら、とうさんはどうなるの?」
「お父さん? お父さんなんて、この塔には誰もいないじゃない」
「ここにはいないけど、けれど確かにこの部屋にいるんだ。今は聞こえないだけなんだ。ねえとうさん、返事をしておくれよ」
少女はきょろきょろと部屋を見渡し、誰もいないことがわかると、少年の次の言葉を待ちます。少年はじっと返事を待ちますが、いつまで経っても返答はありません。部屋には静寂が降り落ちました。それは今までのこの部屋で交わされた塔との全てが、幻であったということを痛切に少年に告げているのでした。
少年は自分の感情を言葉にできず、俯いてしまいました。少年は今まで塔の存在があまりに当然のものだったので気が付かなかったのです。塔がどんな姿をしているのか、塔が自分に何を残してくれたのか、塔が自分をどう思い、そして自分が塔をどう思っているのか、あまりに考えていなかったのです。少年は泣きたくなって、今更になって塔の声が聞きたくなってきました。
「あなたの言う父さんが誰なのかはわからないけど、あなたにとってその人は大切な人なの?」
沈黙に耐えかねた少女が尋ねます。
「ああ、今まで考えたこともなかった。いや、本当は気づいていたけど、目を逸らしていただけなのかもしれない。僕にとっては、そこにいるのが当たり前だったんだ。けれども、もう空っぽになってしまった」
「空っぽ? 何が空っぽになったの?」
「僕とこの塔さ」
少年の目に溜まっていた涙がついに、流れ始めてしまいました。少女はなぜ泣いているのかわからなかったので、心に浮かんだことを素直に言うことにしました。
「少なくとも、あなたは空っぽなんかじゃないわ。だって、あんな素敵な絵が描けるんだもの」
少年は顔を上げ、少女を見つめます。
「出会ってたった一日だけど、私にはわかる。あなたはそんな卑下するような人間じゃないわ。あなたの絵がそう言っているもの。それでも、空っぽだって言うなら、私があなたに注いであげる。絵を描きながらでも、植物を育てながらでもいい。あなたがあなたを見つけるのを、私が手伝ってあげるわ」
少年の目にはさっきまでとは性質の違う涙が溢れてきました。
「僕にも外の世界は綺麗に映るかな?」
震える声で少年は尋ねます。
「もちろんよ」
そう言うと、少女は少年を強く抱きしめました。少年は少女の胸の中でずっと泣いていました。
「準備はできた?」
少女がアトリエから大きな声で尋ねます。外はすっかり夕暮れ刻で、部屋は赤橙色に染まっています。少女は作業を終えたところでした。泣き終えた少年は、塔に唯一の手提げバッグに筆と彩具、それから何枚かの画用紙を入れると、それを肩にかけ、準備ができたことを伝えます。少年のあまりの軽装さに
「まあ、なんとかなるわよ」
と少し呆れ声の少女。
少女はリュックと背負うと、登りと同じようにロープを伝って降り始めました。窓から顔を出してその方法を観察していましたが、いざ自分で降りるとなると、やはり足がすくんでしまいます。少女に応援され、下を見ずになんとか十数メートル降りると、ようやく地面に到着しました。
「えらく時間がかかったわね。さあ、最後の一仕事よ」
そう言うと、彼女はあらかじめ降ろしておいた鉢から植物を丁寧に掘り出し、塔のそばに埋めていきます。少年も少女に続き、穴を掘り始めます。
「案外良いところじゃない。日も当たるし、風も気持ちいいし」
最後の一つを埋め終わると、少年は心の中で唱えます。
今までありがとう。元気に育ってね。
そう言うと、今度は立ち上がって、塔を見上げます。
恐ろしく高いと思っていたけど、そうでも無いんだね。僕を守ってくれてありがとう。僕を支えてくれてありがとう
少年の心にはもう一抹の迷いもないのでした。
「行ってきます」
少年と少女は、塔を背に歩き始めました。少年の足はさくさくと大地を踏みしめていきます。塔の後ろからは夕日が覗いて、二人の背中を後押ししています。あたりには夕凪が訪れ、二人の足音だけが響いているのでした。旅立つ少年と少女を、塔はただ立ち尽くして静かに見守っているのでした。
人里離れた森の奥深く、大きな湖のほとりには、心地の良い春風が吹いています。近くの山では野うさぎが追いかけっこをし、湖の魚たちは春を揺蕩いながら満喫しています。湖のそばにはただたくさんのお花が咲き乱れていて、そこには塔の影も形もなく、ただの平野が広がっているのでした。