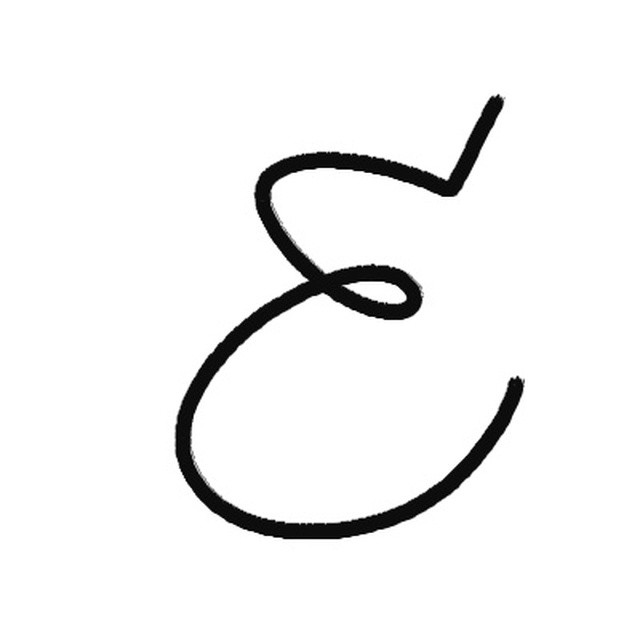第1話
文字数 8,692文字
「序章: 終着点」
永見エルマ
青年は金属かとさえも感じられるほど重くなった瞼を持ち上げ、目を覚ます。人の一生とも感じられるほどの長時間の眠りから目覚めた気分だった。
ここはどこなんだろう。
五畳半ほどの広さの部屋に青年は一人立っていた。その部屋は摩訶不思議な内装で、足元には芝が茂り、壁の隅に生えた様々な植物がその蔓を伸ばしている。正面には木製の丈夫そうなドアがあった。
こんなところに自分で入った覚えはない。頭はまだはっきりとしないし、体は鉛みたいに重い。一体どうなっているんだ。
情報を整理している最中、突然目の前の扉が開いた。出てきたのは綺麗な正装に身を包んだ老人で、こちらを見るとニコリと笑った。
「お待ちしておりました。どうぞこちらへ」
老人はそう言って扉へと手を伸ばした。混沌とした頭の中とは裏腹に、心は男のことを許していた。我ながら警戒心のなさに驚く。あえて理由をつけるなら、目の前の男に何かしらの答えを提示してくれると期待しているからであろうか。安堵さえ感じながら青年は男の後を追った。
扉の先は白い廊下だった。左右線対称にいくつもの扉が並び、一定の間隔でライトが天井に設置されている。廊下は行き止まりが見えないほどに長く、この景色に青年の心はなぜだかざわめいた。
「すみません。ここに来るまでの記憶が全くなくて、事態を飲み込めていないのですが、あなたはどなたですか?」
初老の男の少し後ろを歩きながら、青年は尋ねる。
「無理もありません。そうですね、私は言うなれば案内人です」
「案内人? 僕をどこかへ案内するということですか?」
「その通りです」
「いまいちまだよくわかりません。どこへ案内するって言うんですか?」
「口で説明するのは少々難しいですね。もちろん後できちんと説明するつもりですが、歩きながら軽く説明いたしましょう。」
初老の男は振り返り、青年の隣へ来ると、青年の歩幅に合わせて歩き始めた。
「順を追って、ゆっくりといきましょう。物事には必ず順序というものがある。まず、あなたが一番最後に覚えていることはなんですか?」
そんなことを聞いて何になるのか青年は皆目見当もつかない。困惑しながらも記憶を探る。
「そう…ですね、どこか暗いところを歩いています。歩くというより、登っている?確か階段のようなところを登っていたんです」
「それで?」
「階段を登って、それから夜景を見ました」
「ふむ、なるほど」
「それ以降のことはよく覚えていません。まるでここから記憶が消えてるみたいに真っ白です」
そうですか、と男は言った。青年はその男の様子を注意深く見る。
僕の記憶が無いことがどこか彼にとって不都合そうだ。
「他に何か覚えていることはありませんか?なんでもいいんです」
「そういえば階段を登っている時に黒猫を見たような気がします」
青年は素直に答える。ふむと言ったきり黙ってしまった老人の表情はすこし困ったように見えた。
「では次は少し趣向を変えて、あなたはこの場所、この廊下を見た時どう思いましたか?」
「どうと言われましても、そんなのおかしいと思うに決まっているじゃありませんか。見たことはないし、ここまでの記憶もないしで、混乱の二文字しかありませんよ」
「それはお説ごもっともですね」
男の声は包み込むように優しかった。
「確かにあなたから見ればこの状況は普通じゃないかもしれませんが、この状況が普通じゃないのは私もなんです」
「どういうことですか?」
「あなたが仰ったんじゃないですか。記憶がないと」
言葉の意味を理解できない青年は、黙って男の顔を覗く。男はこちらの困り顔を見て、すこしにやにやとした。その笑みは、企みを隠してこちらをだまそうとするような笑いではなく、むしろ掴み立ちの赤子を見つめるような笑いであった。
「つまり、普通は記憶があるってことですよ。あなたは記憶がなくて、それが普通ではないということです。普通といってもこの状況自体が普通ではないといえばそうなんですが。記憶がないというより正確には記憶が抜け落ちている。ややこしくなるので話を戻しましょう。あなたがこの空間をおかしいと思うのは当然ですが、ではこの空間を見て、何に似ていると思いますか?」
青年は初老の男の回りくどい態度に少し納得がいかなかったが、ここで問い詰めても答えてくれないと感じ、質問に答えた。
「ここはなんというか気が滅入るような場所ですね。ずっと同じ光景が続いているし、飾りもなくて質素だ。まるで刑務所とか…」
そこまで言って、頭に思い浮かんだ単語に不意に言葉が詰まった。目の奥が痛む。
「まるで病院みたい、そう思いませんでしたか」
青年は答えることができなかった。その言葉に連鎖するように新たに湧いて出た記憶に不安を煽られ、一気に体が熱くなるのを感じる。いつの間にか背年の左手は壁につき、立ち止まって下を向いていた。その瞳はフラッシュバックする脳内の映像に焦点が向いている。思わず胸を抑えた右手には汗が滲んでいる。
「大丈夫ですか?」
「い、いえ大丈夫です」
男に背中を優しくさすられ、青年は呼吸を整えていく。老人は膝をついて、そばに立ち寄った。
「何か思い出しましたか?」
「はい。ストレッチャーで病院内を運ばれている自分を思い出しました。ちょうどこのくらい白い壁と天井で、上から白い光が降っては去ってを繰り返して…」
「大丈夫ですよ。なぜ自分がそうなったかわかりますか?」
「いいえ。ただ体が揺れるたびに激痛が走って、すごく苦しかったことは覚えています」
「そうですか」
まるで自分が痛みを感じているかのように辛そうな表情で言うと、老人は青年に手を差し伸べる。
「その後のことは?」
「いいえ、何も」
汗ばんだ青年に老人はハンカチを手渡した。
「歩けますか? 着実に近づいていますから、頑張りましょう」
青年はありがたくハンカチを受け取ったが、そのセリフに少しだけ違和感を覚えた。
しばらく休憩をはさんだ二人はまた廊下を歩き始める。歩き始めてからしばらくたったが、一向に景色は変わらないままであった。ひたすら廊下を歩き、奥まで来たかと思いきや曲がり角だったというのをもう何回も繰り返していた。
「暇つぶしと言ってはなんですが、今度は私がお話ししましょう。私には妻と子がいるんです。結婚してから十五年近く経ちましたが、これがいつまで経っても可愛くてね。もう可愛くてしょうがないんです。目に入れても痛くないという表現がありますが、それでは表現しきれません。可愛くて食べしまいたいって慣用句を考えた人はきっと同じような気持ちだったんでしょうね」
「ついこの間は、娘の参観日に行ったりなんかしましてね。とても可愛かったです。いつか親もとを離れて行ってしまうと思うともう今から寂しいものです。妻は妻でまた苦労人でしてね。十五の時に母に先立てれてしまってからというもの、兄弟二人のために家事なんかをやったりして母親の代わりになろうとしたそうです。いやまあほんと、頭が上がらないというか尊敬の念に尽きるというものですね」
青年は時々相槌を打ちながら、男の話を聞いていた。唐突な惚気話に緊張を抜かれてしまう。それを察知したかのように老人は続ける。
「すこし驚かれましたか。なんてことはない話ですが、これをいつも話すようにしているんです。知らない場所で知らない人に突然付いてこいなんて言われても、不安なだけですからね。少しは私という人間を知ってもらってもらえればと思って始めたんです」
「そうなんですか。確かにそういった話を聞ければ人間味が増していいかもしれませんね」
気が緩んでしまったのだろう。青年がしまったと思った時には、時すでに遅しだった。つい口を滑らせてしまい、怒らせてしまったかと思ったが、予想とは裏腹に男は口を開けて笑った。
「それじゃあまるで私が人間ではないみたいな言い草じゃないですか。いやまあ、私の話が好評ならよかったです。そのへんはまた後ほどですね。私もお話ししたい気持ちは山々なんですけどねえ」
男の笑顔はスッと消え、厳かな顔になる。前を見据えて静かに言った。
「全てが終われば必ずお話しすると約束します」
男の顔は先ほどと同様の仕事人の顔となるが、優しさが無くなったわけではなく、そこには種類の違う優しさを感じ取れる。その証にこちらを見てニコリとした。
「さて、引き続き頑張っていきましょうか」
そうですねと答える。またも突っかかりを覚えた青年は、今度は尋ねてみることにした。
「先ほど記憶を思い出すのを頑張ってと仰いましたよね。そして今も同じ言葉を使いました。僕の考えすぎだったら申し訳ないのですが、何か含みを持っているように聞こえる。例えば僕が記憶を思い出すことに何かしらの困難があるとか。ただ思い出すだけではないんですか?」
「聡いお方ですね。故意ではありませんが、確かにその通りです。初めにも言いましたが今回はいろいろとイレギュラーだ。あなたの記憶がないこと、記憶を取り戻すのには重大な意味があること、全てはひとつの点で繋がっています」
「僕の記憶に重要な意味があることは理解しました。しかし、これ以上思い出すことはできないし、僕からできることもありません」
そう言うと青年は足を止めてしまった。
「なんでもいいんです。趣味とか普段の生活とか…」
何も言えない青年に老人は行き詰ってしまった。沈黙が廊下に満ちる。一か八かの覚悟を決めた老人がくっついた唇を開いた。
「私はどうしてもあなたに自分の力で思い出して欲しかった。きっとそうしないと前には行けないから。しかし行き詰まってしまっては仕方がありません。重大なヒントをお教えしましょう。賢いあなたならきっと辿り着ける。…あなたの記憶がないのはいわゆる逆行性健忘と言われる状態だからです。そしてその原因は脳炎や低酸素性脳症など他に…脳に対する大きな衝撃、脳外傷です。思い出せますか?」
「逆行性健忘…脳に対する大きな外傷…」
「深夜のことです。あなたは突発的に歩き始めた」
「夜…歩いて」
「そうして大きな建物に着きました」
「歩いて着いたのは…学校?」
「そこであなたは無謀にも」
「パイプを伝って登った」
「そして、残念ながら事は為されました」
「僕は…自殺したのか?」
次の瞬間、鮮明に映像が流れた。今度はよりはっきりと。人間の花火。目の前の視界に脳内の映像が混ざり合ってゆく。最初に目眩が起き、次第に呼吸が荒くなる。脳への酸素が足りていないのは明らかだった。先ほどとは比にならない、激しい過呼吸だった。
苦しい。息ができない。言葉が出ない。
青年は必死に空気を貪った。体は痛みを思い出し、体の中で沸騰したように熱い血液が体を巡っていた。すると今度は冷えるような感覚が襲う。脳みそが虚ろになってゆき、次の瞬間青年はその場に倒れた。
目が覚めて真っ先に視界に入ってきたのは白く無機質な天井だった。どうやらベッドの上で横になっているらしい。自身の上には肌触りの良い白い毛布がかけてあった。
「目が覚めましたか?」
音に反射し横を向くと、そこには木製の椅子に老人が座っている。手には本を握っているようだ。ベッドのすぐ横の机の上には古びたラジカセと青色の分厚いファイルが置いてあり、ラジカセからバイオリンを主旋律とするクラシックが流れていた。
「体調の方も大事は無いようですね。よかったです」
青年に気づいた老人は本を机に置き、ラジカセを停止した。
青年の意識がゆっくりと覚醒してくる。それと同時に倒れる前の自分の記憶も湧いてくるのだった。
「僕は自殺だったんですね」
青年は天井を見たままぼそりと言った。それが話しかけたものなのか、はたまた空に向かって放たれたものなのか、男にはわからなかった。男にはわからなかったが、わからなかったからこそ自分の意思で言わなければという責任感に駆られた。
「ふむ。そうですね。これは持論ですが、私は死には良いも悪いもないと思います。確かにキリスト教では自殺が悪だという思想もありますが、では交通事故にあいそうな子供を自ら望んで庇って死んだのなら、その死はどちらなのでしょうか?大量殺戮者を正義もってして殺した場合はその死はなの善でしょうか?結局はみな死んでしまうというのに、いずれ死ぬ者がいずれ死ぬものを助け、生きながらえさせたとして、そこに根源的な善が発生するのでしょうか?死に良いも悪いも、重いも軽いもないと私は思います」
「ありがとう」
「そう返すのですね。本当に聡い方だ」
「思い出したよ。死ぬ前の僕は空っぽだったんだ。思い出に、あの夏に囚われていた。見ず知らずの人にあの子を重ねてしまうほどに擦り切れていた。そんな自分が嫌で…」
老人はこうなることをわかっていた。わかっていたからこそ、助けたいと思ったのだ。自分から会話を始めて流れを断ち切る。
「あなたの質問にお答えしましょう、私が誰なのか。ここはあなた方が言うところのいわゆるあの世で、私は死人の対応、案内をする仕事をしている者です」
「あの世ですか。自分の目で見ていてもにわかには信じられませんね」
「皆そう仰います。ですがあの世だとか死後というのは名前だけにすぎません。私たちは天使などではなく一人の人間で、あなた方と同じように共同体を作り、社会を形成し、ご飯を食べてゆくために働いているのですよ。あなた方と同じです。あなた方が私たちを認識できなかったように、自分たちよりも高次な存在のことは知りません。もちろん自分たちが死んだあとのことも。だからこそ神様だとかを信仰する人も居ます。性質は違えど本質は同じということです。まるで陽光と月光のように」
青年は黙ってただ話を聞いていた。老人は時々合う視線から冷たい落ち着きを感じ取っていた。
「思いのほか冷静なんですね」
「驚くほどのエネルギーがないだけですよ」
青年はハハハとどうしようもなく笑った。老人は思わず青年から目をそらしてしまう。その様子があまりにも見兼ねたからだ。
突然、どこからともなく小粋なポップスが流れ始めた。短いフレーズだったが、ここまで人間の声しか聞いていなかった青年の耳は驚いてしまう。
「もうこんな時間ですか。そろそろ決めなければいけませんね。ふふふ。突然の音楽に驚きましたか?これは終業のチャイムです。今時のこんなチャイムで終業を知らせるなんて、まるで学校みたいですね」
「終業ですか」
雲行きを怪しませる単語が青年の不安を煽る。このあとこの老人はいなくなってしまうのだろうか。だとしたら僕はどうなるのだろうか。そんなことが頭をよぎる。見透かした老人はどうにか覆い被せようと試みた。
「讃美歌でも流れてると思いましたか?ふふふ、讃美歌なんて流行りませんよ。きっと神様なんていないんですから。流行るとすればそれはおそらく人間の心中にでしょうね。人間は神様の中に宿ったりなんかして。きっとあの世ではロックロールでも流れているんでしょうねえ。ああ、君から見たらここがあの世でしたね」
「いろいろと考えをお話ししてくれるんですね」と青年がほくそ笑む。
「お話しすると約束しましたからね」
すこし嬉しそうに老人は答えると、改まって青年をまっすぐ見つめる。その面持ちは神妙で、その様子は青年の心をこわばらせた。
「傷心のところ申し訳ありませんが、私はあなたに選択を迫らなくてはならない」
普段ならこの台詞の後はあれやこれやと話をする場面だ。その人のことを一番深く知ることができるこの会話が老人は好きだった。ある人は真剣だったり、ある人は楽しげだったりする。けれど、今回はそうはいかないことは明白だった。老人は一瞬、言い淀んでしまう。
「選択肢は二つです。一つはこのままこの世界に残り、この世界の住人として生きてゆく未来です。そしてもう一つは、記憶を消して、元の世界に戻る未来です。前者の場合は先ほどお話しした通り、多少の違いはあれど大まかには今までのような生活を送ることになると思ってください。一方、後者の方はあなたが死ぬまで生きていた世界を今持っている記憶を無くしてもう一度生まれ落ちることになります」
青年が黙りこくってしまうことなど老人にはわかっていた。しかし、死人の今後を管理する立場の人間として決めさせなければならない。この決断が残酷になることは、彼が死んだのに死ねなかった地点から約束されていた。老人は彼がこちらに来る前からそのことを予見していたのだ。
「おじいさん」
青年は深く息を吸ってから尋ねる。いまの青年の口からどんな言葉が出てくるか予想がつかない老人は、少し身構えてしまう。
「赤ん坊が生まれてくる時って泣いてるじゃないですか。あれってどうゆう泣きなんでしょうね。怒りなら悔しさならしょっぱい、喜びや悲しみなら甘いって具合に涙の味が変化するからそれで少しはわかるのに、赤ん坊は涙を流さずに泣くからわからないですよね」
老人は答えられなかった。そんなものわかりはしない。赤ん坊が生まれたくて生まれているかだとか、どんな感情を持ってこの世に生を授かるかなんてことは誰にもわからない。しかし、青年はまるでその問いに対してはっきりと答えを持っているかのように思えてならなかった。直接それを言わずに老人に問いかけて、無理やりにその答えを押し付けているかのようにさえも思えた。
「私にはわかりかねます。しかし、死ぬときの感情はきっとみんな死にたくない、ではないでしょうか。あなたはそうは思いませんでしたか?」
「…正直に言うと、思いました。目の前に地面が来た瞬間に決意はあまりにも簡単に揺らいだ。こんなことしなければと思った。その時は思ったけれど、今はそうは思わない。こうゆうときはしなければよかったなんて思わないようにしてます。そう思ってしまうと過去の僕が可哀想だ」
「そうですね。過去の苦しみを軽んじるというのは時にその人への冒涜になる。それが死にたいほどの強い感情であればなおのこと。きっと過去のあなたを肯定してあげ得るのは今のあなただけなんでしょう。過去のあなたを慰めてあげられるのは今のあなたで、今のあなたを慰めるのは未来のあなただ。そして、未来のあなたを決めるのは今のあなただ。だからあなたには真に良いと思えるような選択をしてほしい」
「けれど僕にはそんなことはできない。僕は空っぽなんだから」
そう言われた老人は心の中でそんなことはないと言う。だがそれが喉を通って言葉になるよりも前に、頭の中である人物が閃いていた。それならば彼が空っぽでないことを証明させられる。
老人は机に置いてあるファイルをすぐさま手に取る。少しの間何ページかめくり資料を確かめた。
「このファイルにはここに来た方々の前世の概要があります。もちろんあなたの資料も拝見させていただきました。あなたは空っぽではないことはすでに証明されているではありませんか。少し気になる名前がありましてね。私もこの方には会ったのです」
そう言って、青年にファイルを手渡した。ファイルの中の資料には死亡時の年齢や住所などと共に、縦四ミリ横三ミリの顔写真がついていた。それをみた青年は目を見開く。ファイルを持つ手は小刻みに震えており、口からは言葉がすらすらと出ない。
「どうしてこの子が?」
「ご存じの通りですよ。その子も死んで、そして彼女も来たんですよ。ここに」
息が詰まって、言葉を出させずに2いる青年に老人は優しく語りかける。
「彼女は私に言いました。会わなければならない人がいると。そう言って元の世界に戻られました」
顔写真に釘付けだった顔をばっとあげ、老人を見る。その目には涙が滲んでいた。その目は本当にあの子がと確認を迫っている。
「もうどちらか明白なのではないでしょうか?」
青年は静かに、しかしはっきりと言った。
「はい」
「では行きましょうか」
老人はそう言うと部屋の扉を開けた。やはり扉の先は真っ白に続く廊下であった。青年はまた長い廊下を歩かされるのかと思ったが、今度はそうは行かなかった。何度か丁字路を曲がると、徐に扉を開ける。その部屋に入ると、中は小さな部屋で、すぐ目の前にまた木製の扉があった。その黄金色が真っ白な空間の中で存在感を放っている。
「この扉です。種明かしではないですが、あの選択が決まるまで出られないようになっているんです。業務とはいえ失礼しました」
「いえ。こちらこそお手数おかけしました。ほんとにいろいろ」
「最後の確認です。本当にこちらでよろしいですね」
「空っぽが埋まったわけではないし、これが正解かもわからない。だけど、こっちが良いと僕は思います」
返事の代わりに、老人は笑みを送った。
「では行ってしまう前に一つアドバイス、というよりもただの老人のたわ言
だと思って聞いてほしいのですが、人生を豊かにしてくれるのは創作だと思っています。もちろんそれが全てではありませんが、それでも私はあなたにぜひ創作活動をなさってほしい。芸術の本質はナンセンスだ。音でも文字でも絵の具でも構いません。とにかく自分から新たな何かを生み出す行為をあなたにしてほしいと思います。きっと君に合ってる」
「ありがとう」
青年は扉を開ける。光あふれたその先に、青年は一歩踏みしめた。その後ろには優しい笑顔で手を振る老人がいた。
永見エルマ
青年は金属かとさえも感じられるほど重くなった瞼を持ち上げ、目を覚ます。人の一生とも感じられるほどの長時間の眠りから目覚めた気分だった。
ここはどこなんだろう。
五畳半ほどの広さの部屋に青年は一人立っていた。その部屋は摩訶不思議な内装で、足元には芝が茂り、壁の隅に生えた様々な植物がその蔓を伸ばしている。正面には木製の丈夫そうなドアがあった。
こんなところに自分で入った覚えはない。頭はまだはっきりとしないし、体は鉛みたいに重い。一体どうなっているんだ。
情報を整理している最中、突然目の前の扉が開いた。出てきたのは綺麗な正装に身を包んだ老人で、こちらを見るとニコリと笑った。
「お待ちしておりました。どうぞこちらへ」
老人はそう言って扉へと手を伸ばした。混沌とした頭の中とは裏腹に、心は男のことを許していた。我ながら警戒心のなさに驚く。あえて理由をつけるなら、目の前の男に何かしらの答えを提示してくれると期待しているからであろうか。安堵さえ感じながら青年は男の後を追った。
扉の先は白い廊下だった。左右線対称にいくつもの扉が並び、一定の間隔でライトが天井に設置されている。廊下は行き止まりが見えないほどに長く、この景色に青年の心はなぜだかざわめいた。
「すみません。ここに来るまでの記憶が全くなくて、事態を飲み込めていないのですが、あなたはどなたですか?」
初老の男の少し後ろを歩きながら、青年は尋ねる。
「無理もありません。そうですね、私は言うなれば案内人です」
「案内人? 僕をどこかへ案内するということですか?」
「その通りです」
「いまいちまだよくわかりません。どこへ案内するって言うんですか?」
「口で説明するのは少々難しいですね。もちろん後できちんと説明するつもりですが、歩きながら軽く説明いたしましょう。」
初老の男は振り返り、青年の隣へ来ると、青年の歩幅に合わせて歩き始めた。
「順を追って、ゆっくりといきましょう。物事には必ず順序というものがある。まず、あなたが一番最後に覚えていることはなんですか?」
そんなことを聞いて何になるのか青年は皆目見当もつかない。困惑しながらも記憶を探る。
「そう…ですね、どこか暗いところを歩いています。歩くというより、登っている?確か階段のようなところを登っていたんです」
「それで?」
「階段を登って、それから夜景を見ました」
「ふむ、なるほど」
「それ以降のことはよく覚えていません。まるでここから記憶が消えてるみたいに真っ白です」
そうですか、と男は言った。青年はその男の様子を注意深く見る。
僕の記憶が無いことがどこか彼にとって不都合そうだ。
「他に何か覚えていることはありませんか?なんでもいいんです」
「そういえば階段を登っている時に黒猫を見たような気がします」
青年は素直に答える。ふむと言ったきり黙ってしまった老人の表情はすこし困ったように見えた。
「では次は少し趣向を変えて、あなたはこの場所、この廊下を見た時どう思いましたか?」
「どうと言われましても、そんなのおかしいと思うに決まっているじゃありませんか。見たことはないし、ここまでの記憶もないしで、混乱の二文字しかありませんよ」
「それはお説ごもっともですね」
男の声は包み込むように優しかった。
「確かにあなたから見ればこの状況は普通じゃないかもしれませんが、この状況が普通じゃないのは私もなんです」
「どういうことですか?」
「あなたが仰ったんじゃないですか。記憶がないと」
言葉の意味を理解できない青年は、黙って男の顔を覗く。男はこちらの困り顔を見て、すこしにやにやとした。その笑みは、企みを隠してこちらをだまそうとするような笑いではなく、むしろ掴み立ちの赤子を見つめるような笑いであった。
「つまり、普通は記憶があるってことですよ。あなたは記憶がなくて、それが普通ではないということです。普通といってもこの状況自体が普通ではないといえばそうなんですが。記憶がないというより正確には記憶が抜け落ちている。ややこしくなるので話を戻しましょう。あなたがこの空間をおかしいと思うのは当然ですが、ではこの空間を見て、何に似ていると思いますか?」
青年は初老の男の回りくどい態度に少し納得がいかなかったが、ここで問い詰めても答えてくれないと感じ、質問に答えた。
「ここはなんというか気が滅入るような場所ですね。ずっと同じ光景が続いているし、飾りもなくて質素だ。まるで刑務所とか…」
そこまで言って、頭に思い浮かんだ単語に不意に言葉が詰まった。目の奥が痛む。
「まるで病院みたい、そう思いませんでしたか」
青年は答えることができなかった。その言葉に連鎖するように新たに湧いて出た記憶に不安を煽られ、一気に体が熱くなるのを感じる。いつの間にか背年の左手は壁につき、立ち止まって下を向いていた。その瞳はフラッシュバックする脳内の映像に焦点が向いている。思わず胸を抑えた右手には汗が滲んでいる。
「大丈夫ですか?」
「い、いえ大丈夫です」
男に背中を優しくさすられ、青年は呼吸を整えていく。老人は膝をついて、そばに立ち寄った。
「何か思い出しましたか?」
「はい。ストレッチャーで病院内を運ばれている自分を思い出しました。ちょうどこのくらい白い壁と天井で、上から白い光が降っては去ってを繰り返して…」
「大丈夫ですよ。なぜ自分がそうなったかわかりますか?」
「いいえ。ただ体が揺れるたびに激痛が走って、すごく苦しかったことは覚えています」
「そうですか」
まるで自分が痛みを感じているかのように辛そうな表情で言うと、老人は青年に手を差し伸べる。
「その後のことは?」
「いいえ、何も」
汗ばんだ青年に老人はハンカチを手渡した。
「歩けますか? 着実に近づいていますから、頑張りましょう」
青年はありがたくハンカチを受け取ったが、そのセリフに少しだけ違和感を覚えた。
しばらく休憩をはさんだ二人はまた廊下を歩き始める。歩き始めてからしばらくたったが、一向に景色は変わらないままであった。ひたすら廊下を歩き、奥まで来たかと思いきや曲がり角だったというのをもう何回も繰り返していた。
「暇つぶしと言ってはなんですが、今度は私がお話ししましょう。私には妻と子がいるんです。結婚してから十五年近く経ちましたが、これがいつまで経っても可愛くてね。もう可愛くてしょうがないんです。目に入れても痛くないという表現がありますが、それでは表現しきれません。可愛くて食べしまいたいって慣用句を考えた人はきっと同じような気持ちだったんでしょうね」
「ついこの間は、娘の参観日に行ったりなんかしましてね。とても可愛かったです。いつか親もとを離れて行ってしまうと思うともう今から寂しいものです。妻は妻でまた苦労人でしてね。十五の時に母に先立てれてしまってからというもの、兄弟二人のために家事なんかをやったりして母親の代わりになろうとしたそうです。いやまあほんと、頭が上がらないというか尊敬の念に尽きるというものですね」
青年は時々相槌を打ちながら、男の話を聞いていた。唐突な惚気話に緊張を抜かれてしまう。それを察知したかのように老人は続ける。
「すこし驚かれましたか。なんてことはない話ですが、これをいつも話すようにしているんです。知らない場所で知らない人に突然付いてこいなんて言われても、不安なだけですからね。少しは私という人間を知ってもらってもらえればと思って始めたんです」
「そうなんですか。確かにそういった話を聞ければ人間味が増していいかもしれませんね」
気が緩んでしまったのだろう。青年がしまったと思った時には、時すでに遅しだった。つい口を滑らせてしまい、怒らせてしまったかと思ったが、予想とは裏腹に男は口を開けて笑った。
「それじゃあまるで私が人間ではないみたいな言い草じゃないですか。いやまあ、私の話が好評ならよかったです。そのへんはまた後ほどですね。私もお話ししたい気持ちは山々なんですけどねえ」
男の笑顔はスッと消え、厳かな顔になる。前を見据えて静かに言った。
「全てが終われば必ずお話しすると約束します」
男の顔は先ほどと同様の仕事人の顔となるが、優しさが無くなったわけではなく、そこには種類の違う優しさを感じ取れる。その証にこちらを見てニコリとした。
「さて、引き続き頑張っていきましょうか」
そうですねと答える。またも突っかかりを覚えた青年は、今度は尋ねてみることにした。
「先ほど記憶を思い出すのを頑張ってと仰いましたよね。そして今も同じ言葉を使いました。僕の考えすぎだったら申し訳ないのですが、何か含みを持っているように聞こえる。例えば僕が記憶を思い出すことに何かしらの困難があるとか。ただ思い出すだけではないんですか?」
「聡いお方ですね。故意ではありませんが、確かにその通りです。初めにも言いましたが今回はいろいろとイレギュラーだ。あなたの記憶がないこと、記憶を取り戻すのには重大な意味があること、全てはひとつの点で繋がっています」
「僕の記憶に重要な意味があることは理解しました。しかし、これ以上思い出すことはできないし、僕からできることもありません」
そう言うと青年は足を止めてしまった。
「なんでもいいんです。趣味とか普段の生活とか…」
何も言えない青年に老人は行き詰ってしまった。沈黙が廊下に満ちる。一か八かの覚悟を決めた老人がくっついた唇を開いた。
「私はどうしてもあなたに自分の力で思い出して欲しかった。きっとそうしないと前には行けないから。しかし行き詰まってしまっては仕方がありません。重大なヒントをお教えしましょう。賢いあなたならきっと辿り着ける。…あなたの記憶がないのはいわゆる逆行性健忘と言われる状態だからです。そしてその原因は脳炎や低酸素性脳症など他に…脳に対する大きな衝撃、脳外傷です。思い出せますか?」
「逆行性健忘…脳に対する大きな外傷…」
「深夜のことです。あなたは突発的に歩き始めた」
「夜…歩いて」
「そうして大きな建物に着きました」
「歩いて着いたのは…学校?」
「そこであなたは無謀にも」
「パイプを伝って登った」
「そして、残念ながら事は為されました」
「僕は…自殺したのか?」
次の瞬間、鮮明に映像が流れた。今度はよりはっきりと。人間の花火。目の前の視界に脳内の映像が混ざり合ってゆく。最初に目眩が起き、次第に呼吸が荒くなる。脳への酸素が足りていないのは明らかだった。先ほどとは比にならない、激しい過呼吸だった。
苦しい。息ができない。言葉が出ない。
青年は必死に空気を貪った。体は痛みを思い出し、体の中で沸騰したように熱い血液が体を巡っていた。すると今度は冷えるような感覚が襲う。脳みそが虚ろになってゆき、次の瞬間青年はその場に倒れた。
目が覚めて真っ先に視界に入ってきたのは白く無機質な天井だった。どうやらベッドの上で横になっているらしい。自身の上には肌触りの良い白い毛布がかけてあった。
「目が覚めましたか?」
音に反射し横を向くと、そこには木製の椅子に老人が座っている。手には本を握っているようだ。ベッドのすぐ横の机の上には古びたラジカセと青色の分厚いファイルが置いてあり、ラジカセからバイオリンを主旋律とするクラシックが流れていた。
「体調の方も大事は無いようですね。よかったです」
青年に気づいた老人は本を机に置き、ラジカセを停止した。
青年の意識がゆっくりと覚醒してくる。それと同時に倒れる前の自分の記憶も湧いてくるのだった。
「僕は自殺だったんですね」
青年は天井を見たままぼそりと言った。それが話しかけたものなのか、はたまた空に向かって放たれたものなのか、男にはわからなかった。男にはわからなかったが、わからなかったからこそ自分の意思で言わなければという責任感に駆られた。
「ふむ。そうですね。これは持論ですが、私は死には良いも悪いもないと思います。確かにキリスト教では自殺が悪だという思想もありますが、では交通事故にあいそうな子供を自ら望んで庇って死んだのなら、その死はどちらなのでしょうか?大量殺戮者を正義もってして殺した場合はその死はなの善でしょうか?結局はみな死んでしまうというのに、いずれ死ぬ者がいずれ死ぬものを助け、生きながらえさせたとして、そこに根源的な善が発生するのでしょうか?死に良いも悪いも、重いも軽いもないと私は思います」
「ありがとう」
「そう返すのですね。本当に聡い方だ」
「思い出したよ。死ぬ前の僕は空っぽだったんだ。思い出に、あの夏に囚われていた。見ず知らずの人にあの子を重ねてしまうほどに擦り切れていた。そんな自分が嫌で…」
老人はこうなることをわかっていた。わかっていたからこそ、助けたいと思ったのだ。自分から会話を始めて流れを断ち切る。
「あなたの質問にお答えしましょう、私が誰なのか。ここはあなた方が言うところのいわゆるあの世で、私は死人の対応、案内をする仕事をしている者です」
「あの世ですか。自分の目で見ていてもにわかには信じられませんね」
「皆そう仰います。ですがあの世だとか死後というのは名前だけにすぎません。私たちは天使などではなく一人の人間で、あなた方と同じように共同体を作り、社会を形成し、ご飯を食べてゆくために働いているのですよ。あなた方と同じです。あなた方が私たちを認識できなかったように、自分たちよりも高次な存在のことは知りません。もちろん自分たちが死んだあとのことも。だからこそ神様だとかを信仰する人も居ます。性質は違えど本質は同じということです。まるで陽光と月光のように」
青年は黙ってただ話を聞いていた。老人は時々合う視線から冷たい落ち着きを感じ取っていた。
「思いのほか冷静なんですね」
「驚くほどのエネルギーがないだけですよ」
青年はハハハとどうしようもなく笑った。老人は思わず青年から目をそらしてしまう。その様子があまりにも見兼ねたからだ。
突然、どこからともなく小粋なポップスが流れ始めた。短いフレーズだったが、ここまで人間の声しか聞いていなかった青年の耳は驚いてしまう。
「もうこんな時間ですか。そろそろ決めなければいけませんね。ふふふ。突然の音楽に驚きましたか?これは終業のチャイムです。今時のこんなチャイムで終業を知らせるなんて、まるで学校みたいですね」
「終業ですか」
雲行きを怪しませる単語が青年の不安を煽る。このあとこの老人はいなくなってしまうのだろうか。だとしたら僕はどうなるのだろうか。そんなことが頭をよぎる。見透かした老人はどうにか覆い被せようと試みた。
「讃美歌でも流れてると思いましたか?ふふふ、讃美歌なんて流行りませんよ。きっと神様なんていないんですから。流行るとすればそれはおそらく人間の心中にでしょうね。人間は神様の中に宿ったりなんかして。きっとあの世ではロックロールでも流れているんでしょうねえ。ああ、君から見たらここがあの世でしたね」
「いろいろと考えをお話ししてくれるんですね」と青年がほくそ笑む。
「お話しすると約束しましたからね」
すこし嬉しそうに老人は答えると、改まって青年をまっすぐ見つめる。その面持ちは神妙で、その様子は青年の心をこわばらせた。
「傷心のところ申し訳ありませんが、私はあなたに選択を迫らなくてはならない」
普段ならこの台詞の後はあれやこれやと話をする場面だ。その人のことを一番深く知ることができるこの会話が老人は好きだった。ある人は真剣だったり、ある人は楽しげだったりする。けれど、今回はそうはいかないことは明白だった。老人は一瞬、言い淀んでしまう。
「選択肢は二つです。一つはこのままこの世界に残り、この世界の住人として生きてゆく未来です。そしてもう一つは、記憶を消して、元の世界に戻る未来です。前者の場合は先ほどお話しした通り、多少の違いはあれど大まかには今までのような生活を送ることになると思ってください。一方、後者の方はあなたが死ぬまで生きていた世界を今持っている記憶を無くしてもう一度生まれ落ちることになります」
青年が黙りこくってしまうことなど老人にはわかっていた。しかし、死人の今後を管理する立場の人間として決めさせなければならない。この決断が残酷になることは、彼が死んだのに死ねなかった地点から約束されていた。老人は彼がこちらに来る前からそのことを予見していたのだ。
「おじいさん」
青年は深く息を吸ってから尋ねる。いまの青年の口からどんな言葉が出てくるか予想がつかない老人は、少し身構えてしまう。
「赤ん坊が生まれてくる時って泣いてるじゃないですか。あれってどうゆう泣きなんでしょうね。怒りなら悔しさならしょっぱい、喜びや悲しみなら甘いって具合に涙の味が変化するからそれで少しはわかるのに、赤ん坊は涙を流さずに泣くからわからないですよね」
老人は答えられなかった。そんなものわかりはしない。赤ん坊が生まれたくて生まれているかだとか、どんな感情を持ってこの世に生を授かるかなんてことは誰にもわからない。しかし、青年はまるでその問いに対してはっきりと答えを持っているかのように思えてならなかった。直接それを言わずに老人に問いかけて、無理やりにその答えを押し付けているかのようにさえも思えた。
「私にはわかりかねます。しかし、死ぬときの感情はきっとみんな死にたくない、ではないでしょうか。あなたはそうは思いませんでしたか?」
「…正直に言うと、思いました。目の前に地面が来た瞬間に決意はあまりにも簡単に揺らいだ。こんなことしなければと思った。その時は思ったけれど、今はそうは思わない。こうゆうときはしなければよかったなんて思わないようにしてます。そう思ってしまうと過去の僕が可哀想だ」
「そうですね。過去の苦しみを軽んじるというのは時にその人への冒涜になる。それが死にたいほどの強い感情であればなおのこと。きっと過去のあなたを肯定してあげ得るのは今のあなただけなんでしょう。過去のあなたを慰めてあげられるのは今のあなたで、今のあなたを慰めるのは未来のあなただ。そして、未来のあなたを決めるのは今のあなただ。だからあなたには真に良いと思えるような選択をしてほしい」
「けれど僕にはそんなことはできない。僕は空っぽなんだから」
そう言われた老人は心の中でそんなことはないと言う。だがそれが喉を通って言葉になるよりも前に、頭の中である人物が閃いていた。それならば彼が空っぽでないことを証明させられる。
老人は机に置いてあるファイルをすぐさま手に取る。少しの間何ページかめくり資料を確かめた。
「このファイルにはここに来た方々の前世の概要があります。もちろんあなたの資料も拝見させていただきました。あなたは空っぽではないことはすでに証明されているではありませんか。少し気になる名前がありましてね。私もこの方には会ったのです」
そう言って、青年にファイルを手渡した。ファイルの中の資料には死亡時の年齢や住所などと共に、縦四ミリ横三ミリの顔写真がついていた。それをみた青年は目を見開く。ファイルを持つ手は小刻みに震えており、口からは言葉がすらすらと出ない。
「どうしてこの子が?」
「ご存じの通りですよ。その子も死んで、そして彼女も来たんですよ。ここに」
息が詰まって、言葉を出させずに2いる青年に老人は優しく語りかける。
「彼女は私に言いました。会わなければならない人がいると。そう言って元の世界に戻られました」
顔写真に釘付けだった顔をばっとあげ、老人を見る。その目には涙が滲んでいた。その目は本当にあの子がと確認を迫っている。
「もうどちらか明白なのではないでしょうか?」
青年は静かに、しかしはっきりと言った。
「はい」
「では行きましょうか」
老人はそう言うと部屋の扉を開けた。やはり扉の先は真っ白に続く廊下であった。青年はまた長い廊下を歩かされるのかと思ったが、今度はそうは行かなかった。何度か丁字路を曲がると、徐に扉を開ける。その部屋に入ると、中は小さな部屋で、すぐ目の前にまた木製の扉があった。その黄金色が真っ白な空間の中で存在感を放っている。
「この扉です。種明かしではないですが、あの選択が決まるまで出られないようになっているんです。業務とはいえ失礼しました」
「いえ。こちらこそお手数おかけしました。ほんとにいろいろ」
「最後の確認です。本当にこちらでよろしいですね」
「空っぽが埋まったわけではないし、これが正解かもわからない。だけど、こっちが良いと僕は思います」
返事の代わりに、老人は笑みを送った。
「では行ってしまう前に一つアドバイス、というよりもただの老人のたわ言
だと思って聞いてほしいのですが、人生を豊かにしてくれるのは創作だと思っています。もちろんそれが全てではありませんが、それでも私はあなたにぜひ創作活動をなさってほしい。芸術の本質はナンセンスだ。音でも文字でも絵の具でも構いません。とにかく自分から新たな何かを生み出す行為をあなたにしてほしいと思います。きっと君に合ってる」
「ありがとう」
青年は扉を開ける。光あふれたその先に、青年は一歩踏みしめた。その後ろには優しい笑顔で手を振る老人がいた。