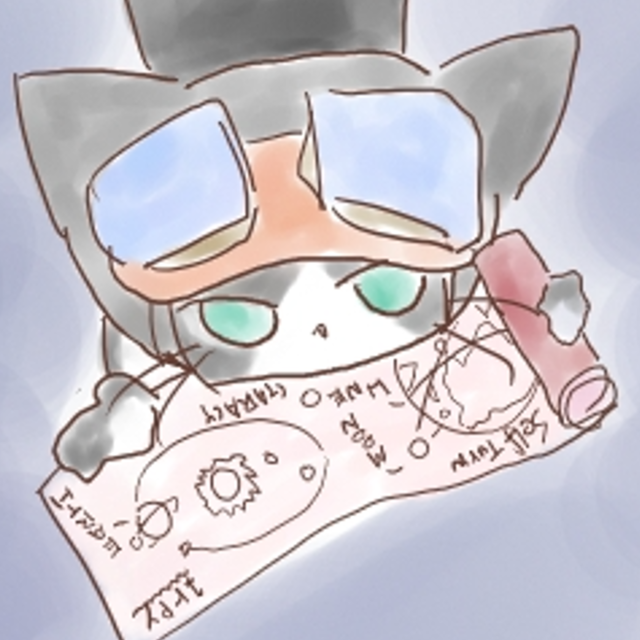第2話 悪魔
文字数 10,505文字
ある日、家に帰る途中で、犬に襲われている悪魔を助けた。
どうやらその悪魔、とても腹が減っていたようで、ジュリーの昼食をせしめようと、電柱の影に隠れてその機会を窺っていたのだ。ほどなくして、悪魔はそれを実行に移したのだが、念願むなしく、ジュリーに返り討ちに合い、小道の袋小路へと追い詰められていた。
近頃の悪魔は発育があまりよくないのか、それとも元来そういうものなのか、怯える悪魔の背丈はジュリーとあまり変わらない。ちなみに、ジュリーというのは近所の鳴海さん宅に五年あまり住まわっている柴犬である。番犬としての役割をなにひとつ果たすことなく、睡眠と散歩と食事を繰り返すだけの優雅な日々を送っている、ある境遇の者からすれば非常に羨むべき犬だ。鳴海さん宅は比較的に裕福な家柄なので、ジュリーに与えられる食事も、その辺りの同胞に比べれば、遙かに質のよいものである。ときに、私の昼食なぞより旨そうな姿形をした食事が与えられていることもあるのだから、こうして悪魔がジュリーの食事に気を惹かれたのも無理はない。
ただ、悪魔は相手を見定める力に欠けていた。普段は、散歩に行くのでさえも億劫がるジュリーであり、おそらくはその悪魔も、鳴海さん宅の軒下でのっそりとうたた寝をしているジュリーを見て、これならい行けると考えたのだろう。だが、その考えは間違いである。人と同じように、犬も見かけにはよらないとういことを覚えておくべきであった。どんなに奇抜な格好をした人間が家を訪ねて来ても、どんなに素晴らしい毛並みの同胞が目の前を通っても、まるで関心を示さず、緩慢を絵に描いたように行動するジュリーであるが、こと食事に関しては態度が一変する。その執着には目を見張るものがあり、三度の食事が滞るものなら、有事を知らせるサイレンの如く吠え叫び、途中で餌皿を下げられようものなら、悪鬼の如き面構えで鋭利な牙を覗かせるのだ。
そんなジュリーが、目の前で自分の食事が奪われそうになるのを見て、何事もなく居眠りを続けられるわけがない。悪魔が餌皿に近づくのを見るや否、野生を取り戻したかのように吠え立て、追い回し、ついには袋小路へ追い詰めたのである。ともかく、そうした理由で、悪魔はジュリーに襲われていたのだ。
私はといえば、話のネタになるかと思い、遠目に様子を窺っていたのだが、悪魔があまりにも怯えた表情をしていたもので、やがて不憫に思うようになって、窮地を救ってやることにした。仕事先でもらった饅頭をバッグから取り出し、指を鳴らしてジュリーの気を引く。いぶかしげに振り返るジュリーの目は、私のことなどほんの一瞬気に留めただけで瞬く間に関心の外へ追い出し、すぐに饅頭の一点に向けられた。それまでは低い唸り声で悪魔を威嚇していたジュリーだが、途端に鳴き声の音程がひとつ上がった。
手に乗せた饅頭を差し出すよりも早く、韋駄天のごとき速さでジュリーが駆け寄ってくる。もはや悪魔のことなど眼中にはない。ついでに私のことも眼中にはない。ジュリーに饅頭を食わせてやりながら、私は悪魔に視線を投げて、いまのうちに逃げるよう合図を送った。悪魔もその意図を理解してくれたようで、ジュリーとはできるだけ距離を取りながら通りのほうへ駆けていった。途中、ジュリーが気づかないように、悪魔の足取りの先へ小さな砂糖菓子を放ってやると、少しだけ戸惑ったようだったが、悪魔はすぐに砂糖菓子を抱え上げ、私のほうに軽く礼をして、また駆けていった。
別段、大した人助けをしたわけではない。しかし、たまにこうした気まぐれに興じるのも、道すがらの気分をよくするものである。
気分がよいのは、空が青いからなのか。それとも、気分がよいから、空が青く見えるのか。そんなことを考えながら、私は帰途についた。懸想する女性へ手紙をしたためる程のことでもない、いつもの昼下がりの出来事であった。
◇
さて。家に帰ると、先ほどの悪魔が私を待っていた。鳴海さん宅のように立派な軒下があるわけではなく、どこにでもありそうな集合住宅に私は住んでいるので、住民が共用する階段に、いくらか居心地の悪そうな面持ちで悪魔は座っていた。いたずらに人前に姿を晒す趣味はないようで、人の往来を気にしながら通りを眺めていたようだ。
私の姿を認めると、悪魔の表情が明るくなった。立ち上がり、鞠のように飛び跳ねながら、こちらへ近づいてくる。心なしか、先ほどよりも二割ほど体格が大きくなっているように見えた。悪魔というのは、体重の変化が見た目に現れやすいものらしい。悪魔の身体が床を蹴る度に、砂の中で鈴を鳴らすような不思議な音が聞こえた。
「一見するとただの柴犬だったのにね。まさかケルベロスの末裔と会うことになるとは思わなかったよ。でも、あいつも時間の規律というものを知らない。本来とは違う時間軸のなかで姿を晒すことって、結局は自分を歪ませちゃうのに。それとも、僕の中に秘めた巨大な力を感じ取って、規律を破ってでも本性をさらけ出さなきゃいけないって悟ったのかな」
ケルベロスとは、地中海に近い国だったかの神話において地獄の番犬と称される三つ首の獣のことである。番犬としての役割など遠に忘れているあの柴犬が、そんな大層なものの末裔だとは、なかなか想像に難かった。それとも、地獄という場所は不審者など無縁であり、番犬が必要ないほどに平穏なのかもしれない。
(血統書を見ればよいか)
心の中で、今度鳴海さんに頼んで血統書を見せてもらおうと算段した。ペットショップのスタッフに、地獄の知り合いがいるのかは知らないが。
「でも、あいつにも運があったよね。僕が少しだけでも普段の力を出す前に、君が現れて戦いの場が流れたんだから」
私の目の前で跳ねながら悪魔は話し続けた。堅苦しい話の内容とは違い、相変わらず表情は明るい。あふれ出る好意を押さえきれないでいるといった様子だ。砂糖菓子がよほど旨かったのだろうか。よく見ると、口の周りに砂糖の粒がついている。
「君が姿を現すのがもう少し遅れたらどうなっていたのか、あいつは真剣に考えるべきだよ。あのとっても美味しそうな饅頭を食べ終わった後にでもね」
ジュリーと同様、悪魔にとっても饅頭とは魅力的な供物であると見えた。ただ、饅頭はジュリーに渡したのが最後である。期待に応えられず、どうしようかと思案していると、悪魔が弁解してきた。
「ああ、気にしなくていいからね。砂糖のお菓子だって、とっても美味しかったよ。それに、こうして君を待っていたのは、お替わりをもらうためじゃない。別の理由なんだよ」
そう言って、悪魔は階段の手すりに着地した。それでも頭の高さは私の胸くらいにしかならなかったので、見上げるような体勢だ。姿勢を正して、深呼吸して、最後に口元を拭って、古くからの作法に従いながら悪魔は言った。
「助けてくれたお礼に、君の望みをひとつだけ叶えてあげよう」
「助けてくれたということは、やはりあれは窮地だったのだな」などと野暮なことは返さずに、悪魔に続きを促した。
「世界を変えてしまうなんてことはできないけれど、君が望むものなら、なんだって与えることはできる。おそらくは、君の一生のうちに一度あるかないかといった、とっても貴重な場面だよ。後悔のないようにしっかり考えてね」
突然の申し出に、私は面食らってしまった。犬に襲われている悪魔を助けただけで、このような礼を受け取ることになるとは。これは、後でジュリーにも礼を言っておかなければならない。手土産には、今日のものより上等な饅頭を持っていこう。
ただ、いくらか気になることもあった。これまであまり考えてはいなかったのだが、そうはいっても目の前で表情を輝かせる小さな生き物は悪魔なのだ。神話や物語にしか聞いたことはなく、実際にそうした経験を持つ知人がいるわけではないのだが、悪魔との取引というのは相応の対価を求められるものと相場が決まっている。よもや砂糖菓子ひとつが、すべての望みの対価となるはずもない。
「用心深さは想像から君を守るけど、可能性の芽は摘んでしまうものだよ」
私の心情を察して悪魔は言った。
逡巡を戒める発言であるのだが、しかし、咎めるような表情を作ることはない。むしろ、同情の念を持って私の顔を見上げていた。
「でも、僕たちからの誘いに用心深くなるのも、最近じゃ仕方ないかなと思っているんだ。だって、君たち人間は、同じ人間に対しても用心深くしていなきゃいけないんだろう? 騙されないように、奪われないように、なにか裏があるんじゃないか、なにか悪いことに巻き込まれるんじゃないか、なんてね。それなのに、僕たち悪魔からの都合のよい誘いなんて、そう簡単に信じられるわけないよね」
階段の手すりのうえで、悪魔は宙返りをした。すると、どこから取り出したのか、着地した悪魔の手の中には、一枚の紙が現れていた。聞けば、それは契約書なのだという。悪魔の誘いを受けるための契約書だ。
悪魔は笑顔を作って、私に見えるように契約書を広げてみせた。
「僕が君の望みを叶える代わりに、僕が君から求めるものは、ここに書かれているとおりだよ。以前は、こんな契約書なんて用意せずに、口頭での確認だけだったり、ときには条件なんて後回しで望みを叶えてしまうこともあったんだけど、さっきも言ったように、君たち人間がずいぶん用心深くなってしまったからね。あとあとのトラブルを防ぐためにも、いまはこうして先に契約内容を確認してもらっているんだ。今回は助けてくれたお礼でもあるからね。特別に、この条件は半分におまけしておいてあげるから。心配せずに、望みを言ってくれていいよ」
悪魔も律儀になったものだと感心した。社会の変化や考え方の変化に適応して、行動や仕事の進め方を変えていくのは人間だけではなかったのだ。世間の変化などお構いなしに日々を過ごすジュリーのことを考えると、この小さな悪魔がとても立派な人物のように思え、私は先入観から抱いていた印象を詫び、契約書に目を通した。
そして、契約書の中のひとつの条件に目を留めて――、
(これは……)
目の前で笑顔を浮かべているのは、やはり悪魔なのだと、再認識した。
「どう? 悪くない取引だと思うよ」
悪魔が笑った。私が指で示した項目は、「半分におまけしてあげる」と悪魔が言った条件だった。どこかの物語で聞いたことがあるような条件だ。
『望みを叶える代償に、残りの人生の半分を支払うこと』
(まいったな……)
心の中で、私はため息をついた。
「本当なら残りの人生の半分がなくなっちゃうのに、今回だけは、そのさらに半分。四分の一だね。なんてお得なんだろう! 今回は特別だから、他の人に言っちゃダメだよ!」
陽気な悪魔が、手すりの上で飛び跳ねている。
「さぁ、君の望みを聞かせてよ!」
悪魔が目をキラキラと輝かせた。その一方で、私の頭は急速に冷却されていく。日常の中に突然現れた、このあまりに非日常な事態に対して、どのように対処するべきか。
ただ、このとんでもない誘いに、いくらかの興味を惹かれているのも事実であった。どのくらいまでの望みを叶えられるのかはわからないが、それでも、多くのものを対価として支払うのだから、私自身では実現できないような望みでも、悪魔は叶えてくれるのだろう。瓢箪から駒。なんてことのない昼下がりから沸いて出てきた、千載一遇の機会ともいえるのだ。
(さて、どうしたものか)
私は唸った。
残りの人生の半分の、さらに半分である。昨今の平均寿命から考えれば、私もまだ四、五十年ほどは生きるだろう。その四分の一だから、少なく見積もっても十年以上だ。それほどの時間をかけてまで、手に入れたいものがあるのだろうか。真剣に考えれば考えるほど、その答えは浮かんでこなかった。
「どうしてそんなに悩んでいるの?」
そんな私の様子を、悪魔は不安そうな表情で見ていた。
「人生が短くなるのって、そんなに困ってしまうことなのかな? だって、人生って何かを手に入れるために送るものだよね。だったら、手に入るかわからずに時間を過ごすよりも、いくらかの時間と交換してでも確実にそれを手に入れたほうが都合がいいんじゃない?」
悪魔の言い分はもっともである。同時に、納得はしがたい事柄であった。私たち人間は、欲しいものを手に入れることより、生きること自体に価値を見出そうとしている。本当はどちらのほうに大きな価値があるのかは別として。
「まあいいや。でも、少しは心が動かされているんだよね。だったら、まずは望みを言ってみなよ。意外と、自分で言葉にしてしまえば、どちらのほうが本当に大切なのかはわかるものだからさ」
悪魔に促され、私は自分の望みを考えてみることにした。悪魔と契約を結ぶかどうかかは、望みを決めてからでも遅くはない。
しかし、いざ実際に考えてみても、人生をかけてまで望むものは、なかなか思い浮かんでこなかった。こどもの頃は、想像のままに欲しいものを口にして両親を困らせていたような思い出があるが、大人と呼ばれる年代になったいま、欲しいものが心の中からなくなっていたのだ。
私は――あるいは私たち大人は――、生きることに価値を見出すことで、自分の中の欲求を抑えようとしている。欲求に突き動かされるのを避けようとしている。おそらくは、それが達成できかったときの反動が怖いから。欲しいものという存在を遠のけようとしているのだ。
「手に入れたいものがなにものないのに、そんなに長い人生を残すことに意味があるとは思えないけど。人間って、いつも不思議な言い訳を使って、自分の生き方を決めつけてしまおうとするよね」
悪魔は飛び跳ねるのをやめて、少しつまらなさそうにため息をついた。
「生きることと、ただ生きていることは、似ているようでまったく違うよ」
契約書を小さく折りたたんで、悪魔はまた宙返りをした。着地する頃には契約書はどこかに消えていた。
失望を隠せずにいる悪魔の身体が、はじめに見かけたときのように、また小さくなっていることに気がついた。私がそれを指摘すると、悪魔が理由を教えてくれた。
「君たち人間が、何も望まなくなってしまったからだよ」
意外な答えに、私は驚いた。
「饅頭や砂糖菓子だって大好きだけど、そんなものだけじゃ、僕たちはエネルギーを貯められないんだ。僕たちにとって本当のエネルギーになるのは、君たち人間の寿命なんだよ。さっきの契約みたいに、君たちの望みを叶えてあげる代わりに、いくらかの命を分けてもらって、それで僕たちは生きているんだ」
私は、どうして悪魔の身体が小さいのかを理解した。
「そうだね。欲しいものがないんだから、僕たちの誘いなんて誰も乗らなくなったんだ。そりゃ、普段から小さな望みくらいあるのだろうけど、でも、人生の多くの部分をかけてまで手に入れたいかと尋ねられると、みんな簡単に手を引っ込めてしまう。そんな、一枚の羽のように軽い望みだけしか持たなくなったから、僕たちもエネルギーを手に入れられなくて、こんなに小さくなってしまったんだよ」
社会不況は人間の世界だけのことかと思っていたが、近頃は、悪魔も大変なのだ。だから、せめてもの食いつなぎに、ジュリーの食事をせしめるなどという努力をしなければならないのだろう。
なんだか自身のことを不甲斐なく思い、私は悪魔に詫びた。すると、悪魔は少しだけ驚いた表情を見せた。
「別に君が謝ることじゃないさ。それに、君は僕を助けてくれたんだから、十分に感謝しているよ!」
屈託のない笑顔が閃いた。悪魔というと、とても意地悪で、人を堕落させるような誘いを渡してくるものだと思っていたが、そんなことはなかった。むしろ、しっかりとルールに則って、私たち人間のことまで考えて、精一杯生きているのだと感じた。
◇
それから私は、しばらくの間、悪魔と話した。近所の和菓子屋で旨い菓子を仕入れ、缶に入った茶を二つ買い、近くの公園のベンチに座って、陽がほとんど見えなく頃まで話し込んだ。
聞けば、悪魔はこの国を去ろうかと悩んでいるのだという。私と同じように、この国の人々は心の底から望むものをなくしている。この状況は、悪魔にとっては食い扶持が見つからないということなのだ。だから、まだ人々が強い望みを持って生きているような、比較的に発展の程度が小さな国へ移り住もうかと考えているのだ。
「僕はね、この国が好きなんだ。季節によって違う花が咲いて、それに合わせて生き物の表情も変わっていく。海の上に浮かんだ小さな国だし、物や資源が豊富だってこともないけれど、でも、ほかの国からの影響をあまり受けずに、自分たちの考え方や様式を残したままでいままで続いている。僕たち悪魔の誘いって、ときには勘違いされるけど、人間のためでもあるんだよ。僕たちだって世界がよくなってほしいと思っているんだ。そのために、僕たちに出来る方法で、人間に力を貸してあげているんだよ」
変わったのは、なにも望まなくなってしまった人間なのだ。私たちは、変化の果てを見たと勘違いしてしまい、あらゆる事柄を見聞きしていると思い上がり、自分から望みを手放してしまったのだ。
「君が、最後だったんだ。助けてくれたから、というのももちろんあったんだけど、せめて望みの代わりにもらう命を半分におまけして、それでもなにも望もうとしないんだったら、もうこの国で相手を見つけるのは諦めて、他の国へ出て行こうと決めていたんだ。だから、君と知り合えて嬉しいけれど、これでもうお別れだよ」
菓子と茶を残らず食べて、悪魔はベンチの上で立ち上がった。
「美味しかったよ。ありがとう」
そう言って、悪魔はベンチから飛び降りた。振り返って私の方へ手を振り、公園を後にした。私は、後ろ姿が見えなくなるまで、ずっと悪魔を見送っていた。
それは、なんとも不思議な気分だった。心の中から抜け落ちた大切なものが、目の前の土の地面を転がって、どこか遠くへ消えていこうとしているようだった。小さなその固まりは、心から離れて行けば行くほど小さく縮んでゆき、やがては目に見えないようになって、そして消えてしまう。
それは、生まれてからこれまでに、何度となく感じてきた気分だった。
(ああ、そうだ。思い出した……)
私はベンチを飛び出し、悪魔を追った。視界の先の方で風景に溶けてしまおうといる悪魔の後ろ姿を見失わないように、必死で目をこらしながら、力の限りに駆けた。その様子が珍しかったのか、公園中の視線が私へと集まった。物珍しそうなものを見つけた視線は、しばし私の行動を眺めて、またすぐに興味をなくして逸らされる。
「もしかして、お土産を渡すのを忘れていた?」
公園の出口で、ようやく悪魔に追いついた。悪魔は、少しだけ驚いたような表情で、いたずらっぽく言った。
私は深く息をついて、心を落ち着けた。そして、言った。心の奥深くに眠っており、知らず心から零れ落ちそうになっていた大切な思いを。長い間、果てることなく抱いてきた夢を。口に出すのが怖く、意識に上げることを押さえていた、人生を掛けるにも値する、私の望みを。
『私は作家になりたい。物語の力で世界を変えたい。それは、叶えられるのか?』
自分で言っているにも関わらず、その声は、まるで音響設備を通して響くかのようにして聞こえた。世界が、私の世界が、その言葉を告げているかのようだった。
私の望みを聞いて、悪魔は笑顔を見せた。
「僕に出来るのは、そのための力を与えるだけだよ。その力をどうやって使うのか、物語を書く力を使って、想像しているような作家になれるかどうかは、君次第だ」
そこで、悪魔は一度言葉を切った。じっと私のことを見つめて、なにかを念じた。
やがて、悪魔は息をついて答えた。
「残念だけど、その望みは叶えられないや」
「――え?」
その答えを聞いて、私は明らかにうろたえてしまった。心の中から零れ落ちたガラスの玉を、ようやくの思いで取り戻したというのに、手にしたときには、粉々に砕けていたのだ。大きな失望が、胸の中に広がった。
だが、そんな私に、優しい口調で、悪魔は言葉の意味を教えてくれた。
「どうしてかと言うとね、僕が与えるまでもなく、君はその力を持っているからだよ」
そんなバカな。
私は、胸を撃たれたように驚いた。自分がずっと望んできたものは、すでに自分の中にあったというのだから。とても信じられることではない。悪魔への信用を揺るがすような答えであったのだが、
(いや、バカなことなんてあるか……)
しかし、その答えが正しいのだということも、頭の隅では納得していた。
私は、自分の力を信じることができず、これまで物語を書くことなどせずに日々を過ごしていたのだ。ただ、作家になりたいという夢を漠然と抱いたままで、しかし、それは奇跡でも起こらない限り実現できないのだと思うことで努力を怠って、日々の中で、なにを強く望むこともなく、こうして時間だけを浪費していたのだ。
なんと、みっともないことだろうか。
「そんな難しい顔をしないでよ。もう大丈夫だって。君は、君の望みを思い出したんだからね」
悪魔は、とても嬉しそうに笑った。子どもが見せる笑顔と同じ笑顔を、悪魔は作って見せた。それを見て、私も笑顔を作った。近頃は作ったことのなかったような、心からわき出てくる、将来へ向けた明るい笑顔だ。
その笑顔を返しながら、私は悪魔に感謝の言葉を贈った。
◇
それから数日が経った。相も変わらず、どんなに怪しい人物が近づいて来ようとも、ジュリーは目覚めることなくうたた寝に興じている。仕事帰り、そんなジュリーを横目に眺めつつ、私は足早に自宅へと戻った。普段は、そこで一日の活動を終わらせて、残りの時間は休憩に当てていたのだが、この日の私は違った。いくらか着慣れてきたスーツを脱いで、普段着に着替え、ブリーフケースとは違うバッグを持って、再び外に出た。そんな私の姿を、重そうな瞼を少しだけ上げてジュリーが見ていたが、やがて興味をなくし、また眠りの世界へ戻っていった。
私は、物語を書くための道具を持ち、近所の喫茶店へ向かった。途中、頭の上のほうから私を呼ぶ声が聞こえたので、そちらを向いた。鳴海さん宅の垣根の上で、私の様子を眺めている悪魔がいた。
「今日は随分と早かったね。仕事は大丈夫なの?」
私が歩くのに合わせて、悪魔も垣根の上を駆けてくる。そんな悪魔に、心配には及ばない旨を伝えた。不思議なもので、毎日の時間の中にやりたいことが増えたとしても、それを考えているうちは時間が足りないように思えるものだが、いざ実行に移してさえしまえば、時間が足りなくなることなどなかった。むしろ、多くのやりたいことを行なうために、日々の密度が高くなり、充実した時間さえ送れるようになるのだ。
「この分なら、君の望みが叶うのも、そう遠くはない未来だね」
僕の肩に飛び移って、悪魔が囁いた。公園での一件以来、悪魔はこうして、僕の近くに住むようになっていた。実はあの別れの後で、私は悪魔をもう一度呼び止め、別のことを悪魔に望んでいたのだ。それは、私が作家になるという望みを叶えるまで悪魔にそばにいてほしい、というものだった。
いつか望みが叶うのかはわからないし、たとえ叶ったとしても悪魔に代償を支払うのは、その後のことである。こうした不確実な契約であったにも関わらず、悪魔はその望みを叶えてくれると言った。それまでの間は、人々の小さな望みを叶えたり、砂糖菓子や饅頭を食べて過ごせばいいのだと悪魔は言った。
「大切なのは、本当に叶えたいと思う望みを誤魔化さないで、そのとおりに生きることだよ」
それは自分にも当てはまることなんだと、悪魔は笑った。
その日、私は喫茶店にこもって閉店時間になるまで物語を書いた。悪魔が店の飼い猫と喧嘩を始めたときにはひやりとしたが、店主には悪魔の姿が見えていないようなので、面倒ごとにはならなかった。
私の書く物語は、決して順調に先へ進むこともないし、多くの人が読んでみんなが面白いと思うものでもない。これまで長い間、心の中の望みを遠ざけていたのだから、すぐに満足のいくものができなくてもしかたのないことだ。だけど、こうして悪魔とともに望みを叶えようと努力する時間は、とても清々しいものだった。
「この国のみんなが、君みたいに自分の望みを思い出すことってあるのかな?」
帰り道、悪魔が聞いてきた。
私は、それに答えた。私はそのために物語を書いているのだ、と。
「もしそうなったら、よその国へ行ってしまった友達を呼び戻せるね!」
期待に目を輝かせて、悪魔は言った。
◇
こうして、私と悪魔との共同生活が始まった。悪魔との契約は特別な形態で結んでいるため、常に悪魔が私のそばにいるということはなかった。悪魔は自分が行きたいところへ出歩き、いつも変な知人を連れて帰ってきた。そうした知人たちは、これまで私が目を向けていなかっただけで、日常のあらゆる場所に棲んでいるのだと言った。彼らはとてもユニークな習性を持っており、それはときに問題を引き起こすことともなったが、そうした彼らとの出会いは刺激のある体験となり、私の望みを後押しするものであった。
きっと、悪魔は、私の望みを叶えるために、自分にできることを考えて実行しているのだろう。悪魔も、人の望みを叶えるために、努力をしているのだ。そうした悪魔の姿こそが、私にとってはなによりの刺激であった。
さて。今日も仕事から帰ってくると、家の前で悪魔が待っていた。隣に立っている不思議な生き物に見覚えはなかったけれど、その出会いは楽しい物語を予感させるものであった。
私が「ただいま」と言うと、悪魔は「おかえり」と応えてくれた。
どうやらその悪魔、とても腹が減っていたようで、ジュリーの昼食をせしめようと、電柱の影に隠れてその機会を窺っていたのだ。ほどなくして、悪魔はそれを実行に移したのだが、念願むなしく、ジュリーに返り討ちに合い、小道の袋小路へと追い詰められていた。
近頃の悪魔は発育があまりよくないのか、それとも元来そういうものなのか、怯える悪魔の背丈はジュリーとあまり変わらない。ちなみに、ジュリーというのは近所の鳴海さん宅に五年あまり住まわっている柴犬である。番犬としての役割をなにひとつ果たすことなく、睡眠と散歩と食事を繰り返すだけの優雅な日々を送っている、ある境遇の者からすれば非常に羨むべき犬だ。鳴海さん宅は比較的に裕福な家柄なので、ジュリーに与えられる食事も、その辺りの同胞に比べれば、遙かに質のよいものである。ときに、私の昼食なぞより旨そうな姿形をした食事が与えられていることもあるのだから、こうして悪魔がジュリーの食事に気を惹かれたのも無理はない。
ただ、悪魔は相手を見定める力に欠けていた。普段は、散歩に行くのでさえも億劫がるジュリーであり、おそらくはその悪魔も、鳴海さん宅の軒下でのっそりとうたた寝をしているジュリーを見て、これならい行けると考えたのだろう。だが、その考えは間違いである。人と同じように、犬も見かけにはよらないとういことを覚えておくべきであった。どんなに奇抜な格好をした人間が家を訪ねて来ても、どんなに素晴らしい毛並みの同胞が目の前を通っても、まるで関心を示さず、緩慢を絵に描いたように行動するジュリーであるが、こと食事に関しては態度が一変する。その執着には目を見張るものがあり、三度の食事が滞るものなら、有事を知らせるサイレンの如く吠え叫び、途中で餌皿を下げられようものなら、悪鬼の如き面構えで鋭利な牙を覗かせるのだ。
そんなジュリーが、目の前で自分の食事が奪われそうになるのを見て、何事もなく居眠りを続けられるわけがない。悪魔が餌皿に近づくのを見るや否、野生を取り戻したかのように吠え立て、追い回し、ついには袋小路へ追い詰めたのである。ともかく、そうした理由で、悪魔はジュリーに襲われていたのだ。
私はといえば、話のネタになるかと思い、遠目に様子を窺っていたのだが、悪魔があまりにも怯えた表情をしていたもので、やがて不憫に思うようになって、窮地を救ってやることにした。仕事先でもらった饅頭をバッグから取り出し、指を鳴らしてジュリーの気を引く。いぶかしげに振り返るジュリーの目は、私のことなどほんの一瞬気に留めただけで瞬く間に関心の外へ追い出し、すぐに饅頭の一点に向けられた。それまでは低い唸り声で悪魔を威嚇していたジュリーだが、途端に鳴き声の音程がひとつ上がった。
手に乗せた饅頭を差し出すよりも早く、韋駄天のごとき速さでジュリーが駆け寄ってくる。もはや悪魔のことなど眼中にはない。ついでに私のことも眼中にはない。ジュリーに饅頭を食わせてやりながら、私は悪魔に視線を投げて、いまのうちに逃げるよう合図を送った。悪魔もその意図を理解してくれたようで、ジュリーとはできるだけ距離を取りながら通りのほうへ駆けていった。途中、ジュリーが気づかないように、悪魔の足取りの先へ小さな砂糖菓子を放ってやると、少しだけ戸惑ったようだったが、悪魔はすぐに砂糖菓子を抱え上げ、私のほうに軽く礼をして、また駆けていった。
別段、大した人助けをしたわけではない。しかし、たまにこうした気まぐれに興じるのも、道すがらの気分をよくするものである。
気分がよいのは、空が青いからなのか。それとも、気分がよいから、空が青く見えるのか。そんなことを考えながら、私は帰途についた。懸想する女性へ手紙をしたためる程のことでもない、いつもの昼下がりの出来事であった。
◇
さて。家に帰ると、先ほどの悪魔が私を待っていた。鳴海さん宅のように立派な軒下があるわけではなく、どこにでもありそうな集合住宅に私は住んでいるので、住民が共用する階段に、いくらか居心地の悪そうな面持ちで悪魔は座っていた。いたずらに人前に姿を晒す趣味はないようで、人の往来を気にしながら通りを眺めていたようだ。
私の姿を認めると、悪魔の表情が明るくなった。立ち上がり、鞠のように飛び跳ねながら、こちらへ近づいてくる。心なしか、先ほどよりも二割ほど体格が大きくなっているように見えた。悪魔というのは、体重の変化が見た目に現れやすいものらしい。悪魔の身体が床を蹴る度に、砂の中で鈴を鳴らすような不思議な音が聞こえた。
「一見するとただの柴犬だったのにね。まさかケルベロスの末裔と会うことになるとは思わなかったよ。でも、あいつも時間の規律というものを知らない。本来とは違う時間軸のなかで姿を晒すことって、結局は自分を歪ませちゃうのに。それとも、僕の中に秘めた巨大な力を感じ取って、規律を破ってでも本性をさらけ出さなきゃいけないって悟ったのかな」
ケルベロスとは、地中海に近い国だったかの神話において地獄の番犬と称される三つ首の獣のことである。番犬としての役割など遠に忘れているあの柴犬が、そんな大層なものの末裔だとは、なかなか想像に難かった。それとも、地獄という場所は不審者など無縁であり、番犬が必要ないほどに平穏なのかもしれない。
(血統書を見ればよいか)
心の中で、今度鳴海さんに頼んで血統書を見せてもらおうと算段した。ペットショップのスタッフに、地獄の知り合いがいるのかは知らないが。
「でも、あいつにも運があったよね。僕が少しだけでも普段の力を出す前に、君が現れて戦いの場が流れたんだから」
私の目の前で跳ねながら悪魔は話し続けた。堅苦しい話の内容とは違い、相変わらず表情は明るい。あふれ出る好意を押さえきれないでいるといった様子だ。砂糖菓子がよほど旨かったのだろうか。よく見ると、口の周りに砂糖の粒がついている。
「君が姿を現すのがもう少し遅れたらどうなっていたのか、あいつは真剣に考えるべきだよ。あのとっても美味しそうな饅頭を食べ終わった後にでもね」
ジュリーと同様、悪魔にとっても饅頭とは魅力的な供物であると見えた。ただ、饅頭はジュリーに渡したのが最後である。期待に応えられず、どうしようかと思案していると、悪魔が弁解してきた。
「ああ、気にしなくていいからね。砂糖のお菓子だって、とっても美味しかったよ。それに、こうして君を待っていたのは、お替わりをもらうためじゃない。別の理由なんだよ」
そう言って、悪魔は階段の手すりに着地した。それでも頭の高さは私の胸くらいにしかならなかったので、見上げるような体勢だ。姿勢を正して、深呼吸して、最後に口元を拭って、古くからの作法に従いながら悪魔は言った。
「助けてくれたお礼に、君の望みをひとつだけ叶えてあげよう」
「助けてくれたということは、やはりあれは窮地だったのだな」などと野暮なことは返さずに、悪魔に続きを促した。
「世界を変えてしまうなんてことはできないけれど、君が望むものなら、なんだって与えることはできる。おそらくは、君の一生のうちに一度あるかないかといった、とっても貴重な場面だよ。後悔のないようにしっかり考えてね」
突然の申し出に、私は面食らってしまった。犬に襲われている悪魔を助けただけで、このような礼を受け取ることになるとは。これは、後でジュリーにも礼を言っておかなければならない。手土産には、今日のものより上等な饅頭を持っていこう。
ただ、いくらか気になることもあった。これまであまり考えてはいなかったのだが、そうはいっても目の前で表情を輝かせる小さな生き物は悪魔なのだ。神話や物語にしか聞いたことはなく、実際にそうした経験を持つ知人がいるわけではないのだが、悪魔との取引というのは相応の対価を求められるものと相場が決まっている。よもや砂糖菓子ひとつが、すべての望みの対価となるはずもない。
「用心深さは想像から君を守るけど、可能性の芽は摘んでしまうものだよ」
私の心情を察して悪魔は言った。
逡巡を戒める発言であるのだが、しかし、咎めるような表情を作ることはない。むしろ、同情の念を持って私の顔を見上げていた。
「でも、僕たちからの誘いに用心深くなるのも、最近じゃ仕方ないかなと思っているんだ。だって、君たち人間は、同じ人間に対しても用心深くしていなきゃいけないんだろう? 騙されないように、奪われないように、なにか裏があるんじゃないか、なにか悪いことに巻き込まれるんじゃないか、なんてね。それなのに、僕たち悪魔からの都合のよい誘いなんて、そう簡単に信じられるわけないよね」
階段の手すりのうえで、悪魔は宙返りをした。すると、どこから取り出したのか、着地した悪魔の手の中には、一枚の紙が現れていた。聞けば、それは契約書なのだという。悪魔の誘いを受けるための契約書だ。
悪魔は笑顔を作って、私に見えるように契約書を広げてみせた。
「僕が君の望みを叶える代わりに、僕が君から求めるものは、ここに書かれているとおりだよ。以前は、こんな契約書なんて用意せずに、口頭での確認だけだったり、ときには条件なんて後回しで望みを叶えてしまうこともあったんだけど、さっきも言ったように、君たち人間がずいぶん用心深くなってしまったからね。あとあとのトラブルを防ぐためにも、いまはこうして先に契約内容を確認してもらっているんだ。今回は助けてくれたお礼でもあるからね。特別に、この条件は半分におまけしておいてあげるから。心配せずに、望みを言ってくれていいよ」
悪魔も律儀になったものだと感心した。社会の変化や考え方の変化に適応して、行動や仕事の進め方を変えていくのは人間だけではなかったのだ。世間の変化などお構いなしに日々を過ごすジュリーのことを考えると、この小さな悪魔がとても立派な人物のように思え、私は先入観から抱いていた印象を詫び、契約書に目を通した。
そして、契約書の中のひとつの条件に目を留めて――、
(これは……)
目の前で笑顔を浮かべているのは、やはり悪魔なのだと、再認識した。
「どう? 悪くない取引だと思うよ」
悪魔が笑った。私が指で示した項目は、「半分におまけしてあげる」と悪魔が言った条件だった。どこかの物語で聞いたことがあるような条件だ。
『望みを叶える代償に、残りの人生の半分を支払うこと』
(まいったな……)
心の中で、私はため息をついた。
「本当なら残りの人生の半分がなくなっちゃうのに、今回だけは、そのさらに半分。四分の一だね。なんてお得なんだろう! 今回は特別だから、他の人に言っちゃダメだよ!」
陽気な悪魔が、手すりの上で飛び跳ねている。
「さぁ、君の望みを聞かせてよ!」
悪魔が目をキラキラと輝かせた。その一方で、私の頭は急速に冷却されていく。日常の中に突然現れた、このあまりに非日常な事態に対して、どのように対処するべきか。
ただ、このとんでもない誘いに、いくらかの興味を惹かれているのも事実であった。どのくらいまでの望みを叶えられるのかはわからないが、それでも、多くのものを対価として支払うのだから、私自身では実現できないような望みでも、悪魔は叶えてくれるのだろう。瓢箪から駒。なんてことのない昼下がりから沸いて出てきた、千載一遇の機会ともいえるのだ。
(さて、どうしたものか)
私は唸った。
残りの人生の半分の、さらに半分である。昨今の平均寿命から考えれば、私もまだ四、五十年ほどは生きるだろう。その四分の一だから、少なく見積もっても十年以上だ。それほどの時間をかけてまで、手に入れたいものがあるのだろうか。真剣に考えれば考えるほど、その答えは浮かんでこなかった。
「どうしてそんなに悩んでいるの?」
そんな私の様子を、悪魔は不安そうな表情で見ていた。
「人生が短くなるのって、そんなに困ってしまうことなのかな? だって、人生って何かを手に入れるために送るものだよね。だったら、手に入るかわからずに時間を過ごすよりも、いくらかの時間と交換してでも確実にそれを手に入れたほうが都合がいいんじゃない?」
悪魔の言い分はもっともである。同時に、納得はしがたい事柄であった。私たち人間は、欲しいものを手に入れることより、生きること自体に価値を見出そうとしている。本当はどちらのほうに大きな価値があるのかは別として。
「まあいいや。でも、少しは心が動かされているんだよね。だったら、まずは望みを言ってみなよ。意外と、自分で言葉にしてしまえば、どちらのほうが本当に大切なのかはわかるものだからさ」
悪魔に促され、私は自分の望みを考えてみることにした。悪魔と契約を結ぶかどうかかは、望みを決めてからでも遅くはない。
しかし、いざ実際に考えてみても、人生をかけてまで望むものは、なかなか思い浮かんでこなかった。こどもの頃は、想像のままに欲しいものを口にして両親を困らせていたような思い出があるが、大人と呼ばれる年代になったいま、欲しいものが心の中からなくなっていたのだ。
私は――あるいは私たち大人は――、生きることに価値を見出すことで、自分の中の欲求を抑えようとしている。欲求に突き動かされるのを避けようとしている。おそらくは、それが達成できかったときの反動が怖いから。欲しいものという存在を遠のけようとしているのだ。
「手に入れたいものがなにものないのに、そんなに長い人生を残すことに意味があるとは思えないけど。人間って、いつも不思議な言い訳を使って、自分の生き方を決めつけてしまおうとするよね」
悪魔は飛び跳ねるのをやめて、少しつまらなさそうにため息をついた。
「生きることと、ただ生きていることは、似ているようでまったく違うよ」
契約書を小さく折りたたんで、悪魔はまた宙返りをした。着地する頃には契約書はどこかに消えていた。
失望を隠せずにいる悪魔の身体が、はじめに見かけたときのように、また小さくなっていることに気がついた。私がそれを指摘すると、悪魔が理由を教えてくれた。
「君たち人間が、何も望まなくなってしまったからだよ」
意外な答えに、私は驚いた。
「饅頭や砂糖菓子だって大好きだけど、そんなものだけじゃ、僕たちはエネルギーを貯められないんだ。僕たちにとって本当のエネルギーになるのは、君たち人間の寿命なんだよ。さっきの契約みたいに、君たちの望みを叶えてあげる代わりに、いくらかの命を分けてもらって、それで僕たちは生きているんだ」
私は、どうして悪魔の身体が小さいのかを理解した。
「そうだね。欲しいものがないんだから、僕たちの誘いなんて誰も乗らなくなったんだ。そりゃ、普段から小さな望みくらいあるのだろうけど、でも、人生の多くの部分をかけてまで手に入れたいかと尋ねられると、みんな簡単に手を引っ込めてしまう。そんな、一枚の羽のように軽い望みだけしか持たなくなったから、僕たちもエネルギーを手に入れられなくて、こんなに小さくなってしまったんだよ」
社会不況は人間の世界だけのことかと思っていたが、近頃は、悪魔も大変なのだ。だから、せめてもの食いつなぎに、ジュリーの食事をせしめるなどという努力をしなければならないのだろう。
なんだか自身のことを不甲斐なく思い、私は悪魔に詫びた。すると、悪魔は少しだけ驚いた表情を見せた。
「別に君が謝ることじゃないさ。それに、君は僕を助けてくれたんだから、十分に感謝しているよ!」
屈託のない笑顔が閃いた。悪魔というと、とても意地悪で、人を堕落させるような誘いを渡してくるものだと思っていたが、そんなことはなかった。むしろ、しっかりとルールに則って、私たち人間のことまで考えて、精一杯生きているのだと感じた。
◇
それから私は、しばらくの間、悪魔と話した。近所の和菓子屋で旨い菓子を仕入れ、缶に入った茶を二つ買い、近くの公園のベンチに座って、陽がほとんど見えなく頃まで話し込んだ。
聞けば、悪魔はこの国を去ろうかと悩んでいるのだという。私と同じように、この国の人々は心の底から望むものをなくしている。この状況は、悪魔にとっては食い扶持が見つからないということなのだ。だから、まだ人々が強い望みを持って生きているような、比較的に発展の程度が小さな国へ移り住もうかと考えているのだ。
「僕はね、この国が好きなんだ。季節によって違う花が咲いて、それに合わせて生き物の表情も変わっていく。海の上に浮かんだ小さな国だし、物や資源が豊富だってこともないけれど、でも、ほかの国からの影響をあまり受けずに、自分たちの考え方や様式を残したままでいままで続いている。僕たち悪魔の誘いって、ときには勘違いされるけど、人間のためでもあるんだよ。僕たちだって世界がよくなってほしいと思っているんだ。そのために、僕たちに出来る方法で、人間に力を貸してあげているんだよ」
変わったのは、なにも望まなくなってしまった人間なのだ。私たちは、変化の果てを見たと勘違いしてしまい、あらゆる事柄を見聞きしていると思い上がり、自分から望みを手放してしまったのだ。
「君が、最後だったんだ。助けてくれたから、というのももちろんあったんだけど、せめて望みの代わりにもらう命を半分におまけして、それでもなにも望もうとしないんだったら、もうこの国で相手を見つけるのは諦めて、他の国へ出て行こうと決めていたんだ。だから、君と知り合えて嬉しいけれど、これでもうお別れだよ」
菓子と茶を残らず食べて、悪魔はベンチの上で立ち上がった。
「美味しかったよ。ありがとう」
そう言って、悪魔はベンチから飛び降りた。振り返って私の方へ手を振り、公園を後にした。私は、後ろ姿が見えなくなるまで、ずっと悪魔を見送っていた。
それは、なんとも不思議な気分だった。心の中から抜け落ちた大切なものが、目の前の土の地面を転がって、どこか遠くへ消えていこうとしているようだった。小さなその固まりは、心から離れて行けば行くほど小さく縮んでゆき、やがては目に見えないようになって、そして消えてしまう。
それは、生まれてからこれまでに、何度となく感じてきた気分だった。
(ああ、そうだ。思い出した……)
私はベンチを飛び出し、悪魔を追った。視界の先の方で風景に溶けてしまおうといる悪魔の後ろ姿を見失わないように、必死で目をこらしながら、力の限りに駆けた。その様子が珍しかったのか、公園中の視線が私へと集まった。物珍しそうなものを見つけた視線は、しばし私の行動を眺めて、またすぐに興味をなくして逸らされる。
「もしかして、お土産を渡すのを忘れていた?」
公園の出口で、ようやく悪魔に追いついた。悪魔は、少しだけ驚いたような表情で、いたずらっぽく言った。
私は深く息をついて、心を落ち着けた。そして、言った。心の奥深くに眠っており、知らず心から零れ落ちそうになっていた大切な思いを。長い間、果てることなく抱いてきた夢を。口に出すのが怖く、意識に上げることを押さえていた、人生を掛けるにも値する、私の望みを。
『私は作家になりたい。物語の力で世界を変えたい。それは、叶えられるのか?』
自分で言っているにも関わらず、その声は、まるで音響設備を通して響くかのようにして聞こえた。世界が、私の世界が、その言葉を告げているかのようだった。
私の望みを聞いて、悪魔は笑顔を見せた。
「僕に出来るのは、そのための力を与えるだけだよ。その力をどうやって使うのか、物語を書く力を使って、想像しているような作家になれるかどうかは、君次第だ」
そこで、悪魔は一度言葉を切った。じっと私のことを見つめて、なにかを念じた。
やがて、悪魔は息をついて答えた。
「残念だけど、その望みは叶えられないや」
「――え?」
その答えを聞いて、私は明らかにうろたえてしまった。心の中から零れ落ちたガラスの玉を、ようやくの思いで取り戻したというのに、手にしたときには、粉々に砕けていたのだ。大きな失望が、胸の中に広がった。
だが、そんな私に、優しい口調で、悪魔は言葉の意味を教えてくれた。
「どうしてかと言うとね、僕が与えるまでもなく、君はその力を持っているからだよ」
そんなバカな。
私は、胸を撃たれたように驚いた。自分がずっと望んできたものは、すでに自分の中にあったというのだから。とても信じられることではない。悪魔への信用を揺るがすような答えであったのだが、
(いや、バカなことなんてあるか……)
しかし、その答えが正しいのだということも、頭の隅では納得していた。
私は、自分の力を信じることができず、これまで物語を書くことなどせずに日々を過ごしていたのだ。ただ、作家になりたいという夢を漠然と抱いたままで、しかし、それは奇跡でも起こらない限り実現できないのだと思うことで努力を怠って、日々の中で、なにを強く望むこともなく、こうして時間だけを浪費していたのだ。
なんと、みっともないことだろうか。
「そんな難しい顔をしないでよ。もう大丈夫だって。君は、君の望みを思い出したんだからね」
悪魔は、とても嬉しそうに笑った。子どもが見せる笑顔と同じ笑顔を、悪魔は作って見せた。それを見て、私も笑顔を作った。近頃は作ったことのなかったような、心からわき出てくる、将来へ向けた明るい笑顔だ。
その笑顔を返しながら、私は悪魔に感謝の言葉を贈った。
◇
それから数日が経った。相も変わらず、どんなに怪しい人物が近づいて来ようとも、ジュリーは目覚めることなくうたた寝に興じている。仕事帰り、そんなジュリーを横目に眺めつつ、私は足早に自宅へと戻った。普段は、そこで一日の活動を終わらせて、残りの時間は休憩に当てていたのだが、この日の私は違った。いくらか着慣れてきたスーツを脱いで、普段着に着替え、ブリーフケースとは違うバッグを持って、再び外に出た。そんな私の姿を、重そうな瞼を少しだけ上げてジュリーが見ていたが、やがて興味をなくし、また眠りの世界へ戻っていった。
私は、物語を書くための道具を持ち、近所の喫茶店へ向かった。途中、頭の上のほうから私を呼ぶ声が聞こえたので、そちらを向いた。鳴海さん宅の垣根の上で、私の様子を眺めている悪魔がいた。
「今日は随分と早かったね。仕事は大丈夫なの?」
私が歩くのに合わせて、悪魔も垣根の上を駆けてくる。そんな悪魔に、心配には及ばない旨を伝えた。不思議なもので、毎日の時間の中にやりたいことが増えたとしても、それを考えているうちは時間が足りないように思えるものだが、いざ実行に移してさえしまえば、時間が足りなくなることなどなかった。むしろ、多くのやりたいことを行なうために、日々の密度が高くなり、充実した時間さえ送れるようになるのだ。
「この分なら、君の望みが叶うのも、そう遠くはない未来だね」
僕の肩に飛び移って、悪魔が囁いた。公園での一件以来、悪魔はこうして、僕の近くに住むようになっていた。実はあの別れの後で、私は悪魔をもう一度呼び止め、別のことを悪魔に望んでいたのだ。それは、私が作家になるという望みを叶えるまで悪魔にそばにいてほしい、というものだった。
いつか望みが叶うのかはわからないし、たとえ叶ったとしても悪魔に代償を支払うのは、その後のことである。こうした不確実な契約であったにも関わらず、悪魔はその望みを叶えてくれると言った。それまでの間は、人々の小さな望みを叶えたり、砂糖菓子や饅頭を食べて過ごせばいいのだと悪魔は言った。
「大切なのは、本当に叶えたいと思う望みを誤魔化さないで、そのとおりに生きることだよ」
それは自分にも当てはまることなんだと、悪魔は笑った。
その日、私は喫茶店にこもって閉店時間になるまで物語を書いた。悪魔が店の飼い猫と喧嘩を始めたときにはひやりとしたが、店主には悪魔の姿が見えていないようなので、面倒ごとにはならなかった。
私の書く物語は、決して順調に先へ進むこともないし、多くの人が読んでみんなが面白いと思うものでもない。これまで長い間、心の中の望みを遠ざけていたのだから、すぐに満足のいくものができなくてもしかたのないことだ。だけど、こうして悪魔とともに望みを叶えようと努力する時間は、とても清々しいものだった。
「この国のみんなが、君みたいに自分の望みを思い出すことってあるのかな?」
帰り道、悪魔が聞いてきた。
私は、それに答えた。私はそのために物語を書いているのだ、と。
「もしそうなったら、よその国へ行ってしまった友達を呼び戻せるね!」
期待に目を輝かせて、悪魔は言った。
◇
こうして、私と悪魔との共同生活が始まった。悪魔との契約は特別な形態で結んでいるため、常に悪魔が私のそばにいるということはなかった。悪魔は自分が行きたいところへ出歩き、いつも変な知人を連れて帰ってきた。そうした知人たちは、これまで私が目を向けていなかっただけで、日常のあらゆる場所に棲んでいるのだと言った。彼らはとてもユニークな習性を持っており、それはときに問題を引き起こすことともなったが、そうした彼らとの出会いは刺激のある体験となり、私の望みを後押しするものであった。
きっと、悪魔は、私の望みを叶えるために、自分にできることを考えて実行しているのだろう。悪魔も、人の望みを叶えるために、努力をしているのだ。そうした悪魔の姿こそが、私にとってはなによりの刺激であった。
さて。今日も仕事から帰ってくると、家の前で悪魔が待っていた。隣に立っている不思議な生き物に見覚えはなかったけれど、その出会いは楽しい物語を予感させるものであった。
私が「ただいま」と言うと、悪魔は「おかえり」と応えてくれた。