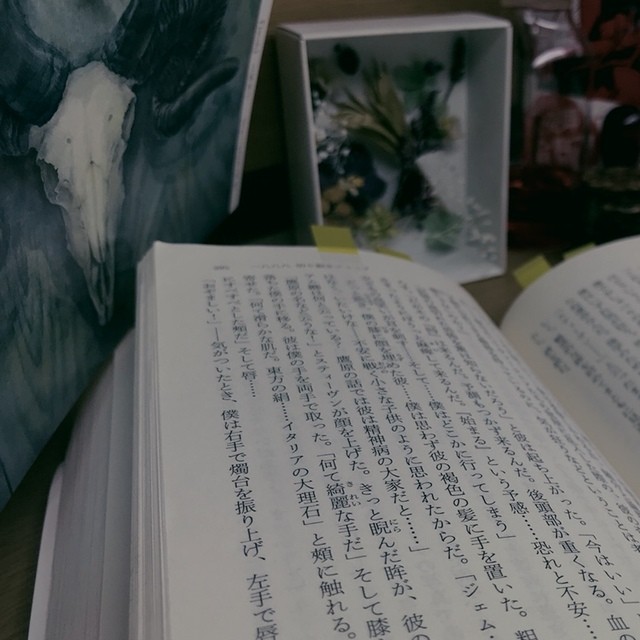第1話
文字数 3,935文字
かつて私の心誇れた居場所は、小さな煙草から数分足らずに燃え尽きた。
数時間前まで、私は見窄らしい格好で、当てもなくネオン街で暇を潰していた。路地の隙間を通り抜け右に角を曲がった先、小さい空き地がある。そこのコンクリートブロックに座り、同時間に来るマキを待っていた。綺麗な黒い瞳をし、毛先は揃ってはいなかったがこの街では気にならなかった。
すると彼女は現れた。早々に「陰気ね」と私の横に座り上機嫌に、摘んだ白詰草の匂いを嗅ぐ。私が「それ、汚いって聞いたが」と言うとすぐ雑草の方へ投げ、舌を出して笑った。笑顔は無邪気で年齢に相応しておらず、細くなった瞳の奥に陰気臭い私が映った。男らしくもない、只々みっともなく自己嫌悪の塊だ。
彼女は「やっぱり、忘れられないのね」と俯いて私を横目で見る。唐突に変わる彼女の雰囲気とその気遣った瞳から、私は申し訳なく「忘れられないさ……また、あれをしてくれても構わないだろうか」と手を差し出す。マキは「ええ、勿論。それで貴方の気が済むのなら」と言って私にそっと近付き、その身を寄せ合う。暖かく少しツンとした匂いで、母の様な温もりがあった。二人の中で深まり、思い出したくもない過去はやがて浄化され、懐かしく思えるものに変わっていく。夢は儚く、同時に思い出も儚く消えていくような……
鳥の溜まり場に一歩足を踏み入れて、砕け散るように鳥は去り行く。それと同様に、愛の加減を知らずに飛び込めば、私を拒んで突き放す。
ユキは私を愛していた。私もその事実を知っていた訳であり、会話のキャッチボールという例えがあるように、愛情のキャッチボールが成立していたことだと思う。
二人で住むには少しだけ小さく、変哲もないアパートであった。いつもユキは私を隠す様にアパートの大家さんを嫌った。私はユキよりも朝早く家を出て、帰ってくるのは夕方だった。いつもご飯がテーブルに乗っていて、それを孤独に食べるのが日課であり、ご飯から伝わる愛情を確かに受け取っていた。ユキは私より遅く出て、電車に揺られながら都心部に出勤していた。家に帰ってくるのも遅く、大抵私が寝ている間にひっそりと帰ってきている。
平日は顔を合わせることも少なかったが、休日には二人よく出かけていた。恋人同士が多くいる公園で噴水を見て(私は水やプールが嫌いだったが)、鳩を驚かせようと立ち向かってみたり。たまに私は公園で、ユキの口中にそっと舌を入れた。彼女は拒んで、私も少し小っ恥ずかしくなってやめてしまった。誰の為になる訳でもないがそのゆっくりと流れる穏やかな時間の数々は私の何よりもの幸福であった。
しかしそれに変わる様に幸せはそう長く続かないものだった。ユキはその朝、私よりも家を早く出た。不思議に思いつつも特に何も言わずに彼女の背を惜しく思いながら見送った。私もいつもの時間に家を出て、住宅街を歩いていた。駅の方まで向かい、するとユキの姿を見つけた。彼女は知らぬ男の人と仲良さそうに歩いていた。まだそれだけなら良かったのだが、公衆の場で熱い接吻を交わし、そのまま二人で改札を通った。私は黙ってそれを見る程我慢強くもなく、思わずユキに向かって叫ぶ。その声は届いた様で、少し此方を振り向いてまた何もなかったかのように電車に乗り込み、それ以上は私も足を踏み入れる事が不可能であった。
その日の夜、私はいつもより長く起き、彼女が何を考えているのかを透かそうとしたのだが、家の中は静かなままで帰ってこなかった。窓を見れば雲の下でじんわりと明るくなる空を感じた。私はそれをこれからの希望を意味していると都合よく考え、少し仮眠をとることにした。今よくよく考えれば希望も何もなかったのだろうが、その時はただ何かに縋って生きていきたかっただけである。
やがて目を覚まし、休日になってまだ澄み渡らずの空に歓迎された。しかしユキは私の目覚めを歓迎してくれないどころかまだ帰っていない様だった。(隠れた陽の光が私の身に届かぬ限りは未来に希望の一つもなかろう)
すると家の前の廊下を歩く音がし、ユキのハイヒールの音ではなく革靴だと思われる足音に耳を澄ましていた。途端私の家の鍵を開ける音がし、唐突に襲った悍ましさと共にユキと会う事への抵抗により棚の方へ隠れた。私が到底入れる大きさではなかったが、少し棚の戸の隙間から様子が見え、丁度良いといえば丁度良かった。
そっと、ギっと、立て付けの悪い扉を開け「ユキさん、起きてください」という男性の声がした。そう、男の人の声がしたのだ! 私は息を殺して目を凝らして彼の方を見た。ユキより二つか三つ、歳下であろう好青年で、昨日見た彼に違いはなかった! 彼はユキをおぶって無防備なユキの脚に触れている。黒タイツの下に透ける白いきめ細やかな肌が見えている。彼は「水、飲みますか?」と言って私達の暖かい冷蔵庫に手を伸ばして麦茶を取った。私達の温もりの食器棚からコップを手に取り麦茶を注いだ。それをユキに差し出したが彼女は拒み、彼は自分で注いだその麦茶を口に含んでユキに口づけをした。そしてユキはゆっくりと喉を伝って飲み込んでいく。
するとユキは彼に近づき首に手をかけ押し倒した。大分酔っている! 同居人であり愛する
ユキは私の方を見て「邪魔だ」と冷たい視線を放って私に言った。途端身体全身が震え上がり、彼女を傷つけてしまったという後悔に呪われて、そこから動けなくなっていた。彼の上に座っていたユキは立ち上がり、私の為に魚などをおろしてくれていた包丁を手に取り、思い切り私に振りかざした。その時だけは死んでしまうかもしれないと身体が自然と動いて胴に数センチ傷がついただけで済んだ。彼はというと彼をも黙って私を蔑んでいる様に見えた。もしかしたらそれはただの被害妄想に過ぎないのかもしれない。だが、彼が元凶で招いた事だ。彼がいけないのだ!
ユキは「お前なんかいらない」とガラスのコップを此方に投げてガラスはパッと砕け散った。私の身体は血で染まり、傷がえぐれてみえた。私が何をしたというのだろうか、いつから彼女は豹変してしまったのか。今酒の熱に浮かされているだけではないのか、という瞑想が頭の中で回るほど苛立ちばかりが募り、赤く色づいたまま外へと飛びだした。
私にこんな家なんぞ必要ない!
ろくな食事もしていない、ろくな生活ルールでもなかった、それが今何になろう?
私の身の一つにもなっちゃあ、いない。
しかし、その人生を明るく輝かせたのは彼女ではないか! 紛れもないユキではないか!
いつのまにか眠りについていた私は温かいマキの胸で安らかでいた。マキも寝ている様で、ここに一人置いていくのも気が引けたが、私にはやらねばいけないことができた。ネオン街は未だ夜を知らない。
ユキと愛し合っていたあのアパートに向かってかけていった。多くの煙草の吸い殻が捨ててあり、まだ火がついている。人間は愚かだ。
街の建物が次々と変わって通り過ぎて行くにつれて走馬灯の様にユキとの愛おしい日々を思い出して、泣く泣く走った。まだ傷が癒えず、風呂にもろくに入れていない見窄らしい私をユキが見て、何というのだろうか。ユキと彼はどう私を蔑んでくれるのだろうか。もういっそいいだろう! 思い切り私を突き放してくれ! ここまできて彼女等に何も求める事はない! とにかく私を駄目だと認めておくれ、未だに私は何がいけなかったのかすらをも分かっていないのだから!
次第に少し古びて安っぽい、アパートが見えてきた。そこに私が咥えてきた火のついたままの煙草を投げた。そして赤く、ユキと温まるのに使っていたタンクから液体をアパートの、彼女等の家に流した。
途端火は思い切り炎と化し、中から悲鳴が聞こえてきた。感に触るのに気にかけてしまう彼女の叫び声が中から聞こえ、昔ならば「虫でも出たのかい?」と思っていたはずの声に今は恐ろしい思いを抱いた。彼の「助けて」の声は快感となり、ユキの愛おしい声は呪いの声になっていく。どれだけ叫ぼうが誰も助けない。火がアパートを包み込み、私も次第に暑くなっていく。私が間違っているのはきっと貴方等の所為だろう? 歪ませたのは、紛れもなく愛らしく、どの世界よりも輝いてみえたあの城 だろう。
そして数分も経たずにアパート全体が燃え、他の住民も共に燃えてしまった様だ。
私は全身を、今更出てきた陽の光に委ねて泣いた。人間の様に涙が出る訳じゃない。ただ声を出すだけなのだが。
大好きなキャットフードと、夕方までずっと続けた散歩も、首に付いたままの私の「タマ」という名が刻まれた意味もない首輪。ユキはどんな気持ちでこれを付けてくれたのか。
空き地に放ったらかしの白詰草、美しかった黒猫のマキ、誰かが吸った吸殼で、アパートがこんなにも燃えてしまうものなのか。
愛に形はないと、教えてくれたのは貴女で……同時に愛はどうしようもなく儚いものだと、教えてくれたのも貴女だった。
私の犯した罪は消えないだろう……ああ、どうだ。人間らしく警察に自首でもしてみようか。
数時間前まで、私は見窄らしい格好で、当てもなくネオン街で暇を潰していた。路地の隙間を通り抜け右に角を曲がった先、小さい空き地がある。そこのコンクリートブロックに座り、同時間に来るマキを待っていた。綺麗な黒い瞳をし、毛先は揃ってはいなかったがこの街では気にならなかった。
すると彼女は現れた。早々に「陰気ね」と私の横に座り上機嫌に、摘んだ白詰草の匂いを嗅ぐ。私が「それ、汚いって聞いたが」と言うとすぐ雑草の方へ投げ、舌を出して笑った。笑顔は無邪気で年齢に相応しておらず、細くなった瞳の奥に陰気臭い私が映った。男らしくもない、只々みっともなく自己嫌悪の塊だ。
彼女は「やっぱり、忘れられないのね」と俯いて私を横目で見る。唐突に変わる彼女の雰囲気とその気遣った瞳から、私は申し訳なく「忘れられないさ……また、あれをしてくれても構わないだろうか」と手を差し出す。マキは「ええ、勿論。それで貴方の気が済むのなら」と言って私にそっと近付き、その身を寄せ合う。暖かく少しツンとした匂いで、母の様な温もりがあった。二人の中で深まり、思い出したくもない過去はやがて浄化され、懐かしく思えるものに変わっていく。夢は儚く、同時に思い出も儚く消えていくような……
鳥の溜まり場に一歩足を踏み入れて、砕け散るように鳥は去り行く。それと同様に、愛の加減を知らずに飛び込めば、私を拒んで突き放す。
ユキは私を愛していた。私もその事実を知っていた訳であり、会話のキャッチボールという例えがあるように、愛情のキャッチボールが成立していたことだと思う。
二人で住むには少しだけ小さく、変哲もないアパートであった。いつもユキは私を隠す様にアパートの大家さんを嫌った。私はユキよりも朝早く家を出て、帰ってくるのは夕方だった。いつもご飯がテーブルに乗っていて、それを孤独に食べるのが日課であり、ご飯から伝わる愛情を確かに受け取っていた。ユキは私より遅く出て、電車に揺られながら都心部に出勤していた。家に帰ってくるのも遅く、大抵私が寝ている間にひっそりと帰ってきている。
平日は顔を合わせることも少なかったが、休日には二人よく出かけていた。恋人同士が多くいる公園で噴水を見て(私は水やプールが嫌いだったが)、鳩を驚かせようと立ち向かってみたり。たまに私は公園で、ユキの口中にそっと舌を入れた。彼女は拒んで、私も少し小っ恥ずかしくなってやめてしまった。誰の為になる訳でもないがそのゆっくりと流れる穏やかな時間の数々は私の何よりもの幸福であった。
しかしそれに変わる様に幸せはそう長く続かないものだった。ユキはその朝、私よりも家を早く出た。不思議に思いつつも特に何も言わずに彼女の背を惜しく思いながら見送った。私もいつもの時間に家を出て、住宅街を歩いていた。駅の方まで向かい、するとユキの姿を見つけた。彼女は知らぬ男の人と仲良さそうに歩いていた。まだそれだけなら良かったのだが、公衆の場で熱い接吻を交わし、そのまま二人で改札を通った。私は黙ってそれを見る程我慢強くもなく、思わずユキに向かって叫ぶ。その声は届いた様で、少し此方を振り向いてまた何もなかったかのように電車に乗り込み、それ以上は私も足を踏み入れる事が不可能であった。
その日の夜、私はいつもより長く起き、彼女が何を考えているのかを透かそうとしたのだが、家の中は静かなままで帰ってこなかった。窓を見れば雲の下でじんわりと明るくなる空を感じた。私はそれをこれからの希望を意味していると都合よく考え、少し仮眠をとることにした。今よくよく考えれば希望も何もなかったのだろうが、その時はただ何かに縋って生きていきたかっただけである。
やがて目を覚まし、休日になってまだ澄み渡らずの空に歓迎された。しかしユキは私の目覚めを歓迎してくれないどころかまだ帰っていない様だった。(隠れた陽の光が私の身に届かぬ限りは未来に希望の一つもなかろう)
すると家の前の廊下を歩く音がし、ユキのハイヒールの音ではなく革靴だと思われる足音に耳を澄ましていた。途端私の家の鍵を開ける音がし、唐突に襲った悍ましさと共にユキと会う事への抵抗により棚の方へ隠れた。私が到底入れる大きさではなかったが、少し棚の戸の隙間から様子が見え、丁度良いといえば丁度良かった。
そっと、ギっと、立て付けの悪い扉を開け「ユキさん、起きてください」という男性の声がした。そう、男の人の声がしたのだ! 私は息を殺して目を凝らして彼の方を見た。ユキより二つか三つ、歳下であろう好青年で、昨日見た彼に違いはなかった! 彼はユキをおぶって無防備なユキの脚に触れている。黒タイツの下に透ける白いきめ細やかな肌が見えている。彼は「水、飲みますか?」と言って私達の暖かい冷蔵庫に手を伸ばして麦茶を取った。私達の温もりの食器棚からコップを手に取り麦茶を注いだ。それをユキに差し出したが彼女は拒み、彼は自分で注いだその麦茶を口に含んでユキに口づけをした。そしてユキはゆっくりと喉を伝って飲み込んでいく。
するとユキは彼に近づき首に手をかけ押し倒した。大分酔っている! 同居人であり愛する
家族
である私が黙って見ていられるものか! そう思って私は棚から飛び出た。彼も彼女も驚いた様に目を丸くした。特にユキの目は虚ろで覚束なく、彼は私の方を見て「驚いた、随分可愛らしいご家族だ」と言ってにっこりと笑った。私を思い切り馬鹿にしているようで苛立った。確かに男らしくはないかもしれないが可愛らしいとはなんだ。私は愛する青色の皿を引っ掻き出し、思い切り彼の方へと投げつけた。ユキは私の方を見て「邪魔だ」と冷たい視線を放って私に言った。途端身体全身が震え上がり、彼女を傷つけてしまったという後悔に呪われて、そこから動けなくなっていた。彼の上に座っていたユキは立ち上がり、私の為に魚などをおろしてくれていた包丁を手に取り、思い切り私に振りかざした。その時だけは死んでしまうかもしれないと身体が自然と動いて胴に数センチ傷がついただけで済んだ。彼はというと彼をも黙って私を蔑んでいる様に見えた。もしかしたらそれはただの被害妄想に過ぎないのかもしれない。だが、彼が元凶で招いた事だ。彼がいけないのだ!
ユキは「お前なんかいらない」とガラスのコップを此方に投げてガラスはパッと砕け散った。私の身体は血で染まり、傷がえぐれてみえた。私が何をしたというのだろうか、いつから彼女は豹変してしまったのか。今酒の熱に浮かされているだけではないのか、という瞑想が頭の中で回るほど苛立ちばかりが募り、赤く色づいたまま外へと飛びだした。
私にこんな家なんぞ必要ない!
ろくな食事もしていない、ろくな生活ルールでもなかった、それが今何になろう?
私の身の一つにもなっちゃあ、いない。
しかし、その人生を明るく輝かせたのは彼女ではないか! 紛れもないユキではないか!
いつのまにか眠りについていた私は温かいマキの胸で安らかでいた。マキも寝ている様で、ここに一人置いていくのも気が引けたが、私にはやらねばいけないことができた。ネオン街は未だ夜を知らない。
ユキと愛し合っていたあのアパートに向かってかけていった。多くの煙草の吸い殻が捨ててあり、まだ火がついている。人間は愚かだ。
街の建物が次々と変わって通り過ぎて行くにつれて走馬灯の様にユキとの愛おしい日々を思い出して、泣く泣く走った。まだ傷が癒えず、風呂にもろくに入れていない見窄らしい私をユキが見て、何というのだろうか。ユキと彼はどう私を蔑んでくれるのだろうか。もういっそいいだろう! 思い切り私を突き放してくれ! ここまできて彼女等に何も求める事はない! とにかく私を駄目だと認めておくれ、未だに私は何がいけなかったのかすらをも分かっていないのだから!
次第に少し古びて安っぽい、アパートが見えてきた。そこに私が咥えてきた火のついたままの煙草を投げた。そして赤く、ユキと温まるのに使っていたタンクから液体をアパートの、彼女等の家に流した。
途端火は思い切り炎と化し、中から悲鳴が聞こえてきた。感に触るのに気にかけてしまう彼女の叫び声が中から聞こえ、昔ならば「虫でも出たのかい?」と思っていたはずの声に今は恐ろしい思いを抱いた。彼の「助けて」の声は快感となり、ユキの愛おしい声は呪いの声になっていく。どれだけ叫ぼうが誰も助けない。火がアパートを包み込み、私も次第に暑くなっていく。私が間違っているのはきっと貴方等の所為だろう? 歪ませたのは、紛れもなく愛らしく、どの世界よりも輝いてみえたあの
そして数分も経たずにアパート全体が燃え、他の住民も共に燃えてしまった様だ。
私は全身を、今更出てきた陽の光に委ねて泣いた。人間の様に涙が出る訳じゃない。ただ声を出すだけなのだが。
大好きなキャットフードと、夕方までずっと続けた散歩も、首に付いたままの私の「タマ」という名が刻まれた意味もない首輪。ユキはどんな気持ちでこれを付けてくれたのか。
空き地に放ったらかしの白詰草、美しかった黒猫のマキ、誰かが吸った吸殼で、アパートがこんなにも燃えてしまうものなのか。
愛に形はないと、教えてくれたのは貴女で……同時に愛はどうしようもなく儚いものだと、教えてくれたのも貴女だった。
私の犯した罪は消えないだろう……ああ、どうだ。人間らしく警察に自首でもしてみようか。