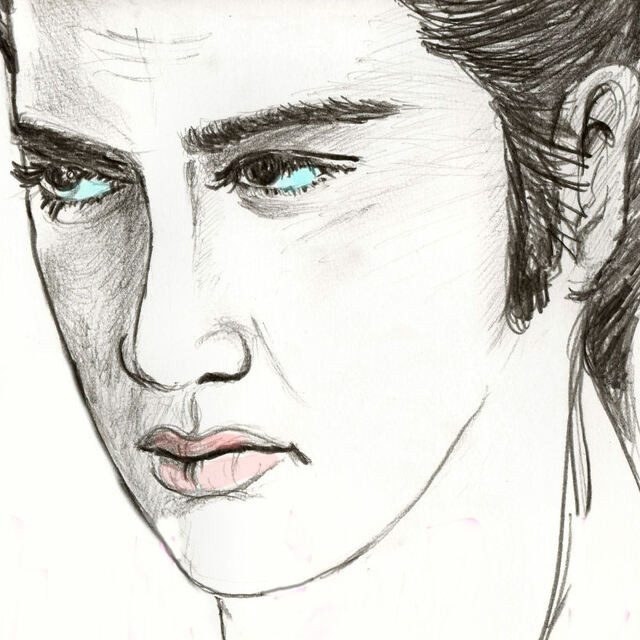こころ
文字数 2,514文字
〈こころ〉
彼はひとり座禅を組みながらその山で瞑想に耽っていた。
その場所は、或る寒空の中にあった。
「寒い……」
その少し高台になっている、今は誰もいない山の中の或る場所で彼は一人でいた。暖かい春ともなれば、夜でも誰かしら来る。なぜなら、ここから見える景色は最高に美しいからだ。
高台から一望に見渡せるこの場所の景色が彼は好きだった。
その場所は彼だけの場所である。
その山上の場所には、それぞれに小さな椅子がいくらかは置いてある。
しかし、彼はその椅子には座らない。今いるその場所からも景色が見渡せるからである。
思うことがありそこへたどり着いた。誰からも干渉されないその場所があるのだ。少し傾斜があり、注意しないと堕ちてしまいそうな危ない場所である。そこは彼しか知らない居場所になる。
或る日、誰もいないときに偶然その場所を発見したのだ。人知れず物思いに耽り瞑想する為には丁度良い。春や秋には草が座布団の代わりになり、冬には枯れ草や枯葉が彼を休めてくれる。一人、物思いに耽るのは、自分の部屋では駄目なのだ。
ましてや街角の喫茶店でも駄目だった。
何故なら、店では誰かしらの人がいるし、自分の部屋でも物体が有りそこには雑念がある。
誰もいない場所、人の眼が気にならないこの場所。そこが彼には必要だった。何も無いこの虚無の境に一人居るだけで彼の「こころ」は浄化されるからだ。
何から浄化されたいのか? 何から逃げているのか? そう聞かれるに違いない。
そのわけを聞かないで欲しいと思う彼がいる。ただ、魂が、こころがそう欲しているからである。それ以外の理由が見つからない。
「こころ」について考えるとき、この場所ほど最適な場所はない。
それに、出来れば誰もいない寒空が良い。漆黒の山の中で光る星空を見ながら瞑想に耽るとき、彼の心は天空と一体になるからだ。流れ星がすっと一筋流れて消えた……。
(あれは誰かのこころなのか? どこかへ旅立っていったのだろうか……)
人のこころほど「うつせみ」を思わずにはいられない。
「うつせみ」とは、或る意味では「現人」とも書く。この世に現存する人間。生存している人間ともいう。
また、「空蝉」とも書く。蝉の抜け殻であり、魂がぬけた虚脱状態の身である。いわゆる意識をせず無の境地になった状態を言うのだ。自分はいま、うつせみなのか?
だれでも、その心の中に悪があり善がある。それは端的な言葉であるが、その濃淡の濃さで「こころ」が変わるのではないか。
善人ぶる人……良識がありそうに振る舞う人、良い所だけを見せたがる人、けっしてこころの中は綺麗ではないのに、それを善しとして思いこんでいる人間。それに善人が持つ、偽善、その中にひそむこころの悪魔……幸せの中にひそむ悪のこころ、悪と善……その比率はどうだろうか。
悪……それに対局して、悪の色の濃い人間。人を人と思わず、行動する人達。悪魔、悪人と称する人達。
彼等はそのこころに素直すぎるから、その誰からも忌みきらわれる行動に走る。
(俺はどっちなんだろうか?
しかしどんな悪人でも持つ優しい心が僅かでも必ずある。それを否定することは出来ない。それらは、善と悪とのその濃さが違うだけで、大差はない。
ただ生まれ落ちたその家、場所、家柄、環境に左右されるのであり、自分だけのせいではない場合が多いのだと、彼は思う。
何故彼は、その寒空の時にここに来たのか? 彼は悪人なのか?
何か、悪いことをして懺悔の為にここに来たのか……それとも臆病な善人で、小さな災いを行ってしまったのか、その罪に苛まれ、苦渋に満ちているのか、人を欺き、その人間を貶めたのか、人を殺めたのか、騙したのか。それとも他愛のない嘘で人を欺いたのか。
誰もそれは知らない、彼がそれを言わなければ、何も分からない。
それは彼の心の中にあるからである。今、彼はその罪の意識の為に、身を投げるわけでもなく、死ぬわけでも無さそうである。ただ、この世の嘘がはびこる世俗が嫌になっただけだった。
自分も含めて人というものが嫌いになったのである。この場所で思い悩み苦しみ、誰ともなく許しを請い、苦しみをこころに抱く人を許したいと想うこころ……。
しかし結論は出ない、どう足掻いても結論のでない空虚なこころ、でも死なずに生きていく為には、そんな世界で生かざるを得ない。虚無の中で、嘘がはびこる世界の中で生きなければならない。
しかし、何も求めず、ただ与えるだけの無償の愛があることにふと気が付く。
「そうか、あのように善も悪も意識せずに、無垢の気持ちになれば良いんだ……」
そう想ったとき、何かを悟ったようなこころが彼の中に芽生えた。
悟ったその時、彼の身体は氷のように冷たかった。寒さの為に身体が凍り付いている。何時間も、寒山にいれば誰でもそうなる。その思いにようやくたどり着けたとき、彼は山を下りることにした。
この寒空の、足元の覚束ない場所で、谷底に墜ちなければ良いのだが。
しかし、彼の足はもう歩き始めていた。その眼には満点の星が輝いている。
来たときとは違って、生き生きとした眼をして歩き始めたそのときだった。
暗闇を歩き始めて、ふと足元に感触がない。
土の肌触り、あの感触がないのだ。足が痺れ、一瞬、彼の身体はふわりと宙に浮いたように軽やかになる。
「あっ!」
そのとき、彼の「こころ」は飛んでいた。天空に包まれた宇宙の果てか……。
その瞬間、彼は今まで生きてきた自分の数々の悪行と、ほんの少しの善行の出来事が走馬燈のように脳裏を過ぎった。
または悪鬼羅刹がはびこる暗黒の世界へ真っ逆さまに堕ちたのか。或いはこのまま生き続けるのか。そのどちらかの世界に堕ちるのか、それはすでに決まっているのだろうか。
それを彼自身が知らないだけである。
ただ真実を言えば、彼は人を殺めてはいないし、素晴らしい行いをしたわけでも無い。いわゆる彼は空想癖がある人物だった。
そこには地獄も無ければ天国も無い。あるのは自我という己が心だった。かれは夢の中を彷徨っていた。朝になればいつものように目覚めるだろう。
彼はひとり座禅を組みながらその山で瞑想に耽っていた。
その場所は、或る寒空の中にあった。
「寒い……」
その少し高台になっている、今は誰もいない山の中の或る場所で彼は一人でいた。暖かい春ともなれば、夜でも誰かしら来る。なぜなら、ここから見える景色は最高に美しいからだ。
高台から一望に見渡せるこの場所の景色が彼は好きだった。
その場所は彼だけの場所である。
その山上の場所には、それぞれに小さな椅子がいくらかは置いてある。
しかし、彼はその椅子には座らない。今いるその場所からも景色が見渡せるからである。
思うことがありそこへたどり着いた。誰からも干渉されないその場所があるのだ。少し傾斜があり、注意しないと堕ちてしまいそうな危ない場所である。そこは彼しか知らない居場所になる。
或る日、誰もいないときに偶然その場所を発見したのだ。人知れず物思いに耽り瞑想する為には丁度良い。春や秋には草が座布団の代わりになり、冬には枯れ草や枯葉が彼を休めてくれる。一人、物思いに耽るのは、自分の部屋では駄目なのだ。
ましてや街角の喫茶店でも駄目だった。
何故なら、店では誰かしらの人がいるし、自分の部屋でも物体が有りそこには雑念がある。
誰もいない場所、人の眼が気にならないこの場所。そこが彼には必要だった。何も無いこの虚無の境に一人居るだけで彼の「こころ」は浄化されるからだ。
何から浄化されたいのか? 何から逃げているのか? そう聞かれるに違いない。
そのわけを聞かないで欲しいと思う彼がいる。ただ、魂が、こころがそう欲しているからである。それ以外の理由が見つからない。
「こころ」について考えるとき、この場所ほど最適な場所はない。
それに、出来れば誰もいない寒空が良い。漆黒の山の中で光る星空を見ながら瞑想に耽るとき、彼の心は天空と一体になるからだ。流れ星がすっと一筋流れて消えた……。
(あれは誰かのこころなのか? どこかへ旅立っていったのだろうか……)
人のこころほど「うつせみ」を思わずにはいられない。
「うつせみ」とは、或る意味では「現人」とも書く。この世に現存する人間。生存している人間ともいう。
また、「空蝉」とも書く。蝉の抜け殻であり、魂がぬけた虚脱状態の身である。いわゆる意識をせず無の境地になった状態を言うのだ。自分はいま、うつせみなのか?
だれでも、その心の中に悪があり善がある。それは端的な言葉であるが、その濃淡の濃さで「こころ」が変わるのではないか。
善人ぶる人……良識がありそうに振る舞う人、良い所だけを見せたがる人、けっしてこころの中は綺麗ではないのに、それを善しとして思いこんでいる人間。それに善人が持つ、偽善、その中にひそむこころの悪魔……幸せの中にひそむ悪のこころ、悪と善……その比率はどうだろうか。
悪……それに対局して、悪の色の濃い人間。人を人と思わず、行動する人達。悪魔、悪人と称する人達。
彼等はそのこころに素直すぎるから、その誰からも忌みきらわれる行動に走る。
(俺はどっちなんだろうか?
しかしどんな悪人でも持つ優しい心が僅かでも必ずある。それを否定することは出来ない。それらは、善と悪とのその濃さが違うだけで、大差はない。
ただ生まれ落ちたその家、場所、家柄、環境に左右されるのであり、自分だけのせいではない場合が多いのだと、彼は思う。
何故彼は、その寒空の時にここに来たのか? 彼は悪人なのか?
何か、悪いことをして懺悔の為にここに来たのか……それとも臆病な善人で、小さな災いを行ってしまったのか、その罪に苛まれ、苦渋に満ちているのか、人を欺き、その人間を貶めたのか、人を殺めたのか、騙したのか。それとも他愛のない嘘で人を欺いたのか。
誰もそれは知らない、彼がそれを言わなければ、何も分からない。
それは彼の心の中にあるからである。今、彼はその罪の意識の為に、身を投げるわけでもなく、死ぬわけでも無さそうである。ただ、この世の嘘がはびこる世俗が嫌になっただけだった。
自分も含めて人というものが嫌いになったのである。この場所で思い悩み苦しみ、誰ともなく許しを請い、苦しみをこころに抱く人を許したいと想うこころ……。
しかし結論は出ない、どう足掻いても結論のでない空虚なこころ、でも死なずに生きていく為には、そんな世界で生かざるを得ない。虚無の中で、嘘がはびこる世界の中で生きなければならない。
しかし、何も求めず、ただ与えるだけの無償の愛があることにふと気が付く。
「そうか、あのように善も悪も意識せずに、無垢の気持ちになれば良いんだ……」
そう想ったとき、何かを悟ったようなこころが彼の中に芽生えた。
悟ったその時、彼の身体は氷のように冷たかった。寒さの為に身体が凍り付いている。何時間も、寒山にいれば誰でもそうなる。その思いにようやくたどり着けたとき、彼は山を下りることにした。
この寒空の、足元の覚束ない場所で、谷底に墜ちなければ良いのだが。
しかし、彼の足はもう歩き始めていた。その眼には満点の星が輝いている。
来たときとは違って、生き生きとした眼をして歩き始めたそのときだった。
暗闇を歩き始めて、ふと足元に感触がない。
土の肌触り、あの感触がないのだ。足が痺れ、一瞬、彼の身体はふわりと宙に浮いたように軽やかになる。
「あっ!」
そのとき、彼の「こころ」は飛んでいた。天空に包まれた宇宙の果てか……。
その瞬間、彼は今まで生きてきた自分の数々の悪行と、ほんの少しの善行の出来事が走馬燈のように脳裏を過ぎった。
または悪鬼羅刹がはびこる暗黒の世界へ真っ逆さまに堕ちたのか。或いはこのまま生き続けるのか。そのどちらかの世界に堕ちるのか、それはすでに決まっているのだろうか。
それを彼自身が知らないだけである。
ただ真実を言えば、彼は人を殺めてはいないし、素晴らしい行いをしたわけでも無い。いわゆる彼は空想癖がある人物だった。
そこには地獄も無ければ天国も無い。あるのは自我という己が心だった。かれは夢の中を彷徨っていた。朝になればいつものように目覚めるだろう。