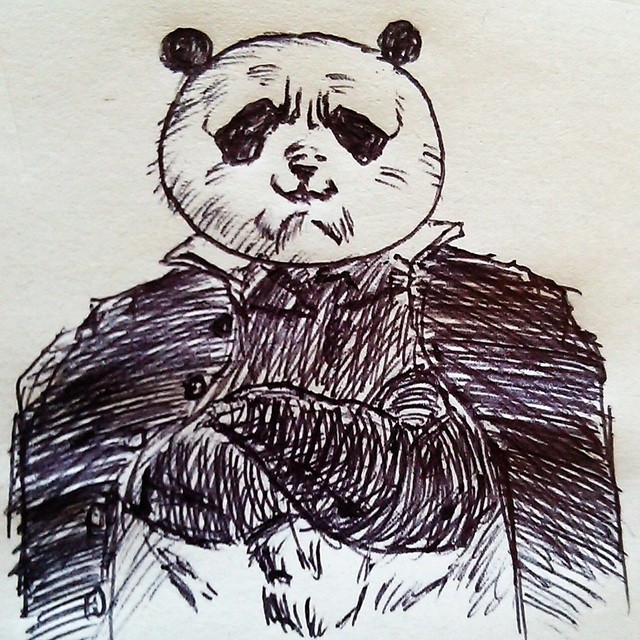#6 【みそぎ】
文字数 3,680文字
橋を渡ってから体感で三分ほど歩き、御曽木堂の北端である現在の入り口へとようやく到達した。
馬の手綱を先々代へと渡し、松明の火は砂をかけて消す。
一礼のあと匣鞍の左側より名帖を取り出す。
また一礼して匣鞍をいったん閉じる。
名帖を抱えたまま送り車の左横へ。
馬に向かって一礼したら送り車の台板に半分だけ腰掛け、名帖を左手に抱えたまま、右手で骨壷を包んである包み布を解く。
包み布は風呂敷と変わらないサイズで、真っ白い特製のものを遺族の方々が購入しているはず。
製作に本家筋や分家筋が関わってさえいなければ良くて、手作りでなければいけないわけではない。
とはいえそれ以外のほとんどが、『もくべさん』か『おくりもん』が用意しているわけだが。
この骨壷も『もくべさん』の作。
だから名帖を嵌 められるくぼみがある。
名帖を嵌めた骨壷を再び包み布で包んで持ち手を作る。「四つ結び」というやつだ。
そして送り車の台板から取り出し、片手で提げ。再び馬へ礼。
今度は送り車の後ろを回り込み、馬の右側へ。『おくりもん』自身が後ろへ下がらないのであれば、こうやって回り込む動きは許されている。
礼をして、匣鞍の右側を開け、飯鉢が二つ嵌っている盆板ごと引き出す。
小豆と白米が幾つか散らばっているが、いったん飯鉢からこぼれたものは絶対に戻さない。
いつもなら烏はこのおこぼれを狙ってきているのだが、今回屋根にいる異常な数の烏たちはじっと見つめるだけ。
不気味さに気を取られないよう、儀式を続けなくては。
骨壷包みを提げた左手で飯鉢の乗ったままの盆板を持ち、右手で匣鞍を閉じる。
一歩下がって馬に礼をしたら、御曽木堂の入り口へと向かう。
屋根に居る無数の烏たちはずっと僕の動向を見つめている。
あれだけ居るのに一羽として鳴いていないのが余計に薄気味悪い。
「御曽ー木ー堂ー、入らーんー」
野辺の渡り橋に居る参列者の方々にも聞こえる勢いの大声で、「独り言」を叫ぶ。
そして御曽木堂へ礼をし、敷石の上へと――まだ赤黒い染みが残っていることに体が躊躇 い、足が止まる。
止まるだけで済んで良かった。出しかけた足を戻しでもしたら大変なことになるところだった。
愛生穂はそれを狙ってここで手首を切ったわけじゃないだろうが、それでも愛生穂の執念のようなものがここには残っていそうで。
あの赤爪の黒い足が、その血溜まり跡の上に乗り、嬉しそうにぴょんぴょんと跳ねる。
ああそうか。この染みも「見ていない」様に振る舞う対象なのか。
今度は迷わずに、染みなどないものとして敷石の上へ乗る。
御曽木堂の入り口扉は両開きなので、その開く扉の軌跡よりも手前に立たねばならない。もちろん戻らないために。
飯鉢の乗った盆板と骨壷包みとを傍らへ置く。
入り口扉は閂 で封がしてあり、その閂を動かせぬよう大きな古い錠前が付いている。
一礼してから首から下げていた板鍵を首から外し、錠前を解錠して閂を開ける。
閂部分は木製で、扉を開ける際に戻らないで済む位置から手を伸ばして開けるには少々重いのだが、足の位置を動かすわけにもいかないので、踏ん張ってなんとか開ける。
その後、開けた閂の金具部分へ、手に持っていた錠前を差さったままの板鍵ごと引っ掛ける。
一礼をしてから左側の入り口扉から開く。
扉の内側に引っ掛けてある戸止め棒をいったん外し、風などで扉が閉まらないように敷石の凹みへと挿して扉が開いたまま固定する。
このときの角度は御曽木堂に対して直角となる。
右側の扉も同様に開いて止めると、両側の扉が細い通路のようになる。
一礼。
盆板と骨壷包みとを再び持ち、さらに一礼の後、ようやく安置場の中へ踏み込む。
中は簡素な作りで、正面の壁以外は全て板で覆われている。
左右両側の壁には片側四段ずつ長板が渡してあり、そこに幾つもの名帖付き骨壷が置かれている。
左が古く、奥から手前へ、下から上へ。現在は右側の壁の半分ほどが埋まっている。
その右側のほとんどは真新しい。
たった一つ、茶色く汚れた愛生穂の骨壷以外は。
本来、野辺には本家筋、分家筋でさえも渡ってはならないとされている。
そのための『おくりもん』であり、この儀式なのだ。
しかしそれを愛生穂が破った。
そのうえ愛生穂の遺体を回収するために駆けつけた警察官の中に、後で分かったことだが分家の血分かれが居た。
不義の子であることを隠されていたがために、その警察官本人も知らなかった事だし、仕方ないことなのかもしれないが。
ただ結果的に、その後連鎖した多くの悲劇のきっかけになったのは愛生穂とその警官――啓介 のせいなのだ。
啓介は僕の五つ上。小学校も中学校も同じはずだが特に接点などはなかったし、それ以前の評判もごくごく普通の新人警察官だったらしい。
だが愛生穂の送りの儀式の最中、骨壷を奪おうとして、それを阻止しようとした愛生穂の父――南の先代と、そして僕の叔父とが命を落とした。
愛生穂の骨壷は血塗れになったものの奪われずに済み、啓介はそのまま失踪した。
啓介が指名手配となった後で、啓介の母親が泣きながらにした告白は、この地域の人々に衝撃を与えた。
その内容は、啓介の本当の父親が南の先代であるというもの。
様々な儀式の掟が実際の被害を防ぐためのものだったのだと皆は改めて思い知ったが、既に破られてしまった禁忌の代償はあまりにも大きなものとなった。
周囲からの非難を苦に啓介の母親が自殺したのを皮切りに、人が死に始めた。
忌まわしき呪いのせいだとしか言いようがないほど、連続して多くの者が亡くなっている。
そのほとんどが事故としか言いようがない状況で。
ちなみに先代が亡くなったのもその同じ時期で、死因は車による自損事故だった。
母は桃歌同様に「見える」人なのだが、啓介失踪後、野辺でしか見なかった黒い影を川の此方側でも見かけるようになったという。
桜の季節、御曽木堂に沿って植えられた桜を此方側から見る人は少なくないのだが、母は桜の時期であっても川岸にさえ近寄らなかった。
さらには、その黒い影がまとわりついている血分かれの人たちが次々と亡くなったと言っていた。
母は精神的に参ってしまい、現在は先々代の勧めで実家へと帰り、療養している。
今、安置場の中に見えている黒い影は、あの赤爪の黒い足のみ。
それは珍しくじっとしている。愛生穂の骨壷の前で。
そらした視線が三つ前の骨壷で止まる。
啓介のものだ。
血分かれということがわかった以上は、犯罪者であろうともここに収めなければならないらしい。
啓介の送りも僕が執り行った――あのときは骨壷を叩き壊してやりたい気持ちをなんとか堪えて儀式を完了したが、いまだにあの骨壷を見ただけで、自分の中にもどす黒い闇が湧くのを感じる。
切り替えよう。
二つ前と一つ前は北と西の分家筋の先代。そして今回は東の分家筋の――儀式終了までは当代。
愛生穂が僕に執着していたことに対して猛烈に反発していた人たちの最後の一人。
これで一連の呪いとも言えるべき死の連鎖が止まればいいけれど――いや止まってほしい。そう願わざるを得ない。
ただそれはそれとして、念のために安置場の増設はもうそろそろお願いしておくべきなのかもしれない。
御曽木堂の増築は地区内の業者には頼めない。地区内の業者はだいたい本家や分家の血分かれになってしまうからだ。
安置場の奥の壁を見つめ、ここでも一礼する。
そこには一世代前の安置場への入り口扉がそのまま残っている。
その向こうには二世代前の安置場への入り口扉も、さらにその向こうには三世代前の安置場への入り口扉もそのまま。
御曽木堂の入り口を封じる錠前は、もうずっと前から同じものを使っているため、一番外側以外の入り口扉にだけ錠前が付く運用だ。
つまり閂を開けさえすれば、一番最初の安置場まで行けてしまう。
まだ遺体をそのまま運び込んでいた時代の安置場まで。
コン、という音が外から聞こえた。
先々代が傘の柄で地面を突いた音だ。
切り替えたはずなのに、手が止まってしまっていたのか。
どうしてこうも儀式に集中できないのか。
手が止まったせいで、あの黒い足も僕のまわりをぱたぱたと歩き回り始めた。
見てはいけない、考えてはいけない、ましてやその爪と思しき場所が赤いことなど気にすることさえいけない。
思考をそれから切り離そうとするほどに、それは僕の中で存在感を大きくする。
こういうのを切り抜けるときは「そのことについて考えないようにする」というのは悪手で、「別のことに集中する」ことで「そのこと」自体から意識を引き剥がしてゆくのが良い、とは聞いている。
眠れない夜に「寝よう、寝よう」と強く考えてしまうと全く眠れなくなるのと一緒で。
それがゆえの、建物なり歴史なりへの集中だったのだが、結果的には僕の見通しが甘かったと言わざるを得ない。
奥の奥の奥の――もう何世代前かもわからない遠くで、入り口の扉が開く音がしたから。
馬の手綱を先々代へと渡し、松明の火は砂をかけて消す。
一礼のあと匣鞍の左側より名帖を取り出す。
また一礼して匣鞍をいったん閉じる。
名帖を抱えたまま送り車の左横へ。
馬に向かって一礼したら送り車の台板に半分だけ腰掛け、名帖を左手に抱えたまま、右手で骨壷を包んである包み布を解く。
包み布は風呂敷と変わらないサイズで、真っ白い特製のものを遺族の方々が購入しているはず。
製作に本家筋や分家筋が関わってさえいなければ良くて、手作りでなければいけないわけではない。
とはいえそれ以外のほとんどが、『もくべさん』か『おくりもん』が用意しているわけだが。
この骨壷も『もくべさん』の作。
だから名帖を
名帖を嵌めた骨壷を再び包み布で包んで持ち手を作る。「四つ結び」というやつだ。
そして送り車の台板から取り出し、片手で提げ。再び馬へ礼。
今度は送り車の後ろを回り込み、馬の右側へ。『おくりもん』自身が後ろへ下がらないのであれば、こうやって回り込む動きは許されている。
礼をして、匣鞍の右側を開け、飯鉢が二つ嵌っている盆板ごと引き出す。
小豆と白米が幾つか散らばっているが、いったん飯鉢からこぼれたものは絶対に戻さない。
いつもなら烏はこのおこぼれを狙ってきているのだが、今回屋根にいる異常な数の烏たちはじっと見つめるだけ。
不気味さに気を取られないよう、儀式を続けなくては。
骨壷包みを提げた左手で飯鉢の乗ったままの盆板を持ち、右手で匣鞍を閉じる。
一歩下がって馬に礼をしたら、御曽木堂の入り口へと向かう。
屋根に居る無数の烏たちはずっと僕の動向を見つめている。
あれだけ居るのに一羽として鳴いていないのが余計に薄気味悪い。
「御曽ー木ー堂ー、入らーんー」
野辺の渡り橋に居る参列者の方々にも聞こえる勢いの大声で、「独り言」を叫ぶ。
そして御曽木堂へ礼をし、敷石の上へと――まだ赤黒い染みが残っていることに体が
止まるだけで済んで良かった。出しかけた足を戻しでもしたら大変なことになるところだった。
愛生穂はそれを狙ってここで手首を切ったわけじゃないだろうが、それでも愛生穂の執念のようなものがここには残っていそうで。
あの赤爪の黒い足が、その血溜まり跡の上に乗り、嬉しそうにぴょんぴょんと跳ねる。
ああそうか。この染みも「見ていない」様に振る舞う対象なのか。
今度は迷わずに、染みなどないものとして敷石の上へ乗る。
御曽木堂の入り口扉は両開きなので、その開く扉の軌跡よりも手前に立たねばならない。もちろん戻らないために。
飯鉢の乗った盆板と骨壷包みとを傍らへ置く。
入り口扉は
一礼してから首から下げていた板鍵を首から外し、錠前を解錠して閂を開ける。
閂部分は木製で、扉を開ける際に戻らないで済む位置から手を伸ばして開けるには少々重いのだが、足の位置を動かすわけにもいかないので、踏ん張ってなんとか開ける。
その後、開けた閂の金具部分へ、手に持っていた錠前を差さったままの板鍵ごと引っ掛ける。
一礼をしてから左側の入り口扉から開く。
扉の内側に引っ掛けてある戸止め棒をいったん外し、風などで扉が閉まらないように敷石の凹みへと挿して扉が開いたまま固定する。
このときの角度は御曽木堂に対して直角となる。
右側の扉も同様に開いて止めると、両側の扉が細い通路のようになる。
一礼。
盆板と骨壷包みとを再び持ち、さらに一礼の後、ようやく安置場の中へ踏み込む。
中は簡素な作りで、正面の壁以外は全て板で覆われている。
左右両側の壁には片側四段ずつ長板が渡してあり、そこに幾つもの名帖付き骨壷が置かれている。
左が古く、奥から手前へ、下から上へ。現在は右側の壁の半分ほどが埋まっている。
その右側のほとんどは真新しい。
たった一つ、茶色く汚れた愛生穂の骨壷以外は。
本来、野辺には本家筋、分家筋でさえも渡ってはならないとされている。
そのための『おくりもん』であり、この儀式なのだ。
しかしそれを愛生穂が破った。
そのうえ愛生穂の遺体を回収するために駆けつけた警察官の中に、後で分かったことだが分家の血分かれが居た。
不義の子であることを隠されていたがために、その警察官本人も知らなかった事だし、仕方ないことなのかもしれないが。
ただ結果的に、その後連鎖した多くの悲劇のきっかけになったのは愛生穂とその警官――
啓介は僕の五つ上。小学校も中学校も同じはずだが特に接点などはなかったし、それ以前の評判もごくごく普通の新人警察官だったらしい。
だが愛生穂の送りの儀式の最中、骨壷を奪おうとして、それを阻止しようとした愛生穂の父――南の先代と、そして僕の叔父とが命を落とした。
愛生穂の骨壷は血塗れになったものの奪われずに済み、啓介はそのまま失踪した。
啓介が指名手配となった後で、啓介の母親が泣きながらにした告白は、この地域の人々に衝撃を与えた。
その内容は、啓介の本当の父親が南の先代であるというもの。
様々な儀式の掟が実際の被害を防ぐためのものだったのだと皆は改めて思い知ったが、既に破られてしまった禁忌の代償はあまりにも大きなものとなった。
周囲からの非難を苦に啓介の母親が自殺したのを皮切りに、人が死に始めた。
忌まわしき呪いのせいだとしか言いようがないほど、連続して多くの者が亡くなっている。
そのほとんどが事故としか言いようがない状況で。
ちなみに先代が亡くなったのもその同じ時期で、死因は車による自損事故だった。
母は桃歌同様に「見える」人なのだが、啓介失踪後、野辺でしか見なかった黒い影を川の此方側でも見かけるようになったという。
桜の季節、御曽木堂に沿って植えられた桜を此方側から見る人は少なくないのだが、母は桜の時期であっても川岸にさえ近寄らなかった。
さらには、その黒い影がまとわりついている血分かれの人たちが次々と亡くなったと言っていた。
母は精神的に参ってしまい、現在は先々代の勧めで実家へと帰り、療養している。
今、安置場の中に見えている黒い影は、あの赤爪の黒い足のみ。
それは珍しくじっとしている。愛生穂の骨壷の前で。
そらした視線が三つ前の骨壷で止まる。
啓介のものだ。
血分かれということがわかった以上は、犯罪者であろうともここに収めなければならないらしい。
啓介の送りも僕が執り行った――あのときは骨壷を叩き壊してやりたい気持ちをなんとか堪えて儀式を完了したが、いまだにあの骨壷を見ただけで、自分の中にもどす黒い闇が湧くのを感じる。
切り替えよう。
二つ前と一つ前は北と西の分家筋の先代。そして今回は東の分家筋の――儀式終了までは当代。
愛生穂が僕に執着していたことに対して猛烈に反発していた人たちの最後の一人。
これで一連の呪いとも言えるべき死の連鎖が止まればいいけれど――いや止まってほしい。そう願わざるを得ない。
ただそれはそれとして、念のために安置場の増設はもうそろそろお願いしておくべきなのかもしれない。
御曽木堂の増築は地区内の業者には頼めない。地区内の業者はだいたい本家や分家の血分かれになってしまうからだ。
安置場の奥の壁を見つめ、ここでも一礼する。
そこには一世代前の安置場への入り口扉がそのまま残っている。
その向こうには二世代前の安置場への入り口扉も、さらにその向こうには三世代前の安置場への入り口扉もそのまま。
御曽木堂の入り口を封じる錠前は、もうずっと前から同じものを使っているため、一番外側以外の入り口扉にだけ錠前が付く運用だ。
つまり閂を開けさえすれば、一番最初の安置場まで行けてしまう。
まだ遺体をそのまま運び込んでいた時代の安置場まで。
コン、という音が外から聞こえた。
先々代が傘の柄で地面を突いた音だ。
切り替えたはずなのに、手が止まってしまっていたのか。
どうしてこうも儀式に集中できないのか。
手が止まったせいで、あの黒い足も僕のまわりをぱたぱたと歩き回り始めた。
見てはいけない、考えてはいけない、ましてやその爪と思しき場所が赤いことなど気にすることさえいけない。
思考をそれから切り離そうとするほどに、それは僕の中で存在感を大きくする。
こういうのを切り抜けるときは「そのことについて考えないようにする」というのは悪手で、「別のことに集中する」ことで「そのこと」自体から意識を引き剥がしてゆくのが良い、とは聞いている。
眠れない夜に「寝よう、寝よう」と強く考えてしまうと全く眠れなくなるのと一緒で。
それがゆえの、建物なり歴史なりへの集中だったのだが、結果的には僕の見通しが甘かったと言わざるを得ない。
奥の奥の奥の――もう何世代前かもわからない遠くで、入り口の扉が開く音がしたから。