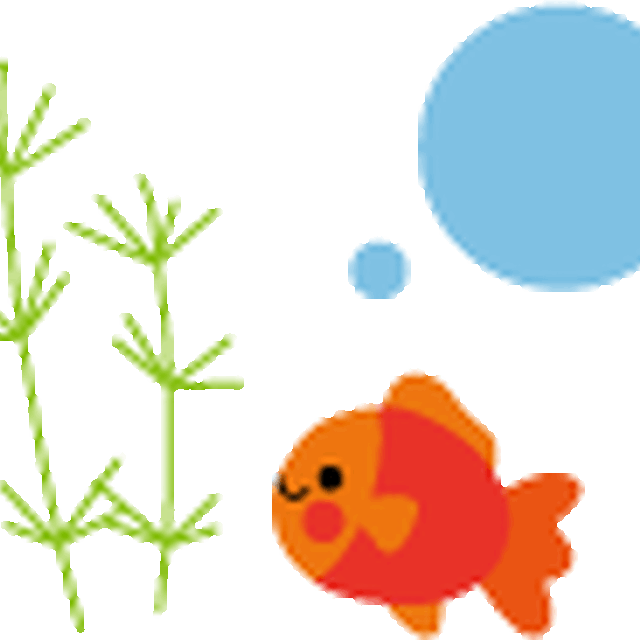日曜日のふうせん合戦
文字数 6,203文字
しずかな坂道をのぼっていると、行く手からたくさんの赤い風船が近づいてくるのが見える。
目をこらすと、それは子どもたちの行列で、みんな、ひとつずつ風船をもって歩いているのだ。
少し遠くの図書館からの帰り道、シンタは思わず足をとめた。そのまま何十人もの行列が通りすぎてゆくのを見ていると、ひとりから「はい、これ」と風船をさし出されて、それがあまりにも自然だったものだから、そのままシンタは風船をうけとった。たくさんの風船をゆらしながら、子どもたちは坂をおりて行った。
日曜のお昼すぎのことだった。
「せっかくだから家までもって帰るか」
風船をうかべたまま歩きだしたシンタは、やがて人通りの多いあたりまでやってきた。すると何だかやけに通りすぎる人の目が気になってきたのだ。なぜかみんな風船をチラリチラリと見てくるように思える。
「おい、そこの小僧」
心ぼそい気持ちになっているところへ、いきなりこんなふうに声をかけられて、おそるおそるふり返ると、ひとりの男が立っていた。あまり会ったことがないけれど、シンタのひいおじいさんくらいに見える老人だ。
「お前、そんなものをそんなふうに、ムキダシにもち歩いたりして、気はたしかなのか」
老人はあきれたような顔をして言う。
「風船は大切にかくしておくものだよ。そうでないと、どんな目に合うかしれない」
そう言われてもシンタには何のことやらさっぱり分からない。そんな彼を見た老人は、
「そら、ちょうどあれを見ろ」
と遠くを指さした。ふたつほど先の交差点を、風船を持った人が歩いている。あの人も風船をもらったのだろうか、やはりまっ赤な風船だ。「あいつをよく見ているんだ。きっと誰かがやらかすから」
言われた通りに見ていると、その人の後ろから、ちがう誰かがこっそり近づいてゆく。そして風船に手をのばした、そう見えたとたん、はなれたところにいるシンタにもとどくくらい、パアンとはでな音をならして風船が割れた。それだけじゃない。風船を割られた人は、手足をバタバタさせながら、ゆっくりと地面のなかへしずんでしまったのだ。もうひとりの方は、さっさと逃げ出して、すぐにいなくなってしまった。
「ほら、割れるとああなっちまう」と言う老人といっしょに、シンタはさっきまで見知らぬふたりがいた交差点まで近づいた。かた足を上げて、いきおいよく道路をふみつけてみる。当たり前だけれど、かたいアスファルトがあるだけだ。
「よっぽどのんびりしてたんだろうな、すんなりとしずんじまって」
言いながらシンタのうでをつかんだ老人は「ちょっと来い、あのガキどものことをおしえてやろう」と返事も聞かずに歩き出した。
つれられてやってきたのは、小さな工場みたいなところだった。おもそうな鉄のとびらを開けた老人がシンタに中へ入るように手まねきをしたけれど、シンタはあやしんで動かない。老人は、まあいい、ちょっとだけ待て。と言いながらひとりで中へ入った。
「あいつらは時々やってくる。遠いむかしにオレも出会った。だが風船をもらったときのことを覚えているやつはほとんどいない。オレくらいかもしれないな」
老人は工場の中からもってきた小さないすにこしかけると、そう話しはじめた。あいつら、というのは風船をもっていた子どもたちのことらしい。
「オレたちはみんな、風船がないと地面に立ってはいられない。そんなのってあるか、ひとつしかないってのに。だから自分でも風船をつくってやるんだ。ここはそのための工場で、研究室だ」
つまり風船をもっている人はたくさんいるし、この老人もそのひとりだということになる。どこにもっているのだろう、そう思いながら見ていると、老人はそれに答えるように、
「オレはちゃんとかくしてもっている。お前やさっきのやつみたいに、まだかくし方をしらないやつも時にはいるんだ」
とつづけた。そのあとは何だかだんだんと早口に、
「あいつらは風船をくばってまわる。何のためかって、そんなの知るもんか。みんなどこかで風船をもらってる。そうしてそのことを忘れるし、オレもしょっちゅう忘れちまう。でもあいつらがあらわれると、またこうして思い出すんだ。思い出している間に、ここへきて研究をするんだ」
そんなことをおこったような顔でいっきに話す。シンタはこわくなって「ぼく、もう帰るよ」とだけ言って工場をあとにした。老人は「なんだ、せっかくおしえてやってるのに」
とふきげんそうではあったけれど、引きとめることはなかった。
風船を割られてしずんでいった人を見た、あれは気のせいだったかもしれない。へんな人に会ったからへんなものが見えた気がしたんだろう。そう思いながらも、風船の糸をはなすのはちょっとこわくて、家まではこのままもっていこう、そう決めたシンタが歩いていると、
「ぐうぜんだね」
と、大学生のヒビキが声をかけてきた。
「今帰るところならいっしょに行こうか」
彼女はとなりの家に住んでいて、日ごろから何かとシンタにも声をかけてくれるから仲が良い。二人はならんで歩き出した。
「いいもの出して、いえ、もっているじゃない」とヒビキは風船を見て言った。シンタはばかばかしいことを言っていると思われたくなくて、風船をもらってからのことをくわしくは話さなかった。ただ、
「これもっているとさ、みんなじろじろ見てくるんだ」
とだけ言った。
「なるほど、ひとの風船って、なんだか気になってしまうのかもしれないね。こまったことだけれど」とヒビキは言う。
「ふうん、よく分からないな」
「だからそんなふうにもってちゃいけないんだよ。ほら、私こまっちゃうでしょう」
「え?なんて言ったの」
と聞き返したのと、パン、と耳元で大きな音がひびいたのは同時だった。「ごめんねえ」と言うヒビキの手に針が光っている。シンタの手から、ちぎれた風船をくっつけた糸がだらんとたれ下がった。
急に足もとの地面が底なし沼にでも変わったみたいに、シンタの体がしずみだした。今日見たものは、やっぱり気のせいなんかじゃなかった。あわてて彼は重い足を動かしながら逃げるようにその場をはなれた。今はこまったヒビキに文句を言っている場合じゃない。
もがいていれば少ししずみ方もゆるやかになるけれど、長くはもちそうにない。シンタが半分くらい体をしずめながらもドロの中を進むみたいにしてやってきたのは、あの老人の工場だ。あやしい人ではあるけれど、ほかにあてがない。
もう首までしずみそうになったシンタが、大声で「おーい」とよびかけると、老人が顔を出した。
シンタを見るとすぐに何があったのか分かったものらしい。「それ見ろ、ゆだんするからだ」老人はシンタのうでをつかんでひっぱり上げた。
「まあ、ずっとこうしていてやるわけにはいかないからな、あきらめるこった。何かにのっかっても、家の中にいたってだめだ。風船が割れりゃあ、しずんでいくだけだ。こんなふうに誰かにつかまっていることはできるが、おんぶされたまま暮らすわけにもいかんだろう」
「そんなのないよ、ちょっと、はなそうとしないでよ」
シンタはそう言って老人のうでにしがみつく。
「だから言ったろう、風船は見えないようにもっているものだって」
「そんなこと言ったって、どうやってかくせばいいのか分らないよ」
「そうだったなあ、自分でもどうやっているのか分からないんだから教えようがない。でもかわいそうだから一度だけやって見せてやろう、まずかくすのをやめる。ほら」
老人の手もとに風船があらわれた。まるで手品みたいだ。そのとき、風船を見たシンタの頭に(今しかないぞ)という考えがうかんだ。老人のうでから手をはなすと、とびおりざまに風船をうばいとる。地面はまたがっしりと両足を受けとめてくれた。「こいつめ、何てことをしやがる」かわってしずみはじめた老人のどなり声を聞きながら、シンタはもう風船をもって走り出していた。
「逃がしゃしないぞ、オレにはあれが…」
彼に聞こえたのはそこまでだ。
シンタは大通りまで逃げてきた。今度はぜったいに風船を割らせないようにと、キョロキョロしながら歩く。そのうち、じわじわと近よってくる人があらわれるようになった。
みんなその手には針をもっていて、シンタの風船にむかってその針をつき出してくるのだ。あまり見られたくないことではあるのか、スキを見てこっそりと割ろうとしては、一度かわされると何もなかったみたいな顔をして行ってしまう。とはいえ、次々とねらわれるものだから気がぬけない。それでも彼が人の多いところにやってきたのは、あの子どもをさがすためだ。
17時をすぎて、少しだけ暮れかかってきた町で、ようやく見おぼえのある姿を見つけたシンタは、「ねえ、ちょっと待って」とかけよった。
「風船を返すよ、そうすれば、何もかももと通りになるよね」
そう言って風船をさし出したシンタを見て、その子どもは「僕じゃない」と言う。そういえばみんな同じような顔をしていた。「じゃあ、あの子はどこにいるの」と聞くと、空の上を指さして、そのまま歩いていってしまった。
「まいったな、返すこともできないのか」
こまりはてて、つい気がゆるんだところへ、ななめ後ろからヌッと針がつき出される。
「もう、じゃまだな」
とっさによけたシンタは、いいかげん腹がたってきて、スーツを着たその男から針を取り上げると、おどかすつもりで相手に向けてつき出した。するとパン、と音だけが聞こえたかと思うと、男は足から順に、ズブズブとしずみ始めたのだった。
どうやら見えない風船を割ったらしい。そのことに気づいたシンタは、しばらくその場でぼうっとしていた。するとだんだんと楽しい気持ちがわき上がってくる。手に持った針をもう片方の指でピンとはじいてニンマリした彼の顔は、少しだけあの老人みたいだった。
その針は、彼のとったそれからの行動にはたいへん役に立った。それと言うのも、彼が進んで人の多い道をえらんでは、手当たりしだいに通りすがりの人の風船を割りはじめたからだ。
知らなかったけれど、誰もかれも、風船をかくしもっているのだった。見えない風船をかくしているところにも見当がつくようになってきて、おもしろいようにパン!パン!と音をたてて割れるのがとっても気持ち良い。コソコソするでもなく、次々と風船を割りにいくシンタに、みんなびっくりした顔でしずんでゆく。
もちろん、シンタの風船をねらってくる人もたくさんいる。何せシンタの風船はあいかわらずムキダシなのだ。けれど今は、風船を割ることの方が楽しくてたまらない。それに風船をひとつ割るたびに、シンタの持つ風船はじょうぶになっていくようだ。ちょっと大きくなってきたようにも見える。それなら、なおさら少しでもたくさんの風船を割る方が良いにきまっている。いや、風船って割るためにあるんじゃないか。今、シンタの頭の中はざっとこんな感じだった。あれ、あそこにヒビキさんがいるぞ。さっきのお返しをしなくちゃ。パン!とこんな調子。
「けっこう割ったなあ、五十はいったんじゃないか」
そう言いながらひといきつくと、気がつけばシンタのまわりにはあまり人がいなくなっていて、いつの間にか糸の先にある風船は、彼のあたまの上で、人間ひとりは入りそうなほどふくらんでいるのだった。そうしてフワリとうかび出す。彼はあわてて風船の糸をしっかりとにぎなおした。
風船はシンタをぶらさげて、やねをこえて、町をひとつ見おろせるところまで。
もうずいぶんと暗くなってきた空に、シンタは気分よくうかんでいた。
風船を行きたいほうにうごかすと、そちらに進んだりもできた。そうやって空のさんぽを楽しんでいると、頭の上から、あの子どもがスッと目の前にあらわれた。たぶん、こんどこそシンタに風船をわたした子だ。子どもは風船をじっと見ると「君のじゃないね」と言った。
「そうとも、オレのだからな」
こんな空の上だというのに近くから声がきこえて、おどろいて見れば、あの老人がシンタとおなじように、大きな風船にぶらさがってこちらに向かってくる。わきにはなにか長いものを二本かかえているようだ。
「どうだ、オレはひとつだけだが風船を自分で作りだしていたんだぞ。お前のまねをして、ここまでこらしめにきてやったぞ」
どうやらシンタがどうやって空にうかんだか見ていたものらしい。
「オレもずいぶん風船を割ってやった。ゆかいでたまらん。だけど、お前も中々やるもんだ。ここは『いっきうち』といこうじゃないか。そんなちっぽけな針じゃあつまらん、これを使え」
と、巨大な針をなげてよこす。もってみると、まるで一寸法師になった気分だ。ふたりとも片手は風船の糸、もう片方の手には針をかまえて、そろそろ月もかがやきだした夜空できみょうな戦いがはじまった。
おたがいの風船をねらって、針のつるぎをうちつけ合うこと二十分ほど。つかれてきたシンタが少しはなれようとしたところへ老人がせまってきた。あぶなく割られてしまいそうになったとき、老人の風船はとつぜん赤い色がうすくなってきたかと思うと、いきなり割れてしまったのだ。花火みたいな大きな音がなりひびく中、老人は「しまった!くそ、これもしっぱい作だったか」と、くやしそうに落ちていった。
勝ったと思ったのもつかのま、となりで見ていたあの子どもが
「君のじゃないから、これはだめ」
ひょいとシンタから風船をとりあげてしまった。
そんなあ、とシンタもクルクルしせいを変えながら落ちていく。地面がどんどん近づいて、先にあの老人が地面の下にすいこまれるように消えていくのがちらりと見えた。それにつづいて地面を通りぬけたのと同時に、シンタは気をうしなった。
空にいた子どもはゆっくり地上へおりると、シンタからとりあげた風船を空へはなした。
何か考えているみたいに少しのあいだ首をかしげて、やがて地面からロープでもひっぱりあげるような手つきで左右の手を動かしはじめる。すると地面の下から、しずんでいた人たちが姿をあらわしはじめた。シンタと老人が風船を割った人もみんな。そうして最後に、あんまりにも高いところから落ちてきたものだから、ほかの人よりもずっとずっと下までしずんでいたシンタと老人がうかびあがってきた。みんなが眠っていた。
風船をもった他の子どもたちも集まってきて、みんなの手に次々と風船をにぎらせていった。風船をもらった人は眠ったまま、自分の家に帰ってゆく。そのあと、子どもたちは最初にシンタが行列を見た坂道をのぼっていった。そのすがたはだんだん小さくなって、そして消えてしまったのだけれど、それを見ていた人は誰もいない。
次の朝、登校中のシンタはぶつぶつとひとり言をいいながら歩く、知らない老人とすれちがった。
「どいつもこいつも忘れちまった。でも風船はあるんだ。こんなことがしょっちゅうあるんだ。ああくそ、でもオレももう、どこに持っているのかも思い出せやしない」
シンタは(どこかで会ったかな)と考えたけれど、分からなかった。「まあいいや」彼はそうつぶやくと、何となく胸のあたりをゴソゴソしながら、学校へと向かった。
目をこらすと、それは子どもたちの行列で、みんな、ひとつずつ風船をもって歩いているのだ。
少し遠くの図書館からの帰り道、シンタは思わず足をとめた。そのまま何十人もの行列が通りすぎてゆくのを見ていると、ひとりから「はい、これ」と風船をさし出されて、それがあまりにも自然だったものだから、そのままシンタは風船をうけとった。たくさんの風船をゆらしながら、子どもたちは坂をおりて行った。
日曜のお昼すぎのことだった。
「せっかくだから家までもって帰るか」
風船をうかべたまま歩きだしたシンタは、やがて人通りの多いあたりまでやってきた。すると何だかやけに通りすぎる人の目が気になってきたのだ。なぜかみんな風船をチラリチラリと見てくるように思える。
「おい、そこの小僧」
心ぼそい気持ちになっているところへ、いきなりこんなふうに声をかけられて、おそるおそるふり返ると、ひとりの男が立っていた。あまり会ったことがないけれど、シンタのひいおじいさんくらいに見える老人だ。
「お前、そんなものをそんなふうに、ムキダシにもち歩いたりして、気はたしかなのか」
老人はあきれたような顔をして言う。
「風船は大切にかくしておくものだよ。そうでないと、どんな目に合うかしれない」
そう言われてもシンタには何のことやらさっぱり分からない。そんな彼を見た老人は、
「そら、ちょうどあれを見ろ」
と遠くを指さした。ふたつほど先の交差点を、風船を持った人が歩いている。あの人も風船をもらったのだろうか、やはりまっ赤な風船だ。「あいつをよく見ているんだ。きっと誰かがやらかすから」
言われた通りに見ていると、その人の後ろから、ちがう誰かがこっそり近づいてゆく。そして風船に手をのばした、そう見えたとたん、はなれたところにいるシンタにもとどくくらい、パアンとはでな音をならして風船が割れた。それだけじゃない。風船を割られた人は、手足をバタバタさせながら、ゆっくりと地面のなかへしずんでしまったのだ。もうひとりの方は、さっさと逃げ出して、すぐにいなくなってしまった。
「ほら、割れるとああなっちまう」と言う老人といっしょに、シンタはさっきまで見知らぬふたりがいた交差点まで近づいた。かた足を上げて、いきおいよく道路をふみつけてみる。当たり前だけれど、かたいアスファルトがあるだけだ。
「よっぽどのんびりしてたんだろうな、すんなりとしずんじまって」
言いながらシンタのうでをつかんだ老人は「ちょっと来い、あのガキどものことをおしえてやろう」と返事も聞かずに歩き出した。
つれられてやってきたのは、小さな工場みたいなところだった。おもそうな鉄のとびらを開けた老人がシンタに中へ入るように手まねきをしたけれど、シンタはあやしんで動かない。老人は、まあいい、ちょっとだけ待て。と言いながらひとりで中へ入った。
「あいつらは時々やってくる。遠いむかしにオレも出会った。だが風船をもらったときのことを覚えているやつはほとんどいない。オレくらいかもしれないな」
老人は工場の中からもってきた小さないすにこしかけると、そう話しはじめた。あいつら、というのは風船をもっていた子どもたちのことらしい。
「オレたちはみんな、風船がないと地面に立ってはいられない。そんなのってあるか、ひとつしかないってのに。だから自分でも風船をつくってやるんだ。ここはそのための工場で、研究室だ」
つまり風船をもっている人はたくさんいるし、この老人もそのひとりだということになる。どこにもっているのだろう、そう思いながら見ていると、老人はそれに答えるように、
「オレはちゃんとかくしてもっている。お前やさっきのやつみたいに、まだかくし方をしらないやつも時にはいるんだ」
とつづけた。そのあとは何だかだんだんと早口に、
「あいつらは風船をくばってまわる。何のためかって、そんなの知るもんか。みんなどこかで風船をもらってる。そうしてそのことを忘れるし、オレもしょっちゅう忘れちまう。でもあいつらがあらわれると、またこうして思い出すんだ。思い出している間に、ここへきて研究をするんだ」
そんなことをおこったような顔でいっきに話す。シンタはこわくなって「ぼく、もう帰るよ」とだけ言って工場をあとにした。老人は「なんだ、せっかくおしえてやってるのに」
とふきげんそうではあったけれど、引きとめることはなかった。
風船を割られてしずんでいった人を見た、あれは気のせいだったかもしれない。へんな人に会ったからへんなものが見えた気がしたんだろう。そう思いながらも、風船の糸をはなすのはちょっとこわくて、家まではこのままもっていこう、そう決めたシンタが歩いていると、
「ぐうぜんだね」
と、大学生のヒビキが声をかけてきた。
「今帰るところならいっしょに行こうか」
彼女はとなりの家に住んでいて、日ごろから何かとシンタにも声をかけてくれるから仲が良い。二人はならんで歩き出した。
「いいもの出して、いえ、もっているじゃない」とヒビキは風船を見て言った。シンタはばかばかしいことを言っていると思われたくなくて、風船をもらってからのことをくわしくは話さなかった。ただ、
「これもっているとさ、みんなじろじろ見てくるんだ」
とだけ言った。
「なるほど、ひとの風船って、なんだか気になってしまうのかもしれないね。こまったことだけれど」とヒビキは言う。
「ふうん、よく分からないな」
「だからそんなふうにもってちゃいけないんだよ。ほら、私こまっちゃうでしょう」
「え?なんて言ったの」
と聞き返したのと、パン、と耳元で大きな音がひびいたのは同時だった。「ごめんねえ」と言うヒビキの手に針が光っている。シンタの手から、ちぎれた風船をくっつけた糸がだらんとたれ下がった。
急に足もとの地面が底なし沼にでも変わったみたいに、シンタの体がしずみだした。今日見たものは、やっぱり気のせいなんかじゃなかった。あわてて彼は重い足を動かしながら逃げるようにその場をはなれた。今はこまったヒビキに文句を言っている場合じゃない。
もがいていれば少ししずみ方もゆるやかになるけれど、長くはもちそうにない。シンタが半分くらい体をしずめながらもドロの中を進むみたいにしてやってきたのは、あの老人の工場だ。あやしい人ではあるけれど、ほかにあてがない。
もう首までしずみそうになったシンタが、大声で「おーい」とよびかけると、老人が顔を出した。
シンタを見るとすぐに何があったのか分かったものらしい。「それ見ろ、ゆだんするからだ」老人はシンタのうでをつかんでひっぱり上げた。
「まあ、ずっとこうしていてやるわけにはいかないからな、あきらめるこった。何かにのっかっても、家の中にいたってだめだ。風船が割れりゃあ、しずんでいくだけだ。こんなふうに誰かにつかまっていることはできるが、おんぶされたまま暮らすわけにもいかんだろう」
「そんなのないよ、ちょっと、はなそうとしないでよ」
シンタはそう言って老人のうでにしがみつく。
「だから言ったろう、風船は見えないようにもっているものだって」
「そんなこと言ったって、どうやってかくせばいいのか分らないよ」
「そうだったなあ、自分でもどうやっているのか分からないんだから教えようがない。でもかわいそうだから一度だけやって見せてやろう、まずかくすのをやめる。ほら」
老人の手もとに風船があらわれた。まるで手品みたいだ。そのとき、風船を見たシンタの頭に(今しかないぞ)という考えがうかんだ。老人のうでから手をはなすと、とびおりざまに風船をうばいとる。地面はまたがっしりと両足を受けとめてくれた。「こいつめ、何てことをしやがる」かわってしずみはじめた老人のどなり声を聞きながら、シンタはもう風船をもって走り出していた。
「逃がしゃしないぞ、オレにはあれが…」
彼に聞こえたのはそこまでだ。
シンタは大通りまで逃げてきた。今度はぜったいに風船を割らせないようにと、キョロキョロしながら歩く。そのうち、じわじわと近よってくる人があらわれるようになった。
みんなその手には針をもっていて、シンタの風船にむかってその針をつき出してくるのだ。あまり見られたくないことではあるのか、スキを見てこっそりと割ろうとしては、一度かわされると何もなかったみたいな顔をして行ってしまう。とはいえ、次々とねらわれるものだから気がぬけない。それでも彼が人の多いところにやってきたのは、あの子どもをさがすためだ。
17時をすぎて、少しだけ暮れかかってきた町で、ようやく見おぼえのある姿を見つけたシンタは、「ねえ、ちょっと待って」とかけよった。
「風船を返すよ、そうすれば、何もかももと通りになるよね」
そう言って風船をさし出したシンタを見て、その子どもは「僕じゃない」と言う。そういえばみんな同じような顔をしていた。「じゃあ、あの子はどこにいるの」と聞くと、空の上を指さして、そのまま歩いていってしまった。
「まいったな、返すこともできないのか」
こまりはてて、つい気がゆるんだところへ、ななめ後ろからヌッと針がつき出される。
「もう、じゃまだな」
とっさによけたシンタは、いいかげん腹がたってきて、スーツを着たその男から針を取り上げると、おどかすつもりで相手に向けてつき出した。するとパン、と音だけが聞こえたかと思うと、男は足から順に、ズブズブとしずみ始めたのだった。
どうやら見えない風船を割ったらしい。そのことに気づいたシンタは、しばらくその場でぼうっとしていた。するとだんだんと楽しい気持ちがわき上がってくる。手に持った針をもう片方の指でピンとはじいてニンマリした彼の顔は、少しだけあの老人みたいだった。
その針は、彼のとったそれからの行動にはたいへん役に立った。それと言うのも、彼が進んで人の多い道をえらんでは、手当たりしだいに通りすがりの人の風船を割りはじめたからだ。
知らなかったけれど、誰もかれも、風船をかくしもっているのだった。見えない風船をかくしているところにも見当がつくようになってきて、おもしろいようにパン!パン!と音をたてて割れるのがとっても気持ち良い。コソコソするでもなく、次々と風船を割りにいくシンタに、みんなびっくりした顔でしずんでゆく。
もちろん、シンタの風船をねらってくる人もたくさんいる。何せシンタの風船はあいかわらずムキダシなのだ。けれど今は、風船を割ることの方が楽しくてたまらない。それに風船をひとつ割るたびに、シンタの持つ風船はじょうぶになっていくようだ。ちょっと大きくなってきたようにも見える。それなら、なおさら少しでもたくさんの風船を割る方が良いにきまっている。いや、風船って割るためにあるんじゃないか。今、シンタの頭の中はざっとこんな感じだった。あれ、あそこにヒビキさんがいるぞ。さっきのお返しをしなくちゃ。パン!とこんな調子。
「けっこう割ったなあ、五十はいったんじゃないか」
そう言いながらひといきつくと、気がつけばシンタのまわりにはあまり人がいなくなっていて、いつの間にか糸の先にある風船は、彼のあたまの上で、人間ひとりは入りそうなほどふくらんでいるのだった。そうしてフワリとうかび出す。彼はあわてて風船の糸をしっかりとにぎなおした。
風船はシンタをぶらさげて、やねをこえて、町をひとつ見おろせるところまで。
もうずいぶんと暗くなってきた空に、シンタは気分よくうかんでいた。
風船を行きたいほうにうごかすと、そちらに進んだりもできた。そうやって空のさんぽを楽しんでいると、頭の上から、あの子どもがスッと目の前にあらわれた。たぶん、こんどこそシンタに風船をわたした子だ。子どもは風船をじっと見ると「君のじゃないね」と言った。
「そうとも、オレのだからな」
こんな空の上だというのに近くから声がきこえて、おどろいて見れば、あの老人がシンタとおなじように、大きな風船にぶらさがってこちらに向かってくる。わきにはなにか長いものを二本かかえているようだ。
「どうだ、オレはひとつだけだが風船を自分で作りだしていたんだぞ。お前のまねをして、ここまでこらしめにきてやったぞ」
どうやらシンタがどうやって空にうかんだか見ていたものらしい。
「オレもずいぶん風船を割ってやった。ゆかいでたまらん。だけど、お前も中々やるもんだ。ここは『いっきうち』といこうじゃないか。そんなちっぽけな針じゃあつまらん、これを使え」
と、巨大な針をなげてよこす。もってみると、まるで一寸法師になった気分だ。ふたりとも片手は風船の糸、もう片方の手には針をかまえて、そろそろ月もかがやきだした夜空できみょうな戦いがはじまった。
おたがいの風船をねらって、針のつるぎをうちつけ合うこと二十分ほど。つかれてきたシンタが少しはなれようとしたところへ老人がせまってきた。あぶなく割られてしまいそうになったとき、老人の風船はとつぜん赤い色がうすくなってきたかと思うと、いきなり割れてしまったのだ。花火みたいな大きな音がなりひびく中、老人は「しまった!くそ、これもしっぱい作だったか」と、くやしそうに落ちていった。
勝ったと思ったのもつかのま、となりで見ていたあの子どもが
「君のじゃないから、これはだめ」
ひょいとシンタから風船をとりあげてしまった。
そんなあ、とシンタもクルクルしせいを変えながら落ちていく。地面がどんどん近づいて、先にあの老人が地面の下にすいこまれるように消えていくのがちらりと見えた。それにつづいて地面を通りぬけたのと同時に、シンタは気をうしなった。
空にいた子どもはゆっくり地上へおりると、シンタからとりあげた風船を空へはなした。
何か考えているみたいに少しのあいだ首をかしげて、やがて地面からロープでもひっぱりあげるような手つきで左右の手を動かしはじめる。すると地面の下から、しずんでいた人たちが姿をあらわしはじめた。シンタと老人が風船を割った人もみんな。そうして最後に、あんまりにも高いところから落ちてきたものだから、ほかの人よりもずっとずっと下までしずんでいたシンタと老人がうかびあがってきた。みんなが眠っていた。
風船をもった他の子どもたちも集まってきて、みんなの手に次々と風船をにぎらせていった。風船をもらった人は眠ったまま、自分の家に帰ってゆく。そのあと、子どもたちは最初にシンタが行列を見た坂道をのぼっていった。そのすがたはだんだん小さくなって、そして消えてしまったのだけれど、それを見ていた人は誰もいない。
次の朝、登校中のシンタはぶつぶつとひとり言をいいながら歩く、知らない老人とすれちがった。
「どいつもこいつも忘れちまった。でも風船はあるんだ。こんなことがしょっちゅうあるんだ。ああくそ、でもオレももう、どこに持っているのかも思い出せやしない」
シンタは(どこかで会ったかな)と考えたけれど、分からなかった。「まあいいや」彼はそうつぶやくと、何となく胸のあたりをゴソゴソしながら、学校へと向かった。