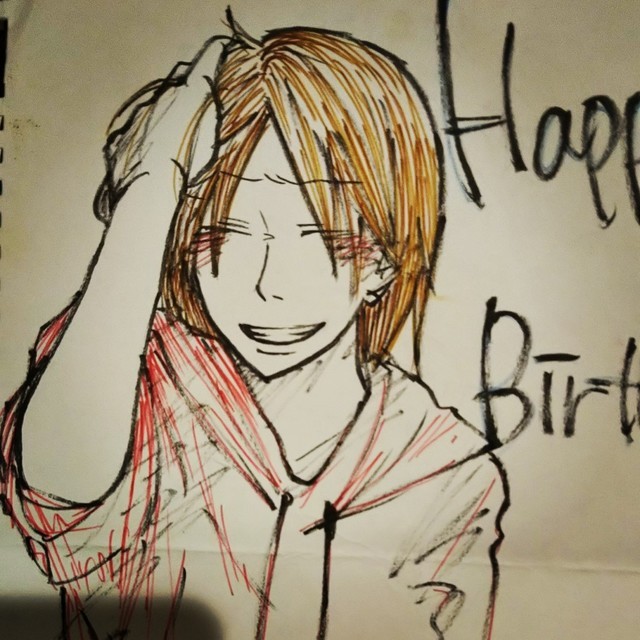第5話
文字数 3,456文字
【二〇一五年八月九日(日)】
頭の芯に残る声。気温に対して冷たい身体。
どこで何を間違えたんだろう。
そうぼんやりと思った時、頭上からした声。
「あ」
顔を上げる。いつも見る姿と違う、ダークグレーの服。
瞬時に身体が強張る。それは杉田さんだった。
「……」
「……」
近所のコンビニ。浴衣のままの自分に、何を言う訳でもなく、何かを察した男は「動くな」と言うとスマホを取り出した。握りしめたままの振動止め。その後、数歩離れた所で通話を始めると、短いやり取りの後、呼吸以外の全てを停止させた状態で待っていた自分の所に戻ってくる。
「……」
「……」
沈黙に殺されるかと思った。そんな深い静寂の後、数分して現れたのは一台の車。降ろされた窓から顔を覗かせたのは五十嵐さんだった。入れ替わるようにして杉田さんが立ち去る。
「どうした浴衣JK」
既にJKではないが、その呼び方に大差はない気がした。
うつむくと、何かを察した男は「どうすっかな。流石に小さいのがいる家はちょっとな。あ、アキラんとこがいいか」とオートで話を進めていく。
「それか……あ、こっからなら寺岡サンとこの方が近いか。猫いるっつってたし、もう一匹増えた所で変わらんだろ」
ヒュッと喉が塞がる。
〈節操のない〉
それは、最も危険な選択肢。
流れを止めようと口を開くと同時に、五十嵐さんの向こうから声がした。
「何言ってるの。女の子よ。ウチでいいじゃない」
その後、車に揺られながらさっきのやりとりを思い出す。
花火を見終わった、その帰りのことだった。行きはバスを使ったが、帰りは危ないからと言ってブラザーが車を出してくれた。時刻は二十一時半。今日は花火が二十一時までだと伝えてあるから、時間で咎められることはなかった。けれど。
ブラザーの車は少しだけうるさい。
紅葉と二人「ありがとうブラザー」と手を振ると同時に、何となく嫌な予感はしていた。いや、それより前「乗ってけ」と言ったブラザーの車がうぁんうぁん音を立てているのを聞いた時から、既に心臓が嫌な音を立て始めていた。
案の定、玄関で仁王立ちになって待っていた母は「今何時だと思っているの!」とご近所迷惑な音量で怒鳴った。すぐさま紅葉が「私がお願いしたの。帰り暗くて怖いからって」と言う。
けれども母にとったら、姉妹で問題を起こした場合、姉であるあたしの責任。その目はあたしをとらえて離さなかった。
弁明を。
謝罪を。
修復を。
今後の在り方を。
音に起こさずとも通るべきルートは、求められているものは分かる。けれども何故だろう。この時初めて、全部どうでもいいと思った。
いつの間にか小さくなった人。御家にしがみつき、御家がために、いつまでも古いものを愛で、そこに護られたつもりになりながら、勝手に生きてくれ、と。あたしを一緒にするな、と。
「お姉?」
微動だにしないあたしを紅葉が見る。
邪魔だった。
手にしているもの、手首にかけているもの、全てその場に落とすと、そのまま玄関を出る。
「お姉!」
追いかけて来たのは妹の声だけだった。その声も母に呼び止められて玄関からは出られない。まるで檻の様だと思った。まるで犬のようだと。
フツフツと沸騰し続ける頭。それでも人気のない夜道に不安を覚え始めた頃、クセのように腰に手を当てた。次の瞬間、血の気が引く。
しまった。
思い出す。玄関に取り落として来たもの。あの中に今日もらったかんざしが入ってる。その時は帯につけておこうと思ったが、無くしてしまってはいけないと、結局巾着に入れたのだ。逆に。
帯の右の方にある膨らみ。ねじって中身を取り出す。
緑色の振動止め。
かんざしをもらった時、返そうと思った。
もう大丈夫だと。これがあるから大丈夫だからと。そうして紅葉に返すタイミングを窺ってた。皮肉にもそれだけが手元に残った。
その後、連れて来られたのはアパートの一室。台所に立つ伊織さんの手前、いつも見ていたコート上のやさしい五十嵐さんは、ここでは目の据わった五十嵐さんに変わっている。
「いいか。俺はすごーく仕事ができるからすごーく忙しいんだ。そんな俺の貴重な帰宅日、伊織チャンと楽しい時間を過ごせないことによって、明日四つある商談の内、一つは頑張れないことが確定した。額にして三千万。お前は一泊三千万でここに泊まるんだ。そんだけのことを肝に銘じろよ」
自炊をすることで何となく分かるようになってきた金銭感覚が、三千万という途方もない数字を前に縮み上がる。瞬時に「帰らなければ」と悟った時、向こうから声がした。
「聞かなくていいわ。居づらかったらどこにでも行くアテあるから。安心してくつろいでね」
「ひどいッ!」と言った五十嵐さんはその後別室に行ってしまった。
それでも長居する訳にはいかない。最低限紅葉には知らせておこうと思って連絡すると、程なくして母親が迎えに来た。母は伊織さん越し、あたしの姿を認めるなり、玄関に足を踏み入れ、腕を掴んだ。幼少期からの刷り込み。それ自体大した力じゃなくても、自分を動けなくさせるのに十分な何かがそこにはあった。
「私達は」
そうして帰ろうとした母にかけられた声は、場違いな程静かだった。
「偶然彼女を見つけた友人からの連絡で、彼女を保護しました。親にとっていつまでも子供でも、十八歳は決して子供ではありません。せめて娘さんの無事と向き合うようお勧めします」
それでは、と言うと、伊織さんはあたしに笑いかけて扉を閉めた。
向き直る。閉められた扉を見つめたままの目。落ち窪んだまぶた。
母は、老けた。幼少期、怒った時に寄るシワが怖かった。でも今は、怒っていなくてもいろんな所にシワが刻まれている。
その小さな背中。常日頃から気にしている世間とやら。一歩外に出れば、この人はこんなにも非力だ。
音もなく動き始めたその後ろ姿を追う。
りんご飴の話をした、と言っていた。
紅葉はいつだってあたし達をバラバラにしないように必死だ。
玄関で落としたあの中に入っていたもの。一番重い音を立てたもの。
一番最初に買ったりんご飴。キラキラキレイで、一緒に来れなかった母にあげようと思った。緑色のものもあったけど、きっと母も見たことはあるだろうから、オーソドックスな、その記憶にあるままのものをあげようと思ったのだ。
あたしは「余計なことをしないで」と言った。
風呂から上がると、ただの自分だった。
三度のシャンプーが必要になった髪は解け、目鼻立ちをはっきりさせていた化粧もなくなり、色のない爪だけが残る。幼い頃好きだった「女の子が変身して戦うアニメ」の中の一番の作り話は、変身が解けても同じ顔をしていることだと知る。
紅葉はほとんど化粧をしない。似たような造作をしている以上、すっぴんの自分が常に隣にいるようで、何度か化粧を強要したが、本人が自分でやるとなると、手先が不器用すぎて結局やめてしまった。そのつぶらな目が足元を見つめている。
「お姉はたぶん、誤解してる」
自分と同じくらいの大きさ、自分と同じくらいの体積を持つ生き物。
その黒い塊が、年々小さくなっていくベッドの隅で膝を抱えて座っている。
「本当に見なきゃいけないのはお母さんじゃない」
その、知ったような物言いにカチンとくる。
強いクセ毛の黒髪。パーマをかけて、髪型を変えた自分。
自然に備わっているもの。よく分からないけど、空気を一杯に含めるふわふわは綿菓子。桃色の、幸せ色をした。例えば、なでて、愛でられるような。
「あんたには甘いからね」
言いながら机の引き出しを開ける。
母はいつだって紅葉にはやさしかった。一番じゃなくても、頑張ったなら頑張ったなりの「頑張ったわね」を与えた。あたしは一度ももらった覚えがないのに。
「違う。お姉はしっかりしてるから」
「は?」
思わず声が出た。
「しっかり」と引き換えにある居場所。誰もしたくてしている訳じゃない。しっかりしなくても生きていける、のうのうと暮らせるあんたには、
「バカには分からないでしょうね」
そうして布団に入る。電気消して、と言うと、少しして電気が消えた。便利な電子家電なんてない時から、あたしには便利な生き物がついている。
引き出しに投げ入れた緑色の振動止め。ふとあのかんざしはちゃんとあるか不安になるが、そのままギュッと目を瞑った。
〈こっちの方が何となく雰囲気に合う気がして〉
真っ直ぐな赤の直線。
せめてキレイな思い出ではキレイなままの自分でいたかった。